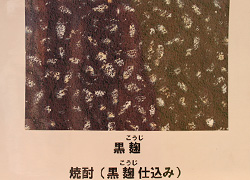「食」カテゴリーの記事一覧
香り高きハバネロ
わさび、からし、唐辛子、山椒、生姜など、
日本にも昔から親しまれてきている香辛料があります。
そんななか、海の向こうから渡ってきた香辛料に魅了された、
一人の男性がいました。
「僕にとって、ハバネロソースは名刺代わりです」

すがすがしい笑顔でそう話すのは、
兵庫県篠山市でターンムファームを営む近藤卓さん。
日本では珍しい、無農薬でハバネロを専門に育てるファーマーです。
ハバネロといえば、中南米が原産の
鷹の爪などの数倍の辛さを誇る、唐辛子の一種。
一体、どんな姿かたちをしているのかと、
恐る恐る、近藤さんの畑を案内いただくと、

そこにはイキイキと実るぷりっとした果実の姿がありました。

たとえていうならば、ピーマンやパプリカのような。
これがそこまでの辛さを醸し出すとは思いもしません。
「よかったらかじってみてください」

言われるがままに、
近藤さんが割ったハバネロの欠片をかじってみると…、
「ん?辛くない。むしろフルーティー」
それが初めの正直な感想です。
しかし、程なくして、じわりじわりと訪れる辛さ。
「キター!!やっぱり辛い!」
この感覚こそが、近藤さんを虜にした証でした。
初めて近藤さんがハバネロに出会ったのは、2002年のこと。
当時、住んでいた石垣島の友人から渡された一つの実が、それでした。

「その色と形。香水のような芳香。
フルーティーなやさしい甘みの後に広がる、とてつもない辛さ。
完全にハバネロに魅了されましたね」

以来、その時に譲り受けたハバネロから種採りをし、
株を大切に少しずつ増やしてきたといいます。

そして2004年、広い土地を求めて、48株のハバネロの苗と共に、
奥さんの実家のある丹波篠山へ移住されました。
ただ、そのまま食べるには辛すぎるハバネロ。
そこで近藤さんが手掛けたのが、ハバネロソースでした。
「子供がいるんですが、小さいうちは料理を辛くできませんから。
自分が食べる料理にだけ使えるようなソースが欲しかった」
そう話す近藤さんは、子供の頃から、料理にタバスコをかけていたそうですが、
酸っぱさをなんとかしたいと思っていたそう。
そして、好みのソースを追求すること1年。

無農薬・無化学肥料栽培のマンゴーやトマト、
自家製のニンニクやタマネギを混ぜたソースが完成したのです。

初めは売るつもりなどなかったそうですが、
瓶が好きで、デザインも好きな近藤さんが手掛けると、
自ずとパッケージも洗練されていきます。

こうして完成したハバネロソースは、
「Mellow Habanero(メローハバネロ)」と名付けられ、
評判が評判を呼び、広がっていきました。
英語が話せるようになりたいと、
写真共有サイトに投稿した英語の栽培日記は、海外にまで反響を呼ぶように。
アメリカやオーストラリア、デンマークといった国々へも出荷され、
スウェーデンでは女性ヘビメタバンドのオフィシャルグッズにも採用されているほどです。
世界広しといえど、ハバネロの栽培から、収穫、加工、出荷までを
一貫して行っている生産者は、希少な存在なようなのです。
近藤さんが自身の人生すべてがそこに入っている、
名刺のようなものと語るハバネロソースは、
国内外を問わず、確かに近藤さんと人々をつないでいました。
今では1800株を育てるまでに至った、ターンムファームのハバネロ畑。

それが近藤さんは家族で手掛けられる最大の規模と話します。
驚いたのがソースを作るミキサーも鍋も、すべて家庭用サイズ。
その理由も、至ってシンプルでした。
「すべて手づくりでやりたいんです。
教わるのではなく自分で切り開いていく、DIYスピリットを大切にしていますね」
自らを"ハバネロマン"と名乗り、
ハバネロソースのおいしさを広める近藤さん。

素材の味を引き立ててくれる心地よい辛さは、
病みつきになる味わいです。

欧米化する日本の食卓において、
ハバネロソースが欠かせなくなる日も近いかもしれません。
【お知らせ】
2012年に開始した「MUJIキャラバン〜日本全国の良いくらしを探す旅〜」
の連載ブログは、今回をもちまして一旦、終了となります。
地域で出会ったみなさま、情報を提供してくださったみなさま、
そしてこのブログを読んでくださったみなさま、
どうもありがとうございました。
日本全国のその地に根ざしたものづくりや食づくり、活動を応援する活動は、
引き続き、新しいかたちで続けていきますので、どうぞご期待ください。
黄金(こがね)生姜
アジア南部が原産と考えられ、
3世紀頃には日本でも栽培が始まっていたといわれる、生姜。

お寿司に天ぷら、冷奴、鍋などの和食に欠かせない香辛料であり、
風邪に効くという言い伝えもある食べ物です。
というのも、生姜に含まれる"ジンゲロール"という成分は、
体内に入ると免疫力を強化し、細菌に対する殺菌力があるといわれているのです。
また、"ショウガオール"という成分には、
血管を拡張して血行を良くし、体を温める効果があるのだとか。
さて、そんな生姜の生産量日本一の高知県へ
10月下旬にお邪魔すると、辺り一面に緑の生姜畑が広がっていました。

高知県は年間の日照量と降雨量がどちらも高く、
高温多湿な気候が生姜の栽培に適しているそう。
「生姜はとてもデリケートでワガママなんですよ。
水を欲するけれど、同時に水はけがよい土壌じゃないといけません」
収穫したばかりの生姜を手に教えてくれたのは、
土佐山田町にある、坂田信夫商店のTさんです。

生姜は畑が湿り過ぎていると病気になりやすいため、
畑には若干傾斜がつけてあるそう。
それでも毎日水の管理が必要で、
逆に水不足の際にはキレイな地下水を散布してあげるといいます。
また、生姜は菌に弱く、畑に入る際には靴を履き替えるか、
靴カバーをするなど、徹底した管理がされていました。
さて、収穫が始まったばかりの畑には大勢の人が集まり、せっせと作業中です。
先述したように繊細な生姜は、機械で収穫するのではなく、
手作業で土の中から引き抜き、
一つひとつ人の手によって土や根っこが取り除かれていました。
「去年は雨が全く降らず、今年は雨と台風の被害がありました。
自然が相手なので難しいですが、安定した生姜づくりを目指しています」
Tさんは、農業高校を卒業後に新卒で坂田信夫商店に入社。
今年で9年目になりますが、
一部の生姜畑を任せられた、若きリーダーです。
1947(昭和22)年創業の坂田信夫商店は、
生姜の栽培・加工・販売を一貫して行っている、生姜専門メーカー。
農業の担い手不足が叫ばれているなか、毎年新卒採用もしており、
若手が活躍している珍しい農業法人といえます。
従業員数も277人と多いことに驚きながら、
会社運営の秘訣を社長の坂田悟郎さんに尋ねてみました。
「自分たちで売り場を確保するために地方を回って、
今では47都道府県すべてに生姜を卸しています。
初めは契約農家さんに栽培を頼んでいましたが、
彼らの高齢化にともない、今では自分たちでも作るようになった。
若い人たちが頑張ってくれていますよ」

実は坂田信夫商店の作る生姜は、
「黄金(こがね)生姜」と呼ばれるオリジナルの生姜。
繊維が少なくておろしやすく、鮮やかな黄金色が特徴です。
また、一般的な生姜(大生姜)が変色するのに対して、
時間が経過しても色が変化しません。

さらに、辛みが強く香りも高いのですが、調べてみると、
辛み成分"ジンゲロール"と香り成分"ショウガオール"の
どちらも通常品種の倍以上あることが分かったそう。
坂田信夫商店では、化学肥料を極力減らして、堆肥や有機質の肥料を使用。
農薬の削減のために黄色防蛾灯を用いて害虫を予防するなど
独自の栽培方法で、安心・安全な生姜づくりに取り組んでいます。
そして、収穫された生姜は、24時間365日、
13~15℃、湿度60%という管理体制のもとに保存され、
品質とおいしさを保ちながら
約14ヵ月をかけて徐々に出荷されていくといいます。
「生姜はマイナー作物ですが、
色味や香り、味などの変化をつけることで他との違いを生み出しました。
また、生の生姜がたっぷり入ったしょうがポン酢など
生姜屋だからこそできる加工品を作って、
付加価値をつけることで勝負していきたいですね」
偶然発見された突然変異の生姜に可能性を感じ、
研究開発を繰り返して、黄金生姜を商品化させた坂田信夫商店。
農家の高齢化をただ憂うのではなく、
直営農園を増やして社員で生姜の栽培を行っている姿は、
農業とビジネスの両方のセンスを兼ね備えており、
今後の農業の未来を示しているようでした。
※Café Meal&MUJIでは、黄金生姜を使った
「まるごとジンジャエール」を提供しています。
甘みがありながら、黄金生姜のピリッとした辛みのある味をぜひご賞味ください。

南魚沼産コシヒカリ
新潟県南魚沼市。

言わずと知れた、日本有数の米どころです。
日本穀物検定協会の米食味ランキングでは、
魚沼産コシヒカリが25年連続「特A」を獲得するほど、
品質には定評があります。

そのおいしさの秘訣はどこにあるのでしょうか?
黄金色に輝く稲穂が眩しい10月半ば、南魚沼市を訪ねました。

「四季がはっきりしているので、冬は豪雪地帯ですよ。
その豊富な雪解け水が、おいしいお米の鍵なんです」

清々しい笑顔でそう話すのは
魚沼伝習館の理事長、坂本恭一さんです。
今の季節は想像するのも難しかったのですが、
この界隈は冬には数メートルの積雪が当たり前なんだそう。

この冷たい雪解け水は、土砂をつたって、
山のミネラルを田んぼにもたらします。
そして、昼夜の寒暖差。
昼間光合成で作られたデンプンは、夜間穂に蓄えられるのですが、
夜も気温が高いとデンプンを消耗し、食味が落ちてしまうといいます。
実際に訪れた10月半ばも、日中は陽射しが暑く感じられましたが、
夜は一気に冷え込み、布団1枚では寒さを感じるほどでした。
「"豊富な雪解け水"と"昼夜の寒暖差"。
これこそがコシヒカリの最適生育条件に適っているんです」
坂本さんはおいしさの秘訣を、そう語ります。
この表情豊かな自然に魅了された坂本さんは、今から18年前、
50歳の時に、東京から南魚沼市へ移住されました。
魚沼の自然と伝統・文化を、後世まで引き継いでいきたい。
そう考えた坂本さんは、様々な学習体験を実践する場として、
「NPO法人 魚沼伝習館」を発足。
しかし、活動を通じて地域の魅力を発信するも、
坂本さんが直面したのは、高齢化によって手放され、
荒れ果てていく田畑の姿でした。
 ※右手前が、休耕田。左奥は収穫後の田んぼ
※右手前が、休耕田。左奥は収穫後の田んぼ
「いくら魚沼産のブランドがあっても、
実態は農業だけで食べていくことは難しいんです。
食べていけなきゃ、後継ぎも生まれませんから」
実際作っている魚沼産のお米の総量よりも、市場には多くの魚沼産が出回っているそう。
つまりそれだけブレンドされてしまっているため、
本来の味がきちんと伝わっていない可能性があります。
また、消費者に届くまでに、様々な仲介業者を介する食品業界において、
末端の農家さんの収入は微々たるものなんだそう。
一生懸命、おいしいお米を作っても
報われない農家さんの実情に奮起した坂本さんは、
独自の販路開拓に立ち上がります。
農家さんと直接契約し、徹底した栽培上のデータを管理。
ホテル、飲食店、高級スーパーなど、真に価値を理解してくれる先にしぼって、
魚沼産ではなく、さらにエリアを限定した南魚沼産として直接販売しています。

また、積極的に移住者の受け入れも支援し、
耕作放棄地、休耕田の復活にも余念がありません。
その際に徹底しているのが、
農業に携わる移住者に、経営計画を描かせること。
そうすることによって、自走していくためには、
どれだけの品数・数量が必要なのか、どんな販路が必要なのかなどを
理解した上で、農業に取り組んでもらえるようになると話します。
「お米のみならず、魚沼には脈々と引き継がれてきている食文化がたくさんあります。
例えば、裏山に行けば、たくさんの山菜が生えていますし、
これらの資源を活かしながら、生計を立てていくことは可能だと思っているんです」

日本の食文化を伝えていきたいと話す坂本さんは、
こうも付け加えられました。
「多様化する社会において、食文化を選択するのも自由ですが、
まずはその実態を知ってほしい。
そして、若い人が専業でも農業をやっていけるよう
レールを敷いてあげることが、
私たち世代の仕事だと思っています」
南魚沼産コシヒカリの新米は、
モチモチとしていて風味が良く、冷めてもおいしく食べられます。

「酒のつまみにもなるお米!」と地元の人に太鼓判の味は、
11月度のFound MUJI Marketでもお買い求めいただけます。
寄磯の味をよりいっそうおいしく
「よかったら食べてみてください」
お会いして早々、出していただいたワカメを口にすると、
そのシャキシャキとした食感に驚かされました。

「噛みごたえのある食感!おいしいですね!」
思わず感嘆の声を上げてしまいましたが、それもそのはず。
「市場の多くのワカメは、増量のために塩と水を入れて出荷されているんですよ。
だからどうしても、ふやけてしまっている」

マルキ遠藤商店の代表で、漁師の遠藤仁志さんが、
日焼けした笑顔で、そう教えてくれました。
遠藤さんの手掛けるワカメは伝統のしぼり製法。
できるだけワカメの色合い、食感、味わいを保つために
適量の水と塩をまぶす、実直なワカメづくりをされています。

三陸海岸の南端に位置する牡鹿(おしか)半島、
その東岸に位置する寄磯(よりいそ)浜に、マルキ遠藤商店はあります。

「この辺りは、陸の孤島なんて呼ばれているんですよ。
石巻で知らない人もいるぐらいですから」

遠藤仁志さんの奥様で、マルキ遠藤商店の総務統括部長の
遠藤由紀さんは、寄磯生まれの寄磯育ち。
仁志さんは、婿養子で迎えられた3代目。
黒潮と親潮がぶつかり、海流の激しい三陸は、
海藻類全般をはじめ、アワビやウニ、ホタテなど貝類の産地としても有名です。
なかでも三陸の名物としても知られているホヤは、
キムチにもよく合うことから、お隣韓国にも多く輸出されていたそうです。

「水が冷たくて波が荒いから、海藻も貝も必死に生きようとする。
それで身が引き締まるじゃないでしょうか」
仁志さんは、おいしさの秘訣をそう語ります。
しかし、そんな漁が復活できたのも、
ホタテは昨年、ホヤは今年の話。
「ここにも大きな津波が来ましてね。
今ここにいられるのも、ご先祖様が救ってくださったからだと思っています」
仁志さんと由紀さんは、壮絶な3.11の日のことを
ゆっくりと話し始めてくれました。
ヒジキの作業日だったその日。
たまたま従業員の一人が、
お彼岸が近いのでお墓の掃除をしたい、と言い出したことをきっかけに、
いつもより早めに作業を解散した後、東日本大震災が寄磯を襲いました。

大きな揺れから間もなくして、
「津波が来る」というアナウンスが入ります。
「早く避難しないと!」
急かす由紀さんに対し、
大切な資料などを避難させなくてはと、事務所内の整理を始めた仁志さん。
かつて襲った三陸地震の時の津波は20㎝ほどだったという記憶が
仁志さんの頭をよぎったそうなのです。
たまたま工場に居合わせた息子の身を守るため、
由紀さんは、先に息子を連れて小学校に避難します。

そして、その間に津波は工場を襲いました。
仁志さんは飲まれ、流されていきました。
津波に一面飲まれていく様子を、避難所から見ていた由紀さんは、
仁志さんの最悪の事態も覚悟したといいます。
「その時に、たまたま流れてきた船に乗っかることができたんです。
波が落ち着いた後、なんとか陸まで泳ぎ切りました」
そう話す仁志さんはその後、なんとか避難所までたどり着き、
由紀さんたちと奇跡の再会を果たしたといいます。
早めに解散していた工場の従業員も全員、無事でした。

以来、「神様に助けられた命、寄磯のために尽くそう」
と、決意された遠藤さんご家族。
仁志さんは、寄磯の復興の窓口として精力的に活動し、
震災から1年後には、新工場で操業の再開を実現します。

石巻でも1、2を争うほど、早い復興だったそうです。

同じ場所での工場の再建にためらいはなかったのかと聞くと、
「ここは自分たちの土地。
海のモノを扱うのに、海のそばにいるのは当たり前」
と、まったく迷いはなかったと話してくれました。
そんな父親の後ろ姿に、娘さんも心動かされます。
「ちまたでは漁業に興味を持っている人は皆無でした。
自分が関わることで、なんとか後につないでいければと思ったんです」

そう話す次女の遠藤裕子さんは、
震災時に通っていた一般大学を卒業後、美大への進学を決めました。
「デザインの力で、商品の魅力のみならず、
食べ方や地域の魅力まで発信していきたかったんです。
親が被災しているのに美大に進学したいって、
頭おかしくなったのか!って言われましたけどね(笑)」
裕子さんは、美大内でプロジェクトチームを発足し、
寄磯の海産物を使った、商品開発に乗り出します。
必要経費は、みやぎ産業振興機構が公募する
「宮城・仙台富県チャレンジ応援基金事業」から助成金を獲得。
現地に通うなかで、
チームメンバーからも寄磯の香りに感嘆の声が聞かれたことに、
裕子さんや地元は自信を深めていったといいます。
「それまで自分の地域の仕事や商品に、
自信を持っていない人が多かったんですよね。
漁師や水産業のイメージを変えていきたい」
こうして裕子さんたちによって生み出された、新しい商品がこちら。

寄磯を代表する5つの海藻が味わえる商品です。
光で中身が傷まないよう、箱で包まれ、
都会生活者でも気軽に食べられるよう、
2人前の分量で梱包されました。
その土地での食べ方をまとめたレシピも同梱。

パッケージには、
「寄磯をよりいっそうおいしく」
とシャレの利いたコピーも添えられました。
「少量でパッケージしていく方が、大変なんですけどね。
娘の想いに応えるために、がんばっています」
遠藤ご夫妻は、これまた娘さんがデザインされたロゴマークを手に、
満面の笑みで、そう話してくれました。

震災をきっかけに、それぞれが役割を果たしながら
動き始めた、マルキ遠藤商店。
寄磯の味が、よりいっそうおいしく感じられたのも、
彼らの想いが深まった証なのかもしれません。
[関連サイト]マルキ遠藤商店「YORIISO」リンク
よりいっそうおいしく YORIISO![]()
地域と歩む、とうふ工房わたなべ
日々、食卓に並ぶことの多い「豆腐」。

原料の大豆は良質なタンパク質や脂質の含有量が多いとされており、
栄養面で優れた健康食品といわれています。
かつては全国各地に小さな豆腐屋がありましたが、
戦後、食の工業化が進み、大規模メーカーが台頭し、
豆腐も量産化の時代になりました。
「全国の豆腐屋は1万軒を切っていると思いますよ。
それでも、他の食品に比べると生き残っている方かもしれませんね」
埼玉県ときがわ町にある、
「とうふ工房わたなべ」の代表・渡邊一美さんにお話を伺いました。
確かに、全国の醤油メーカーはおよそ1500社、
味噌メーカーはおよそ1000社というから、
豆腐屋の数が多いことが分かり、
それだけ豆腐が身近な食材であることがうかがえます。
「戦前までは皆、国産地大豆を使っていましたが、
戦後に食料統制が解けて、安価な外国産大豆を使うようになった。
そうなると他社との違いを出すのも難しく、
価格競争で勝負するしかなくなり、面白くなかったですよね」

とうふ工房わたなべでは、お客様からの要望で、
15年ほど前から国産地大豆を使うようになりました。
当時、食品添加物や魚の水銀汚染など食への不安が高まるなか、
東京・武蔵野市の境南小学校では、
"作った人の顔が見える給食づくりを"実践。
ときがわ町の隣の小川町で作られている有機野菜を扱うようになり、
境南小学校の給食担当者が小川町に来た際に、
渡邊さんのところにも立ち寄っていたそうです。
「有機農家の金子さんのお話はその時から噂で聞いていましたが、
後に縁があって金子さんと出会って、大豆づくりをお願いしたんです」
全量買い取りの契約でしたが、
実際に小川町の在来大豆(青山在来大豆)を使ってみると、
それまで使っていた大豆と同じようには、うまく豆腐づくりができなかったといいます。
渡邊さんは3年かけて、青山在来大豆での豆腐づくりを成功させました。

「青山在来に含まれる糖質は申し分がないのですが、
たんぱく質が少ないから固まりにくいのです。
単純な話、その分大豆を多く使えばいいのですが、
それだと豆腐自体も高くなってしまう…」
それまで一丁80円で販売していた豆腐が、
在来大豆を使うことで一丁230円に。
売れないという不安はなかったのでしょうか?
「最初は35人の仲間が『買い支えるよ!』と言ってくれていたんです。
そのネットワークがどんどん広がり、何百人になって、
その人たちが友人を連れてお店に来てくれるようになりました」
こうして、「とうふ工房わたなべ」は、
製造・直販スタイルを確立させたのでした。

お店の奥にある工房では、なんと深夜2時頃から仕込みが始まります。
今回、私たちが取材に伺った午前9時頃にはすでに仕上げの作業に入っていました。
豆腐の製造方法は、大豆をすりつぶしたものを水と合わせて煮て、
豆乳とおからに分け、豆乳ににがりを加えて固めるというもの。
「豆腐づくりのポイントは"一臼 二釜 三大豆"ですよ。
これは江戸時代から変わらない」
渡邊さんいわく、まず大豆をきちんとすりつぶせているか、
次に大豆の煮加減、そして最後に大豆に関する知識が重要だそう。
「製造業は商品力が命です。そこがゆがまないようにしていかないと。
また、いいものをリーズナブルに提供するには、直接販売しないとやっていけない」
お店には開店と同時にたくさんのお客様が、
作り立ての豆腐を買いに訪れていました。

お店では、豆腐に加えて、地域で作られた野菜や加工品を販売し、
豆腐スイーツなどをその場で味わことができます。
また、製造工程で出るおからや仕込み水である地下水を
無料で持ち帰ることもでき、人気を集めていました。
さらに、「とうふ工房わたなべ」では、
より多くのお客様に商品を届けたいと、数年前から移動販売も行っています。

週1回のスタッフとのコミュニケーションを楽しみにしている
年配のお客様も多いといい、
顔の見える新たな販売方法もしっかりと地域に根づいていました。
「そこでしかできない3つの"しか"(原料・製造方法・販売方法)を武器にすれば、
誰でも勝負できるのではないでしょうか。
わざわざ県外から来てくれた人が、どこでも買えるものは買わないですから」
「とうふ工房わたなべ」では、渡邊さんの代になり、
それまで家族経営で5~6人で運営していたところから、
現在では、50人のスタッフを雇うまでに成長しました。
また、周辺地域で作られている大豆の大方は
渡邊さんが買い取っているといいます。
「生産者とお客様と顔見知りになれて、両者に喜んでもらえるのがうれしいですね。
地域が活性化しないのは、そこに雇用がないから。
小規模の豆腐屋が元気になれば、もっと地域が活性化するはず」

渡邊さんのところで豆腐づくりを学んだ人が
将来のれん分けで独立し、地域に豆腐屋が増えることが夢と、
最後に語ってくださいました。
業界は問わず、「とうふ工房わたなべ」と地域の取り組みに
学べることは多いのではないでしょうか。
美人になる野菜、ルバーブ
「ルバーブ」という野菜をご存じですか?

肉食中心の欧米では、食物繊維を摂取するために、
食卓に欠かせない野菜として好まれています。
野菜といっても、ジャムに多く用いられるなど、使われ方は果物のよう。
パイにするととてもおいしいことから、「pie plant」とも呼ばれているそうです。
そんなルバーブは、寒冷地に育つ作物で、
日本では長野や北海道で育てられています。
大正時代に、避暑地を求めて野尻湖(長野県信濃町)を訪れた
外国人宣教師によって伝えられ、栽培が始まったといわれています。

6月上旬に野尻湖を訪ねると、そこには
大きな葉っぱを一面に広げるルバーブ畑の光景が広がっていました。

「年に数回、追肥するだけで、春と秋の2回収穫できる多年草です。
冬の間は雪の下で眠っているのですが、雪が解けるとまた大きくなるんです。
ルバーブの生命力には驚かされますよ」
野尻湖畔でルバーブを育てる
信州黒姫高原ファミリーファームの農家さんが教えてくださいました。

かつて、株分けして各家に植えられたことにより、
今でもこの辺りのほとんどの農家で栽培されているそうです。
ただ、昔はその使い道が分からず、
ましてや名前すら定かではなかったんだとか。
そんな折、ブルーベリーに代わる信濃町の特産品を発信しようと、
注目を浴びたのがルバーブでした。
「昔、住んでいたオーストリアでは、当たり前のように食卓に並んでいたルバーブ。
信州にそんななじみある野菜があるのであれば、使わない手はないと思いました」

そう話すのは、野沢温泉村で
「ホテルハウスサンアントン」を営む、片桐逸子さんです。
風情ある温泉街に、良質な泉質の湯が湧く日本屈指のスキーリゾートには、
冬季には多くの観光客が訪れます。
ただ、どうしても来訪者が落ち込んでしまう夏季に、
なんとか雇用を生み出すことができないかと、片桐さんが考えたのが、
信州産の農産物を生かしたジャムやジュースなどの加工品でした。

「長野の夏には、たくさんのおいしいフルーツがあるんですよね。
一度にたくさんは作れないけど、
少しずつでも多品種のものを作っていけば、仕事もなくならない」
もともと山菜加工場として使用していた食品工場を使って、
職人たちとジャムづくりをスタートしました。
現在、ハウスサンアントンが手掛けるジャム・ジュースは50種類以上。
そのほとんどが、信州産の農産物を使ったものです。
なかでも上述のルバーブは、繊維質が豊富で、
ビタミンCやカリウム、カルシウムも多い健康野菜。

「食べるとお通じが良くなり、デトックスできる
"美人になる野菜"とも呼ばれているんですよ」
ハウスサンアントンでのジャムづくりは、
オーストリア仕込みの手づくり製法です。
ポイントは、高温で、短時間で仕上げること。
素材感とルバーブのみずみずしさを残すことができるそう。
実際に、できたてほやほやのジャムを
ヨーグルトに混ぜてコンポートとともにご賞味させていただくと、
さわやかな酸味と香りが口いっぱいに広がりました。

「どんなフルーツにも固定観念を持たずに、
その時の素材の味を引き出すよう心掛けているので、毎年味が違うんですよ。
ほら、ワインだってそうでしょ」
片桐さんは、ルバーブのジャムは
月日を置いた方が、味が丸くなると話します。
仕込んだ年ごとのジャムを味わわせてもらうと、
年を経るごとに、確かに味がまろやかに…。

ジャムを食べているというよりも、
果実をそのまま食べているような感覚です。
こうしてスキーのオフシーズンにも、野沢に雇用を生み出し、
信州産の農産物に光を当て続ける、ハウスサンアントンのジャム&ジュース。
ホテルのお客様の朝食にジャムを提供するほか、
夕食の料理やホテル併設のカフェで販売するジェラートにも使用されるなど、
うまく循環していっていました。
信州の自然と、オーストリア仕込みの技が生み出した味は、
Found MUJI取り扱い店舗および、
7月11日(金)~20日(日)の10日間限定で販売予定の、
「Found MUJI Market」でもお買い求めいただけます。
白い醤油
愛知県三河地区のうどん屋さんでは、
つゆを黒と白の2種類から選べるという話を耳にしました。

なんでも愛知県には、黒い醤油と白い醤油が存在するとか。
白い醤油とは、淡い琥珀色で、
ほんのりとした甘みと独特な香りが特長の醤油のこと。

通常、大豆と小麦を半々の割合で仕込む醤油に対して、
黒いたまり醤油は大豆の割合が多く、
白醤油は原料のほとんどが小麦という非常に珍しいものです。
醤油というと黒いイメージを持っていた私たちは、
1938年以来、白醤油を造り続けている、日東醸造株式会社を訪ねました。
「色みを気にする和食の調理において、
料理人が欲したことが白醤油の始まりではないかと考えられます。
真っ黒のたまり醤油文化だからこそ、真逆の白醤油が生まれたんだと思いますよ」

代表取締役社長の蜷川(にながわ)洋一さんに
白醤油の歴史について伺うと、そんな答えが返ってきました。
醤油を白く仕上げるためには、一般的な醤油の醸造過程で行う
「櫂入れ(かいいれ)」というかき混ぜる作業を行わず、
3~4ヵ月の間、静かに寝かせて置きます。
それは空気と触れて酸化することを防ぐためで、
琥珀色を保つ目的の一つだといいます。
加えて、仕込んでいる間に温度を上げないことと、
光に当たらないようにすることも、白醤油の醸造上のポイントだそう。

日東醸造では、「他にないオリジナルの白醤油を作ってみたい」という先代の思いから、
平成6年、国産小麦を通常の2倍量使用して、
大豆を使用せずに仕込む、白醤油を発売しました。
三河地方では、昔から醤油のことを"たまり"と呼んでいたそうで、
三河の白醤油という意味で「三河しろたまり」と命名。
「実は、うちの"しろたまり"は厳密にいうと、醤油ではないんです。
原料に大豆を全く使っていないので、農林水産省の規定で、
醤油と呼ぶことはできずに、"小麦醸造調味料"と表記しています」
農水省の指摘を受けて、蜷川さんは大豆を入れるか、
醤油表記をなくすかの2択を迫られました。
迷った蜷川さんは付き合いの長いお客様に手紙を出し、意見を仰いだそう。
「醤油屋が醤油ではないものを造るのに、少なからず抵抗があった。
それでも多くのお客様が、名称は変わっても中身を変えないでほしい
と望まれているのが分かりました」
最終的に決め手となったのが大豆アレルギーのお客様からの
「やっと見つけた大豆不使用の醤油をやめないで!」
というひと言だったといいます。
そんな「三河しろたまり」を醸造しているのが、
本社のある碧南市から車で1時間強の山間にある、旧足助町(あすけちょう)。

蜷川さんが醸造において重要な水を探し求めていたなかで巡り合った場所で、
標高720mという夏場でも冷涼な気候も、
白醤油をより淡く仕込むのに最適でした。
「最初は水だけ運び、碧南市の本社で仕込むつもりでした。
それが、峠から見た風景に惚れてしまって。
どうしてもここで仕込みたくなってしまいました」
ただ、この場所で実際に醸造をするには、越えなければならない壁がありました。
それは、旧足助町の住民たちの了承です。
「地域の自治会に出て説明して回りましたが、
どうにも怪しまれましてね。
どうして2時間近く離れた醤油屋が、わざわざここで仕込むのかって」
蜷川さんは1年の間に何度も足を運び、交渉を続けたそう。
そして、最後にはマイクロバスを出して、
住民たちに碧南本社の蔵の見学に来てもらったのです。
そこで、ようやく住民たちの理解を得ることができ、
16年前から、「足助仕込蔵」での醸造がスタートしたのでした。

実はこのピンク色の可愛らしい木造校舎が、醸造蔵。
昭和62年に廃校になった校舎を使わせてもらっています。
一見普通の校舎のようですが、中に入ると、
醸造用の杉樽がズラリと並んでいました。

今ではすっかり地元の人ともなじんだ蜷川さんたちは、
平成14年から、仕込み蔵周辺で畑を借り、小麦の栽培も始めました。

毎年、6月下旬には足助仕込蔵の校庭で、
地元の人や関係者、お客様を集めて、
「三河しろたまり」を使った料理を振る舞う収穫祭を実施。
20世帯・50人ほどの町に、今では400人が集うイベントになっているそうです。
「子どもたちが離れていってしまった町に、収穫祭をキッカケに人が戻ってくる。
地元のおじいちゃん・おばあちゃんが、子どもや孫たちに会える機会が増えたと言って、
喜んでくれることが何よりうれしいですね」

先代の想い、お客様の想い、旧足助村の住民たちの想いなど
たくさんの想いが詰まった、日東醸造の「三河しろたまり」。
煮炊き料理を中心に、卵料理との相性がとてもよく、
白身魚のお刺身やカニ酢ともよく合うそうです。
素材の色を消さずに風味をもたらしてくれる万能調味料は、
目でも味わう日本料理に欠かせないものかもしれません。
発酵と人生の設計図
宮崎県のほぼ中央にある綾町は、「有機農業の町」として知られており、
私たちもキャラバン中にその町づくりを取材しに訪れた場所です。
そんな綾町で造られているお酢があると聞き、生産者を訪ねました。
Found MUJI でも取り扱っている「綾の有機黒玄米酢」です。

「うちのお酢は代々、酢杜氏によって引き継がれてきたものです」
大山食品株式会社の4代目社長・大山憲一郎さんに
お酢づくりの現場をご案内いただくと、
そこには辺り一面に並んだ瓶(かめ)の数々が目に飛び込んできました!
南国の太陽が降り注ぐ南斜面にあることに加え、
雨よけのアルミ傘が光を反射し、とても眩しい光景です。

「この瓶の中に、綾産の有機玄米と綾の地下水、黒麹、種酢を
入れるだけのシンプルな製法ですが、
昭和5年の創業以来変わっていないやり方です」

大山食品では、この瓶仕込みの際に、焼いた状態の備長炭を入れるそう。
それは瓶内を発酵しやすい環境にするための工夫だとか。
また、瓶の蓋には通気性の良い米袋を使用し、
その上に5円玉を置くことで、その色の変化で中の発酵状況を
見極めているといいます。
「宮崎の焼酎蔵の多くも瓶を仕込みに使っていますが、
お酢づくりにはこの瓶がもってこいなんです。
瓶の中で最初アルコール発酵が起こると、アルコールは軽いので自然と上に行き、
次に酢酸発酵すると、酢酸は重いので下に行く。
下の部分がとんがった瓶の中で自然と対流が起こり、発酵が促されるのです」
さらに、屋外に瓶を置くことで、昼と夜との温度差が
味に深みとコクを与えてくれるんだそう。
瓶から直接汲んだ黒玄米酢を味見させていただくと、
お酢特有の鼻に抜けるようなツンとした感覚はなく、
とてもまろやかで、コクのある優しい味わいでした。
大山食品の"黒玄米酢"とは、「黒麹」を使ったお酢のこと。
一般的にお酢を仕込む際に使う「白麹」だと、さっぱりとした味の仕上がりに、
大山食品の使う「黒麹」だと、コクのある仕上がりになると大山さんは話します。
また、お酢は春と秋に仕込んで、瓶の中で6ヵ月発酵させ、
さらにタンクに移してからも最低6ヵ月熟成させます。
そうすることで、さらに味がまろやかになるのだそう。
ところで、大山食品の本社は綾町のお隣、国富町にあります。
てっきり「有機農業の町」だから、綾町に工場を構えたのかと思っていたら、
こんなお話を聞くことができました。
「40年ほど前に綾に工場を移転したのですが、
それはお酢の仕込みに欠かせない"水"を求めてきたからです。
当時の綾は過疎化が進み、『夜逃げの町』といわれていたくらい。
それでも『有機農業の町』としての方向性はありましたから、
原料にこだわりのあるお客様からの依頼とも一致して決めました」

今年から会社として、農業の本格スタートもした大山食品。
「目標は、すべての原料を自分たちで作って、加工、販売もすることですね」
そう話す大山さんは、着々と自分の夢を実現させていました。
20歳でお酒の魅力にハマり、将来お酒造りをしたいと決めた大山さんは、
現在、どぶろく造りも手掛けています。
そのための製造や販売を行う施設も作り、一歩一歩前へと進んでいます。
そんな大山さんがいつも持ち歩いている手帳には、
○歳で○○をするという、明確な人生の設計図が描かれていました。
「大きな将来の絵を描いて、それを繰り返し見ることで
やりたいことを潜在意識に摺り込みます。そうすると自然と行動に移せる。
発酵食品を極めて、世の中に貢献するのが私の人生の目標です」
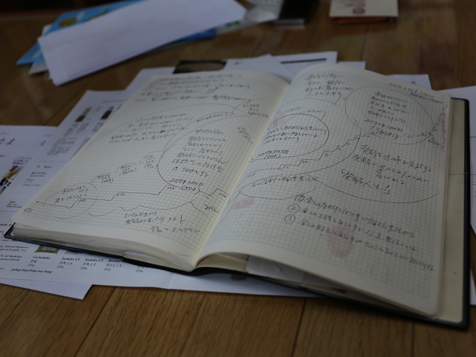
お酢の伝統製法と味は守りながらも、
自らの道を決めて、歩み続けている大山さん。
すっきりと澄んだ「綾の有機黒玄米酢」の味は、
まっすぐとした眼差しで前を向いている、
大山さんの信念そのものかもしれません。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
里山の小規模循環
ある日、我が家に一つの贈り物が届きました。
箱を開けると、そこには真空パック化されたお米が。

洗練されながらも、気張らないパッケージは、
1合、2合、3合と分量別に分けられ、
人数や用途に合わせた使い手への配慮を感じました。
さらに、真空パックだから米の鮮度が長期に保たれるので、
もしもの時への備えにも、もってこいです。
きっとデザイナーとのコラボレーション商品だろう、と思ったら、
生産者の所在地は、熊本市内から1時間ほど北に向かった山鹿市。
「MOYAIの米~里山再生プロジェクト~」
と名付けられたそのお米は、熊本の里山で作られたものでした。
以来、このお米のことが気になっていた私たち。
熊本に立ち寄った際、念願かなって生産者のもとを訪ねることができました。
「お米でもアイスクリームでも、私のやりたいことは一緒なんです。
中山間地で少量しか作られない農産物を、
加工して付加価値をつけて販売すること。
この小規模循環型のビジネスモデルこそが、
日本の里山を再生していく術だと思っているんです」

そう話すのは、(株)パストラルの代表取締役、市原幸夫さん。
お話にあるように、本業はなんとアイスクリーム屋さんで、
平成9年より、小規模多品種の農産物を用いたアイスを作り続けています。
「イタリアではいろんな味のジェラートがありますでしょ。
日本でも、ご当地アイスが産業になりうるって思ったんです」
市原さんの狙い通り、
各地の道の駅で見ないことはないほど、ご当地アイスは一般的になり、
市原さんも年間150種類を手掛けるほどです。
一方、ふと地元を見返してみた時、
広がる休耕田に、危惧を覚えたという市原さん。
「地元には長年、無農薬の合鴨農法で米作りに取り組む
農家さんたちの姿がありました。
ただ、素晴らしい取り組みなのに、農家には後継ぎがいない。
状況を打破するためには、循環化する農業にしなくちゃいけない」
こうして市原さんは、地元の66~83歳の5軒の農家さんと、
息子夫婦たちとともに、「あいがもん倶楽部」を結成。
それまで、他産地の米と混ぜられていたり、自家消費されたりしていた合鴨農法米を、
「MOYAIの米」としてデザインし直し、世に発信していっているのです。
「都心には人がいます。
里山にはその人の心と体を育んだり、癒やしてくれたりするものがたくさんあります。
私は、都心と里山のパートナーシップを手掛けていきたい」
そう話す市原さんは、お米のパッケージにQRコードを付与し、
米作りの様子を動画で伝える仕掛けも組み込んでいました。

そして、米作りに興味をもってもらった方には、
実際に米作りに参加してもらえるグリーンツーリズムも。
栽培に使った合鴨も食肉として出荷し、本格的に特産化を目指します。

「MOYAIの米」には、里山の現状を知ってもらい、
里山が今後も日本の食糧供給基地であり続けられるようにとの
願いが託されていました。

ちなみに"MOYAI"とは共同で一つのことをするという意味。
市原さんは、地域の共同体は、「家族」がベースにあると話します。
「100年、200年続けていくためには、土壌にあるのは家族経営。
企業的に大規模な生産効率を追求するのではなく、
家族単位で、小規模循環を追求することが、
里山の豊かで幸せな暮らしの再生につながると思っています」
現に市原さんの傍らには、
アイスクリームの企画・販売に携わる長男夫婦と、
新規就農した次男夫婦の姿がありました。

一度は上京した息子さんたちが帰郷したのも、
父、幸夫さんの信念に共感を覚えたからといいます。
こうして親子が自然な形で仕事を営む姿こそが、
里山の持続可能な暮らしを実現していく秘訣とも感じました。
市原さんのいう"小規模循環型"のビジネスが
各地で行われるようになれば、
きっと日本の未来は明るいのではないでしょうか。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
300年続くお酢
和食の味付けの基本とされる調味料「さしすせそ」。
そのうち、「せ」醤油と「そ」味噌は日本独自のものですが、
「さ」砂糖と「し」塩、そして、「す」酢は世界中に存在するものです。
なかでも酢は、世界各地で飲まれるお酒との関わりが強いことをご存じでしょうか。
「酢酸菌(さくさんきん)は、アルコールを餌に酢をつくるんです。
ですから、世界各地のお酢は、その地のアルコール文化との関係が深いんですよ」

そう教えてくださったのは、福岡県大川市の老舗蔵、
庄分酢の14代目、高橋一精さんです。
思えば、
ワインの産地フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルでは"ワインビネガー"、
ビールの本場、イギリスやドイツでは"モルトビネガー"、
アメリカでは"シードルビネガー"と、
各地のお酒文化によってお酢の種類も様々。
フランス語で酢を意味する「vinaigre」とは、
「vin=ワイン」と「aigre=すっぱい」を合わせたもので、
「お酒をすっぱくしたもの」という意味でした。
当然、日本酒文化の日本では「米酢」が造られており、
酢蔵には、かつて酒蔵だったところも多く存在します。
庄分酢もその一つ。

筑後川の水に恵まれ、豊かな大地の米どころの筑後で、
庄分酢が産声を上げたのは、1711年のこと。
造り酒屋の4代目、清右衛門がお酢造りを始めて以来、
300余年にわたって、お酢を造り続けてきているのです。
「高橋家で代々、引き継がれてきている家伝書がありましてね。
今も"玄米くろ酢"は、この製法にのっとって造っています」
高橋さんがそう話すのは、昔から使われ続けている
大甕(カメ)仕込みのくろ酢のこと。

以前、鹿児島県福山町で見た壺畑の光景を思い出しましたが、
それよりも、一つひとつのカメのサイズが大きいことが特徴です。
「大きい方が、中の温度が一定に保たれやすいんです。
温度変化に対応するための先人たちの工夫でしょう」
カメが半分、地中に埋まっているのも、
中の温度を一定に保つための知恵でした。
くろ酢の醸造に用いるのは、水と麹菌と、
熊本県から仕入れた有機農法の玄米のみ。
カメのなかでゆっくりと、麹菌によって米が糖化され、
その糖分をエサに酵母がアルコール発酵を促し、
カメに生息する酢酸菌が、アルコールを酢に変えていきます。

市場に多く流通する酢は、速醸法と呼ばれる製法で、
醸造用アルコールを原料に24時間ほどで造られていますが、
この静置発酵法だと3カ月ほど歳月を要します。
「静置発酵させているあいだ、黙っているわけではありません。
菌膜の状態はカメによって異なるので、一つひとつ見守りながら手入れをします。
子育てに似ていますよね」
酢職人は語ります。
その後、さらに長い熟成期間を経て、ようやくくろ酢として完成するのです。

効率を追い求めては、決して造られない酢。
その分、酢に深いコクと旨みがもたらされます。
「守るべきは守りながらも、
現代のくらしのなかで取り入れやすい酢も提案していきたい」
高橋さんがそう語る通り、庄分酢では米酢以外にも、
様々な果実から造られた酢も手掛けています。

ドレッシングやドリンク、食事の隠し味などにも重宝するりんご酢も、
有機栽培で作られたりんごのみを用いて造られていました。
 ※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます
※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます
さらに、酢の可能性を広げていきたいと、
蔵の2階を改装して、レストランもオープン。
酢を使った料理やスイーツを提供し、
酢のあるくらしを提案していっています。
「高橋家では代々、長男の名前には"清"か"精"という漢字が使われているんです。
常に、精進しながら、清らかな酢を造り続けたいと思っています」
300余年にわたり、"庄分さん"の名で親しまれ続ける酢の背景には、
頑なに守りながらも、攻め続ける蔵の姿勢がありました。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
長期熟成麦味噌
おふくろの味の代表格ともいえる「みそ汁」。
出汁、味噌に加え、具材も各家庭によって千差万別であるため、そう称されています。
このキャラバンでは各地の味噌に出会ってきましたが、
毎回新たな発見があるのが、味噌の面白いところ。
実は、味噌とルーツを同じくするといわれる醤油には
JAS(農林水産省)による規格が設定されているのに、味噌には設定されていません。
というのも、味噌はあまりにも種類が多く、
グループに分けて規格を規定するのが難しいということと、
味噌の多くが加熱殺菌をしない、いわば"生き物"であることが主な理由とか。
そんな数ある味噌のなかで、今回は大分県臼杵市で製造されている、
「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の現場にお邪魔してきました。
 ※Found MUJI取り扱い店舗で購入可能です
※Found MUJI取り扱い店舗で購入可能です
麦味噌は、かつては農家の自家用として造られたものが多く、
別名「田舎味噌」とも呼ばれており、全国に分布しています。
なかでも、私たちが全国を回った感覚からすると、
九州地方には麦味噌が多いイメージがあり、
そして、"麦味噌=甘い"という印象が脳裏に刻まれています。
しかし、なぜ九州は麦味噌が多いのでしょうか?
そしてまた、なぜ麦味噌は甘いのでしょうか?
「この辺りでは、もともとお米づくりの裏作として麦を育てていたから
麦味噌を造るようになったのだと思います。
ちなみに麦味噌が甘いのは麹歩合が高いからですよ」
そう教えてくださったのは、製造元の二豊味噌協業組合の専務理事、
渡邊郁(かおる)さんです。

「パッケージの裏を見てみてください。
原材料名のところに、原料の多い順に表示がされていますが、
麦味噌の場合、大豆よりも麦が先に書いてあるでしょ」
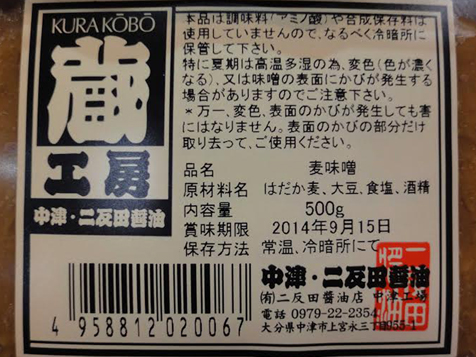
渡邊さんいわく、米味噌の場合、大豆10に対して米麹の分量が7〜8のところ、
麦味噌の場合、大豆10に対して麦麹の分量がおよそ25。
米や麦に含まれるデンプンが麹によって糖化するので、
麹に使う原料(米や麦)の量が多ければ、その分甘くなるということなのです。
さらに、一般的に米味噌の塩分が約12%なのに対して、
麦味噌の塩分は約10.5%といわれており、
麦味噌は塩分が低い分、みそ汁に入れる味噌の量が多くなり、
その分甘くなるんだとか。
では、同じ麦味噌のなかでの味の違いは何でしょう?
「『蔵づくり長期熟成 麦味噌』には、大分県産の裸麦を使用しています。
裸麦は殻がない大麦の一種なのですが、これをさらに25%削って使っています。
お酒でいう吟醸ですよね」
写真下左が削る前の裸麦で、右が削った後の裸麦。

削ることで、体積に対して麹がすみ着く表面積が大きくなるため、
麹の働きがより活発になるそう。
また、味噌になった時のくすみをなくすことも目的だといいます。
「大豆の表面の皮も取ってから使っています。
仕上がりが鮮やかな色になるのと、のどごしが滑らかになりますからね」
 (左:皮を取る前の大豆、右:皮を剥いた後の大豆)
(左:皮を取る前の大豆、右:皮を剥いた後の大豆)
続いて、こだわりの原料から実際どのように味噌が造られているかを
工場長の上野康成さんにご案内いただきました。
「味噌の品質は7割が麹づくりによって決まるといっても過言ではありません。
ある程度の量を仕込むため、機械の力を借りていますが、
良い麹が仕上がるタイミングを見極めるのは、職人にしかできません」
また、良い麹づくりのポイントは適度な水分を裸麦に吸わせること。
天候など日によって、水に浸ける時間は異なるといいます。
「私たちは味噌を造っているとは思っていません。
麹菌などの菌が主役ですから、その支援をしているだけなんです」

ちなみに、味噌の味は熟成期間によっても異なります。
一般的な麦味噌は1.5〜2ヵ月熟成させるところ、
「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の熟成期間は6ヵ月。
味噌づくりには、麹菌の他に酵母菌の活躍も外せないというのですが、
熟成期間が長いと、酵母菌が麹菌の造った糖分を餌にするため、
甘みが抑えられ、辛口の味噌ができるそう。
「口あたりがとてもまろやかな麦味噌です。
『蔵づくり長期熟成 麦味噌』は地元向けのつもりでおりましたが、
おいしいと感じた味がその人にとってのおいしい味。
ご自身に合う味を見つけてもらいたいですね」

最後に、「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の販売元である、
二反田醤油店の二反田新一さんがそうおっしゃいました。
知れば知るほど、奥が深い味噌の世界。
パッケージ裏の原料や熟成期間などを意識して、
自分好みの味噌を探してみてはいかがでしょうか?
毎日のみそ汁がもっと楽しみになるかもしれません。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
鷹の爪
とある催事場に足を運んだときのこと、
とても香ばしい香り漂う一角がありました。

その香りに引き寄せられるように集まる人だかりの中心には、
貫禄あふれる風貌の男性の姿が。

大阪堺市で100年余り、和風香辛料をつくり続けている老舗、
「やまつ辻田」の4代目、辻田浩之さんです。
「日本人は昔からほのかな香りを楽しんできました。
さらに、目でも辛みを味わってきたんです」
辻田さんが手掛けるのは、国産唐辛子を使った七味唐辛子。
それも、この時は高知県北川村で、
種から60~100年かけて育てられた「実生の柚子」もふんだんに加えた
「柚七味」の配合中でした。

その香ばしい香りと、豊かな色彩に、
自然と味覚が反応し、思わず唾液が溢れそうになります。
「唐辛子を使った食べ物といえば、何を思い浮かべますか?
漬け物、きんぴら、辛子明太子…、色々と使われていますが、
たぶん皆さん口にしているのは、ほとんどが外国産のものです」
辻田さんいわく、
現在、日本に流通している赤唐辛子の99%が外国産で、
その多くが「天鷹」に代表される中国産品種だそう。
そんななか、やまつ辻田で代々、こだわり続けているのが、
国産純粋種の「鷹の爪」。
よく耳にする名前ですが、
実は絶滅の危機に瀕している希少な唐辛子の品種なんだそう。

やまつ辻田のある大阪府堺市も、
昭和30年代までは鷹の爪の一大産地だったといいます。
ただ、複数の実が同時に収穫できる三鷹などの品種に対し、
一房ずつ摘み取る鷹の爪は、手間がかかるため採算が合わず、
多くの農家も栽培をやめてしまったのです。
そんななか、やまつ辻田では100年以上に渡り、
この鷹の爪の純粋種を守り、伝えてきているのです。
「国産の鷹の爪は香りが高い。
そして、辛みのもとであるカプサイシンは外国産辛口品種の約3倍。
香り、辛み、そして風味において、他に勝るものはありませんよ」
江戸時代の医師であり、学者であった平賀源内も、
72品種の唐辛子について解説した「蕃椒譜(ばんしょうふ)」の中で、
鷹の爪についてこんな記載を残しています。

「甚だ小さくして、愛すべき風情」
「食するには、これを第一とすべし」
そんな鷹の爪に恋していると話す辻田さんは、
その役割をこう表現してくださいました。
「名脇役。素材を汚さずに、引き立ててくれる存在」
確かに、麻婆豆腐やキムチなど、香辛料の味が強く効いたものと比べ、
日本での唐辛子の味わい方は、実に慎ましいものがあります。
千枚漬けやきんぴらごぼう、明太子にしても、
主菜の持っている本来の味を損なないほどのアクセントですよね。

さらに、そこに風味を求めるのも日本人ならではかもしれません。
唐辛子に6種もの香辛料を加えた七味唐辛子が、
日本生まれというのも、興味深い事実です。
江戸時代、江戸・両国の近く薬研堀(やげんぼり)で誕生した七味唐辛子は、
漢方薬を参考につくられ、当時は薬の一種として考えられていたそうです。
「薬味」という言葉があるように、それぞれの効能も無視できませんが、
今日まで日本人に愛され続けているのも、
その絶妙な風味のハーモニーからこそでしょう。
「ただ、それは一年中、同じじゃない。素材にはそれぞれの旬があります。
唐辛子の旬、山椒の旬、柚子の旬…。
それら原料のその時期にしか楽しめない香りを大切にしたいんです」
辻田さんがそう話す通り、やまつ辻田では旬の素材が生きるよう、
時期によって微妙に配合を変えているんだそう。

注文を受けてから七味唐辛子の配合を行うのも、
こうした理由からでした。
「モノを売るだけでなく、魂を伝えていきたい」
と話す辻田さんは、夜は地元道場の剣道師範としての顔も。

その子供たちに対する厳しくも愛情のこもった態度と、
唐辛子を語り接するときの態度が、妙にリンクしたのは、
そこにかける辻田さんの魂が同様だからなのかもしれません。
取材後、家で早速「極上七味」を、すき焼きの溶き卵に振っていただくと、
七味の香りと辛みが口いっぱいにふんわりと広がりました。

「国産鷹の爪、七味唐辛子を守り伝えていくことは、
日本の食文化を守ることです。
そして、それは自分の使命だとも思っています。」

そう話す辻田さんのつくる七味唐辛子から、
どこかやさしさを感じたのも、
辻田さんの魂が宿っていることの表れなのかもしれません。
昔ながらのレトルト食品
日本一周の道中、愛媛で立ち寄らせてもらった
西予市明浜町にある「無茶々園(むちゃちゃえん)」。

今から約40年前、
できるだけ農薬や化学肥料に頼らないみかんづくりをしていこうと、
立ち上がった生産者団体です。
そのネーミングは、無農薬・無化学肥料なんて無茶といわれた当時、
とにかく無茶苦茶がんばってみようと、名付けられたものでした。

環境にやさしいみかんづくりは、特色ある地域づくりにもつながり、
現在では、全国からIターンの若者が集まり、有機農業に取り組んでいます。
その若者のチームが、「ファーマーズユニオン天歩塾(てんぽじゅく)」です。
てんぽとは、この地方の方言で"無茶"を表し、
「てんぽなことすんな~」といえば「無茶なことしてんな~」という意味だそう。
そんな無茶々園の遺伝子を引き継ぐ天歩塾のリーダーに、
今回愛媛を再訪した際に、お会いすることができました。
村上尚樹さんは、石川県出身の32歳。
昔、バイクで全国を旅して巡るなか、
たどり着いたのが、ここ明浜町のくらし方でした。

「ここの気候風土、そして人々の距離感が心地よかったんです」
学生時代、大阪のテレビ局でアルバイトをしていた村上さんにとって、
仕事とくらしが表裏一体の明浜町のくらし方は、新鮮に映ったそう。
そして、しばらくこの地でくらしているうちに、
「こんな生き方もありかな」と思うようになったといいます。
「なんせ、ここの環境は"原始の工場"なんですよ」
村上さんがいう環境とは、この入り組んだ地形のこと。

宇和海に面し、さえぎるもののない丘陵地には、
陽が沈むまで太陽の光が注ぎ込みます。
そして、海からこんもりと隆起した山に囲まれているため、
ミネラルをたっぷり含んだ潮風が吹き込むのです。
そんな環境で、農業を営んでいた村上さんは、
数年前、とあることに気が付きます。

夏場に盛んなシラス漁の網が、冬場には眠っていたのです。
有機栽培の野菜にシラス漁用の網、そして太陽と潮風。
これらが組み合わさり、村上さんが思い付いたのが、
「乾物」でした。

それまで天歩塾では、野菜は生鮮として出荷していましたが、
不ぞろいなものや傷物の野菜は、自家消費か廃棄するしかありませんでした。
そんな野菜を加工して、乾物にすれば、
価値を見いだせるのではないか。
こうして生まれたのが、「切り干し大根」。

大根は、沿岸で天日干しすることによって、
太陽の光とミネラルをたっぷり含んだ潮風にさらされ、
長期保存を可能にしました。
乾きかけの切り干し大根を一口いただくと、これがとても甘い!
さらに、これまで畑の堆肥にされていた大根の葉も、
茹でてカットし、乾物にすることで、商品化に着手。

このように、これまで価値を見いだされずに捨てられてきた野菜たちが、
乾物となることで、日の目を浴び始めているのです。

「乾物って、いわば昔ながらのレトルト食品ですよね」

前回ご案内いただいた、無茶々園で企画を務める高瀬英明さんもそう話す通り、
これなら野菜を買っても余らせがちな、一人暮らしの人たちにとっても、
必要な分だけ湯がいたり、スープや麺に入れたりして食せるのがいいですよね。
「田舎が成り立っていくためには、仲間が必要です。
そのためには雇用を増やさないと」
村上さんがそう話すように、このアイデアによって、
大型設備を導入することなく、産地の経済にも活力を与え始めています。
現に、天歩塾の加工場には、
各地から移住してきた若者たちがイキイキと働く姿がありました。
ちなみにパッケージのデザインは、地元のデザイナー井上真季さんが担当。
なんとこの方、以前高知で取材させていただいた、
地デザイナーの迫田司さんのお弟子さんでした。
もともと地元にある資源を見直し、
いわば昔からある保存の技法から生まれた、無茶々園・天歩塾の乾物。
町を活性化するためのアイデアは、
意外と身近に眠っているのかもしれません。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
我が子菓子
小さい頃、家庭で食べたおやつの味を覚えていますか?

それらはお煎餅にかりんとうなど、とても素朴な味。
だけど、どこかホッとする懐かしい味として脳裏に刻まれています。
「大切な我が子に安心な菓子を与えたい」
愛媛県喜多郡内子町にある、宮栄商事有限会社の作る
「我が子菓子 善蔵シリーズ」は、店主のそんな想いから生まれました。

宮栄商事は昭和14年に、食器やお菓子の卸・小売店として創業。
その後、仕入れていたお菓子の製造元が廃業してしまうなどあり、
自分たちでも一部のお菓子を作るようになったそう。
「どうせ作るなら、自信を持って売れるお菓子を作りたいと思いまして」

宮栄商事・3代目の宮瀬貴久さんは、
大学卒業後、大手食品会社と菓子問屋で修業を積んだ後、
家業の宮栄商事に入社。
「自分の子どもに食べさせても安心なものを作りたい。
そうすれば、みんなにも受け入れられるはずだと思ったんです」
宮瀬さんの作るお菓子は、
そのコンセプト「多くを加えず、手を加える」の通り、
保存料、香料などの添加物を一切加えていません。
「昔ながらのお菓子は、もともと添加物など使っていないですからね」

そう話す宮瀬さんは、地元産の素材を使った
新商品開発にも乗り出しています。
工房へお邪魔すると、ちょうどその商品の製造中。
「どうぞ食べてみてください」
そう言われ、ひと口食べてみると、そのフワッとした食感と
意外な酸味と塩味に驚きました。

これは、内子町で栽培された、
"イタリアントマト"を使用したお煎餅でした!
「水の代わりにトマトピューレを使っています。
以前使っていた機械だと、分厚くしかお煎餅を焼くことができず、
しんなりとしか仕上がらずに、一時はあきらめたんです…」
そんな折、機械が壊れてしまい、新しく機械を入れ替えたことで、
うす焼きが可能になったと宮瀬さんは振り返ります。
それでも、"サクッ"とした食感を表現するのに苦労したそう。
そこで、試行錯誤のうえ、米粉を使用することに行き着いたといいます。

こうしてできた「米粉のとまと煎餅」は、小麦粉、卵不使用なので、
アレルギーのお子さんにも安心して食べていただけます。
また、おやつとしてのみならず、
ひと口食べた瞬間に、「これはチーズとワインに合う!」と直感しました。
「このとまと煎餅は、うちの子たちの一番のお気に入りになりました。
手づくりの、まかない料理みたいな我が家用のお菓子ですが、
一人でも多くの人に届けていきたいと思っています」

宮瀬さんが「地味で素朴だけど、飽きずに食べ続けることができる」
と話す、我が子菓子の一部は、
無印良品のFound MUJI 取り扱い店舗でもお買い求めいただけます。
ちなみに、愛媛には柚子の皮を砂糖と醤油で味をつけて煮詰めた
「ゆねり」という郷土料理があり、ごはんのおかずに食べるそう。
ゆず入り芋菓子には、このゆねりの製法を用いた柚子が使われているといい、
お芋と柚子の他にないハーモニーを味わうことができます。
愛媛県の内子町で、一つひとつ手で作られている我が子菓子は、
まさに多くを加えず、手を加えた自然の味わい。
それがまた懐かしい味として、子どもたちの記憶に残っていくことでしょう。
鳥取砂丘らっきょう
鳥取県といって、想像する方も多いであろう「鳥取砂丘」。

東西16km、南北2km、起伏は日本最大の47mにも及ぶもので、
昔も今も多くの観光客を魅了してやみません。
この鳥取砂丘に代表されるように、
鳥取県内には砂地の土壌が多く存在します。
砂地というと水はけが良く痩せた土壌のため、
植物が育ちにくい印象がありますが、
鳥取には、その環境を逆手にとった特産品がありました。
「砂丘らっきょう」です。

らっきょうは、砂地や荒廃地などの痩せた土壌でも育つという特性を持っており、
鳥取砂丘の東部の福部町には、120ヘクタールに及ぶ
砂地のらっきょう畑が広がっています。
夏場には砂地の表面温度は60~70℃にまで上昇し、
冬場には雪に覆われることのある過酷な環境下でも、
らっきょうはたくましく育つそう。
かつて「不毛の地」と呼ばれた砂丘地での農業は、水の確保が最大の課題でした。
浜井戸から桶で水を汲み、炎天下のなか天秤をかついで畑に何度も水を撒く作業は
「嫁殺し」と呼ばれるほど過酷なものだったとか。
この環境を改善しようと戦後、鳥取では日本初のスプリンクラーを導入するなど、
様々な技術開発が進み、不毛の地は特産品が生産される優良農地へと生まれ変わったのです。
そんななか、オーガニックで
らっきょう栽培に取り組まれる方がいると聞いて、訪ねました。
鳥取市気高町(けたかちょう)で
「鳥取らっきょう本舗」を営む田中正貢さん。

「健康食品ともいわれるらっきょうなんですから、
オーガニックの方がいいでしょ」
そう、健康そうな表情で話す田中さんは、
今から6年ほど前にサラリーマンから農家へと転身されました。
もともと農薬を売る仕事もしていた田中さんでしたが、
口から入れるものが体を作っているという意識が高まっていき、
食べる人のことを考えた野菜づくりをしたいと考えるように。
無農薬での収穫量は、農薬を使った時の1/10ほどだそうですが、
はじめから無農薬栽培を手掛ける田中さんの畑では、
徐々に収穫量も高まってきているそうです。
田中さんのらっきょう畑にお邪魔すると、
そこにはらっきょうと雑草が共存する光景が広がっていました。

「雑草の根が水分を蓄え、微生物がはびこる。そして、その周囲に栄養分が溜まる。
この雑草こそが、おいしいらっきょうを育てる鍵なんです」
一見、分かりにくいのですが、実はこの畑も砂地。
水はけの良い砂地で水分を蓄えるために、雑草は重要な役割を担うのだそうです。
「よかったら少し持って帰りませんか?」
そう言いながら、田中さんが掘ってくださったオーガニックらっきょうは、
しっかりと根を張りながら育った、生命力にあふれるものでした。
「収穫のたび、この大地からの恵みに喜びを感じるんです。
これを枯渇させることなく、限りなく自然の状態で、
後世に引き継いでいくことが、私たちの責任だと思うんです」
今では、土よりも砂地の方が作業しやすいと話す田中さんは、
らっきょうのみならず、様々な在来種の栽培にまで着手。

そして、こうした動きを個人的なものにとどめるのではなく、
この夏「鳥取オーガニックマーケット」を立ち上げ、
地域ぐるみの取り組みを始めていました。

高知のオーガニックマーケットにヒントを得たというこのマーケットは、
7月からの毎週土曜日開催で延べ2300人が訪れるほど、
定番化しつつあるそうです。

「自分で作ったものを、自分で売る。
自分が欲しいものを、作った人から買う。
このシンプルで無駄のない行為のなかに、
なんともいえない安心感と充実感を覚えるんですよ」

「まぁ昔に戻っているだけなんですけどね」
と、田中さんは優しく微笑みました。
砂丘地帯という不毛な土地を、優良な農地へと変革した
鳥取の乾燥地における農業技術。
それらに感謝し、後世につないでいこうと努力を惜しまない人たちの姿。
与えられた環境を、より良くしようと耕す姿勢を、
鳥取からは教えられているようです。
原木われ椎茸
1980年、無印良品が生まれた年に発売された、
「こうしん われ椎茸(しいたけ)」。

生のものと比べ、旨みも風味も豊かで、高額だった干ししいたけを、
不ぞろいや割れたものも一緒に販売することで、市場に安価で流通させたのです。
「大きさはいろいろ、割れもありますが、風味は変わりません」
パッケージに印刷されたそのコピーには、
「訳あって安い」という無印良品の理念が込められていました。
それから三十余年。
市場環境は変化し、原木栽培が主流だったしいたけは、
菌床栽培(おが粉等をブロック状に固めたものに種菌を接種し、
きのこを栽培する方法)が、全体の約85%を占めるほどになりました。
現代において原木しいたけはもはや希少な存在ですが、
今でも原木でしかしいたけを栽培していないという地域があります。
長崎県の対馬(つしま)です。

海からこんもりと山が突き出したような地形の対馬には、
コナラやアベマキといった落葉樹が豊富にありました。
その風倒木などに、大陸から飛来する胞子が付着したのが、
対馬の原木しいたけのはじまりといわれています。
「対馬でも一時期、しいたけの菌床栽培がされたこともありました。
ただ、やっぱり原木栽培のものには敵いませんでした。
以来、誰が作ったしいたけでも、対馬産のものはおいしいと思ってもらえるよう、
原木栽培一筋でがんばり続けていますよ」

そう話すのは、とても朗らかな笑顔が印象的な永尾賢一さん。
対馬市で10名ほどしか認定されていない、原木しいたけマイスターの一人です。
永尾さんのほだ場(原木しいたけの栽培場所)を訪ねると、
そこには、見渡す限りに立てかけられた原木の光景がありました。

主に使われている原木は、アベマキやクヌギ。
いわゆる"ドングリ"ができるような木が、栽培に用いられています。
この原木に、等間隔で無数に打ちつけられているのが、
しいたけの菌です。

この菌が、原木に蓄えられたいっぱいの養分を吸収しながら、
夏場を越えて、秋から冬にかけてしいたけが生えてくるのです。

「おいしいしいたけが育つ環境は、人間にとっても気持ち良い環境なんです。
夏場は風が通って涼しく、冬場はぬくい(暖かい)。
いかに子育てに最適な環境を選ぶか、これが大事なんです」
そう話す永尾さんについて、今度は森の中にあるほだ場を訪ねると、

そこは木漏れ日が注ぎ込む、気持ちの良い環境です。

「むかで伏せ」と呼ばれる絶妙な組み方で並べられているのも、
できる限り陽の光が当たるようにとの工夫からでした。

それでも毎年、思うような天候にならないのが自然。
冬の寒さで、しいたけの成長が遅くなったときには、
袋がけで対策していたこともあるそうです。
「そうすると、"余計なことはすんな"としいたけから言われるんですよ。
現に、袋がけして育てたしいたけは、食感がいまいち。
やっぱり、自然のままに育ったしいたけが一番、おいしいんですよね」

こうして自然の力で育った原木しいたけは、
香り高く、身が締まっていて、肉厚です。

ただ、なかには厳しい自然環境の中で
割れたり、形がいびつに育ったものも。

「割れていても風味は一緒ですよ。
干すことによって、さらに旨みも凝縮されているんです。
良かったら食べてみませんか」

水に浸して戻した干ししいたけを、
永尾さんがバターと塩コショウでササッと調理してくださいました。

お言葉に甘えて、一口食べさせていただくと、
その歯ごたえと、口いっぱいに広がる風味に驚愕。
浸しておいた水には、しいたけの旨み成分、グアニル酸が溶け込み、
簡単に出汁もとれていました。

「おいしいでしょう。森を食べているようなものですから。
良い食品は、毎日食べていても飽きないのですよ」

満面の笑みで話す永尾さんの食卓では、
煮物から、炒め物、お味噌汁など、様々な料理にしいたけが使われるそう。
なんともうらやましい限りですが、
思えばしいたけはパスタやハンバーグソースなど、
和食のみならず洋食などとの相性も良いですよね。
干ししいたけなら、戻し水で簡単に出汁がとれてしまうのも嬉しいところ。
ちなみに、干ししいたけは急いで戻すのではなく、
冷水でゆっくりと戻すのがよいといいます。
我が家の食卓も早速、しいたけのおかげで、旨みも風味も豊かになりました。
そんな永尾さんをはじめとした、
対馬の生産者が丹精込めてつくった原木しいたけが、
12月7日(土)から、
無印良品 MUJIキャナルシティ博多で始まる
「Found MUJI九州」で、限定販売される予定です。
12月7日(土)14:00〜は、しいたけマイスター永尾さんのトーク&試食イベントも。
(参加費無料)

無印良品としては1980年以来、三十余年ぶりに「われ椎茸」が復活です。
しかも、価格は当時と同じ568円。
原木しいたけの風味を手軽にお試しいただく絶好の機会です。
近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください♪
対馬の海と森が育てた塩
長崎県に属する島、「対馬」(つしま)。
九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶことから、"国境の島"と呼ばれています。
長崎空港、福岡空港から飛行機で約30分、
または博多港からフェリーで、4時間前後で行くことができます。

対馬は島の約89%が山地で、山のミネラルがそのまま海に注ぎ込んでいます。
「対馬の海はとてもキレイで海藻の宝庫。
これだけの海と海藻があるんだから、それを活かした塩を作りたいと思いまして」
株式会社白松の浜御塩(はまみしお)工房を訪ねると、
代表の白木桂介さんが迎えてくださいました。

「もともとは塩の輸入からスタートしました。
専売法解禁後、やはり国産の塩づくりがしたいと思うようになり、
日本全国の塩を調べていくなかで、対馬にたどり着いたんです」
白木さんたちは、"アラメ"や"ホンダワラ"といった海藻を使った
藻塩の作り方を独自に開発。
その作り方を見せていただきました。
まず、取水した海水を逆浸透膜や立体式塩田で濃度を上げていきます。

続いて、塩分濃度の上がった海水に海藻を入れて煮詰め、
平釜で炊いていきます。
海藻をじっくり煮詰めることで、旨み成分が海水に溶け込んでいくのです。

また、この工房では他では見たことのない、
珍しい現場を目にすることができました。

それは、塩工房とパイプでつながったこの小屋の中にあり、
入るとヒノキ風呂のような、木の香りが漂います。
それもそのはず、こちらの塩工房では2011年からバイオマスボイラを導入。
木材チップを燃やして、その蒸気熱を使って釜を焚いていました。
「うちの塩づくりの理念は『ミネラル還元運動』なんです。
山のミネラルが海になり、海水とそこで育った海藻から塩ができる。
燃料には対馬の山から採れる間伐材を利用しています」

工場長の権藤正展(ごんどうまさのぶ)さんが
ボイラ導入の背景を以下のように語ってくださいました。
「木材チップの場合、重油の変動にも振り回されないし、
地域の業者からチップを購入するので、地域内循環が可能になります」
こうして地元の木材と海水、海藻を使ってできた塩は、
まさに対馬の海と森が育てた味。
塩を口に含んでも、しょっぱさをほとんど感じずに
むしろ甘みを感じるほどです。

世界中の塩を知る白木さんに世界の塩との違いを聞いてみました。
「岩塩は塩自体の味が主張するので、お肉などに合います。
一方、海水からできる塩は、食材のうまみを活かしてくれる。
おにぎり、天ぷら、野菜などに合いますね。
海水はそもそも体の蘇生成分に似ているから、
体に入れても抵抗を感じないと思います。
体にスーッと溶けるように吸収されていくはずです」
同じ塩でも、海水からなのか岩塩なのか、はたまた塩湖水なのか、
海藻を入れるのかなどの原料によっても、
釜炊きなのか天日干しなのかなどの製法によっても、味が変わってきます。
その日のメニューや好みによって塩を使い分ける。
それだけで普段の食卓が豊かになるかもしれませんね。
※対馬で作られている「浜御塩(はまみしお)藻塩」は、
Found MUJI取り扱い店舗でお買い求めいただけます
未来に伝える、伝統の醤油づくり
「機(とき)有るべし」

これは、兵庫県養父市(やぶし)にある、
大徳醤油株式会社がつくる醤油です。
「戦後、醤油づくりの姿が変わってしまいました。
もろみに熱を加え、培養酵母を添加することで熟成期間を短縮し、
大量生産・低価格販売を実現しました。
生産量だけみれば、大手の醤油メーカーだけで、
日本で使われるすべての醤油がまかなえる。
そんななか、私たちみたいな小さな醤油蔵の存在意義は何かを考えながら、
醤油づくりをしています」

企画営業部部長の浄慶(じょうけい)拓志さんが、
醤油業界に関するいろはから、丁寧に教えてくださいました。
浄慶さんによると、全国に1400軒ほどある醤油蔵のうち、
きちんと原料から仕込んでいる蔵は少なく、
また、原料を見てみても、市場に出ている醤油の80%以上が
脱脂大豆を使用しているそう。

脱脂大豆とは、大豆から溶液で油を抽出した後の、形を成さない大豆のこと。
大豆と聞いて想像する丸いままの大豆からできた醤油は
市場の醤油のわずか15%というから驚きます。
「醤油づくりにおける大豆の自給率は約6%、小麦の自給率は約9%。
自分たちが食べる分くらいは、自国でまかなっていきたいですよね」
外国産の原料を使用する蔵がほとんどのところ、
大徳醤油では、国産原料の醤油づくりにこだわります。
原料の丸大豆は地元但馬地方でつくられたものと、
熊本県の契約農家にお願いしているもの。
小麦はお隣の豊岡市でつくられているもの、
塩は長崎県崎戸島産のものをそれぞれ使用しています。
ただ国産というだけでなく、生産農家とのつながりを大切に、
生産農家と消費者をつなぐ存在でありたいと、浄慶さんは話します。
さらに、冒頭でご紹介した「機有るべし」には、
北海道の契約農家が栽培する、有機大豆と有機小麦が使われています。
「日本の有機農業の先駆者の一人が、
『有機はすべての生命の活動を表したよい言葉だ』と伝えたと聞いています。
醸造という行為は、幾億の微生物の命の活動をいただくことだと思うので、
この醤油にも『すべての命は機(とき)なくしてはありえない』
という意味を込め、"機有るべし"と名付けました」
実はこの醤油、無印良品のCafé&Meal MUJIの調味料として使用されています。
国産原料でつくられた醤油自体が希少であるなか、
有機栽培の原料が使われている醤油がいかに貴重であるかを知りました。
また、大徳醤油が守っているのが、日本の伝統である"天然醸造"の醤油づくり。
天然醸造とは、四季の温度変化の中で、
蔵にすみ着いた微生物が醤油を醸していくことで、
醸造に1年以上の時間をかけています。
「人が醤油をつくっているのではなく、微生物が醤油をつくっている。
私たち人間にできることは、いかに微生物のすみやすい環境をつくるかだけです」
蔵を見せていただくと、そこには地元の杉でつくられた、
珍しい四角い桶が並んでいました。

杉は、微生物がすみやすい自然の環境であるものの、
メンテナンスなどの問題から、杉樽ではなく、
ホーロータンクを使う蔵が一般的に増えています。
大徳醤油では、この先仮に桶職人がいなくなっても
工事でメンテナンス対応できるようにと、
このような四角い桶にしているといいます。
「農村ではかつて、自分たちがつくった畑の大豆と小麦を原料に、
家庭で醤油をつくっていました。
私たちは規模が大きくなっても、家庭の醤油づくりを原点にしたいと考えています。
命を育む食べ物が、工場ではできて家庭でつくれないものであってはならない」
こうした考えのもと、大徳醤油では麹を販売し、
家庭で試せる手づくりしょうゆキット「こうじ君ともろみさん」
も企画・販売しています。

Café&Meal MUJIのスタッフも、過去に何度か蔵見学にお邪魔しており、
その際に醤油づくりを体験していました。
今回は昨年5月に仕込んだお醤油を搾らせていただくことに!

1年以上熟成したもろみをガーゼの上にのせると、
手を添えるだけで、すーっと醤油が滴り落ちました。
できたての生醤油の味は、とても香ばしく、
しょっぱさの後にコクと甘みを感じます。
「初めにお話ししたように、
日本の伝統である醤油づくりが、合理化によって変わってきてしまっている。
だからこそ、伝統が残っているところは、
それを未来に伝える義務があると思うんです。
私たちが小さい醤油屋のモデルになれるように今後も発信していきたいです」

今回伺った浄慶さんのお話は、とても納得感があり、
終始うなずきっ放しでした。
伝統的な天然醸造と原料にこだわる姿勢は、
本来あるべき食づくりなんだと思います。
時代によって変わる業界の中で、つくり手は何を成し遂げるのか。
醤油に限らず、モノが手軽に手に入ってしまう現代において、
つくり手のものづくりに懸ける思いこそが、
その味やモノの違いにつながってくるように感じました。
蛇紋岩米
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

新緑の季節に植えられた稲の苗もすくすくと育ち、
田んぼもすっかり黄金色へと変わりました。
新米、収穫の季節です。
Café&Meal MUJIで使用しているお米、
「蛇紋岩米(じゃもんがんまい)」の収穫のため、
兵庫県養父(やぶ)市を訪れました。
ご案内いただいたのは(有)浄慶米穀の代表、淨慶俊一さん。
冒頭のことわざは「人格者ほど謙虚である」というたとえですが、
そんな表現がぴたりと当てはまるような方です。

「蛇紋岩とは、表面に蛇のような紋様が見られる岩石のことをいいます。
尾瀬や遠野などでも見られる岩石で、宮沢賢治なんかも好んで集めていたそうですよ。
そんな蛇紋岩が広がりまとまった土壌は、全国的に見てもここだけなんです」
そう教えていただいた浄慶さんの背景に広がる岩石こそが、蛇紋岩。

近くで見ると確かに蛇の紋様のような、遠くから見るとキラキラ輝く岩石で、
とてももろくて崩れやすいんです。

この蛇紋岩を、養父市を流れる八木川が削り、
土壌にマグネシウムとカリウムなど、多くのミネラル分をもたらします。

田んぼの水源である八木川に流れるのは、
氷ノ山や鉢伏山系からの清らかで冷たい水。
加えて、適度な日照時間と、昼夜の高い温度差が、
おいしいお米が育つ絶好の環境なんだそうです。
稲刈り当日も、日差しは強いけれど風は涼しい、
絶好の刈り取り日和。
Café&Meal MUJIの店長たちとともに、鎌を片手に刈り取り開始です!

「体は稲に向かって真っすぐ!鎌は手前に引くように!」
農家の方々の的確なご指南を仰ぎながら、
次々と稲穂を刈っていきました。
実際にやってみると、その鎌の切りやすさに驚かされながら、
刈り取った稲穂を握りしめていると、なんともいえない喜びの感情が湧いてきます。
昔から五穀豊穣を祈願するのも、分かるような気がします。
足腰が堪えはじめたところで、今度はコンバインの登場。
刈り取りから脱穀までを一気に行える文明の利器です。
こちらも農家の方の丁寧なご指導のもと、
徐々にスタッフたちも自身で操縦できるようになっていきました。
少々、表情が硬めですが…(笑)
こうして収穫された稲は、
次々とコンバイン内で脱穀されていきました。

収穫に参加したCafé&Meal MUJIの店長は、
「普段、なにげなく提供していたお米のルーツが知れて、
お米を炊く時も、提供する時も、気持ちが変わりそうです」
など、感想を述べていらっしゃいました。
Café&Meal MUJI、Found MUJIを扱う一部のお店でも、
蛇紋岩米の新米が並び始めています!

帰りがけ、ご指導いただいたJAたじまの堀田和則さんに、
この辺りにしか生息しない生物がいると聞いて、ご案内いただきました。
コウノトリです。

「日本においては、一時絶滅したコウノトリでしたが、
兵庫県では、1989年に旧ソ連からもらい受けた幼鳥から人工繁殖に成功。
それからというもの、コウノトリが生息しやすい環境を取り戻そうと、
但馬地区では、無農薬・減農薬栽培に取り組んでいるんです」

堀田さんがそう語る通り、
車中から眺めた、野生のコウノトリがのびのびとエサを取る姿からは、
多様な生き物が生息する様子がうかがえました。

近くにコウノトリも生息し、
全国的にも希有な蛇紋岩土壌で育まれた、蛇紋岩米。

炊きあがりのふっくらとした少し大きめの粒は、
冷めてももちもちとした食感でおいしいんです。
その甘く優しい味わいは、
それを育んできた環境から生まれるものなのだと感じました。
本枯節
日本のだし文化を支える、カツオ節。

カツオを干す、カツオを燻す、などが転じて、
「カツオ節」と呼ばれるようになったといわれています。
戦国時代には、"勝男武士"として、
戦に勝つための武士の戦陣食として好まれていたそうです。
米食中心の文化が形成されて以来、大豆製の発酵調味料と並んで、
"カツオの煎汁"は日本人の食卓で支持されてきました。
最近の研究では、カツオに含まれる旨み成分「イノシン酸」が
昆布だし等に含まれる旨み成分「グルタミン酸」を引き立てると確認されたのです。
北前舟の終着地、大阪で花開いた昆布だしに対して、
カツオ節は、主に太平洋岸の地域で発展。
なかでもカツオの水揚げ量の多い鹿児島県、高知県、静岡県が産地で、
約半数が、鹿児島県の枕崎と山川といわれています。
その主要産地の一つである、枕崎を訪れました。

回遊魚であるカツオの漁は南西諸島にまで及ぶため、
薩摩半島の南岸に位置する枕崎は、水揚げ漁港としては絶好の立地。
なおかつ、年間の平均気温18度と温暖な気候は、カツオ節生産には適しており、
薩摩藩の庇護もあって、一大産地へと発展したそうです。
この地で1935年からカツオ節を製造し続ける、マルテ水産株式会社を訪ねると
続々と水揚げされたカツオが運び込まれていました。
この日、運び込まれていたのはソウダガツオ。
一般のカツオと比べると、少し小ぶりです。

運び込まれたソウダカツオは、職人の手によって、素早くさばかれていきます。
大きなソウダカツオになると、3枚に卸された後、背中側と腹側に切り分けられます。
背中側を雄節、腹側を雌節と呼び、ぴったり合うものは世界に一組だけなので、
"鰹夫婦節"として、昔から結納や結婚式の引出物として選ばれてきました。
卸されたソウダカツオは、煮熟(しゃじゅく)の工程へ。

マルテ水産の鮫島喜一郎専務は、この工程が最も大切といい、
過熱による急激な身の収縮で亀裂ができるのを防ぐため、
鮮度の良いカツオは、低温でじっくりと煮ると教えてくださいました。
そして骨抜きや修繕されたカツオは、焙乾(ばいかん)と呼ばれる、燻す工程へ。
昔からカツオ節が保存食といわれるゆえんはここにあり、
燻すことによって、カツオの脂の酸化を防止し、
雑菌の発生を防ぐ効果があるといいます。
燻すための木材は、県内か隣県で間伐されたカシ類や桜の木。
間伐材の利用先で頭を悩まされる地域が多いなか、とても重宝されているそうです。
敷地内には、大量の木材が運び込まれていました。
焙乾の作業は部位によって6~15回も繰り返され、
じっくりと内部の水分を蒸発させていくんです。
 燻した後のムロ節
燻した後のムロ節
ほとんどの産地ではこの時点で出荷され、市場の80%以上はこの荒節で占められています。
しかし、ここ枕崎では、カツオ節の旨みを決定づけるために、
伝統製法に則り、もう一手間加えられたものも作られていました。
「カビ付け」です。

かつて江戸までの道中、カビの発生に悩まされた土佐藩産のカツオ節が、
かえって味が良いと好評を得たことから、生まれた製法なんだとか。
カビ付けによって、
焙乾だけでは除去しきれないカツオ内部の水分を取りのぞくのです。
さらに、カビ菌によって脂肪とタンパク質が分解されるため、
より透明度の高い、香りと風味あふれた旨み成分が生みだされるんだそう。
カツオ節が"発酵食品"と呼ばれるゆえんは、ここにありました。
カビ付け、日干しを4カ月から1年繰り返し完成したものを、
「本枯節(ほんかれぶし)」と呼び、最上級のカツオ節として扱われるのです。
これだけ長い期間かけて水分が取りのぞかれ、旨みが凝縮された本枯節は、
たたくとカンカンと高鳴りするほど。

この音こそが、極上のカツオ節の証なんだそうです。
「本枯節でとるダシの味は、やっぱり上品ですよ。
カツオの風味が格段に違う」
鮫島専務はそう語ります。

幼い頃から本物のカツオだしの味で育った鮫島専務は、
こうも続けてくれました。
「毎日忙しくても、週に3回ぐらいは家族団らんしながら、
おふくろの味を子どもに伝えていってほしいんです。
このカツオ節によって、少しでもその手助けになればと。
その味で、子どもがすくすくと育てば、
日本の味をつないでいくことになりますから」
現に鮫島専務の息子さんたちは、帰郷のたび、
カツオだしのきいたおみそ汁の味で、
故郷へ帰ってきたことを実感するそうです。
早速、私たちも削った状態の「花かつお」を持ち帰り、
自宅でダシから取ったおみそ汁を作ってみました。
お湯を沸かせて火を止め、花かつおを入れて待つこと3分。

想像以上に手軽に、カツオの風味広がる、
いつもより深い味わいのおみそ汁に仕上がりました。
毎日とは言わないまでも、週末ぐらいは、
ダシ料理に挑戦してみるのも良いかもしれません。
日本が生んだ独特の旨み文化、カツオ節は、
これからも親から子へと食卓で引き継がれていってほしいものですね。
バカ正直な、味噌造り
各地によって味の異なるお味噌。
これまで、長野県の「米味噌」や愛知県の「豆味噌」、
山梨県の「調合味噌」を取材しましたが、
鹿児島県では「麦味噌」の醸造元を訪ねました。
「昔は味噌を持って、味見してもらいながら歩いたものです」
営業活動を行うようになったのはここ数年と話すのは、
1964年創業「山門(やまど)醸造」の代表・山門タキさんです。

山門醸造は、毎年冬になるとツルが渡来する出水市(いずみし)にあり、
タキさんのご主人である先代の故・山門康之さんが
地域の人からお土産用に頼まれて造り始めたといいます。
そのお味噌は、ツルを見に来た観光客をはじめ、口コミで全国に広がり、
先述したようにほとんど営業活動をすることなく、多くの人に愛されてきました。
私たちが取材にお邪魔していた時にも、
ちょうど電話で注文が入っていましたが、それは名古屋の方からでした。
各地で味噌が造られているなか、全国の方から愛されている理由は
どこにあるのでしょうか?
「先代は曲がったことが大嫌いでした。
なるべく原価を下げて、おいしいものを安く提供したいと
バカがつくほど正直にやってきて、今もその想いを継いでやっています」
蔵をご案内いただくと、随所にその証を見ることができました。
まず、大豆を蒸しているこちらのシーン。

蒸篭(せいろう)を使っている醸造元も今時珍しいと思いますが、
ボイラーの燃料は重油ではなく、薪。
近所で解体された家の木材が集まる仕組みになっていました。
また、水は地下水を利用。
さらに、1日約1.9トンを仕込むという味噌造りですが、
そのすべての工程における作業が機械ではなく、人の手によるものでした。
どこか懐かしさと優しさを感じるパッケージは、
防腐剤等の添加物不使用のため、真空包装にしていません。
そのため、夏場はゆるくなってしまい、流通には難しいそうですが、
「横着したら絶対にダメ!正直な商売をしないとね」
とタキさんは話します。

取材後、山門みそを使ったお味噌汁を出していただきました。
見た目は、お味噌汁というよりも白いスープといった感じ。

ひと口いただくと、ふわっとした甘みと深み、
そして香りが口いっぱいに広がりました。
一般的に九州のお味噌は麦麹を使う麦味噌であり、甘みの強さが特徴です。
関東出身のキャラバン隊は米味噌の味に慣れているせいか、
甘いお味噌にはじめ少し戸惑いました。
しかし、この山門みそを使ったお味噌汁は
これまで口にした麦味噌のお味噌汁とは違い、自然の甘みがしたのです。
恐らくそれは甘味料などを一切使わずに、
また、人の手によって造られているからではないでしょうか。
「昔、東京で展示会をした時には、お客さんに安すぎて怪しい…
って、敬遠されたんですよ。
だけど、主人は『味を見てから買ってくれればいい』と商品を渡していました。
結果、他のお客さんも連れて翌日戻ってきてくれましたけどね」

「販売価格を変えずに造り続けるのは正直大変ですが、
全国のお客様が喜んで使ってくださっているので、
正直に、慎重にこれからも続けていきたいと思っています」
山門さんご夫妻が50年余にわたり、守り続けてきた「山門みそ」の味は、
Found MUJIの取り扱い店舗でも、お買い求めいただけます。
青みかんのジュース
熊本市内から車で40分ほどの河内町(かわちまち)。
この地では、キラキラと光り輝く有明海を眼下に、
200年以上前から、みかん栽培が行われてきました。

「この町で生まれて、この町に嫁いだ私ですが、
その当時、河内は活気があり、周りからうらやましがられていたものです。
しかし、ある時、この土地の価格が下落していることを知りました。
このままじゃ嫁に来る人がいなくなって、
子どももいなければ学校もつぶれてしまう…
"えらいこっちゃ"っていう危機感の始まりでしたね」

そう当時を振り返るのは、
株式会社オレンジブロッサム・代表の村上浮子さんです。
河内町を元気にするために自分に何ができるか?
3年間女性経営者の会に参加した村上さんは、
みかんジャムづくりからスタートしました。
「やっぱり加工だ!って思いました。
果実として出荷する場合は、収穫量や品質によって毎年
買い取り価格が変わってしまいますが、
加工品であれば価格が変動しないですから」
そうして、2001年に会員を募り、47名で
「フレッシュ河内グループ」を設立。
会員はみんな30~50代の主婦たちです。
「憧れられる女性が増えれば、地域は変わると思ったんです。
それから、ものづくりは1人より10人、10人より100人でやった方がいい」

ある時、会員同士で話をしていると、
栽培時に間引く目的で落としていたみかんを使って、
自分たちのお母さんたちがジュースを作ってくれていた
という思い出話になりました。

あの懐かしい味を再現して商品化できないか?
ジュースに使うのは、8月のお盆過ぎに摘果する青みかんのみ。
村上さんたちは、青みかんの収穫量を確保するために、専用の畑も作りました。
村上さんの青みかん畑に連れて行っていただくと、
そこはとてもワイルドな畑でした。

「クモの巣に気をつけてくださいね。うちの畑はクモの巣だらけだから(笑)
でもそれだけ安心・安全って証拠ですよ」
これらの青みかんは、熊本県が認証する、
熊本型特別栽培農産物「有作くん」基準により栽培されているそう。
そんな青みかんをまるごと搾ったジュースがこちら。
「青二彩(あおにさい)」

1本(600ml)あたりに約50個のみかん果汁が使われており、
さわやかな酸味と少々の苦みが凝縮されています。
「私なんかはストレートで毎日飲んでいますが、
はちみつと水で割ったり、炭酸水やお酒と割ってもおいしいですよ。
青みかんには『ヘスペリジン(ビタミンP)』という
アレルギー抑制効果や血流の改善に働きがあるという成分も
多く含まれているので、健康や美容にもいいんです」
熊本県産業技術センターの研究によると、
青みかんの果汁や果皮成分には、
花粉やホコリをはじめとして、鼻水・くしゃみ・目のかゆみ等
アレルギー症状の緩和や予防対策に効果がある
という分析結果が出ているといいます。
熊本県産業技術センターは、産業技術や農林水産物の加工に関する
研究開発、指導などを行う、熊本県が設置した技術支援機関。
ここでは"県内産業の技術部"という位置づけで、日々研究を重ねています。
村上さんたちも産業技術センターのアドバイスをもとに
商品づくりを行っています。
「やっぱりプロの人たちに相談できるのは心強いです」
と村上さん。
オレンジブロッサムでは、青みかんの果汁や花、果皮を使って、
他にも、ビールテイスト飲料や紅茶、ぽん酢、石けんなども手がけていました。
商品は「安心・安全・無駄をなくす」が合言葉だと、
村上さんはいいます。
「私は河内弁しか話せないおバカさんだけど、
どうせなら、好きなものに囲まれて、楽しく死にたいわね。
それからこの河内の町に後継者を作りたい」

村上さんの飾らない姿と、
河内町の良さを発信していきたいという強い想いが、
周りを巻き込み、どんどんと町の魅力をカタチにしていっていました。
みかんの里・河内は、女性の輝く町でもありました。
八島の黒糖
沖縄の家庭でお茶うけとして愛されている、「黒糖」。
私たちも沖縄の取材先で、お茶と一緒に出していただくことがよくありました。

一般的に私たちが料理などに使っている白砂糖(上白糖)は、
サトウキビの搾り汁から糖蜜を分離させたもので、"分蜜糖"と呼ばれます。
それに対して、黒糖は"含蜜糖"の代表的なもので、
原料であるサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めて濃縮し、
加工しないで冷却して製造したものです。
沖縄の島内を車で走っていると、
あちこちでサトウキビ畑を見かけましたが、それもそのはず。
黒糖は、江戸時代初頭に中国から琉球王国に製法が伝わり、
沖縄の特産品として発展してきたものでした。

沖縄島内では現在も、黒糖の生産が盛んなんだな、
そう思っていると、意外な言葉が聞こえてきました。
「いま、沖縄で黒糖を作っているのは、8つの離島工場のみなんです」
そう教えてくださったのは、
沖縄県黒砂糖協同組合の宇良勇(うらいさむ)さん。

もともと、沖縄本島にも黒糖工場は点在し、
集落ごとに黒糖づくりが行われてきました。
しかし、分蜜糖製造が始まると、国の政策もあり、
小さな工場は大規模な分蜜糖工場に整理統合されていき、
いまや沖縄の砂糖総生産量の9割以上を分蜜糖が占めるといいます。
「黒糖は、上白糖やはちみつと比べても、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。
疲労回復にもうってつけで、今年の甲子園で
沖縄の選手たちが黒糖を常備している姿がテレビで映っていました。
ただ、昔に比べると、どうも"黒糖=年寄りの食べ物"になってきてしまった」
そこで、宇良さんたちは、若い人に向けた商品企画を始めました。
そうしてできたのがこちらの「八島黒糖」。

8つの離島工場で作られた、それぞれの黒糖が
カラフルな小分けのパッケージに入っている逸品です。
「黒糖って、ぶどうとワインの関係と一緒だと思うんです。
黒糖はサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めただけのものなので、
サトウキビの生産地の気象条件や土、その年によっても風味が変わってくる。
食べてみると明らかですよ」

宇良さんに試食を奨められて、いくつか食べてみると
確かに全く味が違います!
ふわっとした柔らかい食感もあれば、カリッとしたものもあるし、
苦みの奥に甘みを感じるものや、少し酸味のあるものなど、様々。
「僕は伊江島のものが好きだな…私はこっちかな…」
と人によって好みも分かれます。
そして、自分の好みの味が見つかると、
今度はそれがどんな島で作られたものなのか、自然と気になってきます。
まさにそれが狙いでした。
「この商品を通して、沖縄の島の個性を伝えていきたいのです。
8つの島には高校がないので、若い人はみんな島外に出ていってしまう。
そして一度島から出ると、なかなか戻ってこないのが現状で。
それに、地元の人でも他の島には行ったことがないことが多い」
可愛らしいパッケージのデザインは、それぞれの島の自然や
芸能文化がモチーフになっていて、島の特徴を伝えていました。
例えば、多良間島のものは、五穀豊穣を祈願して毎年夏に行われる
"多良間の豊年祭・八月踊り"の衣装が描かれ、
小浜島のものには、小浜島の海で出会える"マンタ"、
伊江島は、毎年春に100万輪の花を咲かせる"てっぽうゆり"、
そして西表島には、国の特別天然記念物にも指定されている"イリオモテヤマネコ"
が描かれています。
「黒糖は、島々の未来永劫産業なんです。
サトウキビがなくなると、その島のくらしがなくなってしまう…。
黒糖を作って売って、島のくらしが成り立つようにサポートするのが我々の役目。
沖縄黒糖は、輸入品や加工品(原料糖が海外産のもの)と全く違う、
ということを今後も多くの人に知ってもらいたいと思っています」

ちなみに、黒糖は、商品の原材料表示が「サトウキビ」となっていて、
8つの島で作られている黒糖には、
サンサンと輝く太陽とサトウキビがモチーフの"沖縄黒糖"マークがついているそう。
また、沖縄黒糖は、一般財団法人食品産業センターによって、
日本各地の豊かな食文化を守り、育てるために設けられた表示基準
「本場の本物」に認定されています。

製造者の原料と製法へのこだわりがあり、
生活者が安心して味わえる、本物の味の証。
全国でも今のところ33の品にしか与えられていないものだといいます。
「八島黒糖」を通じて、好みの黒糖の味を知り、
島にも興味を持って、人々が回遊する。
そんな好循環が続くことを願っています。
※「八島黒糖」は無印良品のFound MUJI取り扱い店舗でも
お買い求めいただくことができます。
"業"としての有機農
「私たちが実践しているのは有機栽培ではなく、有機"農業"。
つまり"業"として、それを生業にしているのです。
食べていける農業でなくちゃ、人に勧めることはできませんから」

モアークグループ代表の西村松夫さんは、開口一番そう切り出しました。
モアークグループは、
茨城県つくば市に本拠を置き、長野県佐久市、パラオにも農園を構える、
有機野菜の生産・加工・流通までを手掛ける企業グループ。
安全安心の作物の流通および、
汎用性の高い有機農業の普及活動にも取り組んでいます。

「日本の有機野菜の流通は全体のわずか0.2%。
これは由々しき事態です」
そう話す西村さんはもともと、アメリカの大手穀物商社に勤務。
そこで、品種改良に改良が加えられていく農作物の実態に危惧を覚えたといいます。
「改良され生産しやすくなった農作物は、生産者にとっては都合が良いかもしれません。
ただ、生態系を壊しながら作られるような農作物が、消費者にとっても良いわけがない。
目先のことしか考えずに、次の世代に残そうという気がないんですね」
こうした問題意識の芽生えた西村さんは、その後、大手金融機関勤務を経て、
消費者にとって本当に良いものを追求すべく、
18年前にパラオへと渡り、農業の実証実験を始めました。

なぜ、パラオだったのか?
それは、地球全体の温暖化から、と西村さんは話します。
「日本も既に亜熱帯化し始めていますが、やがて熱帯になる可能性もある。
そのためには、熱帯地方での農業の技術を学んでおく必要があると思ったんです」
こうして始まった西村さんのパラオでの挑戦は、
現在では「パラオ・オーガニック・ファーム」として、
つくばと同様、葉物類や日本では作れないノニを生産しているそうです。
そして、西村さんがたどり着いたのが、"草農法"でした。
自然界では、植物は枯れた後、微生物によって分解され、
腐葉土と呼ばれる土に還っていきます。
草農法とは、この自然界の循環に従い、草を主原料とした堆肥づくりを行うもので、
農薬や化学肥料が使用されるより以前より
世界中で古来より行われてきた伝統的な農法だそう。
草が腐葉土になるという話には一瞬、首を傾げましたが、
モアークの堆肥場には、河川敷で刈られたという草が大量に置かれていました。
切り返しを行いながら半年間寝かされた草は、
実際に土へと変化していることがうかがえました。
河川敷の刈り草を使用するのは、
河川の水が飲用にもなるため、農薬などの散布が禁止されているから。
これまでは大量に廃棄処分されていたものの再利用にもつながっているそうです。

「この草はやがて分解され、やがて+と-のイオンへと変化します。
-イオンは主に微生物が食べ、+イオンを野菜が吸収するんです。
この+と-を掛け合わせると"土"という字に変わるでしょう。
昔の人は知っていたんだと思いますよ。草さえあれば、農作物は作れるんです」
西村さんのいう、汎用性のある有機農業とは、このことでした。
草をベースにした堆肥づくりは自然循環そのもので、
除草剤など使用していない土地であれば、どこでも実現できることでもあります。
こうして土壌に有機物をきっちりと供給してできた野菜は、
ミネラルを多く含み、作物から作られるビタミンの含有量も多くなるそう。

こんな野菜のおいしさを、ごく一部の人のみならず、
多くの家庭で味わってもらいたいと、
モアークの培養土と草堆肥などをセットにした
「有機野菜栽培キット」も作っていました。

さらに、"業"として成り立たせるためには
「加工」も大切と、西村さんは語ります。
「加工品を作るのは、昔でいう"保存"の目的です。
どうしても出荷できない分の野菜ができてしまうこともありますからね」
旬の野菜を収穫後すぐに加工できるよう、農園内に併設された加工工場では、
合成人工添加物を一切使用せずにジュースやドレッシングが作られていました。

試しに有機トマトジュースを味見させていただくと、
その濃厚さと、自然の優しい甘みに驚かされました。
トマトジュース嫌いのキャラバン隊も、思わず「おいしい!」と驚愕したほどです。
こうした旬の野菜や加工品を基に食事療法を意識した店舗・レストランが、
今年秋、東京都目黒区にオープン予定。
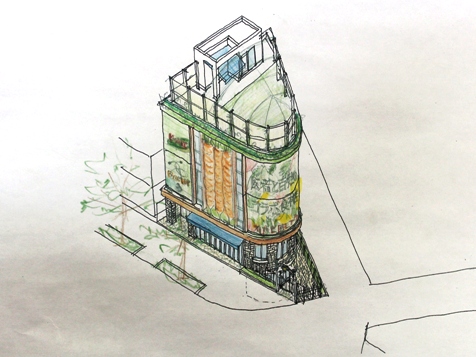
これまで培ってきたノウハウを普及するための講座も開催し、
より多くの人に食べていける有機農業を教えていく予定だそうです。
「経済優先を変えられない世の中だけど、
一人ひとりが歴史から学び、太陽と対話しながら、
自然になじんでいくことが大切だと思うんです。
それを伝えていくことが、私にできる最後の天命だと思っています」

20人もの若者を雇用しているのも、
後世につないでいける農業を普及したいという、
西村さんの想いの表れのように感じました。
地球にも人間にも優しい農業と、現代社会で生き残っていくための経済活動。
一見、両立しにくいこの両輪を見事に回していきながら、
西村さんは自身の天命を追求し続けています。
小さな蔵の"信"のある味噌造り
日本人の食卓に欠かせない食品のひとつ、味噌。

これまでのキャラバンでも米味噌、麦味噌、豆味噌、合わせ味噌など、
全国各地、その気候風土に合った原料で造られる味噌に出会ってきました。
なかでも全国に広く普及しているのは、日本人の主食の米を使った米味噌で、
実にその4割を長野県で造られる信州味噌が占めています。
かつての信濃国で、味噌づくりが普及したのは、
武田信玄が兵糧として「川中島溜」を造らせた戦国時代以降。
関東大震災や第二次世界大戦で被害を受けた東京に、
信州産の味噌を救援物資として送り、好評を得たことが、
信州味噌が普及していった理由といわれています。
そんな味噌の産地・長野県に、国産原料だけを使用し続ける
こだわりの味噌蔵があると聞いて訪れました。
松本市郊外に、ひっそりと佇む醸造蔵、大久保醸造店。

本物を求める全国の顧客からの注文で飽和状態のため、
地元でも知る人ぞ知る、醸造蔵です。
蔵内には所狭しと、国内産の等級の記載された
大豆・小麦・食塩・米が山積みにされていました。
「味噌、醤油、酒、納豆…、昔はそこで採れる物を使って造ったから、
国産原料なんていうのは当たり前でした。
今も当たり前のことをやっているだけで、
それを実現している人が少なくなったから珍しいだけ。
うちみたいに小さい蔵ならそれができますから」
そのように、あくまでも謙虚に話されるのは、
3代目を担う、大久保文靖さん。
快活な話しぶりとは裏腹に、その謙虚さは、
自身の写真撮影は遠慮してほしいという点にも表れていました。
そして、大久保さんらしさは、蔵の随所からも感じ取ることができました。
蔵内は驚くほどキレイに管理されており、
木桶には漆が塗られているのです。

「かっこいいでしょう。漆を塗ることで長持ちするし、何より美しい。
環境をキレイにしないと、味もキレイなものはできませんから」
大久保さんの衛生管理は、蔵の見えない部分にも行き届いていました。
蔵の壁や地下には、何トンもの炭が敷き詰められているんだとか。
「この炭によってカビくさくならないのです。
江戸城の石垣の土台にも炭化させた木材が敷かれているとか…。
敷地内にそれを施工すれば、自然の力で環境をキレイに保ってくれる効果があります」
また、蔵内でまかなう電灯用電力は、すべて太陽光発電。
蔵に換気扇はなく、自然対流を利用した開閉式天窓から抜ける風が
空気の循環を促します。
そして、地下に構えられた収納庫は、天然のクーラーボックスのようで、
初夏の暑い日に訪れたにもかかわらず、半袖では肌寒いほどです。
「うちの冷却用エネルギーはただですよ」

さらに、全国へ出荷している一升瓶は、すべて回収しているといい、
そこにはすべて、"ゴミ化しない"という
大久保さんの理念が行き届いていました。
「日本は、原発のすぐ隣近所に人が住んでいるような環境。
一升瓶3本のうち1本は原発のエネルギーという計算上、
容器としての瓶は大切に取り扱わなくてはなりません。
外国のような広大な大地じゃないから、ゴミを埋める土地もないでしょ。
環境を保つことが、日本にとってはとても大切なことだと思っているんです」
その環境に対する畏敬の念に感銘を受けましたが、
「自然の力を駆使した醸造蔵にとっては、当たり前のこと」
と大久保さんはサラリと言い切ります。
醸造においても一切、化学的な工程を用いずに、
微生物の力を使って発酵熟成させていました。
こうしてこだわり抜かれた原料で、
長い期間かけて造られた各玄米味噌・米味噌・麦味噌からは、
甘さ控えめながら、濃厚な旨みを感じました。

「人間も自然の一員なんだから、食品も自然が一番。
今、食べている物が、直接血となり肉となるのですから、
人が健康に生きていくための食品づくりが重要です。
生産者の顔の見える原料しか使いたくないから、量はたくさん造れないんですよ」
そう話す大久保さんは、「大豆100粒運動を支える会」の幹事も務め、
全国の小学生と一緒に、大豆を植える運動にも精を出しています。
「私がやっていることはどれも素朴なことですよ。
日本の食文化において大豆は大切な存在。
自国の食文化を大切にしないと、他国からも尊敬されませんからね」
無理をしない範囲で、当たり前に国産原料を使い、
環境と文化を大切にしながら味噌を造り続ける大久保さん。
全国からの引き合いが強いのも、
そんな信念を貫き通しているからに違いありません。
顔晴れ!塩竈
宮城県、塩竈(しおがま)市。

日本三景の一つに数えられる松島湾岸に位置するこの地は、
その名の通り、古くから塩づくりの里として知られています。
全国にある塩竈神社の総本社がその象徴で、その末社である御釜神社には、
製塩法を伝えたといわれる鹽土老翁神(しおつちのおじのかみ)が祀られています。

これまでキャラバンでは、石川県・能登の「揚浜式製塩法」や、

高知県・黒潮町の「流下式製塩法」など、

各地の様々な製塩法について取り上げてきましたが、
塩竈の塩づくりは、これまた異なるものでした。
「藻塩(もしお)」

"ホンダワラ"と呼ばれる海藻でこした海水で作られる塩のことで、
日本の塩づくりの原点ともいわれています。

「松島の綺麗な海水のミネラルに加えて、
ホンダワラのうま味成分も溶け込んでいるから、まろやかな口当たりの塩ができる」

真っ黒に日焼けした「合同会社顔晴れ塩竈(がんばれしおがま)」の総括、
及川文男さんが、そう教えてくれました。
岩塩鉱や塩湖の存在しない日本では、
どんな塩づくりにおいても、いかに濃い海水を作り出すかが鍵だそう。
何度も砂地に海水をかけて濃い塩田をつくる「揚浜式製塩法」や、
流下盤に海水を流し、太陽熱で水分を蒸発させていく「流下式製塩法」に対し、
古来の藻塩は、幾度も海藻に海水を注ぎ塩分を多く含ませ、
これを焼いて水に溶かし、その上澄みを煮詰めて製していました。
ただ、効率が悪いとされた藻塩は、徐々に衰退していきます。
そうして、砂浜が少なく塩田の作れなかった塩竈では、
ほとんど塩づくりは行われなくなっていました。
そんな折、塩竈の若手たちのあいだで、
塩竈のこれからの町づくりを模索する動きが始まります。
塩づくりの聖地でありながら、塩づくりがないのはおかしい、と。
水産加工業を営む及川さんは、他産地の塩を使うことに疑問を感じており、
自身の工場の一角に、塩づくりのための竈(かまど)を設けることを決断します。

2008年、藻塩づくりを営む「合同会社 顔晴れ塩竈」が誕生するのです。
しかし、開竈から3年目の2011年3月11日、
未曾有の震災によって、塩竈は大津波の被害に見舞われました。
目の高さほどに掛けられたカレンダーにまで浸水した痕跡が、
その時の情景を物語っていました。

「大変な震災でしたが、3つの奇跡が起きたんです。
1つ目は、浸水した竈が無傷だったこと。
2つ目は、数cm下で津波はとどまり、事務所の神棚が残ったこと。
3つ目は、社名の"顔晴れ塩竈"の看板も残っていたこと。
これらを見たとき、我々がいち早く復興して乗り越えなければならない、
そう心に誓ったんです」
事務所内の神棚は、今も塩づくりを
しっかりと見守ってくれているかのように佇んでいました。

ちなみに、及川さんの塩づくりは、
奈良時代からの塩づくりを現代に伝えるための、藻塩焼神事にならって、
執り行われています。

樽の上に敷かれたホンダワラに、
松島湾から汲み上げられた海水を注ぎこみ、
アクを取りながら、竈でじっくりと煮詰めていく手法です。

「"手塩にかける"って言うじゃないですか。
ものづくり原点は塩づくりだったと思うんですよね。
点滴の成分に塩が含まれるように、塩は人間にとって欠かせないもの。
だから、古くから人間は塩を作り続けてきたのです」
及川さんが手塩にかけた塩は、
本当にまろやかで優しい味がしました。

今では、お寿司屋さんやお菓子屋さん、食堂など、
市内の様々な店舗で藻塩が用いられ、町興しの中核を担っていました。
なかでも、藻塩を使った塩焼きそばは絶品!

「どんな土地にも隠れた資源があります。
それを誰かが掘り起こしていくことが必要なんです。
塩竈ではも~しおがないから、俺がやっているんだよ(笑)」

冗談を交えながら話す及川さんの竈から立ち上る蒸気は、
まさに復興の狼煙のようでした。
[お知らせ]
2013年7月26日(金)~9月1日(日)まで、無印良品有楽町2F・ATELIER MUJIにて
「MUJIキャラバン展」を開催します。
初日7月26日(金)19:00~はMUJIキャラバン隊のトークイベントを予定。
その他、各地で出会った職人を招いたワークショップも行いますので、
ぜひ遊びに来てください!
ATELIER MUJI「MUJIキャラバン展」イベント情報はこちら
(各イベント要予約 ※申込は定員に達し次第終了致します)
父から息子へつないだお茶
「よかったらお茶をどうぞ」

旅路の途中にも、幾度となく振る舞ってもらったお茶。
ホッと一息、緊張が緩和されるとともに、
その慣れ親しんだ味に、日本人であることを実感します。
そんなお茶の一大産地といえば、静岡県。
江戸末期、大政奉還で追われた徳川慶喜が静岡に移り住み、
その従者たちが生業を作るべく、お茶栽培に専念したことが、
茶葉の一大産地となった要因といわれています。
そんな静岡県に、完全有機栽培を手掛ける一軒の茶農家がありました。
藤枝市の「葉っピイ向島園」。

「父は、敷かれたレールの上を歩むことに疑問を持ち、
常に"生きるとは何か"について考えていました。
そこで、人間と自然は共存していくべきだということに、気付いたんです」
代々引き継がれた農園を担う、
向島和詞(かずと)さんはそう語ります。

「地上にあるものすべて一つひとつが、
自然の仕組みの中では掛け替えのない役割を担っています。
確かに農薬・化学肥料はある面から見ればとても妥当な方法ですが、
生命の次元で見た場合には、つながっている命の流れを断ち切ることになる。
生あるものすべは、単独で生存できているのではなく、
みな一つの輪としてつながっていることを思い出し、
今まで、私たち人間が立ち切ってきた輪を元の状態に戻すことが、
何よりも大切なことなのではないか」
そんな想いから、周囲の反対にあいながらも、
父・和光(よりみつ)さんが無農薬・無肥料栽培に挑み始めたのは、
今から30年ほど前のこと。

初めの頃は、農薬や化学肥料の影響で、
茶木の生命力が弱く、ほとんど収穫することができなかったそうですが、
試行錯誤の末、6年後には以前の収穫量にまで戻すことができたそうです。
しかし、そんな確固たる信念を貫きながらも、
手塩にかけてきた茶畑と家族を残し、9年前に父・和光さんは他界。
18歳にして息子、和詞さんは茶畑を継ぐことに。

父からは何も教わっていないという和詞さん。
というのも、かなりヤンチャだったという青春時代、
アルバイトを2、3掛け持ちしながら、ひたすら稼ぐことに精を出していたそうなのです。
そんな和詞さんが茶畑を継ぐことを決めたのも、
父親の残してくれた茶畑に強いコンセプトを感じたから。
「父は、想いは強かったですが、経営は下手でした。
事実、蓋を開けてみたら借金まみれ。
いくら想いがあっても、つぶれたら周りに面目が立たないですよね。
父の想いを形にしてあげたいと思ったんです」

茶畑には、父から残された向島園ならではの、様々な工夫がありました。
茶樹の種は自家受粉できないため、
同じ茶葉を育てるために挿し木で増やすのが一般的。

しかし、種から育てる場合と比べ、幼少期に経験が少なく、
得てして農薬が必要なほど、弱い木に育ってしまうそうなのです。
そこで向島園では、できるだけ強い茶樹に育てるため、
一葉の段階で挿し木をし、育苗室ではなく、畑に直接植えていました。

また、一般的には収穫量を増やすために、下の写真のように茶樹は密植されていますが、
これでは人間が満員電車に乗っているのと同じで、茶樹にもストレスがかかるそう。

向島園では、茶樹がのびのびとした環境で成長できるようにと、
一本一本ゆとりを持って植えられています。

この一本仕立てによって、しっかりと出来上がった幹は、人の腕よりも太く、
幹を切ると茶樹には珍しく年輪が見えるほどだとか。

根も4~8mほど地下に伸び、病害虫に対しての自己防衛力・自己治癒力、
そして何よりも、生命力の強い茶樹に育っているのです。

そして茶葉からお茶に加工していくのも、茶農家ならではの仕事です。
通常、外部の工場で他の茶葉とともに加工されることが多いそうですが、
向島園は自社に設備を構え、裏山から湧き出る清水を使って
自社で完全オリジナル加工まで行っていました。

明らかに工程の多いお茶づくりですが、
和詞さんは「実に奥が深く、面白い」と語ります。
そして、そのお茶の奥深さを消費者に伝えていく必要がある、と。
「人間なんて、お茶がなくても生きていけるんです。
だからこれからは、"歌って踊れる生産者"が必要。
農業を発展させていくためにも、
その面白さを伝えていくことが求められると思っています」

そのために和詞さんは、お茶にまつわる様々なワークショップを開催し、
新しいニーズを開拓することにも余念がありませんでした。
「有機農家に限って、同業界と付き合わない人も多いんですが、
僕は逆にお茶屋さんと仲良くしてもらっています。
それは、万民と付き合ってもらえるものを作っていきたいし、発信していきたいから。
農家はアーティストたるべき。これからも自分たちの信念を伝えていきたいです」
お茶づくりにおいては、まだまだ父を超せていないと語る和詞さん。
しかし、和詞さんによる新しい展開によって、
向島園へは新しい光が差し込んでいるようでした。

父から子へ引き継がれたお茶からは、とても優しい味がしました。
築地の仲買人
人々が寝静まるころ、活気づきはじめる町、
銀座から目と鼻の先にある東京都中央卸売市場「築地市場」。

荷物運搬用のターレーがびゅんびゅんと飛ばす先には、
深夜にもかかわらず各地で水揚げされた水産物が、
次々に搬入されてくる光景がありました。

この築地市場はもともと、昭和10年(1935年)に
日本橋にあった魚市場と京橋にあった青物市場が移転し誕生。
都内に11ある東京都中央卸売市場のうち、最も古い歴史を持ち、
特に水産物については世界最大級の取り扱い規模を誇ります。
高台から築地市場を拝むと、扇形の建物に囲まれているのが分かりますが、
かつて、ここには線路が引かれ、
列車によって各地からの産品が運ばれてきたそうです。

老朽化のため、豊洲への移転も検討されているようですが、
都心の中心に構えるその様は、まさに中央卸売市場。
そこに集められる水産物は、全国はもちろんのこと、
世界で水揚げされた魚介類です。
ありとあらゆる水産物が取引される築地市場は、
他の市場で取引するにあたっての参考となる価格が決まる
建値市場としての役割も果たしているそうです。
「ここには、世界中の水産物マーケットの縮図があります。
証券取引所じゃないけど、築地が崩れたら他の市場にも影響が出る」

そう話すのは、築地の仲卸業者「音幸」の見市哲也さん。
さかのぼること江戸時代から、漁業に関わる家系に生まれた
生粋の水産物仲買人です。
築地では、各地で水揚げされた水産物を取り扱う「大卸」がいて、
そこから買い付ける「仲卸」が、スーパーや飲食店へと卸しています。
「最近じゃスーパーのバイヤーも直接、築地に買い付けに来ることもありますが、
ここでは魚の目利きが勝負。仲買人は、その目利き力が信用につながる」

アジ一匹に対しても、見市さんの鋭い眼光が光ります。
ただ、それでもさばいてみるまでは分からないのが生き物の性(さが)。
そこは、大卸とのコミュニケーションで、魚の良し悪しを見抜いていくんだそう。

男の世界らしい、快活なコミュニケーションには、
長年、積み上げられた信頼関係を感じます。
実際に音幸が仕入れたアジは、その信頼関係に裏打ちされた逸品でした。

そして、明け方5時過ぎ。
築地の舞台は、マグロのせり市へと移っていきます。

せり場へは基本、このタグを付けた業者以外は入場することができません。

しかし、外国人観光客からの見学希望者が多いため、
朝5時に配布される整理券を獲得できた先着120名のみ、
特別に見学することが許されます。
訪れた日も、明け方3時には定員に達するほどの人気ぶりでした。
せりが始まるまでのあいだ、バイヤーはその日の入荷状況や、鮮度、品質を見定め、
あらかじめ買いたい品物を選び、価格を見積もる姿がありました。

今年も年初めに史上最高値を更新した青森県大間産をはじめ、
アジア諸国、中南米、ヨーロッパと世界中の産地から届くわけですから、
日本がどれだけマグロの一大消費地なのかを実感します。
「カラーン、カラーン、カラーン」

一斉に奏でられる鈴音で、せりがスタート!

せり人の威勢のいいリズミカルな掛け声のもと、
あれよあれよとマグロが売られていきます。
気付けばものの10分ほどで、100本は優に超えるマグロがさばかれ、
次々と戦利品は運び出されていきました。

持ち場へ届けられたマグロは、職人たちの手によって一気に解体され、

最終的には切身となって、
寿司屋をはじめとした飲食店や魚屋、スーパーに並ぶのです。

普段、新鮮でおいしい魚に私たちがありつけるのは、
一般の人が寝静まるころに活動する、魚河岸の職人たちがいてこそなんですね。

最後に見市さんは魚河岸で働く想いを、こう語ってくれました。

「漁師、大卸、仲買人、バイヤー、飲食店…。
すべてが一体となって、はじめて成立する魚市場。
男社会で威勢の良い雰囲気ですが、そこには絶対的な信頼関係が大切なんです。
そして、もっと一般の顧客にも開かれていく必要がある。
四方を海に囲まれた日本の魚食文化を、これからも支えていきたいと思っています」
昼夜逆転した生活で、体力勝負の魚河岸の世界も、
人の想いと信頼関係で成り立っていることを知りました。
そして、豊洲への移転も検討されている築地市場は、
日本を代表する、より"開かれた"中央卸売市場として、
これからも発展していくことを願ってやみません。
砂糖革命
ふと目にした瞬間「かわいい!」と感じた
このカラフルなキューブ。

「MARUKICHI SUGAR CUBES」
雑誌で見かけて以来、気になっていたのですが、
これなんと砂糖なんです。
これまでの道中、塩、醤油、味噌、酢など、
数多くの日本の調味料を紹介してまいりましたが、
砂糖については、なかなか出会う機会がありませんでした。
それもそのはずで、
1997年に専売制が解かれた塩は、各地で生産が始まっていましたが、
砂糖については、実はまだ国の保護下にあるんです。
「砂糖業界は啓蒙が上手くない。故に適切な情報が伝わっていないと思います。
知られているようで、意外と知られていないのが"砂糖"なんです」

そう語るのは、昭和29年創業の日本橋にある砂糖問屋、
竹内商店の代表取締役、竹内信一さん。
上のシュガーキューブの開発者です。
「スーパーの調味料売り場に行くと、塩をはじめ他の調味料はたくさん並んでいますが、
砂糖だけ種類が少ないでしょう。砂糖売り場は哀愁が漂っている、なんて言われました。
業務用が大半を占める砂糖業界は、消費者向けもほとんど進化してこなかったんです」
印刷会社の企画営業を経て、父親の会社に入社した竹内さんは、
旧態依然とした砂糖の業界に驚いたと振り返ります。
それまで付加価値を追求する仕事が当たり前だったなか、
確実に仕事を進める力だけが求められ、定時に上がれる仕事に不安を感じる毎日。
そんななか世間は健康食ブームになり、いつしか砂糖は悪者扱いされるように…。
「このままじゃうちの会社の未来、ましてや砂糖業界の未来はない」
そう感じていた竹内さんの元に、原料糖の精製メーカー、
和田製糖が新しい砂糖を開発したという話が舞い込みます。
それは、原料に沖縄産サトウキビのみを用いた砂糖。
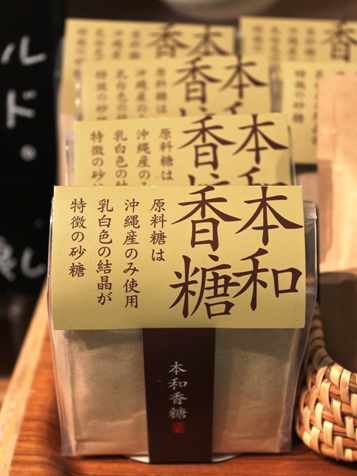
"本当に和の香りのする砂糖"という意味から
「本和香糖(ほんわかとう)」と名付けられていました。
砂糖には大きく、糖蜜を含んだ"含蜜糖"と、
糖蜜を分離させた"分蜜糖"に分けられますが、
この本和香糖は"含蜜糖"に含まれます。
いずれも原料は、サトウキビ。
サトウキビから精製された原料糖には、糖蜜などの不純物が含まれています。
沖縄などでは「黒糖」と呼ばれ、おやつのように食べることもありますが、
調理には雑味と捉えられることもあり、
不純物を分離した分蜜糖が多く流通しているのです。
グラニュー糖などの、見た目が白い砂糖は、
不純物がほとんど除去された糖分99.9%に近い分蜜糖といえます。
この本和香糖は、沖縄産の原料糖から糖蜜以外の不純物のみを除去した含蜜糖。
ミネラル分や風味を残した砂糖で、当時、世の中にはほとんど流通していませんでした。
「当時は藁にもすがる思いでしたね。
砂糖の新しい形を見せるには、本和香糖しかない!って思いました」
竹内さんは、和田製糖とともに業務用のみならず、消費者用にも展開を開始。
ただ、消費者用の売り上げがいくら伸びても
業務用が大半の売り上げを占める砂糖業界においては微々たるもので、
なかなか両社が一枚岩で取り組んでいくのは困難でした。
しかし、「ここでやらなきゃ誰がやる」と
竹内社長は独自ブランドの立ち上げに打って出ます。
それが、会社の屋号を冠にした「MARUKICHI SUGAR」です。

砂糖の卸し問屋としての立場を最大限活かし、
産地ごとに色みの異なる含蜜糖をバリエーション化。
風味の違いを楽しめる砂糖として、世に送り出していったのです。
「商品化も一筋縄ではいきませんでした。
いかんせん、問屋ですからやったことのない領域でしたからね。
ただ、一目で"これ何!?"って興味を持ってもらう仕立てにしたかった」
そこで活かされたのが、前職での経験とネットワークでした。
竹内さんの想いに呼応した元同僚たちが集い、
企画から生産までを一手に担える体制が整います。
竹内さんとともに事業を進める長澤智之さん(写真左)は、
「砂糖業界はまだまだ未成熟。その分、やり甲斐がある。
昔、貴重品として贈答品にされていたような砂糖を、現代に再現したい」
と、その想いを語ります。
生産を担う鈴木清隆さん(写真右)は、
奥さんとともに試行錯誤を繰り返しながら、生産効率の向上を目指しています。
「自分で作ったものが世の中に出せる喜び。愛着が湧きますよね」
鈴木さんは、仲間と一緒に世の中に新たな価値を仕掛けることに、
何よりの楽しみを感じているようでした。
「何でも過剰摂取は良くありませんが、
脳のエネルギー源になるのは、ブドウ糖のみなんです。
カロリーが高いといわれる砂糖は、1g当たりのカロリーは小麦とほぼ同じ4kcal」

竹内さんは、砂糖に対する正しい世の理解を得るために、
現在では、調味料マイスターの講座の講師などを務め、
様々な場面で、砂糖についての講演をして回っています。
「お菓子を作るにも、砂糖の種類を変えれば味は変わる。
風味豊かなおいしい砂糖があることを知ってもらいたいです。
そして、いつかはサトウキビから栽培してみたいですね」
TPPで揺れる日本の砂糖業界において、竹内商店は業界の救世主となるのか。
ただ、その活動によって、
砂糖の可能性が広がりつつあることに間違いありません。
日本の農業を3K産業に!
神奈川県藤沢市で、定期的に開催されているBBQがあると聞きました。

参加費さえ払えば誰でも参加可能なこのBBQは、
いつも各方面から大勢のお客さんで賑わっているとか。
実はこのBBQは、お肉屋さんやスーパーなどの小売店では
手に入らない豚肉を食べることのできるBBQ!
その豚肉とは、宮治さん一家が育てる「みやじ豚」。

「みやじ豚」のおいしさの秘訣は、血統とエサ、そしてストレスなく育てること。
一般的に30~100頭の群れで育てるところ、宮治家では飼育頭数を制限し、
小屋には10頭前後の兄弟のみの環境で育ててあげるんだそう。
現社長の宮治勇輔さんのお父さんの代から養豚を専業で始め、
当時は地域の組合の養豚場運営と並行して、自分の豚を育てていたといいます。
宮治さんは大学卒業後、一般企業に就職。
出勤前に毎朝、将来について考える時間を設け、
その中で自然と実家の養豚業を何とかしたいと思うようになりました。
どうしたら養豚や農業のような一次産業が、
"かっこよくて・感動があって・稼げる"3K産業になるのか?
そんな時、思い出したのが、
宮治さんが学生時代に、コンテストに出した自宅の豚のお肉を使って、
家でBBQを開いた時のこと。
「この豚肉、どこに行けば買えるの?」
という友人のひと言に答えられなかったのです。
「これまでの養豚業では、生産して卸会社に出荷すると、
どう流通して誰が食べているのかわからないのが現状でした。
生産者に価格決定権がなく、消費者の顔も見えない。
BBQならそれが変えられるかもしれない!そうひらめいたんです」

宮治さんは2005年に実家に戻り、友人・知人を誘ってBBQをスタート。
すると、みやじ豚の噂は、参加者による口コミで瞬く間に広がりました。
実家の養豚業は、BBQに加え、飲食店などへの独自流通網を確立し、
軌道に乗ってきたものの、勉強していくうちに、
「このままでは日本の農業がヤバイ!」
そう思うようになったといいます。
「当時、日本の農業の担い手の平均年齢は66歳で、
5年後には6割が70歳を超えている。それって全員が定年してるじゃん!」
宮治さんは
「日本の農業を3K(かっこよく・感動があって・稼げる)産業に」
を自身のミッションに置き、
日本の農業を変えるためには、
自分のような都会で働く農家の"こせがれ"が
実家に戻って農業を始めることが最短最速の道である、
という結論にたどり着きました。
「ビジネスで培ったノウハウ・ネットワークと、
親父の技術力が合わされば、やっていける!」
宮治さんは、2008年10月から
「農家のこせがれネットワーク」と題し、
農家の"こせがれ"の帰農支援を行っています。
全国各地の農家から旬の素材を直送で仕入れて提供する、
"農業体感レストラン"の「六本木農園」などで、
農家と消費者の距離を近づける"農家LIVE"等のイベントを開催したり、

毎週土曜日に、六本木アークヒルズで、
全国各地の農家が出店できる「ヒルズマルシェ」を企画・運営したり、

『「ジブン専用農家」をつくろう!』をコンセプトに、
農家と消費者を直接結びつける「マイファーマー」
というサイトを運営したり、様々な活動をしています。
また、宮治さんは都心だけでなく、他地域でも
農家と異業種の人々のネットワークづくりの支援を行っています。
講演やイベントで訪ねた地は現在42県。
「自分で考え、自分で行動できる"自律型農家"をどれだけ増やせるか。
各地域に"自律型農家"がたくさん出てこないと日本の農業はよくなりません」
私たちが全国を回った中で、「農家のこせがれネットワーク」や
宮治さんの話はよく耳にしてきました。
宮治さんの取り組みによって、日本の農業は確実に変わり始めています。
湘南×ナチュラル
神奈川県では「テラスモール湘南」の無印良品![]() を訪ねました!
を訪ねました!
2011年11月にオープンした、テラスモール湘南は、
東京ドーム3.6個分の敷地に、281店舗が集う大型ショッピングモール。
無印良品の店内も、天井が高く広々とした印象で、
「Found MUJI」や「MUJI Labo」といった限定店舗の取り扱い商品も
多数取りそろえてありました。
「いらっしゃいませ!」と迎えていただいたスタッフさんは、
"爽やか"という単語がぴったりと当てはまる湘南ボーイ☆

こちらのお店の人気商品は、このスタッフさんも着ている、
「オーガニックコットンオックスフォード ボタンダウンシャツ」でした。
「湘南という土地柄、ナチュラル志向のお客様も多いんです♪」
と、爽やかな笑顔で教えてくださいました。
ちなみに、店内には刺繍工房があり、シャツやバッグなどに
好みの刺繍を施してくれるんだそう(500円~)!
テラスモール湘南の他に、有楽町![]() ・池袋西武
・池袋西武![]() ・自由が丘
・自由が丘![]() の4店舗で、
の4店舗で、
刺繍サービスを受け付けているそうです。
無印良品のシンプルなシャツやバッグなどにワンポイント刺繍を入れることで、
オリジナルの逸品になりますね。
また、お子様やお友達の名前を入れてプレゼントしたら、
喜ばれること間違いなし♪
私も試してみたいと思います!
日本地ビールのパイオニア
居酒屋に入ると、決まって聞こえてくる文句。
「とりあえずビールで!」

私たちも日本各地を巡るなかで、たまに飲める機会に恵まれた時は、
そんなふうに喉を潤してきました。
地酒ほど多くはないものの、地ビールにも度々巡り合いました。
実は日本における地ビールの歴史はさほど古くはなく、
地ビール醸造が解禁されたのは、1994年のこと。
その歴史を語るうえで、欠かせないブルワリーが、
神奈川県厚木市にありました。
「サンクトガーレン」

創業者は、日本の地ビール業界では知らない人はいないといわれる、
岩本伸久(いわもとのぶひさ)さん。

日本で醸造解禁になる以前より、
父親と共にアメリカで地ビールを造り続けていた方です。
「父の会社が飲茶店を経営していて、アメリカにも進出していました。
その時に、現地で飲んだ地ビールの味に父が衝撃を受けたんです。
日本のビールにはない、華やかな香り、しっかりした味わい。
こんなおいしいものを知らなかったなんて、これまでの人生損していた!
と、父を目覚めさせてしまった(笑)」
地ビール醸造を始めたきっかけを、岩本さんはそう振り返ります。
初めは日本で醸造を試みるも、国の認可が下りずに断念。
仕方なく、サンフランシスコで醸造を始め、
それを日本へ逆輸入するという形態をとっていました。
すると、その様子をアメリカのTIMEやNEWSWEEKといったメディアが掲載。
「岩本のビール造りの夢はかなった。ただしそれは日本ではなく、アメリカで」
と、日本の産業規制の象徴として、皮肉たっぷりに取り上げられたのです。
このニュースが日本の政界にも飛び火し、
1994年、ついに日本でも地ビール醸造が解禁されます。
「うちが日本で醸造を始めたのは、それから3年後の1997年のことですから。
マニアのあいだでは、日本の地ビールの0号なんて呼ばれているんですよ」
そう話す岩本さんのビール造りは「エールビール一貫主義」。
日本で流通しているビールの約9割以上がラガービールで、
ラガーとエールは、その醸造法の違いによって生まれます。
ラガービールは、酵母がタンクの下段で活動する「下面発酵製法」で造られ、
低温(10度前後)でゆっくり(1週間程)発酵。
すっきりとしたシンプルな味わいに仕上がるそう。

一方のエールビールは、酵母がタンクの上段で活動する「上面発酵製法」で造られ、
高温(20度前後)で一気に(4日ほど)発酵させます。
すると、フルーティーな香りに満ちた味わいに。

これはビール酵母が高温で活動するほど、
果実のような香り成分"エステル"を生成するためです。
その結果、肉に合うビール、魚に合うビール、デザート向けビールと、
個性の強いビールを造ることが可能なんだそう。
「片方のビールしか知らないなんて、もったいないでしょ?」
そう岩本さんが話す通り、
これまではビールといえば初めの一杯がお決まりでしたが、
エールビールならワインのように、2杯目以降も楽しめますよね。
実際に、サンクトガーレンは
様々な香りと味わいが楽しめるビールを生み出していました。

なかでも、岩本さんが印象深いと語るビールが、
「インペリアルチョコレートスタウト」。

チョコレート麦芽を含め通常の黒ビールよりも約2.5倍、
原料を多く使ったというビールは
光を通さないほど漆黒で、2年間熟成可能なヴィンテージものです。
これを発売するまで、岩本さんの目指すビールは、
「自分が飲みたいと思うビール」だったそうですが、
これを境に「飲む相手のことを考えたビール」に変わったそうなのです。
きっかけは、今もともに働く会社の広報を務める中川美希さんに、
「ただ、造るだけではなく、たくさんの人に飲んでもらうことも大切」
と教えられたこと。
以来、どんな人にどんなシーンで飲んでもらいたいか、
ビールが苦手だった人、無関心だった人にも、興味を持ってもらえるように、
飲み手のことを考えたビールづくりを心がけるようになったといいます。
さらに、中川さんの「ビールは苦いから嫌い」という言葉によって、
スイーツビールのラインナップも増やしていったそうです。

こうして生まれた「スイートバニラスタウト」は、
日本最大のビールの祭典「ジャパン・ビア・フェスティバル2007」で、
来場者の人気投票で1位を獲得。
現在では、神奈川県が12年の歳月を経て開発した幻の柑橘
「湘南ゴールド」を使ったスイートビールも開発されていました。

フルーツビールというと、発酵後のビールに果汁を加えているものも多いそうですが、
サンクトガーレンでは、あらかじめ果汁を混ぜたうえで発酵させていました。
すると、香りは柑橘「湘南ゴールド」、味はビールという逸品に。
「ビールのおいしさは"水"で決まるとよくいいますが、実はそうじゃない。
ワインの場合はブドウが肝心なように、ビールの場合は麦芽とホップ。
ただ、それも自然の産物だから毎年同じとは限らない。
何よりも大切なのは、自分の感覚なんです」
多様な麦芽とホップを使い分け、
自身の五感をフルに活かしながらビール醸造にかける岩本さんには、
職人という言葉がぴったり似合いました。

「カマンベール、モッツァレラ、パルメザン…チーズにもいろいろ種類があるように、
ビールにも、ラガー以外に様々な種類があることを知ってもらうこと。そのために
みんなが飲んで楽しくなるようなビールを、これからも造り続けたいです」
岩本さんの努力によって、
「とりあえずビール!」から「まずは○○ビールで!」と、
各種ビールを嗜むようになる日も近いかもしれません。
濱の八百屋
横浜市神奈川区の住宅街に一軒の八百屋さんがありました。

「濱の八百屋」というそのお店に並ぶのは、横浜市内で作られた野菜です。
「鎌倉野菜や三浦野菜は認知されているのに、
横浜で野菜が作られていることはあまり知られていないんです。
横浜野菜の存在をもっと知ってもらいたくて」
店主の三橋壮さんは、21年間のスーパーでの野菜販売業務を経て、
昨年「濱の八百屋」をオープンさせました。
知り合いの農家さんたちの苦悩話を聞いていたのと、
友人たちと2011年7月に行った、消費者と生産者をつなぐ"収穫菜"というイベントが
キッカケだったそう。
地元出身の私たちも、横浜市内で野菜が作られているという事実にまず驚きましたが、
横浜における小松菜の生産量は全国的に見ても3位以内、
カリフラワーも10位以内に入っているというから、さらにビックリしました。
ちなみに、小松菜の生産が盛んなのは、
昔から横浜の中華街で多く使われてきたからだとか。
「通常、農家さんがスーパーなどに野菜を卸すと、
消費者の手元に届くまで5~7日かかります。
直接僕らが販売できれば、1~2日の新鮮な野菜を届けることができる。
それに対面だと、野菜の説明もちゃんとできますしね」

「例えば、このしいたけ。サイズはバラバラだけど同じ種類なんですよ。
スーパーだと均一のサイズしか売られていないけど、
ここではお客様に選んで買ってもらっています」
三橋さんは、より多くの人に横浜野菜を届けたいと、
直営店での販売は週3日にし、それ以外は宅配をしたり、
横浜市内のカフェや居酒屋の前での出店もしています。
また、横浜マリノスのホームゲーム時には日産スタジアムで出店、
東京ガスライフバルのイベントでの出張出店も行っているそう。
「一度食べてもらうと、おいしいって分かってもらえて、
ほとんどが口コミで広がっていっています。
うれしかったのはマリノスの試合の時に、
『冷蔵庫を空にしてきたから』ってお客さんにいわれたことですね」
そう語る三橋さんに、お付き合いのある農家さんの所へご案内いただくと、
横浜駅から車で10分ほどの住宅街の中に、畑がありました!
横浜の農家さんの大半は、広大な農地を持つのではなく、
小規模の農地を何ヵ所かに持つため、多品種小ロットでの生産を行っているといいます。
農家の一人、田澤仁さんは普通のスーパーには並んでいない野菜も生産し、
「三橋さんに販売をお願いするようになって、消費者の声が聞けるようになりました。
それがやりがいにつながりますね」
と語ってくれました。

続いて訪ねた、伊東康範さんは、三橋さんがスーパー勤務時代から
お世話になっている農家の方。
「うちの場合、親は近所の常連さん相手に"引き売り"という手法を取ってきましたが、
僕の代になって別の売り方もしたいと思いまして。
市場には縛られずに自由にやりたい。
三橋くんとは何でも言い合える仲だから、やりやすいですよ」

三橋さんと農家さんが、本当に気心の知れている間柄というのが見て取れました。
「三橋さんが総代理店をしてくれているので、助かっています。
自分で営業してもいいんですが、私は技術屋なのでやっぱり現場にいたいんですよね」
そう話すのは、トマトときゅうりのハウス栽培を手掛ける、山本泰隆さん。

これまで市場への卸しをメインとしてきた山本さんですが、
三橋さんとのつながりを通じて、飲食店のお客様が増えたそう。
これまで市場には出せなかった完熟トマトも、
飲食店では、ソースに使ったり、ジャムにしたりと、
生食以外の使われ方がありました。
そして、食材に対する料理のプロの意見を聞けるようになったといいます。
三橋さんは、対面での販売や宅配業務、また飲食店への納め業務から、
消費者の声を拾って、それを生産者に届け、
また、逆に生産者から野菜の情報を聞いて、
それをFacebookなども活用しながら、消費者に届けています。
「本当に人とのつながりでここまで進んでこられたと思っています」

「濱の八百屋」は、取材当日も同席してくださった、
カメラマンの中村うららさんと、デザイナーの赤尾祐一郎さん、
そして奥様の好美さんとスタッフの方々によって
支えられていると三橋さんは話します。
生産者も含め、協力者みんなに共通するのは、
「横浜野菜を通して、横浜を盛り上げたい!」という想い。
その想いに賛同して、実は無印良品でも3月末にオープンした、
Cafe&Meal MUJI 横浜ベイクォーターにおいて、
「濱の八百屋」に出店してもらっています。
お近くの方はぜひ、横浜野菜を知りに出掛けてみてください♪
循環する有機農場
有機農業の世界で、知らない人はいないといわれる場所が、
埼玉県にあると聞いて、訪れました。
埼玉県、小川町にある「霜里農場」。

「和紙のさと」としても知られる秩父山系に囲まれた丘陵地帯の農場では、
すべてが"自然の循環"のなかにありました。
「人の手を加えなくとも、自然は完全に循環している。
農薬や化学肥料を使わずとも、その循環の流れのなかで作物は作れるんです」

そう話すのは霜里農場の代表、金子美登さん。
今から40年以上前の1971年より、有機農業を手掛けるパイオニア的存在です。
「自然なら100年かかる循環サイクルを、
人の手を加えることで、10年に短縮してあげる技術。
それが有機農業なんです」
実際に、霜里農場には様々な循環サイクルがあふれていました。
まず、金子さんが有機農業で最も大切と話すのが"土づくり"。
自分の田畑で収穫した食べ物から生まれる生ごみや、雑木林の落ち葉や小枝、
おがくずやおからなどをコンポスターに集め、水分を調整しながら数回切り返します。

そうしてあげるだけで、微生物のドラマが始まると、金子さんはいいます。
20分ごとに倍に増殖していく微生物が、生きた堆肥を作り上げていくんだとか。
いい土ができれば、次は"いい種"。
近代農業では、種苗会社から種を買うのが一般的ですが、
それよりも自家採取してきた種に尽きると。

「昔から"品種に勝る技術はなし"といわれたほど、
農家が採ってきた自慢の種こそ、その地の気候風土に合った野菜が育つんです」
そして、有機農業では付きものの害虫対策でも、自然の循環の力を利用していました。
例えば、アブラムシが発生しやすい野菜の隣には、
アブラムシの天敵となるテントウムシが好む野菜を植える、といったように。
「天敵がバランス良く存在している状態がいいんです。
農薬を使うと、そのバランスが崩れてしまうし、
翌年にはその耐性を持った害虫がまた生まれてしまう」
農薬は悪循環を招くだけと、金子さんはいいます。
鶏や合鴨も飼っている霜里農場では、鶏小屋の周りに牛を放牧するようにしたところ、
キツネなどの獣害からも守られるようになったんだとか!
雑草やワラなど、農業で生じる副産物をエサとして与える代わりに、
鶏からは卵を、牛からは牛乳を貰い、合鴨は肉となります。
こうした自然の循環のなかにある霜里農場は、
エネルギーも当然、自然エネルギーによるものでした。
太陽光発電やチューブ内の水が温まる温水器をはじめ、
ガラス温室、糞尿からのバイオガスも活用。
耕運機やトラクター、乗用車はすべて、天ぷら油などの廃食油が燃料という徹底ぶり。
もはや無駄なものは何もないと思えるほどですが、
霜里農場では農場内のみならず、地域との循環も生みだしています。
霜里農場の農産物は、地元の酒蔵、醤油屋、パン屋、麺屋などに卸され、
地域の加工品として生まれ変わっていました。
何もかもうまくいっているかのような霜里農場ですが、
ここまで来るには、様々な背景があったそうです。
なかでも大きなポイントとして金子さんが挙げるのは、
消費者との提携です。
"提携"とは契約した消費者に農産物を送る仕組みで、
今や世界約40カ国でも導入されているんだそう。

「2ヘクタールの農地があれば、10軒の消費者分の作物を賄うことができます。
日本は自給できないのではなく、自給しない国づくりをしてきただけ」
金子さんは、"根の無い国は滅びる"と力を込めて語ります。
本来なら農業のうえに成り立つべき工業なのに、
工業だけが常に重要視され続ける特異な国が日本だ、と。
「今後は食とエネルギーが最大の問題になってきます。
国内に豊富に存在する草、森、水、土、太陽などの農的資源を徹底的に生かして、
食とエネルギーを自給する社会を作る生き方を選択するべき時が来ているのです」
有機農業・農村という文化を土台に、コミュニティ・共同体を作ってきた、
金子さんの約40年間の活動から学ぶべきことは多いです。
"人も有機的な関係が大切"と語る霜里農場では、
奇数月に1回、農場見学会を実施しており、毎年、数名の研修生も受け入れていました。
まずは知ること、そして選択すること。
私たち消費者もできることがあるかもしれません。
手前みそ
海外へ行くと、いつも恋しくなる日本の味、
「味噌汁」。

私の生まれ育った関東では「米味噌」が主流でしたが、
九州では「麦味噌」、愛知界隈では「豆味噌」と、
地域によって味噌の味も様々でした。
そして、終盤に訪れた山梨県では、
これまでに味わったことのない味噌に出会います。
「甲州味噌」

米と麦を用いた、いわゆる「調合味噌」です。
「これらの地域性の違いは、"主食が何か?"で決まってきたんですよ」

甲州味噌の蔵元のひとつ、五味醤油(株)の6代目、
五味仁(ひとし)さんに、分かりやすく解説していただきました。
「大まかに米どころでは米麹、麦どころでは麦麹を味噌づくりに用いましたが、
甲府は狭い盆地で斜面が多く、稲作には適していませんでした。
ですので、米の不足分を、田畑の裏作で作った麦で補ったんでしょう」

時はさかのぼること、戦国時代。
たんぱく質と塩分が賄える味噌は、陣中の兵糧としても重宝され、
各地の戦国武将は、こぞって味噌づくりを推進したそうです。
甲斐の国を治めていた武田信玄も同様で、
冬にほったらかされていた田畑で麦を作ることを指示。
こうして世にも珍しい米麹と麦麹を用いた
甲州味噌が誕生したといわれています。
五味醤油では、今も代々引き継がれてきた製法で、
甲州味噌が造られていました。

「発酵のスピードが違うので、米麹と麦麹は別々に仕込まなくてはなりません」

そう五味さんが語るように、
米麹と麦麹はそれぞれ別々に仕込まれていました。
一般の味噌と比べ、麹の種類が多い分、手間もかかりますが、
それでも、五味さんは甲州味噌を造り続けていきたいと話します。
「甲府の人たちにとって慣れ親しんだ味ですからね」
山梨名物のほうとうも、この甲州味噌が用いられていました。

ほうとうもまた、米飯が食べられなかった甲州の庶民にとって、
収穫量の少なかった小麦を補うために、
かぼちゃをはじめとした多くの野菜を加えた郷土料理でした。
「先代から引き継がれてきた甲州味噌。ずっと造り続けていきたいんです」
そんな想いの五味さんは、甲州味噌を広く伝えていくために、
「手前味噌づくり教室」も開催していました。
そのために「手前味噌づくりキット」も開発。

さらには、なんと「手前みそのうた」まで!

「味噌 味噌 味噌 味噌 手前味噌~♪」
この曲、繰り返し聞いていると、
思わず味噌づくりをしたくなってきますよ!
YouTubeでもアップされていましたので、
よろしければお聞きください♪
思えば、昔は各家庭で味噌が造られていたわけでして…。
私たちも帰京したら「手前味噌づくり」にチャレンジしようと思います!
山梨県の意外な県民性
山梨では、無印良品「ラザウォーク甲斐双葉」![]() を訪ねました。
を訪ねました。
果樹王国の山梨県、さぞかしフルーツ系の食品が人気と思いきや、
スタッフさんの持っているこちらの人気商品は、なんと…、

海産物系のおつまみでした!
島国日本において、海に面していない県は山梨含め8県ですが、
山梨県民は実は、無類の海の幸好き!
マグロや貝類の消費量は、毎年上位にランクイン(総務省「家計調査」)しており、
「あわびの煮貝」なんかも名産品として数えられるほどです。
駄菓子「よっちゃんいか」で有名なよっちゃん食品工業株式会社も、
山梨県内にありました。
意外なる山梨県の県民性…。
ただ、海産物でしたら、
山梨生まれの白ワイン「甲州」にも合いますものね☆
農業は生命産業
山梨県の日本一といえば、
最高峰を誇る富士山は言わずもがな、

桃、すもも、ブドウの果樹類も!

年間日照時間の長い山梨では、その気候風土が果樹栽培に適しており、
"フルーツ王国"と呼ばれるほどです。
なかでも、日本で1000年以上の歴史を持つ日本固有のブドウ品種「甲州」は、
ワイン醸造用にも、勝沼を中心に積極的に栽培されています。

一般に、病害や収穫量が減ることから有機栽培は難しいとされるブドウですが、
50年ほど前から、ブドウの完全有機・無農薬栽培に取り組む生産者に
山梨市牧丘町でお会いしました。
「フルーツグローアー澤登」の澤登芳(かおる)さん。
葡萄愛好会の理事長を務める方です。

「はじめは重い農薬タンクを背負って作業するのが、
嫌だっただけなんですけどね(笑)」
今年、85歳を迎えられるという澤登さんは、
腰のリハビリ中にもかかわらず、終始笑顔でお話しくださいました。
もともと、農家の7男に生まれた澤登さんは、
桑とかいこ、こんにゃくだけだった町の産業の行く末を憂い、
牧丘町の農業関係の仕事に従事し、やがて家業を継ぐことに。
1955年には、気候風土が適しているブドウ栽培を試みはじめ、
巨峰などの栽培法を確立していきました。
以来、農薬から農家を解放しない限り
将来、農業をする者がいなくなってしまう、と危惧し、
完全無農薬でのブドウ栽培に取り組みはじめます。
その最中に、奥さんが急性農薬中毒で倒れ、九死に一生を得るという事件が発生。
こうして考案された施設が「サイドレスハウス」です。

その名の通り、サイドが開いている状態のハウスのことで、
ブドウと外気の温度差を利用して空気の対流を起こし、
ハウス内の湿度を下げる効果があります。
今も無農薬で作られている原生地中央アジアのブドウをヒントに、
湿度が病害の大きな要因ということを突き止め、
雨が避けられて低湿度に保てる環境を生み出したのです。
さらに病気に強い系統を選別しながらの品種改良も繰り返し、
約10年かけて、ブドウの完全無農薬栽培化に成功します。
また、品種に対してもこだわりがありました。
「亜寒帯から熱帯まで、ブドウほど世界中で作られているフルーツはありません。
しかも、それぞれの気候風土に合った品種を作っています。
日本では当然、日本の気候風土に適したものを作るべきなんです」
大きく「醸造用」と「生食用」の2つに分けられるブドウの品種のなかで、
醸造用には、得てして海外生まれの「カベルネ・ソーヴィニヨン」や
「シャルドネ」などが好まれますが、澤登さんのところで栽培されるブドウは、
育種家だった兄、故・澤登晴雄さんとともに開発された、日本固有の品種がほとんど。
なかでも、日本山ブドウ系の「小公子」は、糖度が高くアントシアニンが豊富で、
赤ワイン醸造用としても重宝されています。

同じく、日本山ブドウ系の「ワイングランド」は、ロゼワインの醸造に。

これらの品種を用い、酸化防止剤・防腐剤など一切の添加物を使用せずに、
委託醸造したオリジナルワインは、限定販売の幻のワインと呼ばれています。

また、澤登さんはキウイフルーツ栽培のパイオニアでもありました。
35年前に、キウイフルーツを尋ねて仲間とともにニュージーランドに出かけ、
以来、日本の果物として栽培できるように努力されてきました。

キウイフルーツは収穫から食べ頃まで、熟成期間が必要ですが、
食べ頃を迎えたキウイフルーツは絶妙の味わい♪
もちろん、キウイフルーツも無農薬栽培です。
「農業を"生命産業"として位置付けることが大切です。
日本には素晴らしい気候・風土の国土があるのに、
食料自給率が40%を切るのは、農業がないがしろにされてきた証拠。
生命を育てている産業として認識し、農業を推進していかないと日本は滅びます」
澤登さんがそう警鐘を鳴らすと、長女の早苗さんがこう続けます。
「そのためには、消費者に生産現場のことを伝えていかないと。
体を作り、健康でいるために食べているわけなので、
その食材がどう作られているかをもっと知ってもらいたいですね」

早苗さんは、農学博士の称号を持つ大学教授で、
東京の女子大で教鞭をとられています。
授業の中で有機農業を実践し、食の大切さを教えるのはもちろんのこと、
有機農業の実情を伝えるべく、実家の横に家を構え、
片道2時間かけて大学まで通っているそうです。
「食べるものは、人間の生命を維持するもの。
それに害があってはいけない。
幸いなことに子供たちがこうしてつないでくれている。後は任せようと思う!」
現在、畑作業は次女夫婦が担い、一家総出で畑を守っています。
父が培ったブドウの有機栽培は、確実に後世へとつながっていました。
いでぼく
「いくら牧場をキレイにしながら、良い牛乳を搾乳していても、
大手牛乳メーカーの牛乳に混ぜられれば一緒。それが悔しかったんです」

「いでぼく」の専務取締役、井出俊輔さんは開口早々、そう切り出しました。
いでぼくは、雄大にそびえる富士山の麓、静岡県富士宮市に構える牧場。

それまでは大手ナショナルブランドのために生乳を出荷していましたが、
18年ほど前から自らのブランドで牛乳を出荷するようになり、
今では、静岡県下のスーパーをはじめ、サービスエリアにも直営店を構えています。
その台頭ぶりの秘密を探りにお邪魔すると、
そこは、それまでの牧場のイメージを覆されるような場所でした。
まず驚かされたのが、
牛舎に近づいても、まったくといっていいほどニオイがしないこと。

「掃除は徹底していますから。牛だって人と一緒で、キレイな環境で過ごしたいんです。
糞尿まみれの牧場から、おいしい牛乳が採れるわけがないでしょ」
井出さんがそう語る通り、牛舎内は牛たちが寝そべる"敷きぬか"から餌まで、
湿気が籠って異臭を放たないよう、徹底して衛生管理が行われていました。

これは創始者のおじいさんの代から当たり前にしてきたことだそう。
「意識しているのは、人間のリズムに牛を合わせるのではなく、
牛のリズムに人間が合わせることです。
ストレスのない牛たちは、おいしい牛乳をたくさん出してくれる。
当たり前のことなんですが、"命"を育てている仕事なんです」
いでぼくでの日課は、
あくまでも"牛の"生活サイクルに合わせたものになっていました。

例えば、観光向けに乳搾り体験などは行わず、
1日2回、朝と晩にしっかり手搾りで搾乳しきってあげること。
それも搾乳が許されるのは、選ばれしプロのみという徹底ぶりです。
そうすることで、牛は張った乳にストレスをかけることがありません。
また、井出さんは牛の性格まで把握していました。
乳牛の代表格として知られる「ホルスタイン種」を普通とすると、

口当たりがすっきりしたミルクが特徴の、
日本では希少な「ブラウンスイス種」は"お嬢様"、

濃厚な乳質が特徴な「ジャージー種」は気の弱い"おてんば娘"と。

「ジャージーは、体調が悪くなると大げさにアピールしてくるんですよ。
人間だったら、かわいいけどお付き合いはできない。そんなタイプですね(笑)」
冗談を交えながら、井出さんは親しみを込めて牛のことを語ります。
何よりもいでぼくの最大の特徴といえるのが、
牛舎と生乳加工場の距離が近いこと。

本来、搾乳された生乳は、牧場から加工場に集められ、
一緒くたに殺菌加工処理され、出荷されるのですが、
殺菌加工されるまでに3~4日要することが一般的。
それが、いでぼくでは牛舎の衛生管理が行き届いていることから、
加工場が目と鼻の先に構えられており、
搾乳したての生乳をすぐに殺菌加工することができるのです。
"搾りたて牛乳"とは、まさにこのことですね☆

そんな牛乳をジェラートやソフトクリームにも展開しています。

牛乳を70~80%も贅沢に使用できるのも、牧場ならでは。
出産したての母牛から40分以内に搾乳した
成分の濃い牛乳を使用した「FIRST MILK SOAP」は、
いでぼくだからこその逸品といえるかもしれません。

また、こんな取り組みも。

掃除で集められた糞尿は堆肥にされ、地元の希望農家に配給しているのです。
逆に農家からは、その堆肥で育てた野菜が届けられ、
いでぼくの直営店で販売されています。
化学肥料をできるだけ使わずに豊かな土壌を作るための、
地域内循環のための取り組みです。
「牛という"命"からもたらされる恵みを、極力、無駄にしたくなくて。
あとは、日々の基本をキチンとやる。それだけです」

井出さんの言葉からは、一消費者としても、
牛という"命"から、かけがえのない"恵み"をいただいているという、
当たり前のことを思い返させてくれました。
そして、その恵みを最大限おいしくいただくために、
いでぼくでは努力を惜しまずに取り組まれていました。
その努力の結果は、静岡含む関東県下で約3000ある酪農牧場のなか、
関東生乳品質改善共励会で、最優秀賞を獲得したことが物語っているようでした。

中伊豆の沢わさび
お寿司やお蕎麦などの日本食に欠かすことのできない「わさび」。

わさびは学名を"Wasabia japonica"と呼ぶように日本原産の香辛料です。
抗菌効果や抗虫作用があり、独特の鼻を突き抜けるような辛みと香りは、
食欲を増進させるのにも役立つといわれています。
もともとわさびは山や渓流に自生しているものですが、
江戸時代に現在の静岡市有東木(うとうぎ)地区で栽培が始まり、
徳川家康がそれを愛好し、門外不出の御法度品にしたと伝えられているそう。
そんなわさびの市場出荷量が日本一を誇る、
中伊豆のわさび農家・飯田哲司さんを訪ねました。
飯田さんはちょうどお父様と一緒に収穫後のわさびの出荷準備中でした。

一本一本包丁の角を使って細かい根などをきれいに取り除きます。
この状態(写真右上)だと、見たことのあるわさびの姿ですが、
わさびがそもそもどのように栽培されているのか気になって、
現場へ連れて行っていただきました。
すると、そこには山間に広がる段々畑の緑の絨毯が!

すぐ横には川が流れていました。

わさびの栽培方法は、大きく分けて2つ。
渓流や湧水で育てる「沢わさび」(水わさび)と、
畑で育てる「畑わさび」(陸わさび)があるそう。
飯田さんが育てる沢わさびの栽培には、日陰の立地で
12~13℃の豊富な水が必要だといいます。
「うちのわさびは湧き水のおかげで、露地栽培なのに一年中採れるんです」

飯田さんのわさび田は、天城山の北側に位置し、温度を一定に保つために、
地盤を深く掘り、大きな石から小さな石の順に敷き詰めて表面に砂利をのせた
「畳石(たたみいし)式」が取られていました。
これは、この地区で開発された栽培方式で、
天城地区と中伊豆地区では一年を通じて、わさびが栽培・収穫されています。

自然の湧き水による栽培のため、肥料や農薬は基本的には使うことができず、
水の管理や防虫、除草の手入れを日々行うんだそう。
そんななか、最近とある問題が起こっているといいます。
「温暖化の影響か、渇水や夏に温度が上がりすぎる問題があるんです。
わさびが自然環境を敏感に受ける、こういう場所で育っていることを
まずみんなに知ってもらいたい」
そう話す飯田さんは、わさびの収穫体験を実施しています。
体験に来た子どもたちは、わさびの収穫にはもちろん、
沢に泳ぐカニやカエルなどにも大興奮するんだとか。
水が綺麗だからこそ、見られる光景です。
「あとは、わさびの本物の味も知ってもらいたいですね」
そういって、収穫したばかりのわさびをその場ですりおろしてくださいました!
わさびは反時計回りに笑いながらするのがおいしくするコツだとか。
その理由は「笑うといい具合に力が抜けるから」と飯田さん。

細胞を細かく摩砕できるサメの皮のおろし器を使った、
すりたてのわさびはというと…
爽やかな風味とともに、ほんのり甘みすら感じる衝撃の旨さでした!
種類が豊富なわさびのうち、飯田さんが栽培するのは、
わさびの最高級品種といわれる「真妻(まづま)」のみ。
他の品種と比べて、色みや辛み、甘みなどのバランスが一定していますが、
栽培期間が他よりも長く、栽培できる場所を選ぶといいます。
一度真妻を食べたら、別のわさびを口にできなくなると話す飯田さんは
最後にこう加えました。
「やっぱり自分がおいしいと思うものを届けたいですから。
真妻が育つ、この自然を大切にしていくことも大事な役割だと考えています」
静岡といえば…
静岡といって思い浮かべるものといえば…

お茶!
緑茶の生産量全国1位として知られる静岡県ですが、
その栽培は13世紀に聖一国師という高僧が宋から種子を持ち帰り、
生まれ故郷の静岡市に蒔いたのが始まりといわれています。
静岡のお茶は、徳川家と縁が深く、
幼少期や晩年を駿河(現在の静岡県中部から東部にかかる地域)で過ごした
家康が好んで飲んだそう。家康は、そのおいしさを満喫するため、
夏の間は、標高1000mを超える静岡市北部の井川大日峠に、
お茶を保管するための蔵を建てさせたんだとか。
また、現在お茶の最大生産地である、牧之原台地とその周辺地域は、
大政奉還後に徳川慶喜を、駿府(現在の静岡市)まで警護した
300人にのぼる幕臣の精鋭たちによって、開拓された地でした。
静岡県内を車で移動中には、何度も茶畑のある光景を目にしましたが、
そんな静岡県でお邪魔した、無印良品 アピタ静岡![]() でも、
でも、
ご紹介いただいた人気商品は、やっぱりお茶!でした。

この春登場したばかりの「アロマティー」です!

6種類の果実の香りに合った茶葉が組み合わせてあるのですが、
なかでもこのお店で特に人気なのが、
「アロマティー 白桃&緑茶」だそう♪

飲んでみるまで、その味の想像がつかなかったのですが、
白桃の芳醇な香りが漂うホッとする味でした。
ティーバッグなので、水筒に熱湯と一緒に入れて、
私たちもいつも持ち歩いています。
6種類の香りの中から、みなさんもお気に入りを見つけてみてください☆
八丁味噌
木樽の上で芸術的に石を積み上げるこのシーン。
一体、何の作業中かわかりますか?

実はこれ、八丁味噌を熟成させるための準備段階。
発酵する味噌の振動にも耐えうるように、3トンもの石を積み上げる熟練の技です。
この状態で味噌を2年以上、熟成させます。

今回、このキャラバンでは初めての味噌蔵の取材でしたが、
味噌も地域によってその味が異なるもの。
全国的に広がる「米味噌」、九州を中心に食される「麦味噌」、
愛知を中心とした中京地域では「豆味噌」とありますが、八丁味噌は豆味噌の類い。
味噌はたんぱく質と塩分が多分に含まれているため、
戦国時代には兵糧(陣中食)として重宝され、
強い武将がいた地域では味噌造りが盛んだったそうです。
八丁味噌の名前は、徳川家康が生誕した岡崎城から
西へ八丁(約870m)の距離にある八丁村(現八帖町)で造られていたことに由来します。
この八丁村は、矢作川の舟運と旧東海道が交わる水陸交通の要所で、
原料の大豆や塩を調達しやすかったこと、良質な伏流水があったことなど、
好条件がそろっていたことが、味噌造りが盛んになった理由だそう。

八丁味噌は、味噌蔵としては最も古い歴史を持ち、
今も昔も変わらず2つの蔵が、昔ながらの製法で味噌を造っています。
全国的にもその名が知られている八丁味噌の製造元が、
昔から2社だけだったというのにまず驚きました。
大豆の収穫は秋なので、稲刈りが終わった後に
地域のみんなで味噌を仕込んでいたという歴史があり、
つまり、八丁味噌は八帖町の地域の人によって守られてきたものだったのです。
「この地域は夏場は高温多湿なため、米麹を使った米味噌だと熟成が進みすぎる。
大豆麹を使った場合はゆっくり熟成するので、
この辺りで豆味噌が造られるようになったと聞いています」
「まるや八丁味噌」の石原友保(ともやす)さんが説明してくださいました。

八丁味噌と一般的な豆味噌との違いは、その大豆麹の大きさだそう。
また、仕込みに使う水が少ないことも特徴で、
それは八丁味噌を長期間かけて、ゆっくりゆっくり熟成させるから。
現在でも杉樽を使い、樽の中で大豆麹と塩を混ぜ合わせ、
熟成期間の二夏二冬以上置くと、自然に発酵するんだとか。
その自然発酵を手伝うのが、石積み職人によって一つひとつ並べられた石です。
「石の重さで内部の水分の対流を促してあげるんです。
石には顔があって、表情を見ながら積んでいきます。
熟成の途中で石が動くことがありますが、丸い石だと互いにバランスを取ってくれる」
作業の途中で手を止めて、石積み職人の染次一郎さんが教えてくださいました。

石をうまく積めるようになるまでは7~8年かかり、
社内でも、この石積み職人さんたちだけを「味噌屋」と呼ぶといいます。
熱がゆっくり伝わるという木樽の中で、ゆっくり熟成した八丁味噌は、
大豆のたんぱく質がじっくりと旨味成分へと変化し、濃い赤茶色の味噌が完成します。
名古屋の味噌汁に「赤だし」が多い理由はこれでした。

また、八丁味噌は、熱を加えても風味が損なわれにくい特性があるそう。
「味噌煮込みうどん」や「味噌カツ」など
名古屋名物に味噌料理が多いのも、こうした背景からかもしれません。
「先人たちが作った哲学を商売のために変えてはならない。
欲を出さずにやってきたのが会社を670年以上続けてこられた理由かもしれません。
『極力変えないこと』を大事にしながら新しいことにもチャレンジしていきたい」

そう話してくれた社長の浅井信太郎さんは、
まだ有機という言葉が一般的に認知されていなかった30年ほど前から、
有機栽培の大豆を使った八丁味噌を造り、
当時国内ではなく、オーガニックへの関心が高まっていた海外へ輸出。
現在では海外20カ国へ味噌の魅力を発信し、
最近も自ら海外へ足を運んで、新たな市場を開拓しています。

「八丁味噌は、八帖町の財産。
地域のみんなにとって自慢に思ってもらえるような企業でありたいですね」
最後に見せていただいたのが、
毎日欠かさず付けているという"仕込み帳"の創業時のもの。
今も昔も変わらない味を守り続けられているのは、
先人たちから受け継ぐ作り方に従い、丁寧に歩み続けてきたから。
その証を"仕込み帳"とそこで働く人々に見ることができました。
日本最古のみりん蔵
今でこそ和食の調味料として欠かすことのできない「みりん」。

今日でも正月のおとそに用いられることがありますが、
かつては甘いお酒として女性を中心に愛飲されていたんだとか。
調味料として用いられるようになったのは江戸時代。
高価で手に入りにくかった砂糖の代用品として、
うなぎ屋や蕎麦屋など料理店で使われたことが始まりだそう。
そんなみりんの現存する日本最古の醸造元が、
愛知県碧南(へきなん)市にあると聞いて訪ねました。
「九重味淋(ここのえみりん)」。

創業はなんと1772年。実に240余年にわたって、
脈々と受け継がれてきた伝統製法でみりんづくりに励む醸造元です。
米など豊かな農産物に恵まれた愛知県中南部に広がる三河の平野は、
酒蔵も多く、醸造に適した気候風土でした。
また、海が近く江戸などへの水運の利便性が良かったことも、
三河でのみりんづくりが栄えたひとつの要因だそうです。

現在では埋め立てられ、その光景も想像しにくいのですが、
九重味淋のこの大蔵も、海辺に構えられており、
できあがったみりんは、ここからすぐに水運で出荷されていたんだそう。

築300年という蔵には、醸造の歴史が息づき、
九重味淋ならではの風味を醸し出していました。

本みりんに用いられる原料は、厳選されたもち米と米麹、焼酎のみ。
もち米を用いるのは、うるち米よりも糖化されやすく、芳醇な甘味が多く作られるため。
十分に蒸されたもち米に、二昼夜かけて仕上げられた米麹と、
香り豊かな焼酎が加えられ、「もろみ」が作られます。
このもろみを18~20度に保たれた蔵で、
時に蔵人が「櫂入れ(かいいれ)」を行いながら、
50~60日かけてじっくりと糖化熟成させます。

麹の働きによって、もち米のでんぷん質やたんぱく質が分解され、
ブドウ糖をはじめとした自然の上品な甘みや旨みが生み出されていくのです。
もろみは酒袋に詰められ、
槽(ふね)と呼ばれる伝統的な「佐瀬式圧搾機」で搾られます。
余分な雑味が出ないよう、最初はもろみ自身の重さで、その後、
徐々に圧力を加え、2日間かけてゆっくりと搾っていきます。
搾った後のみりん粕は、
この地域の特産「守口漬」という漬けもの用などに利用。

そして、搾ったみりんは、先ほどの築300年の蔵に移され、
半年から1年のあいだ貯蔵熟成。
味に深みの増した芳醇な本みりんが完成するのです。

この本みりんは、糖度が約50%、アルコール度数は約14%の調味料として、
料理に深い味わいと甘みをもたらすのはもちろんのこと、
アルコール分が魚等の生臭さを抑え、甘い香り成分が生み出されます。
最近では、酒税の対象にならないアルコール度数1%未満の、
水飴などを混ぜて作られる「みりん風調味料」も多く流通していますが、
調味料としての効果もまったく異なるそうです。
九重味淋の出荷先の8割が、老舗の日本料理屋をはじめとした飲食店ということが、
その品質の高さを物語っています。
研究管理課の川崎明子さんは、みりん醸造にかける想いをこう語ってくれました。

「今も変わらず、このみりんを造ることができるのも、
代々、知識だけならず細かい作業までをつないできてくれたからこそ。
これからも、日本の食文化の一端を担っている自覚を持って、
この味を作り続け、後世につないでいきたいです」
そんな想いの背景には、
九重味淋の第二十八代目、石川八郎右衛門氏の、こんな言葉がありました。
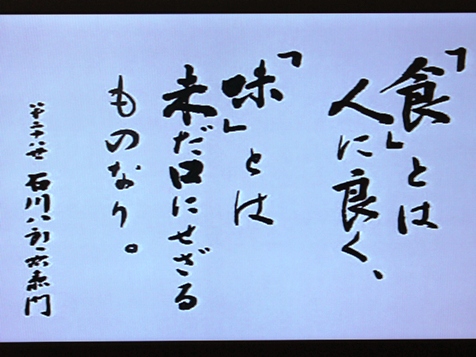
「食」とは人に良く、
「味」とは、未だ口にせざるものなり。
時に言葉に隠された語源に立ち返ることが、
原点を見失わずに進んでいく秘訣なのかもしれません。
尾鷲のかつお節
四方を海に囲まれた島国、日本において、
魚と食生活は切っても切れません。
戦後、急速な食の欧米化にともなって、肉食も一般化していきましたが、
それまでは豆類と並んで魚が、日本人の貴重なたんぱく源となってきました。
沿岸部は、漁業を生業にしてきた町がほとんどで、
紀伊半島東岸の三重県尾鷲(おわせ)市も、その一つ。

漁船が戻ると、そこら中で芸妓を呼んでの宴が催されていたほどで、
漁師はそれぐらい羽振りの良い花型の職業だったそうです。
そして、威勢の良い気質は、今も地域のお祭りに表れており、
毎年2月初めには「尾鷲ヤーヤ祭り」という裸祭が開催され、
極寒の海に素っ裸で海に飛び込む清めの儀式などが行われているんだそう。
現在では港に揚がる魚も少なくなってきたそうですが、
マグロやカツオなど、新鮮な魚料理を振る舞うお店も多い様子。

そんな町で、創業以来、今も変わらぬ製法で、
「かつお節」を作り続ける生産者にお会いしました。
「大瀬勇商店」、ここ尾鷲の地で100年以上続く海産物店です。
魚のダシが染み込んでいそうな一つひとつの道具からは、
その歴史の重さが醸し出されていました。
現在、4代目の大瀬勇人さんが、3代目の大瀬勇喜さんとともに、
昔ながらの製法で「かつお節」や「魚の燻製」を作り続けています。
「今は外国の引き網漁が活発なので、稚魚でも根こそぎ持っていかれてしまい、
尾鷲に水揚げされる魚も少なくなってしまいました。
ただ、尾鷲の魚はおいしいんです。その味を伝えていきたくて」
勇人さんがそう語るように、
安定供給のために他産地から仕入れる加工業者もあるなか、
大瀬勇商店では尾鷲産にこだわり続けています。
そのため、水揚げされるカツオのサイズも様々。
この地域では「生節」と呼ばれる
ある程度、燻製をかけた状態のカツオで食べることが一般的なのですが、
大瀬勇商店では、不ぞろいのカツオを余すことなくいただくために、
あえて一手間も二手間もかかる「かつお節」を作り続けているのです。
桜の木で燻しては乾かすこと、約10日間。
徐々に水分が飛ばされたかつお節が出来上がっていきます。

発酵食品といわれているかつお節は、この状態にカビを付着させることにより、
さらに水分を飛ばしながら熟成した「枯節(かれぶし)」と呼ばれるものです。

ただ、現在この製法で作られているかつお節は、
鹿児島など安定してカツオが水揚げされる地域においてのみだそう。
ここではカビを付着させない分、
水分を飛ばすために燻される時間は長いわけです。
こうして手間隙かけて水分を飛ばされたカツオは、
叩くとコンコンと音がなるほど硬く仕上がっていました。

これを、削り機にかけることで、
「花カツオ」と呼ばれる、食卓でおなじみのかつお節へと変化していくのです。

削りたてのかつお節には、旨みが凝縮されており、
思わず「うまい!」と声をあげていました。
「おいしいでしょ? 尾鷲のカツオは脂身が少ないのですが、
それがかつお節には向いている。尾鷲で水揚げされたカツオに感謝です」

勇人さんのその言葉通り、
大瀬勇商店では、余すところなくカツオをいただくため、
骨は"つまようじ"として製品化していました。

地域の産物に感謝をしながら、
製品ありきではなく、素材ありきでモノを生み出す姿勢。
ここにも地域に根ざして奮闘し続ける生産者のひたむきな姿がありました。
大瀬勇商店のかつお節には、
代々、引き継がれてきた想いが込められています。
三重の美味いもん
三重県では、無印良品イオンモール鈴鹿![]() にお邪魔しました。
にお邪魔しました。
鈴鹿といえばF1の日本グランプリが開催されるサーキットを想起しますが、
そんな店舗での人気商品とは一体!?
ボーダーでそろえた爽やかなスタッフの方たちが持っているものとは…、

「春色のお菓子」シリーズです!
桜と抹茶、それぞれの香りと味を生かしたお菓子で、
見ているだけでも春を感じることができます。
もう春も目前ですし、お花見しながら春色のお菓子を頬張る、
なんていうのも乙ですね♪
ご子様連れのお客様も多く、季節のお菓子に敏感だということですが、
実は三重県は日本有数のグルメ県で、海の幸から山の幸まで楽しめるんです。
「伊勢海老」や「あわび」、

「松阪牛」「伊賀牛」などは言わずもがな、

お伊勢参りの参拝客に提供されてきた、
極太もちもち柔らか麺の「伊勢うどん」など。

その名が全国に知られるグルメが多い印象です。
また、意外にもその発祥が三重といわれるグルメも多数ありました。
まずは、名古屋名物として知られる「天むす」。

津市にある天ぷら定食店が、まかない料理として考案したのが始まりとか。
その後、名古屋にのれん分け店がオープンし、名古屋名物として知られていったそう。
同じく、名古屋名物といわれる「味噌カツ」も津市が発祥という説も…。
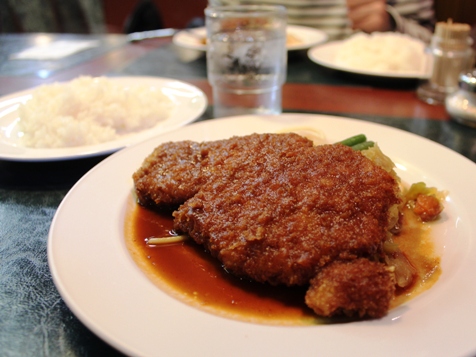
こちらは津市のとある洋食屋さんが、当時まだなじみの薄かったカツに
和風味を加えるために、味噌を混ぜたのが始まり。
近所で工事中の名古屋の業者が毎日通い、名古屋に広めたんだとか。
発祥には諸説あるようですが、
味噌カツの普及に一役買ったことは間違いなさそうです。
さらに、私の大好物でもある「いちご大福」も、
津市を代表するグルメの一つにありました。

津市の和菓子屋さんが、たまたま紅白餅といちごを同時に食べたところ
おいしかったことから、考案されたんだそうです。
今となっては定番ですが、当時はあまりにも斬新すぎる組み合わせだったため、
なかなか売れなかったそうですが、試食サービスを始めたところ、
それが口コミで広まり大ヒット商品に。
どれも津市民のグルメに対する探求心から生み出されたものです。
他にも、四日市の「とんてき」をはじめ、
食べきれないほどのご当地グルメがありました。
さすがは、衣食住の神様「豊受大御神」を祀っている
伊勢神宮を有する三重県ですね。
食に関して、話題を欠くことがなさそうです。
発祥の地の醤油
各地で見てきた「同じようで違うもの」の一つ、お醤油。
これまでもいくつかの場所で醤油蔵を訪れてきましたが、
そんなお醤油の発祥の地が、和歌山県の湯浅町にありました。
鎌倉時代に、禅僧・覚心(かくしん)が中国から
「金山寺味噌」の製法を持ち帰り、味噌づくりを開始。

金山寺味噌は調味料ではなく、おかずや酒の肴としてそのまま食べる味噌で、
瓜、茄子、しそ、しょうがなどを刻んで仕込みます。
この醸造過程で野菜の水分が桶の上に溜まり、
それを使ってみたらとてもおいしいことが分かり、
調味料として改良したのが醤油の起源といわれています。
現在、醤油の四大産地とされる、野田(千葉県)、銚子(千葉県)、
龍野(兵庫県)及び小豆島(香川県)には
いずれも湯浅からその製造技術が伝わったんだとか。
最盛期には湯浅町の醤油メーカーは92軒あったそうですが、
今も残るのは4軒で、さらに原料から醸造しているのは2軒のみ。
「醤油は熟成期間が長いので、お金になるまでに時間がかかる。
それもあって醤油メーカーが減少し、うちも父の代で醤油づくりを縮小しました」
そう話すのは、明治14年創業の丸新本家の5代目で、
現在「湯浅醤油」の代表取締役社長も務める、新古敏朗さん。

新古さんは、高校卒業後に大阪の学校に進学し、
そこで自分の故郷が醤油の発祥の地であることを初めて知り、
「醤油の伝統を絶やしたくない」「本物の醤油を世界に広めるべきだ」
という想いを胸に、周囲の反対を押し切って、
新たに2002年に醤油メーカー「湯浅醤油」を立ち上げました。
平均120年前の吉野杉の樽で作られる醤油は、
すべて国産の原料にこだわり、最低2.5年以上熟成させたものです。
「もろみは生き物なので、杉樽じゃないと呼吸ができないんですよ。
ただし、樽を作れる職人は現在では全国に2人しか残っていない」
蔵のご案内をしていただいた、林一郎さんが教えてくださいました。

「原料の違いでこんなにも味が違うというのが分かります。
ぜひ試してみてください」
そういわれて一つひとつ試してみると…

表現が難しいのですが、口に含んだ瞬間にその違いは明らか。
どれもとてもスッキリとしていて、透き通るような味わいです。
そして、それぞれにストーリーがあるのです。
なかでも、こちらの「魯山人(ろさんじん)」と呼ばれる醤油は、
芸術家で美食家としても知られていた北大路魯山人が、
病床に持ち込んでいた手づくりの醤油差しに合うような、
"今の便利さを一切用いず、その昔あったような醤油"をコンセプトに、
「魯山人倶楽部」と共同開発したもの。

主原料の大豆と小麦は、
無農薬・無肥料の自然農法で栽培した北海道の折笠農場のものを使用しています。
ちなみに、折笠農場の折笠健さんは、
青森のりんご農家で難しいとされる自然農法を成功させた、
業界内では知らない人がいない「奇跡のりんご」木村秋則さんの一番弟子だそう。
「魯山人の名に恥じないような"奇跡の醤油"ができたと思います」
ほかにも、新古さんは伝統を守りながらも、カレー専用の「カレー醤油」や、
まぐろのトロをおいしく食べるためだけに「トロ醤油」を開発する一方で、
「子どもたちに体験を通して湯浅の伝統産業を伝えていきたい」
と、8年前から地元の小学生に醤油づくりの授業を行っています。
驚いたのが、小学生は醤油づくりだけでなく、
大豆づくりや麹づくりをも体験するというのです。
その理由を新古さんは次のように語ります。
「原料から作る大変さを知ってほしい。
子どもらに失敗しながらの成功を知ってほしい」
農業指導は、農家の三ツ橋さんが担当。
自身の息子には農業をさせなかったことを反省し、
子どもに農業のよさを伝えたいと、新古さんと共鳴したそう。
子どもたちの醤油づくり体験は、
地域の伝統産業を未来の担い手に伝えると同時に、
学校が地域の人々と結びつくキッカケにもなっています。
「日本には大事なものがたくさん残っている。
もっと日本の伝統文化に目を向けてほしいと思ってやっています」

小学生と一緒に作ったマイ醤油をうれしそうに眺めながら、
その想いを話してくださった、新古さん。
醤油発祥の地・湯浅町では、伝統の味とその味を守り続ける担い手が
確実に育っていっているのだと思います。
未来へつなげる昔ながらの梅
おにぎりやお弁当でおなじみの「梅干し」。

中国では紀元前より、酸味として用いられており、
塩と並んで最古の調味料といわれています。
料理の味加減を表す「塩梅(あんばい)」の語源も、
塩と梅のバランスが良いことに由来するのだそう。
原料となる梅の国内シェア約6割を誇る和歌山県では、
例年より早く2月上旬に梅の花が咲き始めていました。

一年を通じて温暖な紀伊半島南西部に位置するみなべ町は、
梅の日本一の産地で、代表品種「南高梅」発祥の地でもあります。
南高梅が登場したのは昭和20年代のこと。
地域で栽培されていた114種類の梅の中から、
5年の歳月をかけ、最優良品種を選抜した結果、
最も風土に適した高田家の梅が選定されました。
その際、調査研究に深く関わった南部高等学校園芸科の努力に敬意を表し、
「南高梅」と名付けられたんだとか。
現在では、みなべ町で生産される梅の約8割を占めるそうです。
そんなみなべ町で、数ある梅農家のなかでも、
無農薬・無肥料栽培に挑む農家があると聞いて伺いました。
「てらがき農園」

減農薬栽培を手掛けていた父の後を継いだ、農園長の寺垣信男さんは、
枝の剪定作業まっただ中でした。
「こうして枝を切ってあげないと、梅の実に栄養が行き届かないんですよ。
大変ですが大切な仕事です」
幼い頃から農作業する父親の背中を見て育ったという信男さんは、
驚くほどのスピードで剪定を進めていらっしゃいました。
ただ、そこにはてらがき農園ならではの剪定のコツがありました。
強いものを残し、余計な枝をカットしていく考えは同様ですが、

一般的には開放自然型と呼ばれる形状に仕上げていくのに対し、

てらがき農園のものはこの通り↓

枝が上へ上へと向かっているのが分かるでしょうか?
これは、あえて下に生えてくる枝を剪定しているため。

こうすることによって実が付いても枝が垂れにくくなり、病気になりにくいんだとか。
農薬を与えずに育てるための工夫でした。
「それでも、農薬を使った場合と比べ、出荷できる品数は1/10程度です。
だからといって価格を10倍にするわけにいきません。
すべては、本当に体が喜ぶ梅を作るためです」
そもそも、てらがき農園が無農薬・無肥料に取り組み始めたのも、
お客さんの「これからも体に良い梅を作り続けてください」という
感謝の声からだったそうです。
どれだけ消毒をしても、毎年何かしらの病気が発生していたことから、
いっそ農薬を減らしてみようと実践し、減農薬栽培を確立。
そんな折にいただいたメッセージだったために、
減農薬でも罪悪感を覚えたんだそう。
完全無農薬に切り替えることに葛藤を覚えながらも、挑戦を始めた信男さんは、
有機肥料で栽培した作物が早く腐りやすいことを知り、無肥料にも挑みます。
今では納豆菌などを散布し、
病原体の繁殖を抑制したり、土壌改良に役立てたりしているようです。
「収穫したら、はい出荷ってわけにいかないのが、梅農家ならではですかね」
信男さんがそう話す通り、
てらがき農園では梅干しづくりまで手掛けていました。
最近では消費者が自分で加工する需要から、青梅で出荷することも増えているようですが、
それでも梅干しにする量の1/10にも満たないそう。
完熟の梅を、塩漬けにし、

これを2週間ほど天日干ししていきます。

ほとんどの農家では、3~4日ハウスで乾燥させ、等級分けされた梅を
二次加工業者へ卸し、そこで味の調整が行われ梅干しとして出荷されますが、
てらがき農園ではその後の工程すべてを自社で行っていました。

自社の蔵で3年間寝かせられた梅からは、自然に中の塩分が出て、
梅本来の酸味がきいた、昔ながらの梅干しに仕上がっていくのです。

一粒いただくと、まるで体が欲していたかのように、
口中から酸味が吸収されるような感覚で、
思わず種の中の"仁"までむさぼるように食べてしまいました。
自然にとって優しい栽培法で作られた梅は、
体にとっても優しいものでした。
「シンプルに考えるようにしているんです。
自然の恵みからいただく農業なら、ずっと続けていける。
梅の木が持つ本来の力で、実が付けられるようにお手伝いをするだけです」

今や3児の父となる信男さんは、
まるで子供を育てるような口調で梅についても話します。
次の世代、その次の世代にも続けられるようにと、
100年後も見据えた農業を追求していました。
吉野の葛菓子
小さい頃、私が風邪を引いた時には
母は決まって「くず湯」を飲ませてくれました。
以来、くずとは何なのかを調べることもなくきましたが、
奈良県でついにその正体に出会うことになりました。
吉野葛(くず)。
多量のデンプンを含む葛の根を原料としたもので、
全国的にも山野に自生しているものなんだそう。
吉野葛は全国シェアの約4割を占めていますが、
修行の地であった大峰山を登る際に、
修行僧が持ち歩いていたというほど、葛は栄養価が高いものだといいます。

葛湯に葛餅、葛きりなどの和菓子から、
揚げものの小麦粉や片栗粉の代わりにも万能な素材として使われています。
葛のあんは、常温でも固まるし、冷めてもとろみが取れないのが特徴だそう。
奈良県下では、この葛を使った和菓子屋さんを多く見かけましたが、
なかでも、ひと際目を引いたのがこちらのパッケージ。

千本桜で有名な世界遺産の吉野山にある、
「TSUJIMURA」が手掛けたものです。
葛を使った干菓子に、
黒糖から和三盆、上赤糖など各種糖を配合してあり、
一つのパッケージで様々な風味が楽しめます。

3代目の辻村佳則さんご夫妻は、奈良県の商業振興課が行う
「奈良ブランド開発支援事業」の一環である勉強会に参加し、
講師に「歴史に甘んじるな」と怒られたといいます。
「世界観があってモノが売れる時代。
これまでのいいところを残して、今の時代に合わせてやっていこう」
と、店舗のリニューアルを含めて取り組んでいました。
新しいパッケージで提供する葛菓子「TSUJIMURA」のコンセプトは"贈り物"。
「自分が好きなものをみんなにも紹介してきたい」
と佳則さんは話してくれました。
それぞれのお菓子のタイトルも
「雪あかりの小路」「森の中へ」「星とダンス」と秀逸で、
さらにパッケージには、地元ヒノキの経木や吉野和紙を使い、
吉野ブランドで演出しています。
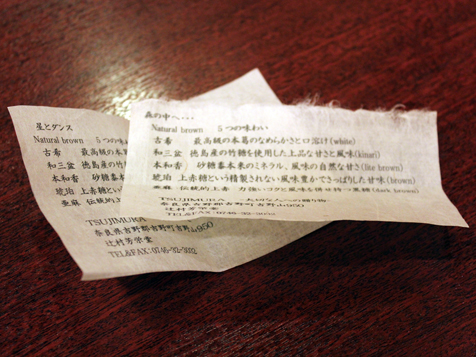
今春、吉野の山に桜の花が咲き始める頃に、
「辻村芳栄堂」は新スタートを切る予定。
地元のお茶屋さんとのコラボ企画なども準備中といい、
今から春が待ち遠しいです。
家の中を快適に
「東大寺」の大仏や、猫も見つめる聖徳太子ゆかりの「法隆寺」など、
数多くの世界遺産を持つ、古都・奈良には
昔から声をかけずとも、多くの人が訪れてきました。
私もそうですが、修学旅行でこの地を訪れたことのある人も多いのでは?
奈良は、大阪の"食い倒れ"、京都の"着倒れ"に対して、
"寝倒れ"という言葉で表現され、
人々はあくせくせず、のんびりと過ごしてきたといいます。
奈良公園周辺にいるシカさんたちを見ても確かにおっとりしていたかも…。

そんな奈良県でお邪魔したのが、無印良品 イオンモール橿原(かしはら)店![]() 。
。
ここでご紹介いただいた人気商品を聞いて、
その理由とともに「なるほど!」と納得しました。
イオンモール橿原店の人気商品は、

「超音波アロマディフューザー」でした!
お店の中でもよく見かける品ですよね。

でもなぜ奈良県でこの超音波アロマディフューザーなのか、
不思議に思っていると、店長からこんなお話が。
「奈良県って、専業主婦率が全国1位なんですよ!」
なるほど☆アロマディフューザーが人気なのは、
過ごす時間の長い家の中を快適にする工夫かもしれません♪
ちなみに一緒に使う、エッセンシャルオイルは20種類近くありました。
たくさんあっていろいろと試してみたいけど、どれから選んでいいか分からない。
そう思っていたら、ネットストアに「香り選びチャート」がありました!
"ホッと癒やされたい"+"お休み前にゆったり過ごしたい"を選んだら、
「ラベンダー1滴」+「ベルガモット3滴」を、

"元気を出したい・いきいきしたい"+
"仕事や家事をひと頑張りする元気がほしい"を選んだら、
「ゼラニウム1滴」+「グレープフルーツ3滴」を提案されました。

これまで1種類のオイルしか使ったことがありませんでしたが、
ブレンドして使う方法もあるんですね★
手延べそうめん
韓国の冷麺、ベトナムのフォー、イタリアのパスタなど…、
ぱっと思いつくだけでも、世界中に広がっている麺文化。
麺の発祥には諸説ありますが、大陸を経て伝わった日本では、
そば、うどんをはじめ、そうめん、ラーメン、近年ではパスタなど、
世界でも有数の麺愛好国となっています。
これまでの旅路でも、
痩せた土地や山間部の傾斜地などでは救荒作物のそば文化が根付き、
良質の小麦が採れる地域ではうどん文化が発展するなど、
各地の気候風土に合わせた麺文化の軌跡を見ることができました。
そして奈良県では、日本ならではの発展を遂げた麺に出会いました。
「三輪そうめん」です。

その歴史は奈良時代にまでさかのぼり、そうめん発祥の地ともいわれています。
三輪山周辺から湧き出る水にミネラルが多く含まれており、
肥沃な土地と湿度により、そうめん造りに適した小麦が採れたのです。
江戸時代、伊勢参りや大神(おおみわ)神社などへの往来で、
三輪の地を訪れた人たちが、参拝ついでに習い覚えて帰り、
各地にそうめん文化が広まっていったそう。
今も三輪(現桜井市)には数多くのそうめん製造業者が存在していますが、
その中でも、老舗で知られる「三輪そうめん山本」を訪ねました。
寒い冬季の作業になるそうめん造りは、農家の閑散期の副業として広まり、
地域とともに発展してきたというから、その功績から考えても、
紛れもなく地域におけるリーディングカンパニーといえるでしょう。
造られているのは、昔ながらの「手延べそうめん」です。
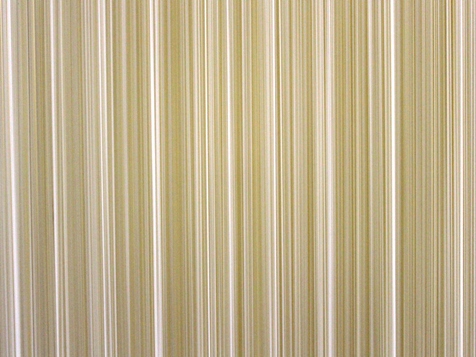
「手延べ」とは、薄く延ばした生地を刃物で切る「切り麺」とは異なり、
その名の通り麺を手で延ばしていく製法。
三輪そうめん山本では、独自のそうめん専用の小麦粉を使用し、
気温や湿度に合わせて小麦と塩を配合、少量の綿実油を塗布しながら、
徐々に麺に撚り(より)をかけながら延ばしていきます。
延ばした麺を8の字にかけたものを細くしていく、
手延べ体験をさせていただきました。

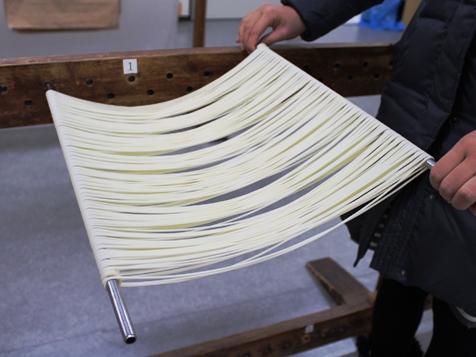
力を入れるとグーッと延びていきました。
まるでチューインガムを延ばしているかのような感覚です!
約60cmまで延ばしたものを、室(むろ)に入れて翌日まで熟成。

この延ばしては寝かせてというのがポイントで、
熟成を促し、麺に粘りが加わるんだそう。
こうしてしなやかになった麺を、さらに
そうめんの細さまで少しずつ引き延ばしていきます。

機(ハタ)にかけて1m程に延ばしたら、登場するのが2本の棒。
8の字に巻かれているため、両サイドへ開くことで
粘着した麺がほぐれていくのです。
2m程まで延びた麺を指で触ってみると、
ハープの弦のように美しくなびいていました。
その後、これらをじっくりと乾燥させ、
人が食べやすい19cmに切りそろえたら完成。

といいたいところですが、そこから蔵に入れられ、
厄(やく)と呼ばれる高温多湿の梅雨期を越すことで、
茹でのびしにくくコシの強いそうめんができるのだそうです。
現在では、機械が導入されていますが、
あくまでも人の手の補助的役割であって、製造工程は全く変わっていません。
実に麺づくりの工程だけでも36時間、
商品として出荷するまでに1~2年を要するのです。

そんな三輪そうめん山本では、
世界最細という手延べそうめん「白髪」も造られていました。

その細さ、なんと直径0.3mm!
繊細な技術が必要とされる手延べ麺において、
ここまで細さとコシを実現できるのも、
あらゆる点で妥協のない証ではないでしょうか。
かつて保存食として生み出された三輪そうめんは、
現在においても、食卓で多くの人に愛されています。
その背景には、地域繁栄のために尽力した先人たちの努力と、
おいしさを保つために、伝統製法を守り続ける
生産者たちのひたむきな姿がありました。
こんぶ出汁(だし)
日本料理に欠かすことのできない"だし"。
日本におけるだし文化のルーツは縄文時代にまでさかのぼるほど古く、
現在のだし文化の基礎は、江戸時代に花開いたものといいます。
土佐(高知県)、紀州(和歌山県)で開発されたかつお節に、
開拓地蝦夷(北海道)から商船"北前船"によって運ばれた昆布、
かつお節や昆布と比べ安価で庶民に親しまれてきたイリコ等など…。
肉ベースのだしが主流の欧米の料理とは異なり、
日本料理には実に多彩な素材から取られただしが使われています。
だしの種類は地域によっても異なり、
大まかに分けると、北前船が寄港した日本海側や関西は昆布だしで、
かつお節の生産が盛んだった四国や関東はかつおだしが主流でした。
北前船の起点であり、終点でもあった大阪は、
北海道から多くの昆布が運び込まれ、昆布の一大集積地となったのです。
そんな歴史を受け継ぎ、今も昆布だしの文化を
世に広める一軒のお店が、大阪中心地の空掘(からほり)商店街にありました。

「こんぶ土居」
大阪市内で100年以上前に創業し、
今やパリの三つ星レストランのシェフが直接買い付けにくるほどの老舗です。
上質な北海道産の昆布を取り扱っていますが、
特筆すべきは、その目利き力。

既に産地で等級分けされてきている昆布を、再度職人の目で確認し、
だし用、佃煮用、とろろ昆布用など、用途によって使い分けをしています。
実際に、味見をさせてもらうと、
右の黒っぽいものは、鼻に抜けるような強い風味があり、
左の白っぽいものは、まろやかで深い味わいを感じる等、
同じ昆布、同じ産地とはいえ、実に風味は様々。

「右のがBランクのもので、左のがAランク」
昆布の種類は14属45種とあるそうですが、
こんぶ土居では、これらの産地や生産者によって異なる昆布を、
毎年きちんと採点していっているんだそうです。
そして、3代目の土居成吉(しげよし)さんは、30年ほど前から
産地に直接足を運ぶようになったといいます。
それは、ちょうど昆布の乾燥方法が変わり、養殖が始まった時期であり、
土居成吉さんは昆布の見た目や味からその変化を察知し、
実際に現場で何が起こっているかを確かめに行ったのです。
以来、毎年産地を訪れ、生産者との信頼関係を作る一方で、
産地の小学校へ出向いて「いかにその地のこんぶが素晴らしいか」
を伝えるなど、生産者の後継者を育成する活動も行ってきました。
最近では父親に続いて、4代目の土居純一さんも
毎年産地に行って昆布漁を手伝うなどされ、
産地では"土居"の名が広く知れ渡っているそうです。
「昆布にはグルタミン酸といった、
うま味成分が多く含まれているんですよ」

そんな息子の純一さんに、だしのいろはについて教えていただきました。
人間の味覚というのは基本的に、甘味・塩味・うま味・酸味・苦味を
感じることができ、その内のうま味成分の一つが昆布に含まれています。
うま味には他にも、かつお節に多く含まれるイノシン酸などもあり、
これらが組み合わさると、よりおいしさが増すんだそう。
「昆布は水出し、かつお節はお湯出しが基本。
ただ、現在売られている合わせだしの素などは、
パックをそのまま煮出すから、昆布のうま味がキチンと出ていないんですね。
うちでは業界初(!?)昆布とかつお節のパックを分けた、だしパックを開発しました」

他にも、昆布とかつお節からとっただしを濃縮した
10倍に薄めるだけで使える「十倍だし」という商品も。

伝統を大切にしながらも、時代にあった本物の品を提供していっています。
「海外では注目されつつある日本のだし文化も、
肝心の日本では下火なんですけどね」
現在、日本では、そもそも素材からだしを取る家庭が少なくなってきており、
洋食化や簡易な化学調味料に流れているのが現状だそうです。
素材から取られるだしには、うま味成分を始め、
化学調味料にはないミネラル等、様々な微量の栄養素が含まれます。
なにより自然素材ゆえに画一化した味にならないため、
調理のおもしろさがそこにあるんだとか。
かつてイタリアの飲食店での勤務経験を持つ純一さんは、
こうした日本食文化の持つ良さを外から気付き、
その維持繁栄のために、父親の後を継ぐ決心をし、帰郷されました。
今では、だしの取り方講座を店舗で開催したり、
だし文化の啓蒙活動にも精を出されています。
「日本独特のだし文化。この文化を輸出産業にしていきたいですよね」

日本料理の命ともいえるだし文化を伝える「こんぶ土居」親子の役割は、
日に日に大きくなっていきそうです。
coccori(コッコリ)
先日のブログでご紹介した「ファブリカ村」を訪れた際、
一際、目を奪われたカラフルな展示品の数々。

一つひとつから醸し出される温かみから、
きっとそれが人の手によってゆっくりと作られたものであることを感じました。
その織物の名は「coccori(コッコリ)」。

実はこれらは、滋賀県の福祉作業所で働く
障がい者の方たちによって作られたものでした。
「素敵でしょ? でも、しばらく作業所の倉庫に眠っていたんですよ」
そう話すのは、Team coccori事業代表の市田恭子さん。

作業所の中間支援を行う (社)滋賀県社会就労事業振興センターで、
障がい者IT利用促進事業コーディネーターとして働く市田さんは、
これらの織物が、作業所の倉庫に保管されているのを発見しました。
繊維関係の工場などから、不要品として調達してきた糸を使って、
障がい者の方たちが一生懸命、はた織り機を使って織ったものでしたが、
売るあてもなく、そのままの状態で眠っていたのです。
「これはかわいい! 倉庫に眠らせておくなんてもったいない。
なんとかできないか? って考えました」
こうして市田さんは、滋賀県内で活躍するデザイナー6名とともに
「Team coccori」を結成。
"作りっぱなしの商品"から"買ってもらえる商品"にするために、
様々な商品を企画していきました。
かけるだけで映える敷物や首ストラップ、
鍋包み(写真右)に、現在企画中のペンケース(写真左)等々。

ストールはこの通り、とっても素敵♪

同じものが二つとない独創的な色合いが魅力的です。
「この事業で実現したいことは、何よりも障がい者の工賃向上なんです」
市田さんいわく、作業所で働く障がい者の賃金は、
全国的にみて月平均1万3000円といったところ。
障がい者年金と合わせてもとても自立できる金額とはいえません。
重度の障がい者がきちんとした社会保障を受けられるようにするためにも、
元気な障がい者が、税金を納められるぐらいの稼ぎを得られるようにする。
市田さんは活動目的をそう話します。
Team coccoriでは、他にもこんな逸品も展開していました。
「湖のくに 生チーズケーキ」

何やら入っているのはおちょこのようで、
一つひとつ書かれている文字が違います。
そう、これらは滋賀県内の琵琶湖周辺にある6つの酒蔵の、
風味の異なる"酒粕"を使ったチーズケーキなんです。
酒粕とは、お酒を作る時にできる米麹の搾りかすで、
近年、栄養素に富んだ食品として価値が見直されており、
酒蔵によっては"しずく"と呼んでいるほどの代物。
これまでも甘酒や漬物などにも利用されてきましたが、
とても使いきれる量ではなく、その使い道に頭を悩ます酒蔵も多かったそう。
それが、県内の作業所で働く障がい者の手によって、
生チーズケーキへと生まれ変わったのです。

そのお味はとても芳醇で、
お酒と同様に、酒蔵によって風味が見事に異なりました!
これを、同じく作業所で作られた「酒粕ビスコッティ」に付けると、
格別な味わい。

スイーツとしてはもちろんのこと、
ワインのつまみにもイケてしまいそうです!
日本酒の酒粕が、ワインに合うなんてまた不思議ですね。
「障がいのある方たちも、基本的欲求は健常者と一緒。
認められて、その対価をもらうとうれしいんです。
これらの事業によって、明らかに生活に張りが出てきた方もいるんですよ」

coccoriによって明らかに変化が生まれている滋賀県の福祉事業。
ただ、そこから生み出される商品は、
作り手が障がい者か健常者かということではなく、
素直に感動を受けるものばかりでした。
すぐき漬け
「柴漬け」「千枚漬け」と並んで"京都の三大漬物"といわれるのが、
カブの変種であるすぐき菜を原材料とする「すぐき漬け」。

もともとすぐき菜は、桃山時代に上賀茂神社の社家によって
栽培が始まったといわれているようですが、
1804年に京都所司代から出された「就御書口上書」で
他村への持ち出しが禁じられたことから、
限られた地域だけで栽培され、栽培技術が口伝で受け継がれてきました。
京都市内から車で約20分の北区上賀茂地域で
すぐき菜を栽培しているという、田鶴均さんを訪ねました。
「普通の漬物は、漬けるのは漬物屋の仕事ですが、
すぐきは農家が全部やるんですよ」

残念ながら私たちが訪問した1月には、
すでにすぐき漬けの仕込みは終わっており、
その現場を拝見することはできなかったのですが、
田鶴さんの家では、すぐき菜の種の採取から、
種蒔き、栽培、収穫、漬けの作業すべてを自分たちで行うのだそうです。
「種は売っているものではなく、各家に代々受け継がれてきたもの。
同じすぐき菜にしても家によって品種が異なるから、漬け方にしたって違う」
収穫したすぐき菜の皮を剥き、一晩塩漬けにした後、
天秤で押しをかけて本漬けし、室で発酵させるそう。
現在五十数軒あるすぐき農家のうち、ほとんどは電気で室を温めるそうですが、
田鶴さんの家では、炭火で温めるという伝統的な漬け方を
今も変わらず行っているといいます。

現代の日本においては、数少ない本格的な乳酸発酵漬物で、
その味は酸味の効いたすっきりしたもの。
このすぐき菜は、京都府によって認定された「京の伝統野菜」のひとつです。
京都には、千年の都の歴史の中で、地方からの献上品をはじめ、
全国各地から様々な野菜の種が集まり、その中から
それぞれの土地にあう良いものだけを残して、代々受け継いできました。
しかし、作り手の農家によって品種が異なるため、
形の統一、味の統一がしにくいことから徐々に市場から嫌厭され、
30年ほど前には絶滅の危機にあったそう。
そんな時、これではマズイ!と立ち上がった
料亭と若手農家のグループがあり、
「復活させよう!京の伝統野菜」という運動を行ったことで、
1987年から行政が「京の伝統野菜」として認定し、
世間で見直されるようになったのです。
実は田鶴さんは、その時の若手農家の一人でした。
「九条葱、賀茂茄子、聖護院かぶら…
京野菜には作られた場所の地名が付いていますが、
それだけその土地に適しているってことです」
ほとんどの京野菜を育てているという田鶴さんの畑では、
冬野菜の「聖護院大根」や「九条葱」が栽培されていました。
「『作物は人間の足音で育つ』っていうんです。日々野菜の顔を見て、
タイミングを見て体調管理をしてあげることが大切」
京の伝統野菜は"京都"というひとつのブランドによって、
他の地域の在来種よりも広く全国的に知られているように思いますが、
その裏には田鶴さんのような、伝統を廃れさせてはいけない
という想いを持った生産者がいたことを知りました。
清らかな酢
日本三景のひとつに数えられる天橋立(あまのはしだて)。
その近くの京都府宮津市に、地元で評判のお酢屋さんがありました。

明治26年創業の「飯尾醸造」。
約400社あるといわれる日本の食酢メーカーにおいても、
自社で醸造設備を持つのは約1/3といわれていますが、
なかでも飯尾醸造は天然醸造を手掛ける希少な酢蔵です。
突然の訪問にもかかわらず、
快く迎えてくださったのが蔵人、秋山俊朗さん。

もともと、酢が苦手だったという神奈川県出身の秋山さんは、
飯尾醸造の酢を飲んで、初めてそのおいしさを知り、
勤めるにまで至ったそうです。
早速、その味を試させてもらうと、
その理由が分かるような気がしました。

深いコクのせいか、実に味わい深く、
酢独特の酸味にツンとしたトゲを感じないのです。
そこには飯尾醸造の酢造りに対する徹底した姿勢が表れていました。
以前、鹿児島県で取り上げた黒酢は、
米から酢になるまでの全工程をひとつの壺の中で完結させていましたが、
一般的には、酒を酢酸発酵させたものが酢となります。
醸造用アルコールを使って作られる酢も多いなか、
飯尾醸造では、なんとその酒造りから手掛けていました。
つまり正真正銘の純米酒から酢を造っているのです。
さらに酒造りには当然、良質な米が必要になるわけですが、
その米においても、農薬・除草剤を一切使わずに作られた
地元・丹後の契約農家と自社で手掛けたものに限る徹底ぶり。

「昭和30年代、現在より毒性の強い農薬が使用され
ドジョウもフナもいなくなった田んぼを見た先々代が、
"生き物も棲めない田んぼで作った米では体がおかしくなる"
と安全性の高い米づくりを提唱したことがきっかけです」
と、秋山さんはその理由を振り返ります。
そして、そんな手間隙かけて作られた米を、
ふんだんに使用していることも飯尾醸造の特徴です。
日本では1リットルの酢を作るのに40gの米を使っていれば、
"米酢"と表示してよいことになっているのですが、
看板商品「純米富士酢」では実にその5倍の200g、
さらに「富士酢プレミアム」では320gもの米を使用しているのです。

こうして造られた酢の素になるもろみを水と種酢と混ぜ、
発酵途中の別のタンクから活発な酢酸菌膜を入れ、発酵させること90〜150日。

さらに、角をなくすための熟成に240日以上。
原料から商品として出荷するまでに1年以上、
米づくりから換算すると1年半以上の歳月をかけているのです。
こうして造られたお酢が、おいしくないわけがありません。

「富士酢」という商品名には、
初代の"日本で一番の酢を造りたい"という想いが込められているそう。
今では、多種多様な果実酢も展開しています。

高酸度のお酢に、甘い濃縮果汁を加える製法とは異なり、
生の完熟果実からもろみを造り、発酵と熟成を重ねています。
どれも果実ならではの風味が口いっぱいに広がりながらも、
お酢としての酸味を損なわない味わいがしました。
安全でおいしいのはもちろんのこと、"地域とともにある"、
というのがモットーの飯尾醸造の酢。
地域で評判の酢は、地域にも優しいものでした。
淡路島の心地よいくらし
淡路島で訪れた「樂久登窯(らくとうがま)」。

祖父母の古民家を改装したという工房、兼「gallery+cafe」は、
地元の漁師さんたちで賑わい、温かみのある雰囲気に包まれていました。
その雰囲気を助長しているのは、これらの器たち。
実に多彩な技法が駆使されているのも、陶工の西村昌晃(まさあき)さんが、
先日のブログでも記した丹波立杭焼で修業をされてきた証でした。
丹波の窯元で6年間薫陶を受けられた西村さんは、祖母の住む淡路島に戻り、
2年前にこの窯、兼「gallery+cafe」を立ち上げられました。
一風変わっているのが、
陶工として器づくりに励みながらも、記者としての一面も持っていること。
「自分の器に盛られる食材の成り立ちと、
生産者の想いを知りたいと思ったんです」

「自分はバトンを渡されている。一体、どこから始まっていたのか?
そんな好奇心から、身の回りの生産現場やその想いを取材し、
一冊の本としてまとめていきたくなりまして」
そう考えるようになっていった西村さんは、
「rakutogama book」の発刊のために、取材活動を始めるようになりました。
島に住みながら、島の生産者の取材をする。
そうすることで、季節を追うことができるし、
家畜牛の出産シーンなど決定的な瞬間にも立ち会うことができる。
その地の利を生かした取材ぶりは、プロも顔負けするほどです。
こうして食材の背景を知ることで、器づくりに対する姿勢も
大きく変化していったといいます。
「何より器の向こう側にある風景を想像できるようになったこと。
形として表現するのは難しいですが、
明らかに自分のなかで変化が起こりました」

以前は東京の展示会や店舗などにも出品していたという西村さんでしたが、
流行や売れ筋に振り回されることに強い違和感を覚えるようになります。
都会のセンスにとらわれずに、もっと身の回りの生産者が作った食材を
おいしく食べてもらうための器づくりでいいのではないか。
そう考えるようになっていったそうです。
そして、長い歳月をかけて取材をされ、
最近、完成したばかりという作品がこちら。

淡路黒炊飯土鍋。
同じ淡路島内で「合鴨農法」という有機農法で米作りをされている
花岡農恵園を取材したことをきっかけに手掛けた逸品です。
「とにかく手間隙かけて作られた合鴨農法米。
いかにおいしくいただくかを念頭に作りました」
そう西村さんが話す通り、そこには時代や流行にとらわれない、
作り手の想いが交錯する空気感を感じました。
そんな西村さんが強いインスピレーションを受けたという「花岡農恵園」を訪ねると、
確かにそこには強い信念のもと、活動される素晴らしい生産者の姿が。
花岡明宏さん、36歳。

花岡農恵園代表の花岡さんは、
3児の父親でもあります。
「子供たちに安全安心なものを食べさせてあげたい」
と話す花岡さんの田畑は、完全有機農法。
有機は困難といわれる米作りにおいても、
先述の「合鴨農法」という方法で、無農薬で生産しています。
私たちが訪れた12月は、ちょうど米の収穫後でしたが、
田植え後1週間から穂が出るまでの2ヵ月ほどは、
その名の通り「合鴨」が田んぼを泳いでいるんだそう。
生まれたての合鴨の雛を水田に放鳥することで、
雑草や害虫を餌として食べてくれ、かつ、排泄物が肥料となるわけです。

ただ、農薬や化学肥料を使用しないため、
手入れに手間隙がかかるうえに、一般的には収穫量が下がることから、
手掛けている農家が少ないのが現状です。
それでも「地域内循環」に強い興味があると話す花岡さんは、
「農薬や肥料も外に頼る必要はないのではないかと。
もっと自分たちでできることを、地域のなかで循環させていければいい。
有機農法は、そのベースになりうると思っています」
と語ります。
現に花岡農恵園では、牛や鶏も飼い、
その排泄物を堆肥にして農園に還元していっています。
「できればこれを島単位でやっていけたらいいですよね。
家畜の餌や堆肥を地域のなかで回していき、そこに雇用が生まれる。
そんな循環を夢見ています」
花岡さんは現在、新規就農を目指す若者の指導もしています。
そんな花岡さんの想いの詰まった「愛鴨米」は、
西村さんの「rakutogama cafe」でも、平日限定ランチで提供されています。

流通の発達から、見失いつつある地元にある宝物。
淡路島では、今一度それらを見直し、生産者同士が強固につながっていくことで、
新しい潮流が生まれ始めています。
「ただ、楽しいことを実践していきたいだけなんですけどね」

最後にそう笑顔で話される西村さんの言葉に、
人間が本来持ち合わせている心の中のセンサーの中にこそ、
これからのくらしのヒントが隠されているように感じました。
極上の甘み、和三盆
江戸時代、鎖国中の日本で唯一、開かれていた長崎県の出島には、
外国との交易のために、日本で大量に採掘された金銀が集められていました。
それら金銀で取引されていた主要な輸入品の一つが、「砂糖」。
当時、輸入のみで賄われていた砂糖は貴重品として扱われていました。
京、大阪、江戸へと運ぶのにたどる長崎街道は別名「シュガーロード」とも呼ばれ、
街道筋では古くから甘い菓子づくりが盛んに。
「長崎カステラ」や、飯塚銘菓「ひよこ」もその類です。
しかし、産出する金銀が枯渇してくると、
幕府は砂糖の輸入を減らすため、国内でのサトウキビの生産を推奨します。
各藩が砂糖生産にしのぎを削るなか、特に高松藩がサトウキビ栽培を奨励。
サトウキビから抽出される黒糖を白糖に精製する技術も確立し、
これらは「和三盆(わさんぼん)」と呼ばれる高級砂糖として流通しました。
この和三盆は、今でも香川県と徳島県の一部地域で生産され、
和菓子づくりには欠かせない砂糖として使用されています。
香川では、この和三盆を干菓子にするための「木型」を作る職人を訪ねましたが、
徳島県では、和三盆そのものを作る現場を訪ねることができました。
徳島県上板町にある「岡田製糖所」。

吉野川の下流域にあたる上板町の土壌は非常に痩せており、
芋さえも満足に育たなかったそうですが、
日照時間の長さと温暖な気候は、サトウキビの栽培には適していたそうです。
訪れた12月中旬は、ちょうど収穫真っ最中で、
50軒弱の契約農家から収穫されたサトウキビが次々運び込まれてきました。
ここで栽培されているのは「竹糖」といって、
沖縄などのサトウキビとは品種が異なり、背丈が低く茎が細いのが特徴です。
ゆえに、搾り汁も限られるため、生産量も多くは確保できません。
ただ、寒さにも強い品種で基本、農薬も必要とせず、
きめの細かい糖分が搾取できるんだそう。
この竹糖の搾り汁から、あくや沈殿物を取り除き、
撹拌しながら煮詰めて、「白下糖」を作っていきます。
この時点では、まだご覧のようなキャラメル色で、糖蜜が含まれています。
糖蜜はミネラル分などの不純物を多く含み、風味が豊か。
ただ、調理の現場からは、風味が少なく甘みの強調されたものが求められるため、
ここから不純物を取り除いた白い砂糖へと加工されていくのです。
ある程度、寝かした状態の白下糖を麻袋に入れ、
酒造りと同じように「押し船」と呼ばれる原始的な器機にかけられます。

徐々に石の重しを加えていくことによって、
ゆっくりと糖蜜を搾り出すのです。
ある程度、蜜を抜いたら、いよいよ和三盆の要ともいえる「研ぎ」の作業へ。

研槽(とぎぶね)と呼ばれる桜の木の台上で、
熟練の職人が精力を注ぎ込みながら、ギュッギュッとこねていきますが、
この時、加える水の量と力具合がポイント。

かつては盆の上で3回研いでいたことから、
和三盆と呼ばれるようになったんだとか。
これを現在では1週間にわたって5回も繰り返し行い、
徐々にとろみのある白色の砂糖へと研いでいくのです。

これを乾燥させ、ふるいにかけるとサラサラの「和三盆」が完成。
ひと舐めさせてもらうと、
ふわりとした上品な甘みが口の中に優しく広がりました。
現在、市場に流通する「上白糖」や「グラニュー糖」といった精製糖の多くは、
機械によって脱色・結晶化したもので、糖度はほぼ100%。
ただ、こうして手作業で研がれた「和三盆」の糖度は85~90%で、
微量のミネラル等がまだ含まれているのです。
父親の後を継いで、研ぎ職人になった坂東永一さんは、
和三盆づくりに対する想いをこう語ります。

「この地域で慣れ親しまれた甘みですから。
父親に負けない和三盆づくりをせんとね」
サトウキビ畑に囲まれて育った坂東さんにとって、
和三盆は小さな頃からの記憶の塊といえるのかもしれません。
この地域で愛されてきた極上の甘みは、父から子へと引き継がれ、
今では全国の甘味ファンの舌を満たしています。
意外な四国の文化圏
訪れるまで四国は一つの文化圏として成立しているのかと思っていましたが、
実際は4県ともにそれぞれ向いてる方向が異なっていました。
香川は岡山、愛媛は広島、徳島は関西、そして、
それら3県に囲まれて独自の文化圏を築く高知は海の先のアメリカ、
というのが、四国人の中でのまことしやかな定説なんだそう。
確かに香川での天気予報は、四国括りではなく岡山と一緒に放送されていましたし、
徳島では関西の放送局が映りました。
そんな徳島で訪れた無印良品「ゆめタウン徳島![]() 」では、
」では、
影響の強い関西TVの番組で紹介された商品が大人気なんだとか。
それは…、

「マイルドオイルクレンジング」です!
オリーブオイル・ホホバオイル配合で、
うるおい成分にはアンズ果汁、桃の葉エキス使用。
無香料で仕上がっています。

スタッフさんいわく、ポイントメイクにも素早く馴染んでしっかり落とし、
目に入ってもくもりにくいそうですよ♪
私も次のクレンジングに試してみたいと思います!
つまみになる塩
広大な太平洋に面した高知県黒潮町(くろしおちょう)。

この町には佐賀地区を中心に、
実に5軒もの工房が塩づくりに励んでいます。
温暖で日射しの強い太平洋性の気候で、
四万十川を源流とする伊予喜(いよき)川が山のミネラルを海へと運びこむうえ、
地元住民によって美しい海が保全されてきたことから、
日本でも有数の塩づくりに適した環境なのです。
そんな黒潮町で、最初に塩づくりを始めた
「土佐のあまみ屋」を訪ねました。

晴天に恵まれたその日は、
12月中旬にもかかわらず長袖では汗ばむほどで、
自然製塩にはもってこいの気候であることを実感しました。
「人間はもともと、海から生まれてきたといわれているんです。
羊水と海水の成分は似ていますから。
塩は人間にとってとても大切な要素なんですよ」

そう話すのは、土佐のあまみ屋の小島(おじま)正明さん。
塩づくりに対する熱い想いを語っていただきました。
「そんな大切なものにもかかわらず、日本に流通している塩の多くは化学製塩、
つまり塩化ナトリウム99.9%のものでした。
いい塩を作り流通させることで、本物を知ってもらいたいんです」
小島さんがこの地で塩づくりを始めたのは昭和56年のこと。
当時、日本は塩の専売法が敷かれており、
タバコなどと同様に、特定業者にしか製塩、販売が認められていませんでした。
電気化学的に海水から塩化ナトリウムだけを取り出して作られる塩は、
味の尖った、刺激の強いものとなり、
過剰摂取によっては現代病を引き起こす要因ともいわれました。
当時より原発をはじめとした化学による汚染を懸念していた小島さんは、
伊豆大島で研究所として唯一、認められていた自然製塩所で研修を受け、
故郷、高知で製塩所を立ち上げるに至ります。
「海からできる塩は、もちろん作り方によりますが、
塩化ナトリウムは80%ほど。残りはミネラル分です」
その作り方は「流化式製塩法」といって、
これまでのキャラバンで見てきた「揚げ浜式製塩法」や
「入り浜式製塩法」をさらに進化させたものでした。

海から汲み上げた海水を、
ネットの張り巡らされた木組みのタワーに上から噴霧し、
海水がネットを伝って落ちていく間に、
太陽と風の力で水分が蒸発し、塩分が凝縮されていきます。
これを繰り返すことで作られる塩分濃度の高い水を
隣接するビニールハウスに移し、天日干し。

こうして太陽の力が、塩の結晶を生みだし、
残った水分はにがりとなるのです。

かつては、釜焚きによる塩づくりも行っていたという小島さんでしたが、
微量のミネラル分を失わないために、15年ほど前に、
ゆっくりと結晶化させる天日干しに切り替えられました。
「塩は生き物だから、全く同じものは作れないんですよ。
そんななか、私の求める"いい塩"とは、ふわっとした塩。
つまみになる塩を目指しています」

結晶が大きく仕上がる天日塩ですが、
小島さんのつくる塩は尖らず、甘みがふんわりと口いっぱいに広がります。
マイルドな味で、おっしゃる通り、お酒のつまみとして舐めたいと思えるほど。
その味の通り「あまみ」と名付けられています。

最後に、大切にしていることを伺うと、
こう応えてくれた小島さん。
「正しいか正しくないかでモノゴトを選ぶんじゃなく、
楽しいか楽しくないかで選択をしていきたいですね」

ただ、ひたすら正しい塩づくりを追求しているのかと思いきや、
それは意外な回答でした。
ほんのり甘くて、つまみになる塩は、
小島さんが楽しみながら作った味でした。
土佐文旦
木の枝にたわわにぶら下がる、山吹色のフルーツ。

これは高知県下で育てられている「土佐文旦」です。
なかでも、土佐市はその発祥の地とされ、
12月初旬に訪れた私たちは、
山の斜面にたくさんの果実を見かけることができました。

高知県では冬になると各家庭で食べる味だそうですが、
生産量があまり多くないため、
これまで県外にはあまり出荷されてこなかったそうです。
県外の人が目にするのはほとんどが贈答品として。
出荷時期が短く、旬は2~3月なので、
土佐文旦は"高知県の春の便り"といわれ、
文旦が届くと受け取った人は「もうすぐ春かぁ~」と思うんだとか。
さて、今回私たちは車がやっと1台通れる幅の坂道をぐるぐると登り、
土佐文旦農家の青木秀成さん、真弓さんご夫妻を訪ねました。

手のひらからあふれそうな大きさの文旦ですが、
もともとはマレー半島やインドネシアの辺りで生まれ、
中国を経て、九州に伝来してきたものだそう。
グレープフルーツに似ているなと思っていたら、
それもそのはず、マレー半島から東に伝わったものが文旦で、
西に伝わったものがグレープフルーツだと教えてもらいました。

グレープフルーツが、柑橘系の果物なのに
なぜ"グレープ"という名が付いたのかというと、
ぶどうの房のように1本の枝にたくさんの実をつけるからだといい、
それは確かに文旦にも当てはまることです。
「100%手をかけて育てるのがモットー。子どもと一緒です」
と、はにかみながら青木さんが話すと、
隣で奥さんの真弓さんがこう加えます。
「これってクールジャパンじゃないかしら。
こんなにも細かく面倒を見るのは、他の国ではやっていないと思いますよ」

温州みかんは、花粉が無くても、実になりますが、
土佐文旦の場合は、着果の安定や品質向上のために、
他のカンキツ(日向夏)で人工授粉を行うのだそうです。
日向夏のつぼみから採った花粉を、
文旦の花ひとつひとつに根気よくつけていきます。
それでも、花粉をつけた花のうち、
約4分の1しか実際に果実にならないというから、
実った果実を子どものように手をかけてかわいがっていくのも納得です。
ちなみに、種があって大きく球体のものが人工受粉でできた果実で、
自然に任せると種が入らず小さくて洋梨型の果実になるそう。
一見、種がない方が食べやすく、よい果実のような気がしてしまいますが、
種がしっかりと入っているのは子孫を残すため、
ひとつでも多く繁殖するための自然現象のひとつなのです。
また、放っておいたらどんどん上に伸びていってしまう枝を、
太陽がキレイに当たるように剪定するのも重要な作業です。
青木さんいわく、
「長年の経験で、剪定するバランスを体が覚えている」んだとか。
それから土佐文旦栽培の大きな特徴が、
収穫後に1年間の農作業の集大成として行う「野囲い」です。
文旦畑の一部を板で囲い、ワラを敷いて、
その上に文旦を並べ、1~3ヵ月寝かせておくのだそう。
これは追熟のためで、酸が抜け、味がまろやかに、
果肉も柔らかくなるんだそうですよ。
ここまで手を加えてから出荷されるなんて、
奥さん真弓さんおっしゃる通り、これぞクールジャパンかもしれませんね。
残念ながらまだ口にすることのできなかった土佐文旦。

「皮をキレイに剥けたら達成感。
さらに食べて満足感が得られると思いますよ」
果汁が少ないので手が汚れずに皮を剥くことができ、
口の中でプリプリの果実の食感と、ジュワ~と広がるうまみを味わえるそう!
なんだか想像しただけで、よだれが出てきますね。

とっても明るく賑やかな青木さんご夫妻の作る土佐文旦は、
Cafe&Meal MUJIのデザートとデリで味わうことができます。
どうぞお楽しみに★
原風景を守る、沢渡茶
「誰にでも思い出の風景ってあるじゃないですか。
それが僕にとってはこの沢渡(さわたり)なんです」

大きな体で、照れくさそうな笑顔を見せながら、
岸本憲明さんはその想いを語ってくれました。
水質日本一の河川のひとつ、仁淀川(によどがわ)上流に位置する沢渡は、
知る人ぞ知るお茶の産地。

ただ過去長い間、この地で生産される茶葉のほとんどが県外へ送られ、
県外の茶とブレンドされて市場に出荷されていたそうなのです。
近年、お茶の消費の落ち込みから価格低迷が続き、
認知度の低い高知の茶農家は、徐々にその数を減らしていきました。
祖父母が茶農家で、幼いころ頻繁に沢渡を訪れていた岸本さんは、
近くの川で遊んだり、おじいさんと一緒に山に登ったり、
また、毎年行われている土佐三大祭のひとつ、「秋葉祭り」にも参加してきました。
しかし、歳を重ねるごとに、
昔から見ていた風景が変わっていくことを実感します。
「原風景を守っていかなきゃならん」
我慢できなくなった岸本さんは、奥さんを口説いて、大工の仕事を辞め、
おじいさんの茶畑を継ぐべく、5年前に高知市内から移住しました。
「昔からこの地には、お茶の木が自生していたんですよ。
お茶を栽培するには最適な環境なんです」

ご覧の通り、山の傾斜地に美しく広がる沢渡の茶畑には、
毎日のように朝霧が降り注ぐんだそう。
その朝霧によって茶葉が水泡をまとい、太陽の光を和らげるので、
茶葉の旨みが凝縮され、お茶に甘みが生まれるということなのです。

実際、今年行われた「高知県茶品評会審査会」では、
最優秀賞を沢渡で生産されたお茶が受賞したんだとか。
素晴らしいですね!
私たちが訪れた12月上旬は、ちょうど剪定を終えた後で、
茶葉は冬眠に入るのを待ち構えている状態でした。

そして、お茶の若葉がいっぱいになる4月下旬頃、
新芽が摘まれ、それが「一番茶」として出荷されていくのです。
こうしてできたお茶を、岸本さんは「沢渡茶」と名付けました。

「岸本茶でも良かったんですけどね(笑)
"沢渡"の地名をもっと多くの人に知ってもらいたくて」
そういいながら岸本さんが出してくれた沢渡茶は、
香り・渋み・甘みのバランスが絶妙でした。
また、沢渡茶は3煎目ぐらいまで、味が落ちずにおいしく飲めるのが特徴だそう。
ただ、ここで岸本さんの挑戦は終わりません。
一番茶のみを摘んでいた沢渡で、初めて、
二番茶の茶摘み(6月中旬)に踏み切ったのです。
「茶畑の景観を守っていくためにも、農家が専業でやっていけるように、
さらなる商品開発が必要だと考えました」
一般的に苦みが強くなるといわれる二番茶ですが、
岸本さんはこれを「緑茶」としてではなく、なんと「紅茶」として加工しました。
茶葉は緑茶にするには、摘んでからすぐに蒸して酸化を止めるのですが、
紅茶にするには、一晩寝かしてから発酵を促すそうなのです。
緑茶と紅茶の違いは、発酵の有無にあり、
発酵させることで、茶葉が赤茶けていくんだとか。
こうして二番茶から作られた紅茶「香ル茶」は、
もちろん「ダージリン」「アッサム」など
紅茶用の茶葉の品種から作られたものとは風味が異なりますが、
独特の甘みが特徴の渋みの少ない"和紅茶"です。

他にも、一番茶を贅沢に釜炒りにした「俺の番茶」も開発し、
高知のお茶として、世に展開していっています。

「原風景を守りたい、その一心だけでやっています。
夢は、法人化して雇用を生みながら、沢渡の景観を守っていくこと。
まだまだ採算は厳しいですけどね(笑)」

そんな岸本さんは、「秋葉祭り」の主役・鳥毛役も担っているそう。
「うちのじいちゃんも昔、鳥毛役やっていたらしくて。
この祭りも失くしたくないし、じいちゃんの地元を失くしたくない。
じいちゃんが守ってきたものを、生活できる農業にして、
子供たちにちゃんと残してあげたい」
別れ際にも照れくさそうに微笑む岸本さんを前に、
「自分にとっての原風景はどこか」を考えている私たちがいました。
2児の父親でもある岸本さんの挑戦は、まだ始まったばかり。
岸本さんの作る沢渡茶シリーズは、
Found MUJIの一部店舗でもお買い求めいただけます。
【お知らせ】
MUJIキャラバン連載ブログの年内更新は本日で終わりです。
2013年は1月9日(水)より再開となりますので
どうぞよろしくお願い致します。
うどん県のうどん事情
「このたび香川県はうどん県に改名いたします」
と斬新なキャッチフレーズで観光キャンペーンを打ち出したのは、
記憶に新しい2011年のこと。
事実、香川県民の家計における「うどん」の消費量はずば抜けており、
観光客も香川の魅力について、第一に「うどん」を挙げるというデータもあるそうです。
滞在した1週間のあいだ、うどんを食さない日はなかったぐらい、
うどん三昧の毎日を送った私たちでしたが、不思議と飽きがきませんでした。
それもそのはずで、その食べ方も具材も実に多彩。
釜あげにぶっかけ、しょうゆにダシ汁、カレーはもちろんのこと、
トッピングは肉、人気のちくわ天、ゴボ天、かきあげ、
なかにはたまご天なんていうものまで!
そのお店のスタイルも「一般店」をはじめ、「製麺所付属店」、
最近では「セルフ」といって、カウンターでうどんの玉数を注文し、
あとは自由にトッピングを加えることができるスタイルのお店も多く、
なかには、自分でうどんを湯通しするところもありました。

県内に700店舗ほどあるといわれるうどん店が、
しのぎを削り合っているわけなので、
そりゃどこもおいしいし、様々な創意工夫が生まれるわけです。
そもそも香川県でここまでうどんが食されるようになったのには、
その風土が大きく影響しているといわれています。
降水量が少なく、たびたび干ばつに悩まされてきた香川では、
お米の安定的な生産ができなかったため、代わりに小麦の生産に力を入れてきました。
また、19世紀はじめには全国の約90%の塩が瀬戸内海沿岸で作られていたほど、
香川でも塩づくりが盛んでした。
さらに、先日ブログにアップした良質な小豆島の醤油、
豊富な瀬戸内海産のダシの素になるイリコ(カタクチイワシ)と、
うどんの原料となる素材が手に入りやすい環境にあったのです。
つまり、香川ではうどんは米の代用食のようなものだった様子。
これが、昭和45年の大阪万博で「讃岐うどん」の名が全国に広まり、
その後の瀬戸大橋開通などによって、店舗展開に拍車がかかったそう。
今ではその圧倒的な安さとおいしさゆえに、
他の外食麺レストランの進出は困難だそうです。
それにしても、なぜ讃岐うどんはここまでおいしいのでしょうか?
せっかくなので、讃岐うどんの本場、琴平町で、うどん打ちを体験してきました!
まずは中力粉に食塩水を加え、全体にまぶしていきます。
この食塩水の塩加減を、冬<春秋<夏と変えることが、
年間を通してコシのあるうどんに仕上げるポイントだそう。
そして、しっかり手でこねあげたら、それを袋に入れて足踏み。


これがコシの強さを生みます!
その後、ある程度(季節に応じて1~3時間)寝かせて熟成。
これに打ち粉を振りかけて手で広げ、麺棒で延ばしていくんです。
麺棒を生地に巻きつけながら前方に押し出すように延ばし、
そのまま生地を浮かせながら手前に戻すという「すかし打ち」は、
讃岐独特の高度な技法だそうです。
こうして均等に延ばした生地を重ね、3~5mm間隔で切っていきます。

これをたっぷりのお湯の中に入れて茹でること約10分。

讃岐うどんの完成です!

これをダシ汁で食べるもよし、ぶっかけで食べるもよしですが、
今回はしょうゆで頂きました。
つるつるしこしこの麺は、
ちょっとした味付けだけで極上の味でしたよ♪
その土地に根ざした食には、
その土地ならではの背景、秘伝がありました。
うどん県での人気商品とは!?
そんなうどん県の県庁所在地にある
「無印良品 高松店![]() 」の人気商品はなんと…、
」の人気商品はなんと…、

自転車でした!
平地の多い高松市内では、自転車で通勤・通学する方も多いんだそう。

高松店は、市街地の中心地にあるため、
自転車を買って、すぐに乗って帰るお客様もいらっしゃるそうです。
なかには、三輪車から始まって、16→20→26インチと
ずっと無印良品の製品を使い続けてくださる方も!

おいしいうどんをたくさん食べて、自転車で消費する。
これがうどん県のライフスタイルなのかもしれませんね!
「醤の郷」の醤油づくり
このキャラバンのテーマの一つでもある、
同じ名を持ちながら、土地によってわずかに違うもの。
その代表格の一つが「醤油」ではないでしょうか。
これまでの旅路にも各県、必ずといっていいほど、
その地に根ざした醤油蔵が現存し、
地域の味覚に合わせた醤油づくりが行われていました。
一般に関東は濃口、関西は淡口、九州は甘口…といわれるように、
地域の味覚が違うことを象徴しているように思います。
そんな醤油にも、日本四大産地と呼ばれる土地があり、
旅のスタート時に訪れた千葉県の銚子をはじめ、
千葉県の野田、兵庫県の竜野、香川県の小豆島(しょうどしま)がそれに当たります。
その内の一つ、香川県の小豆島を訪ねました。

人口3万人強のこの島には、
最盛期には400もの醤油の蔵元が存在したそう。
温暖で雨が少なく乾燥した気候が、
麹菌の発育など醤油づくりに適した環境をもたらすようで、
現在でも20の蔵元がしのぎを削っています。
なかでも小豆島町の馬木(うまき)~苗羽(のうま)地区は
「醤(ひしお)の郷」とも呼ばれ、
昔ながらの街並みに、食欲をそそられる香ばしい香りが漂います。

国の有形文化財に指定されている蔵も多く、
今回訪ねた「正金醤油」もその一つ。

大正9(1920)年から続く蔵元は、
現在4代目の藤井泰人さんによって引き継がれています。

「小豆島で醤油づくりが発展してきた理由は、
その地の利が大きいと思いますよ」
とても優しい笑顔で、小豆島の醤油づくりの歴史を教えてくださいました。
農耕地が少なかった小豆島では、他地域との交易が必要で、
そのために塩づくりが盛んに行われていたそうです。
そこに、本土から醤油や素麺の製法と桶が持ち込まれたことで、
その塩を使った加工業として醤油づくりも栄えていったんだとか。
また、現代のような陸上交通網が整備されていなかった時代において、
海運輸送の要所であった小豆島はとても有利で、
九州から大豆や小麦を仕入れやすく、大消費地、大阪・京都へ出荷しやすかったことが、
小豆島で醤油づくりが発展していった最大の要因だそう。
その後、品質を担保するための自主規制や、醤油税の導入、
戦争による食糧統制という厳しい時代を切り抜けたのが、
現在、残っている20軒の蔵元というわけです。
「20軒ともに、それぞれの作り方があるんですよ。
"管理方法""熟成する期間""出荷時の成分"、これによって醤油の味わいは変わります」
分かりやすくその製法のポイントを教えてくれた藤井さんの後について、
蔵の方へお邪魔すると、そこには大きな杉製の桶が。

この桶のことを、小豆島では「こが」と呼んでおり、
ひとつで5400リットル、搾ると4000リットルの醤油を作ることが可能。
この桶を128も有している正金醤油では、
中身を管理しやすいように桶の高さに合わせて2階部分が建てられており、
そこからの光景は、まるで木製の温泉を思わせます。

「左は昨日、仕込んだばかりの桶、右は仕込んでからもう1年ほど寝かせた桶」

色みからも、その深みの違いを想像できます。
醤油づくりは、蒸した大豆と小麦を混ぜたものに麹菌を加えた醤油麹に、
塩と水を加え、じっくりと発酵・熟成させたもろみを最後に搾るわけですが、
この発酵・熟成の期間は、蔵によっても桶によっても様々だそうです。
麹菌が作る酵素が、大豆や小麦に含まれる栄養素を旨味成分に分解する過程、
いわゆる"発酵"と呼ばれる期間は、自然醸造では5~6カ月といわれており、
そこから先は、味を落ち着かせるための"熟成"の期間に当たります。
機械で温度・湿度の管理が可能な大手メーカーでは、
一般的に、発酵期間が3~4ヵ月と短くて済み、
熟成前の個性の強い状態のもので出荷されますが、
「カレーは一日寝かせた方がおいしいでしょ」
と藤井さんが表現するように、寝かせることで醤油そのものの"角"がとれ、
こなれた味へと変化していくそうです。
正金醤油では、1~2年間熟成させ、
この使いこまれた桶に住む微生物の働きによって、
ここならではの醤油ができあがるのです。

「杉製の桶だからって、いい醤油というわけじゃないんですけどね」
そう謙虚に話される藤井さんは、
その管理もいい醤油づくりの条件として挙げます。
かき混ぜる工程で飛び散ったもろみをキチンと掃除するか、
そういった基本的なところで、醤油の出来が決まってくるそう。
謙虚な姿勢で、基本に忠実にといったあたり、職人らしさがにじみ出ています。
こうしてじっくり醸造された醤油を味見させてもらうと、
これが実にまろやかな味わい。
「うちは"素材の良さを引き出す"ための醤油づくりを心がけています。
醤油は料理の引き立て役だと思っているので」
そう話す藤井さんは、どこまでも謙虚。
醤油にその性格が反映されるのも、当然のことかもしれません。
出荷先も全国に広い正金醤油では、
淡口醤油(写真左)、濃口醤油(写真右)二段仕込み醤油(写真中央)と、
顧客の味覚に合わせた様々な醤油をはじめ、

料理に使いやすいダシやつゆ、ポン酢も作っています。

もちろん調味料づくりにおいても、
「素材の味を引き出す」という姿勢は変わらず。
醤の郷、小豆島の醤油づくりは、
瀬戸内海の気候のように、実におだやかでゆかしいものでした。
知られざる瀬戸内の恵み
「瀬戸内の魚はおいしいですよ!」
この旅路でも幾度となくそうオススメされてきましたが、
ママカリをはじめ実際、本当においしい魚が多い印象です。

そんな瀬戸内海の鮮魚が集まる
岡山県倉敷市の「玉島魚市場」へお邪魔しました。

続々と運び込まれる魚には、

サゴシからタラ、フグに幻の魚と呼ばれるアコウまで。
玉島魚市場の営業・事務リーダーの佐藤真理子さんに、
魚市場の仕事のやりがいを伺うと、

「日本全国、果ては世界各地の魚介類を扱っているので、
職場にいながらにして世界中を感じられる職業なんです。
気仙沼の塩辛業者さんの作るイカの塩辛が、
震災後の10月に再入荷した時にはスタッフみんなで大喜びしたんですよ」
自分の居場所にいながらも、他の地域のことも常に考えていられる、
そんな職場なのかもしれませんが、その思慮の深さに感銘を受けました。
今回、この魚市場にお邪魔したのは、
Found MUJIでも取り扱っている小魚チップスの生産者、
エフピー通販の真田社長が、小魚の買い付けに訪れたから。
「瀬戸内の魚に育てられた身なので、魚市場はわくわくしますよね」
と、話された時の柔和な笑顔がチャーミングな方です。
瀬戸内海沿岸の漁業の町で生まれ育った真田社長は、
漁師たちが売り物にならない小魚を処分しているのを目にしてきたそう。
ただ、知人に「魚は骨が味わい深い」ということを教わり、
骨まで食すことができる小魚をもっと有効活用することができないかと、
4年ほど前から、瀬戸内の小魚チップスの製造販売を手掛け始めました。
「雑魚(ざこ)って言いますでしょ。選り分けられていない
いろいろな種類の入り混じった小魚たちです。価値がない魚として、
ほとんど市場に出ないんですよ。でもこれがおいしいんです」

そう話す真田さんに、
実際に小魚チップスを作っていただきました。
200℃以上に温められたプレス機で、焼かれること10~20秒。
パチパチと音を立てながら、香ばしい匂いが周囲に広がります。
あっという間に、小魚100%のチップスが出来あがりました。

その食感に、骨の感覚はまるでなく、
味付けしていないのに、自然の塩味がほのかに口に広がりました。
「おいしいですね!」
思わず唸っていると、
真田さんはすかさず次のチップスの焼きに入っていました。
小さいイカも、この通り。
パリパリに仕上がっていて、また違った風味がして一度食べだすと止まりません。
「これなら魚離れの子供たちにも食べてもらえるでしょ。
食育の観点でも大切なことだと思っています」

実際、各地でチップスの実演販売を行っている真田さんは、
その手応えを感じていらっしゃるそうです。
また、チップスに加工できないぐらいに細か壊れたり粉になった雑魚については、
ペット用の餌を作る生産者に卸されていました。

真田社長は、この取り組みに対する想いをこう語ります。
「一つには、おいしい魚を余すことなく届けたい。
二つには、世の中に埋もれている価値あるものを知らせたい。
育ててくれた瀬戸内海に対して恩返しできればと思っています」
そんな真田さんの想いがたくさん詰まった小魚チップスシリーズは、
Found MUJIを扱う一部の無印良品でもお買い求めいただけます。

子供のおやつにも、お酒のつまみにも、
はたまた健康食としても、もってこいです。
ぜひ、一度ご賞味ください♪
トットリノススメ
「いいまちに住みたい。
どこかに引っ越してもいいけど、
ここを耕すって方法もある。このまちの特殊性は
僕らが暮らしていることにある。
それは、砂丘やマンガよりずっと深くてゆるぎなく、
かつ、不確実で頼りない。世界のほとんどは気持ちで出来ている、と思う。
僕らはたくさんの仲間とここに居る。
このあいまいで確実なコミュニティーが、
お互いに気持ちのチューニングをし合う
そういうまちに住みたい」
"街を歩いて、発見して、頭の中の地図を書き換える月間"
「トットリノススメ」のキャッチコピーです。
鳥取市では5年ほど前から、秋から冬に入るまでのあいだ、
市内の店舗や空きスペースを利用して、様々なイベントが催されています。
あるレコードショップではドキュメンタリーフィルムの上映会、
あるパン屋さんではトークイベント、旧病院跡では大学生が運営するカフェ、
など…。
どれも街の人が自主的に企画し、運営しているイベントです。
ちょうど私たちが鳥取市にお邪魔した時にも、
韓国焼肉レストランでトークイベントが催されていました。

その日は「ゲストハウスの作り方」というテーマで、
大阪と鳥取でそれぞれゲストハウスを運営する人たちによるトークセッション。
会場には、ゲストハウスに興味のある人から、
単純におもしろそうな人たちの話を聞きたい人までが集まり、
好奇心が交錯しながらの、心地よい時間が流れていました。
「1ミリでもいいから、鳥取に住んでいる人たちで幸せを感じ合いたい。
そんな想いを持つみんなで作っているイベントなんです」

そう語るのは「トットリノススメ」の発起人、本間公(あきら)さん。
鳥取の木を主な木材とした家具製作や店舗内装を手掛ける家具工房
「工作社」を営んでいる方です。
初めてお会いした瞬間、「ようこそ鳥取へ」と手を差し伸べられ、
どこか外国人の雰囲気を感じたのは、本間さんがもともと旅人だったからかもしれません。
岐阜県高山市での木工修業を経て、
タイ、インドネシア、オーストラリアといった外国を1年間放浪。
帰国後、年に5週間は休暇をとるという
オーストラリアのライフスタイルを実現すべく、
故郷、鳥取市に自身の工房を構えられました。
「帰郷したはいいんですけど、カフェはない、BARはない。
周りの人たちの気持ちもどこか都会に向いていて。
だったら、ないない文句言ってないで、作ればいいじゃん!」
そういって、運営したい人と一緒に、空き物件を見つけて、
カフェをオープンさせてしまいました。
古い建屋を改装した店内は、とても落ち着く空気が流れていて、
私たちも2日続けて、訪れてしまったほど。
都会のカフェとはまた一味違う魅力が放たれていました。
「このカフェによって、街中の人の流れも、人の意識も変わった。
"変わる"おもしろさを知ってしまったのはそれからだね」
この経験が、「トットリノススメ」のような企画につながったのでしょう。
旅に出たい衝動に駆られながらも、
「旅に出なくとも自分の身の回りを耕せばいい、
そのためには周りの人たちの意識を変えればいい」
そう考えるようになっていったんだとか。
本間さんは、「トットリノススメ」の役割を、
"気持ちのチューニング"と話します。
数々の民藝に代表されるものづくりや、人と人との近さ。
こうした鳥取の魅力を、この機会に再認識するきっかけになればと。
「イベント打って儲かるわけじゃありません。むしろ、採算は度外視。
各店舗の人たちが、あくまでも自主的に企画・運営しているんで、
気持ちが満ちればやればいいし、満ちなければやらなければいい」
そう話す本間さんは、あくまでもニュートラル。
今年4回目を迎える「トットリノススメ」には、10/28~12/9に、
16カ所(店舗含む)で20を超える企画・イベントが催されています。

「いいまちに住みたいから、ここを耕す」
鳥取のように、皆がそんな気持ちになれば、
きっと地域はもっと楽しくなるのではないでしょうか。
はっさく大福
"フルーツ大福"といったら、
いちご大福を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、
広島の因島(いんのしま)で
「はっさく大福」なるものに出会いました。

袋の緑色のテープが葉っぱを表し、
まさにはっさくそのものを表現しているんだそう。
中を割ってみると…

みかんの皮が練り込まれた、うっすら黄色の餅生地で
白あんと、採れたての因島産はっさく果実がそのまま包まれています。
食べてみると、はっさくの実が口の中でプチプチと弾けます★
そして、ジューシーな果実の酸味と白あんの甘さが合わさって、
大福なのに甘過ぎない、絶妙なコラボレーションが完成しているのです!
大福というと、これまで和菓子のイメージ強かったのですが、
このはっさく大福は、コーヒーやワインなどにも合いそうですよ♪
白あんと、はっさくがここまでしっくりくるとは!
正直意外でした。
「甘いはっさくよりも、すっぱいはっさくを使う方がいいんじゃ」
そう教えてくれたのは、大きな窓からしまなみ街道のひとつ、
因島大橋が一望できるレストハウスで各種餅菓子を製造販売する、
「はっさく屋」代表の柏原伸亮さん。

「はっさく大福」はもともと因島発祥のはっさくを
広く知らせたいという想いから、
平成元年頃に餅菓子「かしはら」で生み出されたもの。
中身は同じなのに、皮の色みなどの問題で
規格外となってしまっていた、はっさくに目をつけました。

その後、家庭の事情で「かしはら」がお店をたたもうとし、
「これをなくしたらもったいない!」と思った柏原さんが
店主に頼んで技を伝授してもらい、「はっさく屋」を始めたのだそう。
「今でこそ、メディアに取り上げられて有名になったもんじゃが、
最初は大変だった。わしが配って歩いたんや」
柏原さんは、はっさく大福のおいしさを多くの人に知ってもらおうと、
土日に車でパーキングエリアを回って、試食を配りました。
後になって、その時大福をもらった人が
お店に訪ねて来ることも多かったと、柏原さんは振り返ります。
現在、はっさく大福は、はっさくが収穫される
10月中旬~お盆頃までの販売です。
使用されているのは、水気の抜けたパサパサの実ではなく、
採れたてのジューシーなはっさくのみ。
「わしの子供や孫の代まで、
因島産のはっさく大福が作れるといいんじゃが…」
因島のはっさく農家は高齢化が進んでいて、
後継者がいない家も多いといいます。
柏原さんご自身がそうだったように、
今度は、はっさく屋のはっさく大福を味わった人が、
「これを未来に残したい」と感じて、
今後につながっていく動きが生まれると素敵ですね。
それにしても、「はっさく大福」おいしかったなぁ…♪
下関の新名物
山口県では無印良品 ゆめシティ新下関![]() を訪ねました!
を訪ねました!
すると、そこで待ち構えていたのは…、

ペアルックを着こなした男性店長と副店長コンビ。
うれしいことに、下関らしいフグの飾り物を掲げて
出迎えてくださいました☆
そう、下関といえば全国で水揚げされたフグの
7~8割が集積される一大拠点。

フグ鍋「てっちり」なんかの季節も近いですね♪
そんなつながりで、
こちらのお店の人気&オススメ商品はこちら↓

「土鍋」です!
「こたつに入って鍋で温まろ~」

なんて季節ももうすぐそこ!
ところで、フグの産地として知られる下関には、
もう一つ漁獲高日本一を誇る魚があることをご存じですか?
その答えは、こちら!

「あんこう」です。
深海魚のあんこうは、
下関漁港を基地とする沖合底曳網漁船が捕獲してきましたが、
5年ほど前までは地元でほとんど消費されず、県外へ出荷されていました。
その奇妙な出で立ちと、ぬめりによる調理のしにくさゆえに、
猫も敬遠して食べない"猫またぎ"と揶揄され、
漁港にあがっても邪険に扱われていたんだそう。

そのあんこうに着目し、
下関の新名物を作ろうと立ち上がった人がいました。

下関市内でふぐ料理屋を営む「旬楽館」の女将、高橋さんです。
高橋さんは、2006年に下関商工会議所が主催した
「下関うまいものづくり名人」のコンペに、
「あん肝のみそ漬」を考案し、出品。

これが見事、「マイスター」を受賞し、
現在では、あんこうを下関地域ブランドにすべく、
「あんこうプロジェクト」も発足し、これに尽力されています。
「昔に食べたことのあった、あん肝の味が忘れられなくて。
あんこうなら、あん肝を使いたいとかねてから思っていたんです」
そう話す高橋さんが開発された「あん肝のみそ漬」は、
病みつきになる味わいでした。

今では、店舗でもフグ料理に加えてあんこう料理も提供し、
あんこうの下関料理への定着にもひと役買っています。

驚いたのが、高橋さんはこう見えて今年70歳を迎えること!
55歳で「女性でも気軽に入れるフグ料理屋を」との想いで起業し、
65歳から、下関のあんこうブランド化事業に携わっているわけです。
なんとお元気なことでしょうか…。
元気の秘訣を伺うと、
「まだまだやらなきゃいけんことが多いですからねぇ」
と、ひと言。
地域の活性化に年齢は関係ないということを、思い知らされました。
下関に行ったら、「フグ」に「あんこう」。
これ、鉄板ですよ!
野菜の一生
人にはそれぞれ生まれ持った個性があるように、
それは野菜においてもいえることを、
長崎県の雲仙市吾妻町で農家を営む
岩崎政利さんに教えていただきました。
「今はまだ赤ちゃんですが、よかったら見ていってください」

岩崎さんが赤ちゃんと呼んでいるのは、野菜の苗のこと。

私たちが岩崎さんの畑を訪れた10月初旬は、
9月に植えたばかりという種が発芽して間もないタイミングでした。
「こいつらは一つひとつ個性が強いので、
欠点を抑えて、良いところを伸ばしながら育ててあげるんです」
岩崎さんは、まるで我が子のことを話すように、
野菜の育て方について話してくださいました。
この個性が強いといわれているのは、在来種のこと。
岩崎さんは絶滅危惧の在来種の野菜を、種から育てているんです。
江戸時代の日本には、大根一つ取ってみても、
全国に150以上の種類があったそう。
それが流通の発達により、形のそろった均一の野菜じゃないと
市場で値段がつかないようになり、
形の良い大量生産に向いた品種に絞られていきました。
「そうした品種は、種ができにくかったり、
できたとしてもどんな子が生まれるか分からない。
これまで代々受け継がれてきた在来種は、
形はいびつですが生命力にあふれています」
岩崎さんの両親の世代ぐらいまでは、
農家は代々作ってきた野菜の種を採取していたそうですが、
現在では、種苗会社が精力かけて開発した
作りやすい野菜の種を買うのが一般的なんだそう。
そのため、各地で作られてきた在来種の野菜は
絶滅が危惧されているのです。
岩崎さんは、こうした在来種の種を地元はもとより全国から譲り受け、
ここ雲仙の土地で育て、後世に残そうとしています。
収穫した野菜から、母となる野菜を選別。
畑の一角に植えられた母野菜は、
冬を越え、春になると花が一斉に咲き誇ります。
花が輝くこの時期が、一番野菜と近づけると岩崎さんはいいます。
どんな野菜になりたいか、と花と語らい合うんだそう。
そして花はやがてサヤとなり、刈り取られ、じっくりと乾燥させられます。
それを一つひとつ岩崎さんが手でほぐし、
風であやしながら種を採っていくんです。
「在来種が、その風土や作り手の想いに応えてくれるようになるには、
最低5年はかかります。種が採れるのは年1回ですから」
こうして何年、何十年と採り続けられる種は、
徐々にその土地になじみ、農薬や肥料をやらなくても
土そのもので育つだけの強い生命力を備えていくそうです。

そもそも岩崎さんがこうした農業を手掛けるようになったのは、
30年ほど前。
それまで当たり前に使っていた農薬の影響か、
2年間ほど寝たきり状態になるほど体を壊したことがきっかけでした。
「はじめは仕方なく有機農業に切り替えたのですが、
やがて自分にしか作れない野菜を作りたいと思うようになったんです」
今では、全国から岩崎さんの元に在来種が集まり、
県の依頼で、有機栽培に強い品種の検査も担っています。

「野菜の一生を見ることができる農業は素敵」
そう岩崎さんはいいます。
最後に、一つの野菜を大切そうに抱えながら、
こんなことを話してくれました。

「このカボチャは、地震の起こる数年前に、
福島の農家から預かった在来種のカボチャ。
今、向こうでは作れなくなってしまったから、
この種をつないでいくのが、私の使命と思っています」
その土地土地で代々受け継がれてきた在来種は、
今こうして岩崎さんをはじめとした
数少ない生産者の手によって守られています。
いただきます
私たち日本人が食事の前に言うことば、
「いただきます」。
当たり前のように日々つぶやいている、このことばですが、
改めてことばの意味を考えさせられる機会がありました。
豚カツ、豚汁、豚キムチ…
これらのおかずが食卓に並んだ時に、その「命」を想像することはありますか?

今回訪れたのは、長崎県北部の佐世保市江迎町(えむかえちょう)にある、
林さん親子が運営する「味菜自然村」。
ここでは約70頭のブタが、高原の中でのびのびと暮らしています。
代表の林拓生さんは大学卒業後、
脱サラして農園を営んでいた両親を手伝い始めましたが、
「自分には細かい農業よりも、畜産が向いている」と考え、
6年前に養豚を始めました。
大学で環境循環を学んでいた拓生さんが取り組んだのは、
「自然」をテーマにした、放牧養豚。
ブタたちは、昼間は放牧地帯で自由に過ごし、
夜になると自分たちで小屋に入って寝るそうです。
私たち人間と同じですね。
5ヘクタール(東京ドーム1個分強)の敷地は、
いくつかの放牧スペースに分けられ、兄弟(5~8頭)ごとに放牧されていますが、
使用する放牧地は、草を育てるためにも半年ごとに入れ替えるそう。
拓生さんについて、放牧スペースに行ってみると
肝心のブタが見当たりません。

「ブーチン!ブーチン!!」
拓生さんがそう呼びかけると、
どこからともなく次々にブタが集まってきました!


自然の中で育っているブタですが、拓生さんには
すっかり懐いている様子。
餌をもらえると思ったのかもしれませんね。
餌は1日1回、夕方に与えるそうですが、
地元の病院や老人ホームからもらってきた残飯や野菜を煮てから乳酸発酵させ、
オリジナルの飼料を作って与えています。
発酵飼料はブタの腸内活性を促し、ブタの健康を保つと同時に、
糞のニオイを抑える役目もあるそうです。
そういえば、ブタの近くにいても、
ほとんどニオイが気になりませんでした!
ムシャムシャ… モグモグ…

ブタって草も食べるんですね。
拓生さんがあげた草をおいしそうに食べる彼ら。
すると、拓生さんから驚きの発言が!
「ブタは土も食べるんですよ。ミネラルが含まれているので」

歴代のブタたちが食べてできた洞窟がありました。
放牧したからこそ、分かったブタの習性です。
「味菜自然村」では、出産も自然分娩で、母ブタの生む力に任せるそう。
ちょうど5日前に生まれたばかりの子ブタを見ることができました。

以前は、竹やぶの中で出産したブタもいたそうですが、
生まれたばかりの子ブタが脱走してしまったことがあり、
今は畜舎で出産し、生後数ヵ月経ってから放牧するそうです。
こうしてブタは食肉となるまでのあいだ、
「自然」の中で極力ストレスをかけずに育てられ、
その生涯をのびのびと過ごします。
拓生さんは
「食べる人のためにも、自然のまま元気に育てることが使命です」
と語ってくれました。
今回の取材で数時間いただけでも、ブタに情が移ってしまった私たち。
生まれた時から愛情を注いで育てている拓生さんは
どんな想いで出荷しているのでしょうか?
「あまり何も考えないようにしています。
ただ、ブタに感謝して、無駄にはしないようにしていますね」

「味菜自然村」で育ったブタのお肉は、会員になった人が購入できますが、
注文が1頭分になるまで待ってもらうこともあるといいます。
食事の前の「いただきます」は、
生き物の命をいただくことへの感謝の気持ちを、
食後の「ごちそうさま」は、
おいしい食材を育ててくれた生産者や
その食材を調理してくれた人への感謝の気持ちを、それぞれ表すことばです。
心のこもった「いただきます」と「ごちそうさま」を言うには、
まずは食材の生産現場を知ることが大切かもしれません。
有田焼カレー
佐賀県有田町(ありたちょう)は、
ご存じ有田焼の産地として知られています。
今回、私たちが有田町を訪れることをTwitterでつぶやくと、
「有田焼カレーをぜひ!」との返信が寄せられました。
「有田焼カレー」
有田焼の器に入ったカレーなのか、
それとも有田で作られた焼きカレーなのか!?
答えはこれでした。

「創ギャラリーおおた」さんで提供されている、
有田焼の器に入った、焼きカレー!!
なんともコクのある味わいで、
上にのったチーズとの相性も抜群です♪
しかも、メニューによっては、
この有田焼の器を持ち帰れるんだそうです。

ひと口食べて、フラッシュバックしました。
あれ? 私、この味知ってる…!
実は東京・中目黒に「アンティロミィ」という姉妹店があって、
そこで数年前に食べた味だったのです!
興奮してそれを店員さんに伝えると、
奥から1人の女性が出てきました。
有田焼きカレー開発者の太田浩美さんでした。
埼玉県出身の浩美さんは、有田焼が好きで
昔からよく有田町に遊びに来ていたんだそうです。
そして、ご縁あって有田焼の商社を営むご主人と結婚。
「大好きな有田のために何か自分が貢献できることはないか?」
そう考えた浩美さんは、18年前に作家さんの作品を紹介する、
ギャラリー兼カフェを始めました。

「得意だったケーキとパンからスタートしたんですが、
ランチ希望のお客様が多くて。
お友達にあなたのカレーはおいしいからそれを出してみたら
って勧められて、カレーを出すようになったんです」
当初は、"カレードリアンコース"というメニューで提供されており、
また、カレーのコースメニューというのも珍しく、
人気があったそうです。
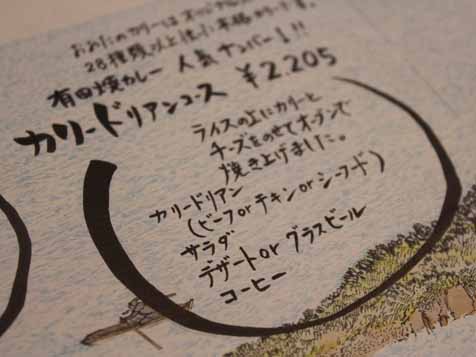
その後2007年に、佐世保バーガーを全国的ヒットに導いた
元JR佐世保駅駅長の西田辰美さんが、JR有田駅駅長に就任され、
西田さんとその他有田を愛するメンバーと一緒に
有田の魅力を発信していく「有田ハートプロジェクト」を発足、
浩美さんのカレーを"駅弁"として販売していくことに。
すると、それは有田焼ファン、カレーファン、
駅弁ファンを中心に、次々と口コミで広がり、
2011年には、全国駅弁ランキングで1位になるまでの
人気メニューになりました。
有田駅構内のキヨスクで販売していますが、
その場で温めてくれるそうです。
また、有田焼の器ごとの販売なので、
お土産として買っていかれる方も多いんだとか。
ところで、カレーをお弁当にしてしまう発想自体が斬新ですが、
カレーは持ち歩いても大丈夫なのでしょうか?
「普通カレーは添加物が入っていないと3日程度しかもちませんが、
うちのカレーは使っている水が特徴で、
冷蔵庫で1週間保存しても検査を通りましたから」
有田焼カレーは、28~31種類のスパイスを
科学者が開発した蘇生水で1週間かけてじっくり煮込んだもの。
もともとマクロビオティックを勉強していた浩美さんが
健康食として考え出した薬膳カレーだったのです。

また、もちろん他の原料にも気を遣っていて
お米は有田の棚田米、牛は佐賀牛と
「日本で一番原価の高いカレーかもしれません(笑)」
と浩美さん。
佐賀で再会した、有田焼カレーは、
新たに考えられたご当地グルメではなく、
これまでもその地にあったものを活かし、
食と器を同時に楽しめる、一度で二度おいしい絶品でした☆
おいしい海苔
お寿司やおにぎり、磯辺巻、ラーメンなど、
日本の食卓に欠かせない食材の一つが海苔。
世界的な寿司ブームに後押しされ、
今や欧米でも海苔が食される昨今ですが、
国産海苔の生産量、消費量ともに日本一なのが、佐賀県です。
佐賀県、福岡県、熊本県3県合わせると、
実に国産海苔の約40%が有明海で作られているものだそうです。
ただ、同じ海で同じように作ったとしても、
作り手によって味は変わるもの。
佐賀市で地元でも知る人ぞ知る、おいしい海苔があると聞いて、
賞味してまいりました。
一見、普通の海苔のように見えますが…

食べてみてその味にビックリ!
口の中で溶けるように磯の香りが広がり、甘さの後には少々の塩気も。
一瞬、味付け海苔と勘違いするほど、しっかりとした味わいです。
そして、この海苔で作られた無添加の佃煮。

おいしくないわけがありません。
ついついご飯を食べすぎてしまいそうです。
さらには、この海苔に佐賀産のジャージー牛のミルクで作った
「焼のりアイス」なんていうのもありました!

ミルクの甘みと海苔の風味が
とても上品な味わいを演出していました。
「海苔ってご飯の他にも意外と合うものが多いんですよね。
いろいろな食べ方を訴求して、美味しい佐賀海苔を知ってもらいたいです」

こう話すのは、佐賀海苔を手がける、
「合同会社 佐賀市漁村女性の会」の代表・古川由紀子さん(写真左)。
良質な佐賀の有明海産の海苔をブランド化しようと、
平成18年に漁業協同組合から独立し、会社を起ち上げました。
「作り手によって海苔の種類や質が変わるのに、
それをすべてまとめて同様の金額で出荷するのはおかしい
と常々思っていたんです」
古川さんがそう話される背景には、
海苔の養殖過程における差異がありました。
海苔の養殖は、「海の農業」と表現できる通り、
別の場所で育てた海苔種(苗)を海に沈めて育てていきます。
海苔種専門業者から仕入れて種付けを行うのが一般的ですが、
古川さんたちが扱う海苔の生産者は
自分たちで海苔種を育てるところから行うそうです。
「海苔種は光合成で成長していくので、
天気が悪い時には電気をつけたり、逆に天気がいい時には遮光を調節したりと
大変な作業なんですが、人間の子と同じで赤ちゃんのうちの育て方で
その子(海苔)の性格も決まると思うんです」
また、昔はほとんどの生産者が、干出(かんしゅつ)と呼ばれる、
海に浸していた海苔を太陽光に当てることによって、病気を予防していたのが、
海苔は海に浸していないと成長しないため、
干出の仕方に違いが生まれるようになってしまいました。
そして、生まれたのが「酸処理」という手法。
海に浸かっている海苔網を一度、
リンゴ酸などの有機弱酸に浸けることによって、病気の予防をするのだそうです。
「決められた酸を使った処理は決して悪いことではありませんが、
一部モラルのない人たちがいるのも事実。
海苔本来の味を引き出すには、やっぱり干出です」
手間のかかる分、多くの生産量も望めないようですが、
古川さんたちグループの漁師さんたちは、酸処理に頼らずしっかりと干出を行っており、
手塩にかけて育ててあげることが、良質な海苔をつくる秘訣だといいます。
それからこうも話してくださいました。
「私たちが母親だからできることなのかもしれません。
未来の子供たちへの食の安全を考えたら、
手間でもこの作り方を選択しました」
こうして作られた海苔は、
生産者と舟の名前を明記して出荷されています。

名前を出すことによって、
中途半端な海苔はつくれないという気持ちが、
生産者側にも生まれるようです。
人間も海苔もすくすく育つには、
母親(生産者)の愛情が大事だと感じました。
大人のおやつ
お茶の請け菓子としても、お酒のおつまみとしても
どちらにも合うお菓子に出会いました。

佐賀県鳥栖(とす)市にある、高砂屋さんの作る
「豆菓子」です。
豆菓子といっても、ピーナッツ(落花生)から
エンドウ豆を使ったものまで、原料の豆の種類はさまざまありますが、
高砂屋さんでは"そら豆"をメインに扱っています。
自分たちにしかできない商品は何かを考え、
他があまり手掛けていなかった、そら豆に目をつけたそうです。
もともと佐賀県内ではそら豆を生産しており、
乾燥そら豆を焼いたものが、腹持ちがよく保存も利くことから
筑豊炭田で作業する人々のおやつとして食べられていました。
しかし、現在、野菜として食べられるそら豆は、
四国と九州の一部で栽培されているようですが、
乾燥そら豆についてはほとんどが輸入だそうです。
「うちは中国の"青海そら豆"を使っていますが、
安いからではなく、質がいいからそれを選んでいます」
と、社長の森光さん。
青海そら豆は、中国最西部のチベットに近い青海地区で栽培されており、
標高約2500mの高地なので、害虫がいないため農薬を使っていない、
安心・安全の原料だといいます。
また、粒が大きく、味が濃いのが特徴だそう。
豆菓子を作るには、まず原料の乾燥そら豆の皮を剥いて、
一晩水につけておきます。

そうして柔らかくしたものを揚げて、フライビーンズに。

この状態で味見をしてみましたが、
サクサクしたスナックのような食感です。
そして、その後の工程は、味つけによって異なります。
黒糖そら豆などりんかけ(砂糖をからめる作業)をするものは、
熱の通りやすい銅鍋に移し、
手作業で糖蜜をゆっくり絡めていきます。

高砂屋さんでは、このりんかけを12~13回も繰り返すのです。
とっても手間のかかる作業で、
さらには全体に均等にかかるように、経験が活きる職人技。

りんかけ後のそら豆を噛むと、
じっくりとした甘さが口の中に広がりながらも、
そら豆のサクサク感と、そら豆自体の味も残っていて
なんとも深い味わいです。
一方のおつまみそら豆は、
フライビーンズをさらに焼いてから味つけします。
よりサクサクッとして、黒こしょうを絡めたものは
まさにビールが進みそうな味に!
他に、みそ味、カレー味、ゆず味など
バリエーションが豊富なのもうれしいですね。
「そら豆の味がしなくなったら意味がないので、洋物は作らないんですよ」
とおっしゃるように、見てみると確かに厳選された
"和"の味が並んでいました。
高砂屋さんでは、そら豆をいかにおいしく食べてもらうかに注力して、
味つけに合わせて製造工程も変え、
また、注文が入ってからしか作らないそうです。
素材の味を存分に引き出したこの豆菓子は、
上品で贅沢な味わいです。
ふと、「大人のおやつ」というワードが頭に浮かんできました。
高砂屋さんの豆菓子は、Found MUJIの商品として
MUJIキャナルシティ博多![]() で一部商品を販売予定です。
で一部商品を販売予定です。

ぜひお試しください♪
※MUJIキャナルシティ博多での販売商品は、別パッケージになります
1年ぶりの再会
佐賀県は実は昨年の今頃にもお邪魔していました。
このMUJIキャラバンの前身企画で「なるほど調査隊 in 福岡周辺」
と称して、福岡・長崎・佐賀の3県を旅しながら
"なるほど"を探す旅をしていたのです。
その際に訪れた、無印良品 ゆめタウン佐賀![]() へ
へ
1年ぶりに行ってきました!
すると、うれしい再会が♪
ちょうど1年前にも迎えてくださったスタッフさんが
今年も笑顔で迎えてくださいました。
早速、恒例の人気商品を伺うと…

「あえるだけのパスタソース」をご紹介いただきました。
しかも、このパスタソースシリーズ、
佐賀県唐津市で作られているんだそう。

現在、8種類の味で展開していますが、
スタッフさん一押しの味は「うにクリーム」!
実は、私のお気に入りもこれでして。

パスタを茹でて絡めるだけなんですが、本当においしい☆
バリエーションが豊富だと、全部試してみたくなってしまいますね。
種麹
日本酒、焼酎、泡盛、味噌、醤油、食酢、漬物など、
発酵食品を製造するときに不可欠な「麹(こうじ)」。
麹とは、米、麦、大豆などの穀物に、
コウジカビなどの食品発酵に有効な微生物を繁殖させたもの。
これまでの旅中、何度か麹屋さんにめぐり会い、
米麹づくりの現場も見学させていただきました。
写真は、蒸かしたお米に麹菌を散らして、素手で均等にしているところ。

これを寝かせて、時間を置くとこの通り。

この米麹を入手できれば、塩麹や甘酒も自宅で
簡単に作れてしまうのです。
それでは、麹菌はどのようにしてできるのでしょうか?
福山町で取材させていただいた、黒酢の伊達醸造さんが使用している
という麹屋さんを紹介していただきました。

鹿児島市内にある「河内源一郎商店」
全国に数軒しかないといわれる種麹屋さんのひとつで、
焼酎メーカーの8割以上に麹を卸しているのだそうです。

今回初めて知ったのが、麹にも種類があるということ。
一般的に広く使われているのは「黄麹」で、
他に、「黒麹」「白麹」があります。
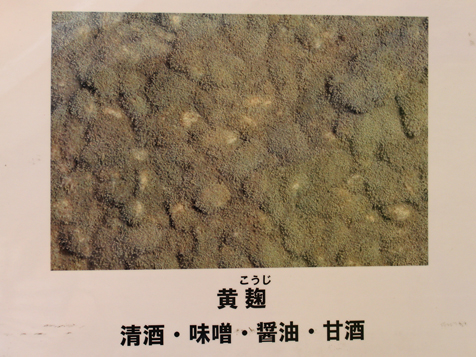
もともとは、焼酎づくりにも清酒と同じ「黄麹」を使っていたのですが、
出来上がった焼酎はすぐに腐ってしまっていたそう。
"本来寒冷地向きの清酒に使う麹が、
暑い場所で造られる焼酎に合うはずがない。
暑いところの酒のモトは同じ暑いところから探すに限る"
そう考えた、河内源一郎商店の創業者、河内源一郎氏は
沖縄の泡盛づくりに目をつけました。
従来、泡盛の製造に用いられてきた「黒麹」から胞子を取り、
焼酎に一番適した麹菌を栽培することに成功。
この麹菌が発するクエン酸が雑菌の増殖をおさえ、
この発見によって焼酎の歩留まりを飛躍的に向上させ、
さらに糖化能力のすぐれた新種も開発したのです。
それが「白麹」(河内菌白麹菌)、
つまり「白麹」はこの河内源一郎商店が生み出した麹菌なのですね。
河内源一郎商店では、現在20種類以上の麹菌を、
木製麹蓋(こうじぶた)を使って、手づくりで培養しているそうですが、
それらはすべて無菌状態の部屋で行われています。
もちろん私たちが入ることはできません。

麹菌は納豆菌との相性が悪いため、
作業に携わる人は納豆を食べられないとう制約があるそうで、
気軽に一般人が入ったら大変なことになりますね…。
今回は、開発室室長の池田さんに麹についてお話を伺うことができました。
「麹菌には原料を分解する役割があります。
お米にしても、麦にしても、別の素材と合わせることで、
麹菌は、酵素源として重要な働きをするんです」

麹菌は、でんぷんやたんぱく質を分解し、甘みを感じさせる
「糖化酵素」(アミラーゼ)、
アミノ酸をつくる「たんぱく分解酵素」(プロテアーゼ)、
そして、脂質を分解する「脂質分解酵素」(リパーゼ)の
三大消化酵素を生成し、これらの酵素の働きと熟成期間を持たせることで、
旨みやコクや香りを食品に与えることができるといいます。
河内源一郎商店は、この素晴らしい麹の能力や
麹の存在自体を知ってもらいたいと、
平成8年にアンテナショップ「麹の館」をオープンさせました。
そして、麹を使った加工品を次々と開発。
そのひとつがこちらの天然クエン酸飲料です。

ひと口飲んでその味にビックリ。
原液のまま飲んだのですが、鼻にツンとくるような酸味ではなく、
まろやかな味わい。
そして、さつまいもとしょうがの素材の香りが
ふわっと口の中に広がりました。
これらの原料はさつまいもorしょうがに、米麹と麦麹のみ。
麹の働きによってできた天然クエン酸は、
乳酸を分解しやすいので、疲れをとりやすいんだとか。
最後に、池田さんがこうおっしゃいました。
「本当の発酵食品は、いい麹を作れば、添加物を入れなくてもできるんです。
栄養素が自然に生まれるから、発酵食品はバランスがいい」
自然の力と、それに携わる人々の研究と努力が
はっきりと伝わりました。
黒酢
肉用若鶏飼育数1位、豚飼育頭数1位、肉用牛飼育頭数2位の
畜産大国、鹿児島県。
(平成21年度総務省調査)
鹿児島に入った途端、引き寄せられるように、
焼肉屋さんに入っている私たちがいました。

訪れた先は、霧島温泉郷にある「焼肉厨房わきもと」さん。
純粋黒豚をはじめ、地元産の新鮮な具材を提供するお店です。

地元産のサツマイモをたっぷりと与えられたかごしま黒豚は、
数ある黒豚ブランドの中でも別格の扱いで、
過去には食肉市場で牛肉並みにランク付けされたこともあるほど。
確かに、その甘み、旨み、弾力、どれをとってもおいしい。
何より、白い脂身の部分が全くといっていいほど
脂っぽさを感じないことに驚かされました。
それには、黒豚そのもののおいしさもさることながら、
「焼肉厨房わきもと」さんならではの、独特の工夫がありました。

つけだれが黒酢タレだったのです。
黒酢の酸味をうまくいかしたタレの味わいは、
さっぱりとしながらも肉の味を引き立ててくれる仕立て。
黒酢といえば、健康食品として7年ほど前に一躍脚光を浴びましたが、
元をたどれば、そのルーツは鹿児島県にありました。
そんな「焼肉厨房わきもと」さんも使っている、
黒酢の生産者を紹介して頂きました
向かった先は、鹿児島県福山町の「伊達醸造」さん。

福山町で黒酢づくりが始まった1820年創業の老舗です。
そこには、目を疑うような光景が広がっていました。


見渡す限りの、壺、壺、壺…!
これ、実は福山町ではよく目にすることができる「壺畑」の光景で、
福山町では昔ながらの製法に則って、
苗代川焼という薩摩焼の一種である「アマン壺」を使用し、
発酵から熟成までを行っているのです。
このアマン壺の大きさは約55ℓという、決して大きくはないサイズ。
もっと大きな壺を使えば、一度に大量の酢が造れるのでは?
と、ふと素人じみた考えが浮かぶと、
そこには福山町の酢づくりならではの理由が隠されていました。
「福山では南国らしい日中の日射しと西陽によって、
黒い小さな壺が温められるんです。
夜は、錦江湾から流れてくる冷たい海風によって冷まし、
この自然環境が、酢づくりには適しているんですね。
大きな壺だと、温度が行き渡るのに時間がかかるので、うまくいきません」

伊達醸造の代表社員、伊達さんがそう教えてくれました。
訪れた時刻は夕暮れ近かったのですが、
確かにそこは西陽の降り注ぐ絶妙な環境でした。

お酢づくりというと蔵の中でというイメージがありましたが、
屋外で屋根もない、完全に自然の環境下でのお酢づくりとは驚きました。
そのため、暑すぎても寒すぎてもダメなので、
仕込みの時期は9月末~の秋と、3~4月の春と決まっているんだそうです。
使う素材も、米麹と水のみ。
アルコールなどを加え、熟成を早めることなく、
自然の力を使って、ゆっくりじっくりと発酵・熟成させます。
特別に壺の中を見せていただくと、中に浮いていたのは麹菌。

振り麹(最後に麹菌を水面に散らすこと)をすることによって
空気に触れさせることで、酢酸発酵を促すんだそうです。
こうして発酵に約4~5カ月、熟成に最低6カ月、
1~3年もの期間をかけて、ようやく福山町の酢は完成するんです。

写真左は「黒酢」、右は「米酢」と呼ばれ、
黒酢には玄米が利用されています。
もともと、「黒酢」とは福山町で上記の製法で作られたお酢を指していましたが、
2003年の黒酢に関するJAS法制定後、
玄米を使用し、発酵および熟成によって褐色に着色したものであれば、
24~48時間で造られるものも、黒酢と呼ばれるようになりました。
ただ、福山町の酢は、米を使った酢においても、
アミノ酸量は玄米を使ったものと同程度に高いようです。
「壺によって、発酵や熟成のスピードが変わるので、
一つひとつの壺に手をかけてあげなければなりません。
大変ですが、これが福山町の酢づくりなので」
福山町のおいしいお酢づくりの秘訣には、
先人の知恵を脈々と守り続ける職人たちの姿がありました。
オリジナルの冷や汁を♪
旅の楽しみのひとつは、地元の味をいただくこと。
食材も、レシピも簡単に手に入ってしまう時代ですが、
その土地や季節ごとに味わうものは、また格別なものです。
私たちが宮崎県を訪れたのは8月下旬。
まだギラギラと光る太陽と暑さに迎えられました。
そんななか、飲食店のメニューに"夏季限定"で見かけたのが
「冷や汁」です。


冷や汁は、古くは鎌倉時代の書「鎌倉管領家記録」に、
「武家にては飯に汁かけ参らせ候、僧侶にては冷汁をかけ参らせ候」
と記されており、僧侶が全国に広めた料理といわれています。
それが後に、夏の暑さが厳しい宮崎県の風土に適して
郷土料理として定着するようになったのだそう。
ただし、宮崎県全域で食べられるようになったのは最近のことで、
各家庭で作られているのは、宮崎市周辺のみのようです。
冷や汁に関しては、
冷たいお味噌汁をごはんにかけて食べるもの、
といった予備知識はありましたが
何が入っていて、どのように作られているのか、
これまで知ることはありませんでした。
今回は宮崎市内の料理店「アンドレ貴島」さんにご協力いただき、
実際に冷や汁づくりにチャレンジしてみました!
材料はこちら。
あじ(素焼きにして身をほぐしておきます)、味噌(麦味噌)、
きゅうり、いりごま、豆腐、みょうが、大葉、水

まず、すり鉢でごまをすり、そこにあじの身を加えてまぜ、
さらに味噌を加えてペースト状にします。

続いて、この味噌ペーストを焼きます。
本来は、すり鉢の内側に味噌をのばしてつけ
逆さまにして炭火で焼くそうなのですが、
今回はアルミホイルにのせて、オーブントースターで焼きました。

味噌を焼くのは、味噌の生臭さを抑えて、香ばしさを出す工夫。
焼き味噌ができたら、味見しながら水をお好みの量加えます。
ごはんにかけるので、少し濃いめでもいいかもしれません。
氷を加えて、きゅうりとみょうが、大葉を入れたら
基本の汁の出来上がり!

これに各家庭によって、種類の違うお豆腐を入れたり、
たまねぎのスライスやトマト、梅干しを入れたりするそうです。

お豆腐入りはごはんにかけなくても、それだけで主食になる味で、
トマト入りはなんだか別の食べ物のよう。
ちなみに、無印良品からも「宮崎風 冷や汁」が出ているので、
お好みの具材を入れて、オリジナルの冷や汁を作ってみては
いかがでしょうか?
もちろん、汁から手づくりもオススメです!
本格カレーをレトルトで♪
忙しくて食事の用意をする時間がない時や、
外食も飽きたし家でごはんを食べたいけれど疲れている時など、
みなさんどうされますか?
そんな時、我が家ではカレーをはじめとする、
レトルト食品が大活躍してくれます。
レトルト食品はアメリカ陸軍が缶詰にかわる軍用携帯食として
開発したのが始まりで、その後宇宙食にも採用されたことで
食品メーカーの注目の的になりました。
その後、一般向けのレトルト食品が世界で最初に開発されたのは日本で、
中身はカレーだったといわれています。
今ではスーパーやコンビニでも
複数種類のレトルトカレーを見かけますが、
レトルト食品の元祖はやはりカレーだったのですね!
ちなみに、無印良品には現在11種類のレトルトカレーがあります。
(※季節によって変わります)

バリエーションが豊富なので、選ぶ楽しみがあるんです!
今回はこのレトルトカレーの生産現場を訪れました。
まず、初めて知ったのがレトルト食品の定義です。
レトルト食品とは、気密性及び遮光性を有する容器で密封し、
加圧加熱殺菌した食品のこと。

この大きな殺菌機の中で120℃の熱水シャワーを浴びて、殺菌されるのです。

レトルト食品=保存食であることは理解していましたが、
保存するために保存料を少しばかりは入れているものかと思っていました…。
後から高温で加熱処理をするため、事前に具材に火はほとんど入れないそう。
家庭で作るカレーと違うところですね。
具材といえば、食べたことがある人は分かると思いますが、
無印良品のカレーの特徴は何と言っても、具材がしっかり入っていること!
今回このシーンを見て、それもそのはず★と納得しました。

各具材をきちんと手作業で量って入れているので、
具材の偏りがなく仕上がるんです。
工場を見学後には、試食をさせていただきました。

無印良品のレトルトカレー、実は
インドカレーのラインナップが新しくなりました!
「バターチキン」と「キーマ」がより本格的にリニューアルし、
新しく「チャナマサラ」「バラックチキン」「チキンクルマ」が仲間入り♪

生産現場の皆さんに、開発秘話を聞くことができました。
「インドで食べたカレーをもとに、スパイスを自分たちで配合して
より本格的な味に近づけました」
このリニューアルに際し、開発チームは
実際にインドに足を運び、現地のシェフにカレーの作り方を教わってきたのだそう。
バターチキンとキーマの、リニューアル前のものと後のものを
食べ比べてみましたが、確かにその第一印象はどちらも
「スパイスの風味が効いていてインドで食べたカレーに似ている!
リニューアル前のものより大人な味かも!?」というものでした。
日本で食べるカレーはどうしても日本人好みの味で、
ましてやレトルトカレーで本場インドの味に巡り合ったことは
これまでありませんでした。
開発チームは、試作当時をこう振り返ります。
「本場のカレーの味を日本にある調味料でいかに作り出すかにとても苦労しました。
北インドで食べたカレーは、チャパティやナンで食べるケースが多く、
ごはんに合う味にするのも難しかったですね」
本場インドの味に近づけながらも、
日本というインドとは違った環境で食べられることを前提に味を調整する。
また、レトルト食品なので加熱処理後に味が多少変化することも
想定しながら味を作っていくのが一筋縄ではいかないところだとか。
新しく生まれ変わった「バターチキン」と「キーマ」は8月22日発売、
「チャナマサラ」「バラックチキン」「チキンクルマ」は8月29日の発売です。
いずれも自信作とのことなので、お楽しみに!!!
※なお、通常のキャラバンブログは9/3(月)より
九州編の連載がスタートになります。
これまで同様、毎日更新していきますのでご期待ください!
あんこ
饅頭、羊羹、大福、どら焼き、おはぎ…。

日本を代表するような多くの和菓子には、
共通して「あんこ」が使われています。

Café & Meal MUJIの一部店舗でも、あんぱんが人気なのをご存じですか?
そこで使われている「あんこ」の生産現場、
北海道は十勝地方、池田町を訪ねました。

あんこの原料となる小豆は、
国内生産量の8割以上が北海道で作られており、
中でも十勝地方がその約半分を占めています。
夏の日照時間が長く、秋の涼しい気候、
そして、清流日本一にも選ばれたことのある札内川の軟水が、
良質な小豆を生み出すのです。

小豆は低温に弱く、冷夏の年は収穫量が落ち込みます。
そのため市場価格も変動しやすく、昔は投機商品の代表とされてきました。
「赤いダイヤ」と呼ばれるゆえんです。
一般にもハレの日の食べ物として、お正月や季節の節目に、
赤飯や小豆粥にして食べられてきました。
(ちなみに、北海道ではお赤飯には小豆ではなく甘納豆を入れるそう!)
このような小豆の食べられ方は、一面、合理性を持っています。
冬期、現在のように新鮮な野菜を口にするのが困難な時代には、
小豆に豊富に含まれるビタミンB1、B2、B6を補給することで、
健康維持、向上に繋がっていたのです。
また、小豆にはポリフェノールも多く含まれ、
抗酸化作用で病気の予防にも役立ってきました。
こうした働きを持つ小豆を、
かつて清流日本一にも輝いた札内川を源とする水を使い煮ます。

この煮加減で均一の柔らかさに仕上げるのが、職人の技。
畑によって異なる小豆の質を見極めながら、
絶妙の水加減や渋きりのタイミングが求められるのです。
そして、味付けにも熟練の技が活きています。
砂糖でも中ザラ糖と上白糖をブレンドしたもので味付けし、
わずかながらに塩を加えます。
それが甘みを際立たせる隠し味だそう。

極上のあんこの出来上がりです。
甘党の私も、その口当たり滑らかな優しい甘さのあんこに、
思わず舌を巻いてしまいました。
このお味は、
Cafe & Meal MUJIで販売中の「あんぱん」でぜひ、ご賞味ください♪
一つ、この日の取材で興味深いものを見つけました。
あんこの生産者にお話を伺っている時に、出して頂いた飲み物。
麦茶かと思って頂くと、微妙に色に赤みがかっています。
そう、これ麦茶ではなく、水に小豆の粉を混ぜたものだったのです。

小豆の煮汁から成分だけを取り出して粉にした「小豆の素」を、
少量、水に混ぜただけで、小豆風味のドリンクに様変わり。
あんこを作る際に出る煮汁には、
前述した小豆の成分がたくさん含まれているようです。
これまで捨てられていた煮汁を見直し、価値あるものとして生まれ変わらせる。
まさに、無印良品。
十勝の大地の恵みが、十勝で加工され、十勝で食される。
その土地の自慢の食べ物を、その地で食べるのが
一番おいしいことを実感する毎日です。
明日は、美瑛町の取り組みについてご紹介します。
牛のミルク
青い空に白い雲、広大な緑の牧草地に赤い屋根の牛舎とサイロのある風景。
これぞ思い描いていた北海道の景色です!

北海道十勝地方は"酪農王国"と呼ばれ、
至るところでこのような景色を見ることができます。
せっかくなので、牧場に立ち寄ってみました。


こちらの牧場ではおよそ900頭の乳牛が飼われていました。
800kgの牛さんは近くで見るととても迫力がありますね。

食事中に失礼して、乳搾りを体験させていただきました。

人間の親指よりも大きな乳首を握ると、ぴゅーっとミルクが吹き出しました。
1頭の牛から1日平均30リットル(1リットルの牛乳パックが30本!)
のミルクが採れるというから驚きです。
本当だったら子牛が飲むためのミルクを私たち人間のために与えてもらっている…
当たり前のことですが、普段冷蔵庫から取り出したパック牛乳を飲んでいると
忘れてしまいがちなことです。
また、牛乳は栄養価の高い食品として古くから親しまれてきましたが、
そのままでは保存性に欠ける上、液体のため運ぶのにも不便であるために
水分を抜いて保存性と運搬性を高めたチーズが生まれました。
今度はそんなチーズが作られている、チーズ工房を訪ねました。

「共働学舎 新得農場」
共働学舎は、1974年に宮崎眞一郎氏首唱のもと、
心や体に不自由を抱える人たちとともに、競争社会ではなく協力社会、
さらには「自労自活」の生活を目指して、始められました。
新得農場は1978年に開かれた、
牛飼いからチーズづくりまでを一貫して行っている場所です。
もともとは牛乳の出荷だけだったのですが、それだけでは生活が成り立たず、
流行に左右されることなくスローペースで生み出せるものが何かを考え、
行き着いた先が当時ほかの酪農家が手を出していなかった、チーズづくりだったそう。

新得農場が教わったのはフランスに伝わる昔ながらのチーズづくりでした。
大切にしているのは「牛乳を傷めない工夫」。
搾ったばかりの牛乳を極力運ばなくて済むように、
衛生管理上、搾乳室とは通常50m以上離すのが常識の工房を23mの位置に作り、
搾乳室から工房まで自然の傾斜をつけて、
自然流下式のパイプラインで牛乳を流しています。
これが実現できているのは、牛舎の虫やニオイを解決するために
木造の牛舎に炭を埋めてマイナスイオンを高め、
牛のエサや寝床に粉炭と微生物を混ぜて、衛生管理をしているから。
確かに、よく牧場付近で香る、鼻をつく臭いがほとんどしませんでした。

また、チーズを熟成させるのに理想的な環境は、
湿度85~95%、気温8~12℃、マイナスイオンが十分にある場所だといいます。
新得農場では、その条件を整えるために鉄筋を使わずに、
札幌軟石を積んで、半地下の熟成庫を作ったそうです。

熟成庫に続く階段を下りると、途端に温度の変化を感じます。
同時にチーズの発酵する匂いがしてきました。

ズラリと並んだチーズ。
大きな固まりのチーズはなんだかカーリングの石のよう!?
こちらの工房で作られたチーズを食べてみました。
定番チーズ5種類の盛り合わせ↓

それぞれ見た目も食感も味も異なります。
左から2番目奥の「レラ・ヘ・ミンタル」と左から2番目手前の「シントコ」、
色の違いが分かりますか?
この違いは仕込みの時期と熟成期間の違いからくるそうです。
「シントコ」は青草が生えている6~10月の放牧時期にのみ製造しているため、
青草に多く含まれているカロチンが、チーズを黄色くするのです。
やはりチーズの原料であるミルク、さらにはミルクを生み出す牛が食べるもの、
そして牛が生活する環境までもが、チーズ自体に大きく関わってくるのですね。
ニセコで出会った「のむヨーグルト」
北海道ニセコ町の泊まった宿で出てきた"のむヨーグルト"、
かなり濃厚なのに後味スッキリ。

この味の秘密を探るべく、早速、生産者の元を訪ねてみることにしました。

「ミルク工房」
高橋牧場で搾られたばかりの新鮮な牛乳をたっぷり使用した、
アイスクリームやのむヨーグルト、シュークリームなどが作られている場所です。


現社長の高橋守さんの父親が高橋牧場を始めましたが、
牛が増えていくなかで、牛乳を捨てなければならないシーンを目にし、
なんとか牛乳の加工をしていきたいと考えるようになったそう。
そして1997年、アイスクリームのお店からスタート。
現在は、牧場を高橋さんご夫妻とご長男が、
加工品の工房をご長女とご次男が管轄されています。
「商品を食べた人がどんな場所で作られているのか見てみたい、
そう思ってもらえるような商品づくりを心がけています」
とご長女の裕子さんは、私たちの来訪を喜んでくださいました。
工房のすぐ後ろに広がる広大な草原には朝方、
高橋牧場の牛たちが放牧されているそうです。

「ここに来て、うちの牛を見てもらうと、
『牛って何も考えてなさそうでいいなぁ。ストレスなさそう…』
って言われるんです。それが私たちにとっての褒め言葉なんです」
広い大地でのびのび育った牛の牛乳がおいしいのも納得です。
また、高橋牧場の牛たちは、ニセコの水と
彼らのために用意された土で作られた牧草を食べて育っています。
広大な土地を有する北海道では、牛の餌を自分たちで作れるんですね。

「ものづくりの際には、牛乳の素材を最大限活かすようにしています。
それは生産者だからこそできることだと思うんです」

そう話す裕子さんは、実は小さい頃から
乳製品アレルギーを抱えていたといいます。
薬をつけ続けたけれど治らず、最後にはもう効く薬がないと
お医者さんに見放されてしまいました。
そこで食事療法に切り替え、徹底的に「食」に向かい合い、
薬で治らなかったアトピーを8年かけて克服しました。
だからこそ、裕子さんは、食のありがたさや
食品の安全性に対して、人一倍敏感なのです。
原料となる牛乳はもとより、
その牛乳を生み出す乳牛の餌までも選び抜いていること、
それが生産者だからこそ生み出せる味であり、
ミルク工房の"のむヨーグルト"のおいしさの秘密だということを知りました。
素材の味
お酒のおつまみと言えば、何を思い浮かべますか?
するめ、さきいか、あたりめ、イカの燻製など、
その多くがイカから作られていることに気付きます。
縄文時代の遺跡にコウイカ類の貝殻が多く出土していることから、
日本には少なくとも約1万年前からイカが食べられてきた歴史があるようです。
そんな深い歴史を持つ日本ゆえに、先述の乾珍味から、
刺身や寿司ネタ、イカの塩辛・沖漬などの生珍味まで、食され方も様々。
その加工のされ方によって、味や好みが変わるといっても過言ではありません。
イカは、イタリアやスペインなど一部の地中海沿岸の地域と、
東南アジア・東アジアの国々で昔から海の幸として食されていますが、
その消費量の約半分は日本が占めているんだとか。
ひと言でイカと言っても、
体長わずか25mmのヒメイカから、15m以上のダイオウイカまで。
その種類は450種ほどに及びます。
なかでも、世界の漁獲量の約80%を占め、
我々が多く口にしているのが「スルメイカ」。

「函館では朝から軽トラックが獲れたてのイカを売り回るため、
朝の食卓には当たり前のようにイカ刺しが並ぶんですよ」
そう教えてくださったのは、
無印良品「甘酢いか」「いかあしカルパッチョ」の生産者の山川さん。

「函館近海のイカは青年の年頃。
いわゆる、美味しい食べ頃のイカが獲れるんです」
山川さんがそう言われる根拠は、
日本近海のスルメイカは、主に九州より南海で秋~冬に生まれ、
主に日本海の対馬暖流、一部は太平洋の黒潮に乗って北上します。
北上しながら小さなプランクトンやイワシなどの魚を食べて成長し、
函館近郊に辿り着く頃には、十分に肉厚となるわけなのです。
こうして収穫された食べ頃の新鮮なイカを加工して作られるのが、
山川さんたちの製造する皮つきさきいか「函館こがね」。

ヒレ、胴体、足の3分割にされた部位のうち、
胴体部分をひらいて味付けし、焙焼の上、引き裂いた品です。

工場内には、焙焼されたイカの芳ばしい匂いが漂っており、
食欲をそそられます。
一方、足部分を使った商品で、
今から14年ほど前に無印良品で考案されたものが「甘酢いか」。

イカを使った新たな珍味が作れないかと、共同で開発された商品で、
当時は、酢に漬けたイカに対して半信半疑であったそうですが、
今やイカ珍味の定番となりました。
また、「いかあしカルパッチョ」は、
アメリカ大アカイカと呼ばれる、大きなイカを使った逸品で、
やわらかいアカイカの繊維を活かした逸品です。

どれも癖になる味わい。
イカは低カロリー、低脂肪なところもうれしいですね。
「できるだけ素材そのものの味を引き出すようにしています。
なぜなら、素材そのものの味は飽きがこないから。
お米を毎日食べていても飽きないのは、
そんな理由からじゃないでしょうか?」
山川さんのおっしゃる言葉に、
思わず首を縦に振っている自分がいました。
素材の味は、ひと言では言い表せません。
是非一度、ご賞味ください♪
あま~いトマト
北海道の大地で、
それはそれはとても甘いトマトに出会いました。

北海道余市町(よいちちょう)にある
「中野ファーム」でつくられる、高糖度トマトです。
「糖度は9%以上ありますよ。
そのためにトマトには厳しい環境を強いていますが(笑)」

優しい笑顔で迎えてくれたご主人の中野勇さんがそう話す通り、
ここのトマト栽培法には、いっぷう変わった特徴がありました。
まずは農園の環境。

眼下に日本海を拝む丘陵地帯で、
日本海からはミネラルたっぷりの海風が吹き上げ、
太陽が沈むまで、いっぱいに光を浴びることができる環境です。
朝晩の寒暖差も激しく、土壌は水はけの良い赤土。

この環境が、
トマトのルーツといわれる南米アンデス地方と類似しているんだそう。
かの永田農法で有名な永田照喜治氏にも、
「日本で最もトマト栽培に適した場所」と言わしめた場所なのです。
最も特徴的なのは、その栽培方法にあります。
それは、
トマトには最低限の水しか与えないこと。

そうすることによって、
わずかな水分を求めて地中に根を張り、空気中から水分を吸いこみ、
トマト自身の力で、必死に生きようとするのだそうです。
生きようとするトマトは、体内に糖分を蓄えるため、
赤くて果実の甘みが高くなるというわけです。

これは、永田農法と呼ばれる、必要最低限の水と肥料しか与えず、
植物本来の生命力を引き出す作物の育て方です。
ただ、水が足りなすぎると枯れたり、しおれてしまうため、
常にトマトの状態を見てあげなくてはならない、
とても手間のかかる農法と言えます。
実際、"尻焼け"と呼ばれる状態になってしまうトマトも。

ただ、中野さんいわく、この尻焼けしたトマトこそ、
甘くて美味しいトマトの証拠なんだそうです。
逆に言うと、尻焼けしたトマトができるぐらい、
ギリギリの水分量で育てるということです。
なんと厳しい育て方…
しかし、こうして育てられたトマトは、
甘くて、実がギッシリ詰まった、とても濃厚な味がしました。

ただ、このトマト、果実としては出しておらず、
すべてはトマトジュースとして出荷されているんです。
厳しい栽培法により、形よりも美味しさや糖度を追求しているためで、
ジュースとなってもその味はまるでトマトを丸ごと食べているかのよう。

甘くて濃厚でありながら、爽やかな喉ごしは、
飲むだけで健康になったような錯覚を覚えるほどです。
「美味しいトマトを届けたい。
手間のかかる農法ですが、その想いでやっています」

人間は自然にはかなわない。
だから、大地の力を最大限に活かすのですね。
ダ サスィーノ
おいしい料理に出会うことはありますが、
印象に残る料理に出会うことはなかなかありません。
青森県弘前市中心街の路地裏で
とても印象に残る料理を提供するお店に出会いました。

「ダ サスィーノ」というイタリア料理のお店。
店名の由来を尋ねると、
「私の名字が笹森っていうんですが、イタリア時代のニックネームです。
"サスィーノ"="ささちゃん"って呼ばれてまして」

弘前市出身の笹森さんは、青森県内に3店舗、
イタリアン、ピザ、そしてガレットのお店を経営するシェフ。
学生時代、イタリアンレストランのアルバイトで
自分の作ったまかないのキノコクリームパスタを褒められ、
それがきっかけでイタリア料理の道に入ったといいます。
仙台と東京、さらにイタリアで修業を積んだ笹森さんは
自分の目標通り、30歳で独立しました。
やりたいことを実現させるためです。
それは、自分のお店で使う食材を自分で生産すること。
地元の生産者と契約して、地場の食材を使う
というのは聞いたことがありますが、
レストランを経営しながら、食材を自分で生産するとは
これまであまり聞いたことがありません。
お店のワインセラーには、笹森さんが作ったという
生ハムやサラミが保存されていました。

このスープもご自分の農園で採れたアスパラを使い、
ジャージー牛乳から手づくりしたリコッタチーズを添えたもの。

スープをひとくち口に含むと、途端にアスパラの香りが
鼻の中にふわぁーっと広がりました。
さらに最近では、醸造免許も取得して、ワインづくりまで
されているというから驚きです。

翌日、厚かましくもお願いして
笹森さんの農園を見せてもらうことができました。
笹森さんのご案内で、ご自宅のすぐ裏にある畑をぐんぐん入っていきます。

きゅうり、ズッキーニ、くろキャベツ、アスパラ、ナス…
スーパーで見たことのないような野菜まで。
これはアーティチョークだそうです。

「あっちは、くるみの木とアーモンド、木いちご、洋梨、
さくらんぼ、マルメロー、キウイ…」

くるみの実って、こんなに大きかったんですね!?

他にも、イタリアンパセリ、ローズマリー、エストラゴン、
ミントなどのハーブ類まで、
30種類近い食材をご自分で生産されています。
コッコッコ…

なんと烏骨鶏(うこっけい)もいました!
笹森さんに初めてお会いした時、
「肌がキレイに焼けてるなぁ。サーフィンでもやるのかしら…」
と感じたのですが、それは農作業焼けだったのですね。
自身で食材の生産を始められたのは、
小さい頃から食べ慣れていたおばあちゃんが作った野菜と、
修業していた頃の仙台や東京のお店で使っていた野菜の味が違ったからだそう。
「食べることって生きていく中でも、一番大事なことだと思うんです。
本来はあちこち走り回って、自分でこしらえて
心を込めて提供するものが"ご馳走"なんですよね」
と、笹森さん。そしてこう続けられました。
「私はたまたま実家の畑がここにあったから弘前でやりました。
私は地元の食材を知らなかったんですね。
今後は地元の生産者さんにもお願いして作ってもらおうと思っていますよ」
なんだか少し意外でした。
自分で生産することは本来の目的ではなく、
おいしい食材を手に入れることが笹森さんにとっての真の目的なんですね。
なんでもチャレンジしてみて見極めていく笹森さん。
これまで、蜂蜜づくりやオリーブオイルづくりも試してみたそう。
これまでのキャラバンで見てきた農作物の場合、
もともとそこの風土が生産に適しているという理由が多数でした。
しかし、笹森さんの場合は違います。
「これだけ情報があるんだから、
温度も湿度もコントロールできるし、作れるだろう」
そう思うんだそうです。
笹森さんにお話をうかがって、
人がやりたいことをするのにその場所は関係ない、
置かれている環境に言い訳はできない
ということを感じました。
最後に今後の野望を聞いてみました。

「やりたかったことはほとんど実現できています。
今後はワインづくりにもう少し時間をかけたいのと、
景色のいい場所で料理を提供できたらいいなと思っています。
あとは、子供が小さいので子供と過ごす時間も大切にしたいですね」
大鰐温泉もやし
公衆浴場の数が人口比で全国一多い、青森県。
寒い冬には体を温めるため、家のお風呂ではなく、
近所の温泉に毎日のように通うそうです。

私たちが訪れた、南津軽郡にある大鰐(おおわに)温泉郷の公衆浴場にも、
この季節でも、近所の方が次から次へと入っていました。
宿泊した宿のお母さん(推定70代)のお肌がスベスベで驚いたのですが、
きっと温泉のおかげなんでしょうね。
毎日温泉に入れるなんて、なんともうらやましい限りです。
さて、この大鰐温泉を使って、
私たちのよく知る野菜が育てられていると聞いて、現場に行ってきました。
小屋の中に入ると、薄暗い室内に、
長細い溝が数列並んでいるのを目にします。

この溝は何のため? 気になります。
冬の野菜で本格的な生産はまだ始まっていないそうですが、
一部作っているものを見せてもらうことができました。

大鰐町で350年以上も前から栽培されている、
「大鰐温泉もやし」です。
町内に豊富にある温泉を利用して、もやしを栽培すれば、
少ない経費で熱源が手に入れられるほか、
冬期の産業になるため、昔から生産が続けられています。
また、流通の発達により、現代では冬でも豊富な野菜が手に入りますが、
1年の半分近くを雪で覆われる大鰐町では、冬場の野菜確保は困難で、
かつて人々にとってこの温泉もやしが何よりの栄養源だったといいます。
これがそのもやし。

手前のボールペンと比べると、とーっても長いのが分かります。
その長さはおよそ40センチメートル。
味が気になって食べてみると、シャキシャキした食感と歯ごたえが抜群!
もやしをメインに使ったこの丼もの、満足感たっぷりの味でした。

また、このもやしは味がおいしいだけでなく、
カルシウム・リン・鉄分等のミネラルやビタミンが、
普通のもやしより豊富なんだそうです。
もやしは水耕栽培が主流ですが、大鰐温泉もやしの場合は土栽培で、
これは全国でも珍しい栽培方法だとか。
光が直接原料の豆に当たってしまうと、発芽する前に光合成をしてしまうため、
栽培小屋の中を薄暗く保ち、深い溝を掘ってそこに豆を植えます。
植えてから収穫まで1週間、湯温を数段階に分けた温泉だけで育てます。
使うのは温泉と土のみ。
本当に無化学肥料・無農薬の食品なんですね。
こうして聞いていると、いいことづくしの「大鰐温泉もやし」ですが、
もやし=安いものという概念や、その割に大変な生産内容から
生産農家が年々減ってきてしまっていたそう。
そこで、有志の町興し団体が町と連携して、
8年前から後継者の育成を始めました。
今回お話を伺った山崎さんは、最初の後継者に認定された方。

「もともと農家だったんで、冬の間にできるもやしづくりを
やってみたいと思って、応募したんです」
応募の基準は夫婦でできること。
このもやしづくりは、昔から、土の入れ替えなどの力仕事を旦那さんが、
収穫後の洗浄、仕上げを奥さんが担当して進めるのです。
今では山崎さん夫妻のもとで2人の若い男性が修業中です。
男性2人が結婚したら、2組の農家が増えるという見込みのよう。
その土地の恵みを使って、そこに生きる人が
家族で協力しながら作っていく伝統もやし。
大鰐町の人々が守り続けてきた変わらない味がそこにありました。
青森県民のお気に入り
青森市の無印良品青森ラビナ店![]() では、
では、
こんなものが大人気だそうです。


「するめシート」
その名の通り、シートのように薄くて一口サイズのするめ。
噛めば噛むほど、味わい深い一品です。
青森県民はこれをお酒のつまみにしているのかな
と思って聞いてみると、大人だけでなく、
小学生がなけなしのお小遣いで購入していったりもするそう!
なかなかシブイですね!?
他に、上記のように温泉好きな青森県民には
無印良品のお風呂グッズも注目されています☆


青森では出かけた先でいつでも温泉に行けるように、
ほとんどの人がお風呂グッズを車に常備しているんだそう。

店長から聞いたお話によると、
無印良品のお買い物かごの小さいものを
「これ買えますか?」と尋ねられることがけっこうあるんだそうですよ!

旅のお供にも欠かせないお風呂グッズは、
私たちにとっても必需品で、いつもお世話になっています。
そうそう、「移動」をテーマに無印良品を編集した商品群
「MUJI to GO」のキャンペーンも始まってますね!
スゴロクゲームで楽しみながら景品が当たるようなので、皆さんもぜひ♪
寒麹と甘酒
私たち日本人が主食のごはん(お米)のお供として、
古くから親しんできているお漬け物。

ひと口にお漬け物といっても、各家庭や地域によって
それが指すものは違っています。
きゅうりや大根、白菜といったお漬け物の原料も違えば、
塩漬け、醤油漬け、糠漬け、浅漬け…といった漬け方も様々。
もともとお漬け物は、野菜をはじめとする食品保存が目的で作られました。
秋田を含む東北地方では、冬の間雪で作物が採れないため塩漬けに、
逆に九州地方では、暑さからの腐敗を防ぐために
醤油漬けや味噌漬けにすることから始まったそうです。
その後、同じ保存食として作るならできるだけおいしく食べたい
という気持ちがお漬け物文化を発展させていったよう。
秋田弁ではお漬け物のことを"がっこ"と呼び、
大根などを囲炉裏の上につるして燻製にしてから
主に米糠と塩で漬けこんだ「いぶりがっこ」が有名ですね。

降雪の時期が早い山間地で、
秋に採れた大根などの野菜を天日で干すことができなかったため、
室内につるして囲炉裏火の熱と煙で干したのが始まり。
噛むと燻した香りがじわりと鼻に広がります。
これは、ごはんのお供よりもお酒のつまみに合うおいしさ!
歯ごたえも普通のたくあんよりコリコリしています。
また、米どころの県南を中心に、
"米麹"を使った「麹漬け」が昔から盛んです。
横手市では、今でも町に麹屋さんが20軒ほどあるそうです。
仙北市の角館で160年の歴史を持つ、安藤醸造さんでも
"寒麹(かんこうじ)"が人気。

最近でこそ、TVや雑誌などで"塩麹"のワードをよく目にしますが、
安藤醸造さんでは20年以上も前から、"寒麹"を販売していました。
米麹と塩、水を混ぜて発酵させた"塩麹"に対し、
"寒麹"は米麹と塩、砂糖、お米(もち米)を原料に
寒い時期に作ってゆっくり発酵させたもの。
お米をお漬け物の素に使うなんて、なんと贅沢なことでしょうか!
"塩麹"も"寒麹"も米麹に含まれている酵素の働きで
食材に甘みや旨みをもたらしてくれます。
特に"寒麹"は、麹が砂糖を分解した時にできる甘みが特徴で、
口に含んだ時、確かにしょっぱさよりも、まろやかな甘さを感じました。
ところ変わって、県北の大館市。
1軒の麹屋さんを見かけて中に入ってみました。

こちらが米麹。

見た目はおこしのようです。
この米麹をそのまま買うこともできますし、
自分でお米を持ち込んで、米麹を作ってもらったり、
大豆を持ち込んで、味噌を造ってもらったりできるそう。
私たちが滞在した10分余りのうちにも
次から次へとお客さんがやってきました。
塩麹を買いに来たおじいさん、
出来上がった味噌を取りに来たおばあさん、
お味噌を購入していったおばさん、
そしてお米を持ち込み、米麹を取りに来たおじさん。

「あら~○○さん、いつもありがとう」
「おじいちゃん、何漬けるの? きゅうりの漬け物ならこの量あれば十分よ」
お母さんの笑顔と、お客さんとの会話から
この麹屋さんが地域のみんなから愛されていることが、一目瞭然でした。
私たちが麹について調べていることを話すと、
「今がらこの麹で甘酒つぐるけど、見にぐっが?」
とお客のおじさん。
ということで、今度はおじさんについて行くことに。
居酒屋を営む杉山さんは2年前に体調を崩して病院に行ったものの、
合う薬が見つからなかったといいます。
そんな時に知人に勧められ、甘酒を飲むようになり
体調が回復したんだそうです。
さらに甘酒を飲み続けると、長年の仕事でできた腕のシミが
いつの間にか薄くなり、肌艶がよくなっていました。
これを自分だけにとどめておくのはもったいないと、
周りに作り方を教えたり、
作った甘酒を販売するようになったのだそう。

よく冷えた甘酒は、フルーティーな香りがして飲みやすい!
これまで甘酒はお正月の屋台などで見かけるくらいで
冬の温かい飲み物かと思っていましたが、
江戸時代には、暑気払いに飲む習慣があり
今でも甘酒は、俳句の季語で「夏」のものなのです。
これからの季節、夏バテ対策に甘酒はいいかもしれませんね!
しかもその作り方は米麹さえあればすぐにできてしまいます。
炊いたお米にお湯を足してミキサーにかけ、
約60℃に冷ましてから、米麹を加えて発酵させたら出来上がり。

「甘酒には人間が生ぎでいぐだめに不可欠なビタミン類が
豊富に含まれていで、"飲む点滴"だぁ」
これまでも、お醤油や日本酒、納豆を作る過程で
"麹"の存在に出会ってきましたが、
改めて"麹"のスゴさを実感すると同時に、
"麹"がこれまでよりも少し身近なものになりました。
秋田県民は食通!?
秋田市の無印良品イオンモール秋田店![]() へ。
へ。
いつものように人気商品を伺うと、
「やっぱり秋田の人は食への興味が高いようでして…」
とご紹介いただいたのがこちら。


無印良品のナッツは、油や塩を使わずに
その名の通り、素のまま香ばしくローストしたもの。
一度食べだすとついつい食べ過ぎてしまうナッツ類ですが、
塩がついていないと、ナッツ本来の味が楽しめます。
また、ナッツ類には若返りのビタミンといわれる
「ビタミンE」がとても多く含まれていて、
なかでもアーモンドの含有量が一番多いんだそう。
もともと好きだったアーモンド、
ますますファンになってしまいました!
それから、この季節に人気なのが
「果汁100%のひとくちゼリー」


果汁100%のゼリーってあんまり見たことがないかもしれません。
冷やして食べるとさらにおいしい♪
いよいよ夏本番へ。
食べて元気に、また涼しくなるお気に入りの一品を
ぜひ探してみてください!
その日しか食べられない団子
山形県北東部にある大石田町(おおいしだまち)を車で走っていると、
人気のほとんどない町で、
突如行列のできるお店に出くわしました。

そこは「横丁とうふ店」というお豆腐屋さん。

気になったので、私たちも車を止めて列に並ぶと、

みなさん注文しているのは、お豆腐ではなく、お団子です。
確かにお豆腐の陳列もありますが、
ここのお団子はお豆腐で作られているのでしょうか?
話を聞いてみると、この地域では
お豆腐屋とお団子の組み合わせは珍しくないんだとか。
お豆腐づくりの過程で、大豆を蒸かす際に
お米も一緒に蒸かすようになり、
それをお団子にするようになったといいます。
同じエネルギーで、2つの商品ができてしまうのは
一石二鳥、素晴らしいことですね。
また、店内にはこんな看板や注意書きやがありました。
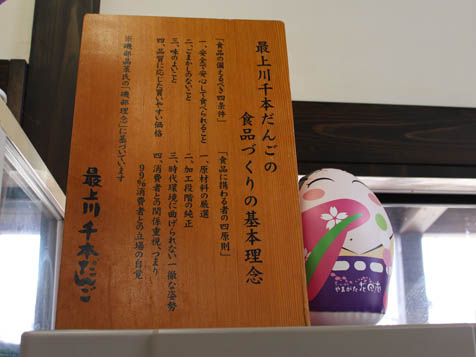

「一本からでもお作り致しますから
本日中に召し上がる分だけお買い求め下さい」
つまり、贈り物やお土産には不向きなお団子なのです。
多く買わせようとするのではなく、
"本物の味を提供しよう"という食品づくりの基本を実現されています。
でもこれは、商売をするうえでは案外実現できていないことかもしれません。
12年前にデパートのフェアで販売した際、
「いつまでもつの?」というお客さんの質問に、
「明日には確実に硬くなります。今日中にお召し上がりください」
と正直に答えたところ、それでも
「本物だから仕方ないわね…」
と1日のうちに1000本以上が売り切れ、
『最上川千本団子』という名称になったんだそうです。

作り置きではなく、注文してから作られるそのお団子は、
ふわふわモチモチで柔らかい!
また、お団子の原料であるお米はもちろん山形県産、
「くるみだんご」(写真上)は地元産のくるみを、
「ずんだんだんご」(写真下)は地元産の枝豆を使用されています。
昨今はインターネットや物流の発達により、
自宅にいながらも全国のグルメやスイーツが味わえてしまう時代ですが、
そこに行かないと食べられない、
作り立てだから美味しい、
もしかすると、それが本来の食のあり方なのかもしれないな…
そう感じました。
納豆汁を作ろう!
山形といえば、

さくらんぼに、

玉こんにゃくが有名ですが、実は「納豆」の消費量が高い
って知っていましたか?
スーパーには山形県産の納豆が多数並び、

"塩納豆"や"南蛮納豆"なんていう、
これまでに見たことのない納豆もありました。

また、家庭料理にも納豆は頻繁に登場するそうです。
例えば、山形でお餅を食べる時には、「納豆もち」が一般的なんだとか。
納豆好きの私たちですが、これまで納豆とお餅の組み合わせは
食べたことがありませんでしたが、おいしい!

次に、山形県の内陸部で食べられているのが、
つゆに納豆と卵、サバ缶などを入れて食べる
「ひっぱりうどん」「ひっぱりそうめん」。
それから、冬の定番料理のひとつが「納豆汁」。
昔から消化が良く体が温まる汁物として親しまれ、
山形では、大みそかや1月7日に七草粥の代わりに
納豆汁を食べる習慣があるといいます。
今回は季節はずれというのと、各家庭で作られているものとあって、
なかなか巡り合えないなか、
酒田市にあるちゃんこ鍋屋「北の富士」さんの料理長にご協力いただき、
「納豆汁」の作り方を教えてもらいました!
材料はこちら。
納豆に、厚揚げ、なめこ、月こんにゃく、山菜、せり。
(季節や家庭によって材料は異なります)
調味料はだし汁、味噌、酒、醤油。

材料がそろったら、まずは納豆にお酒を少々加え、
すり鉢でよくすります。
(すり鉢がない場合は、包丁で細かく刻んでもいいそう)

続いて、だし汁に納豆以外の材料を入れて煮ます。
具材が柔らかくなったら、お味噌と醤油少々で味付け、

最後に納豆を入れます。
(納豆を入れる際に、煮汁でゆるめて溶かし入れるのがポイント!)

器に入れて、お好みでせりやネギをのせたら出来上がり!

とっても簡単です♪
食べてみると、少しとろみがあり、
食べているうちに早速、体がぽかぽかしてきました。
「雪道と納豆汁は後の方がいい」という言葉があるそうで、
降り積もった雪道は、誰か先に歩き踏み固まった後の方が良い。
納豆汁も出来上がりをすぐに食べるよりも、
半日くらい寝かせて食べるとさらにおいしいんだそうです。
高たんぱく、低脂肪で胃腸にやさしい納豆を使用している納豆汁は、
整腸作用や肝臓障害防止にも最適のようです。
すぐに真似のできそうな、山形県の郷土料理「納豆汁」を
家庭で作ってみてはいかがですか?
山形の暑い夏の過ごし方
「山形って夏暑いんですよ!」
無印良品イオン山形北店![]() に伺うと、
に伺うと、
そう店長が教えてくださいました。
山形が冬寒いのは知っていますが、夏暑い?
意外でしたが、山形市は2007年まで、
なんと74年間にわたって日本最高気温の記録を保持していたんだそう。
そんな暑い山形で人気の商品とは…

店長の身につけているもの、なんだか分かりますか?

水だけあれば何度でも使えるクールバンド、いいですね☆
さりげなくつけられますし。
以前、インドの砂漠でラクダに乗っていた時に、
同じく水に浸した布をかけると暑さをしのげると
ラクダ使いに教えてもらったことを思い出しました。
暑さ対策は万国共通なんですね!
他にも山形の暑さ対策を聞く中でお薦めいただいたのがコレ。

氷が浮いたラーメン!?!
山形市のとあるラーメン屋で、常連客の
「夏には冷たい蕎麦を食べるんだから、ラーメンも冷たいのが食べたい」
というひと言から考案された一品、
「冷やしラーメン」だそうです。
食べてみて納得!
さっぱりしたスープにつるつるコシのある麺がおいしい♪
スーパーに行ってみたら、家庭で作れる
「冷やしラーメン」もありましたよ。

また、あるようで食べたことのなかったお蕎麦、
「冷やし肉そば」もぜひ!と言われて実食。

鶏だしのきいた醤油味の冷たい汁そば。
つけ蕎麦の場合、どちらかというとお蕎麦そのものを味わうのに対し、
この「冷やし肉そば」は冷たいつゆと、歯ごたえのある鶏肉が
すべてセットになって出来上がっている味のようですね。
「冷やし肉そば」のルーツは大正時代にさかのぼるそうですが、
こちらも常連さんがおかずのお肉をお蕎麦にのせて食べたのが
キッカケなんだとか。
暑い山形で生まれた「冷やしラーメン」に「冷やし肉そば」。
食文化の中にも、こうした暑さを乗り越えるコツがあるんですね!
みなさんの地域の食べ物はいかがですか?
米沢牛との出逢い
山形県南部の人口8000人に満たない町、飯豊町(いいでまち)。

広大な田園散居集落が広がるその地は、
全国にその名を轟かせる肉牛の産地でもあります。

「松阪牛」「神戸牛」と並んで、日本三大和牛に数えられる「米沢牛」。
その約4割は、この飯豊町で飼育され、出荷されているんです。
その牛を一目見たいと、宿の近くの牛舎の周りをウロウロしていると、
よほど怪しく見えたのでしょう。
「どっから来たね?」
複数の男性に声を掛けられます。
「東京です。取材で」
と応えると、
「そしたら、ええ写真ある。づいでごい」
と言われるがままに、近くの公民館に連れて行ってもらうことに。
そこには、米沢牛の歴史を語るうえで、希少な写真が飾られていました。


「むがしっがら、立派な牛を育てとったんだぁ」
そう、その男性たちは、
飯豊町で畜産業を営む社長の方々だったのです。
しかもそのうちの一人は、
この地区で最も古くから畜産業を営む、田中畜産の田中社長。
偶然の巡り合わせで、米沢牛の歴史、おいしさの秘訣などについて
お聞きすることができました。
米沢牛の名が全国に馳せるようになったのは明治初期。
米沢藩に招かれていた英国人講師チャールズ・ヘンリー・ダラス氏が、
故郷を懐かしんで牛肉を食べ、その味に感激し、任務を終えた際に、
米沢の牛を1頭横浜に連れ帰り、仲間に振る舞ったことに始まるようです。
当時、食肉用というよりも、農耕作業用に飼われていた牛でしたが、
文明開化後、欧米の肉食文化が浸透していくにつれ、
米沢牛の名は徐々に全国的に広まっていきました。
「その美味しさの秘訣は?」
ふと素人じみた質問をすると、
「ええもん食わせてっからなぁ」と。

かねて土壌が肥沃だったこの地域では、
農耕作業用に家族同様に扱われていた牛にも
お米を与えていたんだそう。
今でこそお米は与えてはいませんが、
国産の稲わら、大麦、とうもろこし、大豆かす、フスマ、米ぬかなど、
生産者独自に、おいしい肉質を追求した餌が配合され、
場所によっては米沢産のりんごを与えるところもあるそうです。
田中社長曰く、海外では与えないような独自の餌の配合が、
和牛のおいしさをもたらしているとのこと。
さらに、寒暖差の激しい気候も、
牛の体が寒い冬を乗り越えるべく、脂質を蓄えようとするため、
きめ細かい霜降り肉にするための大切な条件なんだそうです。
「なるほど、それなりにお値段が張るわけですよね…」
「そりゃそうだぁ。2年間、育てっがら!」
そう、生後10ヵ月の仔牛から精魂込めて約2年間、
立派な牛に育て上げたうえで、出荷するわけなんです。
しかも、1頭の母牛から1頭しか仔牛は誕生しません。
ちなみに、
豚は一頭から3~12匹産まれ、出荷までは約6ヶ月間。
鶏は一頭からたくさんの卵が産まれ、出荷までは約2ヵ月間。
牛肉が高い訳も分かります。
それだけに出荷する時は、さみしさも募るようです。
一頭ずつ、番号で呼んでいるのかと思いきや、
きちんと名前も付けているそうですから。


写真は昔の出荷時の光景ですが、
生産者たちが総出で、牛を見送っている姿からも、
その想いの強さを感じます。
「せっかぐだから、食べてけぇ」
普通には絶対に聞けないような話を聞くことができ、
その上、ご馳走にまでなるのはさすがに気が引けましたが、
「ええがら、ええがら」
と笑顔で田中社長に勧められ、結局お言葉に甘えることに…。

そこで出していただいた牛肉は、
口の中でとろけるような味わい。

レバーも、まったくと言っていいほど臭みがありません。

これで、レバ刺しも食べ納めです。
(取材は、6月下旬に行いました)
日本三大和牛、米沢牛のおいしさの裏には、
生産者のあくなき努力と想いが詰まっているんですね。
食卓では、常に感謝の気持ちを忘れずに、
もちろん残すことなく頂こうと心に決めました。
美味しい食づくりを通じて伝える心
長野県下高井郡、野沢温泉村。

日本屈指の標高差を誇るスキー場を有する温泉街には、
冬になると世界中からスキーヤーたちが集まります。
この地を初夏に訪れた私たち。
そこには、熱い温泉と熱い想いを持った人たちによる、
オフシーズンでも楽しめる、様々な取り組みが待ち受けていました。
まず訪れた先が、村のホテル「住吉屋」さん。

風情ある旅館といった雰囲気ですが、
前社長がホテルのプライベート性と旅館のサービスの良いところを目指して
「村のホテル」と命名したそう。
また、贅を尽くしたサービスよりも、
普段着の心でのお出迎えをモットーに、
料理も、野沢で昔ながらに食されているおかずを提供しています。
その代表格が"取り回し鉢"と呼ばれる、
野沢に江戸時代から伝わる祝い膳料理。

特別な材料を使ったものではなく、
地元の野菜や山菜を使った田舎料理で、
夕飯時に2〜3品選ぶことができるそう。
素材の持ち味を生かした素朴な味付けで、
都会ではなかなか巡り合えない味わいです。

それもキチンとした説明と共に提供してくれるのが、うれしいところ。
こうした昔ながらに食べられている味覚こそが、
本当に旅人が求める味なのではないでしょうか?
過剰なサービスはありませんが、十分に心のこもった住吉屋さんのお出迎えは、
無印良品的な宿とでも言いたくなるほど心地の良いものでした。
続いて訪れたのは、ハウスサンアントンジャム工房。

オーストリアで学ばれたというジャムづくりを手掛けるのは、
なんと過去2回もスキーの日本代表としてオリンピックに出場したことのある、
片桐幹雄さんと奥様の逸子さん。
主に長野で採れる厳選した果実と、
腕自慢のシェフの力を使って、
「素材に新しい命を吹き込むようなピュアで素材感たっぷりのジャムを作ろう!」
という想いから、ジャム作りをスタートされたようです。
「同じフルーツでも、その年の気候で味も香りも異なるんです。
素材そのものの味を引き出すよう心掛けているので、
毎年、味が違うんですよ。ほら、ワインだってそうでしょ」
そう話す片桐さんご夫妻のジャム&ジュースは、
常に最高の出来を追求した逸品です。

そのお味は、口の中いっぱいに自然の甘みが広がりました。
Found MUJIを扱う一部の無印良品の店舗でも、
お買い求め頂けます。
こうしてジャムの製造販売を始めたことによって、
スキーのオフシーズンでも、
この地に雇用を生み出していくことができるようになったと言います。
そんなハウスサンアントンさんのジャムがよく合うパン工房があると紹介され、
伺ったのは、長野市にある「ベッカライ麦星」。

偶然にも前述の片桐さんと同様、
オーストリアでパンづくりを学ばれてきたという鈴木さんご夫婦が営む、
ライ麦パンを主としたパン屋さんです。

薪で焼き上げる理由は、
間伐材を燃料にすることで少しでも森の循環を取り戻したかったから。
ライ麦というのも、雪国でも育つ農作物として、
追々は近隣の休耕畑を生かしたいと考えているからだそう。
一つひとつに想いのある工程から作られたライ麦パンは、
想像していたような酸味は少なく、まろやかな甘みすら感じる味でした。

「ライ麦パンというのは、正しく発酵させてあげれば、
酸味を抑えることができるんです。
今はまだまだですが、美味しいライ麦パンづくりを通じて、地域に貢献したい」
ここにも一つ、これからの時代における、
ものづくりのヒントが眠っていました。
美味しい食づくりを通じて心を伝え、
それが新たな需要を生み出すことに繋がる。
長野で出会った取り組みは、着実に実を結び始めています。
飲む野菜の酢「SURARA」
浅間山の山懐に抱かれた佐久(さく)市は、長野県屈指の米どころ。
この地では、八ヶ岳の伏流水とその冷涼な気候を利用した酒造りが
昔から盛んに行われてきたそうです。
今回は、1887年創業の「芙蓉酒造」さんを訪ねてきました。
酒蔵ではお酒造りの真っ最中ですが、
お酒造りは寒い冬に行うものだったはず。
伺ったところ、
「日本酒は低い温度でゆっくりと発酵させていくものですが、
焼酎は暖かい中でも造れるんですよ」
と教えてくださいました。
確かに東北地方では日本酒が多く、九州地方では焼酎が
多く造られていますものね。

蔵を見せていただくと、長いも、ねずみ大根、
レタス、かぼちゃ、えのきだけ…などと書かれた樽がたくさん。
お芋以外の「野菜焼酎」って、
ありそうでこれまでに出会ってこなかったものです。
お酒造りは、原料によって必要な免許が違ってくるようで、
野菜を使った焼酎を造れる酒蔵は数少ないんだそう。
その情報は口コミで広がり、芙蓉酒造さんでは、
信州で採れた地の野菜を使った焼酎造りをはじめ、
全国の特産物を使った焼酎も委託製造されているそうです。
さて、これまでにも何軒か酒蔵さんにお邪魔してきた私たちですが、
やはりまだまだ分からないことが多いお酒造り。
すると、
「僕ももともと素人でしたから。そもそも飲料には…」
と、黒板を使って丁寧に説明くださりました。


教えてくださった、企画開発部部長の依田さんは、
もともと東京で音楽業界の仕事をしていたそうですが、
4年前に実家に戻り、お酒造りを始められたそう。
そして、彼が1人で企画・開発・製造を手がけるのが、
Found MUJIを扱う店舗で販売中の
「飲む野菜の酢SURARA」なんです。
レタスは清涼感があり、かぼちゃはほっこりと甘く、
えのき茸はまろやかな味わいが魅力です。

いろいろな種類の焼酎が増えてきて、
それを何かに活かせないか…というところから
考案されたのがお酢造りだったといいます。
「負けん気が強いんで、手ぶらで実家に帰るのは嫌だったんです」
と依田さん。
東京で働きながらも、週末に情報収集を重ね、
3年間の研究を経て、2011年7月に発売したのがこの飲む酢でした。
お酢造りの工程は、途中までお酒造りのそれと同じだそうですが、
全国的に見ても、酒蔵がお酢を造るのは珍しいのだそう。
それよりも、むしろタブーとされてきたんだとか。
「初め、お酢造りの構想を父親に話したら、猛反対を受けました。
他の周りの人からもバカか…と言われましたね」
さらに、お酒業界は情報流通があるようなのですが、
お酢業界には情報の流通があまりないのだそう。
「お酢造りについて、聞く相手がいなかったのが一番大変でした」
業界の常識を打ち破ってまでSURARAを生み出した依田さんには、
並々ならない信念を感じました。
"お酢を楽しく飲んで、健康で軽やかな人生を過ごして欲しい"
というコンセプトのSURARAは、
ドリンクとして飲むほかに、料理の調味料としても、
もちろんお酒と合わせても相性バツグンだそう♪
永年培われてきた技術を活かして、新たなコトに取り組む姿勢。
モノづくりだけでなく何事にも、参考にできるヒントではないでしょうか。
オバマ市からもらった、くらしのヒント
米・オバマ大統領を応援する市として
一躍有名になった、福井県小浜(おばま)市。

街の至る所に、オバマ大統領が…!
次の大統領選でも注目されることは間違いありません。
さて、そんな小浜市は若狭湾に面しており、海産物が豊富に採れます。
平安・奈良時代には、サバをはじめとする高級特産物を朝廷に献上していた、
御食国(みつけのくに)のひとつなんです。

食の歴史もあるなかで、2001年には、
全国初の食をテーマにした、「食のまちづくり条例」を制定。
これはご当地グルメのような観光客誘致が目的ではなく、
住民を主なターゲットにしたものだそう。
その土地にくらす地域住民にこそ、地場の農林水産物の
ファンになってもらうべく、様々な取り組みがされているようです。
今回、そんな食のまちづくりの拠点施設、
「御食国若狭おばま食文化館」を訪れました。

施設内は、食に関する歴史・伝統・文化の展示があり、
例えば特産物のサバのレシピ30種のレプリカ、なんていうのもありました。

また、「キッチンスタジオ」も併設されていて、
季節の食材を使ったお料理や郷土料理の教室が開催されています。

ちょうどお料理教室の日程に訪れた私たちは、
地元の主婦の方にまざって、季節の調理体験に参加してきました!


旬のたけのこやそら豆を使った煮物や、梅の香寿司をみんなで作りました。
毎月この料理教室に参加している、という方も多く、
地元のみなさんの交流の場になっているんですね。
他県から嫁いできたという方もいて、
「地元の食材の食べ方が分かっていい」とおっしゃっていました。
さらに、小浜市では小浜で生まれ育つ子ども全員に、
"食育"の機会を提供するため、義務食育体制を構築。
公立、私立問わず、市内の全幼稚園・保育園の年間行事に
「キッズ・キッチン」と呼ばれるお料理教室を組み込んでいるそうです。
小学校や中学校の給食では、
近隣の農家や漁師さんに食材を提供してもらい、
「本日の食材の若狭カンラン(キャベツ)は
○○おじさんの畑で収穫されたものです」
といったアナウンスが流れ、
生産者への感謝の気持ちを育み、給食の残食も減少したんだとか。
このキャラバンが始まってから、
各地で"地産地消"のワードを見かけてきましたが、
この小浜市の給食の取り組みは、ひとつの地産地消のお手本かもしれません。
群馬のキャンプ場で焚き火をした時もみんなと語り合いましたが、
"なぜ地産地消がよいのか"ということについて、
私たちは分かっているつもりになるのではなく、
腹に落ちるまで考え続けようと思います。
「無駄な輸送費がかからないためエコである」
ということはよくいわれます。
そして、今回、小浜市で考えたのは、
「生産者の顔が見えることは、安心安全につながるだけでなく、
消費者が生産者や自然の恵みに感謝を忘れず、共に育んでいくことにつながる」
ということでした。
そして何より、その特産物を作る人こそが、もっとも愛情を持っているのだから、
その地域にこそ、その特産物の活かし方が伝わっているんですね!
改めて、地産地消は、これからの良いくらしへのヒント
といえるのではないでしょうか。
いったん立ち止まって考えることは、とても大事なことですよね。
2人の野菜プリンス
能登半島に囲われるようにして存在する能登島に、
全国のレストランから注目を浴びている農園があると聞きつけ、
突撃訪問して参りました。
突然お邪魔したにもかかわらず、快く会っていただいたのが、
高農園を経営する高利充さん。

日本でも希少な赤土の土壌でつくられる、高さんの野菜は、
今や全国200軒のレストランから引き合いがあるそうです。
能登島で唯一、有機認証を受けながらも、
「近隣の農家が農薬を使っていれば、それが飛散してくることもあるので、
無農薬野菜とは呼んでいないんです」
と言うほどの正直さ。
高さんから頂いた野菜は、
野菜そのものの味が口の中でしっかりと広がりました。

ほんのわずかな出会いにもかかわらず、
高さんの誠実さには心打たれるものがありました。
「金沢に加賀野菜のプリンスと呼ばれる人がいますよ」
そう高さんに紹介いただいたら、行かないわけにはいきません。
向かった先は金沢市近江町の「北形青果」。
80年以上の間、加賀野菜を取り扱う八百屋の、
4代目を務めるのが北形謙太郎さんです。

ところで、加賀野菜って一体何なのでしょう?
「○○県では○○野菜、といった大規模産地ブームとは相反して、
金沢では昔から、在来種を使った様々な野菜がつくられてきました。
四季折々で、地元の人に親しまれてきたのが加賀野菜です」
そう話す北形さんのお店の店頭には、
今が旬の大きなたけのこや、

加賀太きゅうりが、強烈な個性を放ちながら並んでいます。

シーズンも終わりに差し掛かったれんこんや、

さつまいもは、均一な大きさごとに分けられ、大きく棚を占拠していました。

加賀野菜の品種は、今では15種にも上り、
旬ごとに、店頭を彩る野菜が違うようです。
そして、それぞれの野菜によって、
幾通りかの地元特有の食べ方があるのも加賀野菜の特徴。
「加賀太きゅうりはだし汁にさっと通して、あんかけで食べるのがお勧めです。
夏には、金時草を使ったおひたしで、夏バテ防止、
冬には、加賀れんこんを使ったれんこん団子汁を食べれば、体が温まりますよ」
こんなふうに、店頭で食べ方まで提案してもらえるんです。
季節ごとに旬の野菜を食べて、厳しい気候を乗り越える。
金沢では、昔ながらの生活の知恵が、今でも生活に根付いていました。
当たり前のように食べたい野菜を食べたい時に買っていた私たちは、
今まで野菜の旬などを意識したことなどほとんどありませんでした。
でも、当然野菜には収穫時期があって、
そこには自然の摂理に基づいた効能もあるんですよね。
このように、地場でつくられた旬の野菜が八百屋に並び、
地元の人が、「旬がきたわね~」とその野菜を買っていく姿こそ自然で、
あるべき光景なのだと思いました。
地産地消とは、まさにこういうことを言うのでしょうね。
バタバタ茶
各地を旅していると、ご当地食材に出会いますが、
なかでも、必ず各地で見かけるのが「お茶」。
千葉では「びわ茶」、茨城で「そば茶」、
栃木で「はと麦茶」、群馬では「桑茶」というように。
ふと考えてみると、お茶は日本国内だけならず、
世界中で様々に飲まれていますね。
私たちが以前世界を回った時には、中国はもちろんのこと、
イギリスのイングリッシュティーをはじめ、
インドのチャイ(ミルクティー)、トルコのアップルティー、
チベットではバター茶なんていうのもありました。
現地では、(特にインドやトルコでは)お茶そのものを楽しむというよりも、
お茶を飲む時間を使って、コミュニケーションを楽しんでいるという印象で、
朝から夜まで、至る所でお茶をしている人々をよく見かけました。
さて、新潟県との県境に程近い、富山県朝日町蛭谷(びるだん)の集落には
今でも独自のお茶文化が残っていると聞いて、行ってきました。
向かった先は「バタバタ茶伝承館」。
公民館のようなその施設の扉を開くと、
「いらっしゃい〜」とおばさまたち。
ちょうどお休みの日で、近くに住むお孫さんたちも遊びに来ていました。
「まぁ、飲んでいってちょうだいよ」
と、グツグツと煮え立つお鍋の中から器にお茶を注ぎ、
慣れた手つきでお茶を点て始めます。


カタカタカタ…
2本連なった珍しい茶せん(夫婦茶せん)を使って
左右にお茶を泡立てて飲む。
そう、これこそが蛭谷で飲まれている「バタバタ茶」です。
バタバタというより、カタカタ音がするから、
カタカタ茶の方が合っているかも?
そんなことを思っていると、このバタバタとはお茶を点てる音ではなく、
あわただしくバタバタと茶せんを左右に振る動作を指している
と教えてくれました。
この地域では、ご先祖様の命日や、その他結婚式や入学式などの行事の際に
お茶会を開くんだそうです。
もともとは浄土真宗の儀式のひとつで、
自分たちがお茶をいただく前に、まずは仏様に供えるんだとか。
また、2009年からはこの伝承館において、
近所のおばさま方が交代制で番を務め、近所の人をはじめ、
私たちのような訪問者を温かく迎え入れ、お茶会を開いているのです。
お茶会と聞くと、なんだか難しい礼儀作法とかいろいろとありそう…。
そう伝えると、バタバタ茶においては、決まり事はほとんどなく、
自由に、何杯でもお茶を飲んでいいといいます。

早速、私たちもバタバタ茶を点ててみました!

手首の力を抜いて、左右にカタカタ、カタカタ。
徐々に泡立っていくのが面白い!
こうして、泡を立てることでマイルドな味になるんだそうですよ。
ちなみに、小学校低学年のお孫さんも上手にお茶を点てていて驚くと、
以前までこの地域にあった幼稚園では、
子供たちにもバタバタ茶の文化を伝承していたそう。
そんなバタバタ茶の原料は、「朝日黒茶」というもの。

お茶は製造方法によって基本的に、
不発酵茶・半発酵茶・発酵茶・後発酵茶の4つに大きく分けられるといいます。
それぞれ代表的なものに、不発酵茶は「緑茶」、
半発酵茶は「ウーロン茶」、発酵茶は「紅茶」があり、
「黒茶」は後発酵茶に該当します。
紅茶・ウーロン茶が茶の葉に含まれる酵素の働きで発酵して作られるのに対し、
黒茶は酵素の働きをいったん止めた後、こうじ菌の働きで発酵させるのだそう。
また出てきましたね、"発酵"に"こうじ菌"というキーワード。
これまでも、お醤油や日本酒、納豆づくりに欠かせないものとして
登場してきましたが、お茶にまでこれらがかかわっているとは!

バタバタ茶のお茶請けには、地元で採れた山菜や野菜の煮付け、
漬け物などがつくのが一般的。
お茶請けというと、和菓子のイメージを持ってしまっていましたが、
そういえば、これも各地で違うかもしれませんね。
茨城や栃木では、お茶と一緒に"おせんべい"が出てくることが多かった気がします。
月・水・金・土の10:00~15:00に開館している伝承館は、
その名の通り、バタバタ茶の文化を後世に伝承していく場でもあり、
地元の人の大切なコミュニケーションの場でもあります。
知らない人が来たからといって、嫌な顔をせず笑顔で迎え入れてくれる。
そして、お茶を飲みながら世間話をして、ゆっくりと時間が過ぎていく。
なんだか、海外を旅した時に味わったような感覚を思い出しました。
自然の恵みに感謝して
群馬県北東部、武尊山の南麓に位置する川場村。
人口約4000人弱のこの村には、豊かな自然とその恵みを求めて、
毎年約90万人の観光客が押し寄せます。
水はけの良い土壌は、豊富な地下水をどんどん流し、田畑を潤すことから、
お米をはじめ、こんにゃく、リンゴ、ブルーベリーなど、
様々な農産物を作り出します。
なかでも、注目されているのがお米。

「雪ほたか」と呼ばれるそのお米は、
平成19年から23年までのあいだ、5年連続で
米・食味分析鑑定コンクールで金賞を受賞しました。
その生産量の少なさから、
一般には流通しない「幻の米」ともいわれています。
実際に、その雪ほたかで握られたおにぎりを頂きました。

米粒がしっかりしていながらも、絶妙のもちもち感。
美味しいお米を作り続けられる要因は何なのでしょう?
「特別なことはやっていないんですよ。
あくまでも基本に忠実にお米を育てているだけで、
あとは川場村の土壌や環境が育ててくれるんです」
株式会社雪ほたかの小林社長(写真右)はそう答えてくれました。

基本に忠実にというのが肝のようで、
生産農家には年5回の栽培講習会に、必ず出席してもらっているんだとか。
徹底して量より質を追求する姿勢は、
小さい村の一つの模範ではないかと感じました。
そして、川場村の自然がもたらしてくれる環境…。
武尊山より湧き出るミネラルたっぷりの天然水による恵みのことは、
次の生産者さんも同様のことをおっしゃっていました。
明治19年創業の酒蔵、清酒「水芭蕉」醸造元の永井酒造。

世界初のシャンパン製法を日本酒づくりに取り入れ、
スパークリングする清酒「MIZUBASHO PURE」を開発された酒蔵です。

このお酒は、世界13カ国にも輸出され、
スペインの世界最高峰のレストラン「エル・ブリ」にも採用されました。
日本酒づくりにおいても、顧客の口に運ばれるまでの工程を見直し、
生酒の状態を極力キープするため、マイナス気温下で貯蔵する貯蔵庫や、
瓶詰め後の火入れ処理など、独自の製法を追求していっています。

人でしかできない五感を使った工程は人が行い、
機械でも行える工程は機械を導入し効率的に行う、
という柔軟な姿勢も印象的でした。
「こうしてお酒がつくれる喜びを忘れないようにしたい」
そう語るのは、この酒蔵の杜氏を務める後藤さん。

このお酒がつくれるのも川場村の美味しい水があるからこそ、
という感謝の意を忘れないため、
毎年、社員で川場村の源流で滝行を行うんだそう。
ここまで生産者の方々が、その土地に愛着と感謝の意を持って、
ものづくりに励まれているとは…。
恥ずかしながら、今まで地理や土地を意識しながら
生活してきたことはありませんでした。
ただ、普段、私たちが口にしている美味しい飲食物は、
すべてその土地にある、自然の恵みから来ているんですよね。
自然に感謝するというのは、至極当然のことなのかもしれない、
と思い知らされました。
こんにゃくはお腹の掃除機!?
群馬県が全国における、生産量約9割を誇る作物があります。

これがその作物、こんにゃく芋。
おなじみの上毛かるたにも、登場しています。

こんにゃく芋の栽培が、群馬県で盛んになった理由は、
やはりその土壌と気候にあるそうです。
赤城山一帯には水はけのよい土地が広がり、暑すぎず寒すぎない気候が
こんにゃく芋の栽培に適していたのです。
今回はそんなこんにゃく芋から作る、こんにゃく作り体験をしてきました!

まずは皮を剥きます。
こんにゃく芋を素手で触ると手が荒れてしまうそうで、
手袋を装着して行いました。

あれ? お母さんは手袋をしなくても大丈夫なんでしょうか?
「私は手の皮が分厚くなってるから、大丈夫なんだよ」
とお母さん。
また、こんにゃく芋の汁が目に入ると
激しい痛みをともない、病院送りになってしまうそうなので要注意!
って、これもお母さんは経験済みだそう。

続いて、皮を剥いてカットしたこんにゃく芋と水をミキサーにかけます。
昔はミキサーがなかったため、おろし金を使って行っていたというので
さぞ大変だったことでしょう…。

ちなみに、最初は上の写真のように、中央に穴が開いているのですが、
この穴がなくなってきたら、全体が細かくなった証拠だそう。
お母さんの知恵ですね。

次に、沸かしておいたお湯の中に
ミキサーにかけたこんにゃく芋を入れ、20〜30分混ぜながら煮ます。

しばらくすると、粘り気が出てくるのですが、
さらに凝固剤(水で溶いた炭酸ナトリウム)を加えて混ぜます。

色が変わったら、タッパーにあけて均一になるよう平らにします。

タッパーの中のこんにゃくが固まったら、適当な大きさに切って
再び沸かしたお湯の中に入れ、
30〜40分あく抜きのために煮たら、出来上がり!

食べてみると、弾力があってみずみずしい味がしました。
それもそのはず、こんにゃくは作る工程を見ても分かるように、
こんにゃく芋と凝固剤以外はすべて水、
その約97%が水分からできているんです。
また、こんにゃくには食物繊維が多く含まれていて、
腸の動きを活発にし、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があるといいます。
昔の人は、こんにゃくを「胃のほうき」や「腸の砂下ろし」と呼んで、
大掃除の後には必ずこんにゃくを
体内の毒さらいに食べるという習慣があったくらい。
ところで、普段食べているこんにゃくって
黒い斑点のようなものがあった気がします。
聞いてみると、市販のこんにゃくの黒い斑点は
ひじき等の海藻なんだそうですね。
昔は凝固剤として灰汁を使い、またこんにゃく芋の皮が入って
黒っぽいこんにゃくが出来上がっていたそうなのですが、
その後、こんにゃく芋を製粉したものと凝固剤を使うようになり、
白いこんにゃくができました。
しかし、白いこんにゃくは見慣れないために売れなかったそうで、
黒いこんにゃくにするために、海藻類を入れるようになったんだとか。
そんなこんにゃくですが、みなさんはどのように食べますか?
おでんに入れたり、煮物に入れたり。
今回、こんにゃく作りを体験させていただいた、関さん宅では
いろいろなこんにゃくレシピを開発されていました。

サクサクなのに、噛むと弾力がある、
「こんにゃくの唐揚げ」
これは市販のこんにゃくだと、ツルツルしすぎていて衣がつかないそう。

デザートなのにカロリーが低くてうれしい、
「こんにゃく羊羹」
こうして見てみると、こんにゃくの効用ってすごくないですか?
こんにゃく自体の味はほとんどないので、
こんにゃくを使ったレシピもまだまだ幅がありそうですね。
健康のためにも、もっとこんにゃくを食べようと思います!
栃木の"人気もの"
栃木県民ならびに周辺の茨城県民や福島県民がお買い物に行くのが
インターパーク宇都宮南。
北関東最大の複合型ショッピングセンターです。
行ってみると、本当に広い!!!
敷地内の駐車場収容台数は1万台以上に達し、
駐車場で迷ってしまいそうなほどでしたが、
その中にある無印良品に行ってきました。

平日の午前中だったのですが、お子様連れのお母さんたちで
賑わっていましたよ。
さて、そんな宇都宮インターパークビレッジ店![]() の人気商品を伺ってみました。
の人気商品を伺ってみました。


なかでもオールインワン美容液ジェルは、洗顔後にそれひとつをつければいい
ということでとても便利なんです!
子育てで忙しいお母さん、朝時間のないOLさん、
私のようなめんどくさがり屋さんなどにピッタリですね。
そう、私たちキャラバン隊の一人もこれ愛用しているんですが、
とにかくお肌がしっとりしますよ。
続いて、地元出身のスタッフに宇都宮の情報を聞いてみると、
やっぱり出てきました、餃子の話題!
もともと宇都宮が餃子の街として知られるようになったのは、
1990年に、町興しにつなげられるキーワードを探していた市の職員が、
総務庁統計局の家計調査年報において「餃子購入額」で
同市が常に上位に挙がっていることに注目し、
餃子による町興しを提案したのがきっかけだそう。
地元の人には「正嗣(まさし)」と「みんみん」が人気だそうですが、
時間のない人にお薦めの場所を紹介していただきました。

宇都宮餃子会に加盟する27店の味が味わえる、「来らっせ」。
日替わりで、2個ずつ5店の味を1皿で
楽しめるプレートもありました。

観光客はもちろん、地元の人たちにも人気の場所だそうですよ。
さて、他に栃木といって思い浮かぶものといえば…

「いちご」です。
栃木県は昭和43年産から平成22年産まで、
43年間連続日本一のいちごの生産量を誇る県なのです。
県央部から南部に広がる関東平野の肥沃な大地とキレイな水、
そして冬の日照時間が長いことがいちごの生育に向いているのだそう。
さらに、地下水の豊富な芳賀町にある、「きみじまいちご園」で伺った話によると、
地下水を利用した自然のウォーターカーテンで、ビニールハウスを暖め、
長い間、甘いいちごが収穫できるようにしているんだそうです。
ちなみに、いちごは、実はビタミンCの宝庫。
ビタミンCが100g中62mgも含まれていて、
中程度の大きさのいちごを1日9~10粒ほど食べれば、
必要なビタミンCがとれてしまうとか。
オレンジやグレープフルーツよりも、ビタミンCが多いというから驚きですね。
他に栃木の人気ものといえば、これ↓

「レモン牛乳」
てっきりレモンの酸っぱい味がするのかと思って飲んでみると、
レモンは風味程度で、酸っぱいわけではありませんでした。
宇都宮市の老舗製乳メーカー「関東牛乳」が
第二次世界大戦後、間もない頃に開発し、
同市内の牛乳販売店のほか学校の購買部や運動会など学校行事での販売を通して
売れ筋商品となったそうです。
最後に、栃木の郷土料理。
「ちたけそば」

チチタケというきのこと、炒めた茄子だけが入った
シンプルなものでしたが、
チチタケから出るだしが風味豊かでとても美味しかったです。
ちなみに日本産のチチタケは貴重で、松茸よりも高額で
売られていることもあるそうです。
他にも、佐野市周辺には「佐野ラーメン」、
日光市では「ゆば料理」など、
各地域に"人気もの"がありました。
みなさんの地域には、どんな"人気もの"がいますか?
麻をもっと身近に
古くから、人間のくらしと共にあった麻。
かつては、日本でも全国各地で生産され、
織物や袋、綱、紐などの原料として利用されてきましたが、
戦後、化学繊維の台頭による需要の減少によって、ほとんどの地域で生産が途絶えました。
現在に残る生産地域は、岐阜県や滋賀県、群馬県の一部と栃木県。
その中でも、日本最大の麻の産地、栃木県鹿沼市永野(旧粟野町)を訪れました。
良質な麻が育つ土壌は、一般的には痩せた土地と呼ばれる、砂礫地で水はけが良い土壌。
栃木県のこの界隈は、台風や雹害の少ない地域としても、適地であるそうです。
この地で収穫された麻は「野州麻」と呼ばれ、
昔から品質の高い国産麻として知られています。
そんな野州麻を見に行くと、3月末に種まきをしたばかりで、
今はちょうど芽が生えてきたところでした。

「これが、7月中旬の収穫期には、2m30cm程度にまで大きくなるんです」
そう教えてくださったのは、この地で8代にわたって麻の生産を続けている、
大森家の芳紀さん。

失われつつある麻の文化を現代に伝えるべく、
9年ほど前から麻を原料にした和紙づくりを始め、
その和紙を使ったランプも手掛けています。
家族で営むカフェでは、大森さんの作ったランプで
あたたかみのある雰囲気に包まれるなか、
麻の実の入ったピザを食べることもできました。

現在、国産麻の用途の7割程度は神事用(しめ縄や鈴縄など)、
残り3割も弓道用の弓具や、日光下駄の縫紐、
喧嘩凧などの特殊な用途が多いんだそう。
「育ちが早くて丈夫な繊維である麻を、
今一度、生活の身近なところに感じてほしかったんです」
大森さんは、麻紙づくりを始めたきっかけを、そう語ってくださいました。
しかも、麻紙の原料は、
麻を紡績の原料(セイマ)になるように精製する過程でできる「オアカ」。

昔は堆肥として、使われていたようですが、
1kgのセイマを作るのに、1.5kgのオアカができるため、
今では堆肥としても使いきれていなかったそうなのです。
その製法も、稲わらやぬかを使って発酵させ、
麻から繊維を取り出すという、自然の原理を利用したやり方。
「化学製品を使ってみたこともあるのですが、やっぱり繊維が傷んでしまうんですよね」
麻の繊維は丈夫であるという特徴を活かすために、
徹底的にこだわりぬく姿勢には脱帽でした。
昔から人のくらしを支え続けてきた、麻。
丈夫で、通気性も良く、濡れても乾きやすいため、
現代のくらしの中でも、もっとたくさん活用できるシーンがあるはずです。
無印良品でも、麻を使ったくらしのキャンペーンが始まりました。
麻のある生活、初めてみませんか?
救荒作物、そば
救荒作物ってご存じですか?
米・麦のような主食となる作物が凶作時でも、生育して、
ある程度の収穫量を得られる作物のことです。
以前に記した「雑穀ごはん」でも登場した「あわ」や「ひえ」、
また、慣れ親しまれている食では「そば」もそれにあたります。
そばは75日間程度で成熟する短期作物のため、二毛作も多く、
先述の麻の裏作としても多く作られているようです。
そんな特性のため、そばは日本各地で作られていますが、
栃木県日光市で、初めてのそば打ちを体験してきました。
元々、米の穫れなかったこの地域では、
そば打ちができないと、お嫁に行くことができなかったそうですよ!
まず、そば粉8に対して、小麦粉2を混ぜた粉に
卵と、サラダオイルを少し加え、混ぜます。

水を少しずつ加えながら、
耳たぶと同じぐらいの柔らかさになるまでこねていきます。

これが結構な重労働…。
ふっくらと弾力のある状態までこねあげたら、

今度はそれを少しずつ引いていきます。

手早く伸ばしていかなければ、「そばが風邪を引く」と呼ばれる
そば粉が乾いて、ひからびる状態になってしまうため、
休んでいる暇はありません。
切らずに均等な状態に伸ばしていくためには、
絶妙な力加減が求められるため、難しいんです。
1回目の引きは思いっきり失敗してしまい、
こね直す結果となりました。
2回目の引きでなんとかまとめ上げたそばを、
何層かに折り重ね、そば包丁で切っていきます。

薄く切らないと、きしめんのように太い麺になってしまうと言われましたが、
結果、出来上がったそばは…

この太さになってしまいました!
初めてにしては、そばの形に仕上がっただけよかったですが、
太さ、長さともに、お店で出てくるそばにはない形ですね。
ただ、そのコシは、今まで味わったことのないほどで、
美味しく頂けました。
そばの生産の背景を知ったうえで、自らの手で打ったそばのため、
美味しく感じたのかもしれません。
モノの背景を知ることは、
モノの価値を再認識することにつながりますね。
茨城の郷土料理
常陸大宮市でお世話になったお宅では、
茨城県のこの地方で食べられている郷土料理を
一緒に作らせていただきました。
「豆腐もち」(くるみもち)と呼ばれるもので、
お正月の三が日に、お雑煮の代わりに食べるのだそうです。
まず、くるみを割りやすくするため、温めます。

そのくるみを叩き割って、

中の実を取り出します。

ちなみにくるみは裏山で拾ったといいます。
くるみの実を軽く火で炙って、

自家製豆腐(市販の場合は木綿豆腐)と混ぜ合わせ、

砂糖適量と塩少々を加えてミキサーにかけ、くるみと豆腐のソースを作ります。

その間にお餅を焼いて、ソースを絡めれば完成です!

味は甘いスイーツそのもので、
くるみ風味のなめらかな豆腐ソースがとても美味しいのですが、
これをお雑煮代わりに食べるというのは、少し想像がつきにくい…かもしれません。
でも、ソースのベースが豆腐というヘルシーさがまたうれしいですよね。
また、「豆もち」と呼ばれる、あおのりとピーナッツの入ったおもちを
日常的に食べると聞いて、スーパーに行ってみると確かに置いてありました。

他にも茨城県は、そば粉の産地としても知られ、おそば屋さんも多く見かけます。
そばは痩せた土地でも育つため、
農業の盛んな茨城県では二毛作にうってつけなのだそう。
写真は「けんちんつけそば」と呼ばれる、郷土料理。

野菜や山菜がふんだんに入った、けんちん汁につけて食べるそばは、
農業大国の茨城県ならではの感じを受けました。
こうして見ていくと、食はまさにその地の特徴を表していますね。
皆さんの地域の独特な食べもの、食べ方など、情報をお待ちしています!
エビデンスのある野菜
茨城県取手市にある「シモタファーム」。


40年以上、ハーブを中心とした生野菜を生産している農家さんを訪れました。
「日本は先進国の中で、最も安全性に遅れている国です。
肥料と土づくりが遅れている」
そう語るのは、オーナーの霜田増雄さん。

霜田さんはもともと農家に生まれ、高校卒業後、農業の道に進みました。
その後、昭和41年にヨーロッパの有機農業とハーブを視察し、
それ以降、独自の栽培方法で野菜を育てています。
その方法とは、1つの作物を作る間に4回成分を調査するというもの。
まず、作物を植える前に畑の土の数値を測り、次に肥料を入れてまた測る。
今度はそうして出来上がった作物の数値を測り、
最後に作物を収穫した後の土を測るんだそう。
「すべてのデータを取っていれば、良いか悪いかが分かる。
悪ければ改善すればいいし、
数値を出さないと良いか悪いかが分からないからね」
と霜田さん。

実際にその味を試してみると、
これまで食べたことのある野菜とは全く違う、
口の中で野菜の存在感がバツグンに広がる味でした。
30年かけて土壌改良を続けてきた、霜田さんのデータ分析方法を用いれば、
どこの畑においても、美味しい野菜づくりができるそうです。
そして、霜田さんはこの技法をみんなに広めていきたいといいます。
「食べ物は、生きる権利がある人は誰でも食べるものだから、
みんながちゃんとした野菜を食べられないと意味がない」
この霜田さんの言葉を聞いて、特許は取っていないのか?
と、浅はかな質問をしてしまった自分が恥ずかしくなりました。
そんなシモタファームに行って、最初に感じたことは
「若い人が多いなぁ」ということです。
データ分析を担当している鈴木さんは、知人の紹介で霜田さんと知り合い、
農大卒業後、シモタファームに就職したそう。
他にも霜田さんの所には、若者たちが働きたい!と志願してくるというから、
農家=若手不足、後継者不足という、これまで思い込んでいた方程式が崩れました。
また、シモタファームでは、12年前からインドネシア国立大学の農学部の学生を
研修生として受け入れているそう。
彼らは単位を取るために住み込みで働いているのです。

1年間霜田さんのもとで学んだ学生たちは、インドネシアに戻り、
卒業後、農業の指導者や大学の教授になったりしているといいます。
霜田さんが生み出した栽培方法が、インドネシアでも実行されている
というから驚きですよね!
霜田さんが大切にしていることは、
「自分が作った野菜を食べた人が健康になること」
味はもちろんのこと、成分が数値によって立証されている野菜、
これこそが安心・安全、そして健康につながる野菜なのではないでしょうか。
雑穀ごはん
突然ですが、こちらの料理、中身は一体何でしょう?

一見、何の変哲もない揚げ物に見えます。

食べてみると、味は挽き肉の入ったコロッケと、白身魚の揚げ物です。
ただ、中身の正体はなんと...、

これらの雑穀だったのです!
コロッケに入っていた挽き肉と勘違いしたものが「うるちあわ」、
白身魚のフライと勘違いしたものが「ひえ」。
もちろん調理法によりますが、見た目も味も、言われなくては分からないほどでした。
こちらの料理を振る舞ってくださったのは、
Found MUJIの商品として無印良品の一部店舗に並ぶ、
「雑穀キッチン」シリーズの生産者、川口さんと林さん。

写真左の川口さんは、それまでの食生活を改善し、雑穀食を取り入れた結果、
なんと14kgの減量に成功したんだとか!
私たちも、翌日はデトックス効果抜群で、雑穀の効用を身をもって実感しました。
先程の「うるちあわ」は、白米の約6倍の鉄分を含み、
「ひえ」は、白米の約8倍の食物繊維を含んでいるなど、栄養価が豊富なのも雑穀の特徴。
米の量産にともない、消費も生産も廃れつつあった雑穀が、
最近になって、健康食品として見直されつつあるんです。
「休耕田を有効活用することもできるんですよ」
林さんは、自宅前の痩せた田んぼを、雑穀栽培のファームとして復活させ、
実際に農業を営んでいらっしゃいました。

「人間の歯は、穀物を噛む臼歯が20本、菜類を噛みきる門歯が8本、
肉を噛む犬歯4本なので、人類は本来、穀食動物なんですよね。
肉や魚は毎日食べる必要はないんです」
毎日、肉・魚をメインメニューに考えていた私たちにとっては、驚きの言葉でした。
「今から50年ほど前には、日本人の食卓では、あわ、きび、
ひえなどの雑穀が当たり前のように食べられていました。
栄養価の高い雑穀の食事に戻すことで、現代病の多くは改善できると思います」
そんな川口さん、林さんの生産する「雑穀キッチン」、「雑穀茶」及び「ぽんせん」は、
Found MUJIを扱う一部の店舗でお買い求めいただけます。

プレーン(30g・294円)、ごま(30g・315円)、青まぜのり(30g・315円)、
3アイテムを無印良品では販売しています。
最初の千葉県にして、食に対して深く考えさせられる滞在となりました。
食について考えるくらし
近年、「マクロビオティック」と呼ばれる食生活法が注目されています。
「玄米菜食」を基本にしたこの日本生まれの食生活は、
世界の著名人やスーパーモデルたちによって健康と美容のために注目され、
日本へ「マクロビオティック」という呼称で逆輸入され、広まりました。
そんなマクロビオティック料理が食べられる場所が、
千葉県いすみ市にあると聞き、行って参りました。

「Brown's Field」と呼ばれるその場所では、
雑穀やお米、オーガニック野菜などを生産し、
マクロビオティックの理念に基づき生活が営まれています。

金土日には、カフェもオープンし、その食を味わうこともできます。

見た目がとってもキレイなこのプレートは、肉や魚、乳製品を一切使っていませんが、
発酵食品や自然塩を使った味つけはしっかりとしたもので、お腹もいっぱいになりました。
また、砂糖未使用のガトーショコラなんていうのも絶品です。

こちらを営むマクロビオティック料理研究家の、中島デコさんにお話を伺いました。

もともと東京ご出身のデコさんですが、5人の子供をオーガニック食品で育てるには、
東京は物価が高すぎると考えたそうです。
何も、このまま東京にいる必要はない。
そして、自給自足可能な移住先を探すなか、千葉県のいすみ市に辿り着いたのだそう。
東京の都心から越してきたデコさんに不便がないか尋ねてみました。
「不便を感じることは何もないですよ。友達みんなが嫌っていうほど遊びに来てくれるし、
ここには都会になかった、降るような星や、鳥の鳴き声があるから」

また、こうも話してくれました。
「田舎に住むには、広い意味でのコミュニティが大事。
全部自分たちでやるのではなく、みんなでやればできる。
昔は近所の人と、お醤油の貸し借りをしたりして、ある種共同生活をしていたようなものが、
今の時代では、お隣さんの顔も知らない。
だけど実際、各家庭だけで生きていくのは難しいですよね」
希薄なご近所付き合いの都会で生活していた私たちにとっては、
ハッとさせられる言葉です。
「でもまずは、健康な体と、人に使われることなく、
自分主体で周りとつながり合って生きていく術を身に付けることが大事かな」
今回、中島デコさんのお話を伺ってみて、すべてはつながっているのだなと感じました。
デコさんが今のくらしを実現させているのは、「マクロビオティック」と出会い、
自分の食生活を見直すところから始まったのです。
食のことを考えると、体が変わる。
体が変わると、精神が変わる。
精神が変わると、いずれ行き着く先が変わる。
自ら描いたくらしを実現させている彼女の言葉は、説得力がありました。
しょうゆの里、銚子
私たちが昔から慣れ親しんでいる和の味、しょうゆ。

そのしょうゆの生産量1位を誇るのが千葉県です。
なかでも、暖流(黒潮)と寒流(親潮)が沖でぶつかり合う銚子は、
海洋性の気候風土で湿度が高く、夏涼しく、冬暖かいため、
しょうゆ醸造のための麹菌などが活動するうえで最適な気候なようです。
さらに、利根川、江戸川で江戸とも結ばれて、水運にも恵まれていたことが、
銚子が江戸時代からしょうゆの町として栄えた訳なんだそう。
実際、銚子の町を歩くと、どこからともなくしょうゆの芳ばしい香りが漂ってきます。
至る所にしょうゆメーカーの看板も。

この「ヤマサ醤油」と「ヒゲタ醤油」は
銚子の町でも代表的な二大しょうゆメーカー。
まるで銚子の街を二分するかのように、
東に「ヤマサ醤油」の工場、

西に「ヒゲタ醤油」の工場が存在しているんです。

ヤマサを使うか、ヒゲタを使うかは、各家庭によって違うようですが、
おもしろかったのが、町中の飲食店や宿には両社のしょうゆが置かれていること。
両社に繁栄してもらいたいという、町の人の心配りが感じられます。
皆さんの家では、どのしょうゆを使っていらっしゃいますか?
思えば、毎日のように口にするしょうゆは、
関東では濃口しょうゆ、関西では薄口しょうゆと、地域や家庭によっても違うもの。
その差は、原料の大豆、小麦、食塩に何を使うかはもちろんのこと、
各社が昔から引き継いできている麹菌や、
発酵・熟成する期間や醸造法で変わってくるんだそうです。
右は1年熟成させ搾り、加熱していないもの。左はそれを加熱したもの。

見た目ではさほど違いを見ることはできませんが、
味は、加熱前のものはあっさりした印象で、
加熱後のものにはコクが加わった印象でした。
同じようで違うもの、しょうゆ。
普段から口にするものゆえに、こだわっていきたいものですね。
千葉のご当地料理って?
旅先での楽しみといって、外せないのが「食」!
日本各地には、その土地ならではの郷土料理が存在しています。
まず、代表的な千葉の食材が落花生。
全国生産量の約7割を千葉県で生産しているそうです。

そんな千葉県民のごはんのお供が「みそピー」こと、ピーナッツ味噌。

千葉県民いわく、給食にも出たこのみそピーは、
もともと落花生農家の人たちが、商品にならない規格外の落花生を食べるために、
炒った落花生に味噌と砂糖をからめて作ったのが始まりなんだとか。
続いて、しょうゆ。
そんなしょうゆメーカーが集まる銚子市で人気なのが、「ぬれせんべい」です。

しょうゆがしみ込んだ、しっとりとした歯ざわりのおせんべいですが、
その始まりは失敗作だったそうです。
いつもよりしょうゆのタレがしみ込んでしまい、売り物にならないので、
おまけとしてお客様に配るとこれが「おいしい!」と大好評で商品化されたといいます。
ぬれせんべいをそうと知らずに食べると、一見湿気っているようにも感じてしまい、
千葉県に嫁いできたお嫁さんの実家にぬれせんべいを送った際に
「せっかく頂いたのですが...」と連絡があったという笑い話を聞きました。
また、銚子市にあるヤマサ醤油の工場で食べられるのが「しょうゆソフト」!

食べるまでその味が想像できませんでしたが、蜜のような味で美味しかったですよ♪
それから、ご当地の食事情を知るのにとっておきの場所、それはスーパー。
房総半島南部でおなじみのスーパーODOYAへ行ってきました。
店内をぐるっと見回して、驚いたのがコレ。

え? くじら??
そうなんです、千葉県南部の安房地方ではつち鯨の赤身肉を食べるのだそう。
試しに「くじらのたれ」を買ってみました。

これは、くじらのお肉をタレに漬込んで、天日で干したもの。
お味はというと・・・血抜きをしていないだけあって、少し臭みのある味でした。
また、こちらも初めて見ました。

通常、伊達巻といったら、おせち料理の一品を思い浮かべますが、
千葉県でいう伊達巻とは「伊達巻寿司」を指すようです。
そして、今回は千葉県の代表的な郷土料理のひとつである
「太巻き祭り寿司」作りに密着してみました!
「太巻き祭り寿司」は古くから冠婚葬祭などのご馳走として食べられるもので、
切り口が金太郎飴のように絵柄を楽しめる、おもてなし料理でもあるそうです。

まずは卵を焼いておきます。
続いて、絵柄である花びらの素材を準備します。

縦に1/4に切った海苔でピンクの酢飯を巻いていきます。
花びらの数だけ、5本用意します。
次に、準備しておいた卵焼きの上に白い酢飯を平らにのせます。

さらに、その上に絵柄になる素材(先ほど準備した花びら、かんぴょう、菜っ葉)
を並べていきます。


かんぴょうや菜っ葉を並べる際、周りの酢飯を盛り上げ、壁を作っておくのがコツのよう。
また、5本の花びらの中心にはお新香を入れておきます。


最後はこれを巻き込んで、切ったら出来上がり♪

この季節にピッタリの、さくら柄の太巻き祭り寿司ができました!
世界的にも人気のお寿司とあって、
こんなに見た目も美しければ、海外でも受けること間違いなしです。
その土地の文化や風土を表す食。
同じ日本でも各地で違いがありそうです。
皆さんの地域では、どんな郷土料理がありますか?