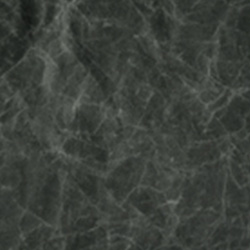「ものづくり」カテゴリーの記事一覧
マスキングテープの舞台裏
生活のあらゆるシーンで活躍してくれる、マスキングテープ。

シンプルな文具や雑貨、ギフト用ラッピングなど、使い方次第で
彩り豊かなオリジナルのグッズを生み出すことができます。
今では文具店や雑貨店、書店など、
私たちの身近なお店でも手に入るようになりましたが、
その仕掛け役が、岡山県倉敷市にある、一軒の工業用テープの専門メーカーでした。
カモ井加工紙株式会社は、1923年にハイトリ紙の製造からスタート
(岡山ではハエのことをハイというそう)。
その後、時代の流れに合わせて、粘着技術を生かした
養生(ようじょう)テープ(=マスキングテープ)の製造も手掛けるようになります。
養生(マスキング)には、"包み隠す""覆い隠す"などの意味があり、
養生テープとは塗装などの際に、作業部分以外を汚さないために貼る、
保護用の粘着テープのこと。
それまで工業用のテープとして販売してきた
カモ井加工紙のマスキングテープでしたが、
ひょんなことから、現在の雑貨としての地位も築くことになります。
「当社のマスキングテープ『mt』のはじまりは、2006年に届いた1通のメールだったんです」
とは、専務取締役の谷口幸生さん。

メールは、マスキングテープの熱烈なファンだという東京の3人の女性からで、
マスキングテープが作られている工場を取材したい、という内容だったそう。
初めての消費者からの要望に社内で対応に困っていると、
同じ女性たちから、今度は1冊の手づくりの本が送られてきました。
「他のメーカーのものとも比較しながら色の話や文字の書きやすさ、
自分たちのマスキングテープの使用例など、
徹底的にユーザー視点で研究がされていました。
これはただ者じゃないなと思って、お会いしたくなりましたね」
こうして彼女たちの工場取材は実現し、
「柄ものを作ってほしい」という要望を残して帰りました。
しかし、それまで工業用テープを大量ロットで生産してきたカモ井加工紙が、
すぐに雑貨用のマスキングテープを作るには至らなかったといいます。
「当時、工業用テープの売り上げが順調ななか、
多品種少量生産の雑貨用テープを手掛けることに対して、
社内の理解を得るのが大変でした」
mtの立ち上げに最初から関わってきた、
広報・企画担当の高塚新さんは、そう当時を振り返ります。

「テープの技術には絶対的な自信がありましたけど、
雑貨用になると、パッケージや販路など、ノウハウが全くありませんでしたから」
それでも工場見学の際に女性たちが興奮していた様子が忘れられず、
数ヵ月後に連絡を取り、2年という年月を経て
2008年3月にマスキングテープ「mt」を発売しました。

発売から6年、生み出されたmtの柄は1000を超え、
日本のみならず、フランス、台湾、オーストラリアほか、世界中で愛されています。
そんなmtの魅力は、選ぶ楽しみのあるデザインはもちろん、
「手で簡単に切れる」「貼って剥がせて繰り返し使える」「文字が書ける」など、
多様な機能性にもあります。
そして、そこには日本の和紙の性質が関係していました。

「最初から狙って使ってきたわけではないと思うんですが、
和紙は繊維を長くすいているから、薄くてしなやかな強度があります。
ただ、和紙は湿気などの気候の違いで、すぐに伸び縮みするため、
毎日カットする機械の幅をミリ単位で調整する必要があるんです」
と、作る難しさを製造課の古江係長が教えてくださいました。
今回工場を見学させてもらって目についたのが、
工場内の様々な場面でmtが活用されていたこと。
実は、カモ井加工紙では定期的にファクトリーツアーを開催しており、
一般ユーザーが生産現場を見学することができます。
工場内での機材やロッカーにデコレーションされているmtを見て、
使用の想像の幅が広がることもそうですが、
ファクトリーツアーの効果を谷口専務は次のように語ります。
「黙々とものづくりをしていた現場に、ある日突然ユーザーが来る。
すると直接、ユーザーの反応や声を聞くことができるんです。
ただ作るのではなく、ユーザーの気持ちを知りながらものづくりをしていきたいですね」
また、カモ井加工紙は積極的に
国内外で展示会やワークショップなどのイベントを行い、
ユーザーにmtを体感してもらう場も提供しています。
「私たちは従来、工業用製品のメーカーなので、使う用途を決めたがる傾向があります。
ただ、mtについては用途を決めなかったことがよかったんでしょうね。
お客様からの要望でその幅がどんどん広がっています」
高塚さんがそう話すように、mtは自転車や窓、
さらには車のデコレーションにまで、その装飾の対象はとどまることを知りません。

和紙でできているというと、水には弱いイメージがありますが、
特殊な和紙を使用しているため、
mtは貼った後に水に濡れても問題ないんだとか。
最近では、水を抜いた噴水にmtでデコレーションをしてから水を戻した、
mt噴水なるものも登場したといいます。
自分たちの"粘着技術"という得意分野を生かして、
雑貨用のマスキングテープという新たな市場を作り出した、カモ井加工紙。
その裏に一般ユーザーの声があり、
そこに真摯に向き合いながら歩んできた結果が、
今の世界中から愛される商品「mt」につながっているのだと知りました。
未来へ向かう、大槌復興刺し子プロジェクト
毎週、火曜日と水曜日になると、
岩手県大槌町(おおつちちょう)のとある民家に女性たちが集まってきます。
「刺し子会」と呼ばれるその日、
女性たちは自身が手掛けた刺し子の商品を持ち込みます。

刺し子とは、手芸の一種で、布地に糸で模様を刺繍して縫いこむこと。
震災後の避難所では、女性たちの仕事があまりなく、
やることがない状況でした。
そんななか、東京から来ていたボランティアが主となり、
「針と糸さえあればできる刺し子をやろう」と、
2011年6月から刺し子の制作がスタート。
「大槌復興刺し子プロジェクト」と名付けられたこの活動は、
現在も継続しており、これまでに累計180名、
20~80代の刺し子(作り手)さんが関わってきました。
2012年からプロジェクトに参加している金崎美枝子さんは、
もともと洋裁学校出身。
「刺し子自体は初めてだったけど、自分の服や子どもの服は
昔から自分で作っているんですよ。
刺し子は細かい部分が難しいけど、おかげさまで助かっています」
と話してくれました。

毎週恒例となった刺し子会は、刺し子さんたちの交流の場でもあり、
放課後にスタッフのお手伝いをしてくれている、刺し子さんのお子さんの姿も。

なんと勉強よりも刺し子のお手伝いの方が楽しい、とか!
女性たちが手掛けた大槌刺し子は、
ネットショップやイベントなどで実際に販売され、
女性たちの生活再建の促進に一役買っています。
そんな大槌刺し子をよく見てみると、
その多くに「かもめ」がデザインされていることに気付きます。
かもめは大槌町の鳥で、日常のくらしに取り入れやすいようにと、
一般的な刺し子に多い伝統柄だけでなく、少しポップなデザインに仕上げているそう。
また、限られた人だけでなく、より多くの刺し子さんに関わってもらいたいという想いと、
幅広い層の人に手に取ってもらいやすいように、
価格を抑える意味でも、刺し子の分量を調整しているといいます。
現在、プロジェクトの運営は、NPO法人テラ・ルネッサンスが行っていますが、
運営スタッフには、元刺し子の女性たちもいます。
「外の人が大槌に来て仕事を作ってくれているのに、
地元の私たちがやらないわけにはいかないですよね。
刺し子作業のほかに、アイロンがけだけでも手伝えたらって、手を挙げました」
1年前からスタッフとして働く佐々木加奈子さんは、そう話します。

この仕事をするようになって、
パソコン作業を初めて学んだという加奈子さんですが、
今では在庫管理を任されるなど、大活躍の様子。
また、別のスタッフも刺し子をしながら胸の内を語ってくれました。
「中学生の時にミシン針を指に貫通させたことがあって、
それ以来、トラウマで裁縫はやってこなかったんです。
今は自分なりにうまくいったと思えた時が満足。
この機会がなかったら、刺し子の面白さも知らないままでしたよ」
高校卒業後、北上市に出て製造業で働いていた佐々木静江さんは、
震災を機に出身地の大槌町に戻ってきたそう。
居酒屋で働いており、子どもたちとコミュニケーションが取れないことから
昼間の仕事を探していた時に、刺し子の仕事と出会いました。
「工場でも居酒屋でも言われたことをやるだけの仕事でした。
今は自分で考えて仕事をしていて、
仕事のやりがいってこういうことなんだなって、初めて感じています。
年配の方とも話をする機会ができて、
娘のように接してもらえることがうれしいですね」
このように地元の女性たちに根付いてきている、大槌刺し子の仕事。

プロジェクトマネージャーの内野恵美さんは、
今後について次のように語ります。
「今後は復興支援としてではなく、モノの良さで買ってもらえるように、
素材にもこだわり、もっと岩手らしいプロダクトにしていきたいです。
刺し子の可能性は布以外にも展開できて幅広いはず。
まずは、"大槌=刺し子のある町"というブランディングをしていきたいですね」

実は、大槌復興刺し子プロジェクトでは、
無印良品とも共同で商品づくりをしました。
無印の店舗に並んだことで、刺し子さんには、
離れた場所にいる子どもや孫たちから連絡があるなど、反響があったといいます。
女性たちの笑い声と穏やかな時間が流れる刺し子会を後に、
帰り際、内野さんに大槌町の中心地が一望できる場所に
連れていってもらいました。

ふと空を見上げると、太陽に向かって飛んでいく一羽のかもめ。

なんだか大槌町の刺し子プロジェクトを応援しているかのようでした。
南部裂織
「バブルの頃は恥ずかしいものだったんですよ。
貧しい現金収入のない人が古布を裂いて織っていたものなので」
ここ数年、エコの観点からも世間で再び注目されている
「裂織(さきおり)」についてそう語るのは、
青森県十和田市にある南部裂織保存会の事務局長、小林輝子さんです。

裂織とは布を裂いて緯糸にして織った、織物のこと。
布を大切にする女性の知恵から生まれたもので、
そうした織りは全国および海外でも見ることができます。

寒冷な気候のため、綿を栽培できなかった雪国青森では、
麻布がメインで、冬にはそれを重ねて刺し子をして防寒していました。
明治26年鉄道の開通以降に綿が入ってくると、
経糸に木綿糸、緯糸に古布を使い、こたつ掛けや帯を織ったといいます。
「南部には赤い裂織が多かったのですが、
それは暗い家に少しでも明るい光を、という母親の家族に対する愛情の表れでした」
また、こたつ掛けの縁も赤色で作られることが多かったそうですが、
それは昔炭を使ったこたつだったため、
火事にならないように、という"おまじない"の要素も含まれていたとか。
さて、南部裂織保存会の話に戻りますが、保存会は1975年に、
故・菅野暎子さんによって発足されました。

菅野さんは1971年、叔母の形見分けの中にあった裂織の帯に出逢い、
それが地元で織られたものだと知ります。
そして、そこから消滅しかけていた裂織のルーツと、
技を教えてもらえる師を求めて訪ね歩きました。
1年かけてようやく織り手に出会った菅野さんですが、
最初は「お金にならないからやめておきなさい」と拒まれたそう。
昭和初期頃までは各家庭で織られていた裂織でしたが、
その頃、地元の人に裂織は"ボロ織"と呼ばれ、
周りからは見向きもされていなかったのです。

それでも菅野さんは東京の手織り教室に通い、惚れ込んだ裂織の技術を研き、
南部裂織保存会を設立して、自宅で裂織教室を開くなど
裂織の普及に心血を注ぎました。
2002年には、より多くの方に南部裂織を体験してもらえるように、
道の駅の隣に「南部裂織の里」をオープン。
現在、高い天井の梁の見える広々とした工房内には、
過去30年以上にわたって、農家の納屋や古い民家などから
菅野さんが集めた地機(じばた)が70台も並んでいます。

ちょうど教室に来ていた生徒さんの織りを拝見させていただくと、
なかなか一筋縄ではいかない様子。
地機では、「腰当て」という布を文字通り腰に当てて、座って織るのですが、
自分自身が機の一部になって、手だけでなく足も使っていくのです。
「無心で織って、キレイなものが出来上がる。
ここは女性たちの和みの場でもあるんです。
芸術家を養成するのではなく、あくまで裂織を伝え、つなげていく場所です」
小林さんはそう話し、保存会の合言葉をご紹介くださいました。
『暮らしに創る喜びを 手仕事の温もりをいつまでも』
「裂織は京都の友禅のように雅な文化ではないけれど、
とっても華やかですよね。
十和田は自然が豊かで、色彩溢れる環境です。
私自身、知らないうちに"美"に対する意識が育てられたと思っています」
その日、たまたま工房を訪れていた小林さんの娘である、
小林ベイカー央子(ようこ)さんにも話を聞くことができました。

央子さんは、仕事の傍ら「裂織3Gプロジェクト」を運営。
裂織にアートなスパイスを効かせ、
新しいプロダクトを生み出すというプロジェクトです。
3Gは3つのジェネレーションのことを表し、
十和田で活動する南部裂織保存会(60代)と、
プロのデザイナーやクリエイターからなる姉部(40代)、
そして、美大生を中心とする妹部(20代)で構成されています。
そんな裂織3Gプロジェクトからは、
普段づかいがしやすいバッグやネックストラップなどの
プロダクトが開発されていました。
「叔母の家に行くと、ボロ布がたくさん置いてあったのを覚えています」
実は、央子さんの母である、事務局長の小林さんは
保存会の創設者である、菅野さんのお姉さんだったのです。
「妹の菅野暎子は子どもたちに裂織の素晴しさについて伝えていきたい、
という想いで活動していました。
今では市内の中学生はほとんど、裂織を体験しに
ここに来ているのではないでしょうか」

活動当初は、反対していたという小林さんですが、
後に保存会の事務仕事を手伝うようになり、
今では妹の菅野さんの遺志をしっかりと継いで活動されていました。
古くなった布を一度裂いて、それを新たに織って作り上げる裂織は、
個性豊かですべてが一点物。

美しく温もりのあるこの織物が、
かつて"ボロ織"と呼ばれていたとは信じ難いほどです。
ものがなかった時代に、
古の女性たちの、ものを大切に使い続ける創意工夫から生まれた裂織には、
時代が変わった現代でも、
女性たちの想いがたくさん詰まっているように感じました。
浄法寺の漆掻き
「仕事場は山奥なんで、車体の高い車でいらしてください」
事前にそう言われていた意味を、
現地に着いて、ようやく理解するに至った私たち。
漆掻き職人、猪狩史幸(いがりまさゆき)さんの走らせる軽トラは、
ぐんぐんと未舗装の山道を奥へと入っていきます。
普通の軽自動車で来たことを後悔するも、時すでに遅し。
なんとかたどり着いた先は、人里離れた山林でした。

ここは岩手県二戸市、浄法寺(じょうぼうじ)町。
国産漆の約8割を生産する一大産地です。
「静かでしょ。漆掻きの職場は孤独なんですよ(笑)」
そう話す猪狩さんの周りには、
まるで何かの模様のように傷付けられた木々の姿がありました。
これが猪狩さんの仕事相手、漆の木です。
「木を慣らすために、初めは傷口を小さく、だんだんと広げていくんです」

そう言いながら、おもむろに仕事を始められた猪狩さんは、
次から次へと漆の木に向かい合い、傷を付け始めました。
毎年、6月上旬から始まる漆掻きの仕事。
訪れた7月上旬は、5本目の傷を付ける頃でした。
「一気に深くて長い傷を入れても、漆は採れますが、
木の寿命が縮まってしまう。
木と長く付き合っていくための先人からの知恵ですね」
ほどなくして、傷口からにじみ出てきたミルクのような液体。

これこそが漆器などに塗られる漆の正体でした。
これは木が傷口を守るために出すもので、
触れたり、近づいたりするだけで肌がかぶれることも。
こうした性質から、古の人たちは、
漆には邪悪なものを寄せ付けない力があると考えていたそうです。
この涙ほどの液体を、猪狩さんは余すことなくヘラでかき集めていきます。

1本の漆の木から採れる量は年間約200ml、わずか牛乳ビン1本分ほど。
一つの椀に塗られるのが30mlほどですから、
一滴一滴が貴重で、かけがえのない木からの贈り物です。

「中国では、木に漆の樹液が溜まるような仕掛けをするようで、
それだと雨など、不純物も混じってしまう可能性があります。
日本の作業は、きめ細かくて地道ですよね」
もともと、サラリーマンという経歴を持つ猪狩さんは、
いつからか漆器の魅力の虜となり、初めは輪島で漆塗りの勉強に。
そんななか、自らが塗っている漆を掻くための職人が、ほとんど高齢ということを耳にし、
6年前、浄法寺の漆掻きの道に飛び込みました。
漆の生息に適した山間地の浄法寺には、他に目立った産業がなかったことから、
漆掻き職人が多く残っていたそうです。

「ただ、塗る側としては、日本産の漆は野性的で扱いにくいんですよ」
と、猪狩さん。
それでも、"素性の見える漆"を掻き続けたいというのは、
長い歴史のなかで必要とされてきたものだから、という確信からでした。
古くから汁椀や塗り箸など、和食器に用いられてきた漆。
函館で約9000年前の漆塗りの副葬品が出土するなど、
日本人と漆の歴史は古く、密接なものでした。
漆は、吸水性がある木地の器を、長く使い続けるために、
必然的に用いられるようになったと考えられています。
また、江戸時代、接着力のある漆は、
割れてしまった陶磁器の修復にも用いられるようになりました。
金継ぎとよばれる金粉をまぶす手法で、割れ物に美を見いだし、
わびさびとして楽しんでいたことも興味深い話です。

しかし、明治期以降、中国産の漆の流入や、
ウレタン樹脂などの代用品が増えると、国産漆の需要は激減。
日光東照宮や京都金閣寺など、文化財修復時の特需によって、
浄法寺漆は需要をつないできたといいます。
最後に、自ら掻いた漆で、塗りまでを仕上げた
猪狩さんの器を見せていただきました。

漆器は完成するまでの工程が多いことで知られていますが、
漆掻きという木と漆の狭間を行き来するような職業をしている猪狩さんらしく、
赤や黒の顔料を加えずに、採取した漆そのままを5回塗り重ねて器が作られています。
「漆器は技の方ばかり追求されていきましたが、
漆そのものについて追求していくことも大切ではないでしょうか」
その奥深い輝きには、しばらく目を奪われるほどでした。
「なくなるべき産業なら、なくなればいい。
ただ、漆は奥深いもの。その深さを知ってしまった今、
それを後世につないでいくのも僕の使命だと思っています」

漆の効能を知り、その力を最大限生かした日本人。
「漆」という漢字のなかに、木と水と人という文字が隠されていることも、
人と漆の関わりを象徴しているかのようです。
猪狩さんのような漆の伝道師がいる限り、
その文化が引き継がれていくことを確信しています。
[関連サイト]猪狩さんのHP「漆掻き 猪狩」![]()
EAST LOOP
胸元を飾る、ハート型のブローチ。

これは東日本大震災後にいち早く始まった、
「EAST LOOP」と呼ばれる、ものづくりのプロジェクトで作られたものです。
2つのハートが重なったこのブローチは、
作り手と使い手がハートでつながっていたい、
というイメージから作られました。
「私自身が阪神淡路大震災で被災しています。
それもあって、東日本大震災後はフラッシュバックで
しばらくまいってしまっていました。
ただ、自分にできることを考えた時に、それはものづくりによる支援だと思って」
EAST LOOPプロジェクトを立ち上げた、株式会社福市の代表取締役、
高津玉枝さんは、そう当時を振り返ります。

「世の中で光の当たっていない素敵なものを紹介していきたい」と、
雑貨を中心とした売り場のプロデュースやPRなどを手掛けていた高津さんは、
90年代後半に"フェアトレード"の概念に出会います。
フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を
適正価格で継続的に購入することで、
生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易の仕組み」のこと。
その頃、フェアトレードの商品は、
その分野に興味がある人だけがターゲットでした。
高津さんは、そうではなく、全くフェアトレードを知らない人に届けようと、
大手百貨店や雑貨店に売り場を展開。
2006年に福市を設立し、
2008年から本格的にフェアトレード商品の取り扱いをしています。
「現地にもともとあったものを日本人向けにアレンジすることが仕事です。
現地に負荷をかけすぎず、ブーム性を作らないで
細く長く展開できるように努力しています」
そう話す高津さんが震災後に思い出したのが、
ネパールのタルー族に言われた、
「自分たちで生きていきたい」という言葉でした。
「それは震災で被災した人も同じで、生きている意味を感じるためには、
施しを受けているだけではダメなんです」
高津さんは震災から1ヵ月後の4月中旬に現地入りし、
東北の人と初めて接点を持ちました。

しかし、その時期には、高津さんの構想は時期尚早であり、
「君は被災者に仕事をさせる気か」と言われてしまったそう。
それでも、自身の経験から
「被災者にも何かすることがないと、
すべてがネガティブな方向へいってしまう…」
と高津さんは危惧し、翌5月に再訪。
岩手県遠野市のNPO法人「遠野山・里・暮らしネットワーク」が
現地パートナーとなり、
あとは何を作るかが議論の観点となりました。
そこで高津さんが考案したのが、
「1人で完成できるもの」「作り手のペースで作れるもの」「高く売れるもの」
の3点を軸に据えた、ニット製のブローチでした。

「これなら、糸とかぎ針だけあれば、場所を選ばずにどこでも作れます。
失敗したらほどいてやり直せるのも、
作り手に負担がかからずによかったことですね」
沿岸部の女性を中心に、
最初は20人ほどの作り手からスタートしたプロジェクトも、
これまでに約200人が参加。
出来上がったブローチの裏には、作り手の名前が刻まれていて、
商品代金の50%が生産者グループの収入になります。
作り手の女性からは「生きる力になった」「このお金で美容院に行ける」
などの声が多数上がってきたといいます。

また、「可哀想だからではなく、かわいいから手に取ってもらいたい」
とこだわって作ったブローチなどは、これまでに7万個以上がお嫁に行きました。
「消費者のマインドを少しだけ動かせたかなと思っています。
買い物が自分のためだけでなく、
必ずその裏に作り手さんがいることを知るキッカケになったらうれしいです」
と高津さん。
と同時に、以下のようにも話し、
すでに次なる展開に行動を移していました。
「チャリティーグッズはどんなに頑張っても10年後には売れません。
また、東北に行った際に、震災以外でも仕事がなくて困っている現状を目にして、
東北発の新しい手づくりブランドを作らなきゃと思って」
2013年9月には、「被災地の支援」から「被災地の自立」へとステージアップを目指し、
遠野山・里・暮らしネットワークを中心とした生産者グループに、
これまで福市が担ってきた役割の多くを移管。
また、今年の7月1日より、新たに設立した
合同会社東北クロッシェ村に事業移管し、
ここで新たに活動をすることにしていました。
ちなみに、東北クロッシェ村は、
編み物を得意とする女性たちがその技術を活かして、
企業のOEMなどマーケットニーズに合わせた製品を手掛ける会社です。
「遠野ではジンギスカンが名物なのを知っていますか?
それは、昔から『ホームスパン』が盛んで、羊がいたから。
そんな遠野に"ニットミュージアム"を作るのが私の新たな夢なんです。
ミュージアムができれば海外からも人を呼べるし、
人々がそこへ足を運ぶキッカケになる」

東日本大震災を機に始まった、EAST LOOPプロジェクトでは、
形を変えながらも、東北の地に根ざしたものづくりが継続されていました。
OCICA
三陸海岸の最南端に位置する、宮城県石巻市・牡鹿半島(おしかはんとう)。

リアス式海岸に囲まれた半島全域が山地で、
その名の通り、鹿が多く生息しています。
「神聖な動物として崇められている金華山の鹿が、
泳いで牡鹿半島に渡ってきたといわれているのよ」

牡鹿半島の西岸、牧浜に住む阿部たい子さんが、
包み込むような笑顔で、私たちを迎えてくれました。
「牡の鹿にだけ生える角は、1年に1回生え変わるの。
そんな鹿の角は、昔から水難・海難のお守りだったんです」
阿部さんはそう話しながら、
輪切りにされた鹿の角を、入念に磨き始めました。
阿部さんが作っているのは、
「OCICA」と呼ばれるアクセサリー。

鹿の角をドリームキャッチャーに見立て、
良い夢を運んでくれるよう、復興への祈りが込められています。
「牡鹿半島」という名前を象徴するようなモノづくりが始まったのは、
2011年の東日本大震災がきっかけでした。
太平洋に面した東岸の、ホタテやホヤ漁などに対して、
石巻湾に面した西岸は、昔からカキの養殖業が盛んな地域。

しかし、震災の影響で漁はストップ。
養殖施設も加工施設も津波で壊滅し、再建の目処も立たないなか、
行く末が見えず、途方に暮れていた人も少なくなかったといいます。
そんな折、漁を支えてきた働き者のお母さんたちに、
少しでも仕事を創出したいという想いから立ち上がったのが、
「OCICAプロジェクト」でした。
ここにしかないモノを用いて、お母さんたちが手掛けられるもの、
ということで、最初に作ったのは「鹿の角のストラップ」。

「ただ、初めはどうしても"手作り品"の域から抜け出せなかった」
と、OCICAをプロデュースする一般社団法人つむぎやの
現地コーディネーター斉藤里菜さんは、当時を振り返ります。

「復興のためのモノづくりではなく、
本当に市場で受け入れられるものなのかが大切だと思っています。
そのためにイベント等で展示販売して、お客さんの反応を見ていきました」
そんななか出会ったのが、横浜のデザイン事務所「NOSIGNER」。
社会的意義を踏まえたデザイン活動を続ける彼らによって、
鹿の角に、細くて丈夫な漁網の補修糸を用いたアクセサリーが考案されたのです。

鹿角と漁網は、牡鹿半島では身近な素材。
できるだけシンプルな制作工程も、年齢幅の広い浜の女性たちに配慮されたものでした。

こうして生み出されたOCICAは、
1年間で2000個以上も販売されるほどの人気商品に。

漁網とは思えない鮮やかなカラーが、
耳元や胸元を華やかに彩ります。

最初からこのプロジェクトに参加していた阿部さんは、
「身近にある素材で素敵なものができてとてもうれしい」
と話します。

「糸ノコなんかも初めはうまくできなくてね。最初の頃できなかったことも、
だんだんとできるようになっていくのが楽しいです」
こうして牧浜のお母さんたち一人ひとりが、
使い手に「幸せになってほしい」と想いを込めながら、
作り上げられていくOCICA。

商品は一つひとつ、作り手さんの屋号の印が押され、
売れた分の一部がお母さんたちの収入に直接つながっています。

これも、カキ養殖の時に浮き輪に屋号を付けることから、
活かされた知恵でした。
「これを主な生業として暮らすのを目指しているのではなく、
公民館に集まってのOCICAの作業日の後、決まって催される、
お茶っこ(お茶会)が楽しいから続けてるのよね」
と話す阿部さん。
実際に、隣の浜の人とも仲良くなって、
道で会ったら挨拶したり、お茶を飲むようにもなったそうです。
OCICAは単なるモノづくりのみならず、
コミュニティを再興することにもつながっていました。
「多いときには12~13人ほどいた作り手さんも、
カキ養殖が再開した今は、4~5人になりました。
これも復興している証だから、寂しくはありませんよ」

震災前、カキ養殖が主要産業だった土地に、
地元の資源を使った新たな生業を生み出したOCICAプロジェクト。
震災というきっかけですが、
他の土地においても参考になる事例が、
東北では次々と生まれているように感じました。
石巻工房
「電気もガスも水道も止まって、何もなくなったとき、
生き延びていくために、どのように行動しますか?」
そう問いかけるのは、石巻工房の千葉隆博(ちばたかひろ)工房長です。

「ある居酒屋は、店主自らが店を直して、いち早く営業を再開していたんです。
結局、DIYできた人が一番、復興が早かったんですよね」
東日本大震災によって、未曽有の被害を受けた石巻市。

石巻工房は、そんな石巻市の商店街で、
東京のデザイナーを中心とした有志から提供された補修道具や木材を基に、
復旧・復興のための誰もが自由に使える公共的な施設としてスタートしました。

「当時、"待ち得"って言葉がありましてね。
待っていれば色々もらえるので、被災者は待ちの姿勢になっていたんです。
ただ、そうなると人間ダメになっていくんですよ」
そう当時の様子を振り返りながら、
いつまでも支援に頼りきりの状況に、危惧を覚えていたと話す千葉さん。
そんななか、当初から支援に入ってくれていたアメリカの家具メーカー、
ハーマン・ミラー社による支援の姿勢に、ヒントを得たといいます。
「魚を与えるんじゃなく、釣り方を教える」
その姿勢こそが自立を促す、と考えた石巻工房では、
当時、外でビールケースに座って話していた仮設住宅で、
ベンチづくりのワークショップを催します。
材は、レッドシダー協会より提供してもらった、カナダ産のレッドシダー材。
よくウッドデッキなどに用いられる木材です。

「レッドシダーは、耐久性が高く腐りにくい。
被災直後の現場では、外で使うケースが多く、
必然的に強度と耐久性のある材が求められたんです」
こうして、地元の人たちと需要や技法を検証しながら
生み出された数々の製品。
これらが、現在の石巻工房の製品のベースとなりました。
コンセプトは「スモール・アウトドア」、
シンプルで簡単ながら、頑丈で機能的なデザインです。
「外でも使い倒せる家具は、意外とありそうでなかった」
と千葉さんが話すように、
石巻工房の家具はコンパクトで、簡単に運べるように軽い。
仮設住宅では、自分たちで作ったベンチに座りながら、
街の未来を思い思いに語り合ったそうです。
また、「"考えるスキを残しておくモノづくり"も大切」と
千葉さんは語ります。
「すぐ使えるものばかりだと、ユーザーは何も考えなくなってしまう。
石巻に自衛隊が到着したのは震災から4日後でした。
自ら考えて行動しないと、サバイバルできないんです」
石巻工房で用いている木材が無垢なのも、
自分で塗装するもよし、傷ついたら削るもよしという意味からでした。

石巻工房のロゴマークが、途中で囲いが切れているのも、
そんな想いを象徴しているかのようです。
「これまで石巻は他の地方都市同様に、閉塞感に包まれた場所だったんです。
これからの石巻は開かれた場所でありたい。
そんなメッセージも込め、右上の枠に穴を開けています」
実際、石巻工房には、県内外からの雇用を受け入れ、
常時5人のスタッフが働いています。
最近、引っ越したばかりという工房は、以前の5倍の広さになり、
今後も「市民のDIY工房」としての機能を持ちつつ、
石巻に来たら、必ず立ち寄りたくなる場所にしたいと話します。

「被災地に来てもらったとき、(被災者のために)何かしてあげようというのではなく、
もし自分自身が被災したらどうするかをシミュレーションしてもらえる。
そんな場所として、石巻工房は機能していけたらと思っています」

自らの経験と教訓から生まれた石巻工房。
地元の人の自立のための工房としてはもとより、
地域を活性化する起爆剤として、歩み始めています。
FUNADE~結日丸~
石巻市街の中心に、一際目をひく一軒のお店があります。

「FUNADE studio」という名のそのお店に一歩足を踏み入れると、
そこには眩いばかりの世界が広がっていました。
「FUNADE studio」は、仲間から"テツ兄"と慕われる、
田中鉄太郎さんが手掛けるオリジナルブランドのお店。
京都で日本をテーマにした、グラフィックデザインの服づくりをしていた田中さんは、
震災後、居ても立ってもいられずに、石巻にボランティアに来ました。
瓦礫の処理が終わった頃、自然とものづくりを活かした支援をしたい
と思うようになったといいます。
「復興に甘えずに、ずっと続けていくためには、
この地にあるものを活かさないといけないと思って」

そう話す田中さんが素材を探すなかで出会ったのが、1枚の布でした。

泥まみれになりながらも存在感を放っていたのは、
色とりどりに美しく染め上げられた「大漁旗(たいりょうばた)」だったのです。
大漁旗とは、漁に出た漁船が大漁で帰港する際に船上に掲げる旗のこと。
また、新しい船の進水式で、ゆかりのある人たちから豊漁と海上安全を祈って
船主に贈られる「祝い旗」でもあります。

かつては大漁旗を揚げる様子をよく見ることができたそうですが、
昨今では進水式以外にはあまり使われず、
それでも捨てることはできずにしまっておく人が多いとか。
大漁旗を求めて沿岸部を走った田中さんは、
2日間で約300枚の大漁旗を漁師さんたちから譲り受けました。
「その時点でこっちに居続けることが決定しましたよね。
2011年の9月後半には京都の家を引き払って、
正式に石巻でものづくりを始めました」
大漁旗という伝統ある素材をいかに日常に取り入れるか。
田中さんは試行錯誤をくり返しながら、
大漁旗を使ったオリジナルブランド「FUNADE~結日丸~」を立ち上げました。
そして、自分だけでものづくりを進めるのではなく、
知り合った浜のお母さんたちに作業をお願いしながら、一緒に作り上げています。
「働くことは経済的にも精神的にも自立につながる大切なことです。
浜のお母さんたちはいつも手を動かしていて、
台風なんかで働けないことが耐えられない。
仕事をお願いすることで、お母さんたちは生き生きしています」
生地そのものに存在感がある大漁旗。
2つとして同じものがない貴重な素材を余すことなく使いたいと、
田中さんたちはこんな商品も企画していました。
布を裂いてブレスレットの材料を作る際に出る、
残糸を使ったピアスです。
「大漁旗は東北に限らず、日本全国にあるもの。
今後もこの伝統ある大漁旗という素材を
カタチを変えて色々なモノにしていきたいですね」

一時的な支援のためのものづくりではなく、
初めから未来を見据えてきた、田中さんのものづくり。
その地にある素材を活かして、
現代のくらしのなかに取り入れやすいプロダクトに変換するというプロセスは、
どこの土地においても参考になるものづくりではないでしょうか。
そのブランド名の通り、
田中船長が舵をとる「FUNADE~結日丸~」が、
石巻から全国と出帆していました。
日田の理想的なものづくり
大分県日田市大山町。
筑後川の本流にあたる大山川が流れ、四方を緑に囲まれた山深い場所です。

ここは「梅の里」としても知られ、毎年3月上旬から一斉に花が咲き始め、
辺りは梅の花の良い香りに囲まれるそうです。
大山町では、当時政府が米の増産を推進していた1961年に、
米作には不適な山地の地理的特性を生かして、
作業負担が軽く、収益性の高い梅や栗を栽培する
「NPC(New Plum and Chestnut)運動」を開始。
「梅栗植えてハワイに行こう!」というキャッチフレーズを掲げて推進し、
その結果、実際に全国でも住民のパスポート所持率が高い町になったとか。
「平成8(1996)年に特産品である梅の古木を活用した
ものづくりをしようという話がありまして」

そう話す矢羽田匡裕(やはたまさひろ)さんは、
26歳でサラリーマンを辞めて、農協主体の「梅の木工房」に参加。
もともと好きだったものづくりの分野で、
地元でできることを探していた時に、木工の世界に入りました。
矢羽田さんはその後独立し、
現在は大山町で工房「ウッドアート楽」を営んでいます。
「前職は金型設計の仕事でした。
自分の作ったものがどう役立っているのかが見えにくかった。
今は自分がゼロから作ったものに対するお客様の反応が明らかで、
うまくできたら売れるというのが面白いですね」
そんな矢羽田さんの工房の入り口で目に留まったのが、
成人の背丈よりも高い枝の束。
これは剪定した梅の枝でした。
枝の形状をそのまま生かし、矢羽田さんが手掛けたのがお箸。
梅の木独特の赤茶色の木肌がそのまま残された、
シンプルながら存在感のある逸品です。

それまで剪定された枝は、燃料になる他は廃棄されていたそうですが、
矢羽田さんは木と向き合う際に次のように考えると話します。
「木工の師匠から2つのことを教わったんです。
1つには、育つのに100年かかった木だから100年使えるものづくりをすること。
2つには、限りある資源だから無駄なく使うということ」
矢羽田さんはその考えのもと、梅のほかに、桜や杉などの地元材も使いながら
オリジナル商品の開発やOEM生産も行っています。
「日田には"絞り丸太"という、幹の表面に
天然の凹凸模様を持つ杉があり、昔は床柱に重宝されていました。
山主から『せっかくいい木があるんだから、何かに使えないか』
という話があって」
"九州の小京都"と呼ばれる日田市豆田町にある、
日田産の家具や雑貨を取り扱うセレクトショップ「Areas(エリアス)」
のオーナー兼デザイナーの仙崎雅彦さんは、お店を始めた当初から
矢羽田さんにものづくりをお願いしてきました。

通常、木材は芯(年輪の中心)を残したままだと
後から割れてしまうという課題があります。
それでも、独特の美しい波状模様を持つ、絞り丸太の年輪に惚れた仙崎さんは、
どうにかできないかと矢羽田さんに相談。

すると、木を切ってすぐの生木の状態で特殊加工を施すことで、
割れを解決することができると分かりました。
「これは山と加工場が近くないと実現できないものづくりですよね」
と、仙崎さん。
特殊加工された日田杉の絞り丸太は、
矢羽田さんの手によってひとつひとつ削られ、カップへと形を変えていきました。
この絞り丸太のカップは内側の年輪ももちろんですが、
カップの外側には、樹の表面の出絞(でしぼ)模様が現れ、
天然木ならではの、自然が生み出す意匠を楽しむことができます。

「日本は世界から"森林破壊のテロリスト"と呼ばれているんです。
日本は森林保有率を豪語しながら、
一方で海外の木材を使って、海外の森に影響を与えている。
森を守るためには木を使うことが必要なので、
もっと自国の木を使えば、みんながwin-winになれるんですよ」
森林に苗木を植えてから15~20年ほど経った後に
一部の木々を間引く"間伐"という作業がありますが、
どうせ後から間引くのなら最初から少なく植えればいいと思うかもしれません。
しかし、仙崎さんの話によると、
最初から少なく植えてしまうと、後から使うのが難しい木が育つんだとか。
「通常の木も間伐材も、それぞれにメリット・デメリットがあり、
その両方を伝えていかないといけない。
日本の森林を活用していくためには、
1次・2次・3次産業が三位一体でやっていく必要があると思っています」
消費者の声を聞き、山主さんとも直接つながる仙崎さんが商品を企画し、
地元の木材を活用して、木工のプロである矢羽田さんがそれを形にする。
理想的なものづくりが日田では行われていました。
地域が誇り進化し続ける、久留米絣
経糸(たていと)または緯糸(よこいと)、
もしくは両方の糸の一部を前もって染めておき、
これを用いて織り上げて文様を表した織物、「絣(かすり)」。
文様の輪郭部分がかすれて見えるために「絣」という名が付いたともいわれています。

絣のような織りの技法は、東南アジアをはじめ世界各国に見られ、
日本国内でも各地で織られてきました。
「久留米絣は、久留米で語られている歴史だと、
偶然の発見から始まったといわれています。
200年以上前に、一人の少女が自分の藍色の服にあった白いシミに気付き、
糸をほどいて、そこから独自の絣の図案を考え広めたと。
女性の社会進出に寄与したともいわれていて、ロマンがありますよね」

そう話すのは、一瞬で目を奪われる久留米絣のシャツに身を包んだ、野口英樹さん。
久留米市で久留米絣の問屋を営む、株式会社オカモト商店の専務です。
野口さんいわく、久留米絣の生産量は現在、
昭和初期の最盛期の約1/20になってしまっていますが、
今も二十数軒の織元が存在し、絣が進化し続けているそう。
福岡県の「久留米絣」のほか、
愛媛県の「伊予絣」と広島県の「備後絣」を日本三大絣と呼びますが、
今でも産業として成り立っているのは、久留米絣だけだとか。
それは産地の風土と歴史にまつわる発展があったからでした。
福岡県南部の筑後地方には、九州最大といわれる筑後川が流れ、
豊かな土壌と豊富でキレイな水が、絣の生産に適していました。
そして、明治の西南戦争で全国から集まった兵士が国元へ帰る際に、
お土産として久留米絣を持ち帰ったことで、全国にその名が知られるように。
しかし、一方で、粗悪品も出回ってしまい、久留米絣の評判が下落。
それではいけないと鑑定所ができ品質チェックを行うようになり、
現在のような質の高い久留米絣になったといいます。

久留米絣は、図案製作、括り(くくり)、染色、織りなど
大まかに分けても30の工程があり、分業制でそのすべてが重要です。
久留米市周辺に点在する生産現場を、野口さんにご案内いただきました。
まず、久留米絣の命ともいわれる、糸の括り作業。
昔は職人の手によって行われていましたが、現在は機械によって生み出されています。
しっかりと糸で縛ることで、その部分が防染され、
織った際に美しい文様を表現できるのです。
続いて、染色の現場へ。
こちらの工房では、伝統的な天然藍を使った染色が行われていました。
「藍は生き物と一緒。
毎日かきまぜて様子を見てあげなきゃいけないから、なかなか遠出もできません」
染色歴50年の小川内龍夫さんは
毎日藍の状態を、舐めて確認するというから驚きます。

括り屋さん、染屋さんを経て織物工場に糸が届いても
すぐに織りの作業に移れるわけではありません。
経糸と緯糸の準備が必要になるのです。
なかでも、絣の文様がきちんと出るように経糸をそろえる
「荒巻」という作業(写真左下)は、絣の完成度を決める大切な作業だそう。
(写真左:経糸の荒巻作業の様子、写真右:緯糸のトング巻作業の様子)
そして、カシャンカシャンと活気のよい音を立てながら、
年季の入った織機が忙しく動いて、
経糸840本と緯糸240本が1枚の絣を生み出すのです。

「織れない柄はないですよ。
量産できるわけではないから、日々技術の進歩を心掛けていくことが、
後世へものづくりを残すことにつながると思っています」
そう胸を張る、野村織物の野村哲也さんの言葉が
産地の強さを物語っているようでした。

こうした各工程のスペシャリストの技の集結によって、生まれる久留米絣。
産地の特徴は問屋であるオカモト商店にもありました。
「うちは昔から異端児だったかもしれません。
両親の代から、生地だけでは勝負できないことを感じ、
自分たちで商品化をしてきたんです」
と野口さん。
兄で現社長の野口和彦さんと英樹さんの代になり、
オリジナル製品の企画製造と販売をより強化し、
今では全国に18店舗を展開するまでになりました。
「久留米絣は小さい頃から身の回りに当たり前にありました。
僕にとって白いごはんのようなものですね。
白いごはんがいろいろな料理に調理されるように、
絣もそれ自体は布だから何にでも形を変えることができる」
最近では、地元の靴メーカーと共同でスニーカーの開発をしたり、
パンツ感覚で使える現代風のもんぺのほか、
気軽に持てるバッグやポーチなどの小物を手掛けたりしています。
「今後も品質を追求して生地づくりを行いながらも、
絣を現代の日常に取り入れられるように、その可能性を探っていきたいです。
そうすることが、200年続いた久留米絣の、次なる200年への礎だと思っているので」
身近にあるとその価値になかなか気付きにくいものですが、
久留米絣にかかわる人たちは、その技術や質に誇りを持ち、
それを守るだけでなく、さらに発展させようとしていました。
この心意気こそが、ほっこりと温かく、透き通った美しさを見せる
久留米絣の魅力につながっているのかもしれません。
日本文化の畳とい草
今でも部屋の大きさを「○畳」と表現するように、
日本家屋と深い結びつきのある、畳(たたみ)。
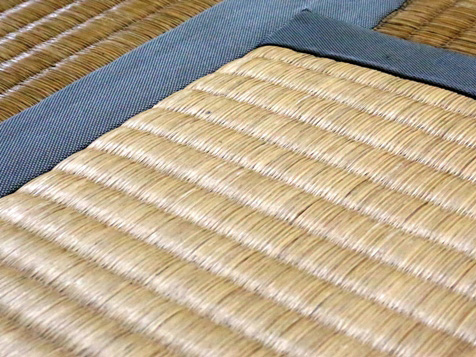
中国大陸から伝わった多くの文化に対し、
畳は日本独自の文化として発展してきました。
一般家庭にも広く普及するようになったのは、明治時代以降の話で、
それまでは茶道の世界や、大名など一部の特権階級のみで使用されるものだったそう。
そんな畳の素材「い草」の一大産地が熊本県八代市。
全国の実に9割以上のシェアを占めています。
7月上旬、八代市千丁町を訪れるとそこには、
風に揺られ、ゆらゆらとなびくい草の絨毯が広がっていました。

辺りがまだ薄暗い夜明け前、
い草田には静寂を打ち破る機械音が鳴り響きます。

「陽に当たってしまうとい草はしおれてしまうので、
収穫は明け方か、夕方の太陽が沈む頃から行います」

この地で3代にわたって、い草を作り続ける農家、
坂井米夫(さかいよねお)さんに教えていただきました。
かつて"緑のダイヤ"とまで呼ばれていたい草は、
この界隈にも28軒ほど生産者がいたそうですが、
今残っているのは3軒のみ。
なかでも坂井さんは、20年ほど前から、
オーガニックのい草を栽培する希少な生産者です。
「ダイオキシンが社会問題になった時があるじゃないですか。
最も影響が少ないといわれていた農薬にも、ダイオキシンが含まれていました。
その時、安全な農薬なんてないと思ったんです」
以来、無農薬・無化学肥料のい草を栽培し続けている坂井さん。

苗の栽培から始まり、11月末に田んぼに植え付けてから7月上旬の収穫までに、
冬草、春草、夏草と3度の除草が必要になるため、
オーガニックの栽培はとても労力が要ります。
食品と違い、JAS規格などで有機栽培をアピールすることもできませんが、
坂井さんは、安心安全のい草を生産することに余念がありません。
通常、刈り取られたい草は「泥染め」といって、
すぐに、粘土質の泥に浸け込まれます。
これは江戸時代から続いている伝統技法で、
い草の吸排湿を高め、畳表の弾力を増して、変色を抑えます。
しかし、坂井さんは収穫したい草の半分は泥染めを行っていません。
それも、泥に含まれる微量物質によって、
アレルギー反応などを起こしてしまう人への配慮からでした。
 (左:無染土畳、右:染土畳)
(左:無染土畳、右:染土畳)
「泥染めによって、香り付けする面もあるのですが、
それも人によって感じ方は様々。
こうしなくちゃいけない、というのではなく、
消費者にとってどんな畳が良いのかを考えなくてはいけない」
そう話す坂井さんは、熊本県で育成された新品種
「ひのみどり」ではなく、在来種の「きよなみ」を栽培。

「ひのみどり」よりも茎が太く、灯芯が多い「きよなみ」の方が、
畳に仕上げた際の踏み心地が柔らかいのだといいます。
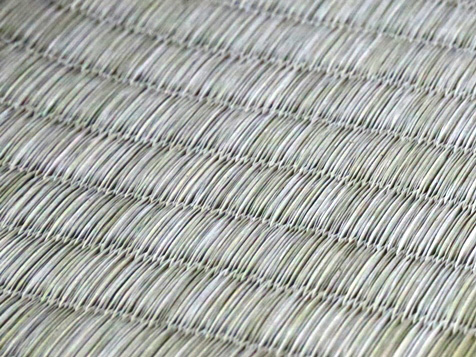
「畳表は目が詰まっているほど、良い畳とされてきましたが、
い草が潰れてしまっては弾力性を失って、硬さだけが残ります。
い草の丸みが残る位が適度で、フローリングにはない
そのしなやかさこそが畳の魅力だと思うんです」
その言葉に、ふかふかの畳の上でゴロゴロ寝転がり、
い草の香りに包まれながら、昼寝をしていた幼少期を思い返しました。
家に上がるとき、靴を脱ぐ文化の日本において、
素足で畳の上を歩くのも気持ち良いものですよね。
それまでのい草栽培を一つひとつ見直しながら、
今一度、生活者にとって良い畳を追求し続ける、職人気質の坂井さん。
「和室=畳と考えるのではなく、
一つの家を彩るパーツとして考えてほしい」
と、話します。

吸湿性が高く、乾燥時には湿気を吐き出してくれる畳は、
夏涼しくて冬暖かく、さらに消臭効果もあるといいます。
また、集まった人数によって使い方を変えられるのも
良さの一つかもしれません。
生活スタイルの変化によって、畳離れが進んでいますが、
日本独自の文化であり、日本の風土に合った様々な利点を持つ畳を
今一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。
東濃のtonono
岐阜県南東部に広がる東濃(とうのう)地方。

裏木曽に当たるこの地方は、激しい寒暖の差に痩せた土地が特徴です。
同じ県内でも、飛騨地方のケヤキやトチといった広葉樹に対し、
東濃地方に育つのは、ヒノキやスギといった針葉樹。
この地で長い年月をかけ成長する木は、年輪幅が少ない良質な木材へと育っていきます。
伊勢神宮の遷宮用のご神木も、この地から奉納されるほど。
こうした木材は、主に建材として用いられ、
端材は曲げ輪の技術で、お弁当箱などが作られてきました。

「なかでも良質の材は、"トロ"なんて呼んだりするんですよ。
ここのヒノキは粘り気もあるから、曲げ輪ができたわけです」

そう話すのは、この地で60年近く木工業を営む、
内木木工所の内木盛良(ないきもりろう)さん。
曲げ輪の職人だった父親に対し、別の分野を極めようと
内木さんが追求したのが、塗装の道でした。

今日では、木材塗装の分野において業界を牽引しています。
実際に、内木さんが手掛けたプロ仕様の卓球ラケットを拝見すると、
そこに刻まれた年輪は、確かに"トロ"のようです。

そんな良質な材がある東濃地方においても、
木工業を取り巻く厳しい環境は変わりありません。
住宅用建材の多様化に加え、安価な外材の流入…。
森は適正に間伐、管理されなければ、
こうした良質な材も育たなくなってしまいます。
「それでも木工の産地、岐阜には仕事があり、危機感が薄いんです。
私も、塗装だけで食べていくこともできました。
ただ、産地の緩やかな衰退を、見て見ぬふりはできなかったんです」
そう話す内木さんは、もともと好きだった加工の技術で、
様々な木工製品を手掛けていきました。
そんななか、NCルーターでカットしたウェーブ状の素材。

それをつなぎ合わせた板を、数カ月放置しておいても、
まったく反っていないことに気が付きます。

内木さんは、県や大学に試験を依頼。
すると、ウェーブ状にカットしたことによって、
木の繊維が短く絡み合い、反りが防がれることが判明したのです。
「普通、無垢の木は板状にすると、数カ月放置していたら、
多少なりとも反ってしまうんですよね。
この技術を用いれば、様々なものに展開できると思いました」
内木さんは、デザイナーに協力を仰ぎながら、
矢継ぎ早に様々な商品を仕掛けていきます。
それまで柔らかく、反りやすいため、
家具には向きにくいといわれていたスギ・ヒノキでしたが、
この技術を用いれば、このように机やテーブルにも。
スギの柔らかい触り心地と吸水性を生かしたバスマットは、
反りにくいからこそ生まれたプロダクトです。

内木さんはこのブランドを、「tonono(とのの)」=東濃の、
と名付けました。
「グローバル社会においては、何か作っても、
すぐに外材で真似されてしまいます。
これからは東濃でしか作れないものを追求しなくてはいけません。
木工の産地の岐阜で、ここでしかできない技術を駆使していきたい」

スタイリッシュなデザインで、
針葉樹の欠点を解消した「tonono」。
ウェーブ状の材をつなぎ合わせるのは、
高度な技術が必要とされるといいます。
この技術によって、東濃の木材が利用され、
山を守り育てていく循環を生み出していく。
内木さんの探求心は今、確実に実を結びつつあります。
想いを結び込む、水引
結婚式のご祝儀や入学祝い、出産祝いなどのお祝い事の際に、
品物や封筒を結ぶ、「水引」。

この「水引」に関するとても興味深い話を
最盛期は全国の水引製品の約70%を生産し、
現在もなお高いシェアを誇っている、長野県飯田市で聞くことができました。
「飯田はキレイな水が流れる町で、江戸時代から紙漉きが盛んでした。
朝廷にも紙を納めていたのですが、
紙を整える際に切り落とした端紙を使って、"元結(もとゆい)"を作っていたんです」

そう飯田水引の歴史から教えてくださったのは、
明治元年創業、老舗の水引屋である
大橋丹治株式会社の専務、5代目大橋丹治さんです。
元結とは髪を結ぶ道具のことで、昔は生活必需品でした。
飯田で漉かれていた、薄くて丈夫な「ひさかた和紙」を使って、
美濃の国(現在の岐阜県)から和紙職人の桜井文七氏を招いて習った元結は、
その質の高さから、「文七元結」として全国にその名を知られるようになったそう。

しかし、明治維新の断髪令により、元結の消費は減少。
その後、元結の技術を生かした水引製品の生産へとシフトすることになりました。
ちなみに、水引という名の由来は、
長くしつらえた紙縒(こより)に、水のりを引いて作ることからだそう。
大橋さんの家業も、元結製造に始まり、水引製造へと移り、
現在は水引の加工を中心に行っています。
以前は結納のための水引セットが主力商品だったそうですが、

最近は、結婚式を挙げるカップルが減ってきており、
ましてや結納をするカップルはさらに減ってしまっています。
「残念ですが、時代の流れは変えられない。
何か別の切り口で、現代のニーズにあったものを作らないと」
4年前に帰郷して家業に入った大橋さんは、
販路開拓のために、新商品の開発に奮闘。
水引のピアスや、ラッピング用資材としての水引を生み出しました。
以来、ありそうでなかった新しい水引は、様々なメーカーのラッピングや、
結婚式の引き出物に招待状、個人のプレゼントと幅広い反響を得ています。

もともとこの水引の由来は、飛鳥時代に遣隋使である小野妹子が帰朝の際、
隋国より日本の朝廷に贈られた贈り物に、
紅白で染め分けた麻ひもが結んであったことが始まりだそう。
「帰途海路の平穏無事を祈願してのことで、
そこから何か贈り物をする時には、想いを一緒に結び込んで贈る習慣ができたようです」
戦時中にも、出兵兵士の無事を願って、
金封を水引で結んで渡していたといいます。
そんなお守りの代わりともいえそうな意味を持つ水引。
実は、現在も結び方に意味が込められているということを知りました。
ご祝儀袋でよく見るこちらの結びは「あわじ結び」というもの。

結び目がアワビの形に似ていることからついた名ともいわれていますが、
一度ほどいてしまうと二度と結べないことから、「結び切り」と呼ばれています。
「一度きりで繰り返さない」という意味が込められており、
結婚式や快気祝い、お葬式などに用いられる結び方なのです。
これをアレンジしたのが「梅結び」。

目の前で職人さんに結んでいただくと、ものの1分ほどで完成。
手の感覚で順序を覚えているといいます。
一方、こちらは「蝶結び(花結び)」と呼ばれるもの。

簡単に結びなおすことができるので、「何度あってもよい」という意味から、
出産祝いや入学祝いなどに使われます。
このように、水引は時代を超えて、
贈り物をする際に自分の想いも結び込んで贈るという、
日本独特の文化として受け継がれてきました。
「今後は、世界を舞台にラッピングという分野で
水引を広めていきたいですね」
最後にそう野望を語った、大橋さん。

素材や形状などが時代とともに変わっていったとしても、
「気持ちを込めて贈り物を結ぶ」という水引の考え方は、
日本人として、未来に残していきたい大切な文化ではないでしょうか。
現代によみがえる、下駄
「花火大会に下駄を履いて行って、帰りに足が痛くなった。
そんな経験あるでしょう?
一日中履いていても足が痛くならなくて、
ジーンズにも似合う下駄を作りたいと思ってね」
そういえば、前回下駄を履いたのはいつだろう…
そんな想いを巡らせながらお話を伺ったのは、
静岡県静岡市にある、株式会社水鳥工業の代表・水鳥正志さんです。

静岡市には"材木町"という町名が存在するほど、かつては林業が盛んで、
下駄製造が地場産業として成り立ってきました。
その歴史は江戸時代の初めにさかのぼり、
徳川家康が駿府城築城や浅間神社造営のために、
全国各地から職人を集めたことが始まりとか。
その後、そのまま住み着いた職人が、静岡の伝統工芸のひとつ、
「駿河塗り下駄」の発展に寄与したといいます。
「昔は下駄が嫁入り道具だったし、地に足がつく暮らしが出来る様にという想いから、
お正月には親が子に新しい下駄をプレゼントする習慣があったんですよ」
 ※嫁入り道具の下駄
※嫁入り道具の下駄
水鳥工業は昭和12年に、下駄の木地製造業からスタート。
しかし、昭和38年頃にはライフスタイルの変化にともない、
下駄木地の需要がほとんどなくなり、
サンダル用の天板や中芯の加工を手掛けるように。
また、昭和50年頃には、シューズの中底の加工を開始しました。
履物という括りでは同じものの、木地製造と中底の加工の技術は全くの別物。
水鳥さんは神戸の靴屋に技術を学びにいったそうです。
それでも、平成元年頃には、今度はサンダルやシューズメーカーの製造が
海外へシフトしていき、水鳥さんは危機感を抱きます。
「このままだと近い将来、日本でのサンダル、シューズ製造は激減する…」
中国の視察に行ってそう感じたという水鳥さんは、
頭を悩ませた末、あることに気付いたといいます。
「日本の気候風土にあった下駄をもう一度作れないか。
足の裏は平らじゃないし、足は左右あるんだから、
その区別のある下駄があったらいいじゃないか!」

帰国した水鳥さんは、早速新しい下駄づくりの話を
メーカーに持ち込みましたが、誰からも相手にされませんでした。
そこで、水鳥さんは覚悟を決めて、自社で下駄づくりを行うことを決めます。
そうして生まれたのが「げた物語」という名のついた下駄でした。

水鳥さんは、なぜ現代において下駄が履かれないかを今一度考え、
それは鼻緒が痛いからということと、今のライフスタイルに合わないからと結論づけます。
そこで、足を優しく包み込むような幅広い鼻緒と、
ジーンズなど現代のファッションにも合うデザインを実現。
履いた時に足にフィットするよう、鼻緒をつける時には、
足の専門家が作る"ラスト"と呼ばれる足型を下駄台に合わせて行います。
また、一日中履いていても足が疲れないように、
足裏のラインに気持ち良くフィットする木地部分は、
職人さんの手彫りで、一足一足仕上げています。

創業当時行っていた下駄木地製造の技術と、
何十もの工程を追って完成する中底づくりの技術の両方が、
まさに生かされていました。
「実は、静岡大学との共同実験で、
水鳥の下駄が健康に良い影響があるというのが分かったんです」
常務の水鳥秀代さんがそう教えてくださいました。

素足の場合と、水鳥の下駄を履いた場合の、
歩行前と30分間歩行した後の、足裏の血流循環量と重心位置を測定。
すると、水鳥の下駄を履いた場合に、
血流循環量が活発になり、体の重心も最適な位置に近づいていたというのです。
さらに水鳥の下駄の場合、浮指(立った時、足指5本が地面に付かない状況)が
改善されることも分かりました。
「履き心地を追求したうえで、履いていて楽しい下駄を作り続けたいですね」
そう秀代さんが話すように、水鳥工業では、
様々な素材にこだわった鼻緒を用いた下駄や、
デザイナーとのコラボレーション下駄、
最近では、木地に静岡産のヒノキを使った下駄も手掛けています。
「下駄は平和な時代に進化する履物。
いつまでも下駄を履いて暮らせる平和な時代が続いてほしい…
そういった願いを込めて、下駄を作り続けていきたいです」
そして、世界中の人にもっと下駄の良さを知ってもらいたい、
そう語る、水鳥さん。

左右形が異なるというのは、靴づくりからすると当然のことですが、
それをこれまでなかった下駄の世界で実現し、
履き心地を追求してきた結果が、
今こうして現代のライフスタイルに受け入れられることにつながっていました。
高温多湿の日本の風土に合った下駄が、
今一度、私たちの生活によみがえろうとしています。
金継ぎ
大切な器をうっかり壊してしまった…

こんな時、あなたならどうしますか?
以前の私たちであれば、泣く泣くゴミに出していたかと思います。
しかし、今なら別の選択肢を選ぶかもしれません。
それは、「直す」という選択肢を知ったから。
日本には、割れたり欠けたりした器を漆で接着し、
金蒔絵を施して直す「金継ぎ」という伝統技法があります。

金継ぎは、「茶の湯」(茶道)の発展にともない、
安土桃山時代から江戸時代初期にかけて完成した、
日本独自の修復技術だといわれています。
当時、茶の湯はお殿様など限られた世界の人のみの嗜み(たしなみ)であり、
茶の湯に必要な茶碗も当然高価なもの。
壊れてしまったとすれば、そのものに対する執着心は
今よりも一層強かったことは容易に想像がつきます。
「金継ぎのすばらしいところは、使うための修復だという点です。
器の割れ目をあえて目立つように、金で装飾するというのは、
日本独特の美意識だと思いますよ」
とは、東京都豊島区にある「金継宗家」の宗匠・塚本将滋さん。

塚本さんは子どもの頃に、ご先祖様の故郷である滋賀県の彦根城で見た、
"朱漆塗りの甲冑"に魅せられ、
それがキッカケで東京芸術大学に進み、彫金と漆塗り、蒔絵の技術を学びました。
そして、金属に漆を塗るという、金胎漆芸の技を独自に開発。
漆アートや漆アート・ジュエリーを手掛けるアーティストとして、長年活躍しています。
また、20代から茶道の遠州宗家に入門。
江戸時代初期の芸術家・本阿弥光悦が手掛けた、
金継ぎの赤楽茶碗「雪峰(せっぽう)」と運命的に出会い、
金継ぎも始めるようになります。
「この『雪峰』は、金継ぎを、単なる修繕技術から、
初めて芸術の域まで高めた記念すべき作品です」
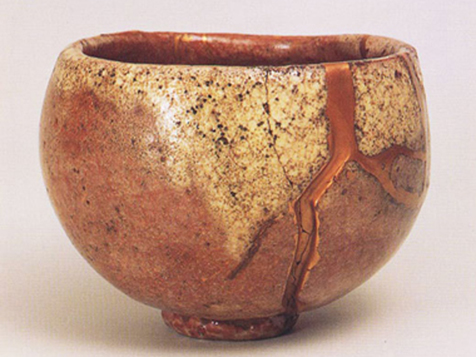 「雪峰」(畠山記念館蔵)
「雪峰」(畠山記念館蔵)
「雪峰」は、もともと窯傷の割れの生じた失敗作だった茶碗を、
茶人でもあった本阿弥光悦が、
朝日があたる雪の積もった峰のイメージとして見立てたんだとか。
金継ぎの世界では、修復した跡を「景色」と呼び、
修復前と異なる趣を楽しむそうなのですが、
金継ぎを施すことで、その器は確かに唯一無二の珍宝に生まれ変わるのです。
全工程に通常数ヵ月を要する、金継ぎの作業ですが、
特別にその工程を追って見せていただきました。
まず、割れた器の破損部分に、
漆とでんぷん糊を混ぜた刻苧糊(こくそのり)を塗り、
そこに、刻苧糊と陶土を混ぜた粘土状の刻苧(こくそ)で充填します。
乾いたら、平らに成形し、その上に黒漆を塗って、さらに乾かし、
研ぎ炭で平らに磨いて下地を整えます。
この工程が、後に行う蒔絵に際して、とても重要なポイントだそう。
金継ぎを行う人のなかには、この磨きにサンドペーパーを使う人もいるそうですが、
サンドペーパーでは真っ平らにならないと、塚本さんはいいます。
続いて、蒔絵を施す部分の下塗りに、"幻の筆"と呼ばれる、
ねずみの毛で作った蒔絵師が使う根朱筆(ねじふで)で絵漆を塗り、

絵漆が乾く前に、"粉筒"(金粉を蒔くための竹の筒)を使って、
純金粉を蒔きつめます。
漆工芸技法の一つである蒔絵ですが、
呼び名の由来は、まさにここにありました。

そして、蒔いた金粉を筆で掃けると、この通り。
絵漆を塗った部分にだけ、綺麗に金が定着しています。

しかし、まだこれで終わりではありません。
瑪瑙(めのう)のヘラ、椿の炭、砥石の粉と菜種油、鹿の角粉を用いて、
光沢が出るように磨き仕上げをして、ようやく完成。
出来上がりの金継ぎ部分を触らせていただくと、
目を閉じていたら、どこが破損部分か分からないほど、
滑らかですべすべな仕上がりです。
「江戸時代から伝承する、壊れたものに新たな価値を与えて蘇らせるという、
素晴らしい技術を失くしてはならない。
蒔絵による正統な金継ぎを途絶えさせてはいけないと思うのです。
私は、先に述べた『雪峰』を手本に、四十数年技を磨いてきましたが、
流儀の金継ぎを後世につないでいくことも使命だと思っています」
塚本さんはそんな想いで、15年前から金継ぎ教室を開催。
20〜70代の幅広い年齢の生徒さんが、金継ぎを学んでいます。
最近では、フランス人とドイツ人も習いに来ているそう。
「生徒さんは、大きく分けて2通り。
思い出のある品を蘇らせたいという人と、骨董品に興味があるという人。
最近、20歳代の男の子が『カッコイイから』と入門したことには驚きましたよ」

かつては庶民のものではなかった金継ぎが、
一般化しつつあることが不思議だと語る、塚本さん。
「ものを慈しみ大切にする日本独特の"MOTTAINAI(もったいない)"精神は、
今も昔も変わらずに、私たちの中にあるのかもしれませんね」
一度割れてしまった器をさらに価値あるものに蘇らせる、「金継ぎ」。
何でも簡単にものが手に入ってしまう時代だからこそ、
特別な一点物を傍に置きたいという欲求が、高まってきているのかもしれません。
あおぞらポコレーション
滋賀県で出会ったカラフルな織物製品、
「coccori(コッコリ)」。

織物産業の盛んな滋賀県で、工場などで不要になった残糸を用い、
県内の福祉作業所で働く方々の独特のセンスで生み出された織物です。
coccoriは、それまで作業所の倉庫に眠っていたこれらの織物を、
日用品に加工し、製品化されたものでした。
その目的は、障がい者の賃金向上のため。
全国的に見て月平均約1万3000円といった障がい者の賃金を、
製品化して流通させることで、少しでも向上させようとしているのです。
こうした試みは、他の地域でも始まっており、
新潟県でも活発な動きが見られることを伺いました。
coccoriさんのご紹介で訪ねたのは、
阿賀野市にある福祉作業所、「あおぞらソラシード」。
新潟市内にある作業所「あおぞらポコレーション」のグループ施設です。
新潟市内から30分余り、内陸に車を走らせた山あいに、
あおぞらソラシードはありました。
「ここでは、社会とつながってお金を稼いでいける力はもちろん、
自分たちで食べていける力、自然の資源を生かしていける力を培っていけるよう、
こうした山あいに作業所を構えているんです」

施設長の本多佳美さんがそう話す通り、
施設の横には今後、農園やキャンプサイトとして運営していけるよう
広い空地が用意されていました。

こうした施設ができたことによって、
町中で働きたい人、自然のなかでのびのびと作業したい人と、
障がい者の働く環境の選択肢が広がったといいます。
本多さんは大学卒業後、就職した福祉施設がトラブルで閉鎖。
路頭にさまよってしまった利用者の受入先を作らなくては、という想いで、
理事長や理事の面々、地域の方々、保護者の協力のもと、
2003年、新潟市内に「あおぞらポコレーション」を設立しました。
杉の加工など、県内の企業の下請け事業で、作業所は軌道に乗りつつも、
震災によって、仕事が途絶えてしまう事態に陥ります。
「下請けだけでは事業基盤が弱い、
もっと独自の事業を手掛けていかないと」
そう考えた本多さんが運命的に出会ったというのが、奈良県にある
国産オーガニック化粧品会社、クレコスの副社長、暮部達夫さんでした。

クレコスは、米ぬかやへちまなど、
日本の伝統的な自然素材を生かした化粧品を20年以上前から手掛けています。
クレコスが、ちょうど新潟に直営店舗を構えたところで、
責任者としてやってきたのが暮部さんでした。
「手ぶらで行くのも失礼だったので、
下請け事業で出た越後杉の端材を持っていきました。
この杉の木で、石鹸箱を作らせてもらえませんか? とお願いしてみたんです」
そう切り出した本多さんに対し、暮部さんは独自のアイデアを返します。
「この杉を蒸留して、リネンウォーターにすれば、おもしろいかもしれない」
こうして生まれたのが、「熊と森の水 リネンウォーター」でした。

リネンウォーターは、カーテンやシーツ、衣類などに噴霧し、
雑菌・雑臭を除去する効果があります。
杉を蒸留することで、越後杉の香りを閉じ込め、
なおかつ杉の抗菌力を生かしたのです。
本多さんたちは、クレコスの暮部さんによる指導のもと、
品質管理や安定供給に対する意識と技術を身に付けてきました。
現在では、作業所員による厳しい成分チェックはもちろんのこと、

大手化粧品会社で商品開発に携わっていた責任者を招へいし、
製造管理全般について指導を仰いでいます。
他にも、地元の杉の端材や新聞紙と、
神社などで不要になった和ろうそくを用いて作る着火剤など、
次々とオリジナル商品を手掛けていく、あおぞらソラシード。
そこには、自然に囲まれた環境で、
イキイキと働く作業員たちの姿がありました。
「役割を与えられると、人は変わっていくんですよね。
これからも、地元の資源を生かしながら、
仲間と楽しくできることを手掛けていきたいです」
そう話す、本多さん。
リネンウォーターを代表とした、良い商品が前に出ていくことで、
作り手である障がい者や福祉作業所についても
世間に知られていく機会が増えていっています。
ちなみに、あおぞらポコレーションの"ポコレーション"は、
「poco(ちょっとずつ・ゆっくりと)」に、
「relation(つながり)」をくっつけた造語。
そこには、
「だれもがお互いを認め合い、幸せにくらせる社会。
青空のようにすっきりとした、ボーダーのない社会。
そんな社会へ向けて、ちょっとずつ、ゆっくりとつながりを広げていきたい」
という想いが込められていました。
施設を設立してから11年。
本多さんたちの想いが今、実を結び始めています。
会津木綿で、3.11をひっくり返す!
約400年の歴史を刻む、「会津木綿」。
1627年に会津藩主の加藤嘉明が、
その前の領地である伊予国松山から織師を招いて、
技術を広めたのが始まりだそう。
厚手で丈夫、保温性や通気性に優れた会津木綿は、
もんぺなどの庶民の日常着として愛されてきました。
そんな会津木綿は「縦縞模様」が特徴で、その種類がとても豊富です。
かつては「地縞(じしま)」と呼ばれる地域ごとの柄が存在し、
衣服の縞模様でどこの出身かが分かるような身近な素材だったといいます。

「もともとは地元にある草木で染めていたから、
地域で柄に違いが出たというようにいわれています」
明治32年創業の、会津木綿の織元である原山織物工場の
6代目・原山公助さんにご案内いただきました。

原山織物工場では、染め・織り・縫製までを一貫して行っており、
工場内では、年季の入った豊田織機がカッシャンカッシャンと
小気味良いリズムを刻みながら動いていました。
明治末期から大正にかけて最盛期だった会津木綿の生産ですが、
ライフスタイルの変化で需要が減少。
30社ほどあった織元は、原山織物工場含む2社を残すのみとなりました。
しかし、そうした状況の会津木綿に、2011年秋に新たな風が吹き始めます。
地元の若手による、会津木綿を使ったものづくりが始まったのです。
「会津木綿のほかに、頼れるものがなかったんです」
そう話すのは、株式会社IIE(イー)・代表の谷津拓郎さん。

会津出身の谷津さんは、東日本大震災後に帰郷し、
喜多方のまちづくりに取り組む、地元のNPOに就職。
しかし、すぐに自分がやらなければならないことに気付いたといいます。
それは、仕事を創り出すということ。
原発事故によって他地域からの避難者を受け入れることになった会津地方には、
人が増えた一方で、仕事がないという現状がありました。
「息の長い活動として、継続していけるものは何かを考えた時に、
"会津木綿"に行き着いたんです。
歴史ある会津木綿を使いながら、何か新しい価値を吹かせられたらと思って」
会津木綿の織元から生地を仕入れて、商品を企画し、
それを仮設住宅のお母さんたちにお願いして加工し、
谷津さんが販売するという内容のプロジェクトを発案しました。
「会津への恩返しの想いも込めて、仕事をしています」
慣れた手つきで作業をしながらお話してくださったのは、
作り手の一人、廣嶋めぐみさんです。
双葉郡大熊町から会津に避難してきた廣嶋さんは、
自宅でできる仕事を探しているなかで、谷津さんに出会いました。
「この仕事をするまでは、会津木綿は会津のお土産物
という認識しかありませんでした。
実際に使ってみると、丈夫で一年中使える素材ということが分かって
私自身も愛用しています」
初めは、地元のカフェからの受注生産で、
クッションカバーづくりからスタートしましたが、
その後、作り手のお母さんの試作で生まれた
フリンジ付きのランチョンマットにヒントを得て、
現在の主力商品であるストールが誕生。

「僕自身、昔からストールが好きだったこともあったんですが、
使えば使うほどになじんで風合いの増す会津木綿は
ストールにピッタリだとひらめいたんです。
丈夫だから洗濯しても問題がない。
汗っかきの僕にはうれしい限りです(笑)」
と谷津さんは語ります。
5人から始まった作り手も今では20人ほどに増え、
震災から2年後の2013年3月には法人化するまでに成長したこのプロジェクト。
「僕は会津木綿という伝統文化を、
日常生活の中にすっとなじむようにしてあげているだけ。
『上からもらったものを下に還す』という自分のモットーに従って、
次の世代に繋ぐものづくりをこれからもしていきたいと思っています」
最後に会社名の「IIE」の意味を伺いました。
「3.11をいつまでも忘れないようにしようと思いました。
でも一方で、"3.11鬱"になりそうなくらい、当時は3.11ばかりが取り上げられていて」
谷津さんに手渡された、IIEのパンフレット。

逆さに見てみると・・・

そこには、3.11をひっくり返して、この会津を復興していきたい
という谷津さんの想いが込められていました。
地元の伝統産業に目を向け、雇用を生み出し、
さらにその産業の新しい可能性を引き出している谷津さんの活動。
3.11以前にはなかった会津木綿の姿が、そこにありました。
時代を越えて愛され続ける、会津唐人凧
男の子の健やかな成長や立身出世を願ってお祝いをする、端午の節句。
この時期には、各地で鯉のぼりが空を泳いだり、
各家庭で兜(かぶと)が飾られたりします。
お正月の風物詩として知られる「凧あげ」も、
端午の節句の行事として、子どもの成長を願って
全国各地で大会が行われるそうです。
中国が発祥の地とされる「凧」は、形や柄が地域によっても異なりますが、
福島県会津若松市では、一度見たら忘れられない表情の凧に出会いました。
「会津唐人凧(とうじんだこ)」

「詳細は分からんのですが、400年ほど前に
東南アジアの方から長崎に伝わって、
それがここ会津にも伝えられたといわれていますよ。
昔は外国人のことを"唐人"と呼んでいましたから」
とっても細かい手作業をされながら、教えてくださったのは、
現在唯一、会津唐人凧を作り続けている、
竹藤民芸店・14代店主の鈴木英夫さんです。

もともと竹材屋として1624年に創業した竹藤ですが、
お店の前の道路環境が変わり、交通量が増えると、
それまで扱っていた長さのある竹などが扱えなくなりました。
その後は、全国の竹細工や民芸品などを扱う雑貨店として、
地域の人や観光客に愛され続けてきています。
築約170年といわれる、会津最古の商業建築である店舗は、
城下町の会津にピッタリの風格ある佇まい。
お店に一歩足を踏み入れると、
別の時代にタイムスリップしたかのような錯覚に陥ります。
さて、江戸時代から昭和初期にかけて、会津で作られていた唐人凧。
昭和初期になり、規格化された安価な凧が大量生産されるようになると、
手間がかかり値段も高くなる唐人凧は、いつしか途絶えてしまったそうです。
そんななか、昭和46年に、会津の長い歴史と文化を守る目的で
「会津復古会」が発足。
竹藤民芸店のある一之町通りは、昔から会津一番の繁華街で、
会津の商人は一之町通りに店を出すのが夢だったといわれています。
しかし、鶴ヶ城などに来た観光客が商店街に立ち寄ることはありませんでした。
そこで、会津の観光振興のために、各商店がやれることを実施。
会津に代々伝わっていた唐人凧も復活させようという話になり、
竹細工を扱っていた鈴木さんに白羽の矢が立ったのでした。
「唐人凧を作ったことなんてなかったですから、
最初は見よう見まねで作りました」

しかし、最初に作った凧はなかなか空に上がらなかったそうです。
「周りは、揚がらなくてもお土産物だからいいと言っていましたが、
でもそれじゃ凧の意味がない」
鈴木さんは、そこから試行錯誤を繰り返し、
厚さや重さを意識しながら凧の骨である竹の削り方を変えることで、
きちんと空に揚がる凧を作り上げました。

ポイントは、いかに竹を細く削るか。
手先の感覚で1mmほどの厚みに仕上げます。

「なるべく長く作り続けたいと思っているけど、
最近は足が悪くなり、目も悪くなり…」
少し弱音を吐かれた鈴木さん。
「せっかくだから揚げてみましょうか」
私たちの目の前で作ってくれた会津唐人凧を
お店の前の駐車場で揚げてみせてくださいました。
「走りながら引っ張って揚げるのは本当の揚げ方じゃないのですよ」
そう言いながら、器用に風を受けて空に揚がった会津唐人凧を
うれしそうに眺める鈴木さんの笑顔は、
職人というよりも、まさに少年そのものの顔でした。

古くは、戊辰戦争の籠城戦の際、
鶴ヶ城に籠城した会津藩士の子どもたちが空高く会津唐人凧を揚げて、
味方の士気を鼓舞していたという逸話の残る、会津唐人凧。
「会津唐人凧は日本一、有名な凧かもしれませんよ」
記憶に新しいNHKの大河ドラマ『八重の桜』でも、
鈴木さんが作った会津唐人凧が、劇中に何度か登場しています。
戦中に味方が生きていることを知らせるために、
コミュニケーションのツールとして活躍していた唐人凧は、
時代が変わった現在も、
子どもと大人や、会津地方と他地域を結ぶコミュニケーションツールとして
人々に愛され続けています。

大きな舌を出しながら空を舞う会津唐人凧が、
「どうだ、すごいだろ!」
と話しかけているような気がしてきました。
天然樟脳
夜の住宅街を歩いているとき、煮物のニオイがして実家を懐かしむ。
こんな経験をされたことはありませんか?
ある特定のニオイがそれにまつわる記憶を誘発する現象のことを
"プルースト現象"というそうですが、
同じように、実家やおじいちゃん・おばあちゃんの家の記憶を思い起こすニオイに
「樟脳(しょうのう)」があります。
樟脳とは、衣類の虫よけや芳香剤などに使われるもの。

その樟脳が何からできているかについて、これまで考えたことがなかったのですが、
その答えは私たちの案外身近なところにありました。

神社などで見かける「クスノキ(樟)」です。
クスノキは、ハッカのようなスーッとする特有のニオイを有しており、
この木があると虫も寄ってこなくなるため、
厄除けの意味から神社によく植えられたともいわれているとか。
また、クスノキには、鎮痛・消炎・血行促進などの薬理作用の性質もあり、
医薬品名「カンフル」として使われていました。
そんなクスノキは、暖かい地域にしか生息しないといい、
世界的に見ても、中国の揚子江以南から台湾、韓国、
そして、日本の西南部一帯にしかないんだそう。
そのため、クスノキから作られる樟脳は、かつてはたばこや塩と同様、
日本専売公社によって専売されていたといいます。
「樟脳がなければ、日本はこんなに栄えていなかったと思いますよ」

福岡県みやま市にある「内野樟脳」の5代目樟脳師、
内野和代さんにお話を伺いました。
内野さんいわく、江戸時代に樟脳は、金・銀に次ぐ輸出品だったそう。
クスノキの自生林に恵まれていた薩摩藩や土佐藩では、
樟脳を売ることで、軍費を稼いでいたんだとか。
「樟脳はセルロイド(合成樹脂)やフィルムの原料でもありましたが、
合成樟脳が生産されるようになると、
天然樟脳を作る生産者はどんどん減少していきました」
現在、国内における樟脳の生産者は4軒あるといいますが、
一時は内野樟脳だけの時代もありました。
ここ数年自然素材が見直されてきたなかで、
樟脳づくりを希望した生産者にその技術を教えたのも、実は内野樟脳でした。
そんな内野さんの工場は、住宅街の一角に佇んでいます。
九州一円から集められたクスノキが山のように積まれていて、
近づくと爽やかな香りがするので、
そこが樟脳づくりの現場であると容易に気付くことができます。

樟脳づくりの工程は、クスノキの木材を特殊な円盤カッターで
細かく砕くところから始まります。

大人が全体重をかけて押し付けて行うので、大変な労力のかかる作業。
また、一つひとつの木材によって癖が異なるので、
それを把握し、カッターに手を取られないように慎重に行う必要があります。
おもわず、「機械で細かく砕いてはいけないのか?」と質問してしまったほど。
すると、このカッターで削った場合に出る細かなひびが
樟脳を取り出しやすくしているといいます。
この木片を大きな甑(こしき:蒸し器)に入れて、蒸すのですが、
この時、木片を杵できちんとつき固めておくことが大切だそう。

その後、甑から発生する蒸気を冷却槽で冷やして、樟脳成分を取り出すのですが、
木片がうまく詰まっていないと、蒸気だけが上に抜け、
樟脳成分が十分に抽出できないというのです。
ちなみに木片を蒸すための燃料は、
樟脳成分を取り出した後の木片を乾かしたもの。
原料から燃料へと循環していて、一切の無駄がありません。
このかき氷のようなものが、樟脳の結晶です。
同時に、樟脳油が分離されますが、これはアロマオイルとして使用されているそう。

結晶をさらに圧搾機に入れて、一晩かけて圧搾すると、
ようやく樟脳の塊が取り出せるといいます。
すべての製造工程に最低でも10日を要す、天然樟脳づくりですが、
約6トンの木片からできる樟脳は、わずか25kg程度。
「樟脳づくりのポイントは『音をよみとる』ことだと思っています。
火の音、水の音…。
代々引き継がれてきているのは"感覚"なんです。
マニュアルはないから、五感を研ぎ澄ませてやっています」

これまで、どちらかというとツンと鼻につくようなニオイだと思っていた
樟脳の香りですが、内野さんたちの手作業によって、
丹精込めて作られた天然樟脳の香りはとてもナチュラルで、優しい香りでした。
衣類にニオイが残ってしまいがちな虫よけや芳香剤ですが、
天然樟脳の香りは、風に当てるとさっと消え、
衣類に残らないのが評判だといいます。
また、原料はクスノキと水のみなので、
化学物質や添加物にアレルギーがある方にも好評だそう。
20年以上にわたり、ご主人とともに樟脳づくりを行ってきた内野さん。
2010年にご主人が他界され、樟脳づくりの継続を迷われたそうですが、
お客様からの熱望と、地元の方の支援があり、今日に至っているといいます。
「使っていただいている人の声に突き動かされてやっています。
先人たちの気持ちを大切にしながらも、
自分の目線で、私にできることを続けていきたいですね」
内野さんのこの言葉を聞いて、昔ながらの手仕事を守っていくのは
作り手だけでないということを改めて実感しました。
【お知らせ】
内野樟脳の手掛ける、天然樟脳と樟脳オイルが
「Found MUJI Market」からご購入いただけます。
Found MUJI Market > 天然樟脳
Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 5ml
Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 10ml
世界にひとつの線香花火
線香花火で、誰が一番長持ちできるか。
そんな夏の一コマを思い出に持つ方も多いかもしれません。

手持ちで楽しむ玩具花火のなかでも、
線香花火は昔も今も変わらぬ魅力で私たちを楽しませてくれます。
ただ、打ち上げ花火は、現在も各地で催される花火大会で用いられますが、
玩具花火は、少子化や町中での火気制限なども相まって需要が低迷。
さらに、安価な輸入品の流入によって、
現在、線香花火を手掛ける花火製造会社は全国で3社を残すのみです。
そのうちの一社が、福岡県みやま市にある
筒井時正玩具花火製造所。
工場を訪ねると、3代目の筒井良太さんが笑顔で迎えてくださいました。

「かつては仏壇の香炉に、線香のように立てて楽しんだことから、
"線香花火"と呼ばれるようになったんですよ」
香炉に立てる?
私たちにとって身近な線香花火は、
柔らかい紙で包まれ、下に垂らして楽しむものでした。
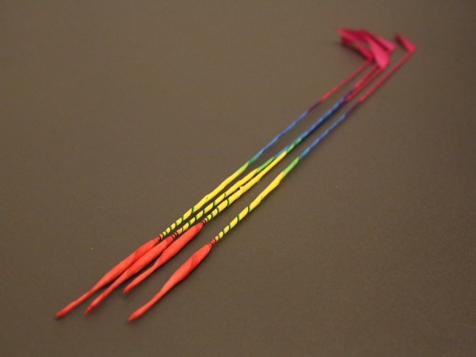
これは「長手牡丹(ながてぼたん)」と呼ばれる形状で、
関東地方を中心に広がったもの。
一方の、関西地方での線香花火といえば、
この「スボ手牡丹(すぼてぼたん)」が一般的だったそうです。
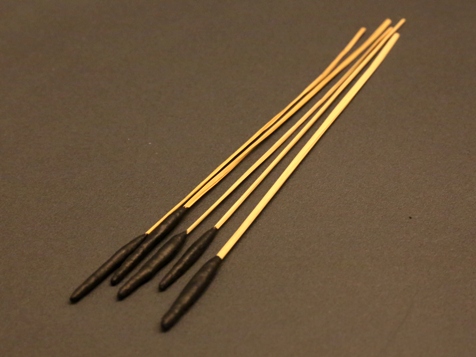
持ち手に紙ではなく、少し丈夫なワラが用いられているため、
香炉に立てることもできるのです。
この違いは、米作りが盛んだった関西地方では、
豊富にあったワラの先に火薬を付けて楽しんだのに対し、
米作りが少なかった関東地方では、
ワラの代用品として和紙で火薬を包んだためといわれています。
「現在では、中国産の輸入品が"長手牡丹"のため、
こちらの形状に見慣れている人も多いかもしれませんね」
良太さんがそう話す通り、関西地方特有の「スボ手牡丹」を作るのは、
全国でもここ筒井時正玩具花火製造所のみだそう。
実際に遊ぶ際には、先を少し上に向けて楽しむ方が、
玉が落ちにくく、火花が大きくなるんだとか。

関東地方出身の私たちにとって、
なんだか新鮮な線香花火の楽しみ方でした。
「主人は何度も研究を重ねて、今の火薬の配合に行き着きました。
それでもちょっとした火薬の量や紙の縒(よ)り方、
空気の状況によっても花火の咲き方が異なるんですよ」

そう話すのは、奥様の今日子さんです。
子育てにいち段落ついた今日子さんは、4~5年前から家業を手伝うように。
目の前で線香花火を作ってくださいました。
一つひとつのすべてが手作業です。
紙の上に少量の火薬を盛り、少しずつ縒っていくのです。
紙が尻すぼみの形で、半分しか染めていないのは、
必要最低限の原料を大切に扱う工夫でした。
1本の線香花火に用いられる火薬の量はわずか0.08グラム。
100分の1グラムの増減で、燃え方は大きく変わるというから、
日本人の繊細さを象徴しているかのようですね。
さらに、驚かされたのが、
「線香花火の一生には、人の人生になぞらえた
4つの段階があるんですよ」
と、今日子さん。
なんと、線香花火の燃え方には
段階ごとに名前が付けられているのです。
「蕾」とは、まるで命でも宿ったかのように、
火の玉が大きく育つ段階のこと。

やがて、迷いながらも一歩ずつ進む青春時代のように、
パチッパチッと力強い火花が散りだす「牡丹」を経て、

勢いを増し火花を咲かせる「松葉」を眺めていると、
結婚・出産・子供の成長といった、幸せなシーンを想起します。

そして、晩年の静かな余生を表すような「散り菊」。

最期は、おだやかに火花が散りゆき、やがて光を失うのです。
実にはかない線香花火の一生。
こうした花火に情緒を感じるのも、日本人らしさなのかもしれません。
「日本の花火の良さを伝えていきたい。
他では真似できない、オリジナルの花火を作れないものか」
そう考えた筒井夫妻は、徹底的に地域にある素材を見つめ直しました。
そこで見つけたのが、地元福岡産の八女和紙。
これを草木染めで色づけし、可愛らしいお花の形に仕上げると、
遊ぶだけでなく、眺めたり、贈ったりできる
唯一無二の線香花火が出来上がりました!

また、現在、工場の近くに、完成すれば日本初となる、
室内で花火が楽しめる建屋も建築中。

地元、筑後産の食を楽しみながら、
自身で線香花火を縒って楽しめるワークショップなども開催予定だそう。
「くじけそうになることもたくさんありましたけど、
足元を見つめ直したことで、歯車が回り始めました。
原料がないと始まらないし、買ってもらえる人がいないと始まらない。
人とのつながりを大切に、何よりも"内助の功"ですかね」

製造を中心に行う良太さんと、営業と販売を中心に行う今日子さん。
意見のぶつかり合いがありながらも、二人あきらめずに進んできたからこそ、
今の筒井時正花火製造所の線香花火がありました。
繊細でやさしい火花が咲き誇るのも、
夫婦の汗と涙が詰まっているからに違いありません。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
棕櫚たわし
掃除・洗い物・料理などに欠かせない、
くらしの道具、「たわし」。

現在、市場に出ているたわしの多くは海外製ですが、
今も国内で生産し、一部、原料も純国産にこだわる生産者がいると聞き、
現場を訪ねてきました。

舞台は、和歌山県の北部沿岸部に位置する海南市。
車で走っていると、山の斜面に
南国の空気を漂わせる植物が生えているのに気付きます。

このヤシ科の植物こそが、元来のたわしの原料である
「棕櫚(しゅろ)」でした。
棕櫚は、廃棄する部分がないといわれるほど、
利用価値の高い樹木として、古くから様々な道具に加工されてきました。
葉はハエたたきや草履に、棕櫚の木はお寺の鐘つき棒などに、
また、種は薬に用いられてきたそう。
そして、耐水性、耐腐食性に優れている、棕櫚皮の繊維は、
たわしやほうき、縄などに使用されてきました。

しかし、大量生産・大量消費の時代になると、国内での原料不足により、
海外産のヤシの実の繊維(パーム)に依存することに。
「うちも一時期は、パーム製のたわしを作っていました。
でも棕櫚の良さには敵わない」

そう話す、髙田耕造商店の代表・髙田英生さんに、
たわし作りの現場をご案内いただきました。
まず、毛捌き機を使って、棕櫚の皮の繊維を整えます。
太さのそろった繊維は、まるで馬の毛のようです。
続いて、短くカットした繊維を針金の間に均一の厚みになるように広げていきます。
この時、繊維の絡みをほぐしながら、適度な量を見極めるのが職人技。
この工程が、後から繊維が抜けにくく、
風合いの良いたわしに仕上げる1番のポイントだとか。
そして、棕櫚の繊維が均一の厚みに広がったことを確認したら、
コイル状に一気に巻き上げます。
繊維が抜けないようにしっかり巻き締め、
たわし用の散髪機にかけて繊維を整え、U字型に曲げたら、
ようやく見慣れたたわしの形状が見えてきました。

「棕櫚製のたわしは、細かくてしなやかな繊維が汚れをかき出すので、
力を入れなくてもよく落ちる。
硬いというイメージが強いたわしですが、
棕櫚は使い込むとさらに柔らかくなるんですよ」
髙田さんがおっしゃる通り、
これまで持つとチクチクした印象のあった、たわしですが、
棕櫚製のものを手にすると、ふっくらと優しい感覚が伝わってきました。
髙田耕造商店では、用途に合わせて様々なたわしを開発。

もともと棕櫚の皮は、雨風にさらされても大丈夫なように、
強くしなやかな特性を持っています。
そのため、パームたわしやスポンジなどに比べて、
棕櫚たわしは長持ちし、カビなども生えにくいといいます。
最近では、国産棕櫚を使ったボディたわし(写真上手前)が人気だそう。
「忘れ去られていた国産棕櫚を復活させようとした当初は、
周りから全然相手にされなかったんですよ。
それを息子が頑張ってくれましてね」
髙田さんがうれしそうに話してくれました。

髙田家の長男、大輔さんは料理人の道を目指しましたが、8年前に帰郷。
大好きな祖母と車で近所を走っている時に、
棕櫚を見て言われたある言葉に、はっとさせられたといいます。
「棕櫚のおかげで、おばあちゃんは髙田家にお嫁に来られたのよ」
家業の原点、すなわち自分のルーツにあった棕櫚の存在。
「その時、棕櫚山を守ることが、自分のやるべきことだと思ったんです」

大輔さんは、駆け回って、当時を知るおじいちゃんやおばあちゃん達を探しました。
そこで出会ったのが、峰伸汎さんです。
当時、峰さんは、これ以上使い道のない棕櫚をどうしていくか頭を悩ませており、
山を手放すかどうかのちょうど瀬戸際だったといいます。
「大ちゃんに出会うまでは、数十年、誰も棕櫚には構わなかった…」
一度は人々から忘れ去られてしまった、紀州の棕櫚でしたが、
髙田耕造商店の取り組みによって、再び日の目を浴びています。

しかし、大輔さんの挑戦はこれにとどまりません。
「日本で唯一の国産棕櫚を使用した、たわしを作るという夢は叶えられつつある。
ただ、僕の使命は、棕櫚山を再生し守ること。まだまだこれからです」
近い将来、海南市に新しい棕櫚産業が生まれているかもしれない、
そう思わせてくれる大輔さんの言葉と、
これからの髙田耕造商店の活躍に、とてもわくわくしてきます。
虎斑竹
「この道はひい爺さんの時代から、ずっと通ってきた道や。
随分、通りやすくなってるやろ」

そう言いながら、急な山道をぐいぐいと山奥へと向かっていくのは、
高知県須崎市にある、「竹虎」の4代目、山岸義浩さんです。
竹虎は、地元でしか生息しないという、
幻の「虎斑竹(とらふだけ)」を扱う竹材専業メーカー。
山岸さんいわく、昔から日本人のくらしに必要不可欠だった竹は、
日本各地に植えられ、竹林を築いてきました。
そして、ザルや竹籠をはじめ、ほうきの柄や、農作業用の熊手、
釣り用の竿など、くらしの様々なシーンで活用されてきました。
「今日は雨上がりやき、いい模様が出ちょります。これが虎斑竹ですき」
山岸さんが指さす虎斑竹は、
表面に虎皮状の模様が入っていることから、そう呼ばれるようになったとか。
興味深いのが、虎斑竹は全国的に見ても
高知県須崎市安和(あわ)の1.5㎞間口のエリアにしか、
生息していないということ。
これまでに何度か、各地に移植が試みられたそうですが、
綺麗な模様が出ることはなかったそうです。
「なぜかは分からんがです。
学者によると、この山の土着菌による作用とも言われちょります。
なんにせよ、昔から貴重な竹として扱われちゅうがです」
かつて土佐藩の年貢としても納められていた虎斑竹は、
日用の道具としてはもちろんのこと、茶菓道の竹器や装飾用の建具としても
重宝されてきたといいます。

「自然が生み出す、2つとして同じでない模様は、
日本人の美意識に通じるものがあるがではないろうか」
山岸さんがそう話す通り、
虎斑竹は一本一本独特な個性にあふれています。

この個性を最大限引き出してあげるのは、熟練の職人技。

1本1本、火であぶりながら油抜きし、
その熱を利用して、ため木を使ってまっすぐに矯正していくのです。

「ここにしかできない竹やき、少しでもいいから残していきたいがです」
竹は自生する植物ではなく、人の手によって植えられてきたものです。
しかし、様々な工業製品が生まれてくると、
いつしか人々は竹林から離れるように。
すると、全国各地の竹林は荒廃し、
繁殖力の強い竹は、他の木々にまで影響を及ぼしているのが現状だといいます。
「けんど竹はそれだけ再生可能な資源とも言えますぞね。
3か月で親竹と同じ大きさに育つし、3~4年で製品に加工できる。
まさに無尽蔵の資源といっても過言ではないがです。
竹林の保全のためにも、竹の使い道を考えないとイカンがです」
そう話す山岸さんは、竹の需要を最大限開拓すべく、
竹細工の他に、竹の持つ抗菌性や消臭性を活かした竹炭や、
竹の葉を使ったお茶など、様々な竹のあるくらしを提案していっています。
「青竹踏みって知っちょりますか?ありゃ気持ちエイですろう。
最近の若い人は踏んだことがない人もいると聞くがです。
自分の使命は、竹の良さを今の人たちにも伝えていくことだと思うちょります」

まさに竹を割ったような性格の山岸さん。
「竹のようにありたい」と話すのは、
その多くが同じ根から生えている竹のように、
皆で手を取り合ってまっすぐに伸びていきたいという意味でした。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
丁寧に暮らす
森林率84%の高知県。
なかでも、県北部で四国のほぼ中央に位置する嶺北地域は、
森林率90%という山深い場所です。

「この辺りは"高知のチベット"って呼ばれています。
知る人ぞ知る、日本最大の棚田もあるんですよ」
この時期の棚田は、残念ながら稲を刈り取った後でしたが、
水を張った時期や、緑もしくは黄金色に輝く棚田をぜひこの目で見てみたい!
と思わせる景色がそこに広がっていました。
ご案内いただいたのは、本山町に拠点を構える
「ばうむ合同会社」の代表・藤川豊文さん。
横浜の建築会社に13年勤めた後、地元である本山町に戻り、
それまでの仕事とのスピード感の違いやギャップに違和感を抱きながらも、
商工会の青年部の仲間と一緒に、地元でしかできない"何か"を模索します。
そして、視察で訪れた栃木県粟野町(現・鹿沼市)でヒントを得て始めたのが、
地元の杉を使った家具づくりでした。
「子どもたちが少ない山間部だからこそ、大切な子どもたちへ
"人の本質を育てる教材"としての学習机と椅子を作りたいと思いました」

藤川さんは、地元の杉製の家具を通じて、
"一つひとつ違うといった個性"や、"モノを大事に使うという心"を育てたい、
と話します。
一般的に、杉材は柔らかく、耐久性を維持するのが難しいのですが、
香りが立って、優しく温かいという利点もあります。
藤川さんたちは、あえて自然のままの杉材の木目を強調した机と椅子に仕上げ、
丁寧に扱わないと、汚れや傷が目立つ仕立てにしました。

今では、地元の小学校や中学校に納品され、
子どもたちは、地元の素材に触れながら、
教科書には載っていない価値を学び始めたといいます。
そして、ばうむ合同会社の手掛ける
間伐材を使ったものづくりのなかで、一際目を引いたのがこちら。

「忙しい日常のなかで、
手にするとホッとするような、自分が欲しくなるようなものを考えました」

そう話す、制作部の門田恵美さんが手掛けたのが、
木でレース編みの模様を表現した「moku-lace(もくレース)」コースターです。
もくレースのコンセプトは、
「丁寧に暮らす 大切に暮らす」。
割れにくい、壊れにくい便利なものに囲まれていると、
つい粗雑にものを扱いがちだと、門田さん。
「もくレースが、気に入ったものを大切に使うという、
丁寧な暮らしへのキッカケになればうれしいですね」
とその想いを語ってくださいました。
そんなもくレースには、間伐材のなかでも
家具などには使用できない、できるだけ小径木を利用。
張り合わせて一枚板にしてから加工していました。
杉製なので軽く、とても繊細。
だからこそ、大切に扱おうという想いが芽生えるように思います。
コースターの他にも、花瓶や植物のプランターマットとしても使えるので、
日常のなかに「丁寧に暮らす」という概念が溶け込みますね。

今年で活動10年目を迎える、ばうむ合同会社。

「林業は衰退しているとよく言われますが、
今はまだ人工林が育っていない状況なだけなんです。
林業はまだまだこれからの産業だし、人間の責任として、
森林の手入れをしていかないといけません。
今後も楽しみながら、地域に雇用と所得を生み出していきたいです」
そう、藤川さんが語るように、
豊かな自然に囲まれた本山町では、
木に触れられる、ぬくもりのある丁寧な暮らしが始まっていました。
墨の可能性
その工房を訪ねると、
中にはまるで白黒写真で撮影したかのような光景がありました。

あえて黒を基調にした空間にしていたわけではなく、
工房で製造されるものによって、だんだんと黒ずんでいったんだそう。
そう、ここは三重県鈴鹿市寺家にある、墨づくりの工房です。

「鈴鹿墨」
1200年以上前から鈴鹿の地で作られているといわれ、
墨としては唯一、国の指定する伝統的工芸品です。
「かつて都のあった場所の近くでは、必ず墨が作られていたんですよ。
公文書に欠かせないものでしたから。この界隈にも7~8軒の墨屋がありました」

そう話すのは現在、鈴鹿墨を生産する唯一の工房、
進誠堂の3代目、伊藤亀堂さん。
気さくな笑顔と豪快な話しぶりが印象的な方です。
江戸時代、墨が一般大衆にも用いられるようになると、
製墨に必要な松や弱アルカリ性の水に恵まれた鈴鹿は、
紀州藩の保護のもと、墨づくりが飛躍的に発展していきました。
「バブル期には飛ぶように売れていました。
子供の習い事といえば、そろばんか習字だったでしょ」
しかし、子供の習い事も多様化し、徐々に需要が低迷。
墨の代わりに簡易な墨汁が用いられることも増え、
一軒、また一軒と、墨屋は姿を消していったそうです。
「ネットのニュースで、鈴鹿墨衰退の記事を読んだんです。
1200年続いてきた伝統がここで途絶えてしまっていいのか。
居ても立ってもいられなくなり、実家へ戻ってきました」

伊藤亀堂さんの息子で、進誠堂4代目の伊藤晴信さんは、
東京での仕事を辞めて、2010年に帰郷しました。
今では中国市場の開拓など、鈴鹿墨の発展に尽力しています。
こうして親子で励む製墨は、早朝4時頃から始まります。
「墨づくりは、寒い冬の時期だけなんです。
それも早朝の空気が乾燥している時間が、一番適しています」
晴信さんに、その一部始終を見せていただきました。
墨の原料は、様々な木から採取する煤(すす)と、
膠(にかわ)と呼ばれる、動物の皮や骨から抽出されるコラーゲンを濃縮したもの。
この膠を水で溶解したものと、煤と香料を混合し、
入念にもみ上げていきます。

「はじめは簡単にできると思っていましたが、大間違いでした。
すりやすい墨を作るためには、このもみ上げの工程が大切で、
中の空気を抜いて、柔らかく仕上げなくてはなりません。
最初の頃は、筋肉痛で体がバッキバキでした…」
もみ上げた墨玉は、艶やかに黒光りしています。
原料が均等に練り上げられ、この光り輝く瞬間の見極めが大切なんだそう。

これを型入れして、万力で挟むこと10分。
型から外すと、見慣れた墨が姿を現しました。
ただ、まだこの時点では墨はまだ柔らかい状態です。
ここから灰をかぶせて徐々に水分を除き、
それをさらに室内干しで2~4カ月乾燥させていきます。
墨は寝かせれば寝かせるほど、人の手では取りのぞけない不純物が抜け、
より純度の高い墨へと変化していくのだそうです。
そして、磨きをかけ、装飾を施して、
ようやく墨として市場に流通していきます。

「日本の墨は"正直"だと、中国では褒められます。
むこうでは乾燥過程で曲がったものなども、多くありますからね。
まぁ、こんなもんでいいか、とならないものづくりが、日本らしさだと思っています」
晴信さんがそう話すように、
鈴鹿墨は原料加工から製品化まで、妥協を許さず一貫して行われていました。
「他の産地では分業制が敷かれているなか、この一貫製造こそが、
一つひとつ、異なる墨を作ることができる産地の特徴でもあるんです」
それに気付いた3代目の亀堂さんは、墨の需要を拡大すべく、
これまで、「1分ですれる墨」「にじまない墨」など、
より使いやすい墨を作り出していました。
なかには、こんなものまで。
多種多様な植物の煤を使った墨や、
煤の代わりに顔料を加えることで実現した、ラメ入りのカラー墨です。
「書道以外にも使えるということを示したかったんです。
気付いたら身の回りにある存在であってほしい」
そんな亀堂さんの想いに応えるかのように、
晴信さんが、墨を使った香袋や墨染めなども商品化していました。
「これからは今一度、原点に立ち返って、墨づくりをしていきたいんです。
命名、遺言、家系図など、人生の大事な節目では必ず墨を使ってもらいたい。
そのために、書道のハードルも下げなくてはいけないし、常に新しい墨を追求していきます」

代々、守り継がれてきた鈴鹿墨は、
親から子へ、さらなる可能性を広げて、つながれていこうとしていました。
思えば、年初めの書き染めでも、墨をすりながら精神を統一し、
今年の抱負を考えている自分がいることを思い返しました。
墨をする時間というのは、何かを記す時にふと立ち止まって考えられる、
貴重な時間ではないでしょうか。
そこには、墨匠たちの、
細やかな配慮と繊細な技が宿っていることを忘れないようにしたいです。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
瀬戸本業窯
800年の歴史と伝統を誇る「瀬戸焼」。

瀬戸焼が"せともの"として陶磁器の代名詞となるなど、
幅広く全国各地に広がっていったのは、
名古屋という大都市に近いことと、純白で良質な陶土が採れたことからだそう。
瀬戸焼はその長い歴史のなかで、1つの産地としては珍しく、
あらゆるジャンルのものを作ってきました。
鎌倉時代には、日本で初めて釉薬を使った焼き物を作り、
耐水性のある実用としての器の可能性を広げました。
また、日本の水回りタイルの第1号も瀬戸で生まれ、
国内のトイレタリー環境の衛生に一役買ったり、
私たちの生活に欠かせない電気を、各家庭に供給するのに必要不可欠な
碍子(がいし)を生み出したのも瀬戸焼でした。
1800年以降に瀬戸に磁器の技術が入ってくると、磁器生産が本格化。
旧来からの瀬戸の陶器を「本業焼」、
磁器を「新製焼」と呼んで区別するようになります。
「うちが本業を守っているのは、
民芸運動の柳さんとの出会いがあったからだと思っています」
この地で250年以上続く「瀬戸本業窯」の8代目、
水野雄介さんに工房をご案内いただきました。

時代の潮流を捉えた新製焼を手掛ける窯元が増えるなか、
瀬戸本業窯はその名の通り、瀬戸本来の日用雑器づくりを生業にしてきました。
今も昔もその生産スタイルは変わらず、
土づくりも釉薬づくりも自分たちで行っています。
釉薬には、アカマツの灰をベースに使うのですが、
右上の写真の量の木材でどんぶり2杯分のマツ灰しかとれず、
年間約400杯のマツ灰(およそ1トン)が必要になるというから驚きます。
 灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿
灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿
「本業焼の美徳は、最低限の手数と材料で、量を生み出すこと」
と雄介さんが話す通り、仕事は分業制で、
作り手は日々繰り返しの修業のなかで、
いいものをスピーディーに作れるようになるといいます。
そうした積み重ねのなかで、徐々に余分なものが削ぎ落され、
本業焼の代表的な「馬の目」(写真左下)や、「麦藁手」(写真右下)といった
シンプルなデザインの器が生まれていったそう。
「反復で早く描けるこれらの柄は、
恐らくデザイナーには生み出せないデザインでしょう」
と、雄介さん。
こうした本業焼のスタイルに目を留めたのが、
先に述べた民芸運動の創始者・柳宗悦氏です。
 (左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)
(左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)
雄介さんの祖父で、6代目・水野半次郎さんの時代に、
柳氏と出会った瀬戸本業窯は、その後も民芸の思想を大切に
瀬戸本来の本業焼を生み出し続けてきたのです。
また柳氏は、瀬戸本業窯のある洞町(ほらまち)の街並みにも感激したといいます。
町を歩くと、この地で窯業が盛んに行われていた歴史を物語るように、
窯を焼く際に使用した窯道具の廃材を積み上げて築かれた「窯垣」を目にします。
この光景を見た柳氏は、
「ここでは一体どんな仕事が行われているんだ…」
と感嘆の声を上げたんだそう。
しかし、地元の人には身近な光景であり、
住民は特に気にすることなく、窯垣を取り崩す人もいました。
そこで立ち上がったのが、雄介さんの父親で7代目・水野半次郎さんでした。
今から20年ほど前に、7代目・半次郎さんが地域住民に呼びかけ、
洞町の景観を守る活動を行ったのです。

「うちの窯は民芸運動があったから活性化したというより、
もともとやってきたことが評価されたということが後から分かりました」
7代目・半次郎さんは、家業に入る前に他の産地に修業に行き、
いくつかの窯元を見て回ったそうなのですが、
勉強しにいったつもりが、逆に瀬戸のすごさを思い知ることになったんだそう。
ちなみに、瀬戸本業窯では、代々当主に「半次郎」の名が引き継がれています。
戸籍そのものから変えるといい、これはとても珍しいことだといいます。
250年以上のあいだ、「水野半次郎」によって守られてきた瀬戸本業窯。
「この先もずっと瀬戸本業窯を続けていくために、
仕事のやり方は変えずに守っていきたいと思います」

最後に8代目・半次郎後継の雄介さんがそう話してくれました。
当主の名を統一することで、個性を出さずに、
元来の本業焼を守り続けているその姿にこそ、
8代にわたって続いている秘訣が隠されているように感じました。
そして、雄介さんの言葉からも、瀬戸本業窯が
未来においても変わらずに続いていくことを容易に想像させてくれます。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
伊勢型紙
染色道具のひとつである「型紙」。
和紙を柿渋で加工した型地紙に、
彫刻刀で繊細な紋様や図柄を彫り抜いたものです。

もともと着物などの生地を一定の柄や紋様に染色するために使われるものですが、
全国を回ってみて、布だけでなく、焼き物や革製品など
その使われ方の幅がとても広いことを知りました。
また、型紙のほとんどが三重県鈴鹿市の白子(しろこ)地区で生産されている、
通称「伊勢型紙」であることも各地で耳にしてきました。
「伊勢型紙の歴史は、1000年といわれていますが、
個人的には500年ほどだと考えています。というのも…」
伊勢型紙の歴史から丁寧に教えてくださったのは、
オコシ型紙商店の起(おこし)正明さんです。

これまで見てきた地域の伝統産業は、その成り立ちの背景に、
風土が適していたことや原料が採れたことなどが関係していました。
しかし、鈴鹿市は型紙の原料である和紙や柿渋の産地でもなく、
地域で染物業が盛んだったわけでもないのに、型紙の一大産地になったのだそう。
「伊勢型紙の発祥には諸説あるのですが、
恐らくキッカケは、応仁の乱ではないでしょうか。
京都から型を彫れる職人さんが散らばったのが起源ではないかと思っています」
起さんは、伊勢が型紙の産地に発展したことには
2つの要因があると話します。
1つは、白子町が江戸時代に入り、紀州藩の天領となり、
紀州徳川家の庇護のもとに置かれていたこと。
2つには、伊勢商人の存在です。
彼らは、紀州藩から「鑑札」を与えられていたため、
全国どこへでも行商ができたし、泊まる宿なども優遇されたというのです。

伊勢型紙の業界は、型地紙の製作業者、型紙を彫る職人、
そして図案の企画を行い、染物屋に販売する問屋からなります。
「伝統産業について語られる際にフォーカスされるのは職人です。
もちろん技術の継承も重要ですが、そもそも売れないと産業ではありません。
文化と産業は違うので、流通させなければ始まりませんから」
起さんは問屋の3代目。
今年で50歳を迎えますが、伊勢型紙に携わるなかでは、最年少だそう。
バブル期の終わりに家業に入った起さんは、
ここ10年でニーズが大幅に減少し、危機感を持つようになったといいます。
和装用としては、現在、20年前のおよそ10%しか製造できていないというから深刻です。
頭を悩ませた起さんは、伊勢型紙の染色道具として以外の使い道を模索。
マーケットを海外にまで広げ、2010年にフランスのインテリア&デザイン関連見本市に、
2011年には、同じくフランスのテキスタイル国際見本市に出展し、
建築・内装、テキスタイルのデザインソースとしての可能性を探りました。

そんな折、2012年に三菱第1号美術館、京都国立近代美術館、三重県立美術館で
「KATAGAMI Style ー もうひとつのジャポニスム」
と題した巡回美術展覧会が行われました。
江戸後期に、「浮世絵(UKIYO-E)」とともに海外に渡った「型紙(KATAGAMI)」が、
世界の美術やデザインに与えた影響を垣間見ることのできる内容で、
起さんいわく、この展覧会が世間に対して
デザインとしての伊勢型紙の可能性を示すキッカケになったのだとか。
起さんは伊勢型紙のデザイン性を活かすべく、
地元のデザイン会社と組んで、アルミ削り出しのスマートフォンケースなどの
開発に勤しみます。

「それでもやはり道具・デザインとしての使われ方の域を越えられません。
今後は型紙そのものを活かした商品を開発していきたいですね」
オコシ型紙商店には、創業以来作りためてきた型紙が約数万点あります。

「型紙は立体でなく、色も単色。
しかし、同じ柄をリピートすることができる、
"エンドレスピクチャー"という魅力があります」
伊勢型紙は一見すると、長方形の中に描かれた
一つの作品のようでもあるのですが、

柄の下部と上部がピッタリ合う仕立てになっているのです。

これこそが伊勢型紙の真髄である、と起さんは話してくれました。
「伝統を守ることの難しさを痛感しています。
攻めることは案外簡単。
引き継がれてきたものを守りながらも、次なる展開に
引き続き、もがいていこうと思います」
和紙と柿渋という自然素材から、
彫刻刀だけを使ってここまで繊細な柄を生み出してきた、伊勢型紙の世界。
この細かい作業を実現できるのは、日本人のきめ細やかさや
粘り強さがあってこそだと思います。
しかし、一目瞭然である美しさや技術の素晴らしさとは裏腹に、
生活スタイルや先端技術が生まれている現代社会において、
これをどう活かしていくかが、まさに今後の鍵。
この答えを探すことは、産地の人たちだけでなく、
全くの異業界出身者や生活者の私たちにもできることかもしれません。
現在、伊勢型紙を彫れる職人の平均年齢は70歳を超えているそう。
500年の歴史を生かすも殺すも、
この先10年にかかっているという事実を突きつけられました。
木を操る、木地師
国土の約3分の2が森林といわれる日本では、
古くから木の恩恵を受けて、暮らしてきました。
その一つが木器。
木器は、その製法によって大きく5種類に分けられます。
板材を組み合わせて作る「指物(さしもの)」、
薄板を曲げて作る「曲物(まげもの)」、
刀やノミなどで木を刳(く)り抜いて作る「刳物(くりもの)」、
短冊状の則板を円筒状に並べて竹などで作ったたがで締めて、
底板を取り付けて作る「結物(ゆいもの)」、
そして、轆轤(ろくろ)を用いて作る「挽物(ひきもの)」。
挽物といえば、汁碗などに多く用いられますが、
日本におけるその一大産地が、石川県加賀市にある山中温泉地区です。
ここは全国の挽物産地の中でも、群を抜いた職人の規模や質を誇ります。

山中温泉地区の挽物産地としての歴史は400年以上にわたり、
安土桃山時代に、良木を求めてやって来た木地師たちが
山中温泉の上流の村に移住したことから始まったといわれています。
「各地の木地師がいなくなってきてしまっているなか、
挽物について学ぶにはここしかないと思いました」

愛知県出身の田中瑛子さんは、高校時代から漆器に興味を持ち、
地元の大学で漆芸を専攻します。
しかし、実際に塗りをやってみると、立体を作る方が好きということに気付き、
大学卒業後に、全国で唯一、挽物轆轤技術を専門的に学べる山中の研究所に入所。
そして7年間研修所と師匠のもとで学び、2012年に木地師として独立されました。
「他の産地は器に対して木の繊維が並行に入った
"横木"(写真下右)を使うのが一般的ですが、
山中は繊維が垂直に入った"竪木"(写真下左)を使うのが特徴なんです」

田中さんいわく、竪木取りの特徴は歪みが少なく、
お椀や茶筒などの高さがあるものを作る場合に
薄挽きにしても縁が強く欠けにくいので軽く仕上げることができるそう。
ただし、竪木は木の半径の幅までしか使えないので、
大きいものを作るためには、大木が必要になるんだとか。
木地師の技は鍛冶仕事から始まるといい、
ベースとなるカンナを曲げられるようになるまで、数年はかかるといいます。
ベースの形はみんな一緒なのですが、
ちょっとした角度などは個人の癖や体型にあわせて変えるので
自分にベストなものを曲げられる様になるのに苦労するそう。
道具づくりが終わると、ようやく挽きの作業。
ここでも山中という産地だからこそのシステムがある、と田中さんは話します。
「山中には、木地屋さんが共同出資して作った製材組合があり、
原木の仕入れから"荒挽き"といわれる状態まで加工してくれています。
私は"荒挽き"を仕入れて、これをさらに加工していきます」
工房内には、ぎっしりと"荒挽き"が積まれていました。
荒挽きを専門に作る作業所があるので、
木地をよりスムーズに周期的に生産することができるのです。
「木地の仕事はマイナスなんです。
削っていって一番いい形になるのは一瞬だから、緊張感を持ってやりますね。
私たちの仕事は"早く、きれいに、揃っている"というのが腕の証。
いかに一瞬で形を見切りサッと決めるかが重要ですが、
日々の訓練のなかで、体で覚えていき、同じものがいくつも作れるようになります」
田中さんがカンナを巧みに操ると、
シャーシャーと音を立てながら、きれいに表面が剥けていきます。

一見、力のいる作業に見えますが、カンナの角度がうまく合っていれば、
力を入れなくても自然に削れていくんだそう。
さらに小刀を使って表面を削いでなめらかに。
すべすべお肌の可愛らしいフォルムの出来上がりです!

「木の個性を感じながら挽くのが楽しいです。
木目は二つとして同じものはありませんから。
こうした木目を楽しめるのは、木地師ならではの特権ですよね」
作家としての一面も持ち、漆塗りの工程までこなす田中さんですが、
その作品からは、木地師らしさがにじみ出ていました。

というのも、どれも木目の面白さを感じられる作品ばかりなのです。
田中さんは珍しい木目の材木を見つけるたびに、ストックしていき、
木の味を楽しめる作品を作り続けています。
そんな田中さんに今後の目標を伺いました。
「何があっても作り続けていきたいと思っています。
先生たちや師匠が長年研究してきた技術を引き継いでいるわけだから、
その技術のレベルをきちんと次に伝えられるようにしていきたいですね」

そう話す田中さんの作った木地は、大半が県外の塗り師へと渡り、
最終的に全国のお客様の手元に届いているそうです。
「職人としては、お客さんの手となり自分の意思を消して効率と均一を意識します。
作家としては、いかに自分を木で表現するかを大切にじっくり木に向かいます。
木を挽く姿勢としては正反対なものですがどちらも重要。
私の中ではどちらもあるからバランスが取れているのかもしれません」
私たちが普段触れている汁碗などは、
木と向き合い、それを操る木地師によって、
木に新たな息吹を与えるところから始まっていることを改めて知りました。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が
ご購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに
産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
現代の風呂敷
モノを持ち運ぶとき、今でこそ鞄に入れるのが当たり前ですが、
一昔前の日本では、少し様子が異なったようです。

そう、「風呂敷」に包んでいたのです。
もちろん、鞄も普及していたようですが、
鞄に入りきらないモノや、ちょっとした買い物などの際には、
風呂敷に包んで持ち運ぶのが一般的だったそうです。
それぐらい風呂敷は、日々のくらしで欠かせない日用品だったため、
地域のたばこ屋さんでも売られていたんだとか。
ただ、レジ袋や紙袋の普及によって、急速にその需要が低迷。
高価な着物をしまっておくときや、
結納の際に、贈答品を家紋入りの風呂敷に包んで贈るときなど、
特別なときにしか使われなくなってしまいました。

そんななか京都に、
異彩を放つ風呂敷屋があると聞いて訪れました。
「京都 掛札」
祇園の交差点から東大路通を北に向かって程なくすると、
見るもカラフルな店内に目を奪われました。

一見、鞄のように見えますが、
実はこれらはすべて風呂敷を結んだだけのもの。

柄も日本の伝統文様を現代風にあしらったものでした。


- 麻の葉
- 七宝
「日本の伝統文様には、それぞれ意味合いが込められているんですよね。
せっかくだから、それらを広く知ってもらいたかった」

例えば、蝶柄であれば、一度さなぎになって華麗に生まれ変わる神秘的な姿を
不滅・復活・立身出世にたとえて武家の家紋や意匠に好まれたそう。
また、つがいで飛ぶことから夫婦和合を、
幼子の衣装の文様として美しい成長を願ったといいます。
デザインを手掛ける3代目の掛札英敬さんが、
その想いを語ってくれました。
もともと染物屋として、家紋入りの絹の風呂敷を手作りしていましたが、
10年ほど前から、こうしたカラフルでポップな木綿の風呂敷も手掛けるように。
現在も、おあつらえ専門でお父様と染色の仕事を受けつつ、
家族で日用使いできる風呂敷を提案していっています。
そもそも風呂敷という名は、室町時代末期に、大名が風呂に入る際、脱衣した服を包んだり、
足拭きに使われたりしたことに由来するといわれていますが、明確ではないそう。
その後、江戸時代に入り商売が盛んになると、商売道具や商品を運ぶ運搬道具として、
また、庶民のあいだでもやはり日常の運搬道具として、支持されていったそうです。

風呂敷なら縦横傾けることなく、
縦長のモノも横長のモノも、包むことができますよね。
「何も風呂敷は日本独自のものでもなく、世界各地に似たようなものはあるんです。
お隣、韓国には"ポジャギ"と呼ばれる包み布があったり」
英敬さんは、こうした文化は農耕民族であることが大きく関係しているといいます。
狩猟民族は、食糧調達の際に副産物として得られる毛皮を、
目的に合わせて裁断して縫合していたため、ごく自然に立体的なものが生み出されました。
一方の農耕民族は、農作物の繊維から布をつくるという風習だったため、
原料となる作物をつくる必要があり、そこから糸を紡いで、一枚の布を織り上げたわけです。

せっかく苦労して織り上げた布を、一度切って袋状にしてしまうと、それ以外に使えない。
平面であれば、包んだり敷いたり掛けたりと、応用次第で様々な使い方ができる。
こうしたモノを作り上げる大変さが、
モノを工夫して大切に使う文化を育んできたのではないか、
ということなのです。
「ただ、この平面から立体をつくるというのは、
特に日本で顕著に見られる文化だと思いませんか。
着物も、帯も結ぶことで立体的に見せたり、折り紙にしたってそうでしょ」
そう話しながら、英敬さんは目の前で一枚の風呂敷を、
バッグのように仕立ててくれました。
「少しアレンジを加えたところもありますが、結び方は昔から伝わっているものですよ。
欧米人には、よくマジックだ!って言われます。
結び方を知っているだけで、一枚の風呂敷は様々な形に化けるんです」
確かに、風呂敷一枚で、ここまで多様な使い方ができるとは…
目からうろこが落ちるような発見でした。
「風呂敷を初めて使う人に提案していきたいんです。
そのためには、パッと見でかわいいと感じるデザインも大事だし、
包み方までキチンと伝えていきたい」
そう話すように、英敬さんはHPや店頭で包み方の指導はもちろんのこと、
「風呂敷のある風景」として、現代における風呂敷の日常使いを訴求していっています。
日本で育まれてきた、平面から立体を生み出す風呂敷は、
繰り返し使えてエコという観点からはもちろんのこと、
便利でかわいい、日常使いのできる代物であることを教わりました。
【お知らせ】
MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が購入いただけるようになりました!
その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。
[特設サイト]Found MUJI Market
革新する高岡の伝統
大みそか、日本全国で響き渡った除夜の鐘。

昔から慣れ親しんでいるせいか、
この音色を聞くと、年越しの気分が一気にわく気がします。
実はこの除夜の鐘、その多くが、
富山県高岡市で作られていることをご存じでしょうか。
高岡は全国で生産される銅器の約95%を占める一大産地。
江戸時代、加賀藩2代藩主の前田利長によって町が開かれて以来、
鋳鉄の原料となる砂鉄、燃料の薪炭、保温材のわら灰、
鋳型をつくる川砂などを得やすかった高岡は、
鋳物の産地として発展を遂げていきます。
高岡駅近くに建立されている「高岡大仏」は、
高岡の職人の技術を結集してつくられたものでした。

そんな高岡の地で、鋳物の技術を活かしつつ、
革新的なものづくりを続ける企業があります。
今年、創業98年を迎える鋳物製造の老舗
「株式会社 能作」。
「うちには営業はいないけど、富山県民がみんな営業してくれるんですよ」

5代目を担う能作克治社長がそう語ります。
能作が最近世を騒がせ、富山県民が胸を張って「富山産だよ」
と周りに話したくなるものが、こちら。

錫製の曲がる器です。
金属なのに、人の力で自在に曲げられます。
使う用途に合わせて、形状も自由自在。
「食器=硬い」という固定観念を見事に覆されましたが、
こうした革新的な器が生まれた背景には、
挑戦し続ける伝統産業の姿勢がありました。
「日本の伝統産業はもう下火といわれていた時代にも、
私たちは横ばいか、少し右肩上がりの業績でした。
日本のものづくりの技術は世界一なんです」
福井出身の新聞記者から一転、婿養子として能作に入社した能作社長は、
17年間、職人として高岡の鋳造技術を教わったといいます。
「富山では、県外から来た人のことを"旅の人"って呼ぶんですよ。
言い換えれば"よそ者"です。ただ、同業者には教えないようなことも、
僕には教えてくれた。だから僕は、そんな高岡に恩返しがしたいんです」
グローバル経済が進み、中国の台頭が顕著に見られるなか、
高岡銅器も他産地と同様に、衰退の一途をたどっていました。
そんななか、能作社長がとった戦略は、多品種少量生産。
それも、一度は機械化した工場を、今一度手作りに戻すほどの徹底ぶり。
「少ロットでも、品質の良さで勝負するしかないと思ったんです。
手作りに戻すことで、職人の技術もさらに磨かれるようになっていきました」
工場に保管されている4000にも及ぶ鋳型が、
まさにその戦略を物語っていました。
ひたすら技術を磨き続けていくなか、やがて能作社長に
「ユーザーの声も聞きたい」という想いが芽生えていきます。
「当時は問屋さんから言われたものを作るだけでした。
ただ、売れなくなったら、末端は何もできないんですよね」
その状況に歯がゆさを覚えていたと話す能作社長のもとに、
2001年、東京で展示会開催のチャンスが訪れます。
それまで仏具や花器を手掛けていた能作でしたが、
これを機に社長直々に新しい製品の開発に乗り出し、
作り上げたのが、このハンドベルでした。

「これが大失敗だったんです。
だいたい家でハンドベル鳴らして奥さん呼んだ日には、
代わりに皿でも飛んできそうでしょ(笑)」
しかし、このハンドベルを見たある店員さんからのアドバイスで、
またたく間にヒットする商品が生まれるのです。
それが「風鈴」。

「風鈴は"鉄"だっていう、勝手な固定観念があったんですね。
私たちが手掛けていたのは"真鍮"でしたから。
この時に、売り場の店員さんはユーザーの志向を知っているんだな、
ということを学びました」
この学びから、今度は「身近な食器を作ってほしい」
という店員さんからの依頼に耳を傾ける能作社長。
真鍮や青銅は口にする食器としては適しておらず、
そこで、考えられたのが「錫」でした。
「当時、高岡の技術では錫は鋳造できないといわれていました。
それを実現できたのも、技術を磨いてきたからでしょう。
ただ、錫100%だとどうしても柔らかすぎて、曲がってしまったんですね」
それを、特徴と捉えるまでに、さほど時間はかからなかったそう。
「曲がるんなら曲げて使えば?
とデザイナーの小泉誠さんにアドバイスいただいたんです。
なるほど、とすぐに受け入れられたのも、
私自身が異業種出身だったからかもしれませんね。
以来、一歩俯瞰して見ることが大事、ということを知りました」
こうして錫100%の、曲がる器が誕生したのです。
今では、高級レストランから特注で発注がくるほど、
売り上げも青銅や真鍮をしのぐまで伸びてきているんだとか。
最近では、金属製の日用品になじみのある欧米を中心に仕掛けも始め、
Made in Japanを、また、高岡の名を世界に広めていっています。
そして、今になってあのハンドベルが海外で売れ出しているそう。
「高岡がなければ、能作は絶対に成り立たない。
そういった意味でも、"伝えられる生産者"でなければなりません。
そのためには、モノの良さはもちろんのこと、コトと心が大切。
コトとは、高岡の伝統産業の技術。そして、心とは職人の想いです。
これからも"攻める"伝統産業であり続けたい」

終始、穏やかなトーンで話される能作社長でしたが、
その内に秘める想いには、並々ならぬ熱意を感じました。
「これからは"競争"ではなく、"共想""共創"の時代。
高岡の同業者と協力して頑張っていきたいですね」
革新し続ける伝統産業の背景には、
高岡に対する誇りと感謝の念が込められていました。
日本の縁起物「キナキナ」と「うるしダルマ」
よいことがあるようにと祝い祈るための品物、「縁起物」。
それらの対象は五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、無病息災、子孫繁栄…
などで、多岐にわたります。
私たちの身近なところでいうと、
"年越し蕎麦"やお食い初めの"鯛"なども縁起物ですし、
居酒屋やお店の軒先でよく見かける
"たぬきの置物"や"招き猫"などが代表的です。
また、各土地によって異なる縁起物が存在するのも
面白いところかもしれません。
例えば、東北地方のこけし。

もともとこけしは、江戸時代後期、木地師が東北の温泉地で、
湯治客や子供相手に作ったのが起源とされます。
ある記録によると、こけしのことが「こふけし(こうけし)」と記されており、
「子授けし」、つまり子供を授かるというお祝いの意味で、
こけしは子供の健康な成長を願うお祝い人形とされている説もあるとか。
こけしの顔や形、模様は産地ごとに様々で、
青森の津軽系、宮城の鳴子系、山形の蔵王系など11系統に分けられていますが、
今回は、岩手県花巻市に、南部こけしの職人を訪ねました。
新花巻駅から車ですぐ、宮沢賢治記念館の隣にある工房へ一歩入ると、
なんだかそこはおとぎ話の世界のようです!

「"こけし"という呼び名は昭和15年に鳴子で行われた会議で決まったんですよ。
この辺りでは首が動く様子から"キックラボッコ"や"キナキナ"と呼ばれています」
作業の手を止めて、南部こけしについて教えてくださったのは、
工房木偶乃坊(でくのぼう)の煤孫盛造(すすまごもりぞう)さんです。

煤孫さんは3代目で、おじいさんが大工さんに依頼された木地仕事の空き時間に、
"キナキナ"づくりをしていたといいますが、この趣がまた珍しい。
こけしというと、細い目におちょぼ口の愛くるしい少女の表情が浮かびますが、
"キナキナ"は、顔や胴の華やかな模様が一切描かれていない
とてもシンプルなものなのです。
また、頭が小さく胴の下部がくびれた形も特徴的。

というのも、"キナキナ"は赤ん坊のための木のおしゃぶりだったそうで、
口に含むことから、絵付けをしなかったのだといいます。
今では、顔を描く南部こけしも出てきていますが、
煤孫さんは、絵付けをする代わりに、木目をそのまま楽しめるようにと、
30種類以上の木を使って、多彩な"キナキナ"を生み出しています。

製作の様子を見せていただくと、その作業の素早いこと!

円柱の木材が煤孫さんの手業によって、みるみるうちに形を変えていきます。
1本の材から先に切り出した頭の部分を、
胴体部分に開けた穴に差し込んだら出来上がり!
「親父の手伝いから始まったこの仕事も、もう40年以上になりましたが、
マイペースに楽しくやってきました」
そう話す煤孫さんは、地元の文豪である宮沢賢治をモチーフとした
「デクノボーこけし」(写真左下)や、「ピエロこけし」(写真右下)などの
創作こけしも作っています。
首が左右にゆっくりと揺れる南部こけし"キナキナ"は、
赤ん坊のみならず、私たち大人にも癒やしを与えてくれます。
もう一つ、このキャラバンで、各地で見て来た縁起物といえば、ダルマ。
そのルーツは南インドの国王の第三王子であり、
仏教の禅宗の開祖の"達磨大師"であると知ったのは群馬県でのことでした。
達磨大使は洞窟で9年間も座禅を組み続けたといわれる人物。
何があっても必ず起き上がるところから、
宗教・宗派を超えた縁起物として、日本全土で広く親しまれており、
その姿形は各地の文化・風習によって少しずつ異なり、
地域の人々の願いが託されています。
そんななか、絶対に転ばないダルマが福井県小浜市にあると聞いて伺いました。
これがそのダルマ「うるしダルマ」

県指定の郷土工芸品であり、
小浜市からアメリカのオバマ大統領に贈られたこともあるそう。
「私の家は父が病気がちで、小さい頃ド貧乏でした。
もうわしは転ばん!って、転ばないダルマを父と一緒に創り出したんです」
そう話すのは、うるしダルマを手懸ける、柄本忠宗さん。

20歳まで外国航路の船員として、海外を回っていた柄本さんでしたが、
父親が海辺で拾ってきた漆の塊がたまたま割れたところを見て、
「これは綺麗だから何か作れるかもしれない」と発想を膨らませました。
そして、子供から大人まで知っていて、
前向きなものとして、ダルマづくりを思い付きました。
実は小浜市は日本の塗り箸の80%以上が作られているという、
若狭塗り箸のふるさと。
柄本さんのお父さんも病気になる前は漆箸職人で、
いろんな模様を考えて独自のお箸を作っていたといいます。
そんな柄本さんのお父さんが見つけた漆の塊とは、
その塗り箸づくりの工程で余った塗料が固まったものでした。
現在は柄本さんが夫婦で思考を凝らし、塗料を固めてだるまの原型を作っています。
実際に塗料を固めたものを割ってもらうと…
中がとってもカラフル!
この塊を小割、研磨して、一つひとつのだるまを仕上げていきます。
そのため、色、形、表情どれをとっても同じものはありません。

表情は描いた時期や気分によっても変わってくるといい、
「最近はダルマと顔が似てきたって言われますね。
でもそれは嬉しいこと。かつて見た仏像の表情を参考に、
いつかその顔を描きたいと思ってやってきましたから」
と柄本さん。
ちなみに下の写真は、
右側のダルマが、柄本さんが20歳の時に描いた顔で、
左側のダルマが数年前に描いたものだそう。

自分たちでゼロから創り出したものが県にも認められ、
一見、順風満帆な人生のようですが、
人手が足りずにお客様が離れていってしまったり、
一時は食べるものに苦労した時もあったといいます。
「ここまでやってこられたのは、奥さんがいたからですね。
年中隣に彼女がいて一緒に作業していますが、ケンカはしません。
ケンカしたらダルマのいい表情が描けませんしね」
小浜一、仲よしといわれる柄本さんご夫妻が作る夫婦ダルマは、
二人の人柄と仲睦まじい様子がそのまま表れていました。
※煤孫さんが作る"キナキナ"と、柄本さんご夫妻が作る"うるしダルマ"は
年始に販売される「福缶」に含まれています。
2014年度の福缶の縁起物は全部で30種類。
どれが出るかはどうぞお楽しみに!
文庫革
書籍や身の回りの大切な物などを保管しておく、文庫箱。
貴重品を箱に入れてしまうという習慣は古代からあり、
その昔は、木や紙の箱に漆を塗っただけのものでしたが、
皮なめしの技術が確立すると、革を貼ったものも作られるようになりました。
皮革産業が古くから盛んな兵庫県の姫路では、
江戸時代中期〜後期にかけて、藩の財政が厳しくなり、
革を生かした工芸が発達します。
真っ白な革を使用して独特な加工を施す、姫路革細工というものです。

この姫路革細工は、その後、一大消費地である江戸に"文庫革"として伝わり、
関東大震災前までは、5軒ほどの工房が東京にあったといいます。
今回訪れた、墨田区にある『文庫屋「大関」』は、
現社長の田中威(たけし)さんの祖父が昭和初期に創業した、
現在東京に唯一残る、文庫革の工房です。
文庫革の製造工程は、まず、姫路でなめされた白皮に
"しぼ"と呼ばれる革の揉みじわを入れた後、
プレス機を使って柄の型押しをしていきます。
現在使用されている型は、銅板のものが中心ですが、
戦前は木版、戦後はマグネシウム板と素材も変化してきました。
型押しが終わると、次に"彩色(さいしき)"という工程で、
皮革専用の絵の具を使って、一筆ずつ色をさしていきます。
「8色の絵の具だけで、無限に色を創り出すんですよ。
同じ色を作るのが難しかったりもしますが」
とは、その道45年のベテラン・大関春子さん。
一時、大関さんが唯一、彩色の後継者だった時期もありましたが、
ネットで文庫革の存在を知った人たちが集まり、
現在は複数名のお弟子さんと一緒に作業をしています。
続いて、"さび入れ"と呼ばれる工程。
色止めをした後、革の表面に漆を塗り、
仕上げに"マコモ"という植物の粉をふりかけて定着させます。
すると、色を塗らずに残しておいた部分にマコモの茶色の色が入り、
独特の風合いが生まれるといいます。
(写真下右:さび入れ前、写真下左:さび入れ後)

「マコモが入ることでそこが影の役割を果たし、
色を乗せた柄の部分が浮き上がって見えます。
古びをつけるというのですが、これですごく味が出てくるのです」
初めて聞きましたが、マコモとはイネ科の植物で、
田中社長いわく、鎌倉彫りにも使われているものだとか。
「兵庫や大阪にも姫路革細工の工房は何軒かあるけれど、
さび入れをしていない所もあるといいます。
私は"さび入れ"が文庫革の面白みだと思っているので、
そこだけは変えずに守っていきたいですね」

文庫屋「大関」はこれまで卸し売りが中心でしたが、
それだけでは文庫革についてお客様にきちんと伝えきれていない…と、
一昨年、念願の直営店を浅草に出店しました。
お店を訪れると、浅草寺のすぐ近くということもあり、
平日の昼間でしたが、観光客や外国人のお客様で店内は混み合っていました。
ズラリと並ぶ色とりどりの柄を目の前にすると、
思わず「どれにしようかな〜」と選びたくなり、心がわくわく躍ってきます!
デザインはおじいさんの時代から使っているものもあれば(写真下左)、
田中社長が手掛ける新しいデザイン(写真下右)もあります。
「色や柄は時代によって好みが変わる。
バリエーションを持つことで、幅広いお客様の要望に応えたいと思っています」
そう話す田中社長に文庫革の魅力を聞いてみると、
次のような答えが返ってきました。
「文庫革は『迷って選んで使って楽しめる革工芸』だと思うんです。
人に見せたくなったり、また欲しくなったりする、
使っていて"楽しい!"と思えるものってなかなかないと思いませんか」

「お客様の手に渡って喜んでもらってこその
ものづくりだと思っています。
そのためにも、この程度でいい、ではなく、
今後も、もっともっと文庫革の良さを伝えていきたいですね」
もともと大切な物を仕舞っておくための箱に使われていた文庫革。
それは貴重品を大事に保管しておくための保護の意味合いだけでなく、
きっと大切な物だからこそ、好みのわくわくする柄に包んでおきたい
という人々の願いが込められていたのではないかと思います。
そして、その想いは、お財布や手帳、ブックカバーなど用途を広げながらも、
しっかりと現代に引き継がれていました。
1200年続く竹細工
その地にある素材を使って、くらしに必要な道具を作る。
焼物にしても、木工にしても、
今ほど物流が整備されていなかった昔においては、
それが当たり前だったことを、キャラバンを通じて実感してきました。
網組細工もその一つ。

日本各地に自生する竹や植物のツルを使って編まれる網組細工は、
芸術品のようでもありながら、日用品として人々の生活を支えてきました。
ただ、時代の変化に伴う安価な日用品の台頭によって、
その技術の継承者は全国的にも希少な存在に…。
そんななか、今でも地域ぐるみで網組細工を作り続けている産地がありました。
岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

1200年もの歴史があるといわれる、竹細工の産地です。
鳥越で使われる素材は、
スズ竹と呼ばれる細くてやわらかい品種。(写真右)

真竹(左から2番目)などと比べても、その違いは一目瞭然です。
太平洋岸に広く自生している品種ですが、
寒くて雪の積もりすぎない気候の二戸地方のものは、
強靭でしなやかと昔から定評があったそうです。

「昔は、集落ごとに秘伝の編み方がありましてね。
門外不出とされたので、結婚も集落内で行われていたんですよ」

鳥越地区で、技術を伝承し竹細工の魅力を広く伝えていくことを目的に設立された
「鳥越もみじ交遊舎」の館長、柴田三男さんはそう語ります。
昭和26年には、農閑期の副業として
日本一の収益を誇っていた鳥越の竹細工でしたが、
少子高齢化による過疎化で、広く門戸を広げるように。
館内では、地域の作り手はもちろん、
遠方からその技術を学ぼうと訪れる人の姿もありました。
「簡単な作業に見えるんですけど、これが想像以上に難しいんですよ」
埼玉県から学びに来ていた女性も、その奥の深さに驚きを隠せない様子。
それもそのはずで、今も原料は、
自生するスズ竹を自分たちで採取するところから始まり、
皮を剥いで、均等に縦4つに分割。(これが難しい)
さらに、内側の厚みを何度も削って薄くし、ようやく材料となるわけです。
この原料にかける手間暇によって、仕上がりにしなやかさと弾力さをもたらせます。

こうして一つひとつ丁寧に編まれた竹細工は、
現代のくらしにも自然と溶け込む普遍的な魅力を放っていました。
使い続けていくうちに、飴色に経年変化していくのも、
竹細工のおもしろいところです。

「それにしても1200年ものあいだ、途切れることなく
地域ぐるみで作り続けられてきているのも、すごいことですよね」
ふと、そんな質問を柴田館長に投げかけてみると、
「よかったらその理由の片鱗を見に行きませんか」
と、ある場所へ連れて行っていただきました。
訪れた先は、もみじ交遊舎の裏にそびえる鳥越山。

もみじの名所としても知られる、紅葉がかった山をぐんぐん登っていくと、
その先に待っていたのは、切り立った崖の岩穴に設けられた御堂でした。

「鳥越観音堂」と呼ばれるこの御堂は、
西暦807年に慈覚大師が開基したという伝説を持つ古寺。
実は、鳥越の竹細工のはじまりには、
この鳥越観音と慈覚大師が深く関係しているそうなのです。
「長い冬の土地柄、人々の冬場のくらしは困窮していました。
そんな折、観音開基のために山堂に籠っていた慈覚大師の夢枕に、観音様が現れて、
"わが化身である大蛇の胴の模様を、竹細工の編組法にとりいれてこれを里人に広めよ"
と教えてくださったのです」

柴田館長がそう話されるように、今もその言い伝えから住民は観音様に感謝し、
村人が殺生しないことを条件に竹細工を教えたとの話もあり、
縁日などには肉・魚・卵を避ける方もいるそうです。
そして、住民は何かの折にはこの御堂にお参りし、
親しみをこめて「観音さん」と呼んでいるのだそう。
確かに、そこには1200年ものあいだ大切に守られてきた
神聖な空気を感じずにはいられませんでした。

「もみじ交遊舎では、地域の小学生にも竹細工を教えていますが、
編み方を覚えて欲しいわけではないんです。
自分の生まれ故郷に、こうした歴史を持つ竹細工があることを知り、
誇りを持って欲しい」
1200年ものあいだ作り続けられてきている鳥越の竹細工には、
単に日用品としての価値のみならず、
生業を授かったことに対する感謝の念が込められていることを知りました。
そしてそれは、広く門戸を開きながら、
後世へとつながれていくことと確信しています。
親子で紡ぐ、ホームスパン
岩手県の産業のひとつである「ホームスパン」とは、
"家庭(ホーム)"で"紡いだ(スパン)"毛織物のこと。
その技術は、明治時代に英国・スコットランドから伝わり、
東京より北の地方に広まったそうですが、
今では全国生産の多数を岩手県が占めています。
「今もホームスパンを続けているのは6軒ほどになりましたが、
コツコツやってきた所が残っています。
うちの工房は、私の祖母である中村ヨシが大正8年に始めました。
当初、ホームスパンの講習会があると聞いた時には、
パン作りかと思ってお鍋を持って出掛けたそうですよ(笑)」
お茶目な笑顔で話すのは、盛岡市内でホームスパンを手掛ける、
中村工房の3代目、中村博行さんです。

中村さんいわく、昔はどこの農家にも織り機があり、
飼っていた羊の毛で、自分たちの着るものを織っていたそう。
その後、時代の移り変わりとともに織りの世界でも当然、機械化が進みます。
中村さんの父親の代には、機械を導入したこともあったそうですが、
海外からより安価な製品が入ってきて、失敗に終わってしまったといいます。
その時の教訓もあり、中村工房では今も手織りにこだわります。

「機械織りだと、シャトルのスピードが速いから風合いが出せない。
手織りは糸がリラックスできるでしょ。そこがよさだと思いますよ」
確かにこれまで訪れてきた機械織りの工場では、
カシャンカシャンと忙しく機械が動いていたのを思い出します。
また、手織りでも綿の場合などは、トントンと糸を詰めながら織りますが、
ウールの場合は、糸に負担をかけずに織るため、工房内はとても静かな印象でした。
織物というと、織る工程にどうしても目が行きがちですが、
中村工房では、羊毛を手で染めるところから始まり、
それを足踏みの糸車で紡いで糸にし、

整経(せいけい)といって織るために糸を整えたりと
一連の工程をすべて手作業で行っています。
工房に並ぶのは、どれも木製の年季の入った道具で、
眺めているだけでどこか懐かしい気分にさせてくれます。

中村工房では、中村さんのご両親の時代までは
服地やコート地を中心に織っていましたが、
中村さんの代になり、マフラーを中心とした小物に商品をしぼるように。
その理由を
「服地は高価なものだからお客様が限られてしまうでしょ」
と中村さんは話します。
また、デザイナーの三宅一生氏との出会いも影響しているそう。
中村さんは20年以上に渡り、イッセイミヤケのコレクションにおいて
マフラーやストールなどを頼まれ、
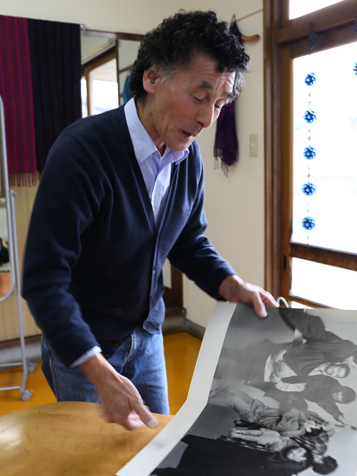
そのなかで、シルクリボンや機械紡ぎの糸を使った、
ホームスパン以外の手織り製品も手掛けるようになったのです。
「冬向けにホームスパン、夏向けにはシルクや麻などを使って織っています。
ぜひ見てください」
そう言われてショールームに入ると、
ナチュラルカラーのホームスパンの横にある
それとは対照的なビビッドな色合いのものが目に飛び込んできました。
「ショールームはお客様に見てもらう場であり、
反省の場でもあるんです」
一つひとつ中村さんが手で染め上げる糸の色は、
織ってみて、初めてその表情が見えてくるといいます。
そして、中村さんがこだわるのが"旬"の色。
これまでに染めた糸をスクラップした、染色ノートは40冊以上もあり、
中村さんはそのための情報収集を日々欠かせません。

毎月10数冊という女性誌に目を通し、気になる色を再現していくのです。
さらに、ショールーム内に飾られた
愛くるしいお人形や小物入れ、香水瓶など、
すべては中村さんの趣味のコレクションであり、
色のヒントを得る大切な研究材料でした。
「ホームスパンだから、ってことにこだわるのではなく、
伝統は守りつつも、あとは時代に合わせて変えていけばいい。
そうしないとつまらないでしょ」
中村さんの、自らのやり方で楽しみながら仕事をする姿を見て、
息子の和正さんも5年前から工房で働くようになりました。

「親父は親父の感覚で、俺は俺でやってきた。
手織りだけは今後も変えないで、楽しみながら続けていきたいですね」
そう語る中村さんの言葉の裏には、息子さんに対して
「お前はお前のやりたいようにやっていけ」
というエールが込められているようにも聞こえました。
4世代に渡り、その技術をつないでいる中村工房のホームスパン。
ゆっくりと時間をかけてハンドメイドで作られる手織り物が
今後どのように変化していくか、とても楽しみです。
古くて素朴で新しい、赤瓦
沖縄の家々を彩る、赤瓦屋根。

古くから強い台風や塩害から
沖縄人(うちなんちゅ)の生活を守ってきました。
晴れていても突然雨が降り、すぐにまた晴れるという沖縄の気候のなか、
赤瓦は雨を吸収し、晴れた時に蒸発させ、
気化熱によって、家の中を涼しく快適に保っていたのです。
漆喰で塗り固められているのも、瓦が台風で飛ばないようにするためとも、
見栄えを良くするためともいわれています。

もともと朝鮮半島と日本本土、それぞれのルートから
沖縄へと伝わったとされる瓦は灰色でした。
灰色の瓦は、空気を入れずに焼く還元焼成というやり方で、難易度が高く、
沖縄で作る際には、どうしても空気が入って酸化焼成になってしまい、
3割ほどは赤や褐色の瓦になってしまっていたんだとか。
しかし、その希少性からか王族や権力者が赤瓦を好むようになり、
やがてそれが一般的に普及していったそうです。

当初、那覇を中心に作られていた赤瓦でしたが、
海運の発達にともない、沖縄北部(やんばる)から船で運ばれてきた木材と、
瓦に適した良い土があったことから、
那覇東部の港町、与那原(よなばる)町へと産地が移行。
現在でも与那原の町中では、赤瓦の工場を散見できます。

しかし、家の建築様式の変化から、その需要は低迷していました。
そんな状況を打破したかったと、
新垣瓦工場の企画担当、新垣拓史さんは話します。
「悶々とした想いで尻すぼみの家業を手伝うなかで、
ある日、事務所で仲間を呼んで飲み会を開いていたんです。
その時、泡盛を割るためのアイスピッチャーが
結露でビチャビチャになっていたので、近くにあった赤瓦を敷いたんですね。
そしたら、ぐんぐん水滴を吸い取ってくれて…。
その時に、これだ!と思いました」

湿度の高い沖縄では、冷たい飲み物は結露で水浸しになるため、
飲み屋などではコップの下におしぼりを敷くのが定番だったそうです。
それを、もともと沖縄にあった赤瓦を使って解消しようと
新垣さんが生み出したのが、こちらの商品でした。
「赤瓦コースター」

屋根瓦と同じ素材なので硬くて丈夫。
そして、抜群の吸水性です。
はじめは周囲に、硬いコースターなんて売れっこないと反対されたそうですが、
実用性に富み、沖縄らしいこのコースターは、
またたく間に、沖縄土産として定着したそうです。
現に私たちが取材でお邪魔した先々でも、
この赤瓦コースターを敷いて飲み物を出していただきました。

ご覧に通り、コップに付いた水滴は、
みるみるうちに赤瓦に吸収されていました。
「はじめは瓦を小さく薄くすればコースターにできると、
高をくくっていましたが、そう簡単ではありませんでした。
薄くすると乾燥時に曲がってしまう…。
だから、乾燥の仕方にも工夫が必要です。
また、吸水性も、焼き方によって変わってくるんです」

そう新垣さんが話すように、赤瓦で培われた技術は、
繊細さを極めながら、コースター製造で活かされていました。
さらに、赤瓦の時よりも小さな窯で済むようになり、
エネルギーのコストダウンにもつながったそうです。
現在、新垣瓦工場では、コースター製造一本に切り替えられ、
かつて使用していた赤瓦用の窯は、打ち合わせ部屋へと見事に変化していました。

「沖縄のモノづくりはこれまで観光に頼ってきた部分が大きいんです。
今後は、どこかに沖縄らしさを残しておきながらも、
自然と日常に取り入れられて、
実はメイド・イン・沖縄という、他が真似できない
質の高いモノづくりをしていきたいですね」
そう話す新垣さんは、
今では、沖縄らしい柄や色のバリエーションを増やしながら、
着実に、赤瓦の新しい可能性を広げていっています。

古くて素朴で新しい、沖縄の赤瓦コースター。
現代のくらしを少し豊かにしてくれる要素は、
意外と身の回りに眠っているのかもしれません。
横浜帆布鞄
横浜みなとみらい、赤レンガ倉庫からほど近い万国橋たもとに、
一軒の鞄工房があります。

「045 Yokohama Canvas Bag」と名づけられたその鞄は、
帆布(はんぷ)製。

キャラバン中、帆布の産地、岡山県ではよく目にしましたが、
横浜にも帆布があったのかと、驚かされました。
「横浜といえばシュウマイにKitamura…。
東京に近い土地柄のせいか、意外と横浜ブランドは少ないんです。
そんな横浜ならではのモノづくりをしたかった」

横浜帆布鞄の開発者、U.S.M.Corporationの代表取締役、
鈴木幸生さんがその想いを話してくれました。
もともとアパレル雑貨業界で長らく企画製造、
マーケティングに携わってきた鈴木さんは、50歳を機に退職。
生産拠点を海外に置くことに疑問を覚えていた鈴木さんは、
日本の繊細な技術力を、わざわざ海外へ移植させることはないと、
国内でのモノづくりにこだわります。
そして、異国情緒を感じさせる大好きな横浜を拠点に、
新しいモノづくりへの挑戦を始めたのです。
「横浜らしさを考えたとき、やっぱり港町を想起しますよね。
港町といえば船、かつては帆船が主流でした。
調べると、やっぱり横浜にも"横浜帆布(株)"という商社があり、
全盛期には、日本製の綿帆布輸出量の約7割のシェアを持っていたほどでした」
しかし、この横浜帆布(株)は、関東大震災で被災。
工場を失った後の主力帆布生産を担っていたのが、
岡山県の「武鑓織布工場(現:株式会社タケヤリ)」でした。

鈴木さんは、その歴史にちなんで、
今も125年の歴史で培われた確かな技術を基に作られる
武鑓(たけやり)綿帆布を使った製品づくりに着手します。

それに加え、現在、日本で2社しかないといわれる帆船のメーカーが、
横浜にあることを耳にします。
「森野帆布船具工業所」は、今年でちょうど創業100年を迎える老舗工場。

船具全般を企画製作している業界No.1メーカーで、
海上自衛隊の船具工場にも指定されています。

横濱帆布鞄で使用している防水性のビニロン・キャンバスは、
日本で初めて開発された合成繊維"ビニロン"で織り上げられた帆布を、
森野帆布船具工業所が別注で、
海上自衛隊のスペックに合わせた特殊加工が施された素材です。
ビニロン・キャンバスは、加工しにくくごわごわするという点から、
これまで衣料品・服飾雑貨品などには使われてきませんでした。
しかし、鈴木さんは、あえてこの素材に注目します。
「ミリタリーに指定されるというのは、究極のアウトドアスペックということ。
日用使いのバッグだから、耐久性に優れているに越したことはありません。
それも日本発の、横浜らしい素材で」
こうして、"森野艦船帆布"を用いたシリーズの鞄が誕生したのでした。

触れると少しザラっとした感触ながら、想像以上に柔らかく、そして軽い。
表面加工されているので、水にも強いというのは、
毎日使う鞄としてはうれしいところですね。
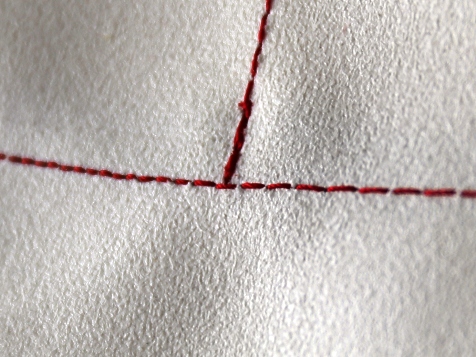
また、生地には模様を施さず、素材感が出るようにシンプルに。
そして、製品後にスタンプ加工を施すことで、
キャンバスに自由に柄を描けるように幅を持たせています。
スタンプは、ラバーインクのため経年変化が楽しめ、
使いこんでいくごとに味わいが増していくそう。
さらには、その素材の特徴をいかしたこんな商品も。

横浜で活動している"agreen project"のクリエーター達とのコラボ企画「Tsuchi Bag」。
その名の通り底面に水抜き穴もあり、土を入れられるバッグで、
プランターの代わりにも、ご覧のように観葉植物の観賞用にも使えるんです。

「モノづくりは現場が何よりも大事なんです。
現場が近くにあることで、その場でトライアル&エラーができる」
あえて事務所内に工房を構えたことで、
お客様からの修理の依頼に直接応えることができたり、
直接の要望を聞くことができるようになったと、鈴木さんは話します。

「これからも横浜の街を愛しながら、
横浜らしいものづくりをしていきたいですね」

歴史を掘り起こし、その土地らしさを追求する姿勢は、
どの土地においても適応できることではないでしょうか。
鈴木さんの表情が終始すがすがしいものに感じられたのも、
きっと、自身の道に一点の迷いもないからに違いありません。
もくロック
国土の約2/3が森林で占められている日本は、
先進国の中でも有数の森林大国といわれています。
その多くは戦後、後世の需要に備えてと植えられた人工林でしたが、
燃料革命と外材の流入によって、手つかずのまま荒れ果てていく森林が増加。
間伐をして新しい木を育てていく必要性と、
間伐材の利用促進が求められている実態を、
このキャラバン中、各地で耳にしてきました。
そんななか、山形県でユニークな木工品に出会いました。
木材×ブロック=もくロック

森林が約75%を占める山形県内の、主に間伐材を利用したおもちゃです。
「山形にいる意味を見出せる事業を作りたかったんです。
周囲を見渡すと、本当に山ばっかりなんですよね。
そんな地域資源を使って何かしたかった」

米沢市にある株式会社ニューテックシンセイの
桒原晃(くわばらあきら)代表取締役は、
もくロックに込めた想いをそう語ります。
驚いたことに、こちらの会社は、OA機器の組み立てが本業でした。

OA機器パーツと木工品。
一見、共通することはなさそうな両者ですが、
もくロックにはそれまで蓄積された技術が活かされていました。

この約3cm×1.5cmほどのブロックが重なり合うように加工を施せるのも、
まさにOA機器製造で培われた精細な技術あってこそ。

製造現場も、これまでの木工品の製造現場では見たことのないほどの
ハイテク機器が導入されていました。
「木をなめるんじゃない、って初めに相談した
林業関係者からはそう言われました」
と、開発課の山岸新司さんは話します。
相手は自然の産物なので、
湿度で変化する木の扱いや、削る順番に苦心されたそうです。
それでも、県の産業技術センターに相談しながら、
2年の月日をかけて、商品化にこぎつけたのは、
「やればできる」という自分たちの技術への確信でした。
「自然の力、美しさを、子供たちに感じてほしい」
そう桒原さんが話すように、
もくロックは、木のままの色・匂い・手触りがそれぞれで、
二つとして同じものはありません。

使う木材は、県内の間伐材のなかでも、
家具や建材などに利用できない木材ばかりで、
これまでに9種類ほどの木を使ってきたそうです。
丸太ごと仕入れているのも、
一本の木さえも無駄にしないという想いから。

「もともと山形には、多くの恩恵を与えてくれる自然への感謝の気持ちを込めて、
草木の命を供養する"草木塔(そうもくとう)"という、
碑や塔を建立する習慣があるんです。
こうした草や木の命も尊く想おうとする山形独自の自然観も大切にしたかった」
桒原さんがいうように、
実際に、現在でも町中で草木塔の碑を見ることができました。

こうした自然に対する感謝の念が、
もくロックには込められていました。

このもくロックを用いて作られた作品の数々が
生き生きしているように感じとれたのも、
そうした木に対する想いの表れかもしれません。
「これだけ自然に囲まれていながらも、
自然の魅力を感じるきっかけが少なくなってしまった現代のくらし。
もくロックを通じて、少しでも自然を、五感を使って感じてもらい、
本来、自分たちが持っている感性に気づいてもらえたらうれしいですね」

地域を想い、自分たちのできることを実行していく姿勢は、
どんな地域においても模範となる取り組みではないでしょうか。
"今あるものをどう活かすか"という視点は、
ものや場所だけでなく、技術に関してもいえることなのだと知りました。
民芸運動と松本家具
国宝・松本城を中心に広がる旧城下町、長野県松本市。
ここもまた、キャラバンの旅中に何度も触れてきた、
柳宗悦氏を中心とした「民芸運動」とゆかりの深い土地柄です。
今回はそんな松本市で、
長野県の伝統的工芸品の指定も受けている、松本家具を作る
「松本民芸家具」を訪ねました。

松本は、日本で3番目の高さを誇る穂高岳や上高地に囲まれ、
とても乾燥しており、木材を乾かすのに適している気候のため、
昔から木工業が盛んでした。
さらに、松本城建造にあたって優秀な職人たちが全国から集結したので、
安土桃山時代を起源として、日本で3本の指に入る和家具の産地へと発展。
しかし、太平洋戦争と時代の変化にともない、和家具の生産は衰退していきます。
「戦後、将来に対して空虚感に襲われていた私の祖父が、
何か人の役に立てることはできないかと、
民芸運動の柳先生に相談して始めたのが、洋家具づくりでした」
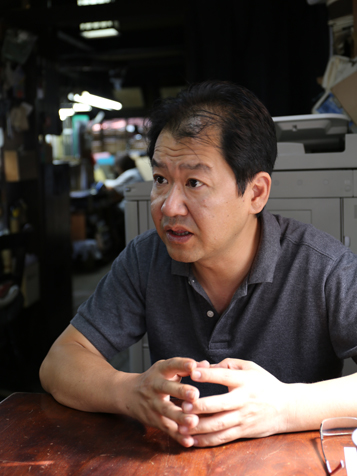
松本民芸家具の創設者・池田三四郎氏の孫で、
現在、常務取締役を務める池田素民さんはそう話します。
これまで民芸運動について私は、
"日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に
「用の美」を見いだし、活用する運動"と理解していましたが、
戦後のタイミングにおいては、
"日本人の心を取り戻す運動"でもあったことを池田さんのお話から知りました。
池田三四郎氏は、友人に誘われて参加した民芸運動の勉強会で、
そこに集まる人々の真剣さに心を奪われ、
「戦争で生き残ったからには何かしなければいけない」
と民芸運動の創始者・柳宗悦氏の門を叩いたそう。
そして、「松本の木工業を再度立て直してみたらどうか」
という柳氏の助言に従い、
生活が西洋化してきていた時代に合わせて、
洋家具を手掛けるようになったといいます。
こちらは、ショールームで見かけた、松本民芸家具の代表作のひとつで、
柳氏の愛用の椅子を基に習作された、「ウインザーチェア」。

背もたれの材が一本柱のチェア(写真左下)に対して、
すべての材がバラバラで角度がついているのが特徴のウインザーチェア(写真右下)は、
椅子としての力学構造が成立していて、踏ん張りが利きます。
他にも、重厚感あふれるこれらの家具は、
そのほとんどが職人による手作業で作られていました。

「うちは図面もCADではなく、手で描くんですよ。
手描きはニュアンスが出せて、そうすると見る角度によって見え方が異なる。
つまり"味"が出せるんですよね」
と池田さん。
作業は分業制で、設計、木材の管理・木取り、組み立て、塗装と
大きく4つのパートに分かれています。
「分業制にすることで、職人の個性を消しています。
また、餅は餅屋に任せた方が合理的。
例えば、作り手が材料を選ぶと、使いやすいものを選んでしまうため、
材料の無駄遣いになってしまう」
そして、手作業でありながら、量産してきた工夫も
工房内に見つけることができました。
天井からズラリと吊るされているのは、木型の数々です。

親方・子方制度で技を身に付けていき、
あとは型さえあれば、
いつでも同じ家具を再現できるようにしているといいます。
「材料、環境に合わせた変化は日々していますが、
基本的に作ってきたものは今も昔も変わりません。
普遍的なものは変える必要がないですから」
もともと伝統を守るために始まったわけではなく、
時代に合わせたものづくりとして始まった、松本民芸家具。
「戦後のものづくりの方向性としては珍しかったかもしれませんね。
それしか道がなかっただけですが」
そう話す池田さんに、伝統とは何かを聞いてみたくなりました。
「伝統とは、技術だけでなく、人の心だと思うんです。
すべて"○○するため"という思いやりから来ているんですよね。
例えば、材料を無駄遣いしないため、
使いやすいため、後で直せるようにするため…」

松本民芸家具では、永く使い続けてもらうために、
修理を受け付けていますが、
修理品である過去の商品から、構造など学ぶことが多いそうです。
そしてまた、池田さん自身も、池田三四郎氏の存命中には、
ほとんど教わった記憶はなく、
亡くなった後に出てきた同氏の写真日記からいろいろと学んだとか。
「日記を読み返して分かったのは、難しい哲学ではなく、
祖父がやってきたことは、人と人のつながりだったということ。
『民芸運動ってすごく人間臭かったんだ』って、
その時すごく腹に落ちたのを覚えています」
さらに、こう続けられました。
「気候、風土と昔の人たちの知恵の積み重ねがあってこそ、今の仕事がある。
これらを次の時代につなげていかないと…。
そのためにも、ものづくりが何かをもう一度考えてみたいですね。
"人の意識"が今後の生命線ではないかと思っているので」

職人の手によって紡ぎ出される、松本民芸家具の使い心地は
説明されて理解するよりも、
使っていく中で自然と伝わってくるものだといいます。
そして、その手仕事の裏には、
未来の日本人に対する先人たちの思いやりが
たくさん詰まっていたことを知りました。
[お知らせ]
2013年7月26日(金)~9月1日(日)まで、
無印良品有楽町2F・ATELIER MUJIにて『MUJIキャラバン展』を開催中。
各地で出会った職人をお招きし、各種ワークショップも実施しております。
夏休み中のお子さんとご一緒にいかがですか?
- 「ギザギザはさみで切り絵を作ろう」
8月4日(日) 11時~(満員御礼)、14時~、16時~ - 「"もくもく絵本"で物語を作ろう」
8月24日(土)11:00~、13:30~、15:00~、16:30~
ATELIER MUJI「MUJIキャラバン展」イベント情報はこちら
(各イベント要予約 ※申込は定員に達し次第終了致します)
麦わら帽子
今でこそ、ファッションの一部として、
私たちの日常に取り入れられている"麦わら帽子"。

明治期以前、"かぶる"という習慣がなかった日本に帽子がもたらされたのは、
開国にともなう西洋文化の移入によるものでした。
横浜など外国人居留地ではじまった帽子の生産は、
やがて原材料の産地へと移行。
大落古利根川と江戸川の水運に恵まれ、
肥沃な土壌で米と麦の栽培が盛んだった埼玉県の春日部市は、
岡山県と並んで、帽子の二大産地を形成していきます。
はじめは農家の副業として、
主に大麦の茎部分を編んだ"麦わら真田(さなだ)"を作り、
帽子の原料として海外へ輸出していましたが、

明治10年頃からは、麦わら真田の輸出の傍ら、
日除けを目的とした農作業用の麦わら帽子を手縫いで作るようになったそう。
そして、その後、ドイツからミシンが輸入されると、
本格的に帽子作りが産業化し、
最盛期には50軒ほどの帽子屋さんがあったといいます。
しかし、専業農家が減り、農作業用の麦わら帽子のニーズが減ると、
レジャー用の帽子や、季節を問わず需要のある園児用の帽子を
手掛けるお店も出てきたものの、帽子屋の数は減少。
現在も帽子作りを行っているのは、
UKプランニング株式会社(田中帽子)を含む、3軒ほどになりました。
「田中帽子は他があまり手掛けない、
ファッション用の帽子も作るようになったんです」

田中帽子の情報発信とネット販売を担う、
有限会社ビスポークの黒木克則さんはそう話します。
春日部出身の黒木さんは、皮革製品を中心としたバッグや小物の
販売を手掛けていますが、ふと地元の麦わら帽子について気になり調べてみると…
「このままではもったいない。
消費者に田中帽子について情報発信していけばもっと売れるはず」
そう思って、黒木さんは
UKプランニングの代表・田中英雄さんに話を持ちかけました。
こうして、歴史や製造工程などの情報をきちんと伝えるホームページができ、
それまでOEM生産をメインに行ってきた田中帽子の帽子が、
私たち消費者の手に直接届くようになったのでした。
工房を覗かせていただくと、そこは"帽子のテーマパーク"のように、
様々な帽子たちが私たちを迎えてくれました。

「カタカタカタカタ…」
ベテラン職人たちがそれぞれの持ち場で軽快に手を動かしています。
その製造工程は、麦わらから帽子の形状にする「帽体縫い」、
形を整えるための「型入れ」、
汗止めやサイズ調整などの機能性を追加する「内縫い」、
そして最後の「装飾」と大きく分けて4つ。
すべてハンドメイドで作られています。
そして、使われている機械も創業以来、大切に使い続けているもの。

木型は日本人の頭に合わせた形になっていますが、
これを作れる職人は春日部に1人、
全国を見ても2人しかもう残っていないんだとか。

ちなみに日本人用の帽子と欧米人用の帽子は
並べて見るとその形の違いが明らかです。
日本人用(写真左下)は丸型、一方の欧米人用(写真右下)は卵型です。
海外で試着した帽子がキツイと感じたのはそのせいだったのかもしれません。

「"守ること"ではなく、"継続していくこと"を大事にしています。
イケイケドンドンな性格だから、一歩立ち止まって考えるのが苦手なんですが、
でも、時に振り返って、続けていくために何をしたらいいかを常に考えています」

そう語る田中さんは、15年ほど前から、
海外の工場でも一部ものづくりをしています。
「海外で生産してきたからこそ、
日本でもこうして今も作り続けていられると思っています」
と田中さん。
というのも、複雑でない生産に関しては、
海外産も日本産もその質はほとんど変わりがないといいます。
それでも逆に生産拠点を日本にも残しておいた理由を
田中さんは以下のように話してくれました。
「国内で作ってほしいというお客様もいましたし、
ロットが少ない場合、海外では受けられないケースもある」
また、黒木さんがこう加えます。
「お客様の細かい要求に応えられるのは
やっぱり日本の技術ではないでしょうか」
例えば、細麦を使ったこちらの帽子は、
幅が狭い麦わらを重ねながら縫っていくため、
製造工程が複雑で、日本でしか作っていません。

伸縮性に富んだ仕上がりになっていて、
かぶった時のフィット感は抜群のものになっています。
"守ること"ではなく、"継続していくこと"。
田中帽子が100年以上にわたり、
日本人の頭に合わせた帽子を作り続けられているのは、
様々なニーズに応えられる体制で、
時代に沿った帽子を柔軟に作り変えてきたからこそ。
最近では、人気漫画や映画などに登場する麦わら帽子を再現するなど、
伝統の技術を生かしてその活躍の幅を更に広げていました。
サステイナブルなカップ
初めてそのカップを見たのは、東京のとあるショップ。
その輝きと発せられるオーラに目を奪われました。

てっきりイタリアなどの海外製品かと思いきや、
話を聞くと、日本製。
「SUS gallery」と名付けられたこのカップは、
なんと結露しないんだとか。
見た目の美しさに加え、機能まで優れ、
一瞬でこのカップの虜になった私たちでしたが、
このたび、念願かなって生産現場を訪ねることができました。
訪れた先は、金属加工の町として知られる新潟県燕市、
豊かな田園風景広がるなかに株式会社セブン・セブンはありました。

笑顔がとてもチャーミングな澁木収一社長は、
同じ燕市で金属原料調達も行う、恒成株式会社の代表でもあります。

「SUS galleryは今でこそブランド名となっていますが、
最初は本当にステンレス製品を展示するギャラリーだったんですよ。
それは大失敗でしたけどね(笑)」
時はリーマンショック以前、
価格の高騰にともない、市場のステンレス離れを危惧した澁木社長は、
ステンレス製品を訴求する目的で、東京・青山の一角にギャラリーを創設。

ステンレス製のキッチンや花器などを展示し、
消費者に直接、より豊かな生活を提案していたそうです。
そんな矢先、リーマンショックに見舞われます。
市場の冷え込みに、ギャラリーの縮小も余儀なくされ、
一時は撤退も検討されるなか、そこに立ち上がったのが、
当時、ギャラリーのディレクションをしていた鶴本晶子さんでした。
「ちょっと待って!って感じでした(笑)
この技術を用いれば、何かできるはず!なんとかしなくちゃ!!
そんな想いで動き始めたんです」

ギャラリーにたった一人残された鶴本さんは、
運営から経理まですべてを担いながら、商品開発へも乗り出します。
当時、セブン・セブンは魔法瓶を生産できる国内唯一の工場でした。
この魔法瓶の原理を元に作られていた、真空二重構造のカップ。
この技術に並々ならぬ可能性を感じていた鶴本さんは、
このカップを"世界のブランド"へのし上げる青写真を描きます。
「世界にない良いものを作れば、売れると分かっていました。
世界の高級金属テーブルウェアのなかでも、他に類を見ない存在になろう!
それも日本の技術で!!」
NYのマンハッタンでの生活経験も持つ鶴本さんは、
日本の繊細な技術を用いて作られる、きめ細かいものづくりに、
確固たる自信と潜在性を感じていたそうです。
そこから足しげく工場を行き来し、職人とも会話を進める日々。
そんななか、鶴本さんが発見したのが、不良品箱の中でいびつに光るカップでした。
「見た瞬間、これだ!と思いました。
これが失敗作と言うから、職人に"もう1回、失敗して!"と懇願したんです(笑)」
こうして秋のギフトショー前夜に生まれたのが、
今のSUS galleryの原形となる6個のチタンカップでした。

鶴本さんの狙いは見事的中。
たった6個のチタンカップが、大手百貨店のバイヤーなどの目に留まり、
そこからSUS galleryの快進撃が始まるのです。
当時の様子を、工場長の幸田正昭さんはこう語ります。
「失敗作を作れって、はじめは訳が分かりませんでしたけどね(笑)。
ただ、言われた通り作ったら、鶴本はキチンと売ってきてくれました。
作れないものを作ることが、私たちの任務だと思っています」

ただでさえ卓越した技術を必要とされる真空二重構造に加え、
いびつに乱反射するチタンの表面加工を施せるのは、
現在においては、ここセブン・セブンのみだといわれています。
この技術は国からも認められ、
2010年、日本で開催されたAPECにおける乾杯のカップ、
および、参加20カ国の首脳への贈答品として選ばれました。

素材がチタンなので、軽くて丈夫。
その構造から、持っても冷たさや熱さを直接感じることはありません。
また、通常のガラスタンブラーと比べると6倍の保温・保冷力のため、
氷が溶けるスピードも格段に遅く、飲料が薄まる前に飲めるんです。
「SUS galleryのSUSには、"sustainability"の意味も含まれているんです。
チタンは金属なので、不要になったら溶かして何度も再生可能。
日々のくらしを豊かにしてくれながらも、ゴミにならないものって、
今の時代に合っていると思いません!?」
チタンの奥深さに魅了されているという鶴本さんは、
最近では、表面の酸化被膜の厚さによって見え方が異なる原理を生かした、
様々な色合いのカップも開発されていました。

一切、着色を施したわけではなく、表面の反射のさせ方で
色みが変わって見えるというから、驚きです。

これらは海外のマーケットでも評価され、
現在では欧米を中心に世界へ展開していっています。
怒涛の快進撃を続けた過去5年間を、
鶴本さんはこう振り返ります。
「私がデザイナーとしてかかわっていたら、ここまでできなかったと思っています。
内部の人間で、マーケティングから販売まで担うファシリテーターとして、
そして消費者としての感覚を忘れないようにしていました。
必要以上にデザインしすぎないこと。
だって日常生活にドレスは必要ないでしょ?」

大分の自然のなかで育ち、海外生活を経た鶴本さんは、
自分のミッションを、日本中の世界一を海外へ伝えることと話します。
そんな東京の鶴本さんに対し、燕市の澁木社長もこう呼応します。
「コストだけ考えたら、海外で作った方が良いでしょう。
ただ、ここに技術がある限り、ここで生み出せるものがあるはず。
これからもこの技術を生かして、人に喜んでもらえる商品を作りだしたい」

日常使いながら、ちょっとラグジュアリーな気分を味わえるカップが、
世界中を席巻し始めています。
そんな華々しい展開遂げているSUS galleryの背景には、
それぞれの場所で必死に役割を果たしてきた人たちの姿がありました。
八尾和紙
昨年、富山県をキャラバン中に出会ったこちらの名刺入れ。

「八尾(やつお)和紙」と呼ばれる、
富山県南部の八尾町で漉かれている和紙を使ったものでした。
一目惚れで手に取ってから、旅路をともにしましたが、
とても丈夫で、1年経っても汚れや型崩れがありません。
今回はその生産現場を見に、1年ぶりに八尾町を訪れました。

八尾町は、平野から飛騨の山脈に連なる街道筋の
富山県と岐阜県との県境に位置し、
飛騨の山々から越中側へのびる8つの山の尾に拓かれた地という意味から
"八尾"と呼ばれるようになったといわれる、自然豊かな地。
かつては、街道の拠点として、飛騨との交易や養蚕、
売薬、売薬用紙の販売による収益などで繁栄していました。
そして、この地で漉かれていた八尾和紙は、
もともと字を書くための紙ではなく、加工する紙として製造され、
薬袋や薬売りのカバンなど、売薬とともに発展してきたそう。
明治初期の最盛期には、「八尾山家千軒、紙漉かざるものなし」
と謳われたほど、ほとんどの家庭で冬の農閑期の仕事として、
紙漉きが行われていたといいます。
しかし、その後、機械漉きが始まると、八尾の和紙産業は衰退。
現在も八尾の地で紙漉きを行うのは、「桂樹舎」1軒のみとなりました。
「うちは大正生まれの父親が始めた工房です。
八尾で和紙産業を再び盛り上げるために、富山県製紙指導所ができて、
父がそこの講習生になりました。
本人いわく、その頃体調を壊していて、暇つぶしに始めたとか」
当時、すでに斜陽産業だった和紙の世界に父親が入った理由を、
息子であり、現社長の吉田泰樹さんが教えてくださいました。

軽い気持ちで紙漉きを始めた父親の吉田慶介さんでしたが、
ある時、民芸運動の指導者・柳宗悦氏の『和紙の美』という本を読んで感動し、
何の面識もなかった柳氏に教えを請いに、東京の日本民藝館に足を運んだそう。
桂樹舎の手掛ける八尾和紙は、
加工用として発展してきたことから丈夫であることと、
カラフルでモダンな目を惹く型染めが特徴ですが、
実はこの型染めを始めた裏には、民芸運動との関わりがありました。

吉田さんは、民芸運動の参加者で染色工芸家の芹沢銈介氏とも知り合い、
戦後、なかなか手に入りにくかった布の代わりに、
和紙に型染めができないかと、芹沢氏と一緒に研究開発を進めるように。
型染めは、図案を作成して型を彫り、
色をつけない部分に糊を置いてから染め、水につけて糊を落とす、
という作業を繰り返すのですが、普通の和紙では水に溶けてしまいます。

研究の結果、楮(こうぞ)の繊維をより多く絡ませて分厚く漉き、
さらにコンニャク糊をしみ込ませて揉む、
という"シワ加工"をすることで水に強い和紙を実現。

初めは素材メーカーとして、芹沢氏の元に和紙を納めるだけでしたが、
そのうちに型染め紙の生産が追いつかなくなり、
吉田さん自身も型染めの技法を学び、
紙漉きから型染め、そして最終的な加工品まで
手掛けることができるようになったといいます。
原料である和紙を漉いて染め、さらに商品企画をして、
最終的な商品に加工する、という一連の工程を一貫して行っている工房は
日本全国探してみても、桂樹舎の他にないかもしれません。
そして、見ているだけでもワクワクしてくるこれらの模様ですが、
そのほとんどが父親の代から使い続けている型紙を使って表現されている
というから意外です。
というのも、それらの模様は決して古臭くなく、
むしろ現代にマッチしていると思うのです。
「父は民芸好きで、日本のものだけならず、アフリカや南米のものなど、
幅広くコレクションしていました。それも紙だけでなく、布も器も。
そこからインスピレーションを受けていたんだと思います。
そう考えると、昔の人はもっと偉いですよね」
そう話す、泰樹さんも大学卒業後、芹沢工房で型染めについて学びました。
そして、その色彩感覚を生かして、数年前から
現代社会により受け入れられるように、カラフルな色遣いをし、
また型紙の使い方も工夫するようになったんだとか。
ところで、現在、桂樹舎には20人の職人が働いており、
そのうちなんと2人を除いて、すべてが女性だそう。
これまで見てきた和紙の産地では、男性職人がほとんどだったので、
それを聞いてとても驚きました。
さらに素晴らしいのが、後継者問題が深刻な和紙業界において、
桂樹舎には20〜30代の若手職人が4人もいるというのです!
「継ぐのは当たり前と思ってこの世界に入りましたが、
こんなにも大変とは思っていませんでしたね。
手間がかかり過ぎているのに、それに見合った価格に紙はできない。
同じ素材である革だと高くて平気でも、紙だとそうは見てもらえない。
だけど、うちがやめてしまったら、室町時代からの
八尾和紙の歴史がなくなってしまうから、
前向きに自分を奮い立たせてやっていますよ」

最近、泰樹さんの元には、娘さんが帰郷し、
和紙づくりに参加するようになったそうです。
1年前にふと手にした名刺入れの裏に、
こうしたストーリーがあったことを改めて知り、
相棒に、より一層愛着が湧いてきました。
富士山テキスタイルプロジェクト
およそ1000年前からあったという、山梨県の繊維産業。
県東部の富士北麓地域一帯は、かつて"甲斐絹(かいき)"の名を馳せ、
明治~昭和初期には、羽織の裏地として全国へ流通し、また海外にも輸出されていました。
「"甲斐絹"は、薄いのに丈夫で奥行き感がある。
日本文化の中でガラパゴス化した究極の絹裏地なんです」
山梨県富士工業技術センター・繊維部の五十嵐哲也さんがそう話す通り、
見せていただいた"甲斐絹"は、
裏地としてはもったいないくらいに美しく、芸術的でした。
「この産地は、日本の中でもアイテム数が非常に多く、
それが強みでもある一方、山梨といえば○○といった知名度がないんです。
海外のトップブランドの生地も手掛けていますが、
OEMが中心なので産地名は出ないですし…」

こうした課題感を持った山梨県では、
5〜6年ほど前から地元織物企業の若手後継者たちがタッグを組んで、
合同で展示会を開いたり、産地のPR活動に勤しんできました。
そうした流れのなか、2009年から行われているのが、
機屋(はたや)と東京造形大学でテキスタイルデザインを専攻する学生が
合同で商品を開発していく「富士山テキスタイルプロジェクト」。
今年3月に行われた、第4回の展示会へお邪魔すると、
そこには色とりどりの目を惹く作品ばかりが展示されていました。
1回目からプロジェクトに参加している、光織物有限会社の加々美琢也さんは、
「今、私たちの地域産業にとって大切なのは、後継者育成です。
分業制が敷かれている産地なので、どこかが欠けると
足並みがそろわなくなってしまう…。
この産地を若い人に知ってもらい、一緒に勉強していきたいと思いまして」
とプロジェクトに懸ける想いを語ってくれました。

戦後に、アルバムの表紙や裏表紙生地の生産から始まった光織物は、
現在は掛け軸用の生地をメインに、
緞子(どんす)と呼ばれるおひな様用の生地を
よさこい衣装や和雑貨用に展開し、問屋に納めています。

「掛け軸はそれ自体が主役ではなく、脇役なので地味なものが多い。
和のテイストを残しながらも、これまでにない配色の小物を作りたいと思いました」
「富士山テキスタイルプロジェクト」は、東京造形大学の准教授で、
テキスタイルデザイナーの鈴木マサル氏がコーディネーターを務めており、
機屋と学生のマッチングを同氏が担当。
加々美さんは、鈴木氏に「色遣いができて、絵が描ける人」と要望を出し、
そこで選ばれたのが、デザイナーの井上綾さんでした。
「大学で染めを勉強してきました。織りのことはほとんど分からないので
光織物さんにお任せしていますが、
『知らないからこそいい』と言ってもらえます。
お互い、できること・できないことを補い合ってできていると思っています」

大学院の1年目からプロジェクトに参加してきた井上さんは、
光織物と一緒に2年間活動し、
「kichijitsu」というオリジナルブランドを共同で起ち上げました。
そして、卒業後の現在も、一緒に仕事をされています。
「日本にしかなくて、私自身も興味がある身近なものを考えた時に、
"お守り"のアイデアを思いついて、加々美さんに提案しました。
最初は『え…』という反応でしたが(笑)」
と井上さん。
こうして誕生したのが、「おまもりぽっけ」でした。
「大切なものを入れるのに使ってほしいですね。
私はお守りと免許証、筆記用具などを入れて使っています」

カラフルで斬新な色遣いがとても印象的ですが、
井上さんは柄の意味を大切にしているといいます。

「一富士二鷹三茄子」といわれるように、縁起物の代表ともされる"富士山"をはじめ、
無病息災の願いを込めたお見舞いや七夕飾りなどとして用いられる"折り鶴"、
魔除けの意味を持ち、輪廻転生をあらわすものともされる"ドクロ"など、
吉祥文様を使うようにしているそうです。
最近では、こんなものも開発されていました。
「GOSHUINノート」と呼ばれる、御朱印帳です。
光織物が神社と仕事でつながっていることを知った井上さんは、
自身が現状欲しいと思える御朱印帳が市場になかったことから、
「これはいけるかも!」と加々美さんに提案したとか。

井上さんが"売れる"商品をデザインし、
加々美さんがそれをできないと言わずに、機元の技術を駆使して形にしていく。
「学生はとんでもないことを言ってきますが、一緒にやっていて楽しいですね。
『毎日が吉日』をテーマに、自分たちもみんなも楽しくなるような
商品を作っていきたいです」(加々美さん)
「"地域発"というのを前面に押しすぎないようにしています。
こんな物語があるんです、というのは後付けでもいいと思っています。
いいものはいいし、悪いものは悪い」(井上さん)
加々美さんと井上さんは今後、富士山をモチーフにした
お土産物を開発していくそう。
富士山の麓、富士吉田市から生まれたブランド、
「kichijitsu」の今後の展開が楽しみです。
富士山テキスタイルプロジェクトでは、「kichijitsu」の他にも
オリジナルブランドや産地ブランドが複数生まれたり、
プロジェクトに参加していた学生がそのまま産地に就職したりと
明るい話題につながっています。
富士工業技術センターの五十嵐さんは、このプロジェクトに関して
以下のように述べています。
「学生たちが現場に来たことで、生産現場がどんなに格好いいか、
生産技術がどんなに素晴らしいかに、生産者たちが気付きました。
まったく違うルールで織物を捉えている"異邦人"同士がコラボすることで
新たな展開が生まれましたね。
今後は個々の企業やブランドを打ち出していって、
結果的に"やまなし織物"が浸透していければと思っています」
"作る産地"から"発信する産地"へ。
かつての産地ブランド"甲斐絹"は、形を変えながらも
しっかりと富士山の麓に根づいているようでした。
レゲエを愛する、金網職人
「好きな食べ物はロコモコ。
京都だからっておばんざいを毎日食べているわけないですよ(笑)」

今回、京都でお会いしたのは、金網職人の辻徹さんです。
HIPHOP系のアパレル会社で働いていた辻さんですが、
10年前の21歳の時に家業を継ぐために実家に戻りました。
「一度しかない人生後悔しないように生きなさい」という母親の言葉通り、
やりたいことをして過ごしていたという10代。
ジャマイカ出身のレゲエシンガー、ジミー・クリフの歌に出会い、
「自分が本当にやりたいことは何か?」と自問自答していたそう。
「自分の目で見たものしか信用できない」と話す辻さんは、
実際にジャマイカに行き、そこで自分のやりたいことは"商売"である
という答えに行き着き、父親が起ち上げた「金網つじ」を継ぐ決心をしたといいます。
辻さんの生まれ育った京都は、古くから都として栄え、
日本の食の中心地として料理文化が発達してきました。
おいしさを育む調理道具も当然、ともに発展。
湯豆腐に欠かせない"とうふすくい"や"焼き網"、
"茶こし"に"うらごし"などの金網細工もその一つです。
昭和の半ばまでは、30軒以上あった金網細工の工房ですが、
プラスチックやステンレスの発達や海外産のものに押され減少。
周りが調理器具以外のフェンスなどの建築関係の仕事に移行していくなか、
辻さんのお父様、辻賢一さんは調理器具一筋で仕事を続け、
今では数軒になってしまった金網工房の代表的存在となっています。
辻さんが実家に戻ってからは、それまで問屋経由が中心だった仕事を、
「技術があるんだからもっと前に出よう!」と、直接の仕事に切り替え、
6年前には直営店舗もオープンさせました。
その後、ネットショップも立ち上げ、プロの料理人だけでなく、
一般個人のお客様にも手作りの調理器具を届けています。
「顔の見えるものづくりではなく、作る時は作る。売る時は売る」
が主義の、辻さんの工房へお邪魔すると、
真剣な眼差しで一本一本銅線を編んでいました。
編み始めが肝心で、細かい作業で集中力を要するんだそう。
しかし、次の瞬間、この顔に!
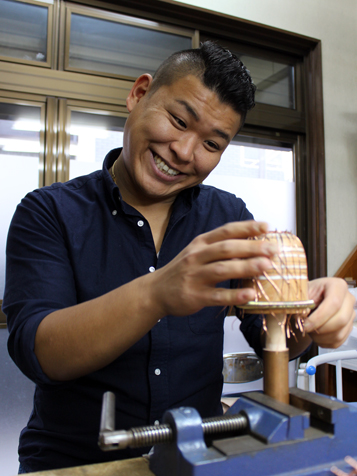
とってもお茶目な職人さんなのです。
「自分はお客様と、ものづくりをする職人の間の位置にいたいと思っています。
よく販売の時に"大は小を兼ねる"とかいいますけど、
今の時代、小さい方がしまう場所や使い勝手がいい場合も多い。
イメージだけでなく、あくまで"使われる道具"として、
きちんとした売り方をしたいんです」
辻さんは国内外問わず、実演に出かけ、
金網の調理器具を自分の言葉で発信していっています。
中国では「日本に若い跡継ぎがいるのはなぜか?」とよく興味を持たれるそう。
なんでも、中国において伝統工芸士はワーカーに過ぎないのだとか。
「伝統工芸に固執していちゃダメだと思うんです。
100均だって別にあり。人の価値観によるものだから。
でもうちは『現代の生活に溶け込む商品づくり』をコンセプトに、
守らなければならない部分は守り、
変えないと売れない部分は変えながら、やっています」
辻さんは、海外での商売のコツは
「その国に合わせるのが大事」と教えてくださいました。
例えば、茶こし。

もともとの日本茶用の茶こし(写真上左)はある程度深さがありますが、
ヨーロッパにこのまま持って行くと、深さがありすぎて
何かをすくう動作しか連想されなかったそう。
そこで、海外用に浅いモノ(写真上右)を開発。
また、フランスのご夫人などが紅茶を入れる際に、
茶こしを2本の指で持つということを知り、
写真のものよりも細い柄のものも作ったといいます。
それでも商売をする際に、あまり国内/海外という風には見ていないという辻さん。
「しょせんみんなワンブラッド。同じ人間ですから」
と語り、あくまでもフラットな視点を持っている方でした。
「今後はもっとお金儲けがしたいですね。そして若い職人を雇いたい。
それができるのは仕事が増えている状態ってことですから。
うちの商品は全部脇役だって親父がいつも言っています。
その創作理念『脇役の品格』を大切にしながら、
うちにしかできないものをもっと作っていきたいと思います」

お父様を背に、少し恥ずかしそうに、でも自信を持って話す辻さんは、
とてもかっこよかったです。
技をつなぐこと、想いをつなぐこと。
それが親子間で実現されていることが、何よりも素敵なことだと感じました。
木桶と日本人
酒蔵、味噌蔵、醤油蔵など、昔から続く醸造元で、
今も大切に使われ続けている「木桶」。
小豆島(写真右)では、桶(こが)と呼ばれ、
今も1000本以上の桶で醤油づくりが行われています。
「風が吹けば桶屋がもうかる」
ということわざがあるほど、桶屋は各地に欠かせない存在だったそうです。
そんな木桶を作る職人は現在、全国でも数えるほどまでに減少。
なかでも、大桶を作れる職人は希少で、
「大阪・堺にはまだ残っている」という噂を道中、何度か耳にした程度でした。
今回、その大阪の桶屋を、念願叶って訪ねることができました。
堺市にある(株)ウッドワーク(藤井製桶所)。


事務所もトイレも桶の技術を用いてつくっている、
生粋の桶屋さんです。
「ここ2~3年で、木桶の価値が一気に見直されはじめました。
それは"発酵"に対して、世の中の注目が集まっているから。
木桶は、日本の発酵食の文化を支えてきた存在なんです」

そう話すのは、ウッドワークの創業者、上芝雄史さん。
「酒や醤油、味噌などを発酵させるのに木桶を用いると、
まろやかに仕上がるといわれているんですよ」
現にキャラバンで巡った、今も木桶を使う醸造元でも、
酒であれば"口当たりがなめらかになる"、
醤油であれば"カドがなくなる"、
といった具合に、木桶による効果を表現されていました。
実際に、多孔質の木桶には、蔵特有の菌が生息するといわれ、
外気の変化に影響を受けにくく、桶の中の温度を一定幅に保ち、通気性もあるため、
発酵を促すには絶好の環境なんだとか。

「そんな木桶に対し、戦後、行政が"衛生的でない"と指導してきました。
以降、全国に100万個あったといわれる桶はみるみるうちに減少。
当然、桶屋の数も、急速に減っていきました」
現在は再び、醸造元からの発注の多いウッドワークですが、
前身の藤井製桶所(現在も存続中)の時代には、薬品会社からの注文も多かったそう。
薬品を調合する際に高温となるため、
木桶のその断熱性と耐久性が評価されてきたといいます。
そうした需要に支えられながら、桶の技術を多面展開するために、
ウッドワークを立ち上げ需要を発掘しながら、今日まで発展してきました。
「100~150年といわれる桶の寿命。
それは、桶が壊れても、桶屋が修復を繰り返してきたからで、
その技術は日本人のくらしのなかにずっと息づいてきたものでした」
桶は小さなもので18枚、大きなもので約40枚の板を用いた寄木細工で、
修復では、腐ったりして使えなくなった板だけを差し替えるんだそう。

初め酒蔵に卸され、使い古された木桶は、その後、醤油蔵や味噌蔵へと渡り、
それらをまた桶屋が削り直して、ひとまわり小さな桶が作られます。
そして最後には、薪になるという循環を繰り返してきました。
今でこそエコやリサイクルといわれますが、
桶屋にとっては昔から当たり前の技術だったのです。
「日本人には、古くから身近な素材をどう使うかの知恵がありました。
材に杉を使ったのも身近に多くあったから。
軽くて木の香りや色が食品に移りにくい杉は、物流にも醸造にも適した素材です」
身近な素材といえば、接着には米糊や竹釘を用いるなど、
昔ながらの技法で、桶を組み立てていました。
そして、上芝さんが何よりも大切にしているというのが、古い桶。

修復のために回収してきた古い桶にこそ、
過去の桶職人からの教えが詰まっているといいます。
「学習する相手はいないけど、そこには技術の証がありますから」

そう話す時の上芝さんの微笑みは、
追求に追求を重ねてきた職人の表情でした。
「産湯の湯桶から棺桶に至るまで」
日本人がお世話になってきた木桶。
効率や衛生面で、一時期、日本人から見放されてきましたが、
その概念が見直され、今一度、醸造元でも木桶を用いようとする動きも生まれています。
これは「日本人が本物志向に戻ってきた傾向」と上芝さんはいいます。
こうした、木桶ならではの味わいを楽しめるのも、
上芝さんのような木桶の技術をつなぐ職人がいるからということは、
いうまでもありません。
中津ほうき
「ほうき」は掃除道具の一つですが、
妊婦さんのお腹を撫でると安産になるとか、
魔を払う意味で亡くなった人の横に置くとか、
地域や時期によって様々な使われ方をされてきました。
日本においてほうきは、古墳時代中期からあったようで、
使われる草の種類や柄の部分は多様化したものの、
その形は1000年以上ほとんど変わっていない普遍的な生活用具です。

かつてほうきは、農閑期の仕事として全国各地で作られていました。
しかし、安価な海外産のほうきや、掃除機の台頭により産地も減り、
国産材を使ってほうきを作っている所は、現在はほぼないんだとか。
そんななか、神奈川県愛川町の中津地方で、
原材料である"ホウキモロコシ"の栽培から手掛けている方たちがいました。
柳川直子さん率いる、「株式会社まちづくり山上」。
一度途絶えてしまっていた中津ほうきを、柳川さんが2003年に復活させたのです。
まちづくり山上の拠点である「市民蔵常右衛門」には、
世界ならびに全国各地から集めたほうきが展示してありました。
世界のほうきと日本のほうきを比べて見てみると、
日本のものほど、草の質が良いものはありません。

それは、日本には靴を脱ぐ文化があり、
足の裏でゴミが分かってしまう生活スタイルだから。
編む作業よりも"草選り"といって、
ほうきに使う草を選り分ける作業が一番大変というほど、
手間暇をかけて作られているそう。
「掃除機を毎日かけるのは大変でしょ。
ちょっとしたほこりやパンくずなんかをさっと片付けられるほうきは
生活になくてはならないもの。
うちがやらなきゃ、誰がやる?って思いましてね」

もともと、江戸末期生まれの柳川さんのご先祖様が、
明治維新の頃新しい生き方を求め、関東地方を渡り歩き、
ほうき草の栽培とほうきの製造技術を学び帰郷。
これを起源として、ほうき産業が中津地方一帯に広まったのでした。
柳川さんはほうきづくりを復活させるにあたり、
ホウキモロコシの種を分けてもらうべく、
種を持つ農家と仲良くなることから始めたそうです。
その土地で育ってきた種を使うのは、柳川さんいわく、
「人間が手を加えていないものがその土地に一番合っている」から。
5月に種を蒔き、7月末~9月頭の真夏に収穫作業があるホウキモロコシは、
暑さと虫と闘いながら、1本1本、手で収穫していきます。
「私たちは太陽の恵みを分けてもらっています。
だからいつも、"お天道様の言う通りにしよう"って言っているんです。
天候によって栽培がうまくいかなければ、
それはみんなに話して理解してもらえばいい」
柳川さんは、昔ながらの無農薬栽培で自然のままにホウキモロコシを育て、
自分で育てた原料を使ってほうきを作ることにこだわります。
「本物じゃないと後に残らない。
全部語れないと意味がないし、自分でやればすべてが分かりますから」
そう話す一方、ほうき自体は自分で作るのではなく、
若い世代に技術を残していこうと、柳川さんはある動きに出ます。
「ほうきをただ作るだけでなく、今の時代に合わせて作らないと残っていかない。
それを作れる人を最短で見つけるには、美大に行けばいいと思って」
柳川さんは武蔵野美術大学大学院に社会人入学し、さらには学芸員の資格も取得。
武蔵野美術大学の構内にある民俗資料館でほうきの展示を行い、
そこでほうきに興味を持った、若手職人たちと出会いました。
「展示を見てドキドキして、ほうきを使う所作に惚れました。
ほうきは説明書がなくても、手に取っただけで自然に使える。
そういうものづくりを求めていたんです」
若手職人の一人、留松里詠子さんは中津ほうきとの出会いをそう振り返ります。
その後、留松さんは、かつて中津からのれん分けした、
京都のベテラン職人さんの元で学び、現在ほうきづくりに勤しんでいます。
「今は美大を出ても、一人立ちできる人はほとんどいない。
それっておかしいですよね。
私たちの世代が、若い人のバックアップをしていかないとね」
会社組織として、中津ほうきを復活させた柳川さんは
若手職人の育成に懸ける想いをそう話すとともに、
子どもたちについても話してくれました。
「今の子どもは、ほうきを与えても掃くことをしないんですよ。
掃く時って手加減するでしょ?
加減をすることは、人とのかかわりにおいても同じ、大切なことなんです」
そうしたことを伝えていきたいと、柳川さんたちは、
ほうきの文化や歴史についての講演やワークショップなども行っています。
「ほうきの工夫する余地はまだまだあると思っていますよ。
例えば、飾っても楽しめるようなものだったり。
今後も中津ほうきを後世につないでいきたいです」

普遍的なものでありながら、
その土地や時代に合わせて作られ続けているほうきを
使い手としても大事にしていきたいと思いました。
FabLab(ファブラボ)
何でもお金で買う時代から、自分で作る時代へ。
そんな"セルフビルド"を提唱する動きが、
岡山のニシアワーの取り組みや、滋賀のどっぽ村などをはじめとして、
全国各地で始まっていました。
特に3.11以降、生きていくための力を身に付けることの大切さが見直され、
その動きが加速しているように感じます。
そうは言っても、ものづくりは
小学校の"図工"の授業以来やってないし、工具も持ってない。
私も含め、そんな方も多いのではないでしょうか?
そんな人たちにうってつけの場づくりが、
首都圏を皮切りに始まっていました。
「FabLab(ファブラボ)」
"個人による自由なものづくりの可能性を広げるための実験工房"のことで、
2002年にボストンのマサチューセッツ工科大学で始まりました。
日本では11年に鎌倉とつくばで同時スタートし、
昨年3番目の国内拠点が渋谷にオープン。
都心型の実験工房とは一体どんな場所なのか…?
FabLab渋谷を覗きに行ってきました!

中に入るとそこには、3Dプリンターやレーザーカッター、
刺繍ミシンなど、様々な工作機械が。

「これまで、こうした工作機械は"作る人"の元にあるものでした。
FabLabではこうした機械の利用機会をオープンに提供することで、
子供から専門家まで"使う人"が自由にものづくりできる環境を創出しているんです」

FabLab渋谷の代表、梅澤さんは、この場の意義をそう語ります。
現に、ちょうど私たちが訪れたタイミングには、
春休み中の子供たちが3Dプリンターでおもちゃを制作中でした。

3Dプリンターと聞くと、聞こえは難しいですが、
3Dプリントのためのデータサンプルはインターネット上で共有されているようで、
それをプリンターに指示するだけというシンプルな操作!
試しに3Dプリンターで作ってみたというハートを、
5歳の女の子が嬉しそうに見せてくれました。

おもちゃも制作工程から見たら、愛着が湧きますよね☆
こんな子供たちに刺激を受け、私たちも何か作ってみようと、
レーザーカッターを使ったオリジナルノート制作に挑んでみました!
といっても、梅澤さんに多くをサポートいただきながらですが…。
ノートをセットし、「MUJIキャラバン」のロゴデータを
PCに読み込んで、レーザーカッターに送信。

すると、小さな閃光を放ちながら、2分と経たないうちに、
ノート表紙にMUJIキャラバンのロゴをカットしてくれました!
カット部分をくりぬけば、無印良品のシンプルなノート(写真右)が、
MUJIキャラバンのオリジナルノート(写真左)に様変わり!

ちょっと手を加えるだけで、
オリジナルの1点ものが生まれるなんて嬉しいですね!
他にも、FabLab渋谷ではスマートフォンカバーから、
オリジナルのコースターまで、様々なものが作られていました。
「FabLabは自発力を形成する場。頭の中のものをできるだけ形にしてもらいたい。
そのためのサポートはします」
と、梅澤さんは語ります。
今や世界200カ所に広がるFabLab。
驚いたのは、その運営はそれぞれ独立しており、
理念と一定のガイドライン(FabLab憲章)を守れば、
どこでもFabLabを始めることができること。
アメリカでは国策で今後3年以内に
1000の小学校にFabLabを導入される予定だそうです。
こうした次世代のものづくりのインフラが各地に広がっていけば、
一人ひとりがクリエーターになりえますね。
そのために、まずはちょっとした身の回り品から、
試しに自分で作ってみるのもよいかもしれません。
江戸切子
今や東京を、そして日本を代表する工芸品のひとつ、
「江戸切子」。

国内のみならず、海外からの評価も高いこのカットガラスは、
東京スカイツリーのお膝元、墨田区・江東区を中心に作られています。

その美しさを国内外に発信し続ける1899年創業の老舗、
墨田区にある「廣田硝子」を訪ねました。

「もともとは江戸のビードロ問屋が輸入品を模してカットガラスを始めたんです。
後にヨーロッパから技法が導入され発展していきました。
ただ、今やヨーロッパのものと比べても、日本人の繊細さが光っていますよ」

廣田硝子会長、廣田達夫さんが、
切子について丁寧に教えてくださいました。
日本には、私たちも以前鹿児島で見た「薩摩切子」(写真左)と
今回東京で出会った「江戸切子」(写真右)があります。

薩摩藩主、島津家の保護のもとで、優美さを追求していった薩摩切子に対し、
江戸切子は、あくまでも庶民のための切子として発展していった様子。
江戸切子も薩摩切子も作り方はほぼ同じです。
透明硝子の上に色硝子を被せ、回転する円盤状のダイヤモンドの刃に
ガラスを当てて、削って模様をつけていきます。
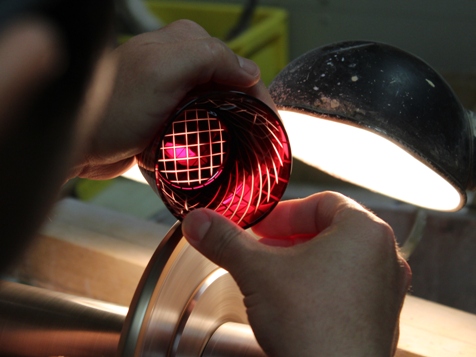
薄い硝子を同じ深さで削っていくわけなので
繊細な力加減と技術が必要で、失敗のきかない作業です。
「日常使いの江戸切子。一品ものではなく、ある程度の量産が求められます。
同じものを幾つも作れる技術が必要。
一日中作業できるように、手に力を入れすぎないようにも気をつけています」

その道21年の切子士、川井更造さんはそう話します。
そして、廣田会長が何よりも大切と語るのが、磨きの工程。

「最近じゃ手磨きの代わりに、薬品を使って仕上げてしまうところも多い。
ただ、最後の磨きで、質の高さが保たれるんです」
効率だけにとらわれすぎないものづくりが、ここにもありました。
しかし、分業制という江戸切子の生産現場では、実はこんな課題がありました。
硝子の生地を作る会社が現在2軒に減ってしまっているというのです。
そんななか、廣田硝子では切子のさらなる可能性を探り、こんな技術も開発。
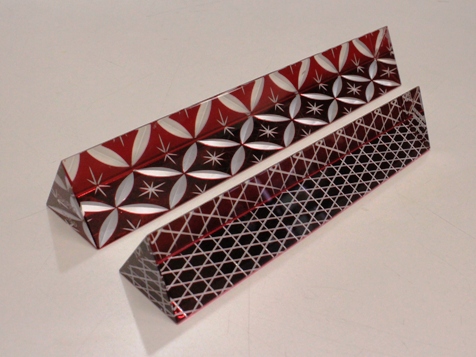
一見普通の切子と変わらないこの文鎮(ぶんちん)は、
なんと色硝子の代わりに会津漆を使ったものでした。
また、長男で4代目の廣田達朗さんは、新たな顧客層を狙って、
新鋭のデザイナーと組み、
伝統的文様をよりモダンに昇華させたデザインを施した
「蓋ちょこ」を生み出しました。

これは国内外から評価を受け、類いまれな江戸切子の繊細さと可能性を
今一度、実感しなおしているそうです。
他にも、ランプシェードや、窓ガラスにも展開。
「江戸切子は庶民の手によって製作されてきたもの。
作品ではなく使ってもらえるものを作り続けていきたい」

その廣田会長の言葉通り、
ホットドリンクも飲める耐熱性の江戸切子も開発されていました。
そんな江戸切子を使ってコーヒーが飲めるカフェを、
次男の廣田英朗さんが運営しています。
スカイツリーのそばに佇む「すみだ珈琲」。

自家焙煎のコーヒーを、江戸切子で飲むことができるんです。

なんとも贅沢ですね♪
英朗さんは、
「家族でこうした歴史ある産業にかかわれていることが幸せ」
と語ります。
この旅でも、多く触れてきた伝統工芸。
それは観賞用としてではなく、日用品として使われることによって、
よりその時代に合わせて磨かれていくことを、
最後の東京、江戸切子で再認識しました。
そのためにも、私たち消費者が身近にあるモノづくりに
今一度、目を向けてみることが大切かもしれません。
寄木細工を現代のくらしに
箱根の寄木(よせぎ)細工。

箱根や小田原を訪れたことのある人なら、
お土産屋さんなどで見かけたことがあるかもしれません。
ちなみに、毎年盛り上がりを見せるお正月の箱根駅伝で、
往路優勝チームに贈られるトロフィーは、寄木細工で作られているそう☆
1200年続くといわれる、箱根・小田原の木工の歴史の中で、
この技法は比較的新しく、江戸時代末期に箱根町畑宿に住む
石川仁兵衛氏によって創作されたといわれています。
石川仁兵衛氏の孫に弟子入りした曽祖父の代から続く、露木木工所の
4代目・露木清高さんを訪ねました。
「箱根山系は、木材の種類の多い所として、日本でも屈指の地域。
字のごとく、その種類豊富な"木"を"寄せて"作ったのが寄木細工です」

箱根で寄木細工が始まった理由を露木さんはそう話し、
「実はすごく地味で、根気のいる作業なんです」
と、その産地が全国に広まることなく、国内では箱根と小田原だけの
技術であることを教えてくださいました。
現在は全国から様々な木材を仕入れ、その天然の色を生かして、
多種多様な模様を作っています。

まず、木を細かく削り、

一定の形に切り出した多くの木片を寄せて、文様のパーツを作っていきます。
そうして作ったいくつものパーツ(写真左下)を組み合わせて、
種板(写真右下)を製作。
その後の工程は2つに分かれ、種板をカンナで薄くスライスしてできた
"ヅク"と呼ばれるものを、木製品の表面に接着して作る「ヅクもの」と、
種板をそのままロクロで削り出して成型する「無垢もの」があります。

寄木細工の模様は、木の組み合わせ次第で幾通りもあるといい、
「ヅクもの」の場合は、量産も可能だそう。
まさか寄木細工が、金太郎飴のように作られているとは
思ってもいませんでした!
そんな寄木細工をもっと多くの人に知ってもらいたいと、
露木さんは2005年に平均年齢30歳の若手職人とともに
「雑木囃子(ぞうきばやし)」というチームを結成。
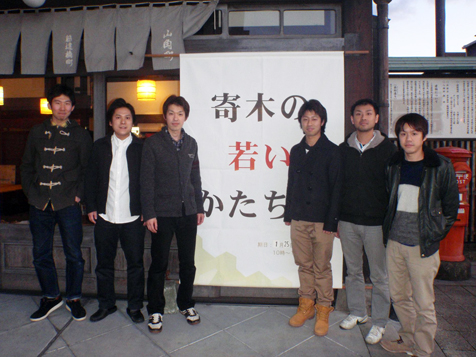
定期的に集まりを設けて、お互いの技術向上を目指し、
また、作品展を開催して、寄木細工のPR活動に勤しんでいます。
そんな雑木囃子に、活動4年目の2009年に転機が訪れたと
露木さんは振り返ります。
神奈川県の産業支援事業で、プロダクトデザイナーの喜多俊之さんが
講師として、商品企画の段階からアドバイスをしてくれることになったのです。
その結果、メンバーそれぞれが自分の得意分野を生かして、
6人6様の商品が出来上がっていきました。
現代の生活に合ったワイングラスやスマートフォン置きを手掛けるのは
石川裕貴さん。

ご自身の娘さんに、とボタンを作ったり、
日常雑貨を作るのは、太田憲さん。

自分と同世代の若い人にも寄木細工を使ってほしい、
とベルトのバックルやアクセサリーを手掛ける、小島裕平さん。

とっても細かい作業を得意とし、小さな秘密箱やオルゴールを作るのは、
篠田英治さん。

音楽を好み、音の出る寄木細工を生み出した、清水勇太さん。

そして、動きのある大胆な寄木を手掛けるのが
今回お話を伺った露木清高さんでした。

彼らの作る作品は、伝統技法を用いながらも、
どこかモダンさを感じるものばかりです。
露木さんは、
「地場で育った寄木細工の技術や考え方を大切にしながら、
ものづくりの幅を広げていきたいです。
日常品に寄木細工を生かして、それを使ってもらえれば、
生活文化に今後も寄木細工が根づいていくと思うんです。
それって素晴らしいことですよね」
と寄木細工に懸ける想いを語ってくれました。
神奈川県にのみ伝わってきた、伝統技術の寄木細工。
これを現代のくらしの中に自然と取り入れられるようなものづくりをしようと、
同世代の職人さんたちが活動していることを知って、
同じ神奈川県民として誇りを感じずにはいられませんでした。
ポンピン堂
1867(慶応3)年に浅草で創業した、江戸型染屋の「更銈(サラケイ)」は
昭和中期に広い染場を求めて埼玉県に移転。
5代目の工藤資子(もとこ)さんがその技術を引き継ぎ、
現在、さいたま市でご家族と一緒に、工房「ポンピン堂」を構えています。
彼らが作るのはちょっとポップでかわいらしい型染め。
"素材・技法・意匠(日本の文様)"を引き継ぎながらも、
どうしたら今のくらしに合わせられるかを考え、生活雑貨を中心に作られていました。

デザインを手掛けるのは、資子さんの旦那様の大野耕作さん。
「妻にとっては家業だったのでなじみ深かったのですが、
日本の伝統に触れる機会がそれまで少なかった僕には、
型染めの伝統文様が新鮮で、素直にかっこいいと思ったんです」

日本の伝統文様はただの柄ではなく、
そこには人々の想いや願いが込められていました。
例えば、「福良雀(ふくらすずめ)」というこちらの文様は、
ふっくらと太った雀がその年の豊作を意味することから、
"豊かさ"の象徴として、女性の帯によく使われてきたそう。

また、伝統柄と聞いて驚いたのがこちら。

「サイコロ」はどう転んでも目が出ることから、
"芽が出る"の語呂合わせで、"出世開運"の縁起柄とされてきたんだとか。
ある文様を使って別の文様を表す「見立て文様」という高度なものもありました。
これは5つの茄子を梅の花の形に並べた「茄子梅」。

「一富士・二鷹・三なすび」でも有名な茄子は、物事を"成す"の語呂合わせから、
縁起の良い模様とされており、"心願成就"の縁起が込められています。
一方、梅の花は学問の神様・菅原道真公の象徴とされることから、
"学業成就"の縁起が重ねられた文様だそう。
日本の家紋も伝統文様が発展していったものといい、
デザインの際に紋帳を参考にすることもあると、大野さんはいいます。

「200~300年続いてきた柄ってすごいですよね。
自分がそれだけ続くデザインを作れるかっていわれたら…。
昔の人はモチーフの意味まで分かって使っていました。
奥行きのあるこの文化をきちんと伝えていきたいと思っています」

そう大野さんが話すと、奥様の資子さんが付け加えました。
「製作にあたっても、一つひとつストーリーを話せるように心がけています。
型染めのよさを出せるように、効率を求めすぎないことを大切にしていますね。
和紙の型紙ともち糊を使うことで、独特のゆるやかな線を出すことができるんです」
型染めは、布の上に型紙を置き、防染部分に糊(のり)をのせます。
型紙は和紙を柿渋で加工した地紙に模様を彫刻したもので、
糊はもち粉と米ぬかから作られ、刷毛はシカの毛でできたもの。
昔からの技法のため、道具もすべて天然素材でできていました。
一つひとつ手仕事で作られる「ポンピン堂」の型染め。
「商品を作っているのではなく、
メッセージを届ける媒体を作っているという意識でやっています。
伝統に興味がなかった人にこそ、これをキッカケに
日本文化に興味をもってもらえればいいなと思っています」

「ポンピン堂」=
「日本(ニッ"ポン")の逸品(イッ"ピン")」
その想いは、「ポンピン堂」の名にも表れていました。
最薄の鋳物
町中でよく見かけるマンホール。

関東の方なら、その蓋に「IGS」という刻印を
見たことがある方もいるかもしれません。
実はこの「IGS」というのは会社名の略称で、伊藤鉄工株式会社のこと。
その伊藤鉄工のある埼玉県川口市は「鋳物(いもの)の町」として知られています。
荒川という水路に恵まれた川口では、一大消費地の江戸に至近だったことから、
鍋・釜・鉄瓶などの産地として名を馳せ、戦時中は軍需関連産業として、
戦後には鋳物生産量が全国の約3分の1を占めるほど栄えました。
現在は、最盛期と比べ工場の数は少なくなりましたが、
町中のマンホールから照明灯、フェンス、車などのパーツに至るまで、
身の回りの多くの金属製品が川口の鋳物で作られています。
そんな川口の地場産業活性化を目的とした、
川口商工会議所のジャパンブランド事業「KAWAGUCHI i-mono」の一環として、
2008年、「Ferramica(フェラミカ)」というブランドが誕生しました。

なんと薄さ2mmという、
鋳物のなかでは最薄といわれる鍋・フライパンシリーズです。
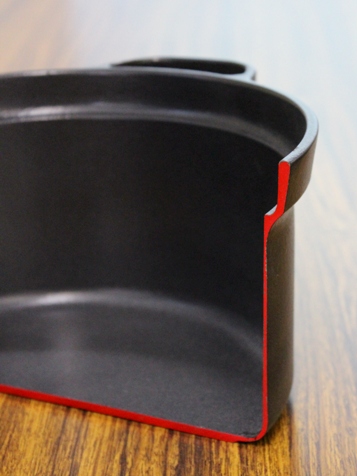
開発者は、先述の伊藤鉄工の松本誠さん。
現在は、子会社として立ち上げた株式会社フェラミカで、
企画・販売までを担っています。

「フェラミカは私の知る限り、日本でしか作れない技術だと思います」
そう松本さんが話される技術とは、
薄くても強度のある鋳物を作るためのもの。
このフェラミカには、「ダクタイル鋳鉄」という、
一般の鋳鉄よりも強度の強い材質が用いられているんです。
「ダクタイル鋳鉄は、強度はありますが、製造上の難点が多々あります。
製品として安定的に供給するためには、いくつか越えなくてはならない壁がありました」
松本さんがまず手掛けたのは、ダクタイル鋳鉄の成分調整。
キューポラと呼ばれる、鋳物工場にはおなじみの溶解炉で、
1500度で溶かされた金属に、マグネシウム合金を加え、化学反応させます。
これを砂で作られた鋳型に流し込むわけですが、

ダグタイル鋳鉄は、流れが悪いため、
この流し込み方に職人の技と感覚が必要なんだそう。

松本さんいわく、コツは「早く静かに!」
鋳型に流し込むと一気に冷却されるため、
そのスピードが遅いと、うまく固まらないんだとか。
その日の天候によっても微調整が必要なため、
手作業による職人技が求められるわけです。
「このように管理工程が多く、製造を安定化させるのが難しいため、
おそらく、ダクタイル鋳鉄で作られた鍋は世界初です」

こうして生み出されたフェラミカは、国内外から評価。
海外の展示会でも、耐久テストと称して地面に落とす実験がされたようですが、
2mmの薄さでも割れることなく、驚嘆の声が聞かれたそうです。
鋳物調理器具の「保温性が良い」「無水調理ができる」という元来の機能に加え、
これまでの「約1/2の重さ」で「丈夫」という機能をフェラミカは実現したのです。
「"うまくいかないから仕方ない"ではなく、"どうしたらうまくいくか"を考える。
これからも難しいことを実現していく会社であり続けたいと思います」

松本さんのいう、この"探究心"こそが、
昔も今も、日本のものづくりの根底を支えているのではないでしょうか。
印伝
山梨県民が一家にひとつは持っているといわれるものがあります。
「印伝(いんでん)」

印伝とは、甲州(山梨県)に400年以上も伝わる鹿革工芸で、
山梨県と国の伝統的工芸品に指定されています。
実際、滞在中にお会いした方の名刺入れやお財布、
携帯ケースなどの身の回りの物に印伝を見かけました。
山梨県内では、お祝い事などの贈り物に使われることも多いそう。

鹿の革に模様を染めるといった皮革加工技術は、
奈良時代には既に日本に伝わっており、
奈良・正倉院宝庫には足袋が、東大寺には文箱が残っているそうです。
鹿の革はとても柔らかく加工しやすいうえ、
軽くて強度や耐久性に優れているという特性があり、
戦国時代には武将たちの武具にも使われていました。

「印伝」の名の由来には諸説あるようですが、
17世紀に東インド会社から輸入した鹿の装飾革に魅了され、
印度伝来を略してそう呼ぶようになったとか。
現代に見られる印伝の代表的な技法のひとつ「漆付け」は、
江戸時代に甲州の地で誕生します。
かつて印伝は全国各地で作られていましたが、四方を山に囲まれた甲州では、
原料である鹿革や漆が手に入りやすく、印伝が発展するには最適の地だったようです。
当時の印伝は、鹿革に塗った漆のひび割れ模様を楽しんでいたといい、
「地割れ印伝」や「松皮印伝」などと呼ばれていました。
その頃には、武家や庶民の間で巾着やたばこ入れなどの
身の回りの物に印伝が用いられ、人々の目を楽しませたといいます。
この「漆付け」の技術を確立したのが、
今回お邪魔した、1582年創業「印傳屋」の遠祖・上原勇七氏でした。
もともとは撥水や防虫目的で使われていた漆ですが、
後に型紙を使った様々なデザインが生み出されるように。
染色した鹿革に模様を切りぬいた型紙を置き、
職人さんがその上からヘラで漆を丁寧に、均等に摺り込んでいきます。
型紙をはがすと、革に美しい模様が浮かび上がります!
漆の語源は"潤う""麗わし"にあるといわれ、時が経つほど光沢を放ちます。
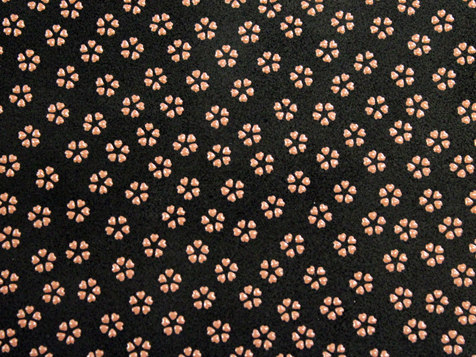
印傳屋には、代々伝わる型紙が100種類以上あるそうですが、
それらの模様は自然や四季に敏感な日本人の美意識が生み出したもの。
青海波、小桜、とんぼなど江戸時代から伝わる「江戸小紋」もあれば、
毎年新しい柄も生み出されています。
また、印伝のルーツとされる最古の皮革加工技法「燻べ(ふすべ)」は、
現在では唯一、印傳屋だけに伝承されている日本独自の技法。
それはなんと、煙で燻(いぶ)して革を染める方法でした!

タイコと呼ばれる木の筒に鹿革を巻き付け、
稲藁を燻した煙だけを用いて着色する技で、熟練の職人だけが駆使できるそう。

職人の神宮寺秀哉さんは、
「『燻べ』は触感、質感、色など鹿革の良さが生きる技法です。
天然のものなのでマニュアル通りいきませんが、
色ムラができないように目を離さず調整していきます」
と、そのコツを話してくださいました。
こちらは量産ができないため、オーダーメイドのみで作られています。

ちなみに江戸後期に数軒あったといわれる印伝細工所のうち、
現代に残るのは印傳屋だけだそうですが、
それは「技」の継承を代々家長にのみ口伝されてきたのが理由だとか。
そして、その技を確実に伝承するために行ってきたことを
お話を伺った総務部長は次のように語ってくださいました。
「伝統の技を途絶えさせることのないよう、細かいことの積み重ねをしてきました。
例えば、毎年行う社員旅行の際には、
万が一に備え、職人は何組かに分けて移動することをしています」
日々の行動に"自分たちが技を守り、後世にそれを伝えていくんだ"
という強い信念を感じましたが、
伝統に加えて、世の中に求められているものを作る柔軟さも
大切にされているといいます。
「作り手がいくら素晴らしいものだと思っていても、
売れなければそれは自己満足に過ぎない。
使う人がほしいと思うものを作るのが我々の役目です」
その言葉は売り場にも表れていました。
レジの後ろにズラリと並んだ引き出しの中には、
売り場に並び切らない、革と模様の色の組み合わせの商品が入っているのです。

さらに、在庫にない色の組み合わせは、
注文に応じてひとつからでもオーダーメイドしてくれるのです!
これも昔から変わらない売り方です。
使えば使うほど艶が出て、味わいが増す印伝。
山梨県民ならずとも、日本独自のこの貴重な鹿革工芸を
使う立場として、守っていければいいなと思いました。
日常使いの「SIWA | 紙和」
紙は、読み書きするためのツール。
一般的に、普段触れている紙から想起するのは、
そんなことではないでしょうか。
しかし、それまで抱いていた紙の概念を覆されるようなモノに、
山梨県で出会いました。
「SIWA | 紙和」
驚くほどの軽さなのも、それが和紙で作られているから。
さらに、

10kgほどの重い荷物も入れられるほど丈夫です。
しかも、

濡れた傘などを入れても、破れることはありません。
軽くて、丈夫で、水に強くて、スタイリッシュ。
和紙でまさかこんな日用品が生み出せるとは…。
作り手は、山梨県市川大門の老舗和紙メーカー「大直(おおなお)」。

笛吹川・富士川の清流に恵まれたこの地では、1000年前から和紙漉きが盛ん。
障子紙の全国シェア40%を誇るほどの産地となっています。
「この障子紙を漉く技術が、今の『SIWA | 紙和』の開発につながったんです」

大直の営業開発・プロデューサーの一瀬愛さんが、
「SIWA | 紙和」シリーズの開発の背景について教えてくれました。
一口に和紙といっても、大直で開発してきた和紙は多種多様です。
かつて江戸幕府に献上されていた、肌のようにすべすべとした「肌吉紙」から、
カラフルなもの、透かしのあるもの、丈夫なもの…、
原料も楮(こうぞ)にとどまらず、バナナの葉やペットボトルのリサイクル繊維まで。

ただ共通していることは、
和紙づくりの技術を用いて、繊維を漉いていること。
伝統技術を生かしながら、時代に必要とされる素材を開発し続けてきました。
「『SIWA | 紙和』シリーズは、弊社の開発した紙の中でも非常に強度のある紙の一つです」
そう一瀬さんが話す紙は、「ソフトナオロン」と呼ばれる、
木材パルプとポリオレフィン繊維を原料に自社開発したもの。
一度シワがつくと取れにくい性質を、逆に利用したのです。
「マイナスポイントと思っていた性質をデザインに生かせたのは、
デザイナーの深澤直人さんのアイデアでした」
この「SIWA | 紙和」を語るうえで欠かせない人が、
同じ山梨県出身の工業デザイナー、深澤直人さんです。
2007年、深澤直人さんが山梨県デザインセンターで講演をしたのをきっかけに、
大直との和紙を使った新商品開発プロジェクトが始まりました。
「生活様式の変化から、障子のない家も増えています。
また、和紙の製品は和風のイメージが強いことから、
お客様も年齢層の高い方が多かったのです。深澤さんには
"幅広い年齢層向けに、生活に密着しているモノを作りたい"と相談しました」
そして、経済産業省の推進する第1回の地域資源活用認定にも選定され、
翌年には晴れて「SIWA | 紙和」シリーズが誕生するのです。
いとも簡単にこうしたプロダクトが誕生したように感じますが、
その裏側には、日本の繊細な技術が隠されていました。
「紙は、布や革みたいに伸びないからね。
繊維も詰まっていて、間違えて針を刺したらやり直しもきかない。
寸分違わぬ裁断と縫製する技術が求められるんですよ」
「SIWA | 紙和」製品の縫製を手掛ける方はそう語ります。

製造の過程で生じるシワが、商品にそのまま反映され、
そして、使い込んでいくごとに、そのシワは刻まれ深みを増していくのです。
和紙で作られた、シワを育てていく日用品。
日本にも既にファンが定着しつつある「SIWA | 紙和」ですが、
驚いたことに、その反響は海外からの方が強いそう。
パリの「メゾン・エ・オブジェ」に出展したことをきっかけに、
今や世界各国、欧米、北欧、台湾を中心に展開中で、
製品の出荷量は国内販売を上回る月もあるそうです。
その広がりは、一瀬さんがパリへ出張で訪れた際に、
地下鉄の構内で、目の前の人が持っていたのを目撃したことで実感したといいます。
何もかも順調に進んでいるかのように見えますが、
一瀬さんは、まだまだと語ります。
「紙の可能性はもっとあるはず。
モノがあふれている時代、本当に世の中に必要とされるものを、
優れた知恵、技術を持った色々な方々と力を合わせて
垣根を越えて作っていきたいです」
日常から離れた工芸品を仕立てるのではなく、
伝統技術を生かし、現代のくらしへ発信し続ける大直は、
「SIWA | 紙和」を通じて、和紙の可能性を限りなく追求していました。
ビタミンやまなし
「富士山、武田信玄、フルーツにワイン…
山梨には単体では有名なものが多いんですが、
これまでそれらと山梨があまり結びついてこなかったんです」
「こんなに観光資源に恵まれているんだから、ちゃんとそれを生かしていかないと!」
そう話すのは、山梨県 観光企画・ブランド推進課の
佐藤浩一(ひろかず)さんです。
山梨県では、2009年から「ビタミンやまなし」と題し、
A~Zの頭文字に合わせて山梨の観光資源をPRするキャンペーンを仕掛けています。
例えば、AはAqua(水)、

QはQuiet(静かさ)、
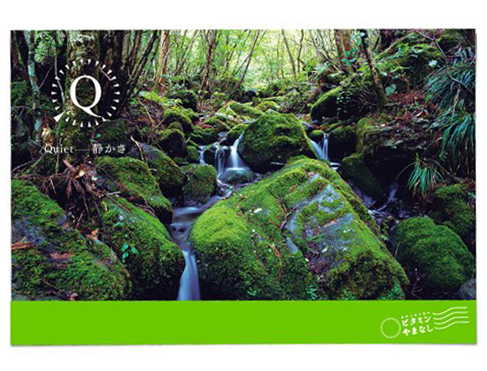
SはSpa(温泉)…。

「実はいずれも"美・健康・癒やし"に紐づくものなんです。
そして、これらは首都圏に住む30~40代の女性の興味とシンクロする」
今回の「ビタミンやまなし」キャンペーンは、
都会で生きる女性たちに届けたい26の栄養素(ビタミン)として、
明確なターゲットを設定し、行ったそうです。

「広く、あまねく、平等に」が基本スタンスの行政において、
ここまでターゲットを絞った戦略は珍しいです。
「これまでのPRはやっている側も、見る側も、
誰に向けてのメッセージかが分かりにくかった。
今回は、発信力・行動力・購買力の強い層に向けて"えこひいき"しました」
昨年は「女子会推進課」を県庁に設置するなど、次々と斬新な戦略を打ち出し、
全国から注目を浴びています。
「地域資源はどこにでもありますし、PRもどこもやっていますよね。
山梨が違うのは、きちんとした戦略を持っていることではないでしょうか」

順序よく、とても分かりやすく説明してくださった佐藤さんですが、
話を聞いていると、県内外の人脈がとても多いことが分かりました。
仕掛け人の佐藤さんご自身にも興味がわいて、根掘り葉掘り聞いてしまいました。
すると…
「僕は実は八百屋の息子なんですよ。
小さい頃からごはんを食べていても、お店にお客さんが来たら対応する。
目の前の人、ゲストを楽しませることが僕の基礎にあるんでしょうね」
佐藤さんはプライベートの時間を使って、
9年前から「得々クラブ」という名のコミュニティを創設。
「自分たちにとって、得になる情報を共有しよう」というコンセプトのもと、
地元の本屋さんで購入した課題図書を月1回ディスカッションする「読書会」や、
朝の時間を有効に使うための「三文会」、
公務員のための「ワンコイン学習会」など、各種勉強会を行い、
様々なインプットをしながら、
山梨県内外の異業種の方とのネットワークを築いていました。

「先月の読書テーマが『武士道』だったんですけどね。
それを読んで分かったことがあって。僕は『商人道』なんだなぁって。
人と人との関係の中で生き続けているんです」
佐藤さんが仕掛ける山梨のPR戦略は、表面的なものではなく、
人とのつながりの中から有機的に生み出されたものでした。
Koo-fu
「ビタミンやまなし」のJはJewelry(宝石)。

かつて水晶の原石が発掘され、研磨加工技術が発展していった山梨県は、
国内唯一の県立ジュエリー専門学校を有し、
国内ジュエリーの約1/3を生産する、日本一のジュエリー産地です。
現在、水晶原石は枯渇してしまいましたが、
1000社を超えるジュエリー関連業者が、今も技術に磨きをかけています。
ジュエリーの素材である宝石の研磨・彫刻から、
それを使ってジュエリーを作る貴金属加工まで、
ジュエリーを完成させるすべての工程が賄えるのは、世界的にも珍しいんだとか。

今回お話を伺った、ピアス&イヤリングメーカー、
(株)イノウエのジュエリーデザイナー大森弘子さんは、
高校の授業で彫金を体験してから、その面白さに目覚めたといいます。
「紙切れの上だけではいいものは生まれないと思うんです。
山梨は職人さんとデザイナーの距離が近い、とっても恵まれた地です」
大森さんは新作の企画を考える際には、職人さんと頻繁に相談しながら進めるそう。

そんなジュエリー産地の山梨県は、業界の更なる活性化を目指し、
2008年に産地ブランド「Koo-fu(クーフー)」を立ち上げました。
「Koo-fu」の名は"甲府(Koufu)"から来ていて、
海外に発信していく際にも分かりやすいようにとのこと。
希望するメーカーのデザイナーが参加し、同じテーマで意見を交わしながら
各メーカーがKoo-fuで開発したオリジナルの素材を使った
ジュエリーを作るプロジェクトで、(株)イノウエも参画。
大森さんはこれまで4回担当してきました。
「初めて他のメーカーのデザイナーさんと交流して勉強になりました」
と語る大森さんの作品は、
どれも洗練さの中に力強さがあふれるものばかり。
「小さい頃から、買ってもらったおもちゃで遊ぶよりも、
自然の中で創作して遊ぶのが好きでした。
身に着けるとワクワクするような、
気持ちを動かすことのできるアクセサリーを作っていきたいですね」

(株)イノウエには、デザイナーの大森さんをはじめ、
職人さんにも若手が多くいらっしゃいました。
県内の専門学校で学び、地元のジュエリー企業で働き、業界を盛り上げる。
将来の担い手が今も育っている山梨県のジュエリー業界の未来は、
キラキラと輝いているようでした。
遠州産のコーデュロイ
先月、Found MUJIで「日本の布」という企画が行われました。
日本全国の布の産地を訪れ、作り手と一緒になって
新しい価値の創造を行おうというもの。
今回、私たちキャラバン隊もその企画でお世話になった、
コーデュロイの生産者を訪ねました。
もともと、コーデュロイは、ベルサイユ宮殿を建てたことでも有名な
フランスのルイ14世が、庭仕事をする召使いの制服として用いたことが始まりだそう。
語源はフランス語の「Corde-du-Roi(王様の"畝(うね)")」
から来ているという説もあります。
日本では明治時代前期に、鼻緒の需要から江戸で製造が開始され、
その技術が静岡県西部の旧磐田郡福田町(現磐田市界隈)に伝わり、
現在も同地域で全国の95%以上のコーデュロイが作られているといいます。
コーデュロイとは、縦方向に"畝"のある、主に綿の織物のことで、
厚手で耐久性に優れ、保温性が高いため冬物の服によく用いられます。

コーデュロイに限らず、静岡県西部の遠州地方は繊維産業が盛んですが、
その理由は3つありました。
1つ目は、立地条件。
江戸時代中期以降、各藩の奨励もあって綿作りは全国に普及しましたが、
遠州地方は、温暖な気候などに恵まれていることから、
愛知県東部の三河、大阪南部の泉州と並び、
3大綿産地の一つとして全国に知られるようになりました。
2つ目は、海沿いの地域で、漁船のための帆布が作られていたため、
厚い布を作る技術があったのです。
そして、3つ目の理由を、Found MUJIの企画でコーデュロイの布を織ってくださった、
福田織物の福田靖さんが教えてくださいました。
「この地域には、昔から織機を作る合金技術があったんです。
浜松に本社がある、スズキ自動車も本田技研もヤマハもそうですし、
スズキもお隣のトヨタも最初は織機を作っていたんですよ」

そう聞いて、以前、別の織物工場で「豊田織機」の機械を見て、
それが自動車のトヨタであることを知って驚いたことを思い出しました。
コーデュロイは毛皮のような動物素材ではなく、
自然素材(綿)を用いたもので冬に適した唯一の素材だそう。
コーデュロイの保温性が高いのは、
パイル繊維の間に空気層ができるからだそうですが、
生産工程において、よこ糸で形成されたパイル糸を切る
"カッチング"と呼ばれる作業がとても重要だと福田さんは話します。
しかし、残念ながらこの技術を持つ職人が年々減少しているそう。
福田さんは、引退宣言をしていた高い技術を持つ、職人の星野秀次郎さんを説得し、
2年前からオリジナルのコーデュロイ生地を一緒に開発するように。
それがFound MUJIで今回お披露目された生地だったのです☆
パッチワーク柄のコーデュロイで、綿花のようなフワフワの手触りです。
福田さんに紹介いただき、星野さんの工場、ホシノへ。
すると、星野さんがちょうどカッチングの作業中でした。

福田さんの工場で織られた布のパイルよこ糸(写真下)を
1本ずつ切っていくのですが、
こんなに細かい糸を一体どのように切っていくのでしょうか?

その答えはこれでした!
「ガイドニードル」と呼ばれる細い針の先で、パイルよこ糸を持ち上げ、
その上がった部分を、円形カッターで切っていくのです。

細かい畝のコーデュロイを作るには、
ミクロン単位で、ガイドニードルやカッターを削り、
それらを一つひとつ手作業で設置していく必要があるんだとか。
「細かすぎてもう目では見えないから、指の感覚で見るんですよ」
職人歴47年の星野さんは、過去使ってきた様々な種類の
ガイドニードルやカッターを捨てずにとっておいたからこそ、
現在の細かいカッチングにも対応できているといいます。
星野さんの手にかかれば、絵や文字を表現することも可能ですし、
この波模様のようなカッチングも、8年かけてその技術を完成させたそうです。

「コーデュロイが"メイド イン 福田町"というのを知ってほしい。
技術の底上げのためにも、オンリーワンじゃなくて、
ナンバーワンを目指してやっていきたいですね」

星野さんがカッチングに懸ける想いを話すと、福田さんも続けます。
「産地が生き残っていくためにも、"いいモノ"ではなく、
"人を感動させられるモノ"を作りたいと思っています。
そのためにも、私が世界一だと思っている星野さんのカッチングの技術が必要。
星野さんとの新しい技術の開発は、若い世代にコーデュロイの可能性を知ってもらい、
後継ぎを作ることが目的なんです」

「先輩たちが頑張ってきてくれたコーデュロイを守りながらも、
新しいコーデュロイ開発していくのが自分たちの使命。
一人でも多くの人に、遠州がコーデュロイの産地であることを伝えていきたいです」
福田さんと星野さんの想いが一つになり、
そこから新たな技術が生み出されていく。
その魅力を発信していくことのお手伝いを、
Found MUJIやMUJIキャラバンで少しでも担えたら、
これほどうれしいことはありません。
からみ織り
私たちの生活に寄りそう最も身近な素材といえば、
繊維ではないでしょうか。
一言に「繊維」といっても、その素材は化学繊維と天然繊維に分けられ、
天然繊維のなかでも綿や麻などの植物繊維、絹やアルパカなどの動物繊維とあり、
素材によって特徴も様々です。
素材は、原料の繊維を紡いで糸にする"紡績"、
その糸を交差させていく"織り"の工程を経て、はじめて布地となり、
洋服やカーテンなど、様々な繊維製品に用いられていきます。
また、素材の良し悪しを決める"織り"の手法も様々で、
一般的には「平織り」「綾織り」「しゅす織り」の3つが主流ですが、
今回訪れた静岡では、代々継承される独特の織りがありました。
「からみ織り」

2本のたて糸を交差させながら、その間によこ糸を通していく織り方です。
この2本のたて糸がねじられているのがポイントで、
よこ糸をしっかりとキープするためズレにくく、粗い目を出すことができます。
通気性が良いことから、夏用の浴衣やタオルケットなどに用いられますが、
静岡県の遠州灘に面した地域では、かつて漁網を編むのに用いられてきました。
その技術を継承する職人がいる、磐田市福田にある工場を訪ねました。
愛犬のももとともに迎えてくれたのが、からみ織り職人の佐野公生さん。
「昔はうちも漁師をやっておりましてね。半漁半網とでもいうのでしょうか。
私も"網屋の子"なんて呼ばれていました」
しかし、漁業の衰退や化学繊維の台頭によって、徐々に漁網の需要は減少。
佐野さんの父親の代から、布巾やボディタオルといった日用品向けに、
からみ織りの技術を活かしていくようになりました。
「蚊帳の素材としても注目されたんですよ。
糊づけされた蚊帳だと洗うことができませんが、
からみ織りであれば、よこ糸がズレにくいため、洗うことも可能なんです」
通気性が良くて、丈夫で洗える。
そんなからみ織の特徴を活かし、無印良品のオーダーメードのカーテンも、
からみ織りで作られています。

このからみ織りを織り成すのは、
昔ながらの織機と佐野家で代々引き継がれている技術。
「天然繊維を用いているので、
織機の力加減が利かずに糸を切ってしまうことも多々あります。
だから、付きっきりで調整してあげる必要があるんですよ」
佐野さんがそう話しているあいだにも、
けたたましい音を上げながら稼働していた一つの織機がストップ。

佐野さんはすぐさま不具合を判断し、調整していました。
「最近は目が悪くなってしまってね。息子に助けられることも多いんですよ」
今では、静岡県下でからみ織り専門の織屋(はたや)は3軒のみというなか、
後継者のいる佐野さんは、希少な存在です。
ただ、佐野さんは今のままでは難しいと警笛を鳴らします。
「私も父親から、継ぐなら自分で糸を買って織り、
自分で売っていかないとダメな時代が来るといわれていましたが、
実際それは当たっていました。息子には、このからみ織りの技術を活かして、
もう少し"味"を加えていってほしい。それが日本のものづくりの生きる道です」
佐野さんが継いだ頃は、
発注先からいわれた通りのものを織っていればお金が入ってくる時代でしたが、
一般的なものが徐々にコストの安い海外産のものにシフトしていくにつれ、
日本製のものはオリジナリティが求められる時代に。
佐野さんは、からみ織りの技術を活かして様々な柄を生み出し、
婦人服用の布地としても用いられ、その需要を開拓していったのです。
「それまでできなかった織りが、
何年か続けると突然できるようになることがあるんです。
その時はうれしいですね」
そう笑顔で話される、根っからの職人気質の佐野さん。
最近では、テキスタイルデザイナーとともに企画し、
佐野さんの織ったストールがニューヨークのMOMA美術館の目に留まり、
併設のSHOPで扱われることが決まったそうです。
伝統技術を、その時代に合わせて展開していくことは、
どの業界にも求められていることなのかもしれません。
未来へ向かう、常滑焼
愛知県常滑(とこなめ)市は、知多半島西岸の中央部に位置し、
市の西部にある伊勢湾の海上埋立地には、
中部地方の玄関口"セントレア"(中部国際空港)を有しています。
そんな常滑市では、港に近く、良質な粘土と豊富な燃料があるという土地柄から、
日本六古窯の一つの「常滑焼」が古くから作られ、
窯業が主要な伝統産業とされてきました。
朱泥(しゅでい)の茶褐色の急須が代表作といわれますが、
土管や工業用タイルなどの産業陶器が多いことも特徴。
衛生陶器やタイルのメーカーとして知られるINAX(現LIXIL)の創業の地でもあります。
市内にある「やきもの散歩道」と呼ばれる道には、
登窯、煉瓦煙突、黒い板壁の工場など昭和の窯業施設の跡地が多く残っていました。
また、常滑は日本一の招き猫の産地でもあるそうで、
巨大招き猫が迎えてくれました!

実は無印良品でも数年前に、常滑焼シリーズを扱ったことがあります。
朱色は伝統的な朱泥で作り、黒色は同じ朱泥の生地を使い、
本焼後に炭でいぶすことで黒く仕上がります。
お茶をいれた時、朱泥に含まれる酸化鉄とお茶のタンニンが反応して、
苦み渋みがほどよくとれて、まろやかな味わいになるといわれているそう。
同じく無印良品のテラコッタ鍋も常滑産でした。

テラコッタとは、土の味わいを生かした素焼きの焼き物のことで、
水に浸してから、食材を入れて電子レンジにかけると、
鍋が吸った水分が蒸気に変わり、蒸し器へと早変わりするという逸品です。
(※無印良品の常滑焼シリーズは現在、販売を終了しています)
「常滑は職人気質が強くて、創作意欲の高い産地ではないでしょうか」
東京の陶器問屋に務めた後、常滑焼の窯元である実家に戻った
鯉江(こいえ)優次さんが産地の特徴について教えてくださいました。

全盛期300軒以上あったという窯元は、現在では約120軒に。
そして、今後も後継者不足の問題でさらに減少していくといわれているそうです。
問屋が販売してきた常滑焼の産地において、
窯元が自分たちで販売をするのは本来タブーとされていたそうですが、
9年前に実家に戻った鯉江さんは、
「自分たちが使いたいと思う陶器を発信していきたい」
とオリジナルのブランド「MOM Kitchen」を立ち上げました。
「MOM Kitchen」では"かわいい"をキーワードに
ひと手間かけた手づくりの器を展開。
「市場がF1のレースカーのスピードで進んでいるとしたら、
これまでの常滑は、軽自動車のスピードでした。
市場と産地のスピード感を埋めるのが自分の役目だと思っています」
と話す鯉江さんは、より多くのお客様に喜んでもらえるように
小ロットでの生産を心がけているといいます。
それが実現できるのは、祖父の代から引き継いでいる水引きろくろ機や、
自社で鋳込みの型職人を抱えていること、
さらには釉薬づくりも自社で手掛けていることが理由のようでした。

ここまで多様な機械・技法を用いる窯元は、
全国的にも珍しいと感じたほどです。
また、これまで窯元はきっちりとした納期を設けることなくやってきたそうですが、
鯉江さんは「一企業として納期を設定するのは当然のこと」と話します。
「僕が子供の頃の記憶ではこの産地も元気でした。
時代を築いてきた人たちが、子供には働かせたくない…というのが嫌で。
やり方によってまだまだやれることがあると思うんです。
まずは自分たちの窯が元気になって、周りを引っ張っていきたいです!」

力強い言葉を残してくださった鯉江さんは、
「今後は海外の市場に合わせたものも展開できたら」と
私たちが訪問した前日に、ドイツへの視察出張から帰ったばかりでした。
古くから常滑の地で作り続けられてきた常滑焼。
技術の面で伝統を残しながらも、一企業としてやり方を今の時代に合わせる。
一見当たり前のようなことこそ、伝統産業の発展の一歩なのかもしれません。
まり木綿
名古屋駅から電車で30分ほどの有松地区は、
かつて丘陵地帯で稲作に適する土地ではなかったため、
新たな産業として"絞り染め"を行うようになりました。
旧東海道沿いの地域だったので、街道を行き交う人々に、
三河木綿に絞り染めを施した手ぬぐいをお土産物として販売したのが始まり。
江戸時代以降は日本国内における絞り染め製品の大半を生産していたそうです。
そんな有松地区の有松駅から程近い場所に、
一軒の絞り染めのお店を見つけました。
店内を覗いてみると…

「か、かわいい~♥」と思わず叫んでしまう世界がそこに!!!
以前、藍の葉の産地である徳島県で絞り染め体験をしましたが、
それまで持っていた絞り染めのイメージは、藍や柿渋などの単色に施したもの。

しかし、このお店に並ぶ絞り染めはどれもとってもカラフルなものばかり。
見ているだけで、なんだかわくわくしてきます♪

「これらは絞りの中でも、"板締め絞り"といって、
昔は赤ちゃんのおしめに染めていたそうなんです。
年配の方がお店に来られると、『これおしめだね』って言われます(笑)」
食い入るように商品を見ていると、一人の女性がそう声をかけてくれました。

彼女はこのお店「まり木綿」の店主、伊藤木綿(ゆう)さんです。
名古屋芸術大学在籍中に、授業で「有松鳴海絞り」と出会い、
大学卒業後に、クラスメイトの村口実梨(まり)さんと一緒に
自分たちのブランド「まり木綿」を立ち上げました。
「授業の課題で作った有松鳴海絞りの作品が、
講師である『SOU・SOU』の社長に気に入ってもらえて。
『若い子のテイストでやってみたら』っていわれて、
有松の老舗染め工場にもお世話になりながら、2011年の5月にオープンしました」
「SOU・SOU」は、日本の伝統の軸線上にあるモダンデザインをコンセプトに
オリジナルテキスタイルを作成し、地下足袋や和服等を製作・販売している京都のブランド。
私たちも京都滞在時にショップを訪れ、その斬新さに目を奪われました。
「伝統のものは得てして高価で手が届きにくいものが多い。
もっと気軽に手が届く、自分たちが買えるようなものを作りたい」
と、2人は手ぬぐい、地下足袋に加えて、小物や洋服も扱うように。
「同じ方法で染めても、一つひとつ柄が変わるんです。
全部均一である必要はないと思っています。
均一だったらプリントと同じだし、違うからこそ、選べる楽しみもある」
そういって、見せてくださったTシャツの柄は同じようで違うものでした。

伊藤さんいわく、伝統工芸士の絞りにおいては、
柄の大きさが均一ではないことは御法度なんだとか。
伊藤さんと村口さんは交代でお店に立ち、
お店にいない方が工場で染めるという体制を取っています。
お店が休みの日には2人で染めていると聞いて、後日工場にも訪れました。
この日は2人で地下足袋に筆で絵を描く作業中。
30分以内に仕上げる必要がある染料とあって、
2人とも黙々と染色に没頭されていました。
ちなみに、"板締め絞り"の場合は、三角形にたたんだ手ぬぐいを
三角形の板に挟んで留め、染めていくそうです。
「伝統工芸士でしかできない、ではなくて、誰でもできるようにしないといけない。
伝統工芸のどこに価値があるか、現在がゴールではなく
次のゴールがどこかを見極めていくことが必要だと思います」
そう話すのは、まり木綿の2人に工場の一角を提供し、
技術指導も行う、大正元年創業の久野染工場・4代目の久野剛資さんです。

久野さんは、
「有松鳴海絞りが次の時代をどう切り抜けていくかを考える際に、
自分たちの世代だけでは答えはみつからない」
と話します。
「本来必要なのは、『絞りの要素(挟む・縛る・縫う)を使いこなしながら、
いかにデザインに取り入れるか』なんです。
彼女たちと一緒にやっていて、私たちも勉強になっている。
2人にはここの産地におけるモデルケースになってもらって、
後輩たちに自分たちのストーリーを語っていってほしいですね」
色違いの長靴にキュートな作業着姿の、まりさんと木綿さんが
最後に今後に懸ける想いを語ってくれました。

「この地域に"なくてはならない存在"になりたいです。
ギフトに地元のものを贈りたいと思っても、みんな知らないことが多い。
絞りが高級なものとしてではなく、
身近な存在として根づいていければいいなと思います!」
伝統の技術を分解して、今の時代に合わせたものづくりが、
有松地区では始まっていました。
これも伝統産業そのものの底上げにつなげていくための、
ひとつの方法ではないでしょうか。
せともの
一般的に陶磁器のことを総称して「せともの」と呼んだように、
日本人の食卓で慣れ親しまれた存在の「瀬戸焼」。
その名の通り、愛知県瀬戸市周辺で作られる焼き物は、
朝鮮から伝わった焼き物の産地とは成り立ちが異なり、
備前・信楽・越前・丹波・常滑と並んで「日本六古窯」のひとつに数えられています。
その歴史は、古墳時代にまでさかのぼるようですが、
他の産地と異なる特色を出すようになったのは、鎌倉時代。
高温で吸水性がなくなるまで焼き締める方法が一般的だったなか、
本格的に釉薬(うわぐすり)をかける技法を駆使していたのは、
当時、瀬戸が唯一の存在だったのです。
瀬戸焼に代表される1977年に伝統工芸指定された「赤津焼」には、
赤津七釉と呼ばれる代表的な7種類の釉薬が用いられています。
平安時代からの「灰釉(かいゆう)」にはじまり、
「黄瀬戸釉(きぜとゆう)」、

茶器に多く見られる「織部釉(おりべゆう)」、

「御深井釉(おふけゆう)」、

他にも「鉄釉」「古瀬戸釉」「志野釉」と、
茶華道の発展にともない、優雅な美しさの釉薬が生み出されていきました。
その後も、強度に優れ良質な美しい白土が取れた瀬戸は、
尾張徳川家の御用窯として栄え、焼き物の一大産地に発展していきます。
 ※写真は今も採掘される鉱山の様子
※写真は今も採掘される鉱山の様子
19世紀には、九州から伝わった磁器の生産もはじまり、
日用雑器から茶道具、美術工芸品まで、あらゆる陶磁器が作られるように。
さらに、現在の瀬戸を語るうえで欠かせないのが、
戦後、海外輸出用に生産されてきた「セト・ノベルティ」の存在です。
 ※写真提供「テーケー名古屋人形製陶株式会社」
※写真提供「テーケー名古屋人形製陶株式会社」
まるで布地で作られたようなこの人形は、
実は陶磁器で作られたものでした。
明治期には陶彫技術や石膏型製法が確立していたという瀬戸では、
その技術の高さが海外から評価され、戦後の瀬戸窯産業を牽引するほど、
陶磁器製の置物や装飾品が輸出されていたのです。
現在では円高の影響で、輸出品はほとんどなくなってしまいましたが、
この頃に礎を築いた石膏型製法が、今の瀬戸の産地としての特徴のひとつになっています。
「陶磁器の一大産地として栄えてきた瀬戸は、どんなものでも作れてしまう産地です。
なかでも、"ガバ鋳込み(いこみ)"製法は得意といえるかもしれません」

そう話すのは、瀬戸の地で古くから産地問屋を務める、
霞仙商会の加藤陶忠社長。
ガバ鋳込みとは、石膏型に液状の粘土を流し込み、
石膏に面している粘土が乾いてきたところで排泥し、成形する製法のこと。
泥をガバっと捨てることから、ガバ鋳込みと呼ばれているのだとか。
ローラーマシンによる大量生産を得意とする至近の美濃に対して、
この"ガバ鋳込み"は瀬戸の得意とする分野。
ポットなど、いわゆる"ふくろもの"に使われる技法で、
近年、この技術を持つメーカーが少なくなりつつある貴重な技術です。

無印良品のふくろものの磁器ベージュ商品も、
実はここ瀬戸で作られています。
型の継ぎ目にどうしても付いてしまう"バリ"は、
一つひとつ、職人によって舐めされていました。

驚いたことに、そのほとんどが手作業によるもの。
ひとつ、またひとつと、丁寧に次の工程に進んでいきます。
「常に使っていただく人の気持ちに立って、ものづくりに励んでいます。
いつもこうして仕事ができることに感謝しているんですよ」

自ら窯を立ち上げて四十余年になる酒井五鈴子さんは、
ものづくりに対する姿勢を笑顔で語ってくれました。
お孫さんが窯を継ぎたいと自ら志願してきたというのも、
そのイキイキと仕事をする姿を見てきたからに違いありません。
栄枯盛衰を繰り返しながらも、
1000年以上にわたって日本の焼き物を牽引してきた瀬戸焼。
それを支えてきたのは、紛れもなく
代々ひたむきに陶器づくりに励んできた瀬戸の陶工たちであって、
これからもそうあり続けることを願ってやみません。
名古屋名物!
かつて織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の歴代の名将を生んだ
尾張(現愛知県)の中核都市、名古屋。

豪華絢爛を誇った名古屋城の金のシャチホコが、
現代においても「名古屋嬢」や「豪華結婚式」に表れるような
名古屋人の気質を象徴しているかのように思います。

そんな名古屋の繁華街、栄にある、無印良品 栄スカイル店![]() を訪ねました。
を訪ねました。
日本三大都市圏の人気商品とは!?
スタッフさんたちにご案内いただいた先は、飲料コーナー。
「こちらなんです♪」と手に持たれているものは…、

コーヒー豆でした!
そう、名古屋といえば喫茶店文化の中心地。
朝の時間、コーヒーを頼めばトーストなど軽食が付いてくる
通称「モーニング」のサービスも、名古屋が発祥といわれています。

名古屋市以北の一宮市で、
早朝から喫茶店に集まった繊維産業で働く従業員のために、
店がピーナッツやゆで卵を付けたことがきっかけとか。
実際、愛知県民の喫茶代への家計の支出額は、
同じくモーニングの盛んな岐阜県に次いで全国2位。
喫茶店に足を運びながらも、自宅用のコーヒーが人気というから、
愛知県民のコーヒー好きは本物ですね!
雑誌や新聞が置いてありゆっくりできる喫茶店も多く、
モーニングしたいがゆえに早起き!
なんてモチベーションが湧くのも良い効果かもしれません。
この文化、全国的に広がったらうれしいものです☆
地の利を活かす、萬古焼
"土"の地と書いて「土地」というように、各地によって土の性質は違うもの。
今まで巡ってきた陶器の産地でも、
その地で採れた土を使い、代々受け継がれてきた技法を用いて
作られている陶器が多くを占めました。
そういった意味において、四日市萬古(ばんこ)焼の発展は、一風変わっています。
今や中京工業地帯の中心地として栄える四日市の雰囲気からして、
これまでの焼き物の産地とは異なりました。

山奥に窯元があるのではなく、住宅街にメーカーが存在していました。
というよりも、窯元がある場所に、後から住宅ができたのです。
「萬古焼には、この四日市の立地が大きく影響してきました」

そう語るのは、佐治陶器の佐治卓弥社長。
東海道沿いで、伊勢湾の良港にも恵まれた四日市は、交通の要所として栄え、
物流においても情報においても、外との交流が盛んでした。
その歴史は、日本のものづくりの変遷をたどるようなものでした。
江戸中期、桑名の豪商、沼波弄山(ぬなみろうざん)が、
茶の趣味が高じて、自分で茶器を焼き始めたのが始まりといわれる萬古焼。
「変わらず永遠に残っていくように」との意味から
「萬古」「萬古不易」の印を押したのが、その名の由来といわれています。
焼き物の俗称に珍しく地名が入らないのも、そうした理由から。
地元で採れる「紫泥(しでい)」と呼ばれる赤土は、鉄分を多く含み、
主に急須や土瓶が作られ、煎茶の普及とともに好評を博しました。

その繊細な装飾や本体と蓋を合わせる「すり合わせ」の技術などは、
四日市の陶工の右に出るものはない、と評されたほどで、
今も数名の伝統工芸師によって作られています。
伝統工芸士、実山窯の伊藤実山さんもその一人。

木型に薄く土を引いて成型していく「型萬古」も、
萬古焼を語るうえでは欠かせない逸品です。
提灯を製作する際の型をヒントに考案したといわれ、
東日本を中心にその製法は広まりました。
こちらは実山さんの奥さまが手掛けられたもの。
無釉ゆえに、使うほどに艶と深みが出てくるという、
急須と湯呑みでいただいた煎茶は、香りが高く格別な味わいでした。
ここまでは、他産地と同様に、地元の土・技法が活かされた焼き物です。
しかし、萬古焼の発展はここにとどまりません。
その地の利の良さから、全国各地から陶土・陶石を移入できたのです。
それらを活かして明治末期に水谷寅次郎によって作られた半磁器製品は、
翌年から大正に改元されたため「大正焼」と名付けられ、
磁器と異なる味わいが人気に。
原料の移入とともに、出荷もしやすかった四日市からは、
国内のみならず、海外へも積極的に輸出されていきます。
主に欧米向けの洋食器「ストーンウェア」は好評を博し、
最盛期の頃には生産額の約85%を輸出品が占めるほどでした。

その後は円高が進み、徐々にその輸出額を減らしていきますが、
紛れもなく萬古焼は世界の陶磁器産業の一角を担ってきた存在といえるでしょう。
そして、萬古焼を語るうえで欠かせないのが耐火陶器の存在です。
同じ三重県内の内陸部、伊賀では、成形しやすく耐火性の高い土が採れたため、
交通の要所となる四日市へ陶土が運び込まれ、多くの耐火陶器が作られたのです。
なかでも、萬古焼を代表する商品の一つが土鍋。
料理屋から一般家庭にまでその需要が拡大していくに従って、
萬古焼の土鍋も進化を遂げていきます。

アフリカ産のペタライトという長石を40~50%含んだ土の開発によって、
直火にかけたり、空焚きに対しても十二分に耐えうる
"割れない陶器"ができあがっていったのです。
さらに、機械化をすることによって、品質と価格の安定を実現。
クオリティに定評がある土鍋専門メーカーの利行(りぎょう)を訪ねると、
品質に影響する部分は機械化、味わいを出す部分は手作業と明確に役割を分け、
驚くほどのスピードで土鍋が生産されていました。
こうして、国産土鍋の約8割のシェアを占めるほどまで、
萬古焼はその性能と品質を高めていったのです。
ここまで見てきただけでも、急須・半磁器・土鍋とその裾野が広い萬古焼。
それを手で引く陶工にも器用さが求められることはいうまでもありません。
山本安志さんは、四日市でろくろを回すこと40年の職人。

どんな土でも、その性質に合わせて力をコントロールし、
そして素早く引くことができるといいます。
我々の目の前でも、一瞬の間に大皿を引いてくださいました。
それも限りなく薄く!

「できないとはいわないようにしているんです」
と、山本さん。
顧客からの要望に応えるために、従来の作り方ではできなかったことを
徹底して研究して、できるやり方を作り上げていくんだとか。
様々な土、技法、顧客の要望に対応してきた萬古焼ならではの、
職人魂を感じずにはいられませんでした。
昨今の萬古焼では、長年の研究による耐熱陶器の技術と商品の裾野の広さから、
鍋を洗う必要がなくなる、そのまま火にかけられるラーメン鉢や、
火にも電子レンジにもかけられるご飯窯まで生み出されていました。
直火で炊けるからおこげもできるし、
そのまま保管して、次の日レンジで温め直すこともできるから便利です。
「歴史と技術を培ってきた萬古焼で、
これからも家庭に受け入れられるものを作り続けていきたい」
と話す佐治社長。

その地の利を活かして発展してきた萬古焼には、
これからも新たな食器・調理器具の誕生を期待せずにはいられませんでした。
コミュニケーションを生む土鍋
「震災を通して日本人は今、絆の大切さに改めて気付き始めている。
だけど、家族の絆を作れなくて、社会の絆を作れるわけがない。
毎日は無理でも、家族できちんと食事ができる時間を作るべきだとワシは思っとる」

そう語るのは、無印良品の伊賀焼土鍋の生産を手掛ける、
長谷(ながたに)優磁さんです。

鎌倉時代より本格的に作られるようになったという伊賀焼。
伊賀焼が発展したのは、良質な陶土の産地だったことと、
燃料である赤松の森林が豊かだったことが大きな理由だそう。
長谷さんの窯元には、昭和40年頃まで使われていた
16連房の巨大な登り窯が残っていました。

もともと伊賀焼の土の出所は、お隣、滋賀県の信楽焼と同じだそうですが、
伊賀焼には、水簸(すいひ)といって、水中での異なる沈降速度を利用して、
大きさの違う土粒子群に分ける技術が早くから導入されたことで、
空気も水も吸う「呼吸する土」が使われるように。
そうして、大物を得意とする信楽焼に対して、
伊賀焼はその陶土の耐火度が高い特性を活かして、茶陶や食器を作り、
その後土鍋作りがメインになったそう。
製造途中で表面の土を削ったばかりの土鍋を見せてもらうと、
その土の荒々しさが一目瞭然でした。
土に気孔がたくさんあるからこそ、熱で土が膨張した際でも
空気の逃げ場があり、割れずに済むんだとか。
1300年ほどの歴史を持つ伊賀焼ですが、長谷さんは
「歴史を大事に守りながらも、古いものの模倣だけだったら
伝統を守っていることにはならない。
今の時代に合わせて使う人が求めているものを作ろう」と、
使う場所やシーン、使い手に合わせた様々なオリジナル土鍋も開発されています。
IHや電子レンジ対応の土鍋をはじめ、
卓上で簡単に燻し料理が作れてしまう燻製器や、
マンション等の室内でも気軽に焼き肉が楽しめるよう、
煙が出にくい作りになっている卓上オーブン、
さらには、卓上で串揚げなどの揚げ物が作れてしまう鍋や、
湯豆腐などを温めながら同時に熱燗も作れるお鍋まで。
「ワシの作る鍋のコンセプトは『卓上で"ながら"』。
食事をしながらのコミュニケーションこそ人を育てる"卓育"じゃ」
長谷さんいわく、
卓上で調理しながら食べる日本の鍋文化は世界を見ても珍しく、
卓上での調理は、火加減を見守る子どもも、
食材を入れる人も、小鉢によそう人も"みんなが調理人"だそう。

お鍋は、誰もバタバタせずに、お母さんのいる食卓を実現させてくれるもの。
そして、鍋を囲んだ家族の食事は
「しつけの場」であり、「思いやりの場」でもあるのです。
「今の時代は便利になりすぎて、
本当のうまいごはんを食べたことがない人が多い」
長谷さんは、昔食べていた薪で炊いていたごはんの味を
土鍋で再現するべく、研究を続けました。
そして、およそ4年の歳月を経て、火加減がいらず、
吹きこぼれを防いだ、便利さを追求した逸品が完成。
長谷さんは、「作り手こそ真の使い手たれ!」をモットーに、
新商品開発の際には、娘さんのいる東京のマンションにしばらく滞在して、
自分自身で使い心地を試しているといいます。
そんな長谷さんと一緒に作った、無印良品の土釜がこちら。

内蓋がなくても吹きこぼれにくいように、
深みがあり、口部分が広がりのある形になっています。
「伊賀でしかできないことを追求してきただけ」

伊賀の土の特性を活かして、今の時代の生活に合わせた土鍋を
生み出している長谷さん。
そのすぐ近くには、2人の息子さんが寄り添い、
また2人の娘さんも含めて、家族みんなで伊賀焼を守り続けていました。
無印良品のシール織り
和歌山県では、無印良品 ガーデンパーク和歌山![]() を訪れました。
を訪れました。
「待っていました!」と店長に連れられて向かったのは、寝具コーナー。
「これ、和歌山県で作られているんですよ!!!」
そういって見せてくださったのは、「綿シール織毛布」でした。

この毛布は日本の中でも和歌山県の高野口地区だけで、
昔ながらの製造方法で作られているものなんだそう!
高野口とは、弘法大師空海が修行の場として開いた高野山の麓。
私たちも週末に、プチ修行体験に出掛けていた場所でした。
既に通ってきてしまった後で、
この旅路では取材に訪れることができない場所で残念がっていると、
「こうやって手作業でよこ糸を引き抜くんですよ」
と、店内でまさかの実演を見ることができました。

実は、昨年10月に近畿エリアのスタッフのみなさんで、
高野口の綿シール織毛布の生産現場に、実際に足を運んでいたのでした。
シール織りとは、SEAL(アザラシ)の毛皮のようにふわふわとした風合いの織り方で、
両面のパイル糸がしっかりと挟み込まれて織られていて、
パイル糸が抜けにくい構造になっているといいます。
シール織りの歴史は明治時代の初めに、
シール織りのルーツとなる再織(さいおり)という特殊織物の製法が
高野口に住む前田安助氏によって創案されたことに始まります。
再織は世界的にもチェコスロバキア以外に類のない手工業的技術の特殊織物で、
当時の外国商館からカーテンやテーブルクロスなどの注文を受け、
アメリカに輸出して好評を博していたとか。
その後、大正時代に研究が繰り返され、シール織物が考案されて、
量産可能な機械化にも対応するように。
とはいえ、生産工程には、手作業の部分が多分に残っています。
よこ糸を引き抜く作業は熟練の職人さんが2人ペアで、
息の合ったテンポで行うそうです。
1本でも抜き漏れると、スジになってしまうので、
集中力と腕力が必要なことの想像が容易につきます。
私たちも店舗で体験させてもらったのですが、
なかなか力のいる作業で、均等に引き抜いていくのは至難の技でした。
表面は機械的に毛羽立たせた起毛ではなく、
糸の撚り(より)を糸に傷がつかない掻き方でブラッシングしてほぐしていくので、
肌触りが抜群! ふんわり綺麗に仕上がることから"花を咲かす"と呼ばれるそうです。
起毛の場合は掻きだすので、
綿だと洗濯後の形状変化や毛羽落ちの問題が出てしまうのですが、
シール織りは使用中に毛玉にもなりにくく、
洗濯を重ねても、毛羽落ちしにくいという優れた特長があるそうです。
裁断も機械ではなく手作業で、
2人組で目視検品しながら行うので、ほとんどのキズなどはこの工程で止められ、
仕上がりがキレイなのはこのためでした。

実際に生産現場へ行ったスタッフからは、以下のような感想が挙がっていました。
「当たり前のように無印の店頭に並んでいると感じていた商品が
『大工場』による『大量生産』でなく、
『職人の手仕事』により『一つひとつ丁寧に作られている』
という事実に改めて驚き感動した」
「国内生産、地場産業により地域の歴史と伝統の継承、
雇用促進、経済活動へつながっていることを知った」
「一つひとつの商品には作り手の想い、愛情、熱意が込められており、
それをそのままの温度でお客様へお伝えしていければ…」
シール織り毛布のよこ糸抜き体験にご興味ある方は、
無印良品 ガーデンパーク和歌山のスタッフさんにお声がけしてみてください♪
紀州備長炭
旅の序盤、栃木で取材させてもらった「下野菊花炭」。

くぬぎを原料に低温で焼かれる"黒炭"で、
樹皮も残り、軟らかい仕上がりでした。
その切り口が菊の花のように美しいことから「菊炭」とも呼ばれ、
火着きもよく、茶道の世界で重宝されています。
一方、焼鳥屋やうなぎ屋など、炭火を使う店先で、よく目にする「備長炭」の看板。
高温で焼き締められる"白炭"で、硬くて火持ちがよく、
調理用の炭として重宝されています。
そんな備長炭発祥の地・和歌山県、
その中でも紀州備長炭生産量日本一の日高川町を訪ねました。
人里離れた山中に、炭焼き窯は点在していました。

「煙が出るから、あまり人里に近いわけにいかんわけです」

田中孝(たかし)さんは、その道30年以上の製炭業のプロ。
備長炭の"備長"とは、紀州・田辺藩(現田辺市)の商人、
備中屋長左衛門が販売したことに由来するんだとか。
現在では、その製法が伝わった高知で"土佐備長炭"、
宮崎で"日向備長炭"が作られています。
紀州備長炭の原料は主にウバメガシと呼ばれる、
紀伊半島南部に多く生息する繊密で極めて堅い木材。

主に樫の木が用いられる"日向備長炭"と比べると、さらに堅い印象です。
 ※写真左「ウバメガシ」、右「樫」
※写真左「ウバメガシ」、右「樫」
曲がった枝の角に切れ目を入れて、木製のくさびを挟むことで真っ直ぐにして、

これを自家製の窯の中で縦にくべ、3日間かけて徐々に蒸していきます。

「土佐備長炭の方では、同じウバメガシを用いながらも横にくべる。
このやり方は紀州備長炭の特徴やな」
縦にくべる方が、木内部の水分が抜けやすく、高い温度で焼成できるそう。
こうして徐々に乾燥させた木を、窯口を閉めて蒸し焼きにし、
その後、徐々に窯口を広げて酸素を送り込み、炭化を促すのです。

この時、窯の温度は1000度以上。
自然と対話しながら、天候によって窯の加減を最高の状態を保てるか。
炭焼き師の腕の見せどころです。
そして、徐々に窯から出し、素灰をかけて消火。

ゆっくりと温度を下げ、完成した炭は、
もともとのウバメガシの大きさの1/7程度に縮んでおり、
叩くと金属音のようなキーンという音が響きました。

こうして焼き締められた炭は、着火しにくいものの、
火持ちがよく、煙が出にくいことから、
料理に雑味を与えずにじっくり焼けるのです。
また一見、内部に隙間がないほど焼き締まっているように見えますが、
実は、その内部には無数の小さい空洞が通っていました。
端に石鹸水をつけ、息を吹き込むと、ほらこの通り。

空洞から息が伝わり、細かい泡ができました!
水道水に備長炭を入れておくとカルキ臭が抜けるとか、
部屋に置いておくと消臭効果があるなどいわれるゆえんは、
この細孔に化学物質が付着しやすいためだそう。
時代に合わせて炭の用途は変化してきています。
「これは私の父が焼いた炭です。重くて堅いでしょう。
今の時代、ここまで焼き締めてしまうと、着火しにくくて好まれない。
使ってもらう人に合わせて、炭づくりも変化させていかなくてはならないんです」

田中さんと窯を並べる和歌山県木炭協同組合の副理事長でもある、
日高川町紀州備長炭保存会の会長・足川修さんは、
炭を見つめながらしみじみとそんなことを話してくれました。
伝統製法を守りながらも、時代のニーズに柔軟に対応していくことは、
どの業界においても必要なことなのかもしれません。
吉野の山を守る〜出来杉計画〜
「将来節が出ないように、枝を落としていくんですよ」

この日、山でヒノキの枝打ち作業中だった梶谷哲也さん。
6メートルの一本はしごに上りながら枝を斧で切り落としていきます。
こうしてきちんと手入れをされた森では、
木に日の光が十分に当たり、土からの栄養も行き渡って良質な木材が育つのです。
日本は島国であるとともに、実は国土の約3分の2を山地が占める山国でもあります。
このキャラバンで各地を車移動するなかにもそれを実感しますが、
一方で、手入れの行き届いた山が少ないことにも気付かされます。
道中、切った木がそのまま倒れている現場を目にし、
それを梶谷さんに伝えると、こんな答えが返ってきました。
「使い道のない木はそのまま置いておくんです。腐ってそのまま土に還るので。
業界用語では"捨て切り"っていうんですが、
東京から来た僕も最初はびっくりしましたね。
なんだか申し訳なくて、僕は"切り置き"っていっています」

梶谷さんは東京生まれ東京育ちですが、昔から田舎暮らしをしたい
という想いがあり、15年前に奈良県中部に位置する黒滝村に移住。
組合の森林作業員として、働いています。
山仕事を始めて3~4年経った頃、
使い道がなく土に還っていく間伐材を使って何かできないか…
そう考え、2000年に日本に入ってきたばかりの「チェーンソーアート」に挑戦。
2006年には吉野町で仲間と一緒に
「吉野チェーンソーアートスクール」を立ち上げて、月1回講師を務めたり、
地元の高校で授業を行ったり、県内外のイベントで実演をしたりと活動しています。
「あくまでも山仕事がメインですが、いきなり林業の話をしても
みなさん戸惑うと思うんですよね。
チェーンソーアートを見せながら木の説明をしたりして、
林業のPR活動としてやっています」

梶谷さんは、活動全般を"杉のために出来る事をスギスギ(次々)やっていこう!"
「出来杉計画」と命名し、ブログも開設して、情報発信をしていっています。

「人工林や花粉症など何かと印象の悪い"杉"ですが、
昔からその扱いやすさで日本人とともに歩んできたのも事実。
杉の学名は『Cryptomeria japonica(隠れた日本の財産)』というくらいですから」
吉野の林業従事者は梶谷さんが移住した15年前と比べると半減。
梶谷さんは杉の可能性を見つけるために、杉の葉を使って染物をしたり、

杉のおがくず堆肥を作って、自家菜園で使ったりと、
まさに"スギスギ"と活動の幅を広げられています。
「この辺では山で仕事をする人のことを"山行(やまいき)"って呼ぶんですが、
それは昔から町で働けない人っていう見られ方もしていて。
自分は東京から山仕事がしたくて来ている。
子どもや家族に胸を張って『お父さんは山行なんだ』って言ってもらえるように、
そんな気持ちでこれからも山に入っていきたいですね」

吉野の山を守る〜聖山〜
梶谷さんたち作業員によって間伐された吉野の木材は、
山の麓の製材所へと運ばれ、そこで加工されてから市場に並びます。
「これまでは吉野の丸太にブランド力がありすぎて、
自分たちの力を入れてこなくても正直売れていました。
だけど、見つめ直さないといけない時代になりました」
そう話す、坪岡林業の坪岡常佳さんは、
県の商業振興課が行う「奈良ブランド開発支援事業」の一環である勉強会に参加し、
"製材所でできること"を改めて考えるようになったといいます。
「突き詰めていったら、それは『板』やったんです」
そして、2年前から親族のデザイナー・坪岡徹さんと一緒に
「聖山(ひじりやま)」というブランドを立ち上げます。
「聖山」は、もともと坪岡さんらのご先祖様で、
江戸時代の樽職人が屋号として使っていたもの。
吉野郡川上村に実際に「聖」という地区が実際にあるんだそう。
彼らが最初に開発したのが、吉野杉で作った「折敷」です。
とてもシンプルで、天然の年輪が美しいこの折敷は、
「それぞれに使うシーンを創造してほしい」
と、最低限の様式美を追求し、無駄を省いた作りになっています。
他にも、坪岡さんは、
"製材所としてできることで、どのようにしたら今の生活に取り入れられるか"
を考え、いろいろと考案中。
「ヴィンテージデニムのように、木のキズも風合いにして、
それを味方に変えていければ」
と、木肌にヴィンテージ加工を施したり、
 ※左板は加工後、右板は加工前
※左板は加工後、右板は加工前
製材所で作業に使っている"馬"と呼ばれる鉄の作業台をヒントに、
スツールとしても使え、2つ置いてそこに板を乗せたら、
簡単にテーブルができてしまう「馬」を開発したりしています。

「加工だけではなく、ものづくりをしたことで、
初めて直接お客様から"ありがとう"っていってもらえましたね。
自分で土俵作っていかないとダメやと思ってます」

梶谷さんも、坪岡さんも、これまでの吉野木材の歴史を踏まえつつ、
それぞれが今できることを、それぞれのやり方で発信し、
吉野の山を守っていっています。
吉野割り箸
私たちの生活に欠かせない道具のひとつ、お箸。
なかでも、外食時に多用している「割り箸」については、
「使い捨てはなんだかもったいない…」
そのように考えている人も少なくないかもしれません。

しかし、もとを正せば、この割り箸こそ、
「もったいない精神」の産物だったのです。
奈良県吉野地方は、古代から杉やヒノキが多く生えており、
1500年頃に造林が行われた記録があり、"林業発祥の地"と呼ばれたりもします。
一般に吉野の木材が多量に搬出されるようになったのは、
豊臣秀吉が大坂城や伏見城の建築を開始し、その建材利用や、
神社仏閣の用材としての需要が増加し始めた頃からだといいます。

江戸中期以降には酒樽の生産が盛んになり、
吉野杉材で作る樽の材料の端材が捨てられるのを惜しんで
「割り箸」が考案されました。

現在も、家の柱などの建築材として使われる中心部分を切り取り、
"木皮(こわ)"と呼ばれる残った部分を材料として、
「吉野割り箸」は作られています。
実は無印良品でも、毎年年末に吉野杉の割り箸を取り扱っています。

その生産者を訪ねると、端材を割り箸の長さにそろえるところから、
割り箸の形に加工されるまでの工程を見せていただくことができました。
また、驚いたのが、加工後の選定作業。
割り箸一本一本の年輪の幅や色を目でチェックし、ランク別に仕分けていくのです。
気の遠くなるような作業です…。

並べてみると、その違いが一目瞭然。
同じ杉を使っていても部分によって色が異なるのです。
左から順にランクの高いものですが、一番左の赤杉は木の中心部分を使うため希少で、
香りや抗菌作用が、白い部分よりも強いのだとか。

「残念ですが、日本で消費されている割り箸の98%は輸入品なんです。
海外産の割り箸は大根のかつら剥きのようにした板から作るので、
木目の向きなど関係なく、仕上がります。杉の割り箸はまっすぐに割れますよ」
生産者の涌本友晴さんがそう教えてくれました。

割り箸の大きな特徴は「食べる直前に割って使う」という点。
日本において、割り箸を割る行為は、
祝い事や神事などの「事をはじめる」という意味を持ち、
大事な場面には真新しい割り箸が用意される風習があります。
塗り箸もナイフやフォークも、何度も使うものなので、
1人1回きりしか使用しない割り箸が、
実は、本来客人をもてなすための「ハレの日」用なのだそう。
私たちも普段割り箸を割る際に、2本が均等に割れると
何かいいことが起こるような、そんなハッピーな気分になるものです。

ところで、吉野の割り箸は、
吉野で切った木をそこで加工し、そのまま出荷するので、
今回その工程を見てみても、何か薬品を使ったりすることはありません。
一方で、海外産の(特に竹製の)割り箸は、輸入の際に防カビ剤や防腐剤、漂白剤などが
使われているといいます。
使い捨てから"もったいない"というイメージを持たれがちな割り箸ですが、
本来そのまま捨てられるはずの端材や、森林整備で生じた間伐材を
有効活用することから生まれた、アイデア商品。
既にコンビニエンスストアや外食チェーン店の一部で、
国産材を使った国内産割り箸が使われているようですが、もっとそれが普及すれば、
割り箸が日本の森林を継続的に支えることのできるアイテムとなるかもしれません。
普段なにげなく使っているものが、
「どこでどのように作られているのか」を知ったり、
「"もったいない"といわれているものは本当にそうなのか」
などと掘り下げていくことが、
日本の森林問題のような大きなテーマに結びつく第一歩なのかもしれません。
履き心地の良い靴下
普段は当たり前だと思っていることでも、
よくよく考えてみると不思議なことってありますよね。
「なぜりんごは落ちるのか?」の疑問から
ニュートンが万有引力を発見した話はあまりにも有名ですが、
まだまだ日常に疑問は眠っています。
例えば、「なぜ日本車は右ハンドルなのだろう?」とか、
「なぜバレンタインは女性から男性にチョコレートを渡すのだろう?」
「なぜテレビは長方形になったのだろう?」などなど…。
そこには様々な背景が隠されているのですが、
得てして、外からの目線で気付くことが多いものです。
無印良品の足なり直角靴下も、こうした疑問から生まれたそう。
「なぜ人のかかとは90度なのに、靴下は120度なのか?」
そんな疑問を抱いたのも、無印良品の開発担当者が、
チェコのおばあちゃんが編んだ90度の靴下に出会ったことからでした。
疑問を解消すべく、靴下の歴史について調べていくと、
1560年頃、エリザベス女王1世に贈られたという手編みの靴下が、
直角だったことが分かります。
120度の靴下が一般的になったのは、工業化以降のことで、
機械で量産できる角度が120度だったというわけなのです。
さらに、靴下をお店に並べる際、かかとから半分に折り畳むため、
キレイな形に畳めるように、角度が決められていたんだとか。
つまり、生産効率や店頭での見た目の美しさが重視され、
形による履き心地については注目されないまま、現在に至っていたわけです。
チェコのおばあちゃんの手編みの直角靴下は、
かかと部分がすっぽりと収まって余ることなく、ズレ落ちにくく、
とても履き心地の良いものだったそう。
そんな直角靴下の履き心地の良さを、
もっと多くの人に手軽に味わってほしい。
無印良品の開発担当の想いから、編み機の改造を加えるなど試行錯誤を重ね、
2006年11月、満を持して3種類の「足なり直角靴下」が誕生します。

大ヒット商品となり、2010年2月にすべての靴下が直角となり、
2012年10月には、さらなる履き心地の良さを追求してリニューアルを果たしました。
そんな無印良品の「足なり直角靴下」を作る現場を訪ねました。
実は、奈良県は靴下の国産生産約6割を占める一大産地。
1910年代に、とある農家が農業の閑散期における副業として、
アメリカから靴下製造の機械を導入したことがきっかけで、
今も納屋に機械設備を構える家内工業の生産者が多いそう。
ただ、最盛期には920社あったといわれる生産者も、
2000年以降、安価な海外産の靴下に押され、現在では150社ほどに減少。
それでも、これだけの生産者が残っているのは、
国産の品質の良さが評価されてのことです。
驚いたのが、その糸の種類の多さ。

昨今、様々なデザインの靴下があるので、
糸の色の種類が豊富なのは分かるのですが、
なんと1足の靴下に表糸、裏糸、ゴム糸に加え、柄糸と、
3種類以上の糸が使われているのです。
これも足によりフィットさせるための工夫で、履き心地を追求した結果です。
工場内は、リーズナブルな価格で提供できるようにと、
驚くほどの機械化が進められていました。

編み方を指示すると、自動で刺繍の様な織柄も含め編み上げてくれるという優れた機械。
5分ともしないうちに、1本の靴下が編み上がっていきました。
この時点ではつま先部分は縫合されておらず、なかには連なっているものも。
「この機械を使いこなせるか。ここがメーカーの腕の見せ所」

その道47年の生産革新部の向井部長はそう語ります。
この工場では右足用と左足用とで編み分けており、
こうした技術が培えたのも、普通なら機械を調整する会社しか触らないところも
積極的に自分たちでいじって、改良を加えていったからだそう。
右足用と左足用とで作り変えている箇所も、
かかとの内側と外側のアーチの角度だとか。
ここまで細部にこだわった靴下ですから、履き心地が悪いわけがありません。
左右によって違う靴下は「R」と「L」の刺繍の様な織柄が目印です。

実は、向井部長は、過去に健康を害し入院生活を送ったことがありました。
そんな寝たきり状態では、それまで履いていた靴下がとてもキツく感じたそうで、
より履き心地の良い靴下を開発しようという想いが巡ったんだとか。
靴下って健康と同じで、不快に感じると気になるものですよね。
私たちもこの旅でずっとこの足なり直角靴下のお世話になっていますが、
今まで一度も不快に感じることも、買い換えることもありません。
それだけ足になじんでいて、さらに丈夫なのです。
最後に吉谷社長は、靴下生産にかける想いをこう語ってくれました。

「一度、技術を途切れさせてしまったら、復活させるのは難しいことです。
この技術を途絶えさせないように、雇用を大事にしながら、
常に新しい技術革新を起こしていきたいです」
無印良品の足なり直角靴下は、
こうした様々な方たちの「想い」が結晶となったものでした。
良い石鹸
江戸時代、生活物資の多くが集積し、
それを全国の消費地へと送っていた大阪は、
「天下の台所」と呼ばれていました。
その名残からか、大阪は今もものづくりが盛んです。
そのうちの一つが「石鹸」。
石鹸の起源は紀元前にまでさかのぼるようですが、
日本に伝わったのは種子島に鉄砲が伝来した頃といわれています。
明治初期には、日本で本格的に石鹸生産が始まりましたが、
当時は高価なもので、一般的に普及していったのは明治後期以降のこと。
CMソングで知られる「牛乳石鹸、良い石鹸♪」が大阪に誕生したのもその頃で、
当時から既に日本の石鹸産業の中心地は大阪でした。
そんな地で、創業以来、
天然素材と伝統製法で作り続ける石鹸メーカーがありました。

桶谷石鹸株式会社。
伝統の釜炊き製法で作られる、
無添加・無着色・無合成界面活性剤の国産純正石鹸です。
「グツグツ、ポコポコいってるのが聴こえるやろ。
今、石鹸が良い石鹸になりたいって、ワシに語りかけてきてるんや」
と、まるで我が子のことを語るかのように石鹸のことを話すのは、
2代目の桶谷正廣さん。

蒸気を吹き込みながら煮込まれた原料は、
ちょうど界面活性剤の一種、石鹸へと変化を遂げる過程でした。

「常に自然環境は変わるやろ。
毎日同じ作り方しとっても、同じ変化はしてくれへん。
だから舐めて味を見たり、五感を使って確かめるんや」
桶谷さんが使う原料は、牛脂とヤシ油、苛性ソーダに食塩水のみなので、
舐めても刺激を感じることはありません。
さらに排水後、成分は1日以内にバクテリアによって分解されるため、
環境に負担をかけることもないそうです。
現在、一般に多く流通している、香料など化学成分が添加されている合成洗剤は、
バクテリアによる自然分解に時間がかかるうえ、その歴史も浅いため、
何世代にもわたり使い続けた際の人体や生態系への影響は
まだ判明していないのが実態だそう。
「合成洗剤は安くて、匂いや効果など即効性があるように感じる。
一方の石鹸は、体に刺激を与えない。敏感肌の人はすぐ分かるで」

桶谷さんは、石鹸は漢方薬のようだと話します。
「良い石鹸を使い続けることで、冬場の肌のトラブルなどを緩和してくれる」
その自信はあると語ります。
6~7時間ほど炊かれた釜には、
できたてホヤホヤの石鹸の姿がありました。

これを2~3日枠に入れて成型し、カットして自然乾燥させ、
製品となって出荷されていくのです。

「何も語らんけど、かわいいやろ」

できたての石鹸を眺めながら微笑む桶谷さんは、
まさに石鹸の父親の表情をしていました。
自然にも体にも優しい桶谷石鹸には、
作り手の優しさがにじみ出ているかのようでした。
西の旗艦店で人気の逸品!
大阪の二大繁華街の一つ、ミナミの玄関口「難波(なんば)」。
その一角の一等地に、無印良品難波店![]() がありました。
がありました。

難波センタービルB2~3Fの5フロアを占有する
無印良品、関西の旗艦店です。
B2フロアには、Cafe&Meal MUJIのレシピ本で知られる
松岡シェフが腕を振るう『Meal MUJI』を構え、
食品コーナーには、
全国の良品が集められた「Found MUJI」のラインナップが展開されています。
上階は、ゆったりとした店舗スペースをふんだんに活かしたレイアウトで、
ファーニチャーを扱う3Fでは、収納アドバイザーの相談を受けながら、
オーダー家具の注文をすることもできます。
これだけ大きな無印良品の人気商品とは一体、何でしょう?
さぞかし大きな商品が人気だろうと思いきや、
スタッフさんにご案内頂いた先は…、

なんと化粧品コーナーでした!
そして、その手に持っている人気商品はなんと、

「洗顔用泡立てネット」!
空気と水分をたっぷりと含ませ、石鹸を包むようにしてよく揉むと、
ふわふわの泡ができ、優しく洗顔ができる逸品です。

奇遇にも石鹸つながりの商品でした。
それもそのはずで、
店舗面積の広い難波店では、ビューティー&コスメコーナーで、
よく泡立て方のデモンストレーションも行っているんだそう。
情報に敏感なエリアに位置しているがゆえに、
お客さんにもスキンケアに敏感な方が多いのかもしれませんね☆
日本人による、日本人のための自転車
今でこそ、誰もが気軽に乗っている自転車ですが、
日本で一般的に普及したのは明治時代のこと。
当時、大半の自転車はアメリカ、イギリスからの輸入品でしたが、
明治末期頃から、国内の製造会社が技術力と販売力をつけてきました。
その頃、活躍したのが戦国時代から培われてきた金属加工技術を持つ、
大阪・堺の鉄砲鍛冶でした。鉄砲の銃身を作る技術が、
自転車のフレームのパイプを作る技術として転用されたのです。
現在では、その生産拠点のほとんどが海外に移ってしまった自転車産業ですが、
今でも自転車利用者の多い大阪。
そんな大阪の街角で、一際目を引く自転車に出会いました。

お店の前に並べられていた自転車は、これまであまり
日本では見たことのないスタイルのもの。

なんだか過去に旅した自転車王国・オランダで見かけた
自転車を想起しました。
※2010年オランダ・アムステルダムで撮影
「これ、僕が通勤に使っている自転車なんですよ」
そう話すのは、日本製ハンドメイド自転車フレームを手掛ける、
「E.B.S.(Engineered Bike Service)」代表の小林宏治さんです。

「僕自身が大阪市内に住んでいて、車を持たない生活なんですが、
自転車がそれを補えるツールでありたいと思って。
荷物をたくさん積める自転車を作りました」
長年、自転車の流通業に携わっていた小林さんは、
欧米製の自転車を輸入・組立てしていく中で、
日本人の体型や生活に合った自転車のリクエストを
数多くお客様から聞いてきたといいます。
そんな時に出会ったのが、かつて自身も選手として自転車競技の実業団に所属し、
大阪の名門フレームファクトリーに勤務していた経歴を持つ、
佐々木隆二さんでした。

「自転車の可能性を広げたい!」と意気投合した2人は、
レンガ倉庫の一角を借りて工場を構え、
ゼロからの自転車作りをスタートしました。
彼らの作る自転車のコンセプトは、
「生活に即した修理可能で、永く快適に使える自転車」。
最近、スポーツ自転車フレームの素材として使われているのはカーボンが主流で、
その場合、溶接等ができないため修理が利かないそうですが、
「E.B.S.」では、修理や仕様変更の自由度が高い、
クローム・モリブデン鋼(クロモリ)を使っています。
例えば、この"LEAF-LONG"というお子様の送り迎え用の自転車は、
子供が成長した後に、フロントのカゴと後ろの荷台を取り外せば
スポーツ自転車として使えるのです。

また、自分たちが試乗して感じたことや、お客様からの声で、
その仕様は日々改善されていくそう。
"LEAF-LONG"では、子供の乗せ降ろしの際にしっかりと動かないようにと、
安定感のあるスタンドに変更されました。

さらに、小林さんは自転車のほかにこんなものも開発されていました。
「箱具」と呼ばれる、持ち運びできる木製の組み立て椅子で、
木工職人と共同で作ったものです。

「これを自転車のカゴにポンと乗せて出掛けたら、
どこでも走って出掛けた場所がピクニック空間になる」

斬新なアイデアを次々と形にしていっている「E.B.S.」ですが、
果たして肝心の乗り心地はどうでしょうか?
お店の前で試乗させてもらうと…

ビックリするほどにスイスイと坂道を上れてしまうではないですか!
一瞬、電動自転車に乗っているのかと錯覚してしまうほどでした。
それは、プロ仕様の自転車に用いられてきた技術を
佐々木さんが一般向けにアレンジして採用しているからです。
最後に、佐々木さんと小林さんそれぞれに
自転車づくりにかける想いを伺いました。
「乗ってよかったと思ってもらえるように、
常に乗る人のことを考えて作っています。
僕自身が自転車に乗っていたからこそ、
自転車の寿命や乗る人の気持ちが分かるんです。
幼稚園児の頃、祖母に買ってもらった自転車で遠出してしまい、
迷子になってパトカーで送ってもらった思い出があるくらい自転車が好き。
自分は自転車に乗るために、自転車を作るために生まれてきたんだと思っています」
(佐々木さん)
「20~30年のライフスタイルで永く使える自転車を、永く作り続けたいですね。
目の届く範囲で、派手ではなくコツコツと誠実に続けていきたいです」
(小林さん)

性能はもちろんのこと、乗ってわくわくし、
いつまでも使える自転車を作り、提案し続けている「E.B.S.」。
日本人による、日本人のための自転車がそこにありました。
ダンボールの可能性
このカフェ、一見普通のカフェと同じようですが
何かが違うのが分かりますか!?

実はこのカフェの机も椅子もライトも、全部ダンボールでできている、
その名も「cafe だんぼうる」なんです!

これは、天王寺にあるダンボールケース製造会社・矢野紙器の運営するカフェ。
矢野紙器では、就労領域の拡大のための活動の一環として、
「cafe だんぼうる」を3年ほど前から行っています。
というのも、矢野紙器は"障がい者雇用"という概念がほとんどない時代から、
聴覚障がい者をはじめ、障がいのある方を複数採用してきた歴史があり、
昨今増えている発達障がい者やニートと呼ばれる人も含めて
彼らの職業体験の場としても機能させるべく、カフェを始めたのです。
「僕のいる部署は、『人の可能性とダンボールの可能性を
もっと社会に役立てること』がミッションなんです。
ダンボールを使った工作教室や、
ダンボールでできた遊具や展示品のレンタルなんかもやっていますよ」
Able Design事業部 プロダクトマネージャーの
島津聖(しまづきよし)さんが説明してくださいました。

「工作教室は材料と道具だけ用意して、あとは自由にするんです。
子どもの発想力って面白いですよ。
親子で教室をすると、大人は自由といわれると悩みますが、
子どもがテーマを与えてくれるんですよ。
『これで家作りたい!』『飛行機がいい!』とか」
「子どもと一緒にお父さんがたくさん参加してくれる人気のイベントです。
お母さんと一緒のイベントはあっても、
お父さんが活躍できるイベントはあまりないので」
材料はもちろん工場で作っているダンボール箱や端材、
折り紙、紙コップなどできるだけ手に入れやすいものを用意。
それは、家庭でもできるように考えてのことです。
「ダンボールが親子のコミュニケーションのツールになれば」
と、島津さん。
ダンボールでできた巨大なボウリングや、

全長4.6m、高さ2.6mにも及ぶダンボールのマンモス、
通称「ダンモス」は人が集まるイベントなどで大活躍だそう!

矢野紙器のダンボールを使ったこれらの斬新な取り組みが
なぜ行われるようになったのか、
気になって尋ねてみると、こんな答えが返ってきました。
「僕自身がものすごい田舎で育って、遊び場がないから
自分でものづくりして遊んでいたんですよね。
近所のおじちゃんに手伝ってもらったりして、
そこで大人との対話が生まれて。
僕の原風景を形にしているのかもしれません」

広島県出身の島津さんは、大学のゼミで「福祉と経営の融合」
について勉強しており、
事例を調べていく中で矢野紙器と出会い、卒業後に入社。
その際、社長から「ダンボール」「障がい者」
「ダンボールを好きな形に切れる機械」をキーワードに
やりたいことをするようにいわれ、今の活動があるといいます。
「よく"ダンボール=強い"って思われがちなんですが、
箱が頑丈すぎると中に衝撃が伝わってしまって意味がないんです。
"ダンボール=弱い"という特徴も伝えていけたら」
また、今後は地域のクリエーターと組んで、
ダンボール製品も増やしていきたいと、島津さんは話します。
尊敬する人の言葉で「やればわかる やればできる」
をモットーとする島津さん、
そして矢野紙器のダンボールへの挑戦は今後さらに広がりを見せそうです。
大阪文化の象徴!?
大阪万博のシンボルとして、
今も存在感を発揮する「太陽の塔」。

その場所に程近い「無印良品イオン茨木![]() 」で、僭越ながら、
」で、僭越ながら、
我々、MUJIキャラバン隊がイベントを開催させていただきました!

この日本一周前に果たした世界一周の話も交えながら、
旅路で見つけてきた逸品が当たるというトーク&クイズイベント。
札幌、福岡に引き続き3回目にして、初めてのクイズ形式だったのですが、
さすがは大阪の方々です!

正解かどうか定かでなくても、お構いなし。
手が挙がる!挙がる!
積極的に参加していただけたので、
話しているこちらも楽しくて仕方がありませんでした。
イベントにご来場いただきました皆様、
誠にありがとうございました!
そんな、こちらの店舗での人気商品もご紹介!
MUJIキャラバンのハッピでそろえた
素敵なスタッフさんたちの持っているものは…、

「優しい昔菓子」。
このシリーズ、私たちも好きなんです!
マーブルチョコに、ふがし、ボーロ、きなこ棒、わた菓子等々…。
その名の通り、昔懐かしいお菓子ばかりで、
見ているだけでもワクワクした気持ちになれます☆
店長によると、
「大衆文化の色濃い大阪ならではの人気商品じゃないでしょうか!」
とのこと。
確かに大阪には、
「中野の都こんぶ」や「当たり前田のクラッカー」など、
昔ながらの名物おやつが生まれていますからね。
無印良品にお立ち寄りの際には是非、おやつコーナーへ♪
大阪人ならずとも、童心に返った気分に浸れると思います。
coccori(コッコリ)
先日のブログでご紹介した「ファブリカ村」を訪れた際、
一際、目を奪われたカラフルな展示品の数々。

一つひとつから醸し出される温かみから、
きっとそれが人の手によってゆっくりと作られたものであることを感じました。
その織物の名は「coccori(コッコリ)」。

実はこれらは、滋賀県の福祉作業所で働く
障がい者の方たちによって作られたものでした。
「素敵でしょ? でも、しばらく作業所の倉庫に眠っていたんですよ」
そう話すのは、Team coccori事業代表の市田恭子さん。

作業所の中間支援を行う (社)滋賀県社会就労事業振興センターで、
障がい者IT利用促進事業コーディネーターとして働く市田さんは、
これらの織物が、作業所の倉庫に保管されているのを発見しました。
繊維関係の工場などから、不要品として調達してきた糸を使って、
障がい者の方たちが一生懸命、はた織り機を使って織ったものでしたが、
売るあてもなく、そのままの状態で眠っていたのです。
「これはかわいい! 倉庫に眠らせておくなんてもったいない。
なんとかできないか? って考えました」
こうして市田さんは、滋賀県内で活躍するデザイナー6名とともに
「Team coccori」を結成。
"作りっぱなしの商品"から"買ってもらえる商品"にするために、
様々な商品を企画していきました。
かけるだけで映える敷物や首ストラップ、
鍋包み(写真右)に、現在企画中のペンケース(写真左)等々。

ストールはこの通り、とっても素敵♪

同じものが二つとない独創的な色合いが魅力的です。
「この事業で実現したいことは、何よりも障がい者の工賃向上なんです」
市田さんいわく、作業所で働く障がい者の賃金は、
全国的にみて月平均1万3000円といったところ。
障がい者年金と合わせてもとても自立できる金額とはいえません。
重度の障がい者がきちんとした社会保障を受けられるようにするためにも、
元気な障がい者が、税金を納められるぐらいの稼ぎを得られるようにする。
市田さんは活動目的をそう話します。
Team coccoriでは、他にもこんな逸品も展開していました。
「湖のくに 生チーズケーキ」

何やら入っているのはおちょこのようで、
一つひとつ書かれている文字が違います。
そう、これらは滋賀県内の琵琶湖周辺にある6つの酒蔵の、
風味の異なる"酒粕"を使ったチーズケーキなんです。
酒粕とは、お酒を作る時にできる米麹の搾りかすで、
近年、栄養素に富んだ食品として価値が見直されており、
酒蔵によっては"しずく"と呼んでいるほどの代物。
これまでも甘酒や漬物などにも利用されてきましたが、
とても使いきれる量ではなく、その使い道に頭を悩ます酒蔵も多かったそう。
それが、県内の作業所で働く障がい者の手によって、
生チーズケーキへと生まれ変わったのです。

そのお味はとても芳醇で、
お酒と同様に、酒蔵によって風味が見事に異なりました!
これを、同じく作業所で作られた「酒粕ビスコッティ」に付けると、
格別な味わい。

スイーツとしてはもちろんのこと、
ワインのつまみにもイケてしまいそうです!
日本酒の酒粕が、ワインに合うなんてまた不思議ですね。
「障がいのある方たちも、基本的欲求は健常者と一緒。
認められて、その対価をもらうとうれしいんです。
これらの事業によって、明らかに生活に張りが出てきた方もいるんですよ」

coccoriによって明らかに変化が生まれている滋賀県の福祉事業。
ただ、そこから生み出される商品は、
作り手が障がい者か健常者かということではなく、
素直に感動を受けるものばかりでした。
ファブリカ村
滋賀県東近江市にある「ファブリカ村」。
琵琶湖の東に位置する東近江市は、
湖からもたらされる湿気が麻の製織に適していたことから、
麻織物の産地として栄えてきました。
ファブリカ村の前身である、北川織物工場は1964年に建てられました。
ちょうど東海道新幹線が開通したり、
東京オリンピックが開催されたりした年のこと。
当時、北川織物工場では、
麻織物を用いた布や寝装品、和装小物などを作っていたそうです。
京都や名古屋が近い立地から、
婚礼布団や婚礼座布団のニーズが高かったんだとか。
「昭和初期は、織機をガチャンと動かせば万単位で儲かる。
当時は麻織物が"ガチャ万産業"っていわれていたんですよ」

そう教えてくださったのは、北川陽子さん。
繊維産業は下請けから脱却して
提案型の産地になっていかなければならない…という、
「産地の高度化プロジェクト」がスタートした1980年代に、
京都の美大で染色コースを卒業した北川さんは、家業の北川織物工場に入りました。
それまで洋服をただ着ていた時代から、ブランドの時代へと変遷。
ヨウジヤマモトなどの有名デザイナーが直接素材を探しに産地へ赴き、
素材からデザインしていた面白い時代だったと、
北川さんは振り返ります。
「うちには、おじいちゃんの時代から作っていた、
手仕事の括り絣(かすり)が残っていたので、
絣に特化してデザインを起こすようになりました。
当時、うちにもヨウジヤマモトさんが来て、絣を見て
『モダンだ!』っておっしゃって。
その時、地域の素材は残していかないといけないな、と思ったんです」

しかし、次第に素材は海外のものを使う時代に…。
半年間かけて作った絣に少し傷があっただけで
焼却処分されてしまう現場を目にし、
北川さんはものづくりに対して疑問を持つようになったといいます。
この頃から素材として絣を作る一方で、
直接販売できるクラフト市などに参加するようになり、
値段だけの取引ではなく、産地について考えるようになったそう。
「実際に自分で販売してみると、近所の人でも
近江が麻の産地であることを知らないんですよ。
ここの土地にできてきた意味を考えないと…って、
この頃から地域を意識するようになりましたね」

もともと人と話すことが大好きという北川さんは、
地域の集まりや組合、異業種交流会などにどんどん参加し、
それまで関わってこなかった人たちとの関わりを通して
ものづくりに加えて、「ことづくり」の楽しさを知ります。
そして、"きちんと地域のものを残していきたい"、
"北川織物工場が守り続けてきた手仕事の良さを伝えたい"と
休んでいた工場を「つくるよろこびにふれる場所」として復活させました。
それが、「ファブリカ村」です。
「ファブリカ村」では、染めや織りなどのワークショップを行ったり、
地元の食材を使ったカフェや、地域の作家が作ったものを買える場を提供したり。
「海外との価格競争に巻き込まれるのではなく、
本当に欲しい人にものを届けられるように。
この空間を共有してもらい、
生活者の意識を少しでも変えられる場所にできたら」
そんな想いを形にし、場の大切さを実感した北川さんは
次々に行動を起こします。
"まずは自分たちが地域のことをもっと知ろう"
"横のつながりを作ろう"
と、異業種の作り手を集めた「湖の国のかたち」を結成。
地場産業の産地めぐりツアーを企画したり、
様々な勉強会や交流会を実施したりしています。
時代とともに自身の考え方が変わってきた北川さんが中心となり、
学び、出会い、そして体験することで
新しいものを生み育てていきながら、
自らの感性と次の世代の感性を育んでいこうというこの取り組み。
その裏には、近江の国から多くのものを全国へと流通させていった、
近江商人の商訓「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」
が今でも残っていました。
もちろん、北川さんは本業のものづくりも続けていらっしゃいます。
近江の麻を使った服や小物のオリジナルブランド「fabrica」を展開中。

北川織物工場は、ものづくりの現場に加えて、
滋賀県のモノ、コト、ヒトが集まる情報発信基地「ファブリカ村」として、
その活躍の幅を広げていっています。

「滋賀は面白いですよ!独立してもやっていける」
北川さんのこの言葉は、地元を知っているからこその言葉だと感じました。
紫香楽研究所
先日、京都の綾部で訪問した半農半X研究所の塩見さんが
世の中には多種多様な"研究所"があると話していましたが、
お隣の滋賀県で早速、とある研究所に遭遇しました。
「紫香楽(しがらき)研究所」

奈良時代、近江国甲賀郡(現在の滋賀県甲賀市)には
聖武天皇が造営した離宮「紫香楽宮」があったそう。
聖武天皇は742年に紫香楽の地に都を移し、
大仏建立のプロジェクトが紫香楽の地で進められ、
各地から技術を持った人々が集いました。
しかし、天災が続き、都は平城京に戻り、
大仏像は現在の東大寺で造立。
この時残った技術者が定住し開発したのが、
日本六古窯の一つの「信楽焼(しがらきやき)」です。
昔、琵琶湖の湖底だった場所の山から採れる土は、
粘り気が強く成型しやすいため、
大物を作るのに適しているといいます。
火鉢やすり鉢から始まり、
現在の信楽焼は、食器や花器、植木鉢、傘立てやタイルなど幅広く作られ、
常に人々の生活とともに歩んできた焼き物であることがうかがえます。
無印良品でも、信楽焼の飯碗を扱っていますが、
こちらは白土の素朴な風合いを生かしたものです。

信楽焼は各窯元の土のブレンド方法によって、
その表情の幅がとても広いのです。
また、全国のお店の軒先などで見かける、
愛くるしい狸の置物、これも立派な信楽の焼き物。
信楽町には、もしかしたら人よりも狸の方が多いんでは!?
と思うほど、あちこちで狸の置物が迎えてくれました。
ご案内いただいた、紫香楽研究所の寺脇達夫さんは
長年、信楽陶器工業協同組合に勤めた後、
「信楽焼に欠けている部分を担いたい」と58歳で独立。
紫香楽ラボ株式会社と、紫香楽研究所を立ち上げました。
「社会に必要な産地であり続けるためには、歴史と伝統的技法を改めて耕し、
デザイン力や流通力、知恵を持つ人々と情報交換し
連携してやっていく必要がある」

紫香楽ラボをマネージメント母体として、
紫香楽研究所は、時代を先取る
ソフトウェアを生み出す孵化(ふか)装置と考えていると話します。
そんな紫香楽研究所で研究・企画された商品は、
従来の焼き物に現代生活者向けの機能を持たせたものばかり。
例えば、ラジウム鉱石を粉砕して釉薬に使用したボトルで、
中に入れた水がアルファ線の作用によってイオン化して
味がまろやかに感じられるようになるという「魔法のボトル」や、

信楽焼のメーカーと一緒に開発した陶製のスピーカー、

また、東京のデザイン会社とのコラボ商品である
フタと本体の間の溝からお茶が流れ出る仕組み(昔からある伝統技法)の
茶こしを使わない絞り出し方式の急須の提案などを行っています。

1250年の歴史を持つ信楽の地で改めて"研究所"を作って、
信楽焼の研究開発を続ける、紫香楽研究所。
「自分たちから発信しない限り、何も始まらない。
コミュニケーションと情報の交流ができた時に
初めてモノが売れる時代ですから」

伝統を生かしながらも、現代のニーズに合わせた信楽焼が生み出されているのも、
寺脇さんを筆頭に、情報の流通を促す方々の存在があってこそだと感じました。
Made by Japanese
京都市河原町にある、明治8年創業の「開化堂」。

茶筒専門店としては、日本で最も古い歴史を持つといわれています。
そんな長い歴史を持ちながらも、創業以来からほぼ同じ製法で作られる茶筒は、
今の時代にも色褪せることなく、洗練された輝きが放たれています。

明治初期の文明開化の頃、
英国から輸入された錻力(ブリキ)を使って缶を作ったのが始まりとか。
銅や真鍮をまとった美しさは、思わず目を見張るほどです。

茶筒の使い心地を左右するのは、蓋のフィット感。
キツすぎても緩すぎても、どうも心地悪く感じてしまいますが、
開化堂の茶筒は、上蓋と下蓋の継ぎ目を合わせるだけで、
音も立てずにゆっくりスーッと閉まってくれます。
この絶妙なフィット感は、開化堂5代目の八木聖二さん、
6代目隆裕さん親子によって生み出されています。
「この感覚は初代から変わっていないんですよ。
実は内側にカーブしていたり、微妙に膨らみがついていたり…。
見えない部分にも手間がかかっていて、その工程は130に及びます」

そう話す6代目の隆裕さんは、職人でありながら、
プロデューサーとしての一面も持っています。
大学卒業後、就職した先で海外勤務を経て、家業に転身。
それまでに培われた語学と適応性を生かして、
5年ほど前から、開化堂ブランドを海外へ展開し始めたのです。
ニューヨーク、ロンドン、パリなどで開催される展示会では、
茶筒づくりを実演し、海外のバイヤーからも高い評価を獲得。

今やその先は欧米を中心に10カ国に広がっています。
「Made in Japanを打ち出して、一部の日本好きをターゲットにするよりも、
いかに海外の人の日常生活に取り入れてもらえるかを念頭に置きました」
と隆裕さんが話すように、海外での見せ方は茶筒としてではなく、
様々な食材の保存容器としての見せ方をしています。

パスタ缶といった容器にまで、その用途は拡大しています。

「ただ、あくまでもこれらは茶筒を知ってもらうためのツール。
祖父の時代、機械化の波に押されながらも、京都のお茶屋さんが
"ワシが買うてやるから、お前のとこはいいものだけ作っておけばいい"
といって使い続けてくださったことを、忘れてはいけないと思っています」
隆裕さんは、開化堂のコンセプトは以下の3つだと話します。
*機能的
*シンプルなデザイン
*長く使える
機能的で、シンプルなデザインというのはいうまでもありませんが、
長く使ってもらえるように、修理までも受け付けているんです。
新しいものを買ってもらう方が、企業としては利益が上がるだろう所、
直せるものはできる限り直す、という姿勢には感銘を受けました。
使い込んでいくうちに変化する光沢と色は、
まさに「用の美」。

錻力(ブリキ)で30~40年、銅で1~2年、真鍮で3~4年ほど使うごとに、
徐々にその味わいを深めていくのです。
さらに、写真右下の真鍮は、使う人の食べているものによって、
右のような赤褐色か左のような黄金色か、どちらに変化するか分からないそう。
そのワクワク感と、いつまでも飽きのくることのない魅力に、
思わず真鍮の茶筒を一つ買わせていただきました。
現在、他の京都の伝統工芸4社とともに、
日本の伝統技術を海外へ打ち出す取り組みにも従事する隆裕さん。

「日本の伝統技術を分解して、海外のマーケットに合わせて展開する。
Made in Japanではなくて、Made by Japaneseが実現できれば、
日本の伝統産業は続いていけると思っています」
日本のものづくりの未来までをも見据え、
海外へも発信できる力を持った伝統工芸の職人は、
これからの時代における模範と呼べるかもしれません。
世界にひとつだけの靴
日本の主要な国際貿易港である五大港のひとつに指定されている、神戸港。
1868年に開港し、同年1月から1899年7月の間、
現在の神戸市中央区に外国人居留地が置かれていました。
外国人居留地は貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、
周辺地域に経済的・文化的影響を与えました。
そして、今でもその街並みや文化の名残が残っています。
当時、草履や鼻緒を作っていた職人は、
居留地に住む外国人の靴の修理や新調を行うために、靴職人に転業。
京都は呉服の街=「着倒れ」、大阪は食の街=「食い倒れ」に対して、
神戸は履物の街=「履き倒れ」と表現されていたほど、
神戸の街には靴屋が軒を連ねていたそうです。
しかし、昭和に入ると、工業製品として開発された「ケミカルシューズ」が
神戸市長田区の地に誕生し、靴職人も長田へと移り、手づくりの靴職人は減少。
そんななか、8年前に会社員から転身して、
オーダーメイドの靴職人として活躍する、大森勇輔さんに会いに行きました。
ビルの一室のドアを開けると…

そこはコンパクトながら靴づくりに必要な材料やミシンなどが並ぶ、
大森さんの靴工房でした。
もともとものづくりが好きだった彼は、
靴のほか、鞄や服飾の道も考えましたが、
「どうせやるなら、一番難しい靴づくりにチャレンジしよう」
「健康に根差した靴づくりを学ぼう」
と、三田(さんだ)市にある足にハンディーキャップを持つ人のための、
靴づくり専門学校に進みます。
「僕たち日本人も椅子を使う生活が中心になってきて、
骨格が欧米化しつつあるんですよ。
だけど、靴がその骨格になかなか追いついていない。
そうすると歩き方が変になって、腰を痛めたり、足に悩んでいる人もすごく多い」
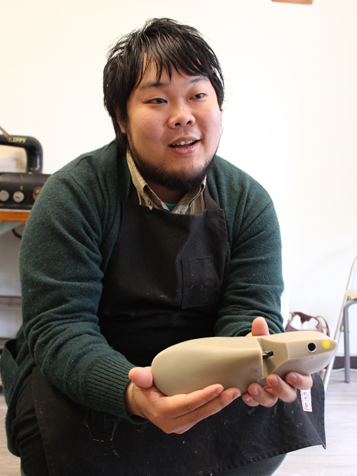
大森さんが学んだのは、ドイツ式の製法。
イタリアはできるだけ細くセクシーに、フランスはエレガントに、
というように各国それぞれの作り方の特徴があるそうですが、
近年、日本人のみならず、人々の足腰が弱くなってきていて、
ドイツの"無理なく骨に合わせた木型を作れる"技術が注目されているんだとか。
こちらが、すべて大森さんがハンドメイドで作った革靴です。

シュッとしたフォルムやステッチ、革の艶、
どの角度から見ても惚れ惚れとしてしまいます。
しかし、同時に「高そう…」と感じてしまうのも確か。
当初は完全オーダーメイド×ハンドメイドで富裕層をターゲットに始めたそうですが、
「オーダー靴に対するハードルを下げたい!」
という想いで、木型をゼロから起こさないで済むように、
工程を簡略化して価格を抑えることに成功しました。
こちらがカジュアルオーダーメイドのシリーズ。

履いてみると、その軽さと革の柔らかさに驚き、
そして靴が足を優しくふわっと包み込んでくれることに気付きます。
「見た目も大事だけど、履き心地を第一に考えていますから」
恥ずかしそうに顔をくしゃくしゃにして笑う大森さんからは、
人の良さがにじみ出ていて、
そんな大森さんが作る靴だからこそ、温かみが感じられるのだと思いました。

せっかくなので、作業の様子も拝見させていただきました。
これは、平面の革を木型に沿わせて立体にしていく「つり込み」というもの。
革の伸び具合を手で確かめながら行えるところがハンドメイドの良さだそう。
しわが入らないように、つま先部分には特に気を遣うといいます。

話をしながらも手は動いていて、
あっという間に靴型に変化していました!
靴を脱ぐ文化のある日本において、
紐をつけたまま脱ぎ履きがしやすい形状や、
修理は街の修理屋さんに頼めばできるような作りにしているそうです。
靴の履き心地はもちろんのこと、
大森さんの人柄や考え方に惚れ込んでしまった私たち。
取材当日はクリスマスということもあり、
自分へのプレゼントに1足オーダーすることに★
まずは足のサイズを採寸し、細かい足の悩みをヒアリングします。
測ってみると、左右の足の長さが実は若干違ったり、
「ここは痛くないですか?」
「かかとが擦れることはないですか?」
とひとつひとつ聞かれると、「そういえば時々…」と悩みが出てくるもの。
また、大森さんが目線を合わせながら、ゆっくり優しく話してくれるから、
ついつい話してしまうんですね。
聞くところによると、大森さんは靴職人になる前は
医療機器の営業をされていたんだそう。
お客様の要望をしっかりと聞き、話しやすい雰囲気を作ってくれているのは、
持って生まれた性格に加えて、営業時代の経験が生きているのかもしれません。
採寸後は、マスター木型で作ったサンプル靴を試着しながら、
足の厚みや幅を下敷きを入れながら調節・確認していきました。

最後に色やデザインを選んで、オーダー終了。
靴のデザインモデルには「栄町通」「元町通」「海岸通」
というように、神戸の通り名がつけられていました。
「僕、めっちゃ地元ラブなんで」
とひと言。
靴の街・神戸で生まれ育ち、別の職業に進みながらも
今こうして靴づくりをしている大森さんが作るオーダー靴の評判は
口コミで広がり、過去には大分県にまで呼ばれて、
出張でのオーダー受け付けをしたこともあるんだとか。
「全国どこへでも呼ばれたら行きますよ!
好きで靴を作って相手に喜んでもらえるし、おまけにお金ももらえる(笑)。
死ぬまで靴づくりを続けていきたいですね」

玄関にそっと掛けられていた大森さんの一足は、
履いた分だけ味が増していました。

お手入れをして、靴底の補修をしていけば、
10年でも20年でも履けるという大森さんのオーダー靴。
世界にひとつだけの靴を大切に履き続けていきたいと思います。
淡路島の心地よいくらし
淡路島で訪れた「樂久登窯(らくとうがま)」。

祖父母の古民家を改装したという工房、兼「gallery+cafe」は、
地元の漁師さんたちで賑わい、温かみのある雰囲気に包まれていました。
その雰囲気を助長しているのは、これらの器たち。
実に多彩な技法が駆使されているのも、陶工の西村昌晃(まさあき)さんが、
先日のブログでも記した丹波立杭焼で修業をされてきた証でした。
丹波の窯元で6年間薫陶を受けられた西村さんは、祖母の住む淡路島に戻り、
2年前にこの窯、兼「gallery+cafe」を立ち上げられました。
一風変わっているのが、
陶工として器づくりに励みながらも、記者としての一面も持っていること。
「自分の器に盛られる食材の成り立ちと、
生産者の想いを知りたいと思ったんです」

「自分はバトンを渡されている。一体、どこから始まっていたのか?
そんな好奇心から、身の回りの生産現場やその想いを取材し、
一冊の本としてまとめていきたくなりまして」
そう考えるようになっていった西村さんは、
「rakutogama book」の発刊のために、取材活動を始めるようになりました。
島に住みながら、島の生産者の取材をする。
そうすることで、季節を追うことができるし、
家畜牛の出産シーンなど決定的な瞬間にも立ち会うことができる。
その地の利を生かした取材ぶりは、プロも顔負けするほどです。
こうして食材の背景を知ることで、器づくりに対する姿勢も
大きく変化していったといいます。
「何より器の向こう側にある風景を想像できるようになったこと。
形として表現するのは難しいですが、
明らかに自分のなかで変化が起こりました」

以前は東京の展示会や店舗などにも出品していたという西村さんでしたが、
流行や売れ筋に振り回されることに強い違和感を覚えるようになります。
都会のセンスにとらわれずに、もっと身の回りの生産者が作った食材を
おいしく食べてもらうための器づくりでいいのではないか。
そう考えるようになっていったそうです。
そして、長い歳月をかけて取材をされ、
最近、完成したばかりという作品がこちら。

淡路黒炊飯土鍋。
同じ淡路島内で「合鴨農法」という有機農法で米作りをされている
花岡農恵園を取材したことをきっかけに手掛けた逸品です。
「とにかく手間隙かけて作られた合鴨農法米。
いかにおいしくいただくかを念頭に作りました」
そう西村さんが話す通り、そこには時代や流行にとらわれない、
作り手の想いが交錯する空気感を感じました。
そんな西村さんが強いインスピレーションを受けたという「花岡農恵園」を訪ねると、
確かにそこには強い信念のもと、活動される素晴らしい生産者の姿が。
花岡明宏さん、36歳。

花岡農恵園代表の花岡さんは、
3児の父親でもあります。
「子供たちに安全安心なものを食べさせてあげたい」
と話す花岡さんの田畑は、完全有機農法。
有機は困難といわれる米作りにおいても、
先述の「合鴨農法」という方法で、無農薬で生産しています。
私たちが訪れた12月は、ちょうど米の収穫後でしたが、
田植え後1週間から穂が出るまでの2ヵ月ほどは、
その名の通り「合鴨」が田んぼを泳いでいるんだそう。
生まれたての合鴨の雛を水田に放鳥することで、
雑草や害虫を餌として食べてくれ、かつ、排泄物が肥料となるわけです。

ただ、農薬や化学肥料を使用しないため、
手入れに手間隙がかかるうえに、一般的には収穫量が下がることから、
手掛けている農家が少ないのが現状です。
それでも「地域内循環」に強い興味があると話す花岡さんは、
「農薬や肥料も外に頼る必要はないのではないかと。
もっと自分たちでできることを、地域のなかで循環させていければいい。
有機農法は、そのベースになりうると思っています」
と語ります。
現に花岡農恵園では、牛や鶏も飼い、
その排泄物を堆肥にして農園に還元していっています。
「できればこれを島単位でやっていけたらいいですよね。
家畜の餌や堆肥を地域のなかで回していき、そこに雇用が生まれる。
そんな循環を夢見ています」
花岡さんは現在、新規就農を目指す若者の指導もしています。
そんな花岡さんの想いの詰まった「愛鴨米」は、
西村さんの「rakutogama cafe」でも、平日限定ランチで提供されています。

流通の発達から、見失いつつある地元にある宝物。
淡路島では、今一度それらを見直し、生産者同士が強固につながっていくことで、
新しい潮流が生まれ始めています。
「ただ、楽しいことを実践していきたいだけなんですけどね」

最後にそう笑顔で話される西村さんの言葉に、
人間が本来持ち合わせている心の中のセンサーの中にこそ、
これからのくらしのヒントが隠されているように感じました。
世界に通じる日本の皮なめし
靴、鞄、財布、ベルトなど…、
今や私たちの身の回り品で、「革」は欠かせない素材の一つです。
人類が地球上に存在し始めた頃から、
動物の「皮」は、衣服や住まい(テント)に利用していたといわれるほど、
必要不可欠な素材として重宝されてきたそうです。
ところで、上記の「皮」と「革」の違いって何なのでしょう?
一般的に、動物の皮膚をそのまま剥いだものを「皮」と呼ぶそうですが、
そのままではバクテリアによって分解されやすく、腐敗しやすい状態です。
それを「なめし」という作業を加えることで、
組織を固定、安定化させ、腐敗しにくくしたものを「革」と呼ぶのです。
その種類も多様で、動物の種類だけあるといっても過言ではありませんが、
皮は食肉用の動物から取れる副産物がほとんどのため、
一般的な革製品の多くは、牛、豚、羊、ヤギ、馬などから取られています。
なかでも、馬の臀部(でんぶ)から採られる皮は「コードバン」といい、
その希少性と、キメの細かい繊維は別名「革のダイヤモンド」と呼ばれるほど。
しかも、そのコードバンのなめしを行えるのは、世界で2社のみなんだそう。
1社がアメリカのホーウィン社、もう1社が日本の「新喜皮革」。
そんな噂を聞きつけ、姫路市花田町に本社&工場を置く、
新喜皮革を訪ねました。
ツンとした獣臭に覆われた工場内には、
60年の歴史を感じさせる趣がありました。

年の瀬のお忙しい時期にもかかわらず、快く迎えてくださったのは、
デザイナーの米田浩さん。

「姫路は、昔から国内皮なめしの中心地として栄えてきました。
現在もここ花田町高木地区に80社ほどなめし工場があるんです」
熱のこもった口調で、なめしのいろはについて教えてくださいました。
この姫路の高木地区が産地になったわけには諸説あるようですが、
豊富な水を必要とする皮なめしにとっては、
穏やかな流水と広い河原がある市川の存在が大きかったそうです。

また、瀬戸内海の温暖な気候や、
皮の処理や保存に必要な塩が容易に手に入ったことも、
産地として発展していった理由だそう。
仕入れる原皮は、ヨーロッパ産の大型の食用馬。

これを「ドラム太鼓」と呼ばれる大きな機械にかけることで、
毛や脂肪を落とし洗浄します。

こうして見えてくる原皮の色は黄土色ベースに、
ところどころ赤や青が交じっています。

この原皮から余計な部分をカット。

コードバンと呼ばれる臀部から取られる皮は、ご覧の通り極わずかです。

他の部位と比べても、明らかに厚みがあるのが分かります。

この状態まで持っていった皮をなめしていくのですが、
なめし方は、用いる「なめし剤」によって異なるようです。
主に、植物に含まれる「タンニン」を使った「タンニンなめし」と、
化学薬品の「塩基性硫酸クロム」を使った「クロムなめし」の
2通りのやり方があります。
クロムなめしの場合は、先述の「ドラム太鼓」を使い、数時間で仕上がるそうですが、
タンニンなめしの場合、ゆっくりじっくり時間をかけてなめしていくため、
新喜皮革では4週間の時間を費やすそう。

時間が経ったタンニン槽は、徐々に褐色へと変化しています。

「なめすことで、皮にもう一度命を吹き込むんです。
ここは僕にとっては物すごいパワースポットですよ!」
米田さんの言葉からは、
皮を提供してくれている動物に対する敬愛を節々から感じます。
なめし後の乾燥させている光景は圧巻です。

「触ってみてください」
といわれ、その手で感触を確かめてみると、
コードバン(写真左下)の方が、圧倒的にスベスベしています。
これこそが「革のダイヤモンド」と呼ばれるゆえんだそう。
最後に熟練の職人によって、写真右下のようなガラスで革の表面を磨く
グレージング加工がされ、光沢が出されていきます。
仕入れから出荷まで、すべての工程に要する期間は約10ヵ月。
コードバンには、それだけの時間と手間、
そして高度な技術を要することから、
世界で2社しかタンナー(なめし業者)がいないわけなのです。
「今まで積み重ねてきたからこそできる仕事。
常に先人たちに感謝をしながら、バトンをつなげていきたい」
そう話す米田さんを中心に、新喜皮革では、
2年前より革製品ブランド「The Warmthcrafts-Manufacture」を立ち上げ、
オリジナル商品の企画販売に乗り出していっています。
使い込むごとに味わいが増していく革のなかでも、
コードバン製品からは、その独特の硬質な素材感がにじみ出ています。
1年使い込まれているという米田さんの鞄も、とても味わい深いです。
この展開によって、消費者へ皮革の製造工程を含めて、
作り手の想いを直接伝えることができるようになったといいます。
最後に米田さんに大切にしていることを伺うと、
こんな答えが返ってきました。
「順番です。
デザインから入るのではなく、素材の皮があって
初めて何を作るかを考えるべきだと思っています」
その言葉は以前、食の取材をした際に聞いた、
「季節ごとに異なってしかるべき収穫できる野菜を、どう調理するかが大切」
という言葉と妙にシンクロしました。
どんなモノも、その多くは自然界からの産物です。
そうした自然への畏敬の念を忘れてはならないということを、
新喜皮革から学ばせていただきました。
丹波立杭焼を後世へつなぐ
800年以上にわたって受け継がれてきた
「丹波立杭焼(たんばたちくいやき)」は、
以前、岡山県でご紹介した「備前焼」とともに、
日本古来の陶磁器窯である"日本六古窯"のひとつに数えられています。
兵庫県中東部にある篠山市(ささやまし)は緑豊かな自然に恵まれた地で、
現在、約60の窯元が軒を連ねています。

そのうちのひとつ、「雅峰窯(がほうがま)」の市野秀之さんに
会いに出掛けると、「まぁ、上がってください!」
と、2階のギャラリー奥にある部屋に案内されました。
窯が開かれてから今日まで、丹波立杭焼は一貫して
主に日用雑器を焼き続けてきたということを事前に聞いていたのですが、
まず驚いたのが、その技法や表現の幅が広いこと!


市野さんにそう伝えるとこんな答えが返ってきました。
「例えば、備前のように伝統的な作風を継承されている産地もありますが、
丹波の場合、全国の窯元に修行に行って、
いろんな技法や釉薬を自由に発表できる産地なんですよ」
もともとは備前焼と同じように、釉薬を使わずに、
登り窯での焼成時につく薪の灰が自然な表情を生み出していましたが、

時代の変化とともに、「墨流し」(写真左下)や「しのぎ」(写真右下)
のような、新たな装飾技法が用いられてきました。
さらに市野さんいわく、作家と職人を同時にこなす人も多いといいます。
市野さんご自身も、"窯もの"と呼ばれる、
丹波立杭焼の伝統に沿ったものづくりをおよそ6割、
"作家もの"と呼ばれる、市野秀之さん個人の表現を踏襲したものづくりを
およそ4割の割合で仕事をされています。
一見、別の人が作ったようにも思える、作風の全く違うこの2つの花瓶ですが、
"窯もの"(写真左下)と、"作家もの"(写真右下)で、
どちらも市野さんが手掛けたもの。
また、問屋制度がないのも顧客の要望を直接反映でき、
丹波立杭焼の作風が広がった要因かもしれません。
立ち寄りやすい1階にギャラリーを置くのが一般的ですが、
雅峰窯では靴を脱いで上がる2階にギャラリーを置き、
さらにコタツに入ってじっくりと打ち合わせをするスタイルを昔からとっています。

「僕の場合、人との出会いが多いからそれだけアイデアが増える。
作陶においては、どれだけ感性を磨けるかだと思っています」

そう話す市野さんは、自身の作陶だけならず、
「丹波立杭焼を後世にどう伝えていくか」
という"橋渡し"の役回りを自ら買って出ています。
今年の11月には大阪でイベントを企画中。
産地の説明や職人のトークショー、飲食とコラボレーションをして、
丹波立杭焼のネームバリューを上げる取り組みを行う予定です。
最後に、「この辺りを案内させてください」
と連れて行ってもらったのが、47mの登り窯。
山麓の傾斜地に作られた登り窯は、その見た目から「蛇窯(じゃがま)」
とも呼ばれてきたそう。

「この窯が地域の共有財産として後世に受け継がれれば良いのですが」
市野さんのような"伝える職人"がいたからこそ、
今の丹波立杭焼があるように感じました。
そんな職人は今日も丹波立杭焼の未来を考えながら、
丹波の土と向き合っています。

ジャパン・ブルー
"ジャパン・ブルー"とは、藍染めの色を指す言葉です。
諸説ありますが、明治初期に来日したイギリスの学者が、
多くの日本人が藍染めの服を着ていることに驚き、表した言葉なんだそう。

しかし、藍染めは日本独自のものというわけではありません。
茜染めや紅花染めなどのように決まった植物で染めるのではなく、
その土地にある"藍の色素"(インジゴ)を含んだ
植物の葉を利用して染めるのが藍染めです。
ヨーロッパではウォード、インドでは印度藍、
日本ではタデ藍や琉球藍がありますが、
日本における藍最大の産地は、阿波の国(現在の徳島県)。
県内を東西に流れる吉野川は、その昔、
台風が来るたびに洪水を繰り返す"暴れ川"だったそうですが、
そのおかげで流域には肥沃な土が運ばれ、藍作を可能にしたといいます。
藍は春に種を蒔き、夏に刈り取りを行うので、
私たちが徳島県にお邪魔した12月中旬には
残念ながら畑での栽培風景を見ることができませんでしたが、代わりに
藍の葉から「すくも」と呼ばれる天然藍染料を作る藍師さんを訪ねました。
作業が行われている「寝床」をのぞいてみると、
建物の中には鼻にツンとするニオイが充満しています。

一見して、土の山かと思ったら、これこそが藍の葉の塊でした。

夏に収穫した後、天日乾燥させ保存していた藍葉に
水をかけてはかき混ぜ、発酵を促すのです。
発酵が進むにつれて、積み上げた藍葉の温度は上昇し、
中心部は75℃近くの熱を持つといいます。
週1回、この水をかけてはかき混ぜる、「切り返し」という作業を行い、
それ以外はむしろの布団をかぶせて寝かせ、
約4ヶ月にわたって一連の作業を繰り返していくのだそうです。

摘みたての葉でも染料にはなるそうですが、
生葉染めの場合、夏から秋のタデ藍が生い茂る季節にしかできません。
そこで、藍の葉を保存しておくために、乾燥させるようになり、
乾燥した葉を発酵分解することで、藍の成分を凝縮させ、
保管、移動に便利になるだけでなく、
布や糸をより濃く鮮やかに染め、堅牢にすることもできるんだとか。
「阿波藍(=すくも)は1年かけて作る染料。
便利になった今の世の中で、これを残すことは時代に逆行していると思うけど、
ここで受け継がれてきたこの仕事を続けていきたい」
江戸時代後期から阿波藍を生産している、
新居製藍所・6代目の新居修(にいおさむ)さんはそう話してくださいました。

そして、仕事を続けていくうえで重要なのは"人材育成"
と語る新居さんのもとでは、
現在、息子さんの他に2人の若者が修業中です。
山形県出身の渡邊健太さん(27歳・写真左)と、
青森県出身の楮覚郎(かじかくお)さん(23歳・写真右)。
彼らは今年の7月から"上板町(かみいたちょう)地域おこし協力隊"として、
藍染め文化の伝承とPRを目的に日々活動しています。
すくもづくりも、染めも両方勉強中の2人に、
今度は染め工房に連れていってもらい、
せっかくなので、藍染めを体験させてもらうことに!
白い布を糸で縛ったり、洗濯バサミで挟んだり、
そのままくくるも、フィルムケースで挟むもよし。
心のゆくまま、染めない部分の模様づくりをしたら、
すくもに"ふすま"と呼ばれる小麦の外皮、石灰、木灰汁を加えて
さらに10日間ほど発酵させた、藍液の中に入れて少し浸けます。
実は藍液は還元状態で、青くありません。
どちらかというと、緑色のようですが、
空気に触れることで酸化反応が起き、
藍の成分が繊維としっかり固着して、そこで初めて鮮やかな藍色を発色するのです。
藍液に浸けては出し、酸素と触れ合わせる作業を
6回程度繰り返したら、水で洗って出来上がり!

想像以上に簡単、そして見栄えのよい仕上がりに大満足です♪
他にも、くしゃくしゃと丸めて茶こしに入れて染めるだけで…
こんな素敵な模様にもできてしまうんです★
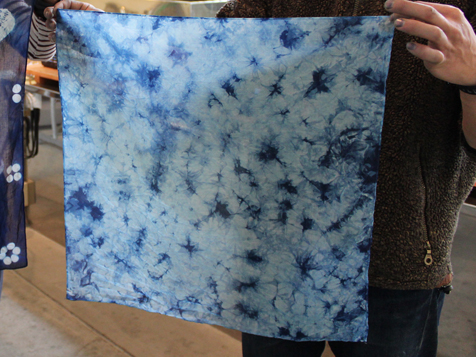
ちなみに上板町の「技の館」ではどなたでも藍染め体験が可能です。
最後に、渡邊さんと楮さんに
なぜ藍染めに興味を持たれたのかを尋ねてみました。
「もともと古来の人のものづくりに興味があって。
初めて天然の藍染めを見た時に言葉にできない感動を覚えたんです。
今は毎日が楽しくて仕方ありません!」
(渡邊さん)
「大学で染めの勉強をしていたんですが、天然染料の中でも藍は特別。
将来、藍を使った自分好みのジーンズを作ってみたいと思っています!」
(楮さん)

天然藍に惚れ込んだ2人は、「BUAISO」というユニットを結成し、
来年春からは畑を借りて、タデ藍を育てるところから行っていくそうです。

「BUAISO」の2人からは、
天然藍を守らなくてはいけない、という使命感よりも、
大好きな藍にかかわるだけで楽しくてうれしい、
その魅力を素直に伝えていきたい、という想いがにじみ出ていました。
現在、灰汁発酵建ての藍染めは全体のわずか1%程度といわれていますが、
天然藍には、肌荒れ、冷え性を防ぎ、殺菌・防虫効果などがあるとされており、
身につける人を優しく守ってくれます。
かつては庶民のための染料であり、
「ジャパン・ブルー」と称えられる美しいこの天然藍に
まずは触れてみる機会がもっと増えたらいいなと思います。
無茶々園
空高く昇っていく太陽のように、青空に輝くみかんたち。

ちょうど収穫のまっただ中の12月初旬に、
みかんの産地、西予市(せいよし)明浜町(あけはまちょう)を訪れました。
辺りを見渡すと、山の斜面にはこれでもか! といわんばかりに
みかんの段々畑が広がっていて、

その前には宇和海がキラキラと光っていました。

ここは、町全体が南向きで日当りがよいうえに、海からの照り返しがあり、
水はけのいい土壌、ミネラル分を含む潮風…と、
おいしいみかんができる自然条件がそろっています。
また、段々畑の石垣が熱を保つ役割をしているそうです。

それにしても、段々畑を目の前にすると、その傾斜のすごさに驚かされます。
収穫したみかんの運搬用に、
各畑にはジェットコースターのようなレールが設置されていて、
もぎたてのみかんが運ばれていました。
一般的に有機栽培が難しいとされる柑橘類ですが、
この畑で栽培されているみかんには、除草剤や化学肥料は一切使用されていません。
生産者の川越文憲(ふみのり)さんは、
「除草が大変かなぁ。夏場は毎日刈っても、すぐに草が生えてくるからねぇ。
だけど、一度自然に育ったみかんの味を知ってしまうと、
いくら頑張ったって自然の力には勝てないって思うんだよね」
と、絶景をバックに話してくださいました。

川越さんいわく、自然に育ったみかんは糖と酸のバランスがよく、
しっかりとした味がするのだそう。
「採れたてのみかん、食べたことあるか?」

そういわれて、渡されたみかんを食べると…
とてもみずみずしく、程よい酸味と甘さが口の中いっぱいに広がり、
「おいしーい!!!」
と感嘆の声を上げた途端、次のひと言に今度は驚きの反応をすることに。
「このみかん、市場じゃ値段はついても10円だよ…」
形が不ぞろいなことと、皮に傷がついていることが問題だそう。
それでも、明浜町を中心に80軒以上の農家が有機栽培をしています。
その理由は「無茶々園(むちゃちゃえん)」にありました。

「無茶々園」とは、できるだけ農薬や化学肥料に頼らないみかんづくりをしていこうと、
1974年に3人の青年によって立ち上げられた実験園のこと。
その後、社会への訴えとともに協力者としての消費者会員を募り、
「無茶々園」の栽培方針に賛同した生産者の輪も地域全体に広がっていき、
現在は生産者団体として活動しています。
また、直営の農園も持っていて、
全国からIターンの若者が集まり、有機農業に取り組んでいます。
今でこそ、"有機"や"オーガニック"という言葉をよく耳にしますが、
約40年前からそれに取り組まれているとは驚きです。
それでも理由を聞いて納得しました。
彼らにとって、有機栽培は第一目的ではなく、
"特色ある地域づくり"が主たる目的だったのです。
農業を主軸として、集落や町全体で気持ちよく暮らせる田舎を作りたい。
環境にやさしいみかんづくりを志すのは、
自分たちの住む地域の自然環境を向上させたい、
というのが大きな動機だったといいます。
「無茶々(muchacha)」とは、スペイン語で「おねえちゃん」の意味。
"ネオン街の蝶を追っ掛けるより、蜜柑畑のアゲハチョウでも追っ掛けようや"
"無農薬、無化学肥料栽培なんて無茶なことかもしれないが、無茶苦茶に頑張ってみよう"
という意味を含めて、設立者は「無茶々園」と命名したのだそう。
「無茶々園」で営業企画を担当している、高瀬英明さんは、
「今、田舎は過疎化が進んで疲弊していくっていわれていますが、
人の流れで問題は解決できると僕は思ってるんですよ」
と爽やかな笑顔で語ります。

彼は、10月に発売になったばかりの、
無茶々園発のスキンケアコスメの生みの親。
ジュースを搾った後の柑橘の皮がもったいない!と、
その活用方法を模索していたところ、
奥様がお子さんの乾燥肌で困っていて、
当時使っていた海外産のオーガニック化粧品の原料を見てみると、
これなら明浜にある原料でも作れると思い、開発に至ったのだそう。
原料は、無茶々園の有機農法にこだわって栽培された柑橘類から採れる精油と
宇和海で手塩にかけて育まれた真珠貝のパウダー、
無茶々園の直営農場で育成されたゆずのシードオイル、
そして、段々畑に咲く柑橘類の花の蜜を集めたみかん蜂蜜。
「今回、スキンケアコスメをこうして作れたのは、
無茶々園に関わる人たちが、"美しい景色を後世に伝えたい"と
ねばり強くやり続けてきてくれたからだと思っています。
このコスメを通して、無茶々園のこと、無茶々園のみかんのことを知ってもらい、
そして農業の未来について考えるキッカケになったらうれしいです」

高瀬さんは、地元に伝わるお祭りのかけ声「やー、えーとこー」から、
明浜の"いいところ"を発信する想いを込めて、
このコスメのブランドを「yaetoco(ヤエトコ)」と名付けました。
約40年前から、川越さんのような生産者とともに、
「無茶々園」がこの地で積み重ねてきたものが、
今、新たな風を明浜に吹かせ始めています。
今治タオル
愛媛県今治市(いまばりし)は言わずと知れた、タオルの生産地で、
全国のタオルの60%以上が今治で作られています。

その温暖な気候から、江戸時代より綿栽培が盛んだった今治では、
農家の副業として生産し始めた「伊予木綿(いよもめん)」が全国的に広がりを見せ、
綿織物の一大産地として知られるようになります。
しかし、明治時代になると、他の産地からの安価な木綿製品に押され徐々に衰退。
今度は、伊予木綿に代わる織物として
「綿ネル(片面だけ毛羽立たせた丈夫な綿織物)」を生み出します。
その後、大阪で生産が始まっていたタオルに可能性を感じ、
綿ネル機を改良してタオル織機としたことが、今治でのタオル生産の始まり。
今治が京阪神という大市場に近く、海洋航路が整っていたことも、
タオル産業の発展に寄与したといえます
(ちなみに、今治は造船の町としても知られています)。

さて、そんな長い歴史を持つ今治のタオルですが、安価な海外産の台頭により、
15年ほど前まで560社ほどあったメーカーが、
数年前には約100社まで減少してしまいました。
「今治タオルは分業制で成り立っているので、
タオルメーカーが100社を切ったらさすがに業界全体がマズイ…」
生産者の一人、山田素裕(もとひろ)さんは当時を振り返ります。

窮地に立たされた今治のタオル業界…。
2006年に、組合の青年部が中心になって話し合い、
「今治タオルプロジェクト」を始動します。
タオルの魅力の抽出から始め、本当に価値あるものを提供していこうと、
独自の品質基準を設け、再スタートを切ることになりました。
みなさんもどこかで目にしたことがあるかもしれない、こちらのロゴ、
これはその厳しい品質基準に合格したタオル商品のみに表示されるマークなのです。

何よりもまず大事にしているのが、タオルの最大の役割である「水を吸うこと」、
そこには驚きの"5秒ルール"が制定されていました。
今治タオルの品質として、1Lの水が入ったビーカーに、
1cm角の試験片(タオル)を浮かべて、
5秒以内に沈み始めたらOKというものです。
また、小さな子どもから大人まで、あらゆる人に安心して使ってもらえるように、
高い安全基準を設けるほか、全11の基準により、品質を守っているそうです。
ところで、そもそもタオルとは、よこ糸を織り込む際に、
たて糸の一部(パイル糸)を緩めて布地にループ状の部分を形成した布のことで、
その織式はひとつなんだとか。
山田さんが白板に断面図を書いて説明してくださいました。
なんだか、繊維学校にでも体験入学した気分です♪
「布の場合、それ自体は素材ですが、タオルの場合、それ自体が商品なので、
そこにどんな想いを詰め込むか、どう味つけするか。
消費者の価値観が多様化している社会において、
作り手としては需要が多い分、挑戦のしがいがありますよ」
どんな糸を使うか、どんな機械を使うか、どんな後加工をするかなどに
それぞれ生産者の個性が表れるといいます。
例えば、通常は綿花の繊維をねじって1本の糸にして使うのですが、
無撚糸(むねんし)という繊維をねじらない糸を使うと、
ふんわりとしたやわらかな仕上がりに。

また、裏面をガーゼで仕上げたものは、
薄手で軽く、洗濯後の乾きが早いという特徴があります。

「ここまで独自の進化をとげてきたのは、
使う人の立場になってものづくりができる、日本人の感性ならでは」
そう話す山田さんは、実は無印良品のタオルハンカチの生産も担っています。
高速・中速・低速と3つのスピードがある織機のうち、
無印良品のタオルハンカチは低速の"シャトル織機"と呼ばれる機械で作られていました。
効率が悪いので、この機械をいまだに所有している人は数少ないなか、
山田さんは大事に大事にシャトル織機を使い続けてきたそう。
それは、ゆっくり織ると、風合いや手触りがよく仕上がるから。
また、後加工に使っている水は、西日本最高峰である石鎚山(いしづちやま)の伏流水で、
極めて重金属が少なく硬度も低い軟水。
こうした水質が、糸や生地の白度や発色、やわらかさと大きく関係しています。
「このタオルを使ってよかったなぁと思ってもらえるように、日々挑戦しています。
『人生て"人間"になる道やなぁ』って思っていれば、
失敗しても楽やし、分からないことを人に聞くのも楽」

価格では海外産のものに勝てなくても、
その品質と挑戦し続ける姿勢で、国内はもとより、
世界でもその存在を認められるようになった今治タオル。
そこには、業界の生き残りをかけて新たな行動をとった生産者たちの団結と想い、
そして、ひとつのものを追求していく
日本人のものづくりへの執念が込められていました。
和紙の可能性
スラリとしたスタイル、キリッとしたまなざし、
物腰柔らかい話し方。
ただ者じゃないオーラを放つその方は、
愛媛県西予(せいよ)市に和紙工房を構える「りくう」の佐藤友佳理さん。

ロンドンでモデル活動後、東京でデザインの勉強を経て、
五十崎(いかざき)和紙発展のために帰郷し活動。
その後、工房を西予市に移して和紙作りに取り組まれています。
「私、中学校の時に、お祭のポスターのコンクールで金賞を取ったことがあって、
その時に和紙でできた十二単を着させてもらったんです。
たぶん、その時から和紙に携わる運命になっていたのだと思います」
そう振り返られる佐藤さんの地元の小学校では、今でも、
自分で漉いた和紙を卒業証書にして渡してもらうんだそう。
その後、モデル活動中に過ごしたロンドンで、
自国のアイデンティティを強く持つ外国人と接するなか、
自分の軸を持ちたい、と思うようになっていった佐藤さん。
一風変わった経歴のように感じましたが、
こうした道を歩まれているのも自然の流れかもしれません。
そんな佐藤さんが作る和紙を一目見て驚きました。

まるで幾何学模様を思わせるような形状。
今まで見てきた和紙は、原料となる楮(こうぞ)の繊維が密に絡み合い、
一枚の紙としての機能を果たすものがほとんどでしたが、
これはその概念を全く覆すものでした。
その名も「呼吸する和紙」。
原料は通常の和紙と同じ楮なのですが、
そこに"ゼオライト"という、結晶構造中に大きな空隙を持つ物質が溶け込み、
湿度調節や消臭機能を有しているとのことなのです。
また、そのモダンな表情ゆえに、趣ある日本家屋にも
現代の住まいにも見事にマッチします。
まさにこれこそが佐藤さんの狙い。
「和紙の持つ可能性の幅を広げたかったんです。
素材は日本の風土に合っているのだから、
デザインももっと今の生活に合うように、と」
その作りは、細くよられた和紙と綿の糸を交互に張り巡らせた土台に、
楮の繊維が軽やかに絡みつき、自然な形で濃淡が生み出されています。

「うちの和紙は漉くというよりも、すくっている感じ。
私、伝統的な和紙の技法を学んだわけじゃなくって」

そう、佐藤さんの和紙づくりは全くのオリジナル。
今まで見てきた和紙づくりでは、
簀桁(すけた)を揺すりながら均一に繊維をならしていっていましたが、
佐藤さんのやり方は、糸で張り巡らされた土台を、
ゼオライト楮が溶け込んだ水に沈めて、すっとすくい出します。
すると、糸の土台が楮の繊維を淡くまとって出てくるのです。

この土台を作るのはお母様の仕事。

まるで熟練の職人のように、一つひとつ丹精込めて編みあげていきます。
こうして母と娘の協働により生み出されたものは「和紙モビール」です。

「情緒に触れるものを作りたいと思っています。
仕事で疲れた時とか、このモビールを眺めて疲れを癒してほしい」
確かに、佐藤さんの作る和紙を眺めていると、
不思議と感傷的な気分に浸れます。

なかにはこんなものまで。

子供向けの「愛媛県から湧き水で漉いた和紙のボール」と名付けられていました。
"和紙は触ってはいけないもの"ではなく、良いものだからこそ小さいうちから
どんどん触って、肌で指でその繊細さやあたたかさを感じてほしい、
というメッセージが込められています。
明らかに和紙の可能性を広げていっている佐藤さんですが、
こうした新しいスタイルを進むことに、不安を感じていたこともあるそう。
ただ、周囲の方のエールがあって今があるといいます。
「どの分野においても、いろいろな人が様々なスタイルを追求していくこと。
そこには伝統的なスタイルも、革新的なスタイルもあっていい。
そうすることで、業界全体の底上げにつながっていけばと思っています」

未来をしっかりと見据えたような視線の佐藤さんは、
紛れもなく和紙業界に新しい風を吹き込んでいます。
日用使いの磁器「砥部焼」
これまでの旅路を振り返ると、
随所に"白"という色への人間の追求がうかがえます。
かつて貴重な調味料とされた砂糖も、
サトウキビから抽出される黒糖を、苦労して黒蜜を抜いて白糖とされ、
お隣香川県では「和三盆」と呼ばれる高級砂糖として重宝されてきました。

土を原料とした陶器が一般的だった焼物においても、
有田で磁器の生産が始まって以来、陶石の産地では磁器づくりが盛んに。
 ※写真は無印良品「白磁めし茶碗・大」
※写真は無印良品「白磁めし茶碗・大」
その後、磁器が伝わったヨーロッパでは、より白い食器を目指し、
ボーンアッシュ(牛の骨の灰)を混ぜた「ボーンチャイナ」が生まれ、
今でも高級食器として扱われています。
 ※写真は無印良品「ボーンチャイナ カフェオレカップ」
※写真は無印良品「ボーンチャイナ カフェオレカップ」
皇室の御用馬に白馬が多いことも、
人々の"白"に対する憧れを象徴しているように思います。
日本でも白い食器として重宝されてきた磁器は、
生産が始まった有田、伊万里をはじめ、九谷、瀬戸など有数の磁器の産地がありますが、
愛媛県の砥部(とべ)もその一つ。

ただ、高級品としてではなく日用雑器を目指してきた点が
砥部焼の一つの特徴といえます。
砥部町では、その地名が示す通り、砥石(といし)の産地として知られ、
江戸時代、「伊予砥(いよど)」の生産が盛んに行われていましたが、
それを切り出す際に出る砥石くずの処理に頭を悩ませていました。
そんな折、天草で採れる砥石が磁器の原料になることを知り、
大洲藩主の命により、砥石くずを使った磁器の生産を始めたことが、砥部焼の由来です。
その後、川登陶石の発見や磁土の改良を重ね、
白い磁器が作られるようになっていきましたが、
それでも他の産地のような白さは実現しなかったようです。
ただ、それこそが砥部焼の特徴につながっていきます。
九谷焼も同様ですが、白さが叶わないと絵付けが生まれます。


あくまでも日用雑器としての焼物を目指した砥部では、
量産のために、複雑な絵付けにも型紙が使用され、
現代の絵付けの多くも、「つけたて描き」と呼ばれる一筆描きのものが多い様子。

また、原料の性質上、ぶ厚く引かないといけなかったため、
ぽってりとした形の、少し重みのある丈夫な器になりました。

この「くらわんか茶碗」は、高台が高く堅牢であると、
揺れる船上でも使われ、評判となったそうです。
「プロが作る料理は、白いキャンバス(お皿)に盛っても美しいですけどね。
砥部焼は、どんな料理も引きたてると評判ですよ」
砥部で最も古い歴史を持つ窯元、梅山窯の岩橋さんはそう話します。
確かに、呉須を基調にサラリと絵付けされた食器は、
和食にも洋食にもマッチするから不思議です。
岩橋さんによると、今の砥部焼のデザインは、
陶工たちが駆り出され廃れそうになっていた戦後、
梅山窯を支えた陶工たちによって、懸命に生み出されたものだったそうです。
その頃に考案されたものが眠る部屋に、特別にご案内いただくと、
そこには何千にも及ぶ、先人たちの努力の結晶がありました。

現代においても、この時デザインされたものが作られているというから、
当時のデザインとしては相当、斬新だったのではないでしょうか。
砥部焼の代表柄の唐草模様は、さりげなく華やかさを演出しています。
(写真右上手前と左下)
そして、その技術は現代の陶工たちに継承され、
今でも手作りで生み出されていました。
最後に岩橋さんは、こうもらしました。
「知ってもらえると、その良さを分かってもらえるんですけどね。
もっと多くの人に知ってもらえたらうれしいです」
梅山窯には資料館があり、砥部焼の変遷や
柳宗悦をはじめとした民藝運動家たちの軌跡を見ることができました。

また、かつて使われてきた大きな登り窯へは、内部に入ることも可能。
内部には人が立っても十分なほど大きな空間がありました。
砥部焼には、
食卓を彩る庶民のための磁器として追求されてきた歴史を
垣間見ることができました。
もうすぐクリスマス★
12月初旬にお邪魔した、松山市近くの無印良品 エミフルMASAKI![]() 、
、
その店内はすっかりクリスマスモードでした☆
スタッフさんいわく、無印良品が年で一番カラフルになる時期なんだそう♪
店内を見ていると、"あの人にはこれあげたいな…"
"あの子にはこれかな…"と次々に贈り物をしたい相手の顔が浮かんできます。
そんなこの時期に選びたいクリスマスギフトの中から
このお店の人気商品をうかがうと…

ご紹介いただいたのが
「自分でつくる お菓子づくりを楽しむヘクセンハウス」
楽しみながら"お菓子の家"を作れてしまう手づくりキットで、
完成した食べられるお家には、作り手の個性が表れますね。
こちらは無印良品の店舗スタッフが作ったヘクセンハウスです。
また、こちらの手づくりキットもお薦めだそう!
「モカシンルームシューズ手作りキット」
自分で作ったモノって、より愛着が湧きますよね。
大切な人へのギフト、頑張った自分へのギフト、
みなさんはこのクリスマスに何を選びますか?
受け継がれる灯
店舗スタッフの紹介で、内子町(うちこちょう)を訪れました。
今でも白壁の町並みが残っている、趣のあるこの地区は、
かつてハゼの木の流通で財をなした商人の町でした。

住宅街に突如として現れるこの建物は、
大正天皇の即位を祝して、地元有志の出資により創建された「内子座」。
地元の人々の娯楽の場として発案されたそうですが、
当時の彼らの裕福さを物語っています。

ハゼの果実から採れる木蝋(もくろう)は、
和ろうそくをはじめ、お相撲さんの髪につけるびんつけや、
木工品の艶出し剤、医薬品や化粧品の原料として幅広く使われてきました。
当時、内子町には、約20軒の和ろうそく屋があったそうですが、
大正時代に入ると、石油系のパラフィン蝋が流通し、
現在も木蝋を使った和ろうそくの生産を続けるのは
「大森和蝋燭屋」1軒のみとなりました。

中をのぞくと、奥の作業場で男性が2人、作業をしています。

6代目の大森太郎さんと、7代目の亮太郎さん親子です。
亮太郎さんはアパレル関係の仕事を4年ほどした後、
家業を継ぐために実家に戻りました。
もともと和ろうそくに興味を持っていなかった亮太郎さんですが、
前職場の上司やお客様に家業の話をすると
「それは素晴らしい仕事」とたびたびいわれ、
いつしか自然と継ぐことを考えるようになったといいます。
和ろうそくづくりの工程は、
竹串に和紙と灯芯草(とうしんそう)と呼ばれるい草の茎の皮を剥いだ髄を巻きつけて、
真綿で留めて芯を作り、
その上から溶かした蝋を何度も、何度もかけていくのですが、
なんとその作業は素手で行われていました!
右手で竹串を転がし、左手で40~45℃ぐらいの蝋をすりつけては乾かし、
この作業を何回も繰り返しながら、少しずつ大きくしていくのです。
最後に50℃ぐらいの温度に溶かした蝋をすりつけてツヤ出しし、
先端部分を削って芯を出して、最後に竹串を抜いたら出来上がり。
一連の作業は、途中で置いてしまうと蝋が乾燥してしまうため、
1日で完結させてしまわないといけないんだそう。
1本1本に魂を込めて作られた和ろうそくの断面は、
まるで長年の歳月を経て生み出される年輪のようです!

「これからもこの和ろうそくを作り続けていきたい」
そう話す亮太郎さんの前には、父の背中がありました。
ふと、店内を見回すと、
5代目の弥太郎さんと6代目の太郎さんの仕事風景の写真が。

時を経て、今は手前に6代目の太郎さんがいて、
奥に7代目の亮太郎さんが座っています。
200年余の歴史の中で、代々、父から子へと継承されてきた
内子の和ろうそく。

すべて自然素材で作られ、着色や絵付けも一切されていない
とてもシンプルなものですが、
その蝋の年輪が生み出す炎はとても大きく、
ゆらゆらとゆっくり揺れる灯が、不思議と見る者の心を癒やしてくれました。
菓子木型と和三盆
ものづくりの現場を見て回っていると、最近、
「これを作るのに使われている道具は一体どうやって作られているんだろう…」
そんなことを考えるようになりました。
そして、今回高松市では、私たち日本人の自慢ともいえる
繊細な和菓子づくりを支える「菓子木型」の職人に会いに行ってきました。
「寝て起きて木型を彫って、寝て起きて木型を彫っての繰り返し。
でもレジャーはいらない。木型がレジャーでもあり、ギャンブルでもあり、
木型の仕事がいろんな所へ連れてってくれるからね!」
「人生菓子木型一筋」ときっぱりと言い放ったのがとても印象的であり、
そんな天職に巡り合っている、目の前にいる職人さんを
うらやましくも感じてしまいました。
その方は、木型工房市原を営む、市原吉博(いちはらよしひろ)さん。
菓子木型の卸し業の家に生まれ、付き合いのあった職人さんから基礎を学び、
28歳で自身の工房を設立しました。
菓子木型の職人は、現在全国に数人しか残っていないという貴重な存在です。

作業をする市原さんに質問を投げかけると、返ってきた答えは、
微笑みながら「ワイパーワイパー」。
こちらがキョトンとしていると、
「嫌とは言わない。もし言わなきゃいけない時は笑って"ワイパー"や。これで幸せ」
"ワイパー"とは、左右に動く車のワイパーのことで、
つまり"NO(ノー)"を表しているそうなのです。
なんともユーモアたっぷりの職人さんです!
その後も次々と名言が口から飛び出します。
「NO(ノー)と言えないアーティスト、それが職人」
「"3D"、"でも・だけど・だって"は禁句」
「愛の連鎖は自分から」
市原さんの発する言葉のひとつひとつは
メロディーのようであり、そのまま書いて飾っておきたい作品のようでもあります。
でも、スゴイのはしゃべりだけでなく、もちろん本業の技も!
木に描かれた細かいデザインを、彫刻刀を使って彫っていきます。

1つの作品を作るのに、形や太さの違った、約50本の彫刻刀を使うといいます。
ズラリと整列した彫刻刀たち…

そういえば、この彫刻刀もまた菓子木型を生むための道具ですね。
彫刻刀の持ち手部分は、自分の手に合うように
市原さんご自身で作られるそうです。
上述した通り、NOと言えない、いや、言わない職人である市原さんが
作ってきた菓子木型の数々がショールームに展示してありました。

木型を眺めているだけでも、なんだかわくわくしてきます♪
すると、市原さんが作ったこの木型を実際に使って、
和菓子を作れる場所があるというのです。
市原さんの工房から5軒先の「豆花」です。
ここは市原さんのお嬢様である、上原あゆみさんが3年前に始めた
"和三盆体験ルーム"。
和三盆とは、東かがわ市と徳島の一部で伝統的に生産されているお砂糖のことですが、
これを型押しして作られた落雁(らくがん)のような砂糖菓子(干菓子)の総称としても、
「和三盆」という名が広く知られています。
早速、あゆみさんの指導のもと、和三盆づくりを開始。
薄力粉のようにサラサラな和三盆を、まずは水でしめらせ、ふるいでこしていくと、
ふわりと甘い黒糖のような香りが漂います。
(ピンク色は食紅で色付けたもので、もともとの和三盆の色は白です)
それを木型に入れて、指でギュッと押さえたら、
木型の上板をはずして、そのまま下板をひっくり返したらもう出来上がり!
想像以上に簡単で驚きました。
これなら、小さな子供からお年寄りまで、誰もが楽しめますね。
実際、おばあちゃんとお孫さんや、3世代で体験に来るお客様もいるそうです。
私たちは、今回、2人で8つの型を使って作らせていただきました!
福梅、おたふく、猫&肉球、合格、千鳥、雪の結晶、オリーブにキューブ。

出来立ての和三盆を口に入れると、ふわぁ〜と甘みが口の中いっぱいに広がり、
あっという間にとろけていきました。
なんともおいしく、そして上品なお菓子なのでしょう!
こうして体験してみると、菓子木型だけを見ていた時よりも更に、
ひと味もふた味も違った感動を覚えます。
木型はお菓子のデザインとは左右逆に彫ってあり、
お菓子にした時に浮き出る部分は、より深く彫られているのです。

市原さんが作る木型はほとんど前例がなく、
いつも試行錯誤を繰り返しながら、ひとつを徹底的に作りあげていくそう。
「これよく見てください! ひとつひとつ表情が違うんですよ。
それが手づくりの魅力ですよね」
と、あゆみさん。

実はあゆみさんは、木型そのものにではなく、
実際に木型が使われているシーンを見て、その虜になったんだとか。
「父の仕事のことはほとんど知らなかったんですよ。
それが、数年前に東京でやった、とあるアート展を見に行って、
そこで和菓子職人さんが父の木型を使ってお菓子を作っているのを見て感動して。
それをみんなに知らせたいと思って始めました」

市原さんが菓子木型を作り、あゆみさんがその使い方を伝える…
この親子のタッグでいろいろな場所へ出掛けていっています。
最近では地元の小学生に、和三盆と菓子木型について講演もしているそう。
「職人だって営業していかないといけない時代」
そう話す市原さんが独自に認定する「木型Girls」が、全国に20人ほどいるそう。
その条件とは、「木型もしくは和三盆が大好きなこと」
「木型を10個以上持っていること」「木型を利用してイベントが組めること」。
これまで脇役だった菓子木型という道具は、市原さんとあゆみさん親子によって、
確かにその存在を世の中に知らしめていっています。
鼻緒のはきもの
高松市の観光通りを1本入った路地にある「黒田商店」の扉を開けると、
目に飛び込んできたのが、とってもカラフルな鼻緒たち。

鼻緒はご存じ、下駄や草履の台部につけて足にかけるひも(緒)のこと。
台と鼻緒の組み合わせを変えるだけで、こんなにもはきものの表情は変わってくるんですね!
黒田商店は、廃材であるタイヤを使ったタイヤ底草履の製造・卸し業として、1916年に創業。
戦後、2代目の時には高度経済成長時代で自社の製造では追いつかず、
仕入れメインにシフトします。
そして、現在は3代目の黒田重憲(しげのり)さんの時代で、
オリジナルの鼻緒や、自社開発したはきものを販売するようになりました。
きっかけは、重憲さんの奥様、恵(めぐみ)さんが自分で履いてみた時に
履き心地があまりよくなかったこと。
加えて、あまり好みのものも見当たらず、
それでは「自分たちが履きたいはきものを作ろう」と、
ご夫妻で7年半の歳月をかけて、オリジナルのはきものを開発しました。
それがこの「マイソール下駄」です。

革張りの下駄の中身には特殊なゴム素材が入っていて、
足にふんわりとしたやさしい履き心地を与え、
履けば履くほどその人の足にぴったりな形になってくるのだそう。
接客時にマイソール下駄を愛用中の、スタッフ村川さんは
ずっと立ち仕事をしていても足が全く痛くならないと教えてくれました。
「最近の靴は性能がよすぎて足の筋肉が育たないんです。
下駄は筋肉や骨を治すというより、本来の姿にもっていってくれるんです」
私たちも少しの時間でしたが、試し履きをさせていただくと、
ソールに少し傾斜がついていて、
マイソール下駄で歩くと自然と体重移動が起こり、背筋がピンとなるのが分かりました。
それから、下駄の鼻緒はもちろん好きなものに変えることができます。
鼻緒の生地は、恵さんが世界中から集めてきた布。
着物の古布から、

こんなにポップでキュートなものや、

さらにはアフリカ・マリ共和国の泥染めなんていうものまで!

その種類は約1000点にも及びますが、
幅2センチ、長さ15センチの小さなキャンパスに表現されるデザインは、
同じものがほとんどないといいます。
また、鼻緒の中には、足当たりがいいようにと、
日本のふとん用の上質綿をブレンドして使っているそう。

「鼻緒のはきものの魅力を全国行脚でみなさんにお伝えしようと思って」
電話口でそう話されたのは、恵さん。
黒田さんご夫妻は、「実際にはきものを履くお客様の声を聞きたい」と
12年前から百貨店などに出向いて、好きな鼻緒とはきものの台を選んでもらい、
その場で挿(す)げる「ライブ」(展示販売会)で全国を巡っているのです。
年の半分くらいは全国をかけ回っていて、残念ながら
今回私たちが高松にお邪魔している時に、お2人は千葉県にいらっしゃいました。
代わりにお弟子さんの松木さんに、実際に挿げていただきました。
一般の下駄屋さんでは畳の上で作業をするのが一般的だそうですが、
黒田商店では椅子に座って洋服で作業するスタイルです。
松木さんは実は、数年前にたまたま銀座でライブ中だった黒田ご夫妻の姿を見かけて、
そのパフォーマンスに惚れ込んで、何度も頼んでこの世界に入った人でした。
「下駄ってかっこいいなと思って。
靴の時よりも、下駄の方がどんな服着ようかってわくわくしてくるんですよね!
将来的に、町を歩いている人の多くが下駄を履くようになればいい」
そう話す松木さんの足元はもちろん、下駄。

村川さんも松木さんも、洋服にごくごく自然に下駄を合わされていて、
"下駄=和服用の靴"という概念が見事に覆されました。
これまで勝手に抱いていたモノのイメージというのは、知らないからだけであり、
それをきちんとプロデューサー本人から教えてもらえる場はとても貴重ですね。
鼻緒のはきものの可能性を追求し、
お店を飛び出してその魅力を発信されている黒田さんご夫妻には
以下のライブ会場でお会いできるそうです。
2012年12月5日〜18日 @三越 銀座店新館(M2階)
2012年12月25日〜30日 @伊勢丹 新宿店(6階)
2013年1月3日〜15日 @松屋 銀座店(7階)
自然界の縮図「盆栽」
日本を代表する文化のひとつ、「盆栽」。

世界でも「BONSAI」として広く親しまれ、
私たちも世界一周中、訪れた欧米では町中に専門店をよく見かけたほどです。
 ※2010年ハンガリーにて撮影
※2010年ハンガリーにて撮影
日本貿易振興機構(JETRO)によると、
庭木をあわせた昨年度の輸出額は10年前の約10倍で、過去最高を記録したそう。
小さな鉢の中で育てられた草木には、壮大な自然の景色が表現されており、
芸術品としての評価も高いようです。

平安時代に中国(唐)から日本へ伝わったといわれており、
江戸時代に武士のあいだで高尚な趣味として親しまれ、
今日まで独自の文化として進化してきました。
「細かい日本人の気質に合っていたんだと思いますよ」

そう語るのは、高松市にある清寿園の園主、平松清さん。
その道40年の盆栽師です。
高松市の西部、鬼無(きなし)と国分寺地区は、
松の盆栽の全国シェア約80%を占める一大産地。
平松さんにその理由を尋ねると、
「昔からこの辺には、よお松が埋まっとったんや。
高"松"っていうぐらいやからのぉ」
高松の名称の所以の真偽は分かりませんが、
その歴史はさかのぼること約200年前、この土地の愛好家が
自生する松を栽培し、販売したことに始まります。
農耕地が少なかった香川では、農家の副業として盆栽の栽培が盛んになり、
水はけのよい砂壌土で育った松は、
「根腐れしにくく、傷まない」として定評があるそうです。
この盆栽、素人の私たちは
てっきり松をミニチュアに品種改良したものと思っていたのですが、
自然に自生しているものなんですよね。
もちろんその種は、秋によく見かける…、

松ぼっくり、通称「松かさ」です!
「この形のええやつを拾ってくるんや。それがいい松に育つ」
平松さんは実際、松かさから苗を育てていました。

本来は松かさから種を採取してそれを植えるようなのですが、
こちらはあえてその姿を見せるスタイルのもの。
鉢の中だけに根を張っていく植物は、
その鉢の大きさに応じて、成長するサイズも変わるんだそうです。

「徐々にその姿形を変えていくのが盆栽の魅力」
そう語る平松さんは、時間をかけてじっくりと育てていく盆栽では、
その植物の特性を熟知し、対話していくことが大切だといいます。
時に「針金かけ」などの技法を利用しながら、枝ぶりを整え、
その芸術性を高めていくのが、盆栽師の腕の見せどころ。

このようにして、様々な樹形が生み出されていきます。
こちらは「吹流し」と呼ばれる樹形。

自然界でも一方向からの風や障害物のために生じる樹形で、
幹も枝も一方向になびいています。
続いて、こちらは「根上がり松」とよばれ、
地中で分岐した根元の部分が、風雨にさらされて露出されている状態です。

縁起が良いとされ、贈呈用としても重宝されてきたんだとか。
平松さんは、人が苗から育て上げるものよりも、
ある程度、過酷な自然環境で育ったものの方が、
素晴らしい姿を見せてくれるといいます。
ただ、現在では気候の変化と松くい虫によって、
自然に自生する松は少なくなってきているそう。
「昔は、近くの山にもいい自然の松が育っとった。
でも、今はなかなか見んようになったなぁ」
そう話す平松さんは、盆栽師のことを"植物のドクター"と呼んでいました。
「販売して以上終了って仕事じゃなくって、
病気などで調子の悪くなった盆栽を、立ち直らせることもよくあります。
キチンとメンテナンスしてあげれば松は100年も200年も生きよるから」
実際、高松市内の名勝、栗林公園には、
樹齢200年余といわれる五葉松がありました。

2世紀ものあいだ、高松を見守ってきた松は、
まさに自然と人間の作り上げる芸術そのものでした。
最後に平松さんに、
「鉢から見上げるように盆栽を見てごらん」
と指南いただき、のぞいてみました。
すると、そこにはまるで自分が小さくなって、森の中に迷い込んだような世界が…。

「盆栽はまさに自然界の縮図。
常に姿を変えていく終わりのない世界ですから、飽きがこないし、楽しいですよ」
平松さんはそういいながら、笑顔で微笑みました。

日本が世界へ誇る盆栽。
それは、自然を身近に感じ、対話していくには、
もってこいの代物かもしれません。
百年の森林構想
以前、岐阜県の石徹白(いとしろ)でも触れた日本の森林問題。
国土の約3分の2を占める日本の森林の多くは、実は30年以上前に植えられた人工林で、
適正な環境に保つためには間伐し続けなければならない状況にあるにもかかわらず、
建材需要の低下と、安い海外産の木材に押され、木を切る人が減少しているのです。
全国各地の森林で起きているこの問題は、各地域の行政も頭を悩ませています。
そんななか、村ぐるみでこの問題に取り組み始めている村が、岡山県にありました。
岡山県の北東部、西粟倉村(にしあわくらそん)。

人口約1600人の小さな村は、
実に面積の95%が森林に覆われています。
「今から約50年前、子や孫のためにと、木を植えてくださった方々がいました。
その想いを忘れてはいけないと、西粟倉村では森林の管理をあきらめるのではなく、
美しい森林に囲まれた上質な田舎を実現していくことを決めたんです」

西粟倉村にIターンでやってきた坂田さんが教えてくださいました。
2004年、平成の大合併を拒み、自立の道を選んだ西粟倉村では、
先人たちが植え、50年にわたって育ててきてくれた森林こそが村の資源と置いて、
もう50年かけて立派な森林に育て、村の産業としていく決断を下しました。
約1,330人が持っている森林を一括して役場が管理、
事業の委託を受けた森林組合が間伐し、
それで得た収益は持ち主と折半、費用は役場負担という試み。
これが、西粟倉村の掲げる「百年の森林構想」です。
この決断に呼応するように2009年10月、一つの会社が立ち上がります。
増加する村の間伐材の加工、販売をはじめ、
地域資源を発掘し、発信していくことを目的に設立されたのが
(株)西粟倉・森の学校です。

拠点を構える廃校になった旧校舎は、
その役割を学校から、地域の情報発信基地として変化させながら、
今も存分にその存在価値を発揮していました。
先にご紹介した坂田さんも、この森の学校勤務。
校内をご案内いただくと、中にはオフィス機能はじめ、
間伐材を使った家具の展示スペースや、

木製雑貨、ならびに、村の特産品を扱うショップ、

さらに、村で採れる食材を使ったカフェまで。

昨今、ハンター不足による過剰な増加が問題視されている
鹿の肉を使ったカレーも提供されていました。

ここは地域と地域外の人をつなぐ場でもあり、
地域資源の循環を試みる場でもあるのです。
もちろん、置かれている木工製品の多くは、
西粟倉村の間伐材を使って開発されたものでした。
木のぬくもりをそのままに感じることができる、
木皿やお盆、木のスプーンや、無漂白の割箸。
さらに机・椅子といった家具まで。

普段の生活のなかに自然と西粟倉の木が溶け込むようなものばかりです。
その昔、建材需要に備え植えられた人工林は、
そのほとんどがスギ・ヒノキのため、木材のなかでは柔らかく、
業界では家具には向かないといわれ、使われることも少ないそう。
「西粟倉の作り手たちは、そうした業界の常識に捉われずに
企画・製作していったため、新しい商品が生まれやすいんだと思います」
坂田さんがそう話される通り、スギ・ヒノキ材の家具をはじめ、
なかにはこんなユニークな商品も。

「モクタイ」
ヒノキの柔らかい質感で、木目がそのまま模様になるという逸品です。
さらに、森の学校で注力しているのが、
セルフビルドという考え方。
家のリノベーションをするにも、施工業者に頼むのではなく、
「ユカハリ・タイル」と呼ばれる、
裏に遮音シートが張られた50cm四方の無垢の木を買ってもらい、

それを自分で床に敷き詰めていくだけで、

この通り、無垢の木に囲まれた温かみのある空間に様変わり。

家族との時間を犠牲にしてまで働いて得たお金で何でも買ってしまう、
という近代の日本の生活スタイルに警笛を鳴らし、
時間の使い方を根本から考え直してもらうための提案なんだそう。
また、「お客さんができるところは任せる」というスタンスで、
つくり手に過剰な手間ひまをかけさせず、
その分、余分なお金をとらないという考え方に基づいています。
ゆえに、タイルは無塗装。
お客さんが自身で好きな色に変化させていくことができるんです。
このように、木と共生することを決めた村では、
木とともに生活するための様々な工夫が生まれていました。
村ぐるみで森林を間伐し、その木材を利用していく取り組みとしては、
全国でも先駆けた事例のように思います。
日本の美しい森林を守るためにも、
こうした実情に目を向け、選択をしていくことが、
私たち消費者にも求められているのかもしれません。
炎が作り上げる芸術
瀬戸焼、常滑焼、越前焼、信楽焼、丹波立杭焼、備前焼。
数ある日本の窯元のなかでも、日本古来より生産が続く上記の窯のことを
"日本六古窯(にほんろっこよう)"と呼び、
中国や朝鮮から伝来したものと区別されているそうです。
岡山県備前市は、そのうちの一つ、
実に約1000年ものあいだ窯の煙が絶えたことのない備前焼の里。
その焼物を一目見た瞬間、
今まで見てきたものと違うことに驚かされました。

釉薬が使われていないのです。
なんの飾り気もない素朴な風合いは、
どこか土器を思わせるような懐かしい感じもします。
「釉薬も化粧土もいっさい使わず、備前の土で成型し、
約1~2週間にわたってじっくり焼き上げるんです。
土のみですが、焼き締まり方が違いますから丈夫ですよ」
そう教えてくださったのは、
備前の地で作陶に励む森本仁(ひとし)さん。

美濃で4年間にわたり薫陶を受けられた後、
9年前に帰郷され、父親とともに作陶に励まれています。
「備前焼の土は、田土(たつち)といって、
田んぼの下を3mほど掘った鉄分の多い粘土層の土を使います。
田んぼに水が溜まるということは、
その下はキメの細かい土の証拠なんです」

見せていただいた乾燥した状態の土は、まるで石のよう。
この土を成型したものを、独自の登り窯でじっくりと焼き締めるんです。

釉薬を使う他の産地では通常1~2日で焼き上げるところも多いですが、
備前焼の場合1~2週間かけて焼き締めるため、
窯の燃料となる薪の量も並大抵の量ではありません。

なによりも備前焼の魅力は、
その窯の中で出会う土と炎が作り上げる模様です。
釉薬を使わないので粘着することが少ないため、
窯の中では下の写真のように作品どうしを組み合わせて焼かれます。

そのため、炎によく当たる部分と、そうでない部分で、
窯変(ようへん)と呼ばれる現象が起きるんです。

焼物のあいだに藁を敷くことで、あえて変化を出すことも。

「いつも窯から出すときはワクワクします。
どんな仕上がりを見せてくれるだろうって」

笑顔でそう話される森本さんですが、
釉薬をかけない分、ごまかしも利かないそう。
「土づくりから成型、焼成に至るまで、
一つひとつを丁寧に進めていかなくてはいけません。
生活が乱れると、それがそのまま焼物に反映されるんです。
土をいじっているのは作業の一部で、
仕事場と生活の環境を整えることが一番大切だと思ってます」

そう話しながら手ろくろを廻す森本さんは、
まるで修行僧のように規則正しい生活を送っているんだとか。
毎日、同じ時間に起床、就寝、食事を摂り、
常日頃からの身辺整理は怠りません。
陶芸に必要な自前の道具も、
すべて自然の産物から丁寧に作られています。

なにより作陶に励む場所そのものが、
とても静かな自然に囲まれた環境なんです。

私たちが訪れた季節はちょうど紅葉の季節で、
落ち葉に彩られた道を歩く森本さんは、
自然と五感を使って心身を整えられているようでした。
そんな森本さんが、備前焼で表現された器の一つがこちら。

すべて落ち葉のように見えますが、
実は手前は備前焼で作られたお皿です。
備前焼は、釉薬を使わない分、土が呼吸するため、
中の水が腐りにくいと花瓶などの用途に定評がありますが、
この器で頂くお茶も格別な味わいでした。

窯の中で土と炎が出会い、自然に生まれる模様は、
人の手で描くものとはまた違った素晴らしさです。
時代を超越して愛され続ける備前焼には、
今も昔と変わらない魅力が放たれているように感じました。
そしてそれは、森本さんをはじめとした、
普遍のリズムのなかで作陶する陶工たちによって、今日も支えられています。
鳥取民藝運動と、因州中井窯
きちんと整理整頓された焼成前の器に、

きれいに並んで天日干しされている陶土、

そして、しっかり組まれたレンガや薪に囲まれた登り窯。

おもわず聞いてしまった、「A型ですか?」という質問に、
「いえ、B型ですよ」と笑顔で答えてくださったのは、
因州中井窯の3代目、坂本章(あきら)さんです。

この因州中井窯の代表的器として知られるのが、こちらの「染め分け皿」。

ひしゃくで順番に釉薬を掛けていくのですが、

このように3色の釉薬を均一に施すのは、技術はもちろんのこと、
坂本さんのきっちりとした性格のなせる技だなと感心しました。
それにしても、この鮮やかな色合いと、大胆なデザインは
これまで見てきた焼き物にはなかったものです。
すると、
「うちの窯の特徴は、"プロデューサー"がいたことなんですよ」
と、坂本さんが因州中井窯の歴史について教えてくれました。
因州中井窯は、もともと農業や教員など別の道を歩んでいた坂本さんのおじいさまが、
焼き物に興味を持ち、近くの牛ノ戸(うしのと)焼の窯場を訪ねては仕事を教えてもらい、
昭和20年に開窯。
そして、その後、因州中井窯を語るうえでは、欠くことのできない
3人のプロデューサーとの出会いが各々の時代にありました。
まず、1人目のプロデューサーが
鳥取民藝運動の指導者、吉田璋也(しょうや)氏。
鳥取で耳鼻科医を営む吉田璋也氏は、
民藝運動の創始者・柳宗悦に強く共鳴し、
地元鳥取周辺の民陶であった牛ノ戸焼の窯場に足繁く通い、
現代の生活に見合う器類を作るように提案、指示します。
そして、それらをすべて引き取って販売する「鳥取たくみ工芸店」を
昭和7年に立ち上げました。
これは民藝品流通の最初の事業であり、日本初の民藝店となりました。
さらに販売を拡大するために、1年後の昭和8年には、東京銀座に「たくみ」を創設。
そうして、吉田璋也氏は商品補充のために、坂本さんのおじいさんに、
中井の地で、生業としての焼き物づくりを奨励し、
製品化した物はすべて「鳥取たくみ工芸店」で販売する道を与えました。
ちなみに、この「3色染め分け皿」の原型は、
鳥取市郊外にある因久山(いんきゅうざん)窯にあったそうですが、
吉田璋也氏がそれを牛ノ戸焼で作らせ、さらに中井窯でも作らせたものなんだとか。
今でこそ、デザイナーとのコラボ商品や、
作り手以外のプロデューサーが生み出した器などが出てきていますが、
昭和初期のこのような動きは、先駆けでした。
そして、これこそが"鳥取民藝運動"すなわち、
"新作民藝運動"の始まりでもありました。
柳宗悦氏の唱えた民藝運動は、無名の職人による民衆的美術工芸の美を発掘し、
世に紹介することに努めたことに対して、
吉田璋也氏の新作民藝運動は、単に発掘してそれを広めるだけにとどまらず、
自身がデザイナーの役割を担って、新しい民藝品を生み出していったのです。
「作り手でもなくて、年上の陶工たちに指導できたのは、
吉田璋也先生の人間力と財力があったからだと思いますね」
吉田璋也氏は焼き物に限らず、鳥取の木工、染織、金工、竹工、漆工、和紙…
と様々な分野で、この土地の材料を生かした新しいモノづくりを指導していきました。
そして、後に、作り手にとっての物の勉強の場として「鳥取民藝美術館」(写真左)を、
器を実際に使ってみせる「たくみ割烹店」(写真右)も創設。
※ちなみに、吉田璋也氏が北京料理をアレンジした「牛肉のすすぎ鍋」は
しゃぶしゃぶの原型になったものなんだそう。
「見る、使う、食べる」の三位一体論を推進したことで
鳥取の民藝運動は躍進していったのです。
続いて、2人目のプロデューサー、
手仕事フォーラム代表で、鎌倉の「もやい工藝」店主の久野恵一氏。
坂本さんはどこか別の窯で修業をするのではなく、
お父様の仕事を見よう見まねで作っていたので、
いい焼き物を作りたいと思っていたものの、
何がいいか、悪いかが分からない状態だったと当時を振り返ります。

しかし、30歳の時に転機が訪れます。
坂本さんにとってのプロデューサー、久野恵一氏との出会いがありました。
久野氏は10年以上にわたり、坂本さんたちの窯へ通って、指導を続けたそう。
「久野さんからは、形よりも縁の作りや削りの仕方に気を配れといわれましたね。
例えば、コーヒーがすっと口に入ってくる形状だとか」
坂本さんのおっしゃる通り、坂本さんの作ったコーヒーカップの口元は
上唇にとてもフィットして、飲みやすいのです。

また、久野氏のつながりで、お父様にもかつて指導した、
柳宗悦氏の息子でプロダクトデザイナーの柳宗理氏に、
坂本さんも教わることになったそう。
これが、3人目のプロデューサーである柳宗理ディレクションの
2色の染め分けと、縁の釉薬を抜く技法を組み合わせたお皿です。

吉田璋也氏、久野恵一氏、柳宗理氏というプロデューサーとともに
成長してきた因州中井窯。
工房の隣には、展示場兼ショップがまもなくオープンするそうです。

「今後も誠実なモノづくりを大切にしたい」
最後にそう語ってくださった、坂本さんの作る器が一堂に会する場所は
きっと素晴らしく、そして整然と置かれているに違いありません。
作り手のぬくもり
その器でコーヒーを飲んだとき、
どこか温かみを感じ、ほんわかとした気持ちになれたのは、
作り手の雰囲気が器に表れていたからかもしれません。

鳥取県岩美町にある「延興寺窯(えんごうじがま)」。

父・山下清志さんと娘・裕代さんの父娘で作陶に励む窯元です。
お二人ともとても柔和で優しい雰囲気をお持ちで、
その空気感がそのまま焼物にも伝わっているようでした。
しかし、ひとたび工房に入れば、父娘から師弟の関係に。

ゆったりとした空気と、ほどよい緊張感に包まれた自宅内の工房は、
まさに、父の背中を見て育つといった環境でした。
父・清志さんがこの地で開窯されたのは今から33年前。
もともとコンピューター制御の仕事で会社勤めしていた清志さんは、
丹波立杭焼で修業していた兄の誘いもあって、生田和孝氏に師事。
故郷の鳥取に戻り、兄とともに磁器による浦富焼を再興し、
その後、陶器の土を求め、1979年にこの延興寺の地にたどり着きました。

「陶工は土を求めて回る。昔の民陶のスタイルはみんなそうでした」
あくまでも焼物の原点を追求する清志さんの案内のもと、
自宅近くの土の採取現場へ。

採取した土はしばらくの期間、天日干しで乾燥され、

自らの手によって生成されていきます。
「こうして大地の恵みに触れていると、謙虚な気持ちになれるんです」
そう話す清志さんが使う釉薬も、もちろん地元で採れるもの。
白釉のためのもみ殻は、地元の農家の方から、
黒釉のための黒石は、近くの河原で採れるそうですが、
そこには推定1600万年前の成分が含まれているそうです。
「私たちは地球の資源に生かされていることを実感しますよね」

清志さんによって成型される器が、
裕代さんに渡り、削りが加えられていきます。

裕代さんは、沖縄県の読谷村焼・北窯で約3年間の修業後、
8年前に帰郷し、父のもとで作陶をはじめられました。
「毎日の仕事を大事にしています」
と話す裕代さんの手仕事も、とても優しく丁寧なもの。
こうして父娘の協働による器が生み出されています。

思わず手に取ってみたくなるような温かみを感じます。
装飾のしのぎや藁描き、櫛描きといった技法は、
清志さんの恩師、生田さんからの直伝です。
師から弟子に継承された技術は今、
父から娘へと伝承されていっています。
最後に清志さんは、自然いっぱいに囲まれる環境で、
ものづくりに対する想いを語ってくださいました。
「普遍的であるがままの世界のなかで、
決して無理をせずに、美しいものを作っていきたい」

作り手のぬくもりを感じる器は、
大地の恵みと父娘の愛情がたっぷりと詰まっているものでした。
"民藝の器"を生み出す、湯町窯
流れるような直線と波線が織りなす文様に、

くまのプーさんのはちみつ壺を連想させる、黄色い釉薬が印象深い器たち。
素朴だけれど、どこかモダンで手づくりの温かさを感じます。

これらは、松江市玉湯町の玉造温泉駅から程近い住宅街にある、
「湯町窯」で作られており、
その地で育まれてきた歴史を踏襲した器たちです。
江戸時代に松江藩の御用窯として始まった"布志名焼(ふじなやき)"のひとつで、
大名茶人でもあった第7代藩主の松平不昧(ふまい)公の好みを反映した
茶器を中心に発展してきた歴史を持ちます。

大正11(1922)年に開窯した湯町窯では、当時、
火鉢を中心に作っていたといいます。
各家庭で会合があり、手を温めたり、灰皿代わりに使ったりと、
1軒で10~20個も火鉢が使われていたんだとか。

昭和に入り、民藝運動(毎日使う実用雑器にこそ美が必要という考えから、
それらを生み出す名もなき職人たちの手仕事に光を当て、それを広めようとした運動)
にいち早く参加し、その創始者である、柳宗悦やバーナード・リーチ、河井寛次郎らから
直接指導を受ける機会に恵まれ、洋食器が多く作られるようになりました。
湯町窯の3代目・福間琇士さんは、当時、2代目である父親の貴士さんの後ろから
その様子を見ていたそうです。
飾られていたこの写真は、バーナード・リーチ氏(左)が作る様子を見守る、
湯町窯・2代目の福間貴士さん(手前)と柳宗悦氏(右奥)。

そして、これはバーナード・リーチが1953年に湯町窯で作ったお皿。

これまで各地で見てきた焼き物の裏には、
必ずといっていいほど、民藝運動の足跡があり、
ここに来て、その実施者と直接かかわりを持った方にお話を伺うことができ、
なんだか感無量でした。
湯町窯では、地元産出の粘土や釉薬を使っていますが、
美しい黄色の釉薬が、英国のガレナ釉(鉛の硫化物)に似ていたこともあり、
バーナード・リーチがとりわけ興味を持ったのだそうです。
「いつも初心に返って、リーチ先生、ご先祖様、諸先生のおかげで
やらせてもらっていることを忘れずに作っています」
そう謙虚に話される、3代目の福間さんに、
バーナード・リーチ直伝の技を見せていただくことができました。
粘土と水を混合した泥漿(でいしょう)釉で化粧掛を施し、
乾かないうちにすぐ別の釉薬が入ったスポイトで模様を描いていきます。
「スリップウェア」と呼ばれる手法です。
その作業の早いこと!
スルスルと描かれ、あっという間に終わってしまいました。
ちなみに、焼き上がった器が、冒頭の写真にある黒いお皿です。
続いて、実演してくださったのがコーヒーカップの取っ手付け。
粘土を細長く伸ばし、コーヒーカップの側面上部に付けると、
指で生地を伸ばしながら、下部になじませていきます。

「取っ手を取って付けるのではなく、木に枝が生えるように付けるようにと、
リーチ先生から教わりました。
長さと厚さをつかむまでに随分と苦労しましたが、指一本が入って、
触れると熱い側面に指がくっつかないような持ちやすい仕立てになっています」
通常、型で取っ手の形を作ってから付ける手法が多いそうですが、
手で生地を伸ばして付ける方が圧倒的に速いといいます。
福間さんがニコニコ笑顔でこう続けました。
「ひとつ自慢してもいいですか?
この手法で1時間に150個取っ手を付けたことがありますよ。
当時それだけ買っていただけたので、上手になったんですけどね」

どこまでも謙虚な福間さんが、「これもうちの代表的な器です」
とご紹介くださったのが、このエッグベーカー。

ふっくらとしたフォルムが愛らしいエッグベーカーは、
50年以上のロングセラー商品で、これもバーナード・リーチ氏のアドバイスをもとに
生まれた逸品だそう。網の上やオーブンで調理して、
そのまま食卓に並べられる、お洒落で機能的な器です。
フタを開けると、ふわりと卵の香りが漂い、
出来上がった目玉焼きはトロリと絶妙な半熟具合に仕上がっていて、
これまでに食べたことのないおいしさでした!
盛りつける器によって、ごはんのおいしさは変わると思いますが、
「これを使って次は何を作ろうかな…」という、調理が楽しみになる器には
初めて出会ったように思います。
そう思わせてくれることこそが、暮らしの中に溶け込む
"民藝の器"である証なのかもしれません。
お茶文化が根づく町
島根県では、出雲市にある無印良品 ゆめタウン出雲![]() へ。
へ。
いつものように人気商品を伺うと、紹介してくださったのがコレ↓

スタッフさんが手にするのは、
有機ハーブティーティーバッグ ルイボスティー(写真左)と、
スティック切れ端干しいも(写真右)です。
上述の通り、大名茶人の第7代松江藩主・松平不昧公の影響か、
出雲人はお茶が大好きだそうで、
お茶とお茶に合うお菓子が人気のようですね!
出雲地方では「ぼてぼて茶」という珍しいお茶も見かけました。
煮出した番茶を茶せんで泡立たせ、
その中にごはんやお豆、たくあん、こんぶなどを入れて飲むというもの。

名前の由来は、泡立たせる際の音から来ているそうですが、
そのルーツは、奥出雲のたたら製鉄の職人さんたちが高温で過酷な作業の合間に、
立ったまま口に流し込んでいた労働食だったという説や、
不昧公の時代の非常食だったという説、
上流階級の茶の湯に対抗して庶民が考え出した、
趣味と実益を兼ねた茶法だとする説などいろいろあるようです。
そういえば、富山県では「バタバタ茶」というものに出会いました。
なんだか響きが似ていますね。
ちなみに、ルイボスティーは南アフリカに伝わるノンカフェインのハーブティーで、
口当たりがとても滑らかで、なんだかホッとする味。
スティック切れ端干しいもは、その生産者を茨城キャラバンで取材しました。
無印良品のお茶もお茶菓子も種類がたくさん。
あなたのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください!
「無地極上」の器
出雲市斐川町(ひかわちょう)にある「出西窯」(しゅっさいがま)へ向かうと、
モクモクと煙の立つ建屋が目に入ってきました。

そう、この日は年に3~4回行っているという、登り窯の火入れ日。

これまでも、登り窯は何度か目にしてきましたが、
実際に火入れ日に遭遇したのは初めてのことです!
窯内の温度を測ることが困難な登り窯においては、
ゼーゲルコーンと呼ばれる粘土や釉薬の成分を固めたものを窯に入れ、
焼成具合を測るんだそうです。
焼物の大きさによりますが、4000~5000個を一気に焼き上げられる登り窯では、
準備に1週間、焼くのに2日間、冷ますのに3日間を要するんだとか。
少人数で運営している窯元が多い昨今、
手間も時間も要する登り窯を、単独で焚ける窯元は珍しいのではないでしょうか。
工房へお邪魔すると、バランスの取れた年代別の陶工たちの姿が。
地元から、県外から、出身地も人それぞれです。
ろくろ成型から釉薬掛けまでをそれぞれが一貫して行っているため、
個人作業になりそうですが、
そこには不思議と和気あいあいとした雰囲気が流れていました。
「出西窯の成り立ちか関係しているのかもしれません」
そう教えてくれたのは、出西窯の2代目代表理事を務める多々納さん。

「1947年、戦後の焼け野原からはじまった出西窯は、
父を含む5人の青年によって創業されました。
民藝運動にかかわった島根県出身の河井寛次郎氏に手紙を送るなど、
積極的に良いモノを作ろうと励んできた窯元なんです」
積極的で柔軟な姿勢の出西窯は、
河井寛次郎や濱田庄司、バーナード・リーチといった、
名だたる民芸運動家たちに手ほどきを受けながら、
その技術を向上させてきたようです。
実際に、出西窯のカップ&ソーサーでコーヒーを頂きました。
鮮やかながら、落ち着きのある釉薬の風合いからか、
不思議とほっとした気分に浸れます。
「カップを手にした時、コーヒーを口に含もうとした時、
その存在を忘れてしまうような器を目指しています。
そこで違和感を覚えてしまうものは、日常使いの器としては適していない」
多々納さんがそう話す通り、出西窯の焼物のコンセプトは「無地極上」。
倉敷民芸館の初代館長、外村吉之介(とのむらきちのすけ)の言葉で、
「日常的に使い勝手が良いものほど無地の品が一番である」
という意味だそう。
また、多々納さんはこう続けます。
「一般の食器棚を想定して、きちんと収納できるよう、
現代の食生活の用途に合うような器を目指しています」
確かに、出西窯の器を見ていると、
これは朝食プレートや取り皿に、これはサラダにもラーメンにも使える、
など使用シーンを想起させてくれます。
食器棚に収容できるように、様々な用途に使えるようにと、
そこまで考えて作られている器とは、うれしい限りですね。
出西窯では創業期の想いを忘れないために、今でも朝礼時に
河井寛次郎氏の「仕事のうた」を全員で音読しているようです。

「仕事が仕事をしてゐます 仕事は毎日元気です
出来ない事のない仕事
どんな事でも仕事はします いやな事でも進んでします
進むことしか知らない仕事 びっくりする程力出す
知らない事のない仕事 きけば何でも教へます たのめば何でもはたします
仕事の一番すきなのは くるしむ事がすきなのだ
苦しいことは仕事にまかせ さあさ吾等はたのしみましょう」
民藝運動のDNAを受け継ぐ窯元は、
現代における民陶を今日も提案し続けています。
100年後の家具づくり
無印良品広島パルコ店![]() を訪ねました。
を訪ねました。

なんとも温かみのある店構え。
中に入ると、店構えに負けない温かいスタッフたちが、
10月下旬からスタートしたキャンペーン
「ウール地球大」を体現しながら迎えてくれました。

すっかり寒くなってきた今日この頃、
世界中の寒冷地帯に生きる動物たちからの恩恵をまとって、
温まってみるのもいいですね☆
そんな広島パルコ店での人気商品は、
こちら!

「リアルファニチャー」無垢材家具シリーズです!
無垢材は、木のぬくもりが感じられて、心安らぐから不思議です。
ところで無垢材って、一体何のことなのでしょうか…?
「純粋無垢」という言葉がありますが、この場合の無垢は
「けがれがないこと」を意味します。
それと似たニュアンスで、無垢材とは、天然木をそのまま切り出し、
余分な手を加えていない木材のことを指すようです。
その分、重たいですが、木本来の質感が楽しめ、
使うごとに色艶が深まり、味わいを増していきます。
実は、これらの無垢材家具シリーズは、広島県で作られていました。
広島県は、全国でも有数の家具の町としても知られているんです。
早速、広島県府中市にある、
無垢材のダイニングテーブルを生産する工場を訪ねました。
案内してくださった瀬尾さんに、
府中市が家具の産地になったゆえんについて教えてくれました。

「もともと、旧松永港(現・尾道糸崎港)に入ってきた桐材を使って、
農閑期に家具を作り始めたのが由来です。
その後、タンスなど婚礼家具の需要にともない、発展していきました。
他の産地に比べ、そこまで木材が多くあった土地ではないので、
ノミ・カンナを使わせたら一丁前ですよ」
職人によってなんと40年も使い込まれたノミ・カンナを
特別に見せていただきました。


「機械化された現在でも、商品の良し悪しを決めるのは、
最後は人の手。木は生き物ですから」
その道40年の職人は、そう語ります。
実際、工場内には、大型機械が導入され、
家具用の大きな木材も自在に姿を変えていきます。

しかし、その多くの工程で、職人の手が加わっていました。
瀬尾さんは、
「何より、木を見る目がとても大切」
と語ります。
FSC(Forest Stewardship Council、森林管理協議会)等が認証した、
世界の森林保全のために、適切に管理された森林からの木材の中でも、
最高クラスの木材を仕入れ、

その中でも、良質な木材が職人の目によって厳選されるのです。
現在では、なかなか手に入りにくい節ありの木材を、
アメリカまで直接、仕入れに行って作られたダイニングテーブルも展開中。

節ありの木材は、そもそも少量しか採れず、扱いにくいため、
これまではあまり市場で使われてこなかったそうですが、
あえてそんな木材に注目し、味のある家具として世の中に蘇らせていっています。
「世界に一つとして同じ模様のないオリジナルのテーブルを、
ぜひ、店頭で見て、触ってみていただきたい」
瀬尾さんがオススメする無垢材(節あり)ダイニングテーブルは、
全国の無印良品大型店舗で、数量限定で販売中です。
続いて、無垢材のチェアを生産する工場を訪ねて、広島市佐伯区へ。
日本で最も古いデザインの椅子を生産し続けている工場で、
木材の複雑な加工を得意としています。

こちらでも同様に、
FSC認証の木材から厳しい目で木材が選ばれていっていました。

工芸の工業化を牽引した工場でもあり、
技術力の結晶のような機械が、目まぐるしく稼働しています。


「高価な機械でも、それを使いこなせるかが鍵です。
複雑なプログラミング技術を要しますが、それが技術力の差を生みます」

生産本部を担う三井さんは、そう語ります。
事実、座り心地を追求した曲線を実現するために、
こちらの機械では、縦×横×高×角度×回転の、
なんと5次元を制御しながら稼働させていました。

優秀な技術者でもプログラムを組むのに、
約2カ月を要するほど高い技術力が求められるそうです。
「ただ、仕上げはやっぱり人の手です。
ここで良品か否かが決まるといっても過言ではありません」
ここにも、日本の職人のていねいな手仕事がありました。
営業部門を統括する千葉さんは、
家具づくりにかける想いをこう語ります。

「100年後も世界で愛され続ける家具を作りたい。
そのために、長くものづくりを続けることが大切だと思っています」
一つひとつ異なる、生きた木材を使って、
常に同じ形のものを作り続ける難しさ。
その背景には、細部にまで手を抜かない、
日本の確かな技術力が生きていました。
国産の無垢材家具シリーズには、
日本のものづくりの技術と想いが結集しているように思いました。
広島から世界へ
広島に国産スニーカーブランドがあることをご存じでしょうか?
「SPINGLE MOVE(スピングルムーヴ)」

今から10年前に、広島県府中市で誕生したブランドです。

実はこのブランド、
1933年創業のゴム総合メーカー(株)ニチマンが立ち上げたものでした。
当初より、ゴム製の長靴や草履などを手掛けてきましたが、
輸入品などに押され、不況のあおりも受けて工場閉鎖の危機に。
「なんとか自社工場を残したい」という一心で、
約70年間にわたり培ってきた技術と知識を結集させ、
2002年に正式にスニーカー市場に参入したのです。

ブランド名の「SPINGLE MOVE(スピングルムーヴ)」とは、
スピンの進行形を意味し、世界に通用するシューズとして
一歩一歩らせん階段を上るように進化し続けたい、
という想いが込められていました。
すでにその技術力は海外からも評価され、
有名ファッションブランドとのコラボ商品も生まれていっています。

特筆すべきは、その製法です。
1839年にアメリカで開発された、
最も歴史のあるスニーカーの基本製法「バルカナイズ製法」。
アッパーとソール部分を別々に作り接着する
「セメンティング製法(写真左)」と比べ、
「バルカナイズ製法」で作られたもの(写真右)は、
アッパーとソールが密着している印象です。
この製法は、基本的に多くの工程を手作業で行うため、
生産効率の問題で、現在、国内工場はほとんど残っていないんだとか。
たまたまバルカナイズ製法で作られた靴が
加硫缶から出されるタイミングを拝見することができました。


「シュオーーーー!!」
という蒸気を発しながら開いた缶の中からは、

宙吊りのスニーカーが!
できたてほやほやのスニーカーに遭遇する機会はなかなかありません。
硫黄を混ぜたゴム材を加硫缶で加熱することで、
弾力のあるゴムに変わるんだそうです。

アッパー部分には創業当時、日本では珍しかったレザーが多用されています。
代表格のカンガルーをはじめ、牛、馬、豚、ラクダ、ゴート(ヤギ)、
シープ(羊)、クロコダイル、パイソン(ヘビ)、リザード(トカゲ)など、
実に様々なレザーが使用されてきましたが、
このバルカナイズ製法の加熱に耐えられる革を探すのは至難だそう。

これまでには、県内の尾道帆布を使用した布製靴など、
多種多様な素材・企業とのコラボレーションを実現していっています。

こうして生み出されるSPINGLE MOVEスニーカーは、
イタリアやアメリカの展示会でも高い評価を受け、海外へも展開し始めています。
おかげで現在では工場も朝から晩までフル稼働だそう。
生産者の持田さんは、
スニーカーづくりに対する想いをこう語ります。

「"安く仕上げよう"ではなく"より良いものを作ろう"。
これが、日本のものづくりに対する姿勢ではないでしょうか。
履き心地を追求して、細部にまでこだわっていきたい」
一度は閉鎖の危機に見舞われた日本の工場が、
想いと技術を結集させて蘇り、世界を席巻し始めています。
尾道帆布
「"すごいね〜すごいね~これ何かに使えないかしら!"
最初はね、そこから始まったんですよ」
少女のようにキラキラと輝く瞳で、
そう話してくださったのは
「工房尾道帆布(はんぷ)」代表の木織雅子さんです。

もともと飲食店を経営されていた木織さんは、
中小企業家同友会 尾道支部女性部の仲間と数名で
尾道に残る、向島の帆布工場見学に出掛けました。
「尾道には食べ物はたくさんあるけれど、
持って帰れるお土産物がないので、何か作れないかねぇ…」
ちょうどそう考えていた1998年のことでした。

織機の大音量が響き渡る工場で、
少しずつ織り上がっていく木綿の布を前に心が躍ったといいます。
尾道はかつて北前船の寄港地だった関係から、
帆布が盛んに織られていました。
帆布はもともと文字通り、帆船の布として生まれましたが、
厚手で丈夫、熱に強く通気性がいいという特徴から、
時代ともにテント、シート、作業服などにも使用されるようになり、
70年前には尾道市内だけでも帆布工場が10社ほどあったそう。
しかし、戦後になると化学繊維の台頭により、
帆布のニーズは減っていき、
今では工場も市内で1ヵ所になってしまいました。
木織さんは、縫製経験のある田口さんを誘って、
1999年に小さなポーチづくりから始めました。
「初めは布が厚くて家庭用ミシンでは針が通らなくて
とても苦労しました。
工場に相談して業務用ミシンを1台もらい、
クリーニング店の片隅でスタートしたんです」
と田口さんは当時を振り返ります。

今では作り手の数も増え、
トートバッグを中心に、小物・雑貨を広く展開しています。

生地がとてもしっかりしていて、使うほどになじんでいく、
シンプルですが、どこか優しい味わいです。
ちなみに、工房尾道帆布にはデザイナーはいません。
このタグのロゴも北前船のシルエットをモデルに
自分たちで考えたんだそうです。

現在、お店と併設して工房を構えており、
使う人の声をヒントにものづくりをされています。
「お客様のワガママをできるだけ取り入れたいと思って。
右利きと左利きの人だと、ファスナーの向きや
使いやすいポケットの位置も違うんですね。
お客様からいつもたくさん教わっています」
近年、尾道にはしまなみ街道のサイクリングを目的に
来られるお客様も増えているとのこと。
そんなライダーさんたちのための、
自転車用グッズもいろいろ開発されていました。

また、木織さんたちは地元とのつながりを大切にしています。
学生と共同で商店街の空き店舗を利用した
「尾道帆布展」を開催したり、
帆布を使ったワークショップを行ったり。
「駆け出しの頃、お金も場所もなくて困っていた時に
手を貸してくれたのが地元の人たちでした。
それを恩返ししていきたいと思っています」
地元の小学校でも、月1回出前授業を行い、
子供たちに帆布を知ってもらう取り組みもされています。
最後に今後の抱負を伺いました。
「今、お店の前でも帆布の原料である、綿(わた)を育てているんですが、
夢はしまなみ街道沿いを綿で埋め尽くすこと!」

帆布工場で「なんだか素敵!」と感じた感性を元に
次々と勢力的に取り組まれてきた木織さんたち。
実は、14年前、木織さんたちが工場見学をした時に、
別の団体も同じく見学に行っていました。
しかし、彼らは工場の社長の話を聞いて、
「繊維産業はもう厳しい」という判断をしていたんだそう。
同じ現場を見ても、こうして未来につなげられるかどうかは、
そこに可能性を感じられるか、
ワクワクできるかなんだなということを知らされました。
木織さんたちの地域に根差した取り組みは、
東南アジア諸国からも注目を浴び、
来月には実際に海外から視察団が来るそうです。
おもしろく生きる
「日本のものづくりの行き過ぎた空洞化は避けなくてはいけない」

山口市でデニムブランド「匠山泊(しょうざんぱく)」をプロデュースする、
岡部泰民さんは開口一番、そう切り出しました。
日本のデニム産業と聞くと、岡山県が有名ですが、
その生産工場は周辺地域に点在しており、山口県もその一つ。
その多くが生産コストの合理化を求め、後に海外に生産工場を移していますが、
岡部さんの工場は、今も山口市内に5つの工場を構えています。
岡部さんが国内生産にこだわるのには、あるきっかけがありました。
1999年、仕事でヨーロッパに視察へ訪れた際、
スペインのアパレルブランドの台頭を目の当たりにします。
それは、フランスのアパレルブランドが
生産工場をスペインに置いてきたため、技術が移転したことによるもの、
という実態を知り、未来の日本と中国をはじめとしたアジア諸国との関係が
それとシンクロして見えたんだそう。
「ものづくりの拠点を残しておかなくては、
日本には何も残らなくなってしまう」
そんな危機感から、ひたすら国産ブランドを追求し、
2005年に「匠山泊」を立ち上げました。

洗練された日本の加工技術と最高品質の素材を結集し、
生まれたブランドです。
「ものづくりというのは、価値創造だと思っているんです。
ものは意思を持ちませんが、価値には意思を込めることができる」
そう話す岡部さんが昨年リリースした新シリーズ「Re維新」には、
日本のものづくりに対するたくさんの想いが込められていました。

まず、プロデュースに携わったのは、日本の叡智を結集した顔ぶれ。

生地には動きやすく夏場でもむれにくい国産素材が使用され、
細部にまで日本の技術の結晶が光っています。

特筆すべきは、バックポケット。

かつての長州藩士、高杉晋作率いた奇兵隊の隊旗がモチーフにされ、
そのポケット状の内部には、
自らの"想い"を入れて縫合できるという仕立てになっています。
維新期の志士たちが、襟に自らの信念を入れていたことに着想したそう。
もちろん、岡部さんも「Re維新」を身に着けていたので、
内部に込めている"想い"を聞いてみると…、

「おもしろく生きる」
高杉晋作の名言「おもしろきこともなき世をおもしろく」を
彷彿とさせる言葉ですが、
岡部さんには、脈々と長州人のDNAが受け継がれているように感じました。
「私は父親から、自分が世に生まれてきた使命を考えろ、と育てられましてね。
松下村塾の吉田松陰先生も、"自分を使う"≒自分がこの世の中で何を為すか、
これに注力していらっしゃった。私も人生を楽しみながらそう生きたい」
まるで現代の吉田松陰のようにも思える岡部さんは、
「Re維新」シリーズを自らが手掛けるデニムにとどまらず、
山口の様々な名産品にまで広げ、その良さを全国に発信しようとしています。
また、若手の育成にも積極的で、
メイドインジャパンのアパレルファッションを世界へ発信しようと
2009年までの10年間、山口市で
「ジャパン・ファッションデザインコンテスト」を開催。
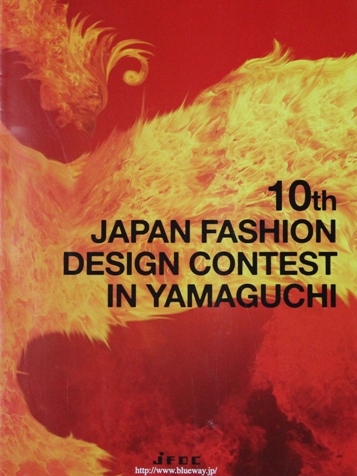
若手ファッションデザイナーやモデルの登竜門となったこの大会からは、
今も様々な場面で活躍する人材が輩出されました。
「大人の役割は、機会を作ってあげることだと思っているんで」

そう話しながら優しく微笑む岡部さんは、
最後に日本のものづくりに対して熱く語ってくださいました。
「成熟した文化の日本には、様々な価値のものがあって然るべきだと思います。
その中で、日本のものづくりは高付加価値で在らねばならない。
高付加価値とは物を超越したもの、『人』その中の『心』が創り出すものです。
歴史的にも高い生活文化を伝承している山口から、
高付加価値なものづくりを発信し続けたい」
長州人の魂が脈々と継がれている岡部さんからは、
日本人としての誇りを感じずにはいられませんでした。
萩焼
萩市内には、縫うようにして藍場川が流れていますが、
かつては農業用水路のほか、日常生活にも利用され、
川舟もここを通っていたそう。
現在は鯉が放流されていて、風情あふれる町並みを演出しています。

そして、この萩市一帯で焼かれている陶器が「萩焼」。
無印良品でも以前FoundMUJIの日本の10窯で販売し、
現在"めし茶碗"は通常店舗でも取り扱っています。

今回はその生産窯を訪ねました。
最初に、この萩焼を手に取ってみて気づいたことを、
生産者の礒部さんにぶつけてみました。
「なぜ、高台部分に切れ目があるのでしょうか?」
諸説あるようですが、一般的に知られているのは、
もともと御用窯で、身分の高い人しか使うことができなかった器を、
意図的に切り欠きを入れて"キズ物"とすることで、
庶民にも手の届く雑器としたのではないかということ。
「この切り欠きは、実は作る時と使う時にも
それぞれメリットがあるんですよ」
と礒部さんは続けます。
切り欠きを入れることで、
高台部分の土が乾きやすいということ、
また、焼成時に熱が伝わりやすいところが理に適っているそうです。

使う際には、熱いお茶を入れて茶托にのせた時に、
高台の切り欠き部分から空気が入るので
持ち上げても茶托がくっつかないことや、
食器洗浄機で洗う際に水が溜まらないのが、
今の時代の生活にも合っています。

萩焼は古くから、「一楽・二萩・三唐津」と謳われ、
茶人の間で広く愛好されてきました。
それは、陶土に吸水性があり、使っていくにつれて
貫入(かんにゅう・表面の細かいヒビ)を通してお茶がしみ込んで、
その色や艶の変化(萩の七化け)を楽しむことができるため。

絵付けによる装飾はほとんど行われない萩焼ですが、
陶土の配合、釉薬の掛け具合、焼成の仕方によって、
シンプルですが、とても味わい深い表情が出ています。
陶土は山口市で採れる「大道土」(白色)、
日本海に浮かぶ離島・見島で採れる「見島土」(赤土)、
萩市の東方で採れる「金峯(みたけ)土」(白土)を
混合して使いますが、
下の写真のように全く違う色の表現が可能です。

また、こちらの「梅花皮(かいらぎ)」という模様は
陶土と釉薬の収縮の違いを活かして作られたもの。

釉薬が溶け切る手前で火を止めるそうですが、
タイミングを見計らうのが難しいそうです。
さらに、
「後から来る酸化を楽しむのも萩焼の特徴かもしれませんね」
と礒部さん。
土に含まれる鉄分が、空気に触れることで赤みを帯び、
美しいグラデーションを生み出すのです。

使うほどに味わいが増していく萩焼は、
地元の陶土や釉薬の特徴を熟知し、
長年培ってきた焼成技術を持つ職人さんたちによって作られていました。
現在でも萩焼の窯元は80以上あるといい、
また、山口県民の多くが何かしら萩焼を自宅に持っているんだそう。
地元で作られ、地元で愛されている萩焼だからこそ、
県外の私たちにとってもなじみやすい民陶となっているのかもしれません。
「約400年前にこの地で生まれた萩焼の歴史を大事にしたい」
そう語る、礒部さんの言葉を聞いて、
歴史と作り手の想いが詰まっていて、
使い込むごとに味わいの増す器を、日常使いしたくなりました。
やちむん
沖縄の焼き物は琉球の方言で「やちむん」と呼ばれています。
そして、「やちむん」といえば、「壺屋焼」(つぼややき)が主流。
1682年に、琉球王府は焼き物産業を発展させようと考え、
各地に点在していた窯場を壺屋(つぼや)地区に集め、
焼き物の里を作ったことが、壺屋焼としての始まりです。
しかし、1970年代に那覇市は公害対策のため登り窯の使用を禁止、
窯場はガス窯への転換を余儀なくされ、
登り窯での制作を好む職人たちが、
本島中部の読谷村(よみたんそん)に窯を移しました。
そうして現在、壺屋焼は、
壺屋地区と読谷村の2大エリアで主に作られています。
今回は300年の伝統を誇る、壺屋地区の窯元「育陶園」へ。

壺屋焼は、中国や朝鮮、日本、東南アジアの国々の技術が
チャンプルーされて(混ざって)、
琉球独自の焼き物として発展してきたといいます。

ぽってりとした厚手の成形と、
陶器というよりも、磁器に描かれるような鮮やかな彩色。
中国の純白の磁器に憧れた昔の陶工が、
赤土の上に真っ白な土を掛けて再現したことから生まれた
「化粧掛け」という技法が使われています。

そして、この化粧掛けに施した「赤絵」も
中国に学んだものだそうです。

また、化粧掛けした上から削っていく「線彫り」は、
ガス窯で出せない色の味わいを
デザインで表現することから発展していったんだとか。
一つひとつ下絵なしで仕上げていくというので
失敗が許されない、熟練の技を要します。

他にも、スポイトで化粧土を絞り出して、
盛り上がった紋様を描く「イッチン」(写真左)や、
福岡の小石原焼や大分の小鹿田焼で多用されていた「飛び鉋」(写真右)
など、様々な技法を使って、壺屋焼は作られていました。
こんなにも種類豊富な焼き物を作る窯元には、
これまで出会っていなかったかもしれません。
ずっと眺めていても飽きない…
とても洗練された器たちです。
ご案内いただいたのは、
6代目・高江洲忠(たかえすただし)さんの
長女で企画・販売責任者の高江洲若菜(たかえすわかな)さん。
「うちは壺屋焼という伝統だけでなく、、
沖縄という伝統を大切にしています。、
そのなかで、形やデザインは現代風にアレンジさせていっています。、
工房とお店が近いので、お客様の声を反映させながら、
進化させていけるのがいいのかもしれません」

育陶園は、壺屋地区に3店舗構えていますが、
それぞれお店のコンセプトや対象としている客層が違うそう。
私たちがお店にいる時にも職人さんがお店に顔を出して
お店のスタッフにお客様の反応を聞いていたのが印象的でした。
それから、育陶園には器の工房とは別に、
シーサーを作る獅子工房もあります。
もともと瓦職人が瓦を打ち砕いてシーサーを作っていましたが、
17世紀以降、壺屋焼きの発展とともにシーサー製作の場は
壺屋に移ってきたといいます。
シーサーは型に陶土を押し込み成形し、
その後、口や耳、表情をつけて仕上げていきます。
型やシーサーの表情は窯元ごとに代々引き継がれていくもの。
育陶園では、作り手がシーサーの歴史的背景などを知ったうえで作るべき、
と週1回「シーサー勉強会」なるものを自分たちで行っているそうです。
沖縄には、昔から琉球信仰が深く根付いており、
魔除けのためのシーサーは、今でも各家の軒先に置かれています。

こうした置物としての焼物が産業として成り立っている地は、
このキャラバンで巡った地の中でも沖縄が初めてでした。
この沖縄の人々の敬虔な信仰心が、
壺屋焼が繁栄してきた一つの要因といえそうです。
琉球王国の時代に生まれ、
沖縄の人たちとともに発展してきたやちむん。
今後も変わることなく、沖縄の象徴として、
沖縄の地で作り続けられてほしいと思います。
島人ぬ宝
「この島の素材を活かして、
島のブランドを作っていきたいと思っています」
そう優しく語ってくれたのは、
(株)オキネシア代表の金城幸隆(きんじょうゆきたか)さん。
"かりゆしウェア"がよく似合う、沖縄生まれ沖縄育ちの社長です。

"かりゆしウェア"って、てっきり観光業にかかわる人たちだけが
着ているものかと思っていましたが、
ワイシャツとネクタイに代わるホワイトカラーの服装として
沖縄の夏に、広く定着しているものだそうです。
確かに那覇市内を走る都市モノレールの"ゆいレール"内でも
かりゆしウェアを着たビジネスマンを多く見かけました。
見ている側もわくわく明るい気分になる☆
服装ひとつで、仕事をする感覚もなんだか変わってきそうですよね♪
さて、話がそれましたが、
金城さんは32歳で「世界を見たい!」と仕事を休職し、
世界一周の旅へと出ました。
未知なる世界を知ると同時に、
これまで見えていなかった郷土「沖縄」に対して
想いを馳せるようになったといいます。
「旅で出会った他国の人は皆、
自分の国の文化や言葉を大事にしていました。
海外で自己紹介をする時に"自分のルーツをきちんと話せるか"
は、国際人として最低限のことだと思うようになったんです」
そうして「モノづくりを通してアイデンティティの種蒔きをしたい」
と36歳で独立。
沖縄の、良い商品・喜ばれる商品・誇れる商品を
ひとつひとつ丁寧に仕立てて、
息の長い県産品に育てることが、ウチナーンチュ(沖縄県民)の
アイデンティティ、つまりは「沖縄を大切に思う心」に
寄与すると考えたのです。
その後、金城さんによって生み出されてきたのは、
食、雑貨、化粧品…と幅広いジャンルの商品です。
沖縄でお茶請け菓子の定番として、よく出される「黒糖」。

さとうきびを搾り、煮つめて固めたものですが、
現在、純国産の黒糖は、沖縄の7つの離島でしか、
生産されていないそう。
オキネシアのひとくち生黒糖「ざわわ」は、
西表島で作られており、7つの生産工場の中で
唯一、山からの天然水を使用しています。

その年のさとうきびの収穫によって生産量が変わる限定商品で、
毎年味が変わるといいます。
口に含むと、じわじわっと黒糖の素朴な甘さが広がります。
沖縄出身ではない私にとっても、なんだかほっとする
懐かしい味なので、沖縄出身者にとっては尚更そうなのかもしれません。
他にも、沖縄の黒糖や塩、島唐辛子などの沖縄産原料を使った
ピーナッツ菓子や飴などがありますが、
それらのネーミングにも沖縄の要素が含まれていました。

例えば、マカダミアナッツ菓子の「ナンチチ」は
琉球古来の方言で「おこげ」を表し、
ピーナッツ菓子の「ぴりんぱらん」は
1970年代の沖縄で流行したコトバで「おしゃべり」という意味。
「ほとんど死語になりつつあるような沖縄特有のコトバでも、
商品名として表舞台に引き出すことで再び輝きを放つのではないか」
という金城さんの想いが込められています。
「これを飲んでみてください」

出していただいたのは、とてもさっぱりとしていて、
控えめな甘さのみかんジュース。
「沖縄の在来みかんで、"カーブチー"っていうものなんです」
"カーブチー"は沖縄北部のやんばる地方で
ちょうどこの時期(10~11月上旬)に収穫できるみかんです。

昔はちょうど運動会シーズンに穫れることから
「運動会みかん」として、広く親しまれていたそうですが、
カーブチーの「カー」は 沖縄の方言で"皮"、
「ブチー」は"分厚い"を意味していて、
名前のように皮が厚くて種が多いので、加工には不向きなことから生産が減少。
沖縄で生産されるカンキツ類全体の1割りにも満たないため、
地元のスーパーなどでもなかなかお目にかかれない、
マイナーみかんだそうです。
金城さんはこの"カーブチー"の復活にも取り組み、
皮を手で剥いて遠心分離させて作った、
カーブチー果汁100%のジュースが出来上がりました。
「私自身が好きなみかんだったので、埋もれていくには惜しい…
と思ったんですね」
金城さんは"カーブチー"の新しい価値を見いだすべく、研究を続けたところ、
カーブチーは在来種で強いため、
「無農薬で放っておいても実がなる」ということが分かりました。
さらに豊かな皮の香りにヒントを得て、
その特性を最大限活かしたアロマオイル「星涼み」と
香水「UTAKI」の開発に成功。

シトラスタイプの香水のほとんどに、
柑橘系の人工香料が使用されているそうですが、
この「UTAKI」は100%天然のカーブチー香料で調香されたものです。
本来、香水はつけてからの時間によって
香りが変化していくのを楽しむものですが、
それが人工香料だと一定の香りで表情がつかないんだとか。
沖縄の素材を使って、香水の本場・フランスの調香と製造技術が
融合してできた「UTAKI」は、移ろいゆく香りを表現できたといいます。
「島の中に散在する有形無形の"大切なもの"を、
私たち自らの努力で"誇り"に変えて守り続けてゆくことこそが
『島人ぬ宝』のような気がするんです」
金城さんのモノづくりには、生まれ育った沖縄への感謝の想いが
たくさん詰まっていました。
※オキネシアの一部商品(「ざわわ」「ナンチチ」「ぴりんぱらん」
「琉球かつお豆」「童玉」)はFoundMUJIを扱う無印良品で
お買い求めいただけます。
紅型(びんがた)
沖縄でよく見かけるこの衣装、
沖縄の伝統衣装の琉装です。

これは、琉球王朝時代の王族や貴族の装いで、
「紅型(びんがた)」という伝統的な技法で染められています。
紅型の「紅」は「色」を意味しており、
紅型とは「色」(顔料)と「型」を使った染物を指すそう。
琉球王朝時代は首里城の周りに染屋が置かれ、
王家から手厚く庇護されていましたが、
廃藩置県後は庇護を失い、さらに第二次世界大戦で多くの型や道具が焼失し、
多くの染屋は廃業を余儀なくされました。
しかし、戦後に、
「沖縄びんがた伝統技術保存会」を結成し、
昭和59年に国の「伝統的工芸品」の指定を受け、
現在では沖縄県内でおよそ30の工房によって、振興が図られています。
そのうちの一つ、糸満市にあるびんがた工房「くんや」を訪ねました。
こちらの工房では宜保(ぎぼ)聡さんと理英さんご夫妻と
2人のスタッフが働いています。
夫の聡さんは着物や帯、風呂敷などを染めています。
昔から紅型の代表的な色である黄色は、高貴な色とされ、
着用できるのは王族のみと決まっていたそうですが、
それは、明るい黄色を皇帝の色と定めていた中国の影響なんだとか。
また、紅型は沖縄の強い日差しのもとで染められているため、
ビビッドでカラフルな風合いに仕上がるんだそう。
確かに、古典柄は、色やデザインがとてもハッキリとしていて、
日本というよりも、どちらかというと中国・韓国や東南アジアの雰囲気があります。
柄には、花鳥風月を取り入れたものが多いそうですが、
面白いのが、それらに季節感がないこと。
沖縄以外で作られる染物は、季節によって柄が違うのですが、
紅型は季節が混ざっているのです。
例えば、下の写真の柄は「桜」と「雪」が同時に表現されています。

琉球には存在していない雪が描かれているのは、
亜熱帯気候に住む琉球人の"四季"に対する憧れから来たのではないか
と推測されるようです。
作業工程は、デザイン制作、型彫り、色挿し、
隈取り(くまどり)、水元(みずもと)…など、
ざっと数えて10以上ありますが、
こちらの工房では、そのすべてを1人の職人さんが担当しています。
「工房内で分業するケースはありますが、
他の染めの産地と違って外注していないのが、
紅型の工房がここまで残っている要因なのかもしれませんね」

聡さんが作った型を見せてもらいましたが、その細かいこと!
型彫りだけでも、相当根気のいる作業だということが分かりました。
一方、妻の理英さんは紅型小物を製作しています。
同じ紅型でも、聡さんの作る古典柄やクラシックな柄とは違い、
ポップで遊び心あふれるオリジナルの柄が中心。
柄が違うとこんなにも印象が変わるものなんですね!
「柄に決まりは特にないんですよ。このゆるさが沖縄らしいでしょ!
あ、でも最近、昔の人は計算してゆるくしていたんじゃないか
って、思うようにもなったんですが…」
と理英さん。

伝統は大切に守りながらも、
新しいデザインも柔軟に取り入れていけるところに、
沖縄らしい民芸を感じます。
さらに、紅型の展開はこんなところまで広がっていました。
南城市に住む、ヨコイマサシさんが作るのは「紅型陶器」。

その名の通り、紅型と陶器を組み合わせたものです。
「沖縄に来て陶芸を始める時点で、構想はあったんですよ」

そう話す陶芸家の横井さんは、仲間の紅型作家と共同で
紅型陶器を生み出しました。
今ではご自身も紅型の勉強をされていて、
型づくりから手掛けているそうです。

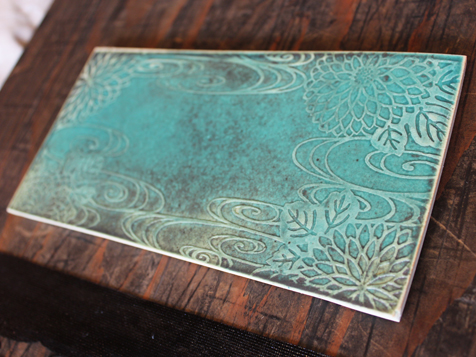
「紅型は最初に色に目が行ってしまうので、
紅型陶器ではあえて色を使わないようにして、
型のよさを引き立てるようにしました」
確かに、紅型の柄そのものを楽しむことができますし、
染物の紅型とはまた違った、落ち着いた魅力があります。
今では沖縄内外から、表札としての発注があるんだとか。
沖縄中の表札が紅型陶器で埋め尽くされたら素敵ですよね。
琉球王朝の終焉、戦争など、過酷な歴史の中で生き残ってきた紅型は、
独特のチャンプルー文化を持つ沖縄の地で、
デザイン・用途を少しずつ変化させながら引き継がれていっています。
最後に、作り手である理英さんがとっても感動されたという
紅型展「琉球の紅型」のご紹介を。

東京目黒の日本民芸館で11月24日まで開催中だそうです。
生の紅型を間近で見るチャンスです!
お近くの方は出掛けてみてはいかがでしょうか。
琉球ガラス
日本のガラスの産地といって、
真っ先に頭に浮かんでくるのが「琉球ガラス」。

沖縄県内のお土産屋さんでは、
必ずといっていいほど目にします。
北海道の小樽もガラスで有名ですが、その由来は全く異なるようです。
明治中期、開拓中で電気の普及が遅れていた北海道では、
ガラス製の石油ランプが重宝され、漁業用の浮き玉とともに、
国際貿易の玄関口だった小樽で、ガラス製造が栄えていきました。

一方、アジアとの国際貿易の拠点の一つであった沖縄では、
明治中期にはガラス製造の技術は伝わっていたようですが、
その生産が本格化したのは、第二次世界大戦後。
駐留する米軍によって持ち込まれたコーラやビールの空き瓶を、
戦後の資源難を乗り切るために、溶かして再生したことに由来するのです。

再生の過程で混入する気泡や、厚みのある琉球ガラスは、
南国的情緒のある工芸として広まっていきました。

そんな琉球ガラスのルーツともいえる工房が、
那覇市内にある「奥原硝子製造所」。

ガラスの原料を手に入れやすくなった今日では、
多くの琉球ガラスの工房が、原料を業者から仕入れているようですが、
奥原硝子では、今でも廃瓶を使い続けています。
例えば、本来捨てられていた窓ガラスの切れ端は、粉砕され、
このように淡いグリーンがかった、美しいガラス食器に生まれ変わります。

バヤリースの廃瓶も、ロゴマーク部分を削ったうえで粉砕され、
この通り、日常使いのコップに様変わり。

一升瓶も渋い輝きを放つグラスに、
緑の瓶は、見ているだけでも心満たされるような器になりました。
その色みとポッテリとした厚みからは、
独特の素朴さと暖かみを感じます。
こうして再生されたガラスは、
当時、米軍基地内やアメリカ本土にも輸出されていたほど、
その技術が評価を受けてきました。
琉球ガラスは、主に「吹きガラス」の製法で作られますが、
吹き竿の先に溶けたガラスを巻き取り、息を吹き込んで膨らませる「宙吹き法」と、
型の中にガラスを吹き入れて形成する「型吹き法」の2種類があり、
その過程の多くはチームプレーで行われています。
ただでさえ暑い沖縄で、約1400℃の窯の焚かれた工房内は
灼熱のような暑さに見舞われますが、
ガラス職人たちは黙々とガラスを作り続けていました。
代表の上里さんは、ガラスづくりに対する想いをこう語ります。

「廃瓶を使ったガラスづくりこそが、琉球ガラスの原点。
これからも廃瓶を日常使いできるガラス食器として蘇らせたい」
琉球ガラスには、こうした深い歴史が刻まれていたのですね。
物事の原点を忘れないためにも、
その歴史的背景を知ることの大切さを痛感しました。
沖縄ならではの人気商品
沖縄県にも、もちろんあります!「無印良品」
県内3店舗あるうちの、国際通りに最も近い
「パレットくもじ」店![]() を訪れました。
を訪れました。
こちらの人気商品は、一大観光地ならでは↓

「ハードキャリー」です。
その人気は沖縄県民からというよりも、
なんと観光客からのものでした!
それにしても、なぜでしょう?
国内はもちろんのこと、中国や韓国からの観光客が多い沖縄には、
琉球ガラスをはじめとした魅力的なお土産品が多く、
それらお土産を大量に買った観光客たちが、
持ち帰るためのケースが必要になるわけなのです。
また、海外にも展開している無印良品ですが、
ジャパンブランドのアイテムは
もちろん日本で買うのが一番安いということで、
海外からの観光客が洋服などをハードキャリーに詰めて、
買って帰るんだとか。
他にも、インナー向きのTシャツや、

携帯用サイズの化粧水シリーズも人気☆

これらも、旅先に忘れ物をした観光客からの需要だそう。
修学旅行生からは、お菓子も人気です♪
店長のオススメは「ぶどうのクッキー」!


レーズンとココナッツを活かした素材の甘さが
控えめでおいしいそうですよ!
ロングライフデザイン
佐賀県と長崎県の県境にまたがる「肥前皿山地区」は、
豊富な天然資源を背景に、各地で焼き物の生産を主産業としてきました。
焼き物の産地に必要だった条件、
1. 斜面があること(登り窯を作るため)
2. 燃料(松)があること(登り窯を焚くため)
3. 水が豊かなこと(唐臼を動かすため)
4. 原料(陶石・陶土)があること
以上の4つが、「肥前皿山地区」にはそろっていました。
4つ目の原料は、「豊臣秀吉の朝鮮出兵」で連れて帰った
鍋島藩の李参平という陶工が、1616年に、有田の泉山で陶石を発見。
ここから、日本で最初の磁器生産が始まったといいます。
肥前皿山地区のひとつで、長崎県の北東に位置する
波佐見町(はさみちょう)は、
四方を山に囲まれた内陸の町で、佐賀県有田町とも接しています。
町を見渡すと、あちこちに窯の煙突を見ることができ、
「やきものの町」であることが一目瞭然です。

献上品などを作っていた隣町の有田と違い、
波佐見では一般の人々が日常使いできる器を作っていました。
その代表ともいえるのが「くらわんか碗」。

江戸時代、商人が小舟で「酒食らわんか餅食らわんか」と声をはりながら
食事などを大型船に対して売った「くらわんか舟」に由来するそうですが、
船の上でも中身がこぼれないように、どっしりとした構えの器です。
手頃な金額で売られた「くらわんか碗」は、多くの庶民の人気を得て、
"磁器は高級なもの、庶民には手が届かない…"
というそれまでの常識を大きく変えました。
そして、需要が増えた波佐見焼の窯は巨大化、
大量生産を行うようになったそうです。
その証ともいえる、全長170m、33窯部屋を持つ、
世界最大といわれる巨大な登り窯の跡がありました。

この手軽で良質な生活の中の器を作る波佐見地区で、
無印良品の波佐見焼および白磁シリーズは作られています。

青みがかった、透けるような白さが特徴です。
そして、これらの白磁を語るのにはずせない人物が、
陶磁器デザイナーの故・森正洋氏。
彼との協業で無印良品の白磁の器が生まれたのです。


今回は、森正洋氏とともに働き、現在も無印良品の器を生産をしている
生産者の元を訪ねました。
「先生はよくこうおっしゃっていました。
"時代やくらしが変わっているのに、焼き物だけ変わらないのはおかしい"と」
当時、森氏のアシスタントをされていた阪本さんはこう振り返ります。
森氏は、素材は伝統を守りながらも、形・デザインは新しく、
現代の生活にいかに根差すかを考えていきました。
森氏が一番大事にしていたものは、
人々の生活の中で長く使われるもの=「ロングライフデザイン」。
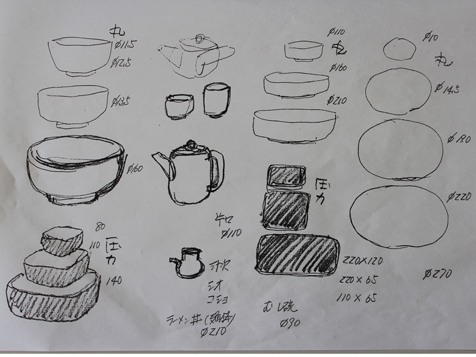 ※森正洋氏の直筆のラフ画
※森正洋氏の直筆のラフ画
「孫の代まで仕事があるように、10年、20年続くものを作ろう」と、
例えば、めし茶碗はこのデザインになるまで、
何度も何度もラインの幅などを見直していたそうです。

さらに、商品化された後も、自分がデザインした器を使って、
"生活に根差したデザイン"かどうかを試し、
その使い勝手を追求し続けていたといいます。
さて、そんな波佐見地区で最近人気のこの商品も作られていました。

一人暮らしや二人暮らしなどの場合に、
スペースをとらずに歯ブラシを置くことができる優れものですが、
実はこの商品、作る工程においても優れたポイントがありました。
器を焼く際の窯の隙間が埋められるため、焼成の工程において無駄がないのです。

これは、森氏が1961年度の「第1回グッドデザイン大賞」を受けた
「G型しょうゆさし」の開発概念と同じ。
このように氏のものづくりへの姿勢は
現在も波佐見地区の職人に受け継がれていました。
「G型しょうゆさし」が今も変わらず私たちの食卓で使われているように、
「白磁歯ブラシスタンド」はじめ、波佐見地区で新たに開発されるものも、
未来へ残るロングライフデザインとして作られていくのだと思います。
体験できる、酒造
福岡県西南部に位置する糸島市。
「おいしい甘酒を造る酒蔵がある」
という噂を耳にしました。
訪れたのは、「白糸酒造」。

早速お目当ての甘酒を試飲させていただくと…

これまでに飲んだことのないような
すっきりとした味わいです。
また、見た目にも分かるように、お米の粒が残っているのが印象的。
「うちのは米麹と水しか使ってないからね」
とっても親しみやすい社長が、そう教えてくださいました。

甘酒といえば、以前秋田で作り方を教えていただきましたが、
その際には確かに、炊いたお米にお湯と米麹を加えていました。
お米を入れていないので、サラッとした口当たりなのですね。
白糸酒造では、昔から蔵びらきの際に
お客様に甘酒を出していましたが、
「販売してほしい」という要望が多く、15年ほど前から商品化したそう。
話を伺っていると、「これも飲んでみてください」
と、奥様が別の飲み物を特別に出してくださいました。

飲んでみると、いちごの酸味とお米の甘さがドッキングした味。
ピンク色のかわいらしい飲み物の正体は、
"甘酒スムージー"でした。
「甘酒は本当に体にいいので、毎日飲んでもらいたいものなんですが、
やっぱり毎日同じ味だと飽きるでしょ?
だからうちでは、フルーツを加えて飲んだりしています」
白糸酒造は、安政2年(1855年)創業の老舗。
全国で唯一、昔ながらの「ハネ木搾り」を守り続けている酒造でした。

ハネ木搾りとは、長さ約8メートルの木の端に
合計1.2トンの石をロープでつり下げ、てこの原理で重みをかけて、
2日間かけてじっくりお酒を搾り出していくのです。
生産量は限られるそうですが、機械搾りに比べて圧力が弱いので、
雑味成分が少ないまろやかな味に仕上がるんだとか。
また、白糸酒造の酒蔵は、酒米の王者ともいわれる
山田錦の田んぼに囲まれています。

収穫前の稲は、キュートな案山子(かかし)たちによって
見守られていました。
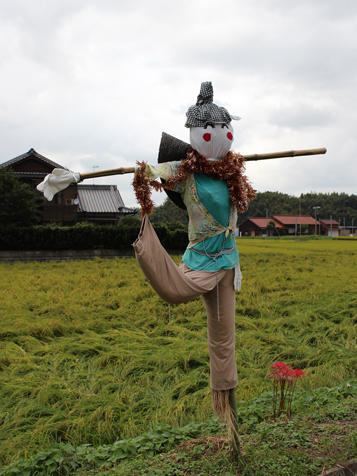
「これはハネ木塾のみんなで作ったんですよ」
ハネ木塾は、白糸酒造が運営する会員制のお酒塾で、
田植え・案山子作り・稲刈り・酒の仕込みから瓶詰めまで、
1年を通じてお酒造りの工程を体験できるのだそう。
最後にオリジナルラベルを作って貼ったら、
自分だけの1本の出来上がり。

○○体験ができる、というのはよく聞きますが、
1年を通して一般の人がものづくりにかかわれるというのは
これまで聞いたことがありませんでした。
地域の人を巻き込み、ともに歩んで来た白糸酒造。
それでも、「もっと地域とかかわっていきたい」と社長はおっしゃいます。
「糸島には最近若い人も増えてきているけど、
この長糸地区は高齢化が進んでいて。
地域のみんなが興奮するようなイベントを仕掛けたいですね。
例えば、滝の上から流す、流しそうめんとかね(笑)」
「COCCIO」
「民陶」ってご存じですか?
毎日の生活のために作られた実用的な雑器をさす言葉です。
大陸から有田へと渡った陶工の技術が、やがて日本各地へと伝わり、
地域ごとに食を受ける器を作る陶工たちが活躍していきました。
現在でも、訪れる先々で各地に根ざした焼物に出会ってきたのは、
こうした民陶づくりがあったからです。
ただ、戦後の急速な食文化の変化と、海外からの安い食器の流入によって、
日本の焼物はたちまち厳しい環境にさらされました。
そんな状況下でも、福岡県東峰村には、いまだに50軒ほどの窯元が残っています。
彼らが作るのは、「小石原焼(こいしわらやき)」です。

1682年に、伊万里から招かれた陶工が窯場を開いたのが始まりといわれ、
陶芸としては初めて、経済経産省の伝統工芸品の指定を受けました。
刷毛目(はけめ)、飛び鉋(とびかんな)、櫛描き(くしがき)
などの模様が特色で、後にその技法は、以前、大分で取材に訪れた、
小鹿田焼(おんたやき)に伝わったといいます。
小石原の陶工たちは、ろくろを自在に操って、
形のそろった食器を大量に生産する高い技術を持っています。
また、卸しとしての道を歩まず、
直販スタイルを続け、顧客からの要望に柔軟に対応してきたことから、
使いやすく手頃な価格の、手づくりの日用食器が生み出されてきたのです。
そんな小石原焼の持つ高い技術を活かしながら、
現代の生活に寄り添う新たな食器を生み出そうとするプロジェクトが、
2007年より始まっていました。
「COCCIO(コッチョ)」

小石原焼の3つの窯元と、
デザイナー兼ディレクターの城谷耕生さん、
そして、九州大学の池田研究室が関わり、
小石原焼の本質を探究し、今と未来のための食器をデザインする挑戦です。
イタリア語で「普段使いの器」を意味するその言葉には、
伝統工芸を守るだけでなく、今と未来の食生活に合わせた食器を開発する、
というメッセージが込められているようです。
COCCIOプロジェクトは、まず、
現代の食生活を徹底的に見つめ直すことから始まります。
九州大学の池田研究室が中心となって、
「食事とは何か?」「デザートとは?」「コーヒーとは?」など、
その由来まで徹底的に調べ上げ、ノートにまとめていきました。

その名も「轆轤(ろくろ)とノート」。
ろくろで器を作るのと同じペースで、ノートを作っていこうという、
とてつもない情報量のリサーチノートです。
こうした様々な調査を行うなかで、
小石原焼のエッセンスを以下の3つに抽出。
※小石原で採れた土を使うこと
※自然の釉薬を使うこと
※ろくろを使って生産すること
作り手の一人、カネハ窯の陶工・熊谷さんは、
COCCIOの制作についてこう語ります。
「飛び鉋や刷毛目の模様のないものを小石原焼と呼んでいいのかって、
はじめの頃は周りからよく言われました。
ただ、COCCIOは今と未来のための食器づくり。
小石原焼とは何なのか? ボウルと小鉢の違いは何?
と、一つひとつ概念を点検していきました」

こうして、これまでの和食器づくりの概念から脱却し、
現代の食生活に合った、
手づくりによる洋食器が作られていきました。
一つ大きな特徴は、高台が広く平らであること。

これは、器を手で持ちながら箸で食べる和食に対し、
洋食は基本、器は持たずにナイフとフォークで食べるという、
食生活の根本的な違いを反映させたものでした。
そのためには、安定感のある平らなお皿が必要だったのです。
さらに、ディレクターの城谷さんは、
「モノがあふれている時代。ただ、カッコいいだけじゃ駄目。
食生活の社会問題を解決できるような食器を作りたかった」
と語ります。

一人で食卓の前に座ることが多くなった現代、
家族や友人と一緒に食卓を囲む時間を、
もっと日常的に楽しんでもらえるようにと、
COCCIOには「シェアの食器」という概念が加わります。
こうして生み出されたのが、こちらの大皿。

大皿に盛った料理を取り分け、
周りを気遣いながら会話がはずむ食事の時間を想像して作られました。

他にも、こんなコーヒーカップたちも。

通常よりも小さめのデミタスカップは、
コーヒーがなくなったら、すぐに
「温かいコーヒーをもう一杯いかが?」
という声が聞こえてくるように、イメージされています。

九州大学の池田美奈子教授は、このCOCCIOについて、
こんな想いを話しました。
「人の生活に合わせてモノを作るのではなく、モノが人の生活を変える、
ということもできるのではないでしょうか」
COCCIOには、こうした様々な想い、研究の成果が
合わさっていました。

現代の食生活のために作られた日常的な食器。
これぞ「現代の民陶」と言えるのではないでしょうか。

こちらのCOCCIOシリーズは、
MUJIキャナルシティ博多![]() で、10月28日まで展示販売されています。
で、10月28日まで展示販売されています。
旬を味わうドレッシング
「北九州にまつわる調味料を作りたいと思ったんです」
そう語るのは、北九州市で地元野菜を使ったドレッシングを手掛ける、
(株)ごとう醤油の五嶋隆二社長。

キッカケは、数年前に東京の物産展に出店した時のことでした。
もともとポン酢など、無添加の調味料づくりを行っており、
味に自信のあった五嶋社長は、東京でも売れるだろうと高をくくっていたそう。
しかし、結果はほとんど売れませんでした。
また、普段地元では、1ℓや1.5ℓの大きな商品が売れていて、
東京向けに360mℓを用意していったものの、
それでも「重たい」と嫌厭されてしまったのです。
この経験から五嶋社長は、
「顧客のニーズに合わせた商品づくりが必要」
ということを学びました。
そして、生まれたのが"職人の技ドレッシング"
地元の農家さんが作った野菜を、
自分の目と舌で確かめてから仕入れ、
旬の野菜をふんだんに使った贅沢な調味料を開発。
"若松トマト""合馬たけのこ""金時人参""大葉春菊"
…どれも地元でしか採れない野菜です。
瓶の大きさも200mℓと100mℓを用意しました。
100mℓの小さな瓶は、持ち帰るのに重くない
というのももちろんありますが、
添加物を加えていないので、
おいしいうちに味わってもらい、旬の味を次々に味わってもらいたい
という社長の想いの表れでもあります。
ちなみに、大人気の「原木椎茸の和風ドレッシング」は
昨日のブログでご紹介した、井上さんの椎茸を使用しているそう。

具材が目に見えるほど、ぎっしり詰まっていて、
購入者からは、「これで採る野菜を1品減らせる」と評判です。
また、これら調味料を通じて、購入者が、
北九州地域の特産品を知ることにもつながっているようです。
今では、ごとう醤油のドレッシングの噂を聞きつけて、
野菜の生産者さんが自ら相談に来るようになったといいます。
さらに、ドレッシングに加えて
地元の食材や料理に合う調味料も展開。
地元の漁師さんたちと一緒に、ワタリガニ用のお酢を作りました。
オス蟹とメス蟹は採れる時期や漁の仕方が異なり、もちろん味も違います。
それならば、それぞれのカニに合うお酢も違うはずと、
こんな商品が出来上がったそう。
その名も「雄酢」と「雌酢」。

ユーモアたっぷりの一品ですね。
「これからも細かいお客様のニーズに合わせた商品づくりをしたい」
と話す五嶋社長。
これからどんな商品が生まれるのでしょうか!?
※ごとう醤油さんの一部商品は、
MUJIキャナルシティ博多![]() リニューアル1周年記念企画中の
リニューアル1周年記念企画中の
同店でも購入可能です。
クールな農家
北九州市で原木しいたけを栽培する、
小倉印株式会社の井上さんを訪ねました。
山の入り口で待ち合わせをしていると、そこで待っていたのは、
勝手にイメージしていた農家のおじさんとは違う、
ファッション雑誌に載っていそうな、お洒落な格好の方でした。

「別に作業用の服を着なきゃいけないって決まりはないですからね。
僕はいつもこんな格好で作業してますよ」
もともと家具職人だった井上さんですが、
農家に転身したのは4年ほど前のことだそう。
井上さんは主に店舗用家具を作っていました。
それらは5~10年で入れ替えがあり、
さらに使用していた木材は一部石油化学製品だったことから、
自分の仕事は環境に優しくないと疑問を持ち始めたそう。
そして、実家の畑を使った農業と、
原木しいたけの栽培の道へと入っていきました。
しいたけ栽培には、天然の木を用いる「原木栽培」と、
菌床(オガクズなどの木質基材に米糠などの栄養源を混ぜた人工の培地)
で育てる「菌床栽培」の2種類があります。
井上さんは前者の原木栽培を手掛けていますが、
それは流通しているしいたけのうち、1~2割と少ないそうです。
というのも、原木栽培の方が重労働なのです。
種菌を植え付けたほだ木を定期的にひっくり返す作業が必要なのですが、
ほだ木を持ち上げようとしてみると、確かに重い…。

しいたけが発生するには、2~3年の月日が必要です。
また、ほだ木を水に浸けたり、
刺激を与えることによって発生しやすくなるようなのですが、
井上さんはすべて自然に任せているそう。
「量は採れなくても、その方がしっかりした味になる気がするんです」

井上さんの育てたしいたけは、
意外なところで手に入れることができます。

「なば in サンカフェ」
今年3月にOPENしたアンテナショップです。
店内には、先ほどのしいたけや畑で採れた野菜、
また井上さんが仕入れた加工品などが並んでいました。

「農業はまだまだ改善する余地がたくさんあると思うんです。
市場で高値がつく野菜は見た目だけで、味は全く無視されているのが現状で、
すると、農家は野菜の形をそろえることに注力する。
努力する部分が間違っているんです。
農家は自分で売る努力をしていない」
井上さんの1日のスケジュールは、
朝から畑作業と山仕事、
午後に仕入れに行き、15~19時頃までお店に立つ。
お店の営業時間は短いですが、その分お客さんは
本当に新鮮な野菜を手に入れることができます。
また、お買い物の途中にちょっと一息、
コーヒーを飲みながら、店主の井上さんご夫妻と語らうこともできます。

最後に井上さんに今後について聞いてみました。
「僕は自分が好きなことじゃないと続けられないんで。
農業はこうしなくちゃいけないという決まりはない。
子どもに将来の夢を聞いた時に"農家"っていうふうに
憧れられるような職業に、農家をしたいんですよね!」
すっかりクールな農家・井上さんに魅了されたとともに、
井上さんの農業に対する改革が、
子どもたちへ魅力ある職業として映ることを願わずにはいられません。
農業の固定概念を覆される出会いとなりました。
食器が持つ役割
数ある有田焼のなかでも、
ふと目に留まった食器がありました。
持ち手が大きく、つかみやすいマグカップ。

さらには、
お皿の縁が盛り上がっていて、すくいやすそうなお皿。
その名も「すくい易い器」シリーズ、
そう、ユニバーサルデザインの食器です。
こちらを手がけるのは「しん窯」。

1830年、有田の地で鍋島藩の藩窯として創業した窯元です。
「そこに目を付けられるとは、お目が高い!
この器がしん窯の原点ともいえる作品なんですよ」

しん窯の8代目、梶原茂弘さんが、
くったくのない笑顔で迎えてくれました。
梶原さんがこの「すくい易い器」を手がけ始めたのは、
今からなんと37年前! 1975年のことでした。
きっかけは、ハンディキャップのある方のための食器づくりに意欲を燃やす、
「でく工房」という木工制作の青年たちとの出会いでした。
それまで料亭などで使われる営業用食器を作っていたしん窯も、
当時、何かを求めていた、と梶原さんは思い返します。
「社会的に意義のあることですから」
といって引き受けた梶原さんでしたが、
そこから試行錯誤の毎日だったそうです。
施策と改良を重ねること約3年、
「すくい易い器」の原型が誕生。

ハンディキャップのある方の使いやすさも考慮に入れた磁器食器の開発は
当時、初めてのことでした。
この食器によって、
介添えなしで食べることができるようになった子どももいたそうです。
「ハンディキャップのある方にも使いやすいと言うことは、
我々、健常者にとってはもっと使いやすいということ。
つまり、我々が一番使いやすいものはなんだということを、
自然に追求していたんですね」
梶原さんは、この食器づくりを通じて、
食器が持つ本来の役割を教えられたといいます。
そして、その翌年、今ではしん窯の柱の商品ともいえる
「青花(せいか)」シリーズが誕生することにつながるのです。

生地は生地屋さんが、と分業制の進む有田において、
できる限りの工程を自社で賄うしん窯の食器からは、
一つひとつ丁寧に作り上げられた温かみが感じられます。
そして、何といっても青花の特徴は、
この呉須(藍色に出る顔料)で描かれた"異人"模様です。

この異人を描いたのは、
梶原さんとともに青花シリーズを立ち上げた職人、藤井さん。

佐賀から目と鼻の先の出島へ訪れた異人(オランダ人)を
イメージして描いたようです。
有田焼というと和食器を連想しますが、外国を思わせる絵柄ゆえに、
この異人シリーズは和洋中、どんな料理にも合うから驚きです。

こうした料理を盛った見せ方をするようになったのは、
梶原さんの甥、藤山雷太さんでした。

「食器は、あくまでも料理の引き立て役。料理が盛られて完成なので。
母が作った料理が映えることからヒントを得ました」
そう話す藤山さんは、
しん窯で作られる食器をショップやネットを通じて販売しながら、
有田焼の見せ方に創意工夫を凝らします。
全国の登録店などを訪問することで与えられる仮想通貨「プラ」を使い、
携帯電話内で自分の町を作り上げるゲーム、
『コロニーな生活☆PLUS』(コロプラ)とコラボレーションしたのも、
有田焼の窯元としてはもちろん、
全国のものづくり現場の中でも初めてのことだったそうです。
実際に、このゲームを通じて、
有田焼「しん窯」に興味を抱き、訪れた人も数多くいるんだとか。
伝統産業を、現代の見せ方で紹介していく。
ここにも一つの伝統産業のヒントがありました。
最後に、梶原さんに、焼物の原点を教えていただきました。

「自然の織り成す5つの要素、地・水・火・風・空。
実は、焼物はこのすべてに関係しているんですよ。
土や陶石といった『地』を使い、『水』を加える、
それを『風』で乾かして、『火』で焼く。
そして『空』は、空間を作るわけですね。
つまり、焼物は自然の恩恵そのものなのです」
梶原さんの言葉で、
思わず納得し、首を大きく縦にふっている私たちがいました。
有田焼の挑戦
「日本の伝統産業は変わらなくてはいけない」

1647年(正保4年)より有田の地で焼物を手がける、
(株)百田陶園の社長、百田憲由さんはそう切り出しました。
「1616年から磁器の生産が始まった有田焼は、
日本で最初に栄えた産業といっても過言ではありません。
今一度、有田焼が良かった時代に戻るためには、変わるしかない」
百田さんの言葉からは、並々ならぬ覚悟が感じられました。
もともと鍋島藩の御用達の窯元として、
窯焼きの仕事に従事していた百田陶園。
今は有田焼の総合商社として、
お客様に喜ばれる商品の提供に尽力されてきましたが、
リーマンショック以降、その業績にも陰りが見えてきたそうです。
「それまではなんとか新商品を企画すれば売れていました。
ただ、リーマンショック以降は何をやっても駄目。参りましたね」
そんな時、百田さんのもとへ、一件のオファーが入ります。
それは今年5月、東京・丸の内にオープンした、
パレスホテル東京のホテルアーケードへの出店でした。
「正直、悩みました。このオファーを断れば、他が入ってしまう。
ただ、やるなら徹底的にやらなくては、と」
百田さんは腹をくくります。
そして、コンタクトを取ったのが、
プロダクト・空間デザイナー、柳原照弘さんでした。
ショップの空間のみならず、プロダクトもゼロから作り上げたいという、
百田さんの想いの表れでした。
はじめは断るつもりだったという柳原さんも、
百田さんの想いに共感。
ここから有田焼・百田陶園の挑戦が始まります。
柳原さんは有田の地まで足を運び、
有田焼の現状を一通り把握し、こうつぶやいたそうです。
「有田は先人に飯を食わせてもらっていますね」
当時のことを百田さんはこう振り返ります。
「さすがにその時は悔しかったですね(笑)
ただ、その後に発した"50年後にも美術館に置かれるものを創りましょう"
のひと言で、気持ちは固まりました」
明確な目標を見据え、改革に向けて歩み始めた百田陶園は、
柳原さんの紹介で、今やminiクーパーのデザインも手掛ける
オランダ人デザイナーのショルテン&パーイングスとも手を組みます。
日本のマーケットを見据えたとしても、
これだけ食生活が多国籍化してきている昨今、
海外の食生活を熟知したうえでの感性が必要と考えたためです。
ここから先、血のにじむような努力の毎日が始まります。
原料、成型、釉薬…、
焼物の基本のすべてを見直すべく、
有田焼の各工程のスペシャリストを招聘するも、
なかなか理解してもらえません。
「新しいものを創るということは、過去の概念を捨てるということ」
職人にそう言い聞かせながら、
百田さんは自分自身を鼓舞していたそうです。
こうして血のにじむような努力の結果生まれたのが、
「1616 / Arita Japan」。

今までにない有田焼の誕生です。
柳原照弘さんデザインのシリーズ1616 / TY "Standard"では、
昔の有田焼をモチーフにしたライトグレーの器が誕生。


釉薬を使わずに焼きしめ、最後に研磨の工程を加えることで、
独特の質感が実現されています。
また、ショルテン&パーイングスデザインの
1616 / S&B "Colour Porcelain"では、
淡く、はかない色合いの器が生まれました。


驚かされたのが、
両シリーズともに、高台が付いていないこと。

高台には、焼成による収縮やゆがみのリスクヘッジ
の意味合いもあるようですが、これをなくすというのは、
それだけ難易度が高くなることを意味するそうです。
努力を重ねたという薄さも、上品さを醸し出しています。

さらに驚かされたのが、その価格帯。
これだけ手がこんでいながら、
なんと500円からラインナップが充実しており、
一般的にも求めやすい値段になっているんです。
「いいね、で終わっては意味がないと思っているので。
日常使いしてもらえる器のために頑張りました」
百田さんは、その価格帯を実現したことに胸を張ります。
事実、今年4月に出展したイタリアの見本市、
ミラノ・サローネではNY Timesを筆頭に各社が大絶賛。
今では、海外の代理店とも契約を結び、
着実に海外展開の一歩を歩み始めています。
「このシリーズで、かつて世界を席巻した有田焼を、
今一度、世界に見せつけたい」

「正直、内心はまだ不安だらけですけどね(笑)」
と照れながら話す百田さんには、
有田焼の未来が託されているようにすら感じました。
きっと50年後、その先も世界中の家庭で
有田焼が使われているのではないでしょうか?
海の恵み
天草(あまくさ)にイルカの棲む島があると聞いて、
行ってきました!

天草下島の北端にある「通詞島(つうじしま)」は、
昔は瀬戸の狭い所を手漕ぎの渡し舟が行き来をする島だったそうですが、
現在は、橋を渡れば簡単に渡ることのできる場所です。
また、船で10分ほど行った通詞島の沖合いには
エサとなる魚が豊富なこともあり、
昔から野生のイルカが群れることで知られています。
99%の確率でイルカに会えるとは聞いていましたが、
こんなに間近に、こんなにたくさんのイルカに会えるとは!
正直、期待以上で驚いたほどでした。

そして、このイルカの棲む美しい海の目の前で、
私たち人間に欠かせない塩を作る人たちがいました。
「ソルト・ファーム塩工房」の福田さん親子。
2人ともこんがりと焼けた肌がよく似合います。
この場所は、日照時間が長く、風が程よく吹き、
そして何よりも海水がきれいという条件がそろっており、
塩づくりに適しているんだそうです。
もともと創業者の長岡さんが
自然塩を作る場所を求めて全国を歩き回り、
最後に行き着いた場所だったといいます。
塩づくりといえば、以前石川県の能登半島で
「揚げ浜式製塩法」という伝統的な手法を取材しましたが、
ここではどのように作られているのでしょうか?
まず、目の前の海から海水を汲み上げ、
太陽と風の力だけで約20日間かけて
塩分濃度3%の海水を18%の濃縮海水にします。
その後の製塩法は、薪で焚く「釜焚き塩」と、

ハウスで天日干しして作る「天日塩」の2通り。

釜で焚く場合、薪をくべながら5日間かけて海水を煮詰め、
水分を蒸発させて結晶化させます。
天日干しの場合は、真夏は70℃近くになるハウスの中で3~4日、
冬は1ヵ月弱蒸発させ、結晶化させるそう。
海水に結晶が浮き上がってきている状態を見ることができました。

ちなみに、私たちがハウスに入った時の室温は50℃で、
30℃近くある外に出たら涼しく感じたくらいです。
釜焚きも天日干しも、この時期は暑さとの戦いです。
また、どちらも雨が降ったり、南風が吹いたりする日は
作業ができないそうです。
私たちが訪れたこの日は、ちょうど釜揚げの作業がありました。
表面の結晶を集めて、釜から樽に移すのですが
これがかなりの重労働。
作業工程の中で一番大変だと、息を切らせながら話してくれました。

この後、にがり成分を程よく取り除いて熟成させ、
さらに天日干ししてようやく出来上がり。
「化学で作る塩化ナトリウム100%に近い食塩に比べ、
海から作る塩には、ミネラルが多く含まれています。
このミネラル量を調整することで、味が変わってくるんです。
その副産物のにがりにも当然ミネラルはたっぷり入っているんですよ」
ソルト・ファームでは"できるだけ甘い塩"
を作るように心がけているそうです。
この最後の調整こそが、職人の腕によるものなのかもしれませんね。
確かに、最後に天日干しする前の塩と、天日干しした後の塩を
舐め比べてみましたが、
後者はなめらかなのに対して、前者は海水が口に入った時のような
しょっぱさを感じました。
こうして完全手作業で根気よく作られた塩、

これはまさに海の恵み、さらには地球の恵みといえます。
なぜなら、美しい海、吹き渡る風、灼熱の太陽…
古来あるがままの自然環境こそが、最高の原料だからです。
この通詞島の海が、イルカにとっても、塩工房にとっても
いつまでも変わらない場所であり続けますように。
ジャパニーズネロリ
「ネロリ」ってご存じですか?
ネロリとは、ビターオレンジの花から
水蒸気蒸留でフラワーウォーターを作る際に、
副産物として得られるエッセンシャルオイル(精油)のこと。
蒸留水に自然乳化したネロリ成分には、
フローラルな香りに加えて抗酸化作用や抗菌作用があるため、
昔から北アフリカ(モロッコやチュニジアなど)の各家庭では、
蒸留水を化粧水のように使用したり、
傷薬や胃薬、また料理の香りづけなどに、幅広く利用されてきました。
また、ネロリはヨーロッパに輸出され、
高級化粧品の原料としてとても人気だそうです。
そんなネロリを日本で生産する方がいると聞いて、訪ねました。
熊本県水俣市、その地を訪れてみると、
とてもきれいな海が広がっているのを目にしました。

もともと海の幸・山の幸に恵まれた土地で、
人々は半農半漁で生活をしていましたが、
水俣病以降、禁漁となり、農業のみになっていたそうです。
そして、この時期にスタートしたのが甘夏みかんの栽培です。

水俣の人々は、自分たちが化学物質の怖さを知っているからこそ、
周囲から無理だと言われていた甘夏みかんの無農薬栽培に
取り組みました。

自然農法で甘夏みかんやグレープフルーツを栽培している
吉田さんにお話を伺うと、
「みかんの生育を邪魔しなければ草は生えていてもいいと思うんです」
と教えてくださいました。

夏場は土が乾燥しないようにあえて草を
長めに刈ったりするそうです。
さて、ネロリの話に戻りますが、
この無農薬甘夏みかんの花に目をつけたのが、
ネローラ花香房代表の森田さんでした。

国際協力団体で、アフリカ・アジア地域の支援に
携わってきた森田さんは、
北アフリカでネロリが作られる現場を見ていました。
そこで、ビターオレンジの花の代わりに、甘夏みかんの花を使い、
ネロリを作ることを思いついたのです。

甘夏みかんは柑橘類の中でも特に花つきがよく、
集荷する果実の何十倍もの花が咲き、
果実の収穫分を残しても、多くの花が収穫できるんだそう。
森田さんは、日本国内で他にネロリの生産を行っている所が
ないことを知り、蒸留器を輸入して、自ら生産を試みました。
10年ほど試作を繰り返し、3年前から製品化に成功。
試作期間が10年というのに驚きましたが、理由を聞いて納得しました。
花の収穫ができるのは年1回だけ、
つまり、試作を行えるのも年に1回のみだったのです。
現在は、摘みたてのお花をすぐに冷凍保存すれば、
香りも成分も失わずに済むことが分かり、
通年での原料確保が可能になっています。
こうして出来上がった国内初オーガニックネロリ化粧品がこちら。

甘夏みかんの爽やかな香りがリラックス効果と
お肌に潤いを与えてくれます。
これまでただ散っていっていた花が
こうして人々に喜ばれる商品に生まれ変わったのです。
また、森田さんは毎年、甘夏みかんの花摘みツアーを
企画・運営しているそうです。
「どうしても水俣には、以前の公害のイメージがあるかと思いますが、
今の水俣は、海も空もみかん畑も、光あふれる本当にきれいなところです。
過去の教訓に基づいて、環境都市に生まれ変わった
新しい水俣を見てほしいという想いで始めました」
ジャパニーズネロリには、香りと効用だけでなく、
こうした森田さんの水俣に対する想い、
そして水俣で無農薬栽培を続けてきた農家の人々の想いが
たくさん詰まっています。
龍門司焼
鹿児島県内には窯元がとても多い印象を受けました。
鹿児島県陶業協同組合のHPに載っているだけでも、59窯元あります。
県内で焼かれる「薩摩焼」は、約400年前、
豊臣秀吉の朝鮮出兵に同行した薩摩藩主・島津義弘公が
陶工を薩摩に連れ帰ったことに始まります。
その後、発展と退廃を繰り返し、今では薩摩焼の系譜として
「苗代川(なえしろがわ)系」「竪野(かたの)系」「龍門司(りゅうもんじ)系」
と分かれているようです。
また、薩摩焼は「白もん」と呼ばれる白薩摩と、
「黒もん」と呼ばれる黒薩摩の2つに大別できます。
白薩摩は乳白色のあたたかみのある生地に、
金、赤、緑、紫、黄などで豪華絢爛な文様を施した気品のある逸品で、
藩主御用達として発展してきました。
幕末のパリ万博にも出品され、その高い芸術性が絶賛されたことをきっかけに
多くの作品が海外に輸出され、「SATSUMA」の名が欧米に知られるようにもなりました。
それに対し、もう一方の黒薩摩は、鉄分含有量が多い土を用いており、
素朴で重厚な面持ちが特徴で、
こちらは、庶民の生活道具として親しまれてきました。
今回は、姶良(あいら)市にある、黒薩摩のひとつ、
「龍門司焼」の窯元を訪ねました。

敷地内に入ると、ズラリと外に並べられた、黒い器たちが
私たちを迎えてくれました。

これらは「黒ヂョカ」と呼ばれる焼酎用の土瓶で、
焼酎大好きな薩摩人に、昔も今も人気のものだそう。
脚がついていて、土間や畑など場所を選ばずに
使えるようになっています。
また、黒ヂョカで温めた焼酎を移して、
宴席などで使われるのが「からから」と呼ばれるもの。

持ちやすい丈夫な首に、注ぎやすくこぼれにくい注ぎ口など、
1日の疲れを癒やす晩酌のお供にふさわしい器です。
龍門司焼は、陶土、釉薬の原料など
すべてを地元でまかなっているそうですが、
なかでも自信を持っているのが「化粧土」だといいます。
有色素地で焼き物を作る際、釉薬の発色を美しくするために、
素地表面に白色の陶土(化粧土)をかけるのです。

もともと赤みの強い陶土の色が、
このようにやさしい白い色合いに変化します。
また、龍門司焼はその独特な装飾が魅力的。
窯に併設されたお店には、目移りしてしまうほど、
たくさんの多種多様な器が並んでいました。


なかでも、白化粧した素地に飴釉と緑釉を掛け流す
「三彩流し」は龍門司焼の代表的な技法で、
美しく明るいやわらかな印象を与えてくれます。

さらに、釉薬がサメ皮のように細かく粒立っている「鮫肌」や

立体的に浮き上がったうろこ状の文様が特徴の「蛇蝎(だかつ)」は
とてもインパクトがあり、目を惹きます。

各地で出会う焼き物。
その地で採れる土を使って、昔から伝わる手法で作られる焼き物は、
自然界にある土のホッとする温かみと手のぬくもりが感じられる、
世界にひとつだけの器でした。
飫肥杉とともに生きる
宮崎県南部に位置する、日南市(にちなんし)。
市の面積の約78パーセントを森林が覆い、
その多くは飫肥杉(おびすぎ)に占められています。

江戸時代に飫肥藩によって植えられたそれらの木は、
まるで運動会に整列する園児のようにズラリと並んでいました。
なかでも、日南市北郷町(きたごうちょう)の森林は、
全国で48ヵ所ある「森林セラピー基地」に認定されています。
「森林セラピー基地」とは、
森林浴によるリラックス効果があり、血圧低下や身体の免疫効果向上など
心身を癒やす効果が高いことが科学的に実証されている地域のこと。
この基地を活用して、北郷町では
「森林ノルディックウォーキング」や「森林ヨーガ」などの
セラピープログラムを実施しています。
このプログラムの企画・運営を行うのが、「NPO法人ごんはる」。
森林セラピーの他にも、地元にあるモノを活かしていこうと、
様々な商品開発および一部製造と販売までを一手に担っています。
スタッフの方が使っていたこのバッグも
彼らが手掛けた商品のひとつ。

すれ違ったら、おもわず二度見してしまうほど
異彩を放っていました!
実際、出張で県外に行くとよく声をかけられるんだそうです。
「木を身近で利用したい」という想いがキッカケで
飫肥杉を使った商品開発に及んだという姫野さん。

飫肥杉は、樹脂を多く含んでいるため水を吸収しにくく、
軽量で強度が高く、曲げにも強いことから
造船用として盛んに利用されていた過去もあり、
バッグにはもってこいの資材だったのです。
また、傷や汚れがついても磨けばまた元通りになり、
さらに杉の香りも楽しめるのが特徴です。

また、こちらのランプも、同じく飫肥杉を使ったもの。
地元住民と一緒に作り出したものだそうです。

灯りを点すと、うっすら木目が浮き上がり、
部屋の中でも、木のぬくもりを感じることができます。

「地元の人には、この杉が当たり前になってしまっているので、
むしろ地元以外の人や都会の人に、木の魅力を発信していきたいと思います」
そう話す姫野さんたちは今日も、飫肥杉と向かい合って生きています。
小鹿田焼
日田市内から車で20〜30分の山間にひとつの集落があります。

小鹿田(おんた)地区。

集落にある家は全部で14軒。
そのうち10軒が小鹿田焼(おんたやき)の窯元で、
そのすべてが開窯時から続く柳瀬家、黒木家、坂本家の子孫にあたるそう。
現地に着いて車を降りると、水のせせらぎとともに
重く、木の軋む轟音が耳にとび込んできました。
「ギーッ、ゴトン… ギーッ、ゴトン…」
音のする方を見に行くと、そこには水の力で動く杵のようなものが。

これは「唐臼(からうす)」といって、
臼を地面に埋めて、てこの原理で杵を動かす仕組み。
昔は人が足で杵を踏む「足踏み臼」が精米などに使われていたそうですが、
ここでは水流を受けて、陶土を粉砕するのに現役で使われています。
静かでゆったりとした時間が流れる空間に響きわたる、唐臼の音。
なんだか別世界に来たような気分にさせられます。
10窯のうちのひとつを訪ねました。

工房の中を覗くと、ちょうどろくろを回して成形中でした。


今から約300年前、福岡県朝倉郡小石原村にある
小石原焼(こいしわらやき)から分窯したと伝えられる小鹿田焼。
江戸中期、天領であった日田の代官により
日田の生活雑器の需要を賄うために興されましたが、
この地が選ばれたのは、何といっても、登り窯を作るのに適した斜面があったこと、
豊富な陶土や薪、そして水力の利用に便利な自然環境であったから、と考えられています。
使用している原土はもちろん昔も今も地元のもの。
小鹿田焼同業組合で山を所有しているのだそうです。

また、驚いたのが、現在も薪を使い、登り窯でのみ焼いているということ。
これまでいくつかの地域で窯元を訪れましたが、
登り窯は多くても年に1〜2回使用するかしないか。
それは、登り窯で焼く器を一定量準備することが難しいことと、
仕上がりの均一性が保証されないためでした。
では、なぜ小鹿田焼では登り窯を使うことができているのでしょうか?


小鹿田焼の窯元は開窯以来、その数が変わっていません。
というのも、一子相伝を守り、弟子を取らずに
伝統的技法を脈々と守り続けているのです。
つまり、登り窯を使うことも「できている」というより
「使うことを決めてやっている」というのが正しいのかもしれません。
登り窯の容量に合わせて、成形した器を作り込んでいくのです。
黙々と山の中で作られていた焼き物。
小鹿田の窯が一躍脚光を浴びるようになったのは、1931(昭和6)年。
民芸運動の創始者、柳宗悦氏がこの地を訪れたことが、キッカケでした。
『どんな窯でも多少の醜いものが交じるが、この窯ばかりは濁ったものを見かけない』
と驚いた柳氏は、後に「日田の皿山」という紀行文の中で、称賛しました。
さらには、1954(昭和29)年に日本の陶芸界に大きく名を残した
イギリスの陶芸家、バーナード・リーチも陶芸研究のために3週間滞在し、
小鹿田焼は日本はもとより、海外にまで広く知られるようになりました。
それまで半農半陶でやってきた窯元の人たちが
焼き物一本になったのは、割と最近のことだといいます。
さて、これまで見てきた焼き物は、その陶土や釉薬の色が特徴的でも
デザインはシンプルなものが多かったように思いますが、
小鹿田焼には美しい装飾が施されているものが多く目につきました。
ろくろを回転させながら、L字型の金具を当てて表面に刻みを入れていく
「飛び鉋(とびかんな)」や、

ろくろを回転させながら、化粧土を塗った刷毛を打ちつけていく
「打ち刷毛目(うちはけめ)」など、

手仕事の温かさが伝わってきます。
見かけは厚く、どっしりと重そうですが、
実際に持ってみるとそうでもありません。
原料の採取から、唐臼による土作り、蹴ろくろの成形、
そして薪窯による焼成まで、
正真正銘、最初から最後まで手作りの小鹿田焼。
作品に銘(作家名)を入れることを慎み、あくまでも日用品に徹する小鹿田焼は、
今日では雑貨店やデパートなど、あちこちで目にすることができます。
私たちのくらしにも取り入れやすく、
すぐに馴染んでいくのが小鹿田焼の魅力ではないでしょうか。
別府のいいものみつけた
大分県別府市。

市内各地で温泉が湧出し、源泉数は2800ヵ所以上。
日本の総源泉数の約10分の1を占めるんだそうです!

別府では、温泉に浸かるのはもちろんのこと、
温泉から噴出する蒸気熱を利用した「地獄蒸し料理」を
楽しめる場所もあります。

温泉地だからこそのアクティビティですね。
でも、この「地獄蒸し」は観光目的に作られたわけではなく、
昔から湯治目的で温泉に長期滞在している宿泊客が自炊に使っているものだそう。
別府は明治から昭和の初期にかけて、観光地として栄えました。
しかし、その後、観光客の数は伸び悩み、
新しい観光振興のあり方が課題となっていました。
そんななか、16年ほど前から民間と市が一緒になり
地域を見つめ直していく動きが始まりました。
今回私たちが取材したのは、2005年に発足し、
町とアートのつなぎ手として活動を続ける「BEPPU PROJECT」。
2009年に別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界![]() 」を実施し、
」を実施し、
現在は同フェスティバル2012の開催準備の真っ最中です。
他にも、中心市街地の活性化を目的に
空き家をリノベーションして、様々な取り組みがなされています。
駅のプラットフォームのように、多くの人が集い交流し、
別府のまちがいきいきとした活動の場となることを目指して作られた
8ヵ所の「platform」があり、そのうちの4スペースの運営を担っているそう。
例えば、築100年のこの長屋はplatform04。
別府の工芸品やアート作品を扱うセレクトショップとして営業しています。


店内にはおもわず手に取ってしまいたくなる、
洗練されたグッズの数々が並んでいました。
この「SELECT BEPPU」店主の宮川さんは、東京都出身。
学生時代に参加した都市デザインプロジェクトをきっかけに別府を訪れ、
大学卒業後、別府に移り住んだといいます。
「別府には面白い人がたくさんいて、
東京ではお金を払って会うようなアーティストさんが
ふらっとお店に来たりするんです」
興奮気味に話す彼女に勧められて、商品の制作現場を訪れました。
商店街の一角にある、platform07「別府竹細工職人工房」では
竹細工職人さんたちが実際に作業している様子を
目の前で見ることができました。

別府竹細工の歴史もやはり温泉とともに歩んできました。
湯治客が滞在中の自炊のために使用するザルなどの竹製生活用品から始まり、
その後お土産品としての市場が拡大し、地場産業として定着したのです。
別府市には全国で唯一の竹細工の訓練学校があり、
全国から竹細工を学びたい人が集まってきているそう。
大阪府出身の竹職人の清水さんもその一人。
大学卒業後、訓練学校で竹細工を学び、そのまま別府の町に住み着いています。

関西弁で冗談まじりにおしゃべりしながら
竹を1mmよりも薄くして、器用に編んでいきます。
話しているうちにいつの間にかこの通り、箸置きを作ってくれました。
まるでリボンを編むかのような早業でした。

もともと東南アジアを旅するうちに竹細工に興味を持ち、
竹細工職人になったという清水さんに
ちょっと意地悪な質問をしてみました。
"海外の竹細工と日本の竹細工の違いってなんでしょうか…?"
「海外にも竹細工の技術が高い人はたくさんいますよ。
王様に献上するモノとか作っていますから。
ただ彼らの作るモノは中国雑技団のように、超人芸というか…。
日本人の作るモノは美しいんです。
そのモノだけではなく、周りの空間も含めて美しくしている気がします」
なるほど。清水さんの言わんとすることが妙に腹に落ちました。
確かに、「SELECT BEPPU」に置かれていた竹細工の商品は
どれも使うシーンの想像を掻き立てられるモノばかりでした。

続いて、伺ったのは「別府つげ工芸」。

昭和5年に建てられた長屋を守り、昔も今もこの地で
つげの木を使った工芸品を作り続けています。
もともとは、3代目の現社長のおじいさんが
くし職人としてスタート。
印鑑や将棋の駒に主に使われるつげの木は、
非常に堅く、細かい細工が可能なんだそうです。
おじいさんが若い頃に作ったというこのブローチ、
その細かいデザインと艶が木材とは思えませんでした。

観光地として別府が賑わっていた頃には、
50人の職人をかかえ、細工品を作っていました。
しかし、お客様が増えれば増えるほど、粗製濫造になり、
ついにはつげの木ではない木材を使ったりもしていたんだとか。
「今は原点を見直している時期なんです。
いいモノを作って、後継者を育てたい。
商品はマネできても、この場所での歴史はマネできないですから」
そう話す安藤社長は、時代に合わせた商品づくりにも余念がありません。
くしの需要が減っていくなか、つげを使ったブラシも作るようになりました。

つげの堅さとブラシの形状が頭皮にマッサージ効果を与え、
またあらかじめブラシに染み込ませてあるツバキ油が
髪に艶を出し、まとまりやすくしてくれるんだそう。
もちろんそれらはすべて手づくりです。

折りたたみブラシのちょうつがい部分にも
つげの木を利用しているのには驚きました。
工房には近所の方たちが集まってきて作業されていました。
「これをきちんとした産業として育てていきたいんです。
職人さんが食べられなくて、商品ができるわけはないからね」
社長の力強いお言葉に、つげ工芸のさらなる可能性を感じながら
工房を後にしました。
ちなみに、「SELECT BEPPU」に置かれていたこれらの商品が
9月末から福岡のMUJIキャナルシティ博多![]() で販売されるそうです!
で販売されるそうです!
※詳細はこちら![]()
実物を手に取って見られるチャンスです♪
別府のいいもの、みつけてみませんか?
天領、日田のものづくり
日田の市街地に、古民家を利用した形の、
ひと際洗練されたショップがありました。

Areas(エリアス)。
既にそこから地域密着型を感じるネーミングです。
店内は、日田の家具・雑貨を中心に、
国内外よりセレクトされたグッズであふれていました。

一品一品が何か語りかけてくるような、
そんな雰囲気すら感じます。
ショップを運営するのは(株)hi-countの仙崎さん。

大学卒業後、デザインをする仕事をしたいと、地元の北九州を離れ、
恩師に薦められた日田の家具メーカーへと就職。
かつて幕府の天領として治められていた
日田のものづくりの魅力の虜になった仙崎さんは、
2006年、日田でデザイナーとして独立します。
その後、日田の職人たちと、家具や小物を創作していき、
2009年、念願のショップをオープンさせました。
ゆえに、ショップで扱うものは、
すべて想いを込めて作られたものばかり。
各種家具をはじめ、

日田産の杉を使った「杉玉ペンダント」(ライト)や、

同じく日田産の檜を使ったアロマの香る
「てる坊のおにいちゃん」まで。

「日田には家具から木工細工、畳、焼物…と、
ここまで職人がいる町も珍しいんじゃないですかね。
彼らと日田産の素材を使ったものづくりをすれば、
自ずとそれが個性・ブランドにつながっていくと思います」
仙崎さんがこう考えるようになったのは、
北欧家具に出会ってからだったといいます。
寒い北欧で、家の中を快適な空間にするために追求された結果が、
世界で人気を誇る北欧家具なんだとか。
「北欧家具はあくまでも一例ですが、
その土地の風土や歴史に必ずものづくりのルーツがあるわけで、
各地でこうした動きが活発化していけば、
各地の個性が表れたものづくりができると思うんです」
そう話す仙崎さんの店内には、約300年続く窯元、
小鹿田焼とのコラボ商品もありました。

これぞまさに、ここでしか作れない商品の一例です。
なかには、こんなに器用な商品もありました。

ステンレス製の指輪のなかに、曲げ木が施されているんです。
これを作るのも、日田市内に工房を構える「ウッドクラフト かづ」さん。
特別に工房へお邪魔すると、そこには
良いものづくりに対する飽くなき探求心を持った職人たちの姿がありました。

どれも寸分のズレも許さない丁寧なものづくり。

また、ここは他社が面倒と感じる曲げ木にも積極的に取り組み、
今や卓越した木を曲げる技術を習得しています。

代表の宮原さんいわく、管理せずとも
職人たちは自らの意思で追求・改善を求めるようです。
「この、より良いものづくりに対する姿勢こそが、
日本と他国とのものづくりの違いではないかと感じます」
最後に、仙崎さんはこう話してくれました。

「伝統は守るものではなく、進化するもの。
日田の伝統技術を活かしながら、
現代の生活様式に合わせたものづくりをしていきたいですね」
その力強い視線の先には、
日田のものづくりの未来が見えているような感じさえ受けました。
ここにもまた、その地に根ざして生きる人たちの姿がありました。
土の魅力
地元に帰ると、心が落ち着く。ほっとする。
お盆に一時帰郷した際にも、なぜかそんな気分になりました。
幼い頃、多くの時間を過ごしてきたその場所には、いつ帰ろうとも、
まるでタイムスリップしたかのように、
昔と変わらない光景、味、やり取りが残っています。
故郷に帰る時に襲われるこの感覚は、
多くの方が感じるものではないでしょうか。
「その土地によって違うものに土があります。
人は、自分の故郷の土に囲まれると落ち着くというか、
土には、なぜかそういったことをもたらす効果があるんですよ」

日田市でお会いした左官(さかん)職人の原田さんは、
長い髭をまとった優しい笑顔でそう教えてくださいました。
左官とは、建物の壁や床、土塀などを、
こてを使って塗り仕上げる職種のことで、
日本のみならず、海外でも多くの従事者がいます。
近年、壁の仕上げには塗装やクロスが利用されるなど、
建築物の工期の短縮化の波に押され、左官仕事の需要が減りつつありましたが、
最近になって、味わいのある手仕事の仕上げが見直されつつあるようです。
原田さんのオフィスは、もちろん土壁に囲まれた空間。
確かにそこには、落ち着いた心地の良い空気が流れている気がしました。
左官によって、使う素材もやり方も様々なようですが、
原田さんが主に使用するのは、昔ながらの自然素材の土と漆喰(しっくい)。
それぞれ別に使うケースもあれば、2つを混ぜて使うこともあるそう。
土は、九州の中でも日田から約1時間圏内で採取可能な
地元産のものを使い、

漆喰には、有明海で採れる貝殻を使用しています。

つなぎとして使うワカメは北海道産、
壁割れを防ぐために加える藁は、なんと自前で生産し、
強度を高めるための本麻は、
以前私たちが取材した栃木の野州麻のものでした。

こうしてすべて自然素材から生み出された土壁には、
丈夫で一つとして同じところのない自然模様ができあがります。

驚いたのが、土の産地によって、
ここまで色合いが違うものが出せること。

これはあくまでも一部分にすぎませんが、
原田さんいわく、その土地によって土の色は異なるそうです。
思えば、土地とは"土"の地と書くぐらいですしね。
「お客さんに色を選んでもらうと、
自ずとその人の土地の土色を選ぶ方が多いんです。
であれば、せっかくなのでその方の地元の土を使ったらどうですか?
と提案するんです。
やっぱり地元の土に囲まれて生活すると、安心しますからね」
かつて日本ではよく蔵に使われた土壁は、
そもそも火に強く、中は外気の影響を受けにくいという特徴があります。
さらに調湿効果にも優れており、
内部は快適な空間を通年保てるんです。
傷ついても何度でも再生可能、というのも、ならではですね。
「ふわっと仕上げる。ザラっと仕上げる。
土の肌をどう仕上げるか、それができるのが日本の左官の特徴です。
それによって中の雰囲気が変わるんですよね。
僕らの仕事は、壁を塗っているんですが
実は、空間を作っている仕事なんです」

とても印象的な原田さんの言葉でしたが、
その後、訪れた原田さんの手掛けた喫茶店で、その意味を体感しました。

その落ち着いた空気と、
どこかモダンさも感じさせる空間。
現代の生活様式のなかにも、自然と土を溶け込ませる。
左官の職人技を感じずにはいられませんでした。
豆田町の酒造
実は上にあげた写真は、日田市街で
酒蔵が運営しているカフェ&パン工房「KOGURA」の店内。
一瞬、聞いて耳を疑いましたが、
日田には酒蔵が営む、天然酵母を使ったパン屋さんがあるんです。
その酒蔵の名は「クンチョウ酒造」

かつて幕府直轄の天領として治められてきた日田の豆田町で、
元禄時代(1702年)より続く老舗の酒蔵です。
この酒蔵では、清酒や焼酎はもちろんのこと、

先述の天然酵母を使ったパン屋から、

酒粕を使ったアイスクリームまで展開しているんです。

これまでも各地の酒蔵を訪ねましたが、
ここまで多角経営をしている酒蔵はありませんでした。
酒蔵を守る冨安さん親子にお話を伺うと、
そこには街づくりと密接に関わる酒蔵の姿が見えてきました。

「日田は立地的にも、福岡、大分、熊本の間に位置し、
昔から天領として栄えてきた風情ある街並みもあります。
ただ、観光客が立ち止まって、一息つくような場所がなかったんです。
そこで、地域の酒蔵として一つひとつできることから始めていったんですよ」
まず手掛けたのは、なんと駐車場の整備。
日田観光の中心地であり、酒蔵のある豆田町には、
それまで大型の駐車場がなかったことから、まずは酒蔵の前の土地を購入し、
大型バスも停まれる駐車場にしたのです。

通常、行政任せと考えがちな仕事を酒蔵が率先して行い、
またそれが功を奏したのです。
私たちが滞在している数時間の間にも、
何台もの観光バスが停まっていきました。
同時に、酒蔵のトイレも整備したことで、
多くの方が酒蔵に立ち寄るようになったといいます。
「そうなってくると、次は一休みしていただける喫茶店。
街歩きしながらでも食べられるアイスクリーム、
という感じに、アイデアが膨らんでいったんです」

アイスクリームは酒蔵らしい吟醸酒粕入りのものが一番人気とか。
今では喫茶店で、地元の作家さんの民芸品も扱っていらっしゃいます。

「顔の見える酒蔵を目指しています。
町でも古い歴史を持つ酒蔵なので、
街づくりのなかで酒蔵が果たせることもあるんじゃないかって」
そう話す女将の冨安裕子さんは、
街づくりの様々な委員会にも顔を出しているそうです。
日田では、日田天領祭りの夜のイベントとして、
3万本の竹燈篭が町を彩る「千年あかり」というお祭りも
平成17年より始まっているそうですが、
裕子さんはこのイベントを仕掛けた人のひとり。
同じ大分県臼杵市の「うすき竹宵」や、
竹田市の「たけた竹灯籠 竹楽」にならったものでしたが、
今では、認知も高まり観光客も多く押し寄せるそうです。
これまで昼のお祭りだけの日帰り客が多かったところ、
夜のイベントを開催したことで、宿泊客が増えたといいます。
「ここから先は、一つひとつのお店の頑張りです。
ネットでもモノが買える時代だからこそ、
ここに来てくれた人にしか味わえない魅力を発揮していきたいです」
クンチョウ酒造では、
単に一所の酒蔵として甘んじることなく、
街づくりのなかの酒蔵として発展をしていました。
ガラスの漆器
以前、福井県でも触れた漆器。
漆器職人・山岸氏との出会いで、
漆の素晴らしさと大いなる可能性を知った私たちでしたが、
会津若松市では、漆器の新たな展開の形を知ることになりました。
会津は、幕末の戊辰戦争によって一時は壊滅的な打撃を受けたものの、
明治中期には日本有数の漆器の産地として、その名を轟かせました。
その歴史は、輪島塗よりも古くから盛えたという会津漆器。


なかでも会津絵は会津漆器を代表する絵柄です。
しかし、生活の洋風化につれて、その需要は落ち込み、
今では後継者不足など大きな問題も抱えています。
そんな会津漆器の置かれている環境のなかで、
ひと際、多くの人でごった返すお店が七日町にありました。

「会津のうつわ 工房鈴蘭」
人々の視線の先にある、
6畳ほどの店内にキレイに並べられていた器は、

なんとガラス製の漆器だったのです。
漆器といえば木地モノとばかり思っておりましたが、
まさかガラス製のものがあるとは、驚かされました。
そのスタイリッシュなデザインには、
思わず足を止めてしまうわけも分かります。

「お店がオープンしたのは2年前。まだまだ若僧なんですよ。
でも、お客様から頂く要望を一つひとつ反映させていった結果、
今の漆の器に繋がっているんです」
そう教えてくださったのは、店番をしていた鈴木あゆみさん。
笑顔のとても素敵な会津漆器職人です。

工房鈴蘭が創業したのは、今から約20年前。
400年ある会津漆器の歴史のなかでは若い工房ですが、
低迷しゆく漆器業界をなんとかしたい、という想いから、
もともと、会津漆器の職人だったあゆみさんのお父さん、邦治さんが独立。
幼いころから、父親の並々ならぬ想いと行動をそばで見てきたあゆみさんは、
大学卒業後、会津漆器技術後継者訓練校へ進学し、
父親とともに、会津漆器の道を歩むことを決めました。
今では2人の同志とともに、4人の職人で
新しい会津漆器の形を提案し続けています。

「会津漆器は本来、日常使いされる食器だったんです。
手入れが大変といった印象で敬遠されるのは、
本来あるべき漆器の姿じゃないはずで。
だから、とことん日常使いできる漆器を提案していきたいんです」
こうして、生み出されたのが、
特殊な技術でガラスに漆が塗られた漆器。


漆で生み出せるカラー(白以外)を使いながら、
ガラスだから、牛乳を飲んでもいいし、
ビールや焼酎なんかにも合いますよね。
「漆器はしまい込まずにどんどん使ってほしいんです。
使い込むことで生まれる独特の風合いの変化も、
漆器の魅力の一つなので」

工房鈴蘭には、汁物用などに、
もちろん木地モノも展開していました。

「伝統は忘れてはいけないと思っています。
ただ、そのなかで、食生活が変わっているのだから、
私たち職人が変わらなくてはいけないとも思うんです」
そう話すあゆみさんの工房鈴蘭には、
漆器の新たな可能性と想いがいっぱいに詰まっていました。

会津若松へ訪ねた際には、
是非とも工房鈴蘭へも足を運んでみてください。
漆器がより身近に感じると思います。
福島でつくる現代の生活用品
思えばキャラバンも福島県で17県目。
ようやく全体の1/3といったところです。
日本は広いですね!
これまでの道中、木工品、陶磁器、ガラス細工、鋳物などなど、
様々な素材のものに巡り合ってきましたが、
福島県では現代の生活において無くてはならない素材を使った
プロダクトに出会いました。
無印良品でも多く扱う、ポリプロピレンを使った製品です。

よくプラスチック製品と呼ばれていますが、
プラスチックにもいくつか種類があります。
レジ袋で多く利用されるポリエチレン、
プラモデルで利用されるポリスチレン、など。
なかでも軽くて丈夫、耐熱性にも優れたポリプロピレンは、
収納ケースの他にも、ファイル、

文房具、

お弁当箱、

ハンガーなど、

私たちの生活シーンの多くで活躍をしているんです。
その防湿力と透明性を活かした収納ケースは、
クローゼットや押し入れ、棚のなかの整理にもってこいですよね。
そんな無印良品のポリプロピレン製品を作る、
福島県中通りにある工場を訪ねました。
早速、見せていただいたのはポリプロピレンの原料。

原油から精製されたもので、透明性のある白色をしています。
無印良品のポリプロピレン製品は、この素材のまんまの色です。
これを融解し、以下のような金型に流し込み成形します。

単純な作業に見えますが、日本の繊細な技術が活きていました。
こうした型物の場合、直方体だと型から抜くことが困難なのですが、
実は、内部の厚みにほんのわずかな角度を付けることによって、
抜きやすくしているんです。
素人目には全くといっていいほど分かりません。

外枠においては、重ねて使うため、完全なる直方体です。
さらに、外面にエッヂング加工(シボ加工)を加え、
若干、表面をザラっとした触感にすることによって、
傷を付きにくくしているんです。

使う側にとっては、ケースの中身が見えにくくなる上、
さらに手垢も付きにくくなっていて、助かりますよね。
こうした細かい部分にも気を配ってくれるのが、
日本の誇るべきものづくりだと感じます。
加えて、ポリプロピレンの特徴は、回収してリサイクル可能な点。
こちらの工場でも、不要になったポリプロピレン製品から、

倉庫や運搬時に使われるパレットを生成していました。

地球環境保全が叫ばれる昨今、
こうしてリサイクル可能な素材は重宝されますね。
この工場で無印良品のポリプロピレン製品を作るようになったのは、
1997年に発売したキャスター付ストッカーが始まりでした。

限られた室内空間を有効活用するために、
生み出された製品でした。
多くの支持を集めたこの製品をきっかけに、
ポリプロピレン製品は続々と生み出され、
今ではその数、100種類超。
欧州のMUJIでは主力商品に数えられるほど支持を集め、
シンガポール・タイ・韓国へも出荷されています。
残念ながら写真はお見せできませんが、
第1~第3まである工場内は、一部の組み立ての工程以外は、
驚くほど機械化されていました。
全工程の基本のくりかえし・積み重ねによって、
品質の向上と合理化されたコストを実現してきました。
しかし、そんな工場にも、3.11東日本大震災が襲います。

写真は一部ですが、機械部分もコンベアが落下するなど、
大きな被害を受けました。
しかし、幸いなことに従業員は全員無事。
一丸となって復旧作業を進めた結果、
3月24日には出荷を、3月30日には生産を再開するという奇跡を起こしました。
「一度は働く場所を失いそうになった身。
震災以降は従業員の仕事に臨む姿勢が変わりましたよ」

震災後の様子を、工場長はそう語ります。
また、「追求」がモットーという工場長は、
現状に甘んじることはありません。
さらに高品質、合理化したコストを実現しようと、
日々、改善改革を推し進めています。
無印良品でポリプロピレン製品を見かけたら、
生産者の熱い想いと、卓越された技術力を、
少しでも感じていただければ幸いです。
伝統こけし
東北地方で見つけた"同じようで違うもの"の代表、
それは「こけし」かもしれません。
こけしには、代々受け継がれてきた形態、絵柄、色彩などが
表現されている「伝統こけし」と、

作家の自由な発想の中で制作されている「創作こけし」がありますが、

東北地方で見られるこけしは、主に伝統こけしです。
もともと農家の副業として、冬の間に作られていたこけしは、
江戸末期、子供用玩具やお土産物としてのものでした。
しかし、明治維新で海外からブリキのおもちゃが入ってくると
玩具としてのこけしは廃れてしまいます。
その後、大人が美術的価値を見いだし、鑑賞用として注目されたそう。
つぶらな瞳に、おちょぼ口。
確かに見ているだけで心がホッとし、癒やされます。
その伝統こけしですが、産地によって特徴に違いがあり、
各系統に分けられています。
例えば、宮城県の鳴子系は首が回るのが特徴で、
福島県の土湯系は頭のてっぺんに蛇の目の模様があるのと、
赤い髪飾りが描かれるのが特徴というように。
「世界を見てもこんなに変化しない人形はないと思いますよ。
僕個人としては、こけしの工人同士はあまり交流しない方がいいと思うんです。
各地のこけしは独特だから面白い。混ざったらつまらないですよね?」

そう話すのは、福島県いわき市で弥治郎系のこけしを作る、
佐藤英之さん。
工房にお伺いして、迎えていただいた時には
その若さと饒舌ぶりに驚きました。
というのも、これまで抱いてきた職人のイメージは
"寡黙なおじいちゃん(おじさん)"だったからです。
英之さんは250年続く弥治郎系こけしを引き継ぐ工房の3代目。
おじいさんが弥治郎系こけし工房に奉公に行き、
当時炭坑で栄えていたいわき市に移住し、
この地でこけし作りを始めたといいます。
震災と原発事故で、一時は群馬への避難を強いられましたが、
避難先でもこけし作りを続けました。
こけしが作れることの喜びを噛み締めながら、
1年後、いわき市の工房へと戻り、現在も家族4人で製作を続けています。
こけし作りを始めて10年という英之さんは、こう語ってくださいました。
「死ぬまでできる仕事だから、まだまだ修業中です。
難しいのは木を扱うこと。日々、木に教えられていますね」
こけし作りは、材料の選定から始まり、
ロクロにかけて削る前にできるだけ近い形に切ったり割いたりする
"木取り"の作業が全体の8割を占めるんだそうです。
「せっかくだから作ってみましょうか」
そう言うと、目の前で英之さんが木を削りだしました。
カンナ棒を使って器用に手首を回しながら行います。

すると、10分もかからないうちに、
筒型だった木がこけしの形に変化していきました。

サンドペーパーで磨き、トクサ(写真右)とヘチマ(写真左)で
木肌が滑らかになるようにさらに磨きます。

こうして裸のこけしが出来上がると、今度は模様付け。
弥治郎系のこけしは、しま模様が多いのですが、
これは"ロクロ線"と呼ばれ、ロクロを回しながら描くのです。
くるくると回るこけしの胴体に、
レコードに針を置くように、そっと筆を入れます。
すると、みるみるうちに、ボーダー服を着たこけしが誕生しました!

弥治郎系こけしの特徴は、頭頂にベレー帽のように描かれた多色の輪。
このデザインは英之さんが頭の中で考えながら
描いているのかと思って質問をすると、
「うちの工房だけで、70種類以上の伝統型があるんです」
と製作手帳を見せてくださいました。

英之さんの工房には、おじいさんを含む5人の師匠の型が
引き継がれているんだそうです。
「誰かが作らないと残らないですからね」
そうなんです、伝統こけしというのは、
名前だけでなく、時代が変わっても、しっかりとその型にそって
作られていっているのです。
最後にフリーハンドで、慎重に表情を描いていきます。

ポッと赤く染まった、ほっぺたを描いたら完成!

英之さんと目が合って、おもわず顔を赤らめる少女。
その慎ましさは日本女性の象徴かもしれません。
また、こけしの表情には、描き手の気分がそのまま反映するといいます。
「おやじが若い頃作ったこけしは、全部うちの母そっくりですからね(笑)」

英之さんの生み出した、この可愛らしいこけしも
英之さんの周りにいる誰かに似ているのでしょうか。
それから、こちらの工房では
「飾るだけでなく、さわってもらえるこけしを作りたい」
という想いから、こけし印鑑も作られていました。

大きさはこけし人形の1/10くらいですが、
製法や模様もすべて通常のこけしと同様。
「ルールがあるからこそ自由になれる。
これからも自由な発想を大切に、こけしを作っていきたいです」

ちなみに、この弥治郎系こけしで一番古い型のこけしが
来年の福缶に登場するので、どうぞお楽しみに♪

「手」で染める
福島県会津若松市は、鶴ヶ城の城下町として栄えた歴史ある町です。
その町並みは今も変わらず、落ち着いた風格のあるたたずまい。

そんな町中を歩いていると、目に入ってくるのが
それぞれのお店に掲げられている「のれん」や「のぼり」です。

「あぁ、ここは酒屋さんなんだな」

「ここは野球用品を扱うお店かぁ…」
のれんはもともと、建物の入り口に外部と内部の仕切りとして垂らし、
直接風や光が入るのを防いだり、寒さよけを目的として
取り付けられたのが始まりとされています。
また、のれんを付けていると、営業中を意味し、
閉店になると店主はまずのれんを片付けるといいます。
一方、のぼりは、かつて自軍と敵軍との識別を行うため
戦陣に用いられましたが、
現在においては主に広告としての役割を果たしています。
「げたや」に「笹だんご」、
車の中からでもそこが何のお店なのかが一目瞭然です。
さて、これらの「のれん」や「のぼり」を
明治時代から作っている工房があると聞いて、伺いました。

「安藤染店」
明治初期の創業で、当初は養蚕と糸染めを行っていたそうですが、
現在は、のれんやのぼり、はっぴ等の染めと縫製をしています。

そのほとんどが地元、会津若松のお客様向け。
昔は何軒もあった染め店が今ではほとんどなくなってしまったなか、
100年以上同じ場所で同じ商売が続いているというのは、
その地域で必要とされているという証拠です。
7代目にあたる、安藤暢昭さんに工房をご案内いただきました。

染めの方法は大きく分けて3つ。
いずれも"手"を使って染め上げていきます。
1つ目はスクリーン型を使って染める「スクリーン捺染(なせん)」
主に、複数枚を染める際に使う手法です。
2つ目は渋紙(しぶがみ)の型を使う、「型染め」
生地に型を置いて、もち粉と米ぬか、石炭、塩から作られた糊を乗せます。
この糊の部分は染料を通さないため、最後に白く残ります。
そして、3つ目は型を使わず、手でデザインを描く「手染め」
水で消える紅を使い下描きし、そこに型染め同様の糊を
手で置いていきます。
まるで、ケーキに生クリームでデコレーションするように。
実はここまでは染色前の準備段階なのです。
糊置きしたものを乾燥させ、その後染色するのですが、
「色がムラにならないようにするかが最も難しいところですね」
安藤さんが笑顔で教えてくれました。

ところで、手染めの魅力はどこにあるでしょうか?
手染めは、ひとつひとつ手作業なので生地の品質を損なわず、
やわらかさや独特の風合いを生み出します。
また、使っていくうちに色が落ち着き、味が出てくるのです。
さらに、微妙な色合いを出せたり、世の中に2つとない
オリジナルの品が仕上がる。
お店の顔である「のれん」に手染めが多く支持されるのもうなずけます。

染める時は手袋をはめると感覚がわからないので、
素手で行うという安藤さん。
会津の町に安藤さんの手仕事が、今日も風に吹かれています。
青いだるま
昨日に引き続き、こちらも来年の福缶に入る縁起物のひとつ。
各地にあるだるまの中でも個性際立つ、
「松川だるま」です。

言い伝えによると天保年間(1830~1844年)に、
伊達藩の武士である松川豊之進が創始したもので、
名前をとって「松川だるま」と呼ばれるようになったのだとか。
特徴的な群青色は、空と海の色で袈裟(けさ)を表し、
また、お腹の部分には宝船や大黒様、松竹梅が描かれ、
さらには金で装飾が施されており、めでたいづくしの縁起物といえますね。
以前、群馬の高崎だるまを取材しましたが、
その時見ただるまとはどうも形状が異なるような…。
左のだるまが「高崎だるま」で、右が「平塚だるま」

まゆ毛の形とひげの形は異なるものの、本体の形状はほぼ同じです。
というのも、だるまはもともと実在の人物、
達磨大師がモデルになっているから。
しかし、今回お目にかかった「松川だるま」はなんだかスリムな気がします。
「仙台のだるまは、伊達政宗公がスリムだったからスリムなんですよ。
あとは政宗公が片目を悪くしているので、
だるまには両目を入れて、四方八方まで見守ってもらおうと、
うちのだるまは最初から両目が入っているんです」

10代目として継承されている、本郷ご夫妻の奥様尚子さんが
そう、教えてくださいました。
同じようで違うもの。
こうなったら、全国のだるまさんを並べてみたいものです。
ちなみに、私たちが訪れたこの日は、だるまの底につける重りを作る日。
工房の前にはドーナツのようなものがたくさん乾かしてありました。

この重りをつけることで、
だるまは転がしても起き上がることができるのです。

庶民の心の拠り所として作り出されたという松川だるまは、
倒れても起き上がり、
昔も今も変わらず、両目でしっかりと見守っていてくれます。
何が入っているか開けてみるまで分からない、福缶。
いずれも職人さんたちが、ひとつひとつ心を込めて手づくりしている品々です。
みなさん、気になるものはありましたか?
写真だけだとその魅力はまだまだ伝わらない!
来年実物に会えるのをご期待ください。
仙台の縁起物
北海道編でセワポロロをご紹介しましたが、
仙台でも着々と準備が進んでいる、福缶に入る縁起物の製作現場を訪ねました。
まずはこちらの「堤人形(つつみ人形)」から。

ネコが鯛をネコババ…したわけではなく、
ネコが鯛を持ってきて"めでたい"縁起物なのです。
もともと焼き物の産地だった堤町において、
冬の間の手仕事として作られ始めたという堤人形は
300年以上の歴史を持ちます。
工房が奥州街道沿いにあり、
かつては商人や旅人のお土産ものとして、各地に広がっていったそう。
このような型を使い、

まず、土人形を作り、

素焼きしたものに彩色していきます。

下描きをするわけでもなく、スーッと筆を入れていく職人の佐藤さん。
職人歴60年以上の匠の技で、次々と人形に息吹を与えます。

じーっとこちらを見つめているようなネコの目。
「どうだ!鯛をとってきたぞ!!」と言わんばかりの表情に
「うんうん、ありがとう。君がいればなんだかいいコトがありそうだ★」
そんなことを感じさせてくれる置物です。
続いて、このなんともかわいらしい、「首振り仙台張子」

一枚一枚染められた手漉き和紙で
ひとつずつ手づくりされた、手のひらサイズの張子(十二支)です。

十二支すべての動物の首がゆらゆらと動くのが
たまらなくかわいく、癒やされます♪
これならお正月だけでなく、通年、
インテリアとして飾っておいてもいいですよね。
実際に目の前で作っていただくと、作業はとても細かく地道なものでした。
動物の顔と胴体を別々に作っていき、

頭が振れるように、粘土で作った重りを頭に糸でつけ
バランスをとります。
そして、細かくちぎった和紙を貼りつけていくのですが、
その仕上がりはまるで1枚の紙を貼ったように、全く継ぎ目が見えないのです。
これぞ職人業ですね!
一度お目にかかったら、忘れられないキュートな張子たちは、
笑い上戸のお父さんと優しさのにじみ出るお母さん、
高橋さんご夫妻によって生み出されています。

おもわず名前をつけたくなる、首振り仙台張子。
来年、誰の手元に届くでしょうか☆
もくもく絵本
岩手県内陸部にある遠野市は、
柳田國男の遠野物語のもととなった町であり、
カッパや座敷童子などが登場する「遠野民話」で知られています。
ここはカッパが住んでいるという伝えのある「カッパ淵」

よく見ると、カッパの好物のきゅうりが仕掛けてあるではないですか!
しばらく見ていると、絵本の中から登場したような
可愛らしいおじさんが登場しました。

その名も「ニ代目カッパおじさん」
二代目は現在も修行中で、本物のカッパを見たことがあるのは
初代のカッパおじさんだけだそうな。
「昔あったずもな…」
(昔あったそうだ)
決まってこのフレーズで始まる民話は
語り部さんによって今でも語り継がれており、
観光施設やホテルなどでも昔話を生で聞くことができます。

市内の小学校でも語り部さんが学校に出向いてお話をしたり、
子供向けの「語り部教室」なるものも存在するそう。
さて、そんな遠野で見つけた「なるほど!」
と思わずうなってしまった、子供のおもちゃがあります。

「だれが」「どこで」「なにを」「どうした」の
4つのキューブを組み合わせて物語を作って遊べる木のおもちゃ、
「もくもく絵本」です。

「おんなのこが・やまで・おにを・たべました」
「ねこが・やまで・おひめさまを・たいじしました」
手の中でコロコロ回していくうちに
あれあれ? 不思議な物語に!
「鬼はおいしかったのかな?」
「おひめさまは何か悪いことしたのかな?」
遊んでいる中でコミュニケーションが生まれます。
そのストーリーの組み合わせは、なんと1296通り!
子供たちは一度遊び出すと、夢中になって止まらなくなるといいます。

「遠野にはこんなに山があって木があるのに、
子供たちが遊べる木のおもちゃがない。
民話の里・遠野らしいものづくりができないか」
そう思った地元の主婦3人が集まり、
遠野市のバックアップのもと、
木のプロ、デザインのプロを加えて2004年にもくもく絵本の研究会を発足、
2年の月日を経て、2006年5月に発売。
すると、子供たちが「もくもく絵本」で楽しく遊ぶ写真が全国紙に掲載され、
「孫にあげたい」「子供と遊びたい」
と問い合わせが殺到したそうです。
さらに嬉しい感想のお便りも続々と寄せられました。
「ゲームだと一緒に遊べなかったけど、もくもく絵本だと毎日一緒に遊んでいます」
「別居中でしたが、もくもく絵本をきっかけに夫婦も復縁できました」
などなど。
「人と人をつなぐことのできるおもちゃだと、
評価いただいています。
子供に対して木の良さを伝える、"木育"にもなりますし」

代表者の前川さんがそう教えてくださいました。
上述の4つのキューブを組み合わせて遊ぶ
「おはなし木っこ(こっこ)シリーズ」のほかに、
昔話が描かれている「昔話シリーズ」もあり、
こちらのイラストは前川さん直筆のもの。

プロの描くイラストにはない、
とっても味のある絵で親しみがわきます。
最近では、岩手大学教育学部と共同で
小学校の英語教育の教材として、英語版を開発しました。
また、「だれが」の部分に名前を入れることのできる
オリジナルシリーズも!
誕生日や記念日のギフトにピッタリですね。

木の香りや手触りを楽しみながらコミュニケーションがとれ、
さらに言葉の習得にもつながる「もくもく絵本」。
イラストや文字はレーザーで焼き付けられているので、なめても安全、
お風呂の中でも遊ぶことができてしまうんです。
これまでも伝承されてきた遠野の民話と言葉を、新しい絵本の形で、
地元の間伐材を用いて表現する。
その土地の日常の言葉を大事にした柳田国男の思想が、
今もこうして引き継がれていました。
南部鉄器~日本から世界へ、伝統から未来へ~
「お茶にしましょうか?」

この旅路でも、幾度となく設けてきたお茶の時間。
思えば海外でも、コーヒーブレイク、アフタヌーンティー等、
それぞれのスタイルで、ティータイム文化は存在していました。
そんな海外のティータイム文化に、
ある日本の商品が受け入れられていること、ご存じですか?

岩手県で作られている「南部鉄器」です。
重厚な味わいを持つ南部鉄器は、一見アジアを想起させますが、
アメリカやフランスをはじめとしたヨーロッパでも大人気。
アジアでは、お湯を沸かす際の鉄瓶が受け入れられ、
欧米では、お茶を入れる際の急須が好まれています。
電気湯沸かし器で沸かしたお湯を、
冷めにくい南部鉄器の急須に入れてティーを楽しむのが、
欧米の乙なティータイムなんだとか。

「もともと、鉄に黒の漆を塗っていたことから、
南部鉄器といえば黒が一般的でしたが、
これらカラフルな急須は、欧米向けに生み出されました」
そう教えてくださったのは、岩手県奥州市で南部鉄器を製造する
及源鋳造株式会社の及川久仁子社長。

なんと160年もの歴史を持つ会社の5代目社長です。
南部鉄器のルーツは、盛岡と奥州で異なるようで、
殿様の献上品としての鉄瓶づくりが主だった盛岡に対して、
奥州は、庶民の生活道具のための鉄器でした。
材料である良質な鉄、砂、粘土が採れたことも、
鉄器づくりがこの地に根付いたゆえんのようです。
「南部鉄器は伝統工芸品ですが、工業製品でもあります。
だからアレンジがしやすかった。それも大きいと思います」
及川社長がそう話すように、
高度経済成長期に工場は機械化。

生産性の向上を図り、
工業製品としてのものづくりを確立させました。
「あとは技術力。
鉄瓶や急須のように、内部が空洞な壺のような形で、
これだけ薄い鉄で、きめ細かい模様を施せる技術は、
他国にはないと思います」

当たり前のように、そのデザイン・技術力を話す及川社長ですが、
15年前までは、鉄瓶・急須は手掛けてはいませんでした。
この産地は、それぞれの工場で作る商品種類が分かれており、
及源鋳造では鉄鍋を中心とした商品ラインナップでした。
しかし、お客様のご要望にお応えするためには、
自ら商品開発をしマーケットを広げていくことが必要と、
及川社長は、鉄瓶・急須づくり進出を決断。
それまで一升が一般的だった鉄瓶も、
核家族化が進む現代においては1リットル以下の容量が必要と、
生み出した小さい鉄瓶は大ヒットを記録しました。

合わせて、欧米で人気を博した急須などを生み出したのは前述の通りです。
また、本業だった鉄鍋においても、とどまることを知りません。
高温で焼きしめ、全体を酸化皮膜で覆うという、
これまで南部鉄瓶に用いられていたサビ止め手法を鉄鍋にも応用。
「超南部鉄器」と謳った「上等鍋」が誕生しました。

サビ止めのための余計なコーティングがされていない分、
熱が伝わりやすく、料理人からの評判も高いといいます。
こうした新しいことに取り組みながらも、
原点の南部鉄器の製法を忘れてはいけないと、
同社では、後継者育成事業にも取り組んでいます。
南部鉄瓶の伝統的な製法を継承すべく、2人の若手を受け入れ、
伝統技法を継承するプロジェクトを立ち上げています。

「伝統があるから、今がある。
これが全く新しい技術だったら、味わいも変わると思うんですよね」
そう言いながら、及川社長が、
南部鉄器で沸かせたお湯で出してくれたコーヒーは、
本当にまろやかで、深い味わいがしました。

「伝統が残っていることに感謝しなくちゃね。
残したくても残せない国や地域もたくさんあるのですから」
確かに、地域ごとに脈々と文化が残っている私たちは、
幸せなのかもしれません。
小久慈焼
7月下旬の岩手はまだ梅雨の中。
満開のあじさいが私たちを迎えてくれました。

久慈市を車で走っていると、ふと窯元の看板を発見。

中に入ってみると、少し厚みのあるぽってりとした、
白と茶色のとてもシンプルな器が並んでいました。


「小久慈焼(こくじやき)」
来年でちょうど200年の歴史を持つ焼き物です。
初代熊谷甚右衛門が福島県の相馬焼の技術者を招いて作陶を学び、
地元、久慈で採れる粘土と釉薬で作り上げたのが始まりだそう。
「土地が痩せていてお米が穫れなかったこの地域で、
年貢に納めるものとして焼き物に目をつけたんじゃないかと思うんです。
ここで暮らしていくための方法だったんでしょうね」
ご案内いただいた、8代目となる下嶽(しもだけ)知美さんは、
そう話してくださいました。
やがて小久慈焼は、八戸藩に納める御用釜へと成長したのですが、
6代目で世襲が途絶えてしまいます。
一時は存続をあきらめかけたものの、久慈市が後継者育成に乗り出し、
智美さんのお父様を含む数名が修業をして、
後にお父様が7代目を襲名されたんだそうです。
そして現在は、智美さんと弟さんが協力し合って工房を支えています。
今使っている材料はかつてと同じ、地元の鉄分が少ない白い土。

これを粉砕して、長石と水を混ぜて精製し、陶土を作るのですが、

12~3月の真冬の時期は置いておくと凍ってしまうので
電気毛布をかけて保管しておくといいます。
冬場の仕事のコツ、北国ならではですね。
また、デザインも伝統のものにアレンジを加えながら引き継いでいます。
初代の頃から作っていたという「片口」

昔は液体を移し替えるための道具として
計量カップの代わりに使っていたそうですが、
今であればお酒を入れたり、
麺類に注ぐおつゆやサラダのドレッシング入れなどに使い勝手がよさそう!
それから、冬に熱々のホットワインを入れてテーブルに並べてもいいかも♪
白くて温かみがありシンプル、でもドシリと構えているこの器は、
どんな使い道も受け止めてくれそうです。
それから、「すり鉢」も昔ながらの定番商品。

この地域ではお正月にくるみをすって、牛乳と砂糖・お醤油を加えた
"くるみもち"を食べるそうなのですが、
安定感抜群のすり鉢が活躍する時です。

「最近はフードプロセッサーが出てきて、簡単に材料を砕くことができるのですが
熱を加えないすり鉢の方が素材の香りが損なわれなくていいんですよ」
と智美さん。
工房を見せていただいているとこんなものが目にとまりました。

左から、成形する際に器を粘土の塊から切り離す時に使用する「切り糸」、
表面を滑らかに整えたり、口縁を締めたりする「なめし皮」、
それから…真ん中のものは、しゃもじ!?
しゃもじのようなこの道具は、先っぽに細かい刻みが入っており、
それを使って器に細かい線を入れると、すり鉢が出来上がるのです。
こちらは足で蹴って回す「蹴りろくろ」

「震災で停電していた時に、物置から引っ張り出してきて使ったんですよ。
昔の人はこれで作っていたんですもんね」
道具もすべて自然素材でできていて、なんだかとっても温かみがあります。
工房の隣には、これまで7代にわたって作られてきた
代々の小久慈焼が展示されていました。
決して派手ではなく、素朴な味わいの小久慈焼ですが、
だからこそ使い手に様々な使い方の選択肢を与えてくれる。
200年続いてきた小久慈焼は、今もこうして久慈の地で
守り続けられています。
セワポロロ
もう、2012年も既に7ヵ月が過ぎてしまいましたね…。
早いものです。
無印良品では今年から年始に、
"福"をお届けする缶詰、「福缶」を販売しています。
中には東北地方(青森県、岩手県、宮城県、福島県)の手づくりの縁起物
いずれか1点が入っていました。
そして、少し気の早いお話ですが、
来年の年始にも、今度は全国から"福"をお届けする予定だそう。
今回は現在準備中のものづくりの現場をちょっとだけお見せしちゃいます♪
訪れたのは、北海道網走市にある「大広民芸店」。
中に入ると、見ているだけで幸せになれそうな笑顔の
大広朔峰さんが迎えてくださいました。

大広さんが作っていらっしゃるのは、
主に北方民族のウィルタ族にまつわる木彫り人形。
網走には戦後、樺太島に住んでいたウィルタ族の人々が移り住んできたそうです。
ウィルタ族はもともと遊牧民で、トナカイを飼育し、
毛皮のテントで生活し、自然に頼る暮らしをしていました。
厳しい自然の中で生き抜くために、彼らは動植物や無生物に精霊を宿していました。
彼らがお守りとして伝えてきたのが、「セワ」(上)と「セワポロロ」(下)。


つぶらな瞳と鼻筋の通った凛とした表情に釘付けです☆
「セワ」とは神をさし、神像として身近な場所において
願い事をして感謝を欠かさないようにと、
家のお守りのためや、狩猟を願うお祭り(オロチョンの火祭り)の時などに
作り出されていたようです。
「セワ」と「セワポロロ」両方に共通するのが
木を薄く削って作られた紐のような部分。
これは「イナウ」と呼ばれるもので、鳥の羽を表し、
古くから神や先祖と人間の間を取り持つ供物として、神聖に扱われてきました。
先述のオロチョンの火祭りにも、欠かせない祭具だそう。
このイナウは、1本の木を削って作られるのですが、
大広さんの手にかかるとスルスルといとも簡単に生まれていきました。

ここで、大広さんがなぜウィルタ族の木偶を作るようになったのかを
尋ねてみると、大広さんご自身がウィルタ族の語り部だということが発覚。
過去には実際にウィルタ族の方に会ってお話を聞いていたり、
年に1回行われている、オロチョンの火祭りの火付け役をされていたり
と活動されていらっしゃいました。

オロチョンの火祭り用の衣装を身につけられると、
先ほどまでの朗らかな印象とは打って変わって、
今度はキリリとした貫禄のある姿に。

そんな大広さんがひとつひとつ心を込めて作ってくださっている、
招福の使者「セワポロロ」が
来年の年初めに福缶の縁起物に仲間入りします!

会えるのを楽しみに待っていてくださいね。
(※福缶の縁起物は、複数ありますので必ずセワポロロに会えるとは限りません)
最後にセワポロロを生みの親、大広さんの手を見せてもらいました。

その手でこれまで何人の子を生み出してきたのでしょうか。
彫刻刀をはさむ小指には、その勲章である大きな豆ができていました。
牛のミルク
青い空に白い雲、広大な緑の牧草地に赤い屋根の牛舎とサイロのある風景。
これぞ思い描いていた北海道の景色です!

北海道十勝地方は"酪農王国"と呼ばれ、
至るところでこのような景色を見ることができます。
せっかくなので、牧場に立ち寄ってみました。


こちらの牧場ではおよそ900頭の乳牛が飼われていました。
800kgの牛さんは近くで見るととても迫力がありますね。

食事中に失礼して、乳搾りを体験させていただきました。

人間の親指よりも大きな乳首を握ると、ぴゅーっとミルクが吹き出しました。
1頭の牛から1日平均30リットル(1リットルの牛乳パックが30本!)
のミルクが採れるというから驚きです。
本当だったら子牛が飲むためのミルクを私たち人間のために与えてもらっている…
当たり前のことですが、普段冷蔵庫から取り出したパック牛乳を飲んでいると
忘れてしまいがちなことです。
また、牛乳は栄養価の高い食品として古くから親しまれてきましたが、
そのままでは保存性に欠ける上、液体のため運ぶのにも不便であるために
水分を抜いて保存性と運搬性を高めたチーズが生まれました。
今度はそんなチーズが作られている、チーズ工房を訪ねました。

「共働学舎 新得農場」
共働学舎は、1974年に宮崎眞一郎氏首唱のもと、
心や体に不自由を抱える人たちとともに、競争社会ではなく協力社会、
さらには「自労自活」の生活を目指して、始められました。
新得農場は1978年に開かれた、
牛飼いからチーズづくりまでを一貫して行っている場所です。
もともとは牛乳の出荷だけだったのですが、それだけでは生活が成り立たず、
流行に左右されることなくスローペースで生み出せるものが何かを考え、
行き着いた先が当時ほかの酪農家が手を出していなかった、チーズづくりだったそう。

新得農場が教わったのはフランスに伝わる昔ながらのチーズづくりでした。
大切にしているのは「牛乳を傷めない工夫」。
搾ったばかりの牛乳を極力運ばなくて済むように、
衛生管理上、搾乳室とは通常50m以上離すのが常識の工房を23mの位置に作り、
搾乳室から工房まで自然の傾斜をつけて、
自然流下式のパイプラインで牛乳を流しています。
これが実現できているのは、牛舎の虫やニオイを解決するために
木造の牛舎に炭を埋めてマイナスイオンを高め、
牛のエサや寝床に粉炭と微生物を混ぜて、衛生管理をしているから。
確かに、よく牧場付近で香る、鼻をつく臭いがほとんどしませんでした。

また、チーズを熟成させるのに理想的な環境は、
湿度85~95%、気温8~12℃、マイナスイオンが十分にある場所だといいます。
新得農場では、その条件を整えるために鉄筋を使わずに、
札幌軟石を積んで、半地下の熟成庫を作ったそうです。

熟成庫に続く階段を下りると、途端に温度の変化を感じます。
同時にチーズの発酵する匂いがしてきました。

ズラリと並んだチーズ。
大きな固まりのチーズはなんだかカーリングの石のよう!?
こちらの工房で作られたチーズを食べてみました。
定番チーズ5種類の盛り合わせ↓

それぞれ見た目も食感も味も異なります。
左から2番目奥の「レラ・ヘ・ミンタル」と左から2番目手前の「シントコ」、
色の違いが分かりますか?
この違いは仕込みの時期と熟成期間の違いからくるそうです。
「シントコ」は青草が生えている6~10月の放牧時期にのみ製造しているため、
青草に多く含まれているカロチンが、チーズを黄色くするのです。
やはりチーズの原料であるミルク、さらにはミルクを生み出す牛が食べるもの、
そして牛が生活する環境までもが、チーズ自体に大きく関わってくるのですね。
世界にひとつだけの椅子
子供が生まれたらプレゼントしたいものがあります。

それは、北海道旭川市近郊で作られる、
世界にひとつだけの椅子。
木でできた椅子は、温かみがあります。
ステンレスよりも傷つきやすいかもしれない。
でも、使った分だけ、時が刻まれる…そんな気がします。

「君の椅子」プロジェクト。
新しい市民となった子供たちに、
"生まれてくれてありがとう"の想いを込めて
居場所の象徴としての「椅子」を贈る取り組みが
北海道旭川市近郊の3つの町(東川町・剣淵町・愛別町)で
2006年から行われています。
「子供が生まれたことを共に喜び合える地域社会を作りたいと思ったんです。
子供は地域社会の宝ですからね」
そう話すのは、「君の椅子」プロジェクト代表の
旭川大学大学院の磯田客員教授。

なぜ椅子なのでしょうか?
子供の椅子は一見すぐに使えなくなってしまうようにも思うのですが、
椅子は座る機能だけではないと、磯田教授はいいます。
例えば、絵本を置くのに使ったり、踏み台として使ったり。
子供の成長に合わせて用途は変わりますが、
日々の暮らしにそっと寄り添いながら、子供の成長を見守っていく椅子は
"思い出の記憶装置"なんだそう。
また、この「君の椅子」プロジェクトは
コミュニティ形成に加えて、
産業振興、ものづくりの観点での目的もあるのです。
もともと旭川市近郊で盛んな旭川家具の技術を活かしたいと、
毎年椅子づくりを地元の工房作家や家具メーカーに交代でお願いしています。
2009年からは全国の誰もが参加できる、「君の椅子倶楽部」が発足。
これにより、3つの町と「君の椅子倶楽部」に参加した方の
新生児分の椅子が旭川市近郊で作られています。
この「君の椅子」プロジェクトにいち早く参加の意思を示したのが、
古くから「写真の町宣言」をして町づくりを行う、東川町。
「東川町は北日本で3番目に大きい旭川市に隣接していて、
旭川空港まで約10分、旭山動物園に日本一近い町だし、大雪山もある。
こんなに条件がそろっている町が活性化しなかったら、他の町は無理ですよ」

そう話す松岡町長の元では、次々と新しいアイディアが生まれています。
例えば、2005年からは新しい婚姻届を採用。
入籍の際には、夫婦になった瞬間の写真を撮影してプレゼントし、
記念のメッセージシートにメッセージを残し写真と共に
保管しておける形の婚姻届です。
用紙の文字の色ひとつとっても、ピンク色でなんだかそれだけでも
ハッピーな気分が増すものです。

「君の椅子」プロジェクトについて、松岡町長に伺いました。
「この椅子は、親から子へ伝えていけるもの。
昨年の東日本大震災の際には、我々にできることは何かを考えた結果、
3月11日に生まれた子供たちに形に残るものをプレゼントしよう
ということで、私も福島に椅子を届けに行ってきました」
2011年3月11日、2万人近い方が亡くなられたあの日、
一方で新しい命が誕生しました。
しかし、その数は誰も統計をとっていませんでした。
「君の椅子」プロジェクト代表の磯田教授は
東川町の松岡町長、剣淵町・愛別町の各町長と相談して、
被害の大きかった岩手県・宮城県・福島県の全128市町村に
「あの日、あなたの町で何人の子供が生まれましたか?」
という手紙を出しました。
ダメもとで送った手紙には続々と返事が寄せられ、
あの日、3県で104人の赤ちゃんが生まれていたことが分かりました。
こうして作られたのがもうひとつの「君の椅子」、
"希望の「君の椅子」"でした。

ひとつひとつの椅子の裏には、
"希望の「君の椅子」"のロゴと名前、誕生日、各県のシリアルナンバー、
そして「〜たくましく未来へ〜」という文字が刻まれています。

今回、椅子の制作をしたのは、東神楽町にある株式会社匠工芸。
設計を担当した業天さんは
「今回の椅子づくりはものづくりの原点を思い出させてくれました。
あの椅子を作れれば、何でも作れるんじゃないかと思うほど」
と振り返ります。

ひとつの椅子を作るのに11個のパーツが使われ、
パーツの接続には、10本の竹釘を使ったそうです。

「私たちには、遠い森からはるばるやって来た木に
かけ心地のいい椅子としての、
あるいは使いやすい収納としての新しい人生を授け、
未来へ船出をさせてやる責任があると思っています」
匠工芸の桑原社長がものづくりへの想いを語ってくださいました。
「木はぶつけると傷つき、乱暴に扱うと機嫌が悪くなる。
でも大切に扱うと素直になるし、心をかけると思い通りに美しく育ってくれる。
まるで子供のようなんです」

世界にひとつだけの「君の椅子」は
発案者の想い、町の想い、そして作り手の想いがひとつになり、
形となって子供たちに届けられているのです。
子供たちへのメッセージはひとつ。
君の居場所はここにあるからね。
生まれてくれて、ありがとう。
君の椅子プロジェクトは、くらしの良品研究所・小冊子でもご紹介しています。
![]() くらし中心 no.06「手渡すこころ」(PDF:10.3MB)
くらし中心 no.06「手渡すこころ」(PDF:10.3MB)![]()
また、『君の椅子』プロジェクト展(Living Design Center OZONE)![]() が、
が、
2012年8月21日(火)まで東京都新宿区で開催中です。
※「君の椅子」プロジェクト展は、2012年9月4日(火)まで会期が延長になりました
あま~いトマト
北海道の大地で、
それはそれはとても甘いトマトに出会いました。

北海道余市町(よいちちょう)にある
「中野ファーム」でつくられる、高糖度トマトです。
「糖度は9%以上ありますよ。
そのためにトマトには厳しい環境を強いていますが(笑)」

優しい笑顔で迎えてくれたご主人の中野勇さんがそう話す通り、
ここのトマト栽培法には、いっぷう変わった特徴がありました。
まずは農園の環境。

眼下に日本海を拝む丘陵地帯で、
日本海からはミネラルたっぷりの海風が吹き上げ、
太陽が沈むまで、いっぱいに光を浴びることができる環境です。
朝晩の寒暖差も激しく、土壌は水はけの良い赤土。

この環境が、
トマトのルーツといわれる南米アンデス地方と類似しているんだそう。
かの永田農法で有名な永田照喜治氏にも、
「日本で最もトマト栽培に適した場所」と言わしめた場所なのです。
最も特徴的なのは、その栽培方法にあります。
それは、
トマトには最低限の水しか与えないこと。

そうすることによって、
わずかな水分を求めて地中に根を張り、空気中から水分を吸いこみ、
トマト自身の力で、必死に生きようとするのだそうです。
生きようとするトマトは、体内に糖分を蓄えるため、
赤くて果実の甘みが高くなるというわけです。

これは、永田農法と呼ばれる、必要最低限の水と肥料しか与えず、
植物本来の生命力を引き出す作物の育て方です。
ただ、水が足りなすぎると枯れたり、しおれてしまうため、
常にトマトの状態を見てあげなくてはならない、
とても手間のかかる農法と言えます。
実際、"尻焼け"と呼ばれる状態になってしまうトマトも。

ただ、中野さんいわく、この尻焼けしたトマトこそ、
甘くて美味しいトマトの証拠なんだそうです。
逆に言うと、尻焼けしたトマトができるぐらい、
ギリギリの水分量で育てるということです。
なんと厳しい育て方…
しかし、こうして育てられたトマトは、
甘くて、実がギッシリ詰まった、とても濃厚な味がしました。

ただ、このトマト、果実としては出しておらず、
すべてはトマトジュースとして出荷されているんです。
厳しい栽培法により、形よりも美味しさや糖度を追求しているためで、
ジュースとなってもその味はまるでトマトを丸ごと食べているかのよう。

甘くて濃厚でありながら、爽やかな喉ごしは、
飲むだけで健康になったような錯覚を覚えるほどです。
「美味しいトマトを届けたい。
手間のかかる農法ですが、その想いでやっています」

人間は自然にはかなわない。
だから、大地の力を最大限に活かすのですね。
BUNACO
クリエイティブで、エコロジカル。
伝統工芸でありながら、モダン。
そんなモノづくりが、青森県にありました。

「BUNACO(ブナコ)」
薄い板状にされたブナの木から生み出される
ユニークなプロダクトです。
とてもモダンなデザインですが、その歴史は比較的古く、
1956年、日本一の蓄積量を誇る青森県のブナの木を
有効活用するために開発されました。
右のコイル状に巻かれたブナの木が、
左の木の器に様変わりするんです。

その実態を確かめるべく、訪れた先は弘前市にある
「ブナコ漆器製造株式会社」。

古くから使われ続けている町工場は、昔ながらの趣きですが、
今やこの地で生み出された品が、世界へ発信されています。
まず、見せていただいたのが、BUNACOの材料。

大根のかつら剥きのような手法で、
厚さ約1mm、長さ約2mに削られたブナの木を乾燥したものです。
通常、様々な形状の木地を作るとき、
ろくろを使って削り出す製法が用いられますが、
その際、削り出された木は廃棄されることがほとんどです。
ただ、このBUNACOの場合、その無駄がありません。
エコロジカルのゆえんはここにあります。
これを、板にコイル状にきつく巻き上げ、ベースを作ります。
これがかなり力のいる作業のようでした。

続いて、成型の段階で出てきたのはこちら。

お茶碗です。
それも、なんと無印良品のもの!
BUNACOの成型にはお茶碗の丸みと大きさが絶妙のようで、
いろいろと試した結果、無印良品の白磁の茶碗に落ち着いたんだそう。
こんなところでも無印良品が使われているとは、驚きでした。
そんなお茶碗を中央から外側にかけて転がしながら、
徐々に型を整えていきます。

私たちも体験させてもらったのですが、
これが見た目以上に硬く、ハードな作業で、
力を入れないと曲がらないし、入れ過ぎてもダメ。
ただ、そこがクリエイティビティの発揮どころで、
力の入れ具合によって、様々な形へと変化させることが可能なんです。
同じ木地から作った、私たちそれぞれのBUNACOも、この通り。


深さもシェードも異なる2つの商品が出来あがりました。
成型後に液状の糊を塗るまでは、何度でもやり直しが可能。
若い職人が仮に失敗しても作り直せばいいだけなんです。
ここもエコロジカルのポイントですね。
ベテラン職人の手にかかればこんな形も!

瞬時に、ねじれた表情を持つモノもできてしまいました。
こうして作られていくBUNACOのフィールドは、
今や食器にとどまらず、ティッシュケースから、

ランプに、

スピーカーまで。

その曲線美は、見る者の感性をくすぐります。
過去、そのシンプルかつユニークな存在感で、
GOOD DESIGN賞をはじめ、各種アワードを獲得。
今では、海外からも注目を浴びる存在となっています。
昔ながらの技術に、モダンなデザインが加わり、
現代の生活にも自然に溶け込む形となって生まれ変わる。
伝統工芸の持つ大いなる可能性の広がりを
BUNACOから感じずにはいられませんでした。
こぎん刺し
「こぎん刺し」は青森県津軽地方に伝わる刺し子です。
津軽地方では、作業着のことをこぎん(小布)と呼び、
作業着には糸の刺繍(刺し子)がされていたため、この名前がついたようです。
刺し子は、以前、岐阜県の「飛騨刺し子」も取材していたので、
地域による違いも気になり、弘前こぎん研究所を訪れました。

刺し子は補強・保温が目的で生まれたもので、
津軽の厳しい自然条件と、当時の藩政が関係していたそうです。
北国、津軽では綿の栽培が困難なために
一般に使用される衣服の多くは麻布でできていました。
麻は繊維が粗く、夏には風通しがよくて涼しく丁度よいのですが、
冬は津軽地方の冬の寒さを防ぐことができませんでした。
そのため、麻の糸で布目を埋めていき、木綿の糸が手に入るようになると
女性たちが競うように刺繍をして、暖かい空気を服の中にとどめたといいます。

同じこぎん刺しでも地域によって、模様は異なるようです。

これは岩木山の麓の地域に多く見られた"西こぎん"で
山に入って重い荷物を背負う林業が盛んだったために、
肩部分に縞(しま)模様があるのが特徴。
また、飛騨刺し子と比べて見ると、その違いは明白です。


こぎん刺し(上)と飛騨刺し子(下)、
こぎん刺しの方が布全体にぎっしり模様がつまっているのが分かります。
手で触ってみると、刺し子部分は布の厚さが3倍くらいに
感じられるほど、しっかりしています。
そして、その理由は作業を見ると分かりました。

こぎん刺しは、麻布の縦糸を数えながら
拾っていくように奇数の目を刺していくのです。
一方、飛騨刺し子の場合は、図案を布に写し、
線に沿って波縫いをしていました。

実際に私たちもこぎん刺しを体験してみました。

模様の図案を見ながら、ひとつひとつ刺していきます。

麻布の目が見えますか?
この縦糸を数えながら横縫いをしていくのです。
素人の私たちは図案が頭に入っていないので、
さらに図案の升目も数えながら行い、
かなりの集中力と根気がいる作業だということが分かりました。

だけど、徐々に模様が見えてくるのが楽しい!
これ、意外とハマりそうな作業です。
ジグソーパズルを完成させた時の達成感に似ているかも。
こぎん刺し歴30年の先生も
「出来上がった時は毎回『やったぁ!』って思いますよ」
とおっしゃっていましたよ。
「こぎん刺しは売り物じゃなくて、自分たちのために作ったものだから
大事に大事に使って、とっておいたんでしょう。
こうして昔の人たちが残してくれたこの技術を、
私たちには必ず次に伝えていく使命があります」
と、弘前こぎん研究所の成田社長。

最近はこぎん刺しの小物や、

はぎれ布を使ったくるみボタンなども作られています。

これはかわいい☆
シンプルな服やアクセサリーにしても、お洒落ですよね!
私は愛用中の無印良品の帽子につけてみました。

布の補強・保温だけであれば、上記の"西こぎん"に見られるような
縞模様だけで事足りたように思うのですが、
300種類以上の模様があるというこぎん刺しは、
女性の美意識が生んだものだと感じました。
美しく着飾りたいと思う感覚は、昔も今も変わらないのですね。
りんごの木のものづくり
落ち着いた木目、趣きのある木目、味のある木目。
木は同じ木材からでも、一つとして同じ姿を見せません。
だからこそ、木で作られたモノには、一つひとつ違った風合いがあり、
選んでいるだけでも、心躍ります。
青森県では、見ているだけでなぜか心安らぐ木工品に出会いました。

こちらの木材、何の木か分かりますか?
答えはこちら↓

全国の約50%の生産量を占める、青森県のりんごの木です。
りんごの木はご覧の通り、高さが低く曲がりくねっているため、
建材として利用することは難しく、
幹にこぶも多いため、加工するのも難しい木材なんだそうです。
ゆえに、役目を終えたりんごの木は、
薪となるか廃材として捨てられてしまうことが多いようです。

そんな木材にあえて注目し、
りんごの木のぬくもりを国内外に発信しているのが、
青森県弘前市にある「木村木品製作所」。
「もともとは、曾祖父の代からヒバ製のりんご用はしごの製造を担っていました。
冬から春にかけての剪定などで毎年大量に切り落とす枝や木をどうにかしたい。
おいしいりんごを育てるだけじゃなく、りんごを育ててくれた木も最後まで大切にしたい」

りんごの木に対する想いを、
木村崇之社長はそう語ってくださいました。
集めたりんごの木を、自然乾燥させること3~4年。
無難に使える木材は、5割がやっとだそうです。
こうして選りすぐられたりんごの木材は、
一つひとつ職人の手によって丁寧に削り出されながら、姿を変えていきます。


しっとりとしていながらも硬く、深みのある色合いは、
なぜかとても心安らぐから、不思議です。
このジャムべらで、パンにりんごジャムを塗ったらおいしそう…
なんて想像を掻き立てられるのも、
作り手のりんごの木に対する気持ちを感じるからかもしれません。
あえて難易度の高いリンゴの木を使った木工品を作ることによって、
木村木品製作所は、単にひとところの木工品屋にとどまることなく、
店舗什器、各種施設のキッズスペースづくりまで行っています。
人を優しい気持ちにさせてくれる木のぬくもりは、
様々なところに活躍の場がありますね。
桜からの贈り物
秋田県仙北市にある角館(かくのだて)は
春になると毎年100万人を超える観光客が訪れるという桜の名所。

かつての侍屋敷が現存している武家屋敷通りの両脇には
見事なシダレザクラの木が立ち並んでいます。
桜の花の季節は既に過ぎてしまいましたが、
今は新緑のまぶしい季節で、それもまた趣がありました。
そんな角館では古くから山桜の樹皮を利用した工芸品、
「樺細工(かばざいく)」が盛んです。

18世紀末から始まり、
藩政時代は下級武士の副収入源となっていたようですが、
廃藩置県後はそのまま角館の代表的産業のひとつとして
発達してきました。
木目を活かしたデザインは海外でもありますが、
樹皮そのものを使ったものは日本ならでは。
樺細工の製品は時代によって変遷があり、
初期には印籠や葉タバコを入れる胴乱が多く作られ、
その後、茶筒や小箱などが作られてきました。

茶筒は、木型に合わせて経木(木を薄く削ったもの)を巻いて芯を作り、

その上に樹皮を貼り付けていくのですが、

経木は通気性・吸水性・耐水性・殺菌性に優れた性質を持つので
茶筒にはうってつけだったようです。
また、桜の樹皮は一度採取しても再生が可能なんです。
伝統工芸品について取材していると、
これらの利点を経験の中から知り、活用していった古人は本当にスゴイ!
といつも感心させられます。
それから、桜の樹皮を磨くことで艶のある深い赤色が出るというのは
偶然の発見だったのでしょうか。
しかし、私たちの生活スタイルは変化し続け、
最近お茶は入れることよりも、買うことが増えてきているのが現状。
そこで、角館では茶筒に加え、今の時代に合わせた
新たな製品群の開発にも着手しています。
例えば、茶筒同様、性質を活かして使える
「パスタ入れ」や「調味料入れ」、


木の肌触りを日常的に楽しめる「iPhoneケース」、

そして、桜の樹皮の色が生きてくるランプなど。

「2つとして同じものがないのが樺細工なんですよ」

そう語るのは、伝統工芸士の鈴木さん。
確かに、樹皮の新しさや遣う場所、磨き方によって
全く違う表情を見せてくれるんです。

使い続けていくうちに、艶が増したり
"味"が出てくるのもステキなところですね。
伝統工芸品はそのモノ自体が魅力的ですが、
そのものづくりの工程や特質を知ることで興味が増します。
樺細工は既にご存じの方も多いと思いますが、
さらに多くの人に知ってもらいたいなと思いました。
海外でも注目され始めているという樺細工、
日本人である私たちが先にそのもののよさに気づきたいものですね。
青いうつわ
秋田は角館で、とても美しい焼物に出逢いました。

赤茶色の土に、ぜいたくに塗られた釉薬が、
青く深い輝きを放っています。
一目惚れとはまさにこのこと。
近くに窯元があるというので、早速お邪魔してみました。

その焼物は「白岩焼」と呼ばれ、
窯は現在ではこの「和兵衛窯」一つのみ。
それも、今から約40年前に、
70年余りの歳月を経て復活を遂げた窯元なのです。
最盛期には6つの窯元が存在し、5000人以上の従事者がいた白岩焼でしたが、
明治維新後、他県の焼物の流入で厳しい競争にさらされ、
追い打ちをかけるように震災が起こり、全ての窯は壊滅状態に陥りました。
そんな折、民藝運動の活動家、浜田庄司氏が
秋田県知事に白岩の土の陶土適性に関する検査依頼を受けます。
結果、良土と判明し、その際、浜田氏に、
「白岩焼の特徴であるナマコの釉薬は、現在各地で似たものが使われているが、
白岩焼がいちばん良い」(昭和49年7月6日付『秋田魁新聞』)
と言わしめたことが、窯元の復活の大きな推進力となったようです。
この海鼠釉(なまこゆう)と呼ばれる青白い釉薬の色は、
土の鉄分と窯の中で化学反応することにより現れるそうで、
顔料の色ではありません。
ゆえに、焼きの温度が少しでも狂うと発色が異なる気難しい存在のようで、
この美しい色みを醸し出すのは、とても手間のかかることなんだそう。

復活を遂げた白岩焼「和兵衛窯」は、
かつて庶民の生活日用品として使われていた時と同じように、
現代の生活スタイルに合わせた様々な焼物を生み出していっています。

一方、秋田県大仙市に「楢岡焼」と呼ばれる
同じくとても美しい焼物がありました。

同じく「海鼠釉(なまこゆう)」の釉薬を使った青い輝きが特徴ですが、
白岩焼とはルーツも異なり、約140年以上の歴史を守る唯一の窯元です。
今や多くの窯元が、原料である土を注文して調達している昨今、
楢岡焼では、地元の土を自らシャベルカーで採取していました。

「決して使いやすい土ではないんですよ。
使いやすくするためには、大きな労力を要します。
ただ、それの方が"楢岡焼らしさ"が出ると思うんです」

そう語るのは、就任すれば6代目となる陶工、小松潮さん。
原料の土の採取から、釉薬の配合はもちろんのこと、
窯には自前の登り窯も構えていらっしゃいました。

「薪を使って焚く登り窯は、多大な労力がかかるうえ、焼成結果が安定しません。
だからこそ、ガス窯では得られない味のある作品を生み出すこともできるんです。
私たちが登り窯を焚き続ける理由はそこにあります」
小松さんがそうおっしゃる通り、
一つひとつの作品が違った輝きを放っていました。
薪の炭がつくとより風合いが増すようです。

最近では、小松さんの感性を生かした、
こんな素敵な作品も。

「こんな時代だからこそ、一つひとつ手間ひまかけた、
違う個性を放つモノがあっていいと思うんです。
ただ、今は注文をさばくので手いっぱいですが…(笑)」
おっしゃる通り、小松さんの作品は他に一つとないものゆえに、
気に入ったモノは、どうしても手に入れたい衝動に駆られます。
昼下がりのブレイクタイムの想像を掻き立てられながら、
コーヒーカップを一客、購入させてもらいました。

その色みと厚さからか、落ち着いた風合いを感じます。
それも、たっぷりと付けられた釉薬に耐えられるように、
素地の土に厚みを持たせるためであって、
ある意味、とてもぜいたくな焼物と言えるかもしれません。
白岩焼に楢岡焼。
どちらも秋田で昔から日用品として使われてきた食器は、
今、時空を超えて、現代の日用品として生み出されています。
紅花染め
今から約300年前に京都で始まった舞妓さんの紅。

インドの女性が額に付けるビンディや、身につけるサリー。

これらの染料にはかつて、同じこの花が使われていました。

「紅花」です。
日本へは7世紀初め、シルクロードを渡って、
染色技術とともに中国から渡ってきたといわれています。
江戸時代、その土地や風土が紅花の栽培に適していた山形県は、
全国生産量の約50%以上を占めるほどの最大の産地に。
山形の内陸で採れた紅花は「最上紅花」と呼ばれ、
最上川を利用して日本海沿岸の酒田に運ばれ、
北前舟の西廻り航路で、京都や大阪へと送られていきました。

当時は金と同じぐらい貴重な染料として取引され、帰りの船には、
陶磁器や美術品、塩、茶、海産物などが積まれてきました。
その返り荷の一つであった雛人形は、
県内の至る所に配置・保管されています。

また当時、この紅花を主とした交易で、
一大財を築き上げた商人たちの家城が現存しており、
当時の面影を見ることができます。

酒田の大商人、本間家などは殿様より力を持っていたと聞きますから、
紅花がどれだけ高価なものであったか想像がつきますね。
紅花から抽出できる色素は黄色と紅色の2色ですが、
そのうち、紅色が占める割合は1%未満。高いはずです。
これに藍色を加え、三原色のすべてがそろうと
染め方によって、大きく6色の色を出すことが可能になるんです。

ご覧の通り、鮮やかな色合い。
こうして、自然の色で染め上げられた紅花染めは、
見ていてもいっこうに飽きがこないから不思議です。

「植物はそれぞれに色合い、色素、風合いというものが違います。
だから同じものがない。
そこが今も植物染めが続いている魅力なのだと思います」
そう、職人も紅花染めの魅力を語ります。
明治時代に入り、外国産の化学染料が輸入され、
急速に姿を消していった紅花産業ですが、
山形県では県花にも認定し、今でもその文化を守り続けています。
昨日のブログでご紹介した佐藤繊維(株)でも、
紅花染めのストールを開発し、世界へ発信。
こうした新たな取り組みで、
歴史が受け継がれていくといいですね。
世界に認められた、メイド・イン・ヤマガタ
山形出身の友人に、
「世界中から注目されているニットメーカーがある」
と聞いて、山形県のほぼ中央に位置する
寒河江(さがえ)市にやってきた私たち。
訪れた佐藤繊維株式会社で
東京出張から戻ったばかりの佐藤正樹社長に、
お話しを伺うことができました。

まずお会いしてみて、その若さとインパクトのあるファッションに衝撃。
お話いただくひと言ひと言に吸い込まれていきます。
「昔からある歴史や機械、ストーリーがあるからこそ今がある…」
そう始められた正樹社長。
さかのぼること80年以上前、もともと農家が多かったこの地域では、
冬に雪で作業ができないことから養蚕が盛んだったそうです。
しかし、その後洋服の文化が入ってきて、東京や愛知で紡績業が本格化。
羊を飼うためには大量の草と広大な敷地が必要なので、
東京や愛知では原料の羊毛(ウール)を輸入していました。
一方、山形では米作が盛んだったため、幸いにもワラがたくさんあり、
正樹社長の曾祖父が近所の各家庭に羊を数頭ずつ飼ってもらい、
手編み毛糸の製造・販売を始めたといいます。
その後、祖父の時代に工業化。
原料を輸入するようになり、糸づくりの量産が始まり、
父親の時代になると、セーターの販売もスタートしたそう。
しかし、時代の移り変わりとともに、セーターの価格はどんどん落ち、
2005年に正樹社長が就任した時も、厳しい時代は続いていました。
約20年前に400~500社あった紡績会社が、
現在三十数社にまで減ってしまっているんだそうです。
「先代から受け継いだものづくりを、次世代につなげることが僕の使命。
息子が継ぎたくなるような会社にするのが目標ですよ」
そう話す正樹社長の転機は、イタリアを訪れた時だったといいます。
「日本人は言われたことをやってきただけ。
もっと自分たちから情報発信していくべきだ。
クリエーターとして、これまでにないものを作ろう!」
そう決意して紡績機の改良から始めました。

最新鋭の機械は安定した糸を効率的に生産するのには適していますが、
個性的な糸を紡ぐことはできない。
そこでわざわざ古い機械を見つけてきて、それを改良して使うようにしました。
ヨーロッパでは効率化を図って
どんどん新しい機械に入れ替わっていく中で、
物を大切にする日本だからこそ、古い機械も見つかったんだとか。
また、同時に最高の原料も探し求め、世界中を自ら歩き回りました。
そして、2007年にイタリアのニット素材展示会で
オリジナルの糸を公表すると、
世界のラグジュアリーブランドの多くが注目。


さらに2009年1月には驚くべきニュースが!
オバマ大統領の就任式で、ミシェル夫人が着ていた
ニナ・リッチのカーディガンに
佐藤繊維が開発したモヘア糸が用いられていたのです。
その後も世界一細い糸の開発に成功した正樹社長は、
オリジナルブランドも起ち上げています。
「糸を細くすることで、セーター以外のアイテムが作れるようになりました。
ニット=セーターの歴史を変えることができたと思っています」
確かにニットと聞くと、モコモコのぬくぬくしたセーターを
思い浮かべてしまいますが、
これからの季節に着られるキャミソールや

ハンドバッグやブレスレットなどのアクセサリーも
同じニットでできているんですよね。


カラフルなニット商品は、
身につけるだけで気分がワクワクしてきそうです♪
「万人に喜ばれるものじゃなくって、変人に喜ばれるものを作らないとね。
玄人が求める"すげぇ"に応えられるか、だと思いますよ。
作り手が自分の強みを理解していないとダメ。
○○を作らせたら世界一!というブランディングをしないといけない。
仮に僕が別のものを作っていたとしても、売る自信がある」

そう、力強くおっしゃる正樹社長が放つオーラはまぶしいほど。
歴史や伝統を重んじながらも一方で、
ものづくりには発想の転換も必要なのかもしれません。
「自分の中の価値観を信じて、夢や目標を決めれば成功できる」
正樹社長の経験から来るこの言葉には、説得力がありました。
今後もメイド・イン・ジャパンならぬ、
「メイド・イン・ヤマガタ」から目が離せません。
大切に使い続けるモノ
島独自の文化・芸能の伝わる佐渡島では、
ものづくりにおいてもいくつか興味深いものがありました。
まずは、相川で見つけた「無名異焼」。

「むみょういやき」と呼ばれるこの焼物は、
佐渡金山採掘の際に出土した、無名異と呼ばれる赤土を使った陶器。
かつてこの赤土は漢方薬として服用したり、止血剤として使われていたようです。
ある意味、体にいい焼物と呼べるかもしれません。

この土をものすごく細かいふるいにかけて、
非常に粒子の細かい土だけを使って焼き上げるため、
焼き上げると3割くらいに縮むそうです。
その分、非常に硬く仕上がっています。

酸化鉄を含むこともあって、叩くとキーンという金属音が響くんです。
使いこんでいくと、表面のざらつきがなくなって、つやが出てくるそう。
「使えば使うほど、それに応えていってくれる焼物ですよ」
窯元の人が、そう教えてくださいました。
長く付き合うほど、愛着が湧いていきそうな逸品です。
続いて、「裂織(さきおり)」。

これは一見、お洒落な新商品のように見えますが、
実は、古くなった布を再利用した織物なんです。
かつて寒冷のため、綿や絹の繊維製品が貴重であった東北や北陸では、
衣類や布団の布などを裂いて、麻糸などで織り直し、
また別の衣類や敷物といった生活用品に作り変えました。
裂織の衣類は、丈夫で風を通さないため、
夏は稲のイガが体に刺さらないように、冬は漁師の防寒用にと、
佐渡では仕事着として大変、重宝されたそうです。
「ネマリバタ」と呼ばれるこの織り機で、
トントンと打ち込んで織られるため、しっかりとした布が出来あがります。


デザインもこの通り、
古い布の風合いを残しながらも、味わいがあります。

こうして古くなった布が、また新しい形になって息吹を取り戻します。

どれも温かみのあるもののように感じるのは、
生活に使われてきた布の風合いからくるものなのでしょうか。
貴重だった布を、何度も繰り返し使えるようにと、
物を大切にする昔の人たちの生み出した技ですね。
「無名異焼」に「裂織」。
あるモノを無駄にしないで使い続けるという、
佐渡の先人たちの知恵は、
現代においても大いに活かしていけるものだと感じました。
同じようで違う、無印良品のキャンプ場
「嬬恋は"湖畔の野原"、南乗鞍は"山間の高原"とたとえるならば、
津南は"里山の森"ですよ」
無印良品キャンプ場スタッフにそう教えられ、
やってきたのは6月上旬に今シーズンが始まったばかりの
無印良品津南キャンプ場![]() 。
。
これでキャラバン隊、無印良品3つのキャンプ場制覇です!

そう、無印良品のキャンプ場の歴史は、
ここ津南で1995年に幕を開けました。
すぐ裏に山伏山がそびえる立地は、
確かに里山の森の中のキャンプ場といった印象です。
その地を知り尽くした地元出身のスタッフたちで運営されていることもあり、
そこでの滞在はとても濃いものとなりました。
まずはキャンプサイト選びから。

眺望、間取りなどを考えながら、場所を絞っていきます。
こうして居住地を選んでいく様は、
人間が昔から繰り返し行ってきた営みなんですよね。
吟味して決めたサイトに、
みんなで協力して、テントやタープを張っていきます。

家づくりも、元来、共同体の重要な営みでした。

こうして見晴らしのいいアジトが出来あがりました!
完成するや否や向かった先は、晩ご飯の調達。
「晩飯は、ここで採れるかにかかってますから」
そうスタッフに告げられ、道なき道をどんどん山奥へと入っていきます。

すると、ありました!
「根曲がり竹」です。

主に東北や北陸といった豪雪地帯の山地に群生する
タケノコの一種です。
これを手で根もとの方からもぎ取ります。
「津南キャンプ場の魅力は、何といっても
山菜やタケノコといった山の恵みですから」

思わず時を忘れて、山菜・タケノコ採りに没頭していました。
汗だくになりながら、みんなでこれだけの晩御飯を集めましたよ♪


大漁!大漁!一食分には十分すぎるぐらいです。
灰汁が少なく、そのまま食べられるため、
晩御飯では、姿焼にしたり、

炊き込みご飯にしたり、

味噌汁に入れたりと、大盤振る舞いで頂きました。

どれも本当に絶品!
なかでもお味噌汁は、今まで食べたことのない出汁が出ていて、
癖になる味わい。
それもそのはずで、このお味噌汁、
なんと鯖の缶詰を入れてあるんです。
この根曲がり竹と鯖の缶詰を入れたお味噌汁は、
長野県の北信地方と、新潟県の上越地方の山間部の郷土料理だそう。
私たち、完全にハマってしまいました。
こんな山の恵みを共にしたら、お酒も進みます。
乾杯!

津南キャンプ場では、今年お酒のセレクションを、
地ビールはもちろん、世界各国の瓶ビールを取りそろえています。
大自然に囲まれながら飲むビールの味は格別ですよ!
夜は火を囲いながら、また語らい合いました。
旅のこと、津南のこと、それぞれのこと。
深夜まで話題が尽きることはありませんでした。

思えば、火を囲って暖をとるのも、
古来からの人間の営みには欠かせないものですよね。
火という自然が放つエネルギーを囲うことによって、
素の自分をさらけ出したくなる気持ちになるのかもしれません。
翌朝も、自然の恵み豊かな津南らしい朝食をとりました。

津南キャンプ場には、他にも、
カヌー・カヤックで全面を漕いで回れる広い湖もあります。

新しくラフティング用のラフトボートも導入され、
暑い夏にはもってこいのアクティビティになりそうですね!
「地元出身のスタッフたちなので、地元の話ができる。
それが何よりも津南キャンプ場の魅力です」
そう語る津南キャンプ場のスタッフたちは、
アウトドアの熟練で、元気いっぱいの方たちでした!

"湖畔の野原"のカンパーニャ嬬恋キャンプ場![]() 、
、
"山間の高原"の中の南乗鞍キャンプ場![]() 、
、
"里山の森"の中の津南キャンプ場![]() 。
。
どこも大自然に囲まれた環境ながら、
その魅力は同じようで、ひと味もふた味も違っていました。
自然は語るものではなく、感じるもの。
今年の夏、是非、無印良品のキャンプ場で、
外遊びしてみませんか?
アウトドアを日常に
新潟県三条市の山間部にその会社はありました。

株式会社スノーピーク、日本のアウトドアメーカーです。
私たちがキャンプ場で使わせてもらったテントや、
写真(下)のアイアングリルテーブルもスノーピークのもの。

三条市は全国的にも金物工業が有名ですが、
スノーピーク社ももともとは金物問屋だったそうです。
登山が趣味だった初代社長が、出入りしていた金物屋に
オリジナルの山道具を作ってもらったことが
アウトドアメーカーとしての始まりなんだとか。
今でも三条市に本社を置くワケを
「ここにはスペシャルな技術を持っている企業が周りにたくさんいますから。
それがモノを作り続ける我々の武器でもあります」
と、販売促進課の片山さんは話してくださいました。
これは世界でも有数の技術を持つ、
燕三条の技術が生んだピカピカのステンレスマグ。

驚くほど軽くて丈夫、そして、研ぎ澄まされたこのデザインですから、
キャンプだけでなく、フェスを楽しむ若者にも人気だそうです。
さらに、分解できるこのお箸。

細い方を太い方にしまえるため、携帯もでき、かつ、衛生的。
海外でも大人気の商品だそうです。
このスノーピーク社ですが、実は1年ほど前に
長年の夢を叶えました。
それは、本社を移転して、キャンプ場の中に置いたのです。

「私たちの商品コンセプトは、『自分たちが欲しい物を作る』。
そのためには、こういう環境で仕事をしないとダメなんです。
社員がユーザーさんより遊んでないとね!」

日焼けしてTシャツの似合う片山さんが発したこの言葉には
とても説得力がありました。
三条市の技術を結集し、海外でも注目される企業へ。
「アウトドアを日常にするのが理想です。
将来的にはアウトドアという言葉をなくしたい」
片山さんがそう語るように、
スノーピーク社のあくなき探求は続きます。
MADE IN SEKI
突然ですが、問題です。
以下の3つの言い回しに共通することって何でしょう?
「相づちを打つ」
「反りが合わない」
「付け焼き刃」
その答えは、岐阜県中部の関(せき)市にありました。
関は、日本はもちろん、世界各国へ輸出されている「刃物」の産地。
そう、先ほどの3つの言い回しはいずれも、その語源が"刀"に関連するものです。
「相づちを打つ」→鍛冶(かじ)が刀を鍛えるとき、
師が槌を打つ合間に弟子が槌を打つことからできた言葉。
「反りが合わない」→「反り」とは刀の峰の反りのことであり、
刀身と鞘(さや)の峰の反りが合っていないと刀身は鞘に収まらないことから、
これを人間関係にたとえた表現。
「付け焼き刃」→切れ味のよくない刀に鋼(はがね)の焼き刃を付け足したものをいい、
鋼を足しただけのものはすぐに切れなくなり、
使い物にならなくなってしまうことからきた言葉。
今から約780年前の鎌倉時代、初めて関で日本刀がつくられました。
関には、刀づくりに必要な良質の土と松炭、長良川と津保川の水があったので、
刀匠(とうしょう)が多く集まるようになったそうです。
明治9年に廃刀令が布かれ、刀の需要はなくなります。
しかし関では、その技術を家庭用刃物の生産に転用し、
刃物の街として発展をしていきました。
家庭用刃物といえば、包丁、ナイフ、はさみ、カミソリ、爪切り…
私たちの身の回りに刃物ってたくさんありますね。
今回は、はさみを中心とした刃物メーカーの
「長谷川刃物」さんを訪ねました。
まず、はさみの製造現場を見せていただくと…

1枚1枚の刃を何度も何度も磨かれていました。

さらに刃の噛み合わせをよくするために
その隙間の空き具合を目視でチェックし、

ひとつひとつ手で調整していきます。
正直、こんなにも手作業ではさみがつくられているとは驚きでした。
続いて、ショールルームにご案内いただくと、はさみがズラリ。

同じはさみでも、事務用、手芸用、園芸用…
とそれぞれ用途によって刃のつくりが違うんだそう。
「事務用のはさみで、テープを切った後に
ベタベタして切れにくくなったことってありませんか?」
あります、あります、そういうこと。
そんな時のために刃に樹脂が塗られベタつかないはさみがあり、

「リサイクルのために牛乳パックを切る時って、
まっすぐのはさみだと手が当たってしまうんです。
このはさみだとスムーズに切れますよ」

確かに!
刃の先が牛乳パックの角にちょうど合うように
設計されているはさみもありました。
長谷川刃物さんでは、お客様の声をもとに
こうした"使い勝手のよい"はさみを開発しているそうです。
さらには"できるだけ多くの人が利用可能であるように"
ユニバーサルデザインへの取り組みもされています。

このカスタ(左)とネイル(右)は
関養護学校の生徒さんと一緒に、考え出した商品。
握力の弱い人でも使いやすく、
はさみは刃の部分にカバーがついていて安心、
また、どちらも切るたびにカチカチと音が響きます。

「価格では中国をはじめとしたアジア諸国に負けてしまうかもしれませんが、
使いやすさや"こんなものがあったらいいな"
というアイデアは負けませんよ!」
案内してくださった長谷川さんはそう、笑顔でおっしゃっいました。
生産の4割以上が世界各国で使われている、関の刃物。
「MADE IN SEKI」を通して、日本の文化を知る人もいるのかもしれません。
でしゃばらない食器づくり
「日本のものづくりを守っていく。そんな気概でやってます」
無印良品の磁器・ベージュの生産現場の竹下さんは、
取材の冒頭、そんな胸の内を語ってくれました。
訪れたのは岐阜県南部の土岐市にある工場で、
この辺り一帯は美濃焼の産地です。
美濃焼というと、
Found MUJIの『日本の10窯』でも取り上げられていたような志野焼や、

織部焼といった陶器を想像される方もいるかもしれませんが、
日本の磁器の生産量の多くは美濃焼が占めていて、
国内の陶磁器のなんと50%以上が、この地域で生産されているんです。
かつて、織田信長の経済政策によって、
瀬戸界隈から陶工たちが移り住み、
現在の一大産地の礎が築かれていったようです。
この大規模生産を支えるのは、確立された多様な形が生成できる生産方式と機械化。

それも、単純に多く作るというだけではなく、
実際の使い心地にまで気を配った配慮が施されています。
こちらは成形時の仕上げの工程。

フチが角張らないよう、滑らかにしてくれています。
「機械化といっても、その工程の多くには人がかかわっているんです」
生産本部の吉田さんがそうおっしゃるように、
工場の至るところに、現代の陶工たちが携わっていました。
「例えば、うわ薬をかける工程。
丸皿など形がシンプルであれば機械でもできますが、
それ以外は人による絶妙な感覚で付けていくしかありません」

また、持ち手の大きさによって、原料が乾くスピードが変わるため、
接着原料の水分を微妙に変えながら、
人の手でひとつひとつ作業が行われています。

こうした、多くの職人の手を介して、
無印良品の磁器・ベージュシリーズは出来上がっていきます。

「あたたかみのある色み(ベージュ)を出すには、
酸化焼成という焼き方で、酸素を適度に入れてあげるんです。
逆に淡青色にするには、還元焼成で焼き上げるんです」

左右の色みの違い、分かるでしょうか?
左が酸化焼成の磁器ベージュ、右が還元焼成の白磁です。
みなさんは、どちらが好みですか。
「このように、天然物を相手にしているので、
温度や湿度、製法によって、仕上がりは変わってくるんです」
そう竹下さんがいうように、安定してモノを作り続けることが、
どれだけ大変なことなのかを知りました。
「食器は本来、食べ物を受けるもの。
これからも、でしゃばりすぎない食器づくりを心掛けます」
そう最後につぶやかれた吉田さんの言葉が、心に残っています。
日常使いできる漆器
古くから日本の食卓で用いられてきた漆器。

欧米では、磁器のことを「チャイナ」、漆器のことを「ジャパン」と呼ぶほど、
日本を代表するものとして知られています。
現在でこそ、漆器のように見える合成樹脂の安価の椀が増えていますが、
北海道では約9000年前の漆器が見つかるなど、その歴史は古く、
陶磁器が広く使われる以前は、日本人にとって最も身近な食器だったようです。
陶器・磁器と、その作りについて学んできた私たちですが、
この漆器は、一体どのように作られているのでしょうか?
福井県鯖江市に、斬新な漆職人がいると聞きつけ、お邪魔しました。

山間ののどかな環境に、漆職人、山岸厚夫さんの
『錦壽(きんじゅ)』と呼ばれる工房はありました。
ここから、東京はもとより日本全国、はたまた海外へ展開される漆器が、
次々と生み出されているんです。
到着するや否や、山岸さんは、
「漆の木って、見たことないやろ?」
と、裏庭にある10mほどの漆の木を見せてくれました。

この木に傷を付けると、木自体から回復作用で出てくる樹液、

これが「漆」の原料なんです。
この生漆に触れたり、近くを通ったりするだけでも、
アレルギー性皮膚炎を起こしかぶれてしまうんだそう。
この樹液を精製したものを、栃木でお目にかかったような「木地」に、

何層も塗り込んでいったものが漆器となるんです。

ただ、漆器というと「傷が付きやすい」、「すぐ剥げてしまう」
などのイメージがありませんか?
ゆえに、現在では漆器は、どちらかというと記念事のお祝い時や、
お客様をもてなす際に使用されるケースが多いです。
そこに疑問符を持たれた山岸さんは、
「だったら、最初っから傷の付いている漆器を作ればいいじゃないか」
と、あえて傷のようなデザインを見せ、
新品のジーンズを洗ったようにすりへった雰囲気に仕上げました。

この漆器は使えば使うほど味が出てきます。
これが当時、これまでの漆器の概念を覆したものとして、
山岸さんは一躍、注目を集めることになります。
「じゃんじゃん使えるものじゃないと、使いにくいやろ。
ワシのテーマは、"日常使いできる漆器"やから」
そう語る山岸さんも、初め父親から家業を継ぐ時は嫌々だったそうです。
ただ、やるからには、斜陽産業の伝統工芸としてではなく、
きちんと人に使ってもらえる伝統工芸として確立したいという想いを抱き、
徹底して顧客のニーズを研究すべく、全国のデパートの漆器売り場などに足を運んだそう。
今でも、国内外問わずに積極的に個展などを展開し、
直接、顧客の反応を見ることで、その感性を研ぎ澄ませています。
結果、生まれたデザインがこれら。


「漆って、別に赤と黒だけじゃないんや。
いろんな色が使えるんだから、こんな現代っぽい柄があっていいやろ」

こうして生み出されていく漆のデザインの用途は、
今や食器だけにとどまらず、店舗の壁などにも利用され始めているそうです。
このような展開も、すべては基本があってこそということで、
山岸さんは山形県の漆研究家の元まで、漆の基本を学びに行っていたんだとか。
今では漆の基礎知識、顧客の視点、そして技術、アートまで、
漆についてはどんな観点からでも話すことができる、山岸さん。
本当の意味での職人とは、こういう方のことをいうのかもしれません。
そんな山岸さんの作る漆器は、無印良品でもお買い求めいただけます。

職人たちの作りだす、無印良品「ボーンチャイナ」
磁器は英語で「チャイナ」と呼ばれるように、そのルーツは中国。
中国から日本へと伝わった磁器は、有田や多治見、瀬戸、先述の九谷と、
日本各地で作られるようになり、やがてそれは海を渡るようになりました。
一方、磁器に適した陶石が採れなかったイギリスでは、
ボーンアッシュと呼ばれる牛骨灰を混ぜた陶器が開発されます。
それが「ボーンチャイナ」の由来のようです。
イギリスのウエッジウッドに代表されるように、高級洋食器として知られていますが、
その特徴は、光に当てると生地が透けるような高い透光性を備えています。
無印良品でも展開されている、この「ボーンチャイナ」。

今回はその生産地、石川県白山市を訪ねました。
ここは、原料加工→生産→出荷までを一手に担う、
国内では希少な生産工場です。

均一の品質を保つべく、原料加工やロクロ成形など、
機械が担える部分は機械が行っていますが、
驚いたのが、手作業による工程が想像以上に多いこと。


検品はもちろんのこと、難しい形の成形やうわぐすりがけまで、
多くの工程が人間の手で行われていました。
「人間の目は、最高のセンサーですから」
そう話すのは、陶磁器事業部の西岡さんと剱持さん。

「Made in Japanのものづくり体制として、
大量生産型ではなく、多品種少量生産型を基本に据えています。
それに対応するためにも、やはり人が担う役割は大きいんです」
そんな人の技術が重要視される工場ゆえに、
人の成長を促すための仕組みも準備されていました。
金バッジホルダーの従業員はシニアマイスター、
銀バッジホルダーの従業員はジュニアマイスターと呼ばれるそうです。
同じ作業の繰り返しの中でも、こうした明確な基準を定めることによって、
従業員のモチベーションを高めることにつながるのだと思います。
そして、何よりも追求されているのが、安全性。

人の目を通した徹底した検品体制はもちろんのこと、
安全性を担保したうわぐすりを利用するなど、
長く使い続ける食器ゆえに、安全面には徹底して力を入れているそうです。
最後に、生産者代表として、お二人の大切にしていることを伺いました。
「本質を追究することです。対症療法ではなく」
と西岡さん。
「ウソをつかないことです」
と剱持さん。
Made in Japanのクオリティは、お二人のようなものづくりに対する
真摯な姿勢から生み出されていることを知りました。
それにしても、これだけ人の手を介して、安全面を担保しながらも、
無印良品のボーンチャイナシリーズの価格を実現できているのは、
生産者の努力の賜物だと感じました。
店舗でボーンチャイナを見かけたら、
こんな国内生産者のことを思い出してみていただけたら幸いです。
金沢市のMUJIの意外な人気商品とは!?
石川県では、北陸の中核都市・金沢市内にある、
無印良品 めいてつ・エムザ店![]() にお邪魔しました。
にお邪魔しました。
入り口を入ってすぐに目に入ったモノとは…

なんと傘やカッパなど、雨除けグッズです!

そう、ここめいてつ・エムザ店での人気商品は、
これらの雨除けグッズなんです。
金沢市内の中心地に位置する百貨店内の、
1F入り口付近に店舗を構えていることもあって、
急な天候変化にも、すぐ応えられるというのもあるかと思いましたが、
「弁当忘れても、傘忘れるな」
といわれるほど、石川県は雨が多いようなんです。
事実、石川県の降水日数は163日で全国4位。
(総務省統計局 『社会・人口統計体系』2009年)
ちなみに、富山県は170日で全国2位、福井県は161日で全国6位と、
北陸はもともと、雨の多い地域なんですね。
そんな雨の多い金沢市内では、
バスや電車の乗降口や、市内の各所に自由に使える傘が置いてありました。

この2009年から始まっている『eRe:kasa![]() 』と呼ばれるプロジェクトは、
』と呼ばれるプロジェクトは、
金沢の街に『自由に使えて自由に返せる置き傘を』をコンセプトに、
本来だったら捨てられるはずだった忘れ物の傘などを利用し、
もう一度、大切に使うことによって、ゴミを減らす試みのようです。
雨の多い都市ならではの、素敵な取り組みですね。
ちなみに、無印良品には「しるしのつけられる傘」なんて逸品もありました。

これなら、どこかに忘れた時も見つけやすく、
傘の取り間違いなんてことも起きにくくていいですね♪
それにしても、店舗ごとの人気商品にも、
やっぱり、その土地柄が出るものです。
さて、他の店舗にはどんな人気商品があるのでしょうか!?
進化する伝統工芸、九谷焼
この旅で初めて触れた焼き物は、栃木県の益子焼。
ろくろでの成型に苦戦した記憶がまだ鮮明に頭をよぎるなか、
次に触れた焼き物は、石川県の九谷焼でした。
2012年2月にFound MUJI青山で催された
"日本の10窯"でも取り上げられた焼き物です。
益子焼は陶器に対して、九谷焼は磁器。
以前のブログ「益子焼を体感!」(栃木編)でも記しましたが、
陶器の主原料は粘土で、厚手で重く、熱を伝えにくい性質を持ち、
磁器の主原料は陶石で、薄手で軽く、熱を伝えやすい性質を持っています。
九谷焼は、かつての九谷村(現在の石川県加賀市)で、
良質な陶石が見つかったことを機につくられ始めたようです。
現在でも、石川県小松市で採掘される花坂陶石が原料に使われていますが、
その色は、一般的な磁器よりも若干、黒みがかっています。
そこに、五彩(緑・黄・赤・紫・紺青)をのせて彩るから、
その色彩はとにかく鮮やか!

デザインも、古九谷から始まって、
木米、吉田屋、飯田屋(赤絵)、庄三、永楽(金襴手)と、
伝統的なスタイルは時代ごとに6種類ありますが、
 (写真は永楽以外の5種類)
(写真は永楽以外の5種類)
伝統スタイルだけにとどまらないところが、九谷焼のすごいところ。

写真のように、今でも数々の新しいデザインが生み出されているんです。
さらには、土鍋や、

ミルクホルダーといったところにまで!

九谷焼の領域はとどまることを知りません。
このように進化する伝統工芸は、どのようにして生まれるのでしょうか?
「五彩を使える九谷焼は、クリエイターの創作意欲を掻き立てるのでしょう。
さらに、若手であろうと抜擢されるチャンスがありますから。
県営の九谷焼の研修所が造られて、県外からも生徒が集まっていますよ」
今では親子2代で、九谷焼の進化を促している、
九谷焼の製造元卸である、北野陶寿堂の北野義和社長はそう語ります。

他にも、九谷焼に携わる多くの若手作家を見かけました。
「"ジャパンクタニ"と海外で称賛される九谷焼で、
これからも面白いものを仕掛けていきたい。
そのためには、顧客からの要望も重要で、できるだけ受け入れていきたいです」
息子の広記さんも、そう意気込みを語ります。
実際、九谷焼の銀彩が施された「骨壺」は、
顧客からの要望から生まれたものだといいます。

親から子、親方からお弟子さんへ伝統が引き継がれ、
そして、新しい感性で伝統が進化していく。
伝統工芸の一つの展開の仕方を、九谷焼から見たような気がします。
温泉とこけしと、時代の流れ
「い」伊香保温泉、日本の名湯。
「く」草津よいとこ、薬の温泉。
「よ」世のちり洗う、四万温泉。

「上毛かるた」の中でも、ひと際多く描かれている群馬の温泉。
確かに群馬には、一度は聞いたことのある温泉街が多いですよね。
四万温泉には、あの『千と千尋の神隠し』のモデルになった温泉宿もありました。

火山の多い日本では、昔からたくさんの温泉が湧き出ており、
温泉宿は人々に愛されてきました。
農業が国民の主な産業だった昔の日本では、
湯治といって、人々がコミュニケーションを楽しみながら、
農作業の疲れを癒やす場として、温泉は1年を通して親しまれていたようです。
1月末の一番寒い時期の「寒湯治」、
田植えの後の「泥落とし湯治」、
8月の一番暑い時期の「土用の丑湯治」など。
今でも、「疲れが溜まってるから、温泉でも行ってゆっくりしようか」
なんて話がよくありますが、
温泉の使われ方は、今も昔もさほど変わっていないのかもしれませんね。
そんな温泉街には、「温泉まんじゅう」をはじめとしたお土産品も数多いですが、
そのひとつとして、昔から慣れ親しまれているものが「こけし」です。

以前、栃木で出会ったような木地師が、
東北地方の温泉街において、湯治客へのお土産品として作ったのが始まりで、
今では「伝統こけし」と呼ばれ、東北地方の名産品として知られています。
名だたる温泉街を有する群馬でも同様に、こけしは作られているのですが、
こちらは「近代こけし」と呼ばれ、作家の自由な発想のもとに制作されています。
その工房のひとつ、「卯三郎こけし」を訪れると、
キャラクターものから、

つまようじさしや七味唐辛子入れ、

なんと、へその緒入れまで作られていました。

へその緒と、生まれてきた子供への手紙を、
タイムカプセルのように、こけしの中に入れておけることから、
大人気の商品なんだとか。
名前や日付なども書いてもらえるので、
友人への出産祝いのプレゼントとしても、きっと喜ばれますよね!
昔は、近代こけしといっても、玩具や観賞用が多かったようですが、
観光客の増減が直接、売り上げに響いてくるため、
出荷できる商品をいろいろと考案し、
今では、都心の雑貨屋にも置かれるようになったようです。
ただ、その製法は今でも、ひとつずつ手づくり。

伝統的な製法に則りながらも、
時代のニーズを汲んだ商品を考案していく姿勢は、
伝統産業におけるものづくりの、これからの時代へのヒントではないでしょうか?
卯三郎こけしのスタッフの方々が、生き生き働いているように感じたのも、
時代のニーズに応えている手応えを味わっているからかもしれません。
栃木の職人魂にふれる
栃木は京都に次いで伝統工芸品の数が多いそうです。
徳川家康公を祀る日光東照宮の建立のために、
日本全国から集められた優秀な棟梁たちが、その後定住したため、
手先の器用な人たちが多かったことが、一つの要因といわれています。
今回はそんな伝統工芸品を作る職人を訪ねました。
まずは、着物でも最高級品として知られる、結城紬。

結城紬というと、茨城県の結城市を想像しますが、
実際は、結城市から栃木県の小山市、
茨城県下妻市にかけた一帯が産地となっています。
この地域は、昔から養蚕業が盛んで、
1本1本の糸を繭から紡いで作られる紬は、本当に軽くて柔らかいんです。
真綿絹を原料に、地機を使い、人によって織られるその代物は、
2010年、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。

「1mmでも模様がズレると、金額に雲泥のような差が出るのが結城紬。
使い心地の良さは変わらないんですけどね」

紬の染め職人の大久保さんから発せられた言葉からは、
作り手としての職人魂と、使い手としての気持ちの両面を感じました。
職人気質で、芸術的な技術を見せてくださったのが、
日光市でお会いした木地師の鈴木さん。

鈴木さんの手にかかれば、みるみるうちに
大きな丸太も生活雑貨へと形を変えていきます。

中にはこんなものまで。

この形の急須を、いっさい接着することなく作りだすのですから、
その技術力は相当なものです。
「私は、言われた通りのものを作りだすことはできるんですけどね。
アイデアをひねり出すのは苦手なんですよ」
こうした技術を生かすのは、
新しい時代にどのようにそれを活用していくか。
そのアイデアが重要なのかもしれません。
日光下駄職人の山本さんは、
伝統工芸を今の時代にアレンジする職人でした。

江戸時代、格式を重んじる寺社では、
社内参入の際、草履を履くことが原則でしたが、
日光エリアでは石や雪、また坂道も多く草履では不便だったため、
草履の下に木の下駄をつけた御免下駄(日光下駄の原型)が考案されました。

その履きやすさゆえに、明治中期には広く一般にも普及したようです。
山本さんは、この日光下駄を、現代においても普段使いしやすいように、
ソールに改良を加えるなど、さらに進化させています。

実際履いてみると、その履き心地の良さに納得。
草履部分の竹皮の清涼感と、鼻緒のフィット感は、
ゴムサンダルよりも気持ちが良い感覚です。
「結局はお客さんに良いと思ってもらわなければ、
伝統工芸品とはいえ、意味がないからね」
伝統を守る立場ながらも、その柔軟な姿勢には、驚きを隠せませんでした。
実際、こうした技術を目の当たりにすると、
伝統工芸は守るべき文化だと素直に感じます。
しかし、今日の生活スタイルの変化によって、
日常生活の中で取り入れられるものと、取り入れられないものがあります。
伝統工芸を今後も残すためには、時代のニーズに合わせて、
その技術の活用方法を変化させるなど、様々なヒントはあるはずです。
麻をもっと身近に
古くから、人間のくらしと共にあった麻。
かつては、日本でも全国各地で生産され、
織物や袋、綱、紐などの原料として利用されてきましたが、
戦後、化学繊維の台頭による需要の減少によって、ほとんどの地域で生産が途絶えました。
現在に残る生産地域は、岐阜県や滋賀県、群馬県の一部と栃木県。
その中でも、日本最大の麻の産地、栃木県鹿沼市永野(旧粟野町)を訪れました。
良質な麻が育つ土壌は、一般的には痩せた土地と呼ばれる、砂礫地で水はけが良い土壌。
栃木県のこの界隈は、台風や雹害の少ない地域としても、適地であるそうです。
この地で収穫された麻は「野州麻」と呼ばれ、
昔から品質の高い国産麻として知られています。
そんな野州麻を見に行くと、3月末に種まきをしたばかりで、
今はちょうど芽が生えてきたところでした。

「これが、7月中旬の収穫期には、2m30cm程度にまで大きくなるんです」
そう教えてくださったのは、この地で8代にわたって麻の生産を続けている、
大森家の芳紀さん。

失われつつある麻の文化を現代に伝えるべく、
9年ほど前から麻を原料にした和紙づくりを始め、
その和紙を使ったランプも手掛けています。
家族で営むカフェでは、大森さんの作ったランプで
あたたかみのある雰囲気に包まれるなか、
麻の実の入ったピザを食べることもできました。

現在、国産麻の用途の7割程度は神事用(しめ縄や鈴縄など)、
残り3割も弓道用の弓具や、日光下駄の縫紐、
喧嘩凧などの特殊な用途が多いんだそう。
「育ちが早くて丈夫な繊維である麻を、
今一度、生活の身近なところに感じてほしかったんです」
大森さんは、麻紙づくりを始めたきっかけを、そう語ってくださいました。
しかも、麻紙の原料は、
麻を紡績の原料(セイマ)になるように精製する過程でできる「オアカ」。

昔は堆肥として、使われていたようですが、
1kgのセイマを作るのに、1.5kgのオアカができるため、
今では堆肥としても使いきれていなかったそうなのです。
その製法も、稲わらやぬかを使って発酵させ、
麻から繊維を取り出すという、自然の原理を利用したやり方。
「化学製品を使ってみたこともあるのですが、やっぱり繊維が傷んでしまうんですよね」
麻の繊維は丈夫であるという特徴を活かすために、
徹底的にこだわりぬく姿勢には脱帽でした。
昔から人のくらしを支え続けてきた、麻。
丈夫で、通気性も良く、濡れても乾きやすいため、
現代のくらしの中でも、もっとたくさん活用できるシーンがあるはずです。
無印良品でも、麻を使ったくらしのキャンペーンが始まりました。
麻のある生活、初めてみませんか?
救荒作物、そば
救荒作物ってご存じですか?
米・麦のような主食となる作物が凶作時でも、生育して、
ある程度の収穫量を得られる作物のことです。
以前に記した「雑穀ごはん」でも登場した「あわ」や「ひえ」、
また、慣れ親しまれている食では「そば」もそれにあたります。
そばは75日間程度で成熟する短期作物のため、二毛作も多く、
先述の麻の裏作としても多く作られているようです。
そんな特性のため、そばは日本各地で作られていますが、
栃木県日光市で、初めてのそば打ちを体験してきました。
元々、米の穫れなかったこの地域では、
そば打ちができないと、お嫁に行くことができなかったそうですよ!
まず、そば粉8に対して、小麦粉2を混ぜた粉に
卵と、サラダオイルを少し加え、混ぜます。

水を少しずつ加えながら、
耳たぶと同じぐらいの柔らかさになるまでこねていきます。

これが結構な重労働…。
ふっくらと弾力のある状態までこねあげたら、

今度はそれを少しずつ引いていきます。

手早く伸ばしていかなければ、「そばが風邪を引く」と呼ばれる
そば粉が乾いて、ひからびる状態になってしまうため、
休んでいる暇はありません。
切らずに均等な状態に伸ばしていくためには、
絶妙な力加減が求められるため、難しいんです。
1回目の引きは思いっきり失敗してしまい、
こね直す結果となりました。
2回目の引きでなんとかまとめ上げたそばを、
何層かに折り重ね、そば包丁で切っていきます。

薄く切らないと、きしめんのように太い麺になってしまうと言われましたが、
結果、出来上がったそばは…

この太さになってしまいました!
初めてにしては、そばの形に仕上がっただけよかったですが、
太さ、長さともに、お店で出てくるそばにはない形ですね。
ただ、そのコシは、今まで味わったことのないほどで、
美味しく頂けました。
そばの生産の背景を知ったうえで、自らの手で打ったそばのため、
美味しく感じたのかもしれません。
モノの背景を知ることは、
モノの価値を再認識することにつながりますね。
自然体のワインづくり
栃木県足利市にひとつのワイナリーがあります。

「ココ・ファーム・ワイナリー」
ここで造られているのは、2000年の九州沖縄サミット、
2008年の北海道洞爺湖サミットで、各国首脳やそのご夫人達に振る舞われた、
100%日本のぶどうからできたワインです。

今回そのワイナリーのぶどう畑を訪れてみて、まず気づいたことがありました。
それは、畑がかなりの急斜面にあったのです。
1950年代に始まったこのぶどう畑ですが、
もともと計算や読み書きが苦手な子供たちとその担任教師
(ココ・ファーム・ワイナリー創設者の川田昇さん)が
山を切り開いてスタートした場所でした。
川田さんは、子供たちに農業体験を通じて、自分の仕事に誇りをもたせようと、
「一年中仕事が尽きない作物=ぶどう」を選んだそうです。
こうして始まったぶどう畑は開墾以来、除草剤が撒かれたことがないといいます。
「今でこそ、無農薬・有機栽培に注目が集まっていますが、
私たちはただ農薬を買うお金がなかっただけなんですよ。
草は手で刈り、置いておけば肥料になりますし。
ぶどうにかける袋は、もったいないから洗ってまた使っていただけですが、
"エコ"って褒められて(笑)」
そう、当時を知るココ・ファーム・ワイナリーの牛窪さんは語ってくださいました。
その後、1980年代に入り、生食用のぶどうづくりからワインづくりに転換。
当時、日本でワインはまだ珍しく、川田さんは
普段かっこ悪いと思われがちな子供たちに、
"かっこいい"仕事をさせてあげたかったのだそうです。
自然のままにできたぶどうを使った、ワインづくりは当然自然体で。
天然酵母を使った、低温醸造です。


このワイン貯蔵庫は夏でも冬でも温度が15℃前後だそうですが、
ここも山を掘ってつくった天然貯蔵庫。
そんなワインが、ソムリエの田崎真也氏の目に留まりました。
ラベルを隠したブラインドテイスティングで良い評価をいただき、
沖縄サミットの晩餐会で振る舞われるワインとして
選ばれるきっかけとなりました。
世界に認められた味は、自然の中で出来上がった味だったのです。
ココ・ファーム・ワイナリーを訪れて、
いいものづくりというのは、買い手のことだけを考えるのではなく、
作り手のことも考える中で、生まれるものだと感じました。
益子焼を体感!
日本には全国にやきものの産地があります。
やきものが始まったのは今から約1万2000年前といわれていますが、
日本でやきものが盛んになったのには、
日本人の生活スタイルが関係していたようなのです。
定着型の農耕民族は、食料を保存するのに瓶や壺が必要でした。
一方、狩猟民族の国は、移動が多い生活なので、
重くて割れやすい、やきものを使う習慣は広がらなかったといいます。
2012年2月、Found MUJI青山では、
"日本の10窯"と題して、日本国内の10カ所の陶磁器の産地で作った器を
販売するイベントを行いましたが、
今回はその10窯のひとつである「益子焼」の産地、
栃木県芳賀郡益子町を訪れました。

益子焼について教えていただいたのは、
益子最大の窯元「つかもと」、企画課の関さん。
現在の企画担当になる前は、17年間陶芸職人をされていた方です。

益子焼についてご紹介する前に、まずはやきものの基本、
陶器と磁器の違いについて。
「陶器は粘土、磁器は石の粉を使ったやきものと考えていただくと
分かりやすいかもしれません」
陶器は粘土が原料で、厚手であるために
"熱しにくく冷めにくい"ので、
熱いお茶や汁物を入れるのに向いているそうです。
一方の磁器は、薄くて丈夫なのですが、
"熱を伝えやすく、冷めやすい"のだとか。
また、磁器は型に流し込みやすい一方で、
陶器は粘土で粘り気があって型に流し込めないため、
小~中量生産しかできないといいます。
ちなみに、益子焼は代表的な陶器の種類のひとつで、
江戸時代末期に、現在の茨城県笠間市で修業した陶工が
益子町に窯を築いたことが始まりといわれているそうです。
当初は水がめ・火鉢・壺などの日用道具が主だったのですが、
その後、ふだん使いのできる食器づくりに移っていったのだそう。

実際に作っているところを見せていただき、

続いて、私たちキャラバン隊も挑戦!
職人さんがやるのを見ていると、スルスルと粘土の形が変化していき、
一見簡単そうにも思えたのですが…

いざ、自分でやってみると手に力が入ってしまい
思うような形づくりができません。


それでも職人さんに助けていただきながら、なんとか形になりました!
焼き上がって手元に届くのは約1ヶ月半後だそうですが、
どんな仕上がりになったか楽しみです。
さて、MUJIキャラバンでは、今後も日本のやきものの産地を
出来るだけ訪ねたいと思います。
それぞれの土地に伝わる器との出会いにご期待ください。
美しい燃料、「菊炭」
かつては一般家庭でも、燃料として使われていた「炭」。
高度経済成長にともない、ガスや石油が普及するにつれ、
その用途は飲食店や、バーベキューなどのレジャーへと移り変わってゆきました。
炭火はじっくりと焼き上げることができるため、
それ自体をうたい文句にしている飲食店も少なくありません。
同じように、炭火でじっくりと温める茶道の世界では、
見た目の美しさも求められるようです。
その茶道で使われる炭が、菊炭と呼ばれる
割れ目が菊の花を思わせる模様の炭です。

東の佐倉炭、西の池田炭と広く名が知られていたこの菊炭も、
今や数えるほどの窯元しか生産をしていません。
その希少な生産者の一つである、
栃木県芳賀郡にある市貝町木炭組合の片岡さんにお話を伺いました。

「小さい頃から、窯から煙が上っているのを見て育ちましたからね。
私の代で、廃れさせてしまいたくなかった」
西の池田炭は、愛媛の内子や大阪の能勢に窯元が残っているようですが、
東の佐倉炭は、震災の影響を受けた福島を除くと、ここ芳賀郡しかないようなのです。
そんな片岡さんの窯は、昔ながらの石窯で、
薪をくべる伝統的な製法を守っていらっしゃいました。

木の水分量や状態に応じて、窯の焚き方や温度を調節し、
一度、火をつけたら、生き物のように見守らなくてはならないんだそう。
主の素材はクヌギ。

「この界隈には、自然のクヌギがたくさん生えています。
クヌギは切ってあげないと、木が死んでしまうんです。
切ってあげれば、また6~7年で新木が生えてくる。
そういう意味でも炭は、理に適った自然エネルギーなんですよ」
森林伐採につながるのでは、と一瞬でも考えた自分の無知さを恥じました。
こうして出来上がった片岡さんの茶道炭がこちら。

「下野菊花炭」
菊の花のような美しさです。
火つき・火持ちも良いようで、
ずっと眺めていても飽きることの無い模様をしていました。
燃料にも美しさを求めるのは、日本人の美に対する感性を象徴するかのようです。
「ガソリンでも、レギュラーとハイオクを混ぜるわけにいかないですよね。
炭も同じで、良いものを作り続けなくてはならないんです」
片岡さんの炭づくりに対する信念を感じる言葉でした。
省エネが叫ばれる昨今、何のエネルギーを使うのか?
消費者である我々も、もう一度考え直す必要がありそうですね。
進化し続ける、酒造り
茨城出身の無印良品スタッフに勧められて、訪れた先。

そこは、地元茨城県を盛り上げたいと、
東京で経験を積んだ後に帰郷されたオーナーが運営するお店でした。
立ち飲みコーヒー屋のバールとイタリア食堂をひとつにした、
「トラットリア ブラックバード」では
魚介、野菜などの食材は地元産のものを使っているといいます。
オーナーの沼田さんに今回の取り組みを話すと、
「世界に誇る、日本の酒蔵がありますよ」
と教えてくださいました。
地元の情報は、やっぱり地元民に聞くに限りますね!
さて、紹介の、これまた紹介で訪れたのは
180年以上続く「木内酒造」さん。

彼らの元には、創業当時から変わらないものがあります。
それは、原料の水。
酒蔵内の深井戸からは、那珂川水系の伏流水が湧き出ているといわれています。
変わらないものがある一方で、時代の移り変わりとともに
進化していくのが、木内酒造のすごいところ。
日本酒に加え、地ビールの生産を始めました。
ネストビールは、早くから海外でも販売し、数々の賞を受賞しているのですが、
その進化は止まりません。
はじめのうちは、海外のビールを参考にしていたそうですが、
それでは現地のビールには勝てない。
そう考えて、日本ならではの、オリジナルビールの開発をしました。

こうして生まれたのが、「NIPPONIA」
昭和30年代で栽培が終了となった"金子ゴールデン"というビール麦を
地元農業後継者団体と共同で復活栽培するところから手がけ、
さらにホップは、昭和50年代に日本で開発された"ソラチエース"という
北海道で育種された品種を使用するなど、
日本の素材に、とことんこだわったビールが出来上がりました。
また、木内酒造には、本格的手造りビール工房があります。


この工房では、お客様が自分好みのレシピで、
ビール造りを体験できるのです!
もちろん、ラベルもオリジナルにできますよ。

代々引き継がれている、伝統の技がありながらも
そこに新しいアイデアを加えながら常に進化している。
それが180年以上の間、お客様に愛され続けている秘訣なんだなと感じました。
山と川の恵みでできた、お線香
「ゴトン…ゴトン…」
筑波山麓の渓流に鳴り響く音。
そう、この音の正体は「水車」でした。

しかも、この水車は観賞用のものではなく、
今でも現役で働いているものなのです。
水車の持ち主は、100年以上もこの場所で杉線香づくりを続けている、
駒村清明堂の駒村さん。

すぐそばを流れる川の水を引いた、水車の動力を使って、
地元で採取した杉の葉を原料に、まずはそれを砕きます。



小屋の中には杉の香りが充満していました。
機械を使ったら、それだけ早く、大量に粉にすることができますが、
じっくり砕いていかないと、杉の葉が熱をもってしまい、
香りがとんでしまうそうなのです。
1日半から2日間かけて砕き、粉状にしたものに
釜で熱した筑波山の伏流水を加えて、練り上げます。
杉線香を作るのに使う材料は、杉の葉と水だけというから、驚きですよね。
杉に含まれているヤニがつなぎの役割をしてくれるのだそうです。
「これを最初に見つけた人がすごいですよね。
ヒノキの葉でもできるけど、それだと油が多すぎて
逆につなぎを入れないとできないから」
と駒村さん。

練り上がった原料を、今度はこの機械を通し成形していくのですが、
ところてんのように出てくる棒状のものを、横から板で受けるのだそうです。
真っ直ぐなお線香の形状を作り出す、職人の腕のなす業です。
ところで、もともとこのご近所では、
みんなが川の水を使った水車を使い、商売をしていたそう。

隣はうどんの粉を挽いたり、また別のところでは菜種油を絞ったり、
同じ水を順繰り順繰りと、使い回していたといいます。
しかし、だんだん合理化を求めて、
周りは水車を使わなくなってしまったんだとか。
「エコ社会が叫ばれていますけど、私たちは昔から自然エネルギー。
大変なこともありますが、自然と共存できれば電気はさほど必要ないんですよ」
電力があって当たり前じゃない時代に生まれた製法は、
今となっては、電力がなくても作れる製法として価値が見直されているのです。

昔から、お墓や仏壇にお供えするものとして使われてきた、お線香。
きっとこの先もずっと使い続けられていくものだと思います。
自然の恵みによる、先祖伝来のお線香づくりを
これからもぜひ、続けていっていただきたいものです。
水戸の美味しい納豆
水戸といえば納豆を思い浮かべますが、
事実、納豆の生産量全国1位は茨城県です。
そんな茨城県に、2012年納豆鑑評会で優秀賞に輝いた、
納豆の生産者がいると聞きつけました!

水戸納豆製造株式会社。
藁で包まれた昔ながらの「水戸納豆」の生産者です。

納豆鑑評会で評価されるポイントは、
「色」「形」「香り」「糸引き」「味」の5項目。
今年、全国から224点出品された中から、「大粒・中粒部門・国産大豆使用」で
見事、この水戸納豆製造の生産する「雪あかり」という納豆が優秀賞を獲得しました。

大豆が納豆菌に雪のように包まれていることから
「雪あかり」と名付けられたようです。
国産大豆の中でもワンランク上といわれる、宮城県産ミヤギシロメ大豆が使われ、
茨城県工業技術センターと共同開発した納豆菌を利用したことで、
見た目・味・糸引きが向上したとのこと。
確かに、今まで食べたことがないようなしっかりとした粒で、
糸引きも抜群でした。
そんな水戸納豆製造さんのこだわりの製造工程は、
蒸し上げた納豆に、じょうろで独自の納豆菌を植菌し、

手作業によって、独自のパッケージに詰められていきます。

昔ながらの「水戸納豆」は、風味にこだわり、一つひとつ藁に包んでいます。
そして、微妙な温度調整をしながら発酵させます。
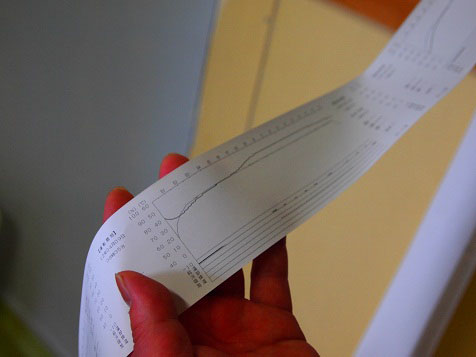
大豆の品種やパッケージによって温度をコントロールするのが、
美味しい納豆を作るコツだそうです。
「菌は生き物なので、同じように作ったとしても、変わってしまうこともあるんです」

そう語るのは、四代目となる専務の高星さん。
納豆菌は、微妙な環境の違いで、活動具合が変わってしまうそうです。
豆の顔色をうかがい、豆と対話しながらの納豆作りは、まさに職人技です。
思えば、しょうゆにしても納豆にしても、
大豆を発酵させて作るという工程においては同様ですね。
ちなみに、納豆は混ぜて糸が引けば引くほど、美味しくなるといいますが、
実際は、ある程度混ぜたら、そう変わらないそうですよ。
日本の誇るべき食文化「納豆」は、
こうした職人たちによって作られていることを知りました。
ほしいも学校
ちょっとお腹がすいた時、
思わず食べたくなってしまう干しいも。

写真は、干しいもを作る際に出る切れ端を集めた、
無印良品の「スティック切れ端干しいも」です。
実は茨城県が国内産干しいもの9割近くの生産量を誇っていること、ご存じですか?
「茨城県でも、ひたちなか市を中心にした地域だけが、
干しいもに向いたサツマイモの品種を栽培するうってつけの土壌なんです。」
そう教えてくださったのは、
無印良品の干しいもの監修も務めている鬼澤さん。

甘くてやわらかい干しいもができる「玉豊」と「いずみ」という品種の生産は、
日本では、ひたちなか市界隈の黒土の土壌が、最も適しているそうなんです。
さらに、海が近いため、潮風に含まれる塩分(ミネラル)も高く、
芋を干すには最高の環境だそう。

5月に苗を植えて、10月に収穫したいもを、
約1ヶ月間貯蔵し、デンプンを糖化させます。
その芋を洗い、ふかし、皮を剥き、干すという、至ってシンプルな製造工程ですが、
芋は形が不ぞろいで機械化が難しく、すべて手作業で行わなくてはならないそうです。

そのため価格は高くなりますが、その分、愛情はこもっているとのこと。
「カリウムや鉄分、食物繊維、さらにはポリフェノールが多いんです」
おやつでも健康に良いものとして食べられるのは、うれしいですよね。
この伝統食のことをきちんと伝えていこうと、
この地域の干しいも生産者と、デザイナーの佐藤卓氏が共同で、
2年ほど前、『ほしいも学校』という本を出版しました。

干しいもの歴史から、成分、人体や環境との関わりまで、
徹底的に干しいもについて書かれた本です。
地域の学校にも置かれており、一部東京の本屋さんでも購入可能だそうです。
こうした取り組みで、
地域産業について多くの人に知ってもらい、地域の人が誇りを持つ。
これからの時代へのヒントを得たような気がします。
ちなみに、今年の干しいもは、例年にない良い出来のようですよ。
私たちも、道中のお供にしたいと思います♪
無印良品のグラス・ガラス食器に込められた情熱
「ガラスって柔らかいんです」
そう教えてくださったのは、
千葉県八千代市にある無印良品のグラス・ガラス食器の生産現場の山本さん。

原料となる珪砂などを、1400℃以上の高温で熱し、
水飴のような流体状態にしたうえで造る、
ガラスの生産現場に携わっている人だからこそ分かるこの感覚は、
私たちにとって新鮮な響きでした。
この工場は、自動成形(機械生産)部門とクラフト(手作り)部門を併設している、
日本で唯一の場所だそう。
様々なガラス製品の生産に対応できるわけです。
そんな生産現場を今回、特別に見学させていただきました。
夏場には気温50℃を超えるという工場内は、
ガラス職人たちの真剣な眼差しにあふれています。

「ガラス職人というと、クラフト(手作り)のイメージがありますよね」
ふと素人じみた感想を述べると、
「自動成形部門で、機械を調整するのも難しい仕事なんです」と山本さん。

ガラス食器成形機メーカーより購入した成形機を
いかに改良できるかが、各ガラスメーカーの技術力の差を生むそうです。

確かに、様々な形状のガラス製品を作るために、
寸分たがわずに動き続ける機械を操るのも職人技です。
ただ、生産コストの安い海外企業との競争も熾烈さを増しているのは、
ガラス業界においても同様。
そんななか、日本の生産体制の強みは何なのでしょうか?
「我々の強みは、製品の安全面を最大限意識した、品質保証体制です」
「源流思考で良品だけを生産する」という考え方のうえで生産された製品を、
さらに、検査機と人により検査する体制は、
驚くほどの厳しい基準でした。

ガラスの形状、不純物の混入などを検査機で見分け、
さらに人の目でも検査する。
排除された不良品を見せていただいたのですが、
素人目の我々には、排除されたポイントが全く分からないほどでした。
この微差を見分けられるかが、良品を生産できる企業の違いではないでしょうか。
「すべては人が造るもの。人のガラスに対する情熱が、一番大切なんです」
最後に、山本さんはこうおっしゃいました。
「人が日々、使うものだけに、それを作る人の情熱が大切です」
これが良いものづくりのための基本なのかもしれませんね。
無印良品のグラス・ガラス食器は、
ガラス職人たちの情熱と技術と努力の結晶の末、生まれたものでした。

これから店頭で商品を見かける度、
そんなガラス職人たちの情熱を思い出すことになりそうです。
無印良品の寝具の歴史
一日のうち、約3分の1の時間を共にする寝具。
より良いくらしを追求する無印良品にとって、
重要な位置づけの商品であることは言うまでもありません。
その無印良品の寝具の歴史を語るに欠かせない人は、
千葉県いすみ市にいらっしゃいました。

1991年に最初のモデルが発売され、
今や無印良品の代名詞とも言える「脚付マットレス」や、
よりしなやかに体を支えるマットレス「ポケットコイルマットレス」の開発など、
国内外で無印良品の寝具の変遷を支えてきた人です。
日本のベッド業界の歴史を知る人でもある矢崎景一さんは、
とても笑顔の素敵な、気さくな方でした。
今回、私たちは特別に「ポケットコイルマットレス」の生産過程を
拝見させていただきました。
まず、マットレスの根幹となる「ポケットコイル」の生産から。
直径わずか1.4mmの銅線を、熱処理を加えコイルにします。

この微妙な形を作るのが難しいポイントのようです。

ちなみに、ポケットコイルマットレスの種類は、
「高密度」「超高密度」「超高密度(増量タイプ)」と3種類ありますが、
コイルの形は一つひとつ異なるんです。

これらのコイルは不織布に包み、束ねられていきます。

シングルベッドサイズで、それぞれポケットコイルが、「高密度」で800個、
「超高密度」で924個、「超高密度(増量タイプ)」で1320個
入っているというから驚きです。
この時点で、気の早いキャラバン隊員は、寝心地を試させていただきました。

一つひとつのコイルが独立しているため、
体の凹凸に合わせて支えてもらっている感覚です。
また、このままでも十分に寝られる心地でした。
実際は、これにウレタンフォームなどを載せ、カバーが被せられ、

熟練の技術者たちによって、縫合されていきます。

最後、熟練の目利きによる厳しい検品を経て、

「ポケットコイルマットレス」完成へ。
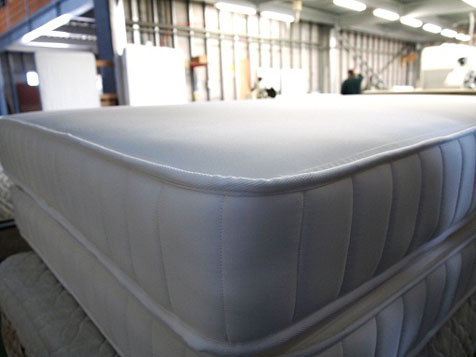
この微妙な隆起具合が、寝心地のクオリティを左右するのだそうです。
そして、その微差の調節は、機械による縫合では難しいんだとか。
やはりここでも、職人の手作業による、良品に対するクオリティの担保がありました。
そもそも、矢崎さんが寝具業界で働き始めた頃、
日本ではまだ布団文化が一般的で、ベッドは高級品だったそうです。
ただ、布団の場合、寝た時の鼻の高さが床上30~35cmという、
温度が低く、埃も溜まりやすい高さゆえ、就寝環境としてはあまり良くない。
そういった意味においても、日本人の寝心地に合ったベッドの開発に意義を感じ、
これまで尽力されてきたといいます。
ものづくりの秘訣について伺うと、
「売り手と作り手が仲良く仕事をしていれば、技術は進歩するんです。
両者が考え方を共有できるか、それが一番重要」
今でこそ笑顔でそう語る矢崎さんですが、
当時、商品企画担当者から投げられる要望は、無理難題が多かったそうです。

脚付マットレスの生まれた背景も、
「日本人の生活空間に合ったできるだけ無駄のないベッドを作りたい」
という商品企画担当者の強い要望から。
その強い要望を正面から受け止めて、開発していった努力の結晶が、
今の無印良品の寝具商品として残っているんですね。
普段何気なく使っている身の回りのそれぞれの物にも、
深い歴史があることを改めて思い知りました。
是非みなさん、矢崎さんの笑顔を思い出しながら、
その自慢のベッドの寝心地をお試しください。